
〔244〕伏見殿の特区鞆町後地の頭首岡崎・中村家は伊達氏の一統 1/1大幅に加筆改良しましたので再読を願う
〔244〕伏見殿の特区鞆町後地のの頭首岡崎・中村家は伊達氏の一統
伏見殿の隠れ所領としての「鞆の浦」の土地柄を〔243〕で見てきましたが、この度の調査に際して、たまたま國體舎人から伝えられたジグソー・パズルの断片と之に基づく落合の歴史解釈を、忘れないうちに記録しておきます。
➀明治新政府の民政は、陸奥宗光(伊達小次郎)を主軸として見なければ理解が及ばない。
➁維新の前夜に紀州藩元勘定奉行伊達宗広の六男で脱藩浪人の伊達小次郎(陸奥宗光)が英公使パークスの部下アーネスト・サトーの仲介により遭った岩倉具視に進言し、一夜に開国主義に転向させた。
➂岩倉の引き立てによって新政府の外国事務局(総督・議定晃親王)の御用掛になった宗光は甲鉄艦ストーンウオール号の引き取りに際して関西豪商から巨額の資金を一夜にして借り入れているが、関西豪商の銀主は実は國體基金を管理する伏見殿であった。
➃つまり外国事務局御用掛陸奥宗光は兵庫商社を造った幕府勘定奉行小栗忠順と同じく、関西豪商を表に立てた伏見殿管理下の國體基金を資金源としていたのである。
⑤当時の外国事務局は、薩長土肥政府の首脳伊藤博文・大隈重信が表面上で統括していたが、実際には堀川御所の國體天皇府の基金に頼らざるを得ず、晃親王を背景にした陸奥宗光の働きによるところが多かった。
⑥新政府では朝敵紀州藩出身と年少(明治元年に数え25歳)のため伊藤博文・井上馨らより格下に置かれたが、背後に伏見殿一統が控えていたため堂々と振舞ったことがその行蔵から十分に察せられる。
⑦紀州伊達家(駿河伊達氏)も仙台伊達家も元は一家で甲州中村氏から出るが、伊達宗弘はドイツから入ったハプスブルク大公隷下の大東社員が楠木氏系宇佐美氏を経て紀州伊達氏の家系に潜入したものである。
⑧陸奥宗光が明治三年に刑部省小判事の職を辞して和歌山藩欧州執事となり「和歌山藩伊達宗介」の変名で渡欧したのは、大東社加盟が主目的と見るべきである。
⑨廃藩置県は天皇(國體)天皇が陸奥宗光に依頼し、陸奥は紀州藩大参事
津田出を動かして廃藩置県と帝国陸軍のモデルを和歌山で造った。
ざっと見て以上ですが、そもそも宗光の父紀州藩勘定奉行伊達宗弘が嘉永
元(1848)年に「大勢三転考」を著したのは伏見殿の加盟によるもので、内容は、太古以来「カバネの代・豪族支配」⇒「ツカサの代・律令支配」⇒「名の代・封建支配」と変転してきた大勢が今や行き詰まり、「オホヤケの代・公論支配」の到来が目前にある事を示唆したもので、折から同年にマルクスとエンゲルスが「共産党宣言」を発表したことと密接な関係あり、と落合が観るのは、「大勢三転考」の社会発展史観といわゆる「マルクス史観」がほぼ一致するからです。
要するに國體天皇府の棟梁伏見殿の計らいで、ドイツからきて紀州伊達氏に潜入した大東社員が伊達宗弘となり、陸奥宗光となったわけです。
幕末に紀州藩で生じた政変で伊達宗弘一家が命じられた蟄居は、素より偽装です。宗弘・宗興・小次郎宗光ら伊達家の男子全員が京都粟田口の青蓮院に住んで、伏見宮邦家の保護のもとで國體国事に勉めていたことが『南紀徳川史』に明記ないしは示唆してあります。
このことを初めて指摘したのが拙著「落合秘史第四巻『京都ウラ天皇と薩長新政府の暗闘』(2014年成甲書房刊)ですが、周辺の事情は「第二巻」の『国際ウラ天皇と数理系シャーマン』(2013年成甲書房刊)に詳説しています。

伏見宮と紀州伊達家の密接な関係はハプスブルク大公隷下の「大東社」を通じたものです。明治維新で國體外交の任を担った宗光の隷下に入った鞆町後路の岡崎家で明治三年に生れた染吉は、出生時から「伏見宮の影」とされることが決まっていたのかもしれません。
この続きは有料領域です。
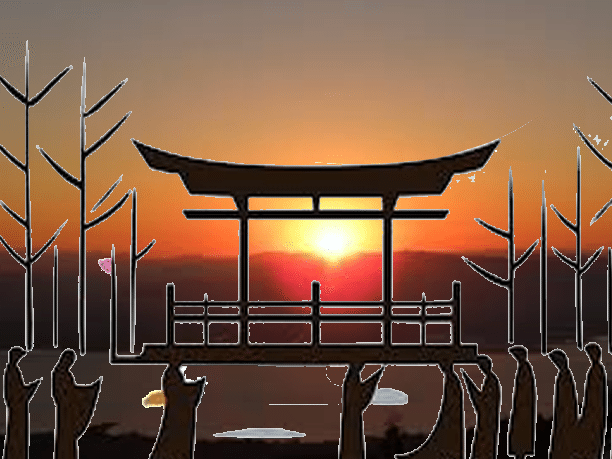
ここから先は
¥ 500
いただいたサポートはクリエイター活動の励みになります。
