
さあ、日本中に帰省しよう!
\ 改めまして、超帰省です!/
2020年9月に超帰省協会を立ち上げました。
このnoteではそもそも超帰省とはなにか、どんなことをするのかなど、2020年の活動報告も兼ね、まとめてみたいと思います。
年末年始、地元について想いを馳せるタイミングに、よかったら皆さんの地元を思い浮かべながら読んでいただけたら嬉しいです。(text:守屋)
超帰省って?
まず「超帰省」とはなにか?
私たちはこういった定義を作りました。

つまり、実家に帰る帰省のときに友達も一緒に帰る(もしくはついていく)ことを超帰省として定義しました。
その体験はガイドブックに載っている旅とは違う、google検索には引っかからない、友人や地元のひとの思い出、思い入れに基づいた最もローカルな体験ができるものだと考えました。

私たちはこの「超帰省」という概念が、これからの時代における「まちとのあたらしい付き合い方」を提唱できると考え、普及させる活動をはじめました。
とにかく地元が好きな3人ではじめました
遅くなりましたが、私たち超帰省は守屋(もりやし)、原田(りょっち)、根岸(あみちゃん)の3人ではじめました。

守屋と原田は大学の建築学科の同期、守屋と根岸は地元が近くて社会人になってから仲良くなったメンバー。
そんな3人に共通していたのは「地元が好き!でも今は東京にいる」ということ。

地元を出てしまったけど、地元のことはすごく好き。そんな自分たちの立場だからこそできる地元へのアプローチがないのか?
そんなことを共通のテーマに持ちながら個々でも活動をしていました。
中でもあみちゃんは地元で「小田原での暮らしをそーぞーするツアー」を季節ごとに実施していました。地元民だからこそ知っているまちの魅力を暮らしベースで案内する一泊二日のツアーで、守屋も一回そこに参加しました。

あみちゃんの両親や姉妹にも会ったり、実家でスイカ割りをしたりすることを経て「もう一つの地元ができた」ように感じました。
これが超帰省のアイデアにもつながっていきました。
実際にやってみて確信した超帰省の可能性
ある程度やりたいことのイメージがまとまってきた頃、原田の地元、静岡県焼津に3人で行ってみる企画を実行しました。
東京駅で車を借りて原田の地元へ。高校の同級生のお茶農家さんでお茶摘みを体験させてもらって、河原でBBQ、夜は原田の実家に泊まり、朝起きるとお母さんとお父さんがいる!そんな旅をしてみて、3人でこれまで考えていたことへの共通の確証をもちました。
「やりたかったのはこれかもしれない!」


1年以上検討した中でもブレなかったこと。
それは「帰省」と「友達」というキーワード。
このふたつがコアアイデアになっていることを再認識し、生まれたのが「超帰省」という概念でした。
SHIBUYA QWSとの出会い
「渋谷から世界へ問いかける、可能性の交差点」をコンセプトに、多様な人々が交差・交流し、社会価値につながる種を生み出す会員制の施設(公式サイトより引用)
として2019年11月にオープンした施設です。「問い」をテーマにプロジェクトを立ち上げることができ、超帰省では「地元にしか帰省しちゃいけないの?」という問いを掲げ、3ヶ月間QWSでプロジェクトを走らせました。

第一線で活躍しているメンターからのアドバイスや別プロジェクトチームのメンバーや時には外部のコンソーシアムとのディスカッションを通じ、超帰省の概念と目標を整理していきました。

全国に広がる超帰省アンバサダー
”「サービス」をつくるのではなく「文化」をつくりたい”
3ヶ月のプログラムの成果発表のプレゼンで私たちはこう宣言しました。
メンターからは「事業化するの?」「マネタイズはどうするの?」といった声をたくさん寄せられましたが、私たちはまずはまずはこの超帰省を「文化」になるようにとにかく広めることを最優先事項としました。

その中でまずは一緒にこの取り組みを広げてくれる「超帰省アンバサダー」というコミュニティをつくることにしました。
周りのひとにヒアリングしていると、今まで名前がなかっただけで「超帰省」をすでにしている人が実はたくさんいて、超帰省に賛同してくれるひとが声をかけてくれるようにもなりました。
そんな人たちと一緒にまずは「#超帰省」という言葉を世の中に溜めていくことをはじめました。

具体的には、(便宜上ではありますが)市区町村別に「超帰省アンバサダー」を募集させていただき、現在では約50人のアンバサダーが集まってくれました。
2020年中に47都道府県にひとりはアンバサダーがいる状態、そして2023年には1741の自治体すべてにアンバサダーがいる状態をつくれたら超帰省が「文化」に近づいていくのではないかと考え、アンバサダーコミュニティづくりを進めました。

このアンバサダーですが声をかけさせてもらう上でふたつ、条件にしていることがあります。
①地元が好きということ。
②一回地元を離れていること。
これは一度地元の外にでることで、地元を俯瞰的にみることができて、地元の魅力がさまざまな角度からみることができるという私たち3人の原体験からきています。
地元にいたままだと気づけなかった、外の視点をもつことで理解できる地元の良さを取り込んでいきたいという想いです。

アンバサダーに声をあげてくれた方全員とは15分のzoomでの顔合わせで超帰省ヴィジョン共有とアンバサダーの想いのすり合わせをしています。
これまで50人以上のひとと顔合わせをしてきましたが、全員違う背景と想い、地元があって、改めてこの超帰省を通じてたくさんの日本を知っていきたいと思うようになりました。
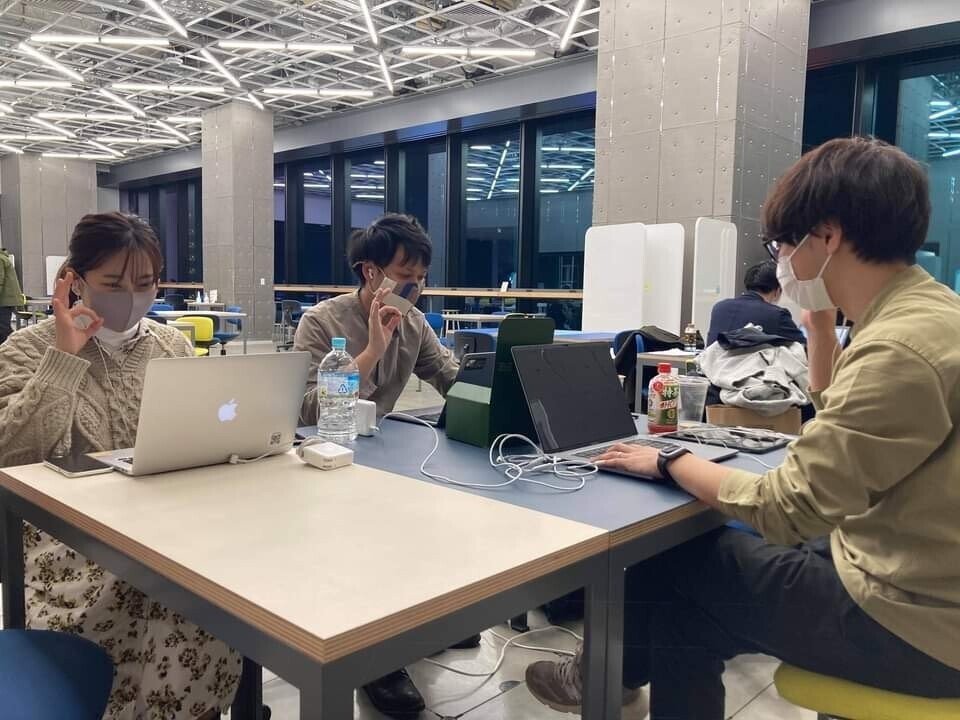
アンバサダーは職業、年齢、性別、居住地など様々な方が参画してくれました。大学生から社会人、地元にUターンした人も、今は地元を離れ東京に住んでいる人、二拠点居住で地元と東京を行き来する人など様々!今後徐々にアンバサダーの取り組みについての情報発信の機会も作っていけたらと思います。
今だからこそできるかたちで超帰省を
本当は毎月でも毎週末でもあちこちの地元に帰省したかったところでしたが、超帰省がはじまったのはコロナ禍真っ只中。なかなか移動するのが厳しいタイミングでした。
そこで実際に移動はできないけど、逆に今だからこそできる企画を展開することにしました。
①オンライン配信「妄想超帰省」
地元に帰る時どんなことするの?もし超帰省したら?
そんなことを写真とトークで展開するオンライン配信を企画!
第一回は沖縄県国頭郡本部町、第二回は静岡県清水市清水区、第三回は高知県高知市。
どのまちも地元出身者だからこそ知っている、かつパーソナリティに則った、そのひとだからこそ見えてくるまちの魅力が盛り沢山でした!
②超帰省アンバサダーの地元を紹介する「超帰省名鑑」
アンバサダーだから知っている地元の魅力を写真とテキストで更新しています。毎週土曜日に配信予定で、これからも定期的に超帰省アンバサダーを紹介していきます!

③TABIPPOさんとオンラインイベント
令和時代・with/afterコロナ時代の新しい観光について考えるというテーマで旅メディアの「TABIPPO」さんのオンラインイベントにゲストスピーカーとして呼んでいただきました。
最もローカルな体験ができることが旅業界の視点からも魅力があることを再確認することができました!


これから超帰省でやっていきたいこと
さて、徐々に超帰省のベースが整ってきたところで、今後どんなことをやっていきたいか。来年の抱負もかねて報告したいと思います!
①超帰省アンバサダーとの連携
まず私たちがはじめたことの取り組みに賛同してくれた50人超の超帰省アンバサダーのみなさんにお礼を伝えたいです!なかなか方針のまとまっていない駆け出しの状態にも関わらず快諾してくださったみなさん、本当にありがとうございます!
そして新年、最初のイベントは超帰省アンバサダーのみなさんとのキックオフイベントを開催!
全国にちらばる超帰省アンバサダー同士の交流と、今後、超帰省というプラットフォームを使ってどんなことができるか、ブレストもできたらと思っています!
任意団体であるので、ぜひ個々のプロジェクトややりたいことと絡めてもらって持続可能な連携ができるかたちを目指していきたいと思います!

②コラボ超帰省を企画!「信頼関係人口」創出へ
この半年間、活動をしていく中で超帰省と一緒にコラボ企画をしてみたい!という声も有難いことにいただくことができました。
例えば、地元で事業をはじめるのでファンづくりをしたい、サウナフェスを開催したい、拠点開発を一緒にしたい!どれも東京などの都市部とローカルを横断した取り組みになりそうなので、まさに超帰省で目指したいひとの流れでした。

そんなありがたい言葉に応えられるように、少しずつではありますが、着実にプロジェクト化していきたいと思います。
私たちが超帰省を通じて目指すものとして「信頼関係人口」という言葉があります。
関係人口ができるのであればだれでもいい訳ではなく、お互いに信頼関係が成立した関係性がないと継続できないと思っています。超帰省は地元愛に基づく取り組みです。私たちの想いがしっかり伝われば必ず信頼関係が生まれると信じています。

そして、この想いに賛同いただける行政・企業・団体様も募集しております!ご興味があります方はぜひ声をかけていただけると嬉しいです!
とはいえ、まずは自分たちがこの取り組みを楽しむこと!それが持続的に継続できることだと考えています。
コロナ禍ということですが、細心の注意を払いつつ、この時代の中で両立できるかたちを考えていきたいと思います。
最後に
2020年、私たちにとって大きな目標に向けた第一歩を踏み出せた年になりました。
そこには支えてくれた多くの方の力があったことは間違いありません。本当にありがとうございました。
また同時にコロナというあたらしい時代への変革期に自分たちが当事者として立っていることも実感しました。地方が生存する上で重要だった観光・飲食という分野でもコロナによって大きな打撃をうけています。その中でこの「超帰省」という取り組みが今後の時代における持続可能な仕掛けとして機能し、社会に貢献できるアクションのひとつになればと願っています。
それでは、長くなりましたがここまで読んでくださったみなさん、ありがとうございました!また来年もよろしくお願いします!良いお年を!

超帰省協会



