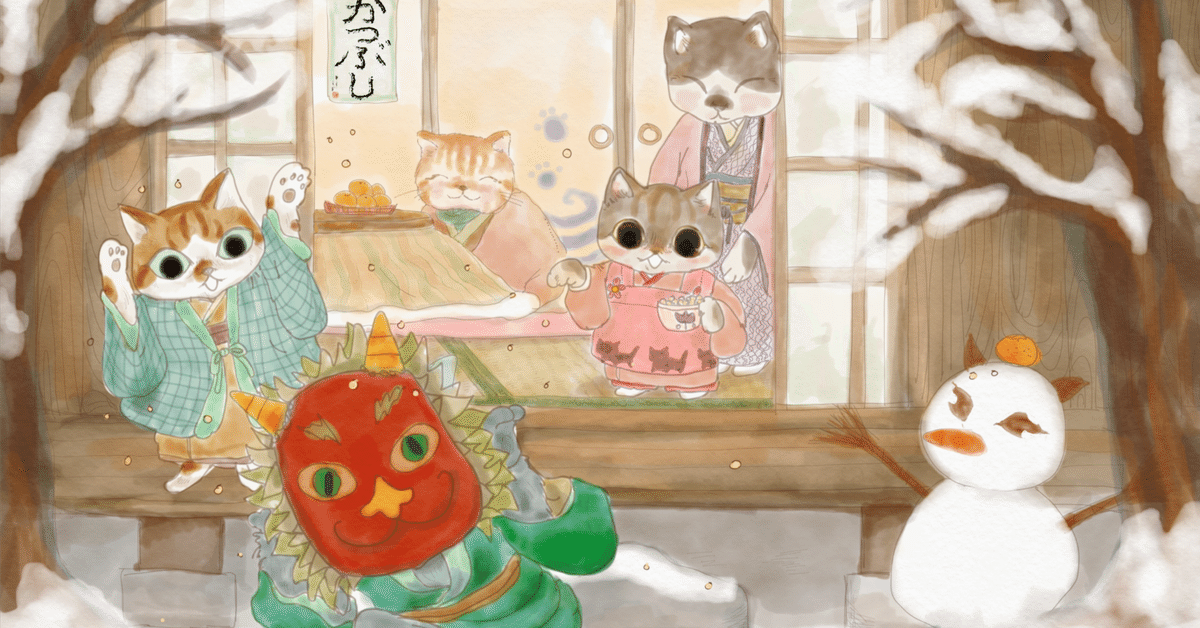
獣鬼玉響
【お知らせ】
本作は設定を変更しエブリスタに引っ越します。
エブリスタ「けもの鬼玉響」
https://estar.jp/novels/26141753
そのためこちらの記事は近日中に削除いたします。(8/13)
1 お巡りさんはオバケがきらい
雨が近いらしい。夜の空気は、重かった。昼間のやらかした自分が頭から離れず、響は大きなため息を吐きだしながら慣れた道を歩いていた。
あと100メートルも歩けばアパートが見えてくる。帰って飼い猫のゴン太を思いっきりもふもふしたい。あのぽにょっとしたおなかをなでて甘いようなにおいを鼻腔いっぱいに吸い込めば、この暗い気分もどこかへ行くだろう。
よし、帰ろう。考えても仕方ない。
そう勢いをつけて足を踏み出した響だったが、妙な感覚を覚えて足をとめた。
電柱の影に男がいる。
薄暗い街灯で顔もよくわからないが、見たところ170センチに少し足りない少し太めのシルエットがゆらゆらと揺れている。
変質者……?
響は、ショルダーバッグを持つ手に力をこめて歩みを進めた。電柱の横を通り過ぎる時、荒い息づかいが聞こえた。
もしかして、泥酔しているのか。
緊張に心臓の音が聞こえるような気がした、その一瞬。男がぬっ、と電柱の影から響の背後に姿を現した。振り返った響は男の腕らしきをつかみ、腹に力をいれて、えいっ、と巨体を投げ飛ばした。
「うわあっ」
きれいに宙を描いて地面にどさりと音を立てて、どこか間の抜けたうめき声をあげた男が、ほの暗い街灯に姿を現した。このまま取り押さえて最寄りの交番に、と考えながら響は近づいて眉を寄せた。
「ちょっと、こんな夜道で女の子を襲うなん……えっ」
たった今投げ飛ばした相手を見下ろして、響は言うべき言葉を忘れた。
どこか打ったのか、うめいている巨漢は確かに先ほど響きが投げ飛ばした相手に違いない。それは間違いない。ただ、そこには大きな問題があった。
「うー……痛い……」
鳥だった。
響の1歩半先に転がってじたじたとうめいているものは、やたらにデカい鳥だった。
それも人間大の、いや丸い体型のせいでさらに大きく見える。
「……きぐるみの変態?」
ハロウィンで羽目を外して逮捕されてしまう、あのタイプだろうか。そう思った響は、徐に空へと突き出ているクチバシを掴んでみた。
「ふぶっ! うぶぶぶぶうっ!」
太い鳥は予想外だったのか、突然クチバシを掴まれパニックになったらしいが、それは響も同じだった。
「えっ、なにこれ、生えてる?」
「ふぶぶぶっ、びたっ、びたっふぶっ」
鳥は涙目でジタバタともがき始めた。羽根がバッサバッサと舞うのだが、腰を打ったのか転がったままで羽を動かすので、非常に視界がうるさい。羽が顔に当たるのを避けてるとどうやら、わめく中に痛い、と聞こえて慌てて手を離した。
手を離すと、鳥が頭を振るいながら体を起こした。
一歩下がってみると、改めてとんでもないデカさの鳥だった。
人間の身長ほどある。見た目は鳥だが、どう常識的に考えてもこれは、クチバシが突然変異で生えたか美容整形で取り付けた成人男性だろう。
じゃなければ、こんな流暢に人間語を話せるわけがない。
「あああっあなたね、なんなんですか! い、いきなり人のクチバシつかんじゃダメでしょ!」
その前にぶん投げられてるのだが、鳥が体を起こして放った第一声は、それだった。
「なにわかんない事いって、……あ、いや。明らかに不審者の動きでしたよ、それにその格好、パーティーでもあったんですか? あんまり飲みすぎたら体にもよくないですよ。さ、帰れます? 立てるかな……」
鳥の腕を支えてやろうと手を伸ばしたのだが、触れたのはどう考えても羽である。最近の着ぐるみはリアルだな、などと感心しながら鳥を立ち上がらせた時だった。なにかがものすごい速さで飛んできた。虫か、と顔を向けた響の口にそれが吸い込まれるのを見ていた鳥の顔に、驚愕が広がった。
「ん? やだ、虫?」
「あああああああああああ!」
突然叫び出した鳥は、驚愕から絶望の表情に変わっていた。コロコロとよく変わるうるさい鳥人間だな、と思いながら交番に連れていこうかと考え始めていた。万が一だが打ちどころが悪かった可能性もある。
「あの、とにかく落ち着いて」
「落ち着いてられますかって!」
「ね、話ならお巡りさんがちゃんと聞いてくれるから、とりあえず落ち着いて」
「あなた、あなたね、あなた、い、いくつです?」
「へ? 年齢?」
「に、二十代前半ですかっ?」
「この期に及んで、ナンパ? いやまあ、そうですけど。それがどう」
「ああならまあ寿命も、いやいや、そういう問題じゃない、ちょっとこれは大変な事ですよおおおおぅぅもぉだめぇぇぇぅぅぅ……」
やはり酔っ払いか、と思いかけた響だったが、わけのわからない言葉を放った鳥は、目の前で縮み始めた。文字通り、縮み始めた。「えっ、えっ、なに、なん」響よりも背の高かった丸い鳥はあっという間に小さくなり、手のひらに乗るサイズになった。
あっけに取られた響は、あたりを見渡すが、先ほどまでここに横たわっていた巨大な鳥はどこにもいない。
いるのはーーーー
「よくも大事な玉を飲み込んだな! 一生お前に取り憑いてやるぞ!」 人間語を話す、手のひらサイズの鳥だった。
六畳のリビング兼ダイニングと、四畳のなんとなく寝室として使っている部屋の窓ぎわは狭い。経年した安普請のせいで窓もサッシも何もかもが薄いせいだろう。窓の木枠すらも幅が狭いのだ。そこにふくふくと太った猫がいる。ほお肉とその上にむっちりと存在感を示す茶色と白の毛並み、三角のような鋭い眼光を携えた全体的にまるいフォルムは、怒りのために毛を膨らましていた。これ以上ないほどに、まるい。
窓枠など、今にも折れそうに頼りなく見える。
「シャアアアアアアッ」
「ぎゃああッねねねね、ねこッ!」
鼻に皺を寄せて威嚇するデブねこの先には、白と黒の手乗りサイズの鳥がいた。
「そりゃ猫だもん、警戒くらいするでしょ。あー疲れた」
極めて当たり前である。ただ、その鳥が人間語を話す以外は。一日の労働を終えて帰宅した響はさっさと風呂でさっぱりとしたい気持ちを横に置いて、ちょうどゴン太と鳥の間に立ちはだかった。
「ちょーっと静かにしてね、ゴンちゃん。とりあえず飛びかかっちゃだめ」
「とりあえず? え? とりあえずって言いました? あーた?」
「不審者として身柄確保の方がよかったかな? ーーうちに勝手についてくるし、道中での説明は何が何だか意味不明だし……説明してくれると助かるんです。このままじゃ調書もとれません」
ペットボトルの蓋に水を入れて置きながら、響がいう。
手のひらサイズの鳥は、威嚇をやめないゴン太をチラチラ見ていたが、仕方ないと小さなテーブルの端にーなるべくゴン太から遠い場所にージリジリと下がってから話しはじめた。
鳥が語った話とは、こういうものだった。
鳥は、鳥野尾次郎というらしく、出身はここからかなり北上した山深い地域で、鳥鬼という一族なのだという。鳥鬼は鬼の一種で、普段は人の形をして鳥鬼の村で生活しているおとなしい鬼だが、時代の要人について護り付き従う影の如き存在なのだという。
「というわけでして、鬼とはいえ決して乱暴を働くものではないのです。むしろ人間に近いですし、コンビニ大好きですし、最近ちょっとメタボも気になりますし」
「えっ、じゃあもしかして、私って日本初女性の警視総監とかになっちゃうのかな!」
「へ?」
「だって! だって今、時代の要人につきしたがうって! さっき一生取り憑いてやるって言ったよね!」
「あー……あー……はあ、えと……ちが」
「わたし、これでも警察官で! ああでも失敗ばっかりで今日も注意されちゃって、ああダメだなぁって落ち込んでて、でもよかった。そんな鬼がついてくれるなら、きっと大丈夫ってことなのかな、どうなの鳥さん?」
勢いよく正座した響は、テーブル端の尾次郎をじっと見ながら聞いている。
「えっ、あっ、普通はもうちょっと驚いたりするん……まあいいか。えーっと、だとしたら、追い出しません?」
「しないしない! 大事な鬼さんに、そんなことしないよ!」
「そこのデブねこの餌にしません?」
「シャアアア「ちょっと黙っててゴンちゃん! しないよ、ゴンちゃんダイエット中だから!」アアーーーーッ!」
威嚇するゴン太と笑顔がはじける響を交互に見て、鳥は目を笑みに細めた。
「……じゃ、そうですね、そういうことです! よろしくお願いします、警視総監!」
「わあ! こちらこそ!」
響は尾次郎に握手の手を差し出したが、よく考えたら羽だったので、少し考えてやめた。
やったあ! 警視総監だ! と言いながら帰り道とは真逆の踊りだしそうな勢いの響はゴン太に鳥さんにちょっかい出すなと言い含めてから、風呂に消えた。水音が聞こえ始めた頃、リビングに残された鳥ーー尾次郎は、水を飲んでからちら、と窓の方を見た。
その視線に気づいたらしいふてぶてしい顔のゴン太が、じっとりと尾次郎を見てからトン、と軽い音を立てて床に降りて向かってくる。
じっと尾次郎を見つめるゴン太はゆっくりと近づき前足で尾次郎の足元にどん、と重いパンチを繰り出した。
食われるのかーーーー
ゾッとした尾次郎が後ろにジリジリと下がるが、そこはテーブルの端である。見れば、ゴン太の目がまんまるになって尾次郎の動きを見つめている。明らかにこれは、鳥ならば飛んで逃げるべき場面だ。
だが、尾次郎は飛ばなかった。ゴン太と尾次郎との睨みあう緊張はずいぶんと長く感じられた。
だがいくらゴン太が前足でテーブルを叩いても、尾次郎は飛ばない。
食われる、と尾次郎が目を閉じた時、ゴン太から深いため息がでた。尾次郎が目を開けると、つまらんやつめ、と言いたそうにふいっ、と踵を返して隣の部屋へとゴン太は姿を消していった。
「見かけによらずいいひと(ねこ)さん……とか?」
そんなわけ、ないですかね。
そう尾次郎はつぶやいた。
2 響さん、出動です!『パーティーは楽しくても程々にね』
少年課の先輩が廊下を歩いていくのを、書類に埋もれながら響は小さくため息をついた。
苦手な書類作成はカラフルな付箋がA4用紙からはみ出している。七夕の短冊みたいだと思ったが、こちらは願いがかなうどころか真逆の雰囲気だ。
総務課に配属の新人である響は、まだ昼前だというのに既に帰りたい気分だった。
ただし帰宅しても癒されるわけではない。
白黒の小さなしゃべる鳥、尾次郎がやってきた夜から、響の小さなアパートは戦場だった。猫のゴン太にとって小鳥など格好のターゲットになるのは火を見るより明らかだし、おまけにゴン太は元野良猫でシェルターに保護される前はボス猫として君臨していたらしい強者だ。
どう考えても、尾次郎などは餌であろう。
だがしかし尾次郎は自らを鬼の一族だと名乗り、事実最初に出会った時は人間大のサイズだった。
鬼族の掟で主人から離れられないらしく、ゆえに響の自宅はしゃべる鳥が逃げ、元ボス猫が狙うという一触即発の野生の王国となっているのだ。
おまけに仕事もうまくいかない。誰かの力になりたくて警察官を目指したのに、配属は総務課で仕事は苦手な書類に埋もれている。
憧れはますます遠くなるような気がした。
「はぁ……」
癒しが欲しい、と願う響はもう行ってしまった憧れの先輩の歩いた方向へ目をやるが無人の薄暗い廊下があるばかり。
うまくいかない時は何をやっても上手くいかない。響の願いとは裏腹に書類と注意と書き直しで数日が過ぎたころ、管轄内で大きな事件が発生した。
多くの人員が動員されたが、決まった仕事をこなして帰宅した。捜査人員ではないのだから当たり前なのだが、緊迫感を漂わせる人々を視界の端に入れながら、どこか寂しいような悲しいような思いを抱きながらアパートまでの道を歩いていた時だった。
夕闇がおりた公園前で、眉をひそめ立ち話をする人々を見かけた。見知った顔だった。ゴミ出しで見かける顔の中に響の住むアパートの大家がいた、と思ったら同じく響に気づいたらしい大家がおおい! と呼びかけた。
「ちょうどよかった、あなた302号室の曳屋さんだよね。あなた確か刑事さんだったよね!」
「えっ」
ここで違うと言えばよかったのだ。
「いやぁ、ちょっと困っちゃっててね…よかったプロがいたよ!」
「えっ」
ただのしがない事務職です、書類一つまともに仕上げられず今日も上司に注意されております、と言えばよかったのだ。
「助けちゃくれませんかね、もうみんな困っちゃってて」
「助ける……わ、わかりました。どんなことでしょうか」
大家と周りに集まった人々は安堵の色を覗かせ、響もつられて笑顔になったのだ。
「それがね……出るんだよ」
そう言って大家は胸の前で両手首をダラリ、と垂らした。
肘を曲げ、胸にひきつけた上で手首から先の力をぬくジェスチャーが示すのは。
おばけ、幽霊、人ならざるもの。
響の天敵である。形のない存在は、意味もなく不安にさせられ苦手というよりも大嫌いだ。ガスなどの気体も形がない上に有害だったりするから、意味がわからない。すみません、そういったものは管轄外で、と言いたかったが、タイミングを逃した響は気がつけば大家の案内でとある一軒家の前にいた。
「ここは……」
築年数は20年そこそこだろうか、蔦が壁を這いあがる戸建てには灯りもなく夜に沈み込んでいる。
「曳屋さんも知ってるかなぁ、空家なんですよここ2年ほど。以前は貸家だったんだけど、持ち主のお爺さんが亡くなってね。相続やらなんやらでまあほら、色々と。誰かに貸すにしてもリフォームやら要るでしょう。誰も借り手がいなくて、ほら雑草なんかも伸び放題でね、近所の人も困ってるんですよ」
「はあ、」
「今の持ち主、ほら相続した息子さんだか娘さんだかがいるにはいるんだけど遠方でねぇ。秋口なんかにあまりに雑草がひどくなると連絡とって草刈りしてもらってるんだけど……そろそろ始まるかな」
なにが、と聞き返そうとした不意に、それ、を聞いた。最初は虫の音かと思ったのだが、それは次第にはっきりとした音になった。
「え、音楽?」
そうだ、と頷く大家の顔からこれがいつものことらしいと知ったが、聞いているうちに音量はどんどん増していき、ついに大声でなければすぐそばにいる大家の声も届かないほどになった。相当な騒音である。
いつもこんななんですか! と声を張ったら、耳を押さえながら大家が頷いたので確実である。聞いていると曲のジャンルはバラバラだが、とにかく音量が半端ない。これでは近隣の人はたまらないだろう。大家はあとは頼む、と言わんばかりに響に頭を下げながら退散していった。
これは耳がやられる。急いでバッグからイヤホンを取り出して耳にしたら、だいぶマシになった。要は民家での騒音問題だ。一応これは立派にお巡りさんの出番案件である。唯一の問題が、誰もいないはずの空家というところだが……
「きっと誰か勝手に住んじゃってる人がいるんだろうな」
生身の人間が相手なら、話は違う。
応援を呼ぼうにも今夜は大きな事件で出払ってるわけで、誰か来るにも時間がかかるだろう。たまたま居合わせて市民に頼られたのだから、これは警察官として対応しないわけにいかない。と響は勝手に判断した。
「よし」
意を決した響は草がぼうぼうと生い茂る庭へと足を踏み入れた。玄関で呼び鈴を押してみたが、反応はない。引き戸に手をかければすっ、と抵抗なく開いた。
「ごめんくださーい」
玄関の上り口、タイルにも靴は見当たらない。スマートウォッチのライトを照らしてみるが、相当な埃で板床は白っぽく見えた。他人の家に勝手に入るのが申し訳ないと思いながら、靴を脱いで上がり、音の出元を探した。しかし曲の傾向がまるで一貫していない。さっきまでは荘厳なクラシックだったのに、今は現在進行形でCMで流れる曲だ。さっぱり趣味がわからないが、パーソナリティの登場もないからラジオではないらしい。
玄関入って廊下の左右に部屋があるが、どの部屋を見ても人気はない。響が歩くたびに床が体重で軋むが、音の出元がわからない。残されたままの家具が埃を被るダイニングに入った時だった。
ギシッ
曲の合間に、体重に軋む音が天井から降ってきた。
「2階だ」
響は廊下の突き当たり、階段へと向かった。相変わらず埃だらけで白っぽい階段を登っていくと、音はさらに鮮明になってきた。イヤフォンをしていなかったら、鼓膜が危なかったかもしれない。曲が繰り返すサビに差し掛かった時、一際大きな音のするドアのノブをゆっくりと回した。
そうっとひらく扉の向こうには、微かに灯りが見えた。やっぱり誰かがいる、と緊張を感じながら押すドアがいっきに引かれた。バタン、と扉が閉じる音が聞こえて、なにが起きたのか、と部屋に引っ張り込まれた響は部屋の中を見て、
「イェぇぇぇぇぇぇぇぇぇッ! 盛り上がってるかぁぁぁぁぁぁイィぃッ!」
思考停止した。
ぐるぐる回るカラフルなライトに、ミラーボール、大音量の音楽。天井からライトまでがあちこちを極彩色に照らしている。
「……は?」
その中心に、ちゃぶ台。
まるいちゃぶ台に乗って、スパンコールのドレス。
「フォぉぉぉぉぉぉぉーッ!」
羽根を背負った人物が、踊り狂っていた。
派手なでかいサングラスに、ラインストーン。スパンコールが光を跳ねまくる。
「なっ」
なんなんだ、と口にしたが大音量でまったく自分の声も聞こえない。
「あの、あなたここの住人ですか! ご近所から騒音で迷惑してると聞いてきたんですが!」
踊りまくるスパンコールは、おそらく響がいることにも気がついていない。
頭をぶん回しているんだから、見えてたとしたらある意味びっくりだ。両耳をふさいでとりあえず音源を探すことにした響は、見つからないように体を低くして見渡した。
畳の部屋、その角に小さなラジオが転がっている。
どうみてもかなり古い小型のそれから、どうやってこの音量が出ているのか知らないが、近所の迷惑なのだ。そしてこんな音量の中にいたら健康被害だってでる。
まずは音源を落とさなきゃ、話もできない。
部屋の隅までジリジリと近づいた響が、ラジオに手を伸ばし触れる瞬間。
音楽と明かりが消えた。
しん、と急に訪れた沈黙と暗闇。かさりと乾いた音が背後に聞こえた。
「あれ、リモコン? あ、あの私すみません勝手に入ってきて。実は私、えと、こう見えて警察のものです。ご近所から騒音の苦情が……」
静かになった人物を向いて、話しかけた。カーテンもない窓からぼやけた街灯の明かりがわずかに入る暗さ。目が次第に慣れてくると、サングラスのラインストーンが見える。
「……ゆるさない」
「えっ、あ、すみません。一応靴は脱いだんですけど、反応がなかったもので、勝手に入ってしまいました。でもですよ、さっきまでのあの音量ね、少し離れたご近所まで聞こえてたんですよ。それにあんな大きな音の中にいたら耳が」
「ゆるさない! ゆるさないゆるさないゆるさないゆるさないゆるさなぁぁぁぁぁ」
ぞわりとした。男か女かわからない小柄な人物は、響よりも小さな体をぶるぶるとふるわせはじめ、その声は地鳴のように部屋を揺らしはじめた。ガタガタと軋む家の揺れは大きくなり、窓ガラスはついに耐えきれずにひび割れ、冷たい音を立てて落ちた。
揺れる床の上に立っていることもできない。畳に膝をついた響は、ゆるさない、と繰り返し続ける人物を見上げた。
ああ、これは人じゃない。
小柄な体は、暗闇の中でどんどん天井へと昇ってゆく。浮いている。足場も何もない空中を浮いている。生きている人間がどうにかできる相手じゃない。
「ゆるさないゆるさないゆるさないゆるさないいぃいぃぃぃぃ」
揺れる畳に座り込む響を、それ、は見下ろした。
「せっかくのぉ、パーティーぉぉ……邪魔する奴はあああああああああ!」
殺される、そう目を閉じたとき、どこからか吹き込んだ風を肌に感じた。
「ぐるにゃあああああああおおおおおおぉぉぉう!」
「ちょっ、ちょっと待って、って、くださぁぁぁぁぁい! ちょっと待っ」
シャァッ! と激しく切り裂くような声とともに、茶白の毛玉が飛び込んできた。なぜか背中に白黒の小さい鳥を乗せている。
「えっ、ゴンちゃん?」
と、鳥? 鳥?
響が暗い中で二度見する中、ゴン太は天井近くにいるそれ、に向かって威嚇を繰り返し、鳥は何やらわあわあと言いながら、響に向かってきた。
「響さん、あなた、あなたね、なんてとこにいるんですか、いやちょっといきなり危ないでしょ」
「え、なんで。尾次郎? なんでゴン太と一緒にここにいるの? うちロック付きのサッシでしょ、どうやって開け」
「どうやって、ってそりゃ」
「シャァァァァアッ!」
ゴン太の威嚇が返事のように尾次郎を遮り、「ああわかりましたって! 動きゃいいんでしょ動けば!」と尾次郎は響の後ろにあるラジオへとテクテク走った。いまいち緊張感のないてくてく走りなのだが、仕様なので致し方ない。
「それに触るなぁあああああああああああ、それ、それにぃいいいいいいい」
尾次郎がラジオに触れる間際、それ、が阻もうと向かってきたがゴン太が飛び上がる方が早かった。ゴン太の前脚と爪のパンチにぎゃあっ、と叫びをあげたときには、尾次郎はもうラジオの電源ボタンに乗っていた。
カチリ、と小さな音がして、それ、は空気の抜けた風船のように小さくなっていった。
ちゃぶ台の上に小さな、響の手のひらに乗るほどの大きさになったそれ、は黒い服をきた少年の姿をしていた。
「……どういう、こと。なに、これ」
あっけに取られる響が、つぶやくと尾次郎が困ったように羽を揺らした。
「ああええとどこから話したらいいのか……とりあえずこの方、ラジオの付喪神さんです。たぶん」
「多分?」
「はあ、まあご本人から聞くのが一番手っ取り早いかと……どうでしょ、お話しできます? 色々あるんでしょうから、お話くらいは聞きますよ、どうです? あーた」
尾次郎に促された尾次郎と似たサイズの少年は、しくしくと泣き出してしまった。
「……なさけないよう、付喪神だなんて、妖怪にバカにされちゃった」
「よっ、妖怪ですって! あーたね、なにを言っちゃってるんですか、ぼ、僕はれっきとした鬼なんですよ、妖怪なんてあんな低級な連中と一緒にされちゃたまりませんよ。いいですか、ちょっとなんだか可哀想に思って優しくすればつけあが」
「あーもういい、話がややこしくなる。事情を聞かせてください。ええと、自称ラジオさん、でいいですか。現在時刻は午後10時を過ぎています。この時間に先ほどのような大音量を出すということはご近所の迷惑になる、そういうことはわかりますかね?」
「あのぅ、響さん? そういうことじゃないと思うんです。鬼である僕が思うに、そもそもラジオが化けることになった理由を聞かないと、こういうお化け的な事案は解決しな」
間に割って入ろうとした尾次郎だったが、ラジオ少年はこくりと頷いた。
「……はい。わかっています」
「え、そこ認めるんですか」
「どういった事情があるにせよ、住宅街でのこういった迷惑行為は近隣トラブルの元にもなりますよね。やっぱりほら、ご近所とはうまくやった方がいいと思いませんか」
「はい、そう思います」
「思うんですか。ラジオのくせに」
「ちょっと鳥さん、黙っててくれないかなぁ、全く。すみませんね、話がそれて。ええとじゃあ、今後はどうされますか。イヤフォンとか、そういった手段じゃダメですか」
「やっぱりその、直に音を聞いて踊りたいんです」
「なるほど、それは困りましたね。音量の点はなんとか改善したいところですが……ところで、先ほどからうちの鳥さんがあなたのことをラジオ出身の方と言っているんですが、これは正しいですか?」
「はい。実はぼく、こう見えて元々はそのラジオだったんです」
「だった?」
「……はい。この部屋、前はこども部屋でナオトの部屋だったんです。もう大きくなってこの部屋にはいないけど。ナオトがいなくなってから、しばらくは部屋の中のものはそのままで、その頃はいつ帰ってくるのかなぁってぼんやり思ってたくらいで、でも長い時間がたって気がついたら……ぼく以外の家具とか服とか、ナオトの持ち物はみんななくなっていて」
とつとつとラジオ少年が語。る言葉が途切れた。はあ、とため息に続いて尾次郎が頷いてラジオからちゃぶ台の上へと飛び乗った
「あーたも苦労したんですねぇ。付喪神っていうのは、そういうものなんですよ。長年大事にされた道具に魂が宿ってしまう、だけど人はそういう変化したものを生活の中に取り入れてはくれません。道具は物言わずに動いてこそなんです。だから、大抵は供養されて人の生活からは消えてゆく。悲しいものです。って田舎のばあちゃんがよく言っ」
「だまれ鳥! ぼくは悲しくなんかない! ナオトは立派な大人になってここを出ていったんだから! きっと欲しがってたステレオがある家に住んでるんだ、成功して、きっと素敵な生活をしてるに決まってる!」
「うーんでも、でもですよ。その素敵な生活には連れてってもらえなかったわけでしょう。それが怨念になって、付喪神になっちゃったんじゃ……本当はナオトに会いたいんじゃないです?」
小首をかしげながら尾次郎が問い掛ければ、ラジオ少年は唇を噛みしめた。少年なりになにか思うところはあるのだろう。尾次郎はナオトを探すことを提案したが、少年は気が進まないという。だがこれでは埒があかない。響の提案で、大音量で音楽を流しても問題のない場所を探すことになった。そして見つかるまでの間は音量を少し下げることと時間帯を午後8時までとした。
「選挙カーと同じ時間帯ですね、考えましたね、響さん」
「まあねぇ。って、つっこんでいい?」
「なにがですか?」と黒くて丸い目で見返してきた鳥の尾次郎は、ゴン太の頭の上にいる。そしてそのゴン太は、響におとなしく抱っこされている。
「鳥さん、って鳥だよね。なんで飛ばないの」
静かになった近所の夜道を一人と一匹と一羽で歩いているのだが、リードもないゴン太は抱っこするしかないのだが、鳥に関しては解せない。
「いいじゃないですか、細かいことを気にしてたら小皺が増えますよ、って余計なお世話でした」
「まだ若いから小皺とか気にしてないけど、それよりなんでゴンちゃんと鳥さんが一緒にいるのかとか色々意味がわからないんだけど、その説明はしてくれるの」
「あ、そうでした! えーと、どこから説明したいいのか……あれっ、あ! あれですよ、外がザワザワっとしてですよ、んでゴンさんがアババババって、そんで、ドシャって、で! 乗ってけって、で! どどどーっと! いやぁすごい勢いで! 乗り心地もかなり荒っぽくてですね、なかなかなジェットコースターな感じでした! というわけですよ」
さっぱり意味がわからない。
黒目をキュルルンと丸くして見上げてくるのだが、響はどつき倒したい衝動を抱いた。
あいにく両手はでっぷり太った茶白ねこ(オプションに鳥)を抱いているので、頬が引きつるだけなのだが。
「あの、ザワザワ、アババ、ドシャ、どどどー、だけじゃ全くわからない……」
「そうです? こんなわかりやすいのに?」
どうしてやろう、この鳥。
偉い鬼とかじゃなければ焼き鳥にしてやりたい、と響の頭に不穏な考えがよぎった時だった。
「……ふん、使えん鳥だにゃ。妖気がただよっていたにゃ。夜になると濃くなる匂いに、今夜は響の匂いが重なった。特異体質の響をそこらの妖怪に遭遇させるわけにはいかないから、にゃ」
にゃ。
響は足を止めた。
石になったように固まった響の腕の中から、その声は聞こえてきた。そしてゆっくり、茶白の丸い頭が響をちら、と見上げた。
「……ゴン、ちゃん……ゴ、ゴ、ゴン……ゴンちゃんが……ゴンちゃんがしゃべった!」
3 ゴン太はイケオジ?それともおじさん?
それは、鳥の尾次郎がやってきた最初の夜だった。風呂に入った響がいない部屋の中、ゴン太と尾次郎は沈黙の中にいた。どすどすと隣の部屋にいった茶白のデブねこは、暗がりの中から光る目を細めて尾次郎を睨んでおり。
その張り詰めた空気に耐えきれなくなったのは、尾次郎の方だった。
「あのー……ゴン太さん、ですよね。ちょっと聞いていただけます?」
おずおずと心持ち、テーブルから和室を覗き込むように小首を傾げたが、ジリとも和室からは反応がない。
「ええと、ですよ、いま私こんな格好ですけど、本来はちゃんと人間の体を持っておりまして、そのう、訳あってあなたの飼い主である響さんのそばにいないといけないわけでして、それはその、僕の一存ではどうにもならないと言いますか、ですのでそのーできればエサにしないでいただきたいんですけど、……あのー……聞いてます?」
反応のない和室をちょいちょい、とテーブルの端から見やれば、キラリと緑の目が光った。
「……んぁーーーー」
返ってきた声は、あまり友好的ではなさそうだ。
猫に何を言っても仕方ない。尾次郎は諦めて、身の安全を確保できそうな場所を探し始めた。鳥籠など気の利いたものがあるわけもない。そもそも響は鳥を飼うつもりもなかったのだから当然だ。
通気性があってなおかつゴン太から身を守れそうな頑丈な箱……とりあえず通販のダンボールに入ってみた。響がいい加減な開け方をしたんだろう、適当な穴が空いており、まあまあ通気性はよい。
今夜の宿はとりあえずここにするか、と尾次郎が座ったときだった。
「にゃあ」
頭上に、でっかい猫がせまってきた。
「……!」
喰われる、と思った尾次郎が白目になったが、「おまえも、鬼かにゃ」続いた言葉に今度は言葉を失う羽目になった。
「 えッ、えッえええええええええッ!」
「うるさいやつにゃぁ」
「えっ、えっ、ゴン、ゴン、ゴン太さんあーた……、まさか、あーた猫鬼……さん……です……?」
おびえつつ聞き返す尾次郎に、ふう、と鼻息を返したゴン太は、ダンボールから顔をあげると何やら口の中でモゴモゴと唱え始めた。うっすらともやがゴン太の頭上に浮かび上がり、見る間にゴン太の全身を包んだ。薄いもやは白から黄金に色をかえ、渦を巻きながらまぶしくいっそう輝いた。
「よう、トリ」
眩しさに目を閉じた尾次郎が見上げると、派手なオレンジ色の頭をしたちょっと渋めのイケオジがダンボール覗き込んで笑っていた。
⬜︎
見慣れたでっぷりと太ったオレンジ色のもふもふを抱えながら、響はフリーズしていた。
「イケオジ……? ゴンちゃん……が……? メタボで獣医さんにダイエットダイエット言われてるゴンちゃんが、イケオジ……?」
「猫の体はアバターみたいなもんだからにゃ。変幻自在にゃ」
まじまじと見つめると、ふっくらしたマズルをムフッ、と自慢げに膨らませて見上げてくる。この立派な顎肉も、腹肉も、背中に乗った肉も、本体に戻れば全てがチャラになるらしい。
「なんちゅううらやましい……」
「本体と鬼化した変化体とをうまく切り離せるのは、上位獣鬼であるあかしにゃ。とくに犬猫は人間界に入り込みやすいぶん、切り離せないと困ったことににゃるからにゃ」
「そうなんだ……なんか、わたし全然しらなかったよ。ゴンちゃんが本当はしゃべれて、本体が本当は人間のおじさんだったなんて」
「イケオジとよべにゃ」
「そうですそうです! ゴン太さん、なかなかのイケオジさんで!」
合いの手を入れた尾次郎を見下ろしながら、響はフーン、と言いながら目を細めた。
「で、君たちは鬼同士でなかよく秘密を守りながら家主であるわたしには内緒で楽しくやってたわけですか」
「そそそそれは誤解ですって! われわれは響さんの身を守ることを共通の目標として手を組むことにしたわけでしてね、だってほらぁ、いきなり飼い猫がおっさんでしたなんてびっくりでしょ!」
「誰がおっさんにゃ」
「あばばばばばば」
「喰ってやるにゃ」
「んぎゃぎゃぎゃぎゃ」
「ちょ、ちょっと人の腕の中で暴れないでよ! 鳥さん、ちょ、頭に乗らないでって! 微妙に痛い!」
賑やかな夜がふけてゆく。
⬜︎
ラジオの付喪神、ラジオ君は響が帰宅時に様子を伺いに行くことにした。音量や時間などはさすがラジオ出身だけあって、正確に理解してくれた。ただ、どうにも不安定そうな様子に、放っておくことはできなかった。数日ほど、めずらしく同僚たちと食事にいった響が立ち寄らなかっただけで、爆音パーティーが再開したのだから、わかりやすい。
これはもう完全なる、かまってちゃんである。
ゴン太が様子を見にいってやる、と提案したのは良かったのだが、それが果たして猫の姿なのか、人間の姿なのかで少しもめた。
響としてはイケオジなゴン太に興味がないわけではなかったのだが、まるくてもっちりもふもふで冬は一緒にふとんに入る愛猫が実は人間のおっさんだった、などとは決して認めたくないのが本音だった。
いや猫でも十分におっさんなのだが。
猫なら許せても、人間ならアウトなのだ。
そして、もうひとつ困ったのが鳥である。
なぜか色々とついて回るのだが、仮にゴン太がラジオ君の様子を見に行くとしてもついてゆく気満々なのだ。飛べないのか飛ばないのかわからないが、てくてくと小さな足で歩いているかゴン太の頭にいるかの姿しか見たことがない響には、いまいち不安要素でしかなかった。
緊急時になれば飛べるのだろうか。
初対面の夜にいきなり本来の鳥らしいサイズになってから、一度も人間大の姿を見ていないので、しゃべらなければただの鳥である。
彼らのいう鬼の世界はよくわからないが、平和ならそれでいい。
「ま、いっか」
あまり深く考えるのが苦手な響は、ゴン太が尾次郎を食べないのならそれでいい、と結論づけた。
「え?」
声に意識を戻すと、コンビニの店員が箸を手に怪訝な顔をしていた。
「あ、いえいえいえ、お願いします。お箸」
へらっ、と愛想笑いを浮かべて買ったものを受け取り道に出ると、もわりと湿り気を含んだ夜に包まれた。街灯とビルの灯りが明るさを保っている夜だ。その中を歩き出そうとして、響はつん、と鼻に届いたそれ、に気づいた。
ーーーーラジオ君のにおいだ
それはあの埃と共に取り残されたラジオが転がる部屋の匂いだった。
匂いの方へ顔を向けると、今まさにすれ違おうとするサラリーマンだった。
三十代後半、男性。安っぽいスーツに、汗が滲んでいるだろうシャツの襟。顔は見えなかったが、なぜか響の脳裏にはある光景が広がっていた。
それは、雨の日。サッシに雨つぶが落ちる薄暗い午後に、少年が床に転がって何をするでもなく部屋にはラジオが流れている。十代半ばのナオトと、そして今よりもツヤのあるラジオの姿だ。
好きな曲が流れてきたのだろう、ナオトがラジオにあわせて口ずさむ。
ふんわりと、若いナオトの感情が流れてくる。
未来への期待と、不安と、希望と、日々のいやなこと、旋律と一緒に、ふわりと流れてかき消されてゆく。
ーーーーああ、これはーーーー
コンビニの店内を振り返ると、そこには背中を丸めて棚の前に立つナオトがいた。
⬜︎
ちゃぶ台の上で尾次郎は、困っていた。鳥の顔面は基本的に羽毛に覆われているので、あまり喜怒哀楽が激しいわけではないのだが、それでも眉間らしき場所が中央に寄っている。
「ちょっと何いってるのかわかんないんですけど」
「鳥の舌ってすごいよな、よくそれだけ完璧に人間語を話せるよ。猫は無理だわ、舌がうっすくて」
眉らしき場所を寄せる尾次郎の視線の先、人間の姿にもどったおじにゃんゴン太は、ちゃぶ台に肘をつきあぐらをかいた格好でテレビのチャンネルをかえた。
「話を逸らさないでくださいって。ゴン太さん、どういう意味です? 響さんは寄せ集めちゃうって」
「どうって、あーまあ、わかりやすくいうと、ハエトリとかあるじゃん、あれ。人ならざるものを寄せちゃう磁石みたいなタイプなんだよ、響の家は代々。だから俺らみたいなのが必要なの。代々」
「人ならざるもの、って幽霊とか妖怪とか、この間の付喪神とかですか」
「まーそう。大変なんだよ、どこいってもあっちゃこっちゃひっつけてくるし……お、県大会はじまったかぁ。ビール買い置きあったっけ」
ハーフパンツにTシャツという、いかにも部屋着な格好の人間版ゴン太が冷蔵庫を開けたところで、尾次郎はハッ、と顔を上げた。
「ハエトリに寄せられるハエってことですか、まさか、僕たちも!」
「んー、俺はちがうかな。鳥鬼もあるだろ、里の掟。長老だかが若者が独り立ちの時に占って、それぞれの仕える主人を導くしきたり」
「……あります」
「俺とか響の家についてる鬼は、そのしきたりで導かれてるわけよ。だから自然発生で鬼がついてきたのは、お前が最初なの」
鳥野尾次郎は、しばし何も言わなかった。情報を処理するために必要な沈黙は、ゴン太がビールの缶を半分ほど空にするまで続いた。
「ええっ、えっ、てことは、響さん一族には鬼がそれぞれついてる……?」
「まーそういうことよ。わかりやすくいうと。んー枝豆かなんか欲しいねぇ。あったっけ……あー、カリカリしかない……萎えるわぁ、せめてモン◯チのウェットとか……ツナ缶あったっけ……」
つまみを探し始めたゴン太の背後、ちゃぶ台から尾次郎がぶつぶつと呟いている。
「自然発生で鬼、って言い方には異議がありますけど、まあいいです。いいいですけど、響さん一族には全員、鬼が……そんなの某アメリカ元大統領一家くらいしか聞いたことがな……ああ、徳川さんちとか……いやいやあれは歴史の解釈が鬼研究家の間でもわかれるって確かばあちゃんが……」
こん、と軽い音を立てて小さなお猪口が置かれた。
「ほれ、あんま深く考えんなって。お前も飲めるんだろう?」
とくとくとビールが注がれてゆく。どうも、とぺこりと頭を下げてから尾次郎はくちばしをつけてみた。
久しぶりのシュワシュワした感覚と苦味に、目を瞬かせた尾次郎に、ゴン太は大きな切れ長の目をちろり、と向けた。
「で、お前が主人を放ってここにいるわけは?」
尾次郎の喉が、く、と音をたてた。
⬜︎
コンビニのガラス越しに、ナオトの背中を見ていた。似たようなくたびれたサラリーマンは他にもいるだろうに、なぜかラジオ君の「ナオト」だ、と響は感じていた。理由は、においだ。
おにぎりと蕎麦を買い、レジに並んだナオトの横顔はさっき脳裏に見えた十代の頃よりも皮膚がたるみ、疲れて見えた。買い物を済ませたナオトが店から出て、再び響の前を通り過ぎてゆくのをしばし見ていた響だったが、意を決したようにあとを追い始めた。いくつかの道を折れて、たどり着いたのは駅から30分ほど歩く距離のさほど新しくないマンションだった。
築10年くらいか、いわゆる駅近物件よりは、少し家賃が安いのだろうか。
そんなことをぼんやり思いながら、正面玄関に消えたナオトが点けたであろう部屋の灯りを確認して響はその場を離れた。その足でラジオ君の様子を見にいくと、最近とくに気に入っているアーティストについて語っていた。いつになく饒舌なラジオ君に相槌を打ちながら、先ほど目にしたナオトの姿が頭に浮かんでいた。
この部屋にいた頃から、20年くらいか。
仕事とか、大変なのかな。
疲れきった、と疲労が滲みでた顔だった。疲れだけであんな風にドス黒く沈んだ顔になるんだろうか。二十代前半の響でも疲れ果てることはある。忙しかったり、ストレスを重く感じることもある。
だけどしっかり眠って週末を過ごしたら何となく復活する。
あんなふうに、顔色まで変わるというのは一体なにが……
「いいでしょ、この曲!」
「え? あ、ああ。うん」
ぼんやりしていたらしい。ラジオ君がパーソナリティーよろしくおすすめしてくれる曲が流れていた。
「最近のてぃっくとおく? とかでまた流行ってるらしいよ、ナオトがすきだったんだ」
ひと昔前に流行ったらしい曲が、六畳の部屋に漂っていた。ラジオ君の目には、今でもあの頃のナオトが見えているのだろうか。
コンビニで見たあの姿と、頭をよぎった若き日のナオトの姿。
ナオトが成功していい暮らしをしていると信じているラジオ君が知ってしまったら、ショックに違いない。
「そうなんだ、うん、私も時々耳にするくらいだから。また流行ってるんだね」
「でしょう! いいものは時代を越えるんだって!」
ラジオ君がうれしそうに何度も同じ曲をかけるのをみて、響は喉元でナオトの名前を飲み込んだ。
アパートに戻ると、デブの茶白ねこはひっくり返ってイビキをかき、鳥は鳥で段ボールの隅で白目をむいて寝ていた。一瞬、死んだのかと思ったのだが、イビキにより生存を確認した。
「……のんきなものね」
理想を夢みて物怪になってしまったラジオ君にとって、現実のナオトを知ることは、夢を壊すことになるだろう。
けれど今のまま、付喪神のままでいいんだろうか。
なにが一番なんだろう。
2匹の鬼たちがイビキを立てる部屋の中、響は軽くため息をついた。だが、ラジオ君とナオトの運命は、意外な展開を迎えることになった。
