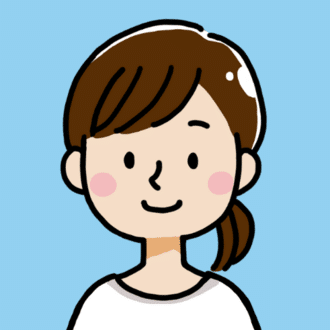【読書めも】I型(内向型)さんのための100のスキル | 鈴木奈津美(なつみっくす)さん
こんにちは、ちなです。
本日は『I型(内向型)さんのための100のスキル』という本を紹介します。
著者の鈴木奈津美(なつみっくす)さんは、ご自身も内向型で、小さい頃から静かで控えめな性格だったそう。
内向性にコンプレックスを感じつつも「自己アピールしなくても誰かが認めてくれるはず」と思っていました。
しかし、キャリアアップもないまま30代に。
社内異動や転職にチャレンジするも何度も失敗を重ねたそうです。
しかし、ある本をきっかけに「内向型の自分を変えるのではなく、強みを活かせばいい」と気づいてからは、人生が好転!
どんな本?
この本は、静かで控えめな自分にコンプレックスを抱いていたり、内向型の強みの活かし方に悩んでいる方向けに、不安を減らして行動にうつすきっかけを与えてくれる本です。
まず、自分の内向性を理解し、肯定的に受け入れるためのステップが解説されています。
▼内向型の強みを活かす4ステップ
【1】内向型の特性を知ること
【2】思い込みに気づくこと
【3】強みに目を向けること
【4】得意なパターンを見つけること
「内向性を前向きなエネルギーに変えていこう!」というメッセージが込められています。
本記事では、内向型の特性を活かしたより良い働き方を構築するための手法を3つに絞って紹介いたします!
①集中できる環境の作り方
1つ目は、集中できる環境を作るということ。
内向型は、視覚や聴覚の刺激に敏感な傾向があるので、いかに集中できる環境を作れるかが重要になります。
外向型の人にとっては刺激がエネルギーになるため、内向型のこの性質はなかなか理解できないこともあります。
在宅ワークやフリーランスと聞くと、どこでも働くことができてパソコン1台で場所を選ばず作業できる働き方に憧れたり注目が集まったりします。
しかし、オープンオフィスに憧れがありつつも、どうも集中できず苦手と感じることもあるかと思います。
これは私も共感できて、オープンオフィスやおしゃれな喫茶店でノートパソコン1台広げて、その日やるべき作業を進められたら…と思うものの、実際は周囲の雑音、匂い、座席の配置による人の視線の動きなどが、気になってしまいます。
本書では、集中できる環境を作る方法として3つ紹介されています。
在宅勤務を活用する
外部刺激が少ない自宅や個別の作業スペース(第3のスペース)で仕事を行うことで、集中力の向上につながります。ただし、孤立しないよう適切なコミュニケーションと人間関係を維持することも重要です。
パーソナル空間を作る
オフィスで働く必要がある人に有効な方法です。パーティションを設置したり、モニター、写真立て、植物などで外部と自分との間に仕切りを作り、視覚的な刺激を減らして集中力を高める方法です。
騒音を防ぐ
ノイズキャンセリング機能付きイヤフォンや耳栓を使用して、聴覚的な刺激を減らす方法です。私はマコなり社長の動画を参考に、イヤフォンを2つ持ち歩いています。AirPodsProとBoseのQuietComfort Ultra Earbudsです。迷ったらAirPods一択です。
なお自然音を聴くなら、YouTubeよりRainy Moodがおすすめ。
YouTubeは関連動画が出てきたり、どれを聴こうかな…と迷ったりして時間を奪われますが、Rainy Moodならそれがありません。
作業画面と別タブで開いておき、再生ボタンを押して流しっぱなしにします。
②「結果目標」ではなく「行動目標」を立てる
次に紹介する方法は「目標達成できず自己嫌悪に陥ってしまうことが多い…」という人におすすめの方法です。
それは「結果目標」ではなく「行動目標」を立てるという方法。
内向型は不安を感じやすい傾向があるため(目標を達成できなかったらどうしよう)と不安になって目標設定そのものを避けてしまうことがあります。
この状況を回避するためには、目標の立て方を変えることが効果的です。
結論から言うと「結果目標」より「行動目標」を立てましょう。
結果目標:「3件の案件を受注する」(自分でコントロールできない)
行動目標:「3件の案件に応募する」(自分でコントロールできる)
自分でコントロールできる行動目標を立てることで、自分の行動に集中することができます。
一般的に言われている目標設定の多くはほとんど「結果目標」です。
ですが「結果目標」に取り掛かることにそもそもハードルを感じているのであれば、まずはこの行動目標を立ててみることをおすすめします!
目標が達成できたら自分を褒めてあげてくださいね。
仮に目標達成がうまくいかなかったとしても、原因を振り返ったうえで、新たに行動目標を設定し直せば良いだけです。
「自分で立てた目標すら達成できなかった」と自己嫌悪に陥るのではなく、「やりながら軌道修正すればいっか」と軽い気持ちで受け止めましょう。
③相手の「タイプ」に合わせて準備する
最後は「一生懸命やっているけどなかなか評価されない…」と悩んでいる人に特におすすめの方法です。
それは、上司など評価する相手の「タイプ」に合わせた準備をするという方法です。
内向型は準備力が強みですので、この準備力を活かしすことで、正当な評価を得られるだけでなく、今後仕事が円滑に進むようになります。
本書では、アメリカの心理学者が考案した性格類型検査の4つのタイプに合わせた準備を紹介しています。
私のようにフリーランスの方であれば、複数のクライアントと取引することも多いと思います。
そんな時も、全クライアントに一律の対応をするのではなく、相手のタイプに合わせて準備しておくと、相手にとっても自分にとっても仕事が円滑に進むようになりますよ。
4つのタイプをそれぞれ紹介していきます
主導型
このタイプは主導権を握っていきたいという傾向があり、リスクを恐れず突き進めるタイプです。
こういったタイプの相手には、簡潔に要点を話せるように準備しておくことがポイントです。
例えば、ミーティングや報告の際は、事前に情報を整理しておいて、伝えるべきことを箇条書きでメモしておきます。その箇条書きに詳細として関連するページやサイトのURL、資料を添付しておいて、何か聞かれた時にはすぐ答えられるよう準備しておきます。
社交型
社交的で相手の気持ちや感情に注意を払うタイプです。新しい考えやイノベーションを好む傾向があります。
このタイプの相手には感謝を伝えることが有効です。また、どんな点が新しいかを伝える準備をしておくと良いでしょう。
安定型
安定を重視する温かい人柄が特徴です。グループや伝統を尊重するタイプでもあります。
このタイプには、前例があるかどうかや、どうやってチームで協力していくかという点を準備しておくと良いです。事前のリサーチが重要になります。
慎重型
じっくりと考えてデータ分析を実施するタイプです。
このタイプの相手には論理的で詳細なデータを準備することが有効です。抽象的な言葉遣いはなるべく避け、具体的な事例や結果を数字で示したり、グラフを用いたりすることも有効です。
以上が本書で紹介されていた4つのタイプです。
必ずしもどれか1つのタイプに振り分けられるものではなく、人間ですのでいくつかのタイプをグラデーション状に持っていることが一般的です。
とは言え「この人はこういうタイプだから、こう伝えると仕事が円滑になるなあ」と把握する時の目安にはなるので、上司やクライアントはどんなタイプだろう?と考えて、相手に合わせた準備や情報の伝え方を使い分けていくとよいでしょう!
内向型が強みを活かしながら自分らしく生きるための3つのポイント
内向型が自分を変えるのではなく、強みを活かせば良いと気づくためのポイントを3つ、私なりにまとめて終わりにしたいと思います!
①内向型の強みを活かすための方法を知る
②「だからこそ」で言い換えクセをつける
③SNSで気軽にアウトプットをする
①内向型の強みを活かすための方法を知る
内向型であることは自分が生まれ持った才能、強みであると捉えて、その特徴を活かすためにどんな方法があるのか考えることが何より重要です。
今回ご紹介した本は、厳選50冊のブックガイド付きなので、数ある内向型さん向け書籍の中でいま自分に必要な1冊を見つけ出す際に役立ちます。
②「だからこそ」で言い換えクセをつける
「内向型だから、新しいことはなるべく避けよう」
「内向型の私には楽しめないから、人との集まりは毎回欠席しよう」
とか…。
消極的に考えるばかりではもったいないです。
だけど、考えが先走って不安になることもありますよね。
そんな時「ネガティブ思考は絶対にダメ!」と考えるのではなく、一旦受け入れる。
ネガティブな気持ちも自分の素直な気持ちであることに変わりない。素直な気持ちなのに、それを「だめ!」って言われたら、やがて自分自身でも自分の気持ちがわからなくなって、もともと持っている良さも特徴も麻痺してしまいます。
なのでまずは受け入れる。
そうだね、ちょっと悩むよね。
不安だよね。
そうやって受け入れた上で、魔法の言葉。
「だからこそ」と言葉をつないで、前向きな方向に言い換える。
例えば、
・私は内向型だし交流会に行っても楽しめない→「内向型だからこそ」1対1のコミュニケーションは得意。まずはひとりと仲良くなろう。
・内向型だし目立つことは苦手→「だからこそ」人の話を聞くことが苦にならない。ほとんどの人は「自分の話を聞いてもらいたい」と思っている。こちらが傾聴することで、相手から心を開いてもらったり、他の人が聞けない話が聞けるかもしれない。
・私は内向型だから即座の対応が苦手→「だからこそ」じっくりした会話では信頼を得られやすい。思いがけない良いことが起こる場合もある。
(あ、私。いまネガティブなこと思ったな)と気づいたら、言い換えのチャンス!
ネガティブな思いや考えを全否定せず、一旦受け入れた上で、「だからこそ〜」と続けてみてください。
③SNSで気軽にアウトプットをする
内向型は他人に目が向いてしまう傾向にあるので、自分に目を向けるためにSNSでのアウトプットを活用します。
SNSで他の人の情報ばかり仕入れて比較して落ち込むのは悪循環ですが、SNSを自己表現ができる場として活用することが大切。
日常的にアウトプットすることで自分に対する理解が深まり、同じ価値観の人とつながることもできます。
例えば、私自身、この本との出会いも、私が内向型についてアウトプットしたポストを見ていただいた著者の方から送っていただき出会うことができました!
もしあなたが「こんなことを発信したら誰かから何か言われるんじゃないか」とか「私ごときが発信しても誰の役にも立たないんじゃないか」と思っていたとしても、それも結局出してみないことには分かりません。
ぜひ、もっと気軽にアウトプットすることを意識してみてください。
私はフリーランス6年目で、Xをメインにアウトプットしてきました。それなりに発信を継続してきて実感することは、自分が「誰も反応してくれないだろうけど備忘録的に書き留めておこう」という感覚で発信したものに、意外といいねが多くついたり、「共感しました」「言語化してくれてありがとうございます」というレスポンスをもらうことがあるということ。
結局、出してみないとわからないということ!
ぜひ、自分の中だけにエネルギーを溜めずに、アウトプットしてみて、そのアウトプットを振り返ることで、また自分軸に気づくという循環を生んでみてください。
そうすると他人(外向型)との比較に自分を見失うことなく、内向型をいう「才能」を持った自分自身の良さや能力、特徴などに自信を持てるようになっていきます。
まずは1日3分、1行でもひとことでもいい。箇条書きのメモでもいい。今日やったこと・課題・明日やること。アウトプットの時間を心がけてみてください。
私も受講した、マインドセットを整える30日間プログラムも、アウトプット素材として使えます。マインドを整えながら、アウトプット習慣も身につく。私の全受講記録をマガジンにまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
さいごに
今後も内向型の人向けの良い本や気づきなどがあれば、共有していきたいと思いますので、楽しみにお待ちいただけると幸いです。
内向型に関する本や発信が増えて「静かな人」の可能性は大きくなっている、と感じます。
ぜひこの本を手に取って、内向型の強みや「特権」を自覚し、仕事や人間関係に活かしていきましょう!
ではでは!
いいなと思ったら応援しよう!