
森、田畑、海をつなぐ「環プロジェクト」/広がるローカルSDGs
環プロジェクトは、森、田畑、海などで育まれたバイオマス(生物資源)を有効利用して、資源とエネルギー、経済の地域循環をつくる取り組みです。地域環境と生産者、消費者をつなぐ製品やサービスを創りだし、環境の再生やごみ問題の解決、地球環境への負担軽減の原動力となるローカルSDGs(持続可能な開発目標)のものづくりや自立力の高い新しい地域デザインを示し、兵庫から世界に発信していきます。
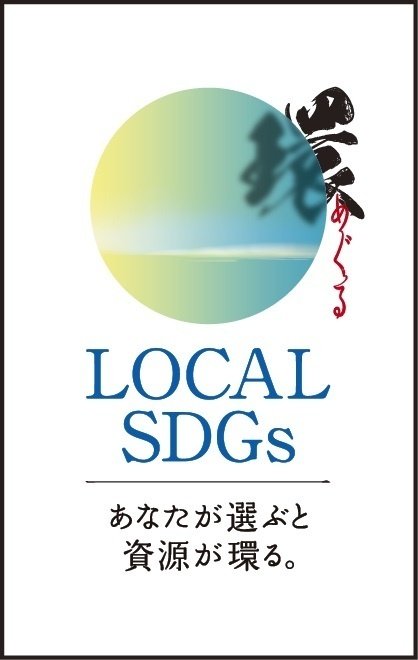
カキ、竹林訪ねるツアー
環プロジェクトの輪を広げるため、神戸新聞社は観光庁の「看板商品創出事業」を活用して、モニターツアーや試食会、セミナーを開催しました。
2月はじめのモニターツアーには30人以上が参加し、初日は「播磨灘のカキと竹林の新しい資源循環」の現場へ。4㌶ある太子町松尾地区の竹林を散策し、古い竹を伐採しながら若々しい竹林を保つことでタケノコを生産してきた歴史や高齢化による手入れ不足の現状などについて聞きました。
たつの市・室津では、播磨灘に浮かぶカキ養殖筏を船から見学。竹の交換作業や海の環境を守るための海底清掃などの漁業者の話に聞き入りました。
2日目は、「地エネの酒 環」の循環をテーマに、弓削牧場(神戸市北区)、豊倉町営農組合(加西市)、富久錦(同)を回りました。


「環」のカキと酒の試食会
環プロジェクトのカキのお披露目&試食会は昨年12月と今年2月に催し、料理店や食品バイヤー、観光業者ら計約50人が参加。日本料理店「玄斎」(神戸市中央区)店主の上野直哉さんと、キッシュとビストロ料理の「近藤亭」オーナーシェフの近藤弘康さんが手掛けるカキ料理を、4蔵の「地エネの酒 環」とともに味わいました。
「環」のカキは、生活協同組合コープ自然派(神戸市西区)が販売を開始しており、今後、取り扱う小売店や飲食店のネットワークを広げていきます。
環プロジェクトの母体となっている「地エネと環境の地域デザイン協議会」(事務局・神戸新聞社)では、「持続可能なものづくりと観光」と「ローカル認証」をテーマに2回のセミナーを開催。鳥取大准教授の大元鈴子さんが、北米西海岸の水環境の象徴であるサケを守るローカル認証「サーモン・セーフ」などを紹介しました。


環プロジェクト第1弾「地エネの酒 環」
飲むことで、地域の資源が回り出す。地球環境への負担を減らす。もちろん、おいしい!そんな役割を担って誕生したのが「地エネの酒 環」です。
食と農の営みから日々生じる有機物の残さを発酵させて得られる有機肥料「消化液」で育てた酒米・山田錦を「福寿」「盛典」「富久錦」「播州一献」の4銘柄の蔵元が醸しました。同時にできるバイオガスは給湯や暖房に生かします。
参加農家の一つ、豊倉町営農組合(加西市)は、冬から水を張って微生物を増やす冬期湛水などの技術を組み合わせ、農業機械利用と化学肥料と農薬を大幅に削減。稲作にかかるエネルギー消費を4割以上減らしています。

環プロジェクト第2弾「播磨灘のカキと竹林の新しい循環」
兵庫県太子町松尾地区は戦後から続くタケノコ産地ですが、高齢化で竹の手入れが遅れ、荒廃の危機に瀕しています。一方、播磨灘では、カキの養殖筏に使う竹を九州や四国から大量に運搬しています。こうした両者の課題をつなぎ、陸と海の新しい循環をつくる「環プロジェクト」がスタートしました。
カキ漁業者が竹林を伐採し、太い竹は筏に活用。細い竹や筏の古い竹はチップにしてタケノコの野菜の栽培に利用します。
これによって、➀竹の運搬の燃料費を大幅削減②高騰する化学肥料から地域資源肥料への転換③竹林の再生とタケノコ増産―などを進めます。

「地エネの酒 環」の主な販売店
神戸阪急、大丸神戸店、酪と酵母、酪と酵母Factory、ほうち商店、酒の美味小家 てらむら、オグラ屋、神戸酒心館 東明蔵(以上、神戸市)、ヤマダストアー(姫路市など)、ミルコート、ライフ夙川店(以上、西宮市)、地酒倶楽 武庫之荘(尼崎市)、高田屋(淡路市)、ふく蔵(加西市)、播州一献 直売所(宍粟市)、岡田本家 直売所(加古川市)
「地エネの酒 環」や「環」のカキを扱う飲食店等の情報は随時、地エネnoteのwebページで紹介していきます。
阪急うめだで22~28日、環プロジェクトのイベント
自然と人をつなぐ新しい循環をつくる環プロジェクトのイベントが大阪・梅田の阪急うめだ地下一階のツリーテラスで22~28日に開催されます。
「地エネの酒 環」や播磨灘のカキ「環」のほか、プロジェクトで発生する竹チップで栽培した野菜、「地エネの酒 環」の山田錦を栽培する消化液を供給する弓削牧場(神戸市北区)のチーズやソフトクリームなどが購入できます。
