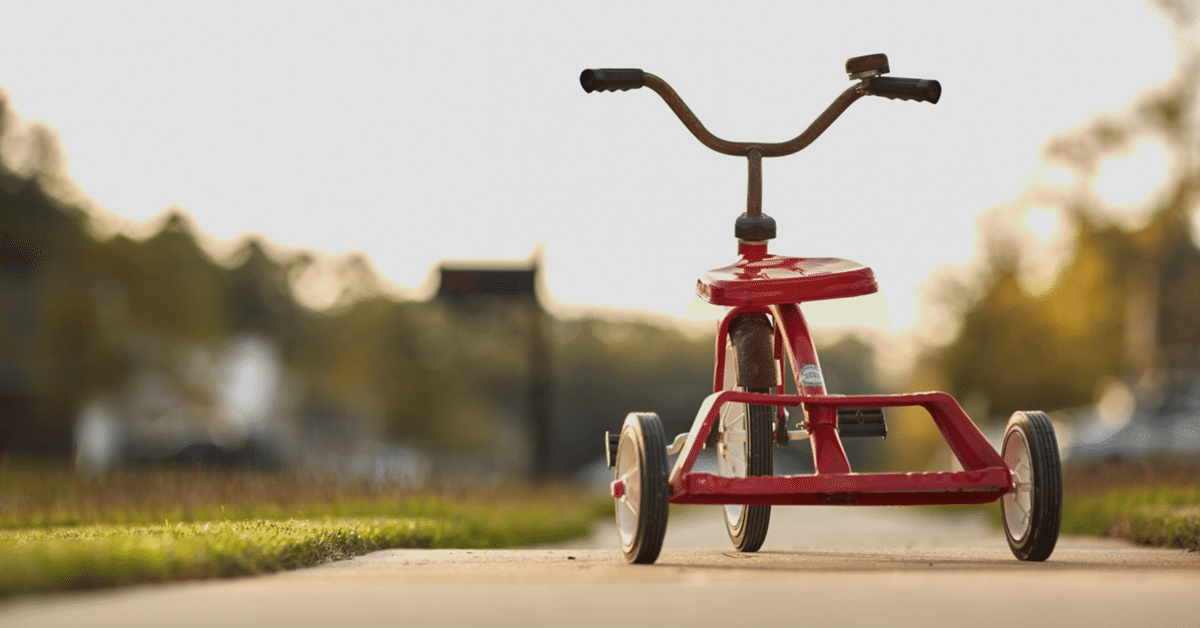
お仕置き三輪車のエレクトリカルドライブ
〈第一章〉
こいつが部屋にいるおかげで、僕は安く住めている。立地を考えると破格と言ってもいいだろう。この部屋は所謂“アレ”で長く空き部屋だったらしいのだが、背に腹はなんとやらで何事も気にしないタイプの僕は、喜んでここに住むことにして、かれこれ一年が経とうとしている。周りからは心配を装った下世話な雑音を散々聞かせられたが、所詮他人なんては一年もすると静かになる。ここは通勤にも便利で今となっては生活は充実そのものだ。Aと呼んでいる彼はここに居て、お互いの存在を感じ合うだけの不思議な間柄で、あえて直接言葉を交わすような野暮な事はしない。
僕には最近気になる人がいて、勇気を出して食事に誘ってみようと思っているのだが、それにはひとつ困った事があって、実は、誰も僕の目を見て話そうとしないのだ。誰にも打ち明けた事はないのだが、まるでAに話しているのかと感じることが少なからずある。おい、アンタにはAが見えているのか?の言葉をこれまで何度も飲み込んで来た。それはおかしな質問だと自覚していて、そんなことを言われても薄気味悪いだけだろうと思うからだ。高いところと怖い話は苦手なんだ。
それはそうと今日はあれだ、デートの下見を兼ねて彼女との相性を占ってもらおうと思っている。
ご乗車ありがとうございます。
同乗者さま。
おいおい、Aよ。
キミが呼んだのか?
このタクシーを?
そもそもこれはタクシーなのか?
僕はこういう得体の知れないものは苦手なんだ。いや、乗るけどさ。ねぇ、ドアを急に閉めないでくれよ、危ないじゃないか。
もくもくと湧き立つような新緑に柔らかくも鋭い陽光が差す。艶やかな葉の一枚一枚が光の風を受けてキラキラと揺れて輝いている。その陽射しが直接当たらないようにと慣れない手つきでベビーカーを押す夫婦。不動産屋に張り出された物件情報の前で立ち話の二人連れ。その向かいのフラワーショップでブーケを選んでいる誰かがいて、Tシャツ姿の子どもたちがひとかたまりになって広場を駆け回っている…クルマの中からぼんやりと街を眺めていると、生命は有限というものに後押しされてこそ強い輝きを放つものだな…などと思いに耽る。
信号が黄色から赤に変わる。
エアコンの音だけが響く静かな車内で運転手と目が合う。
「いやぁ、すっかり暖かくなりましたなぁ。
街も賑やかになってきて、こんな日は飲みにでも行きたくなりますな。
この近くに豚足のうまい店があってね…」
ミラー越しに伺う恐らく長身であろう運転手は何かを懐かしむように、それでいて力強い眼差しで真っ直ぐに僕の目を見ている。運転手は“僕に”語りかけている。
ああ、そうか。
思い出したよ。
信号が青に変わる。
微かなモーター音を響かせクルマは滑るように加速を始める。
なぁ、Aよ。次の更新からは家賃が相場に戻るのかも知れないな。でもキミなら大丈夫だ。もう、大丈夫だったんだ。
僕の眼からは涙が溢れていて、ミラーに映っていたはずの僕の姿は見えなくなっていた。
✳︎
〈第二章〉
顔色を伺いすぎたせいか、僕は透明人間になっていた。桜とかいう花が見頃を迎えるとアナウンサーが嬉々として話してた姿を忌々しくみたのを最後にテレビのコンセントは抜いてしまった。ツバメが軒下を飛び回るのに気付かず、空気がどんよりと湿り気を帯びて澱のように街に沈殿する頃、鈍くなり始めた僕の身体の反応はそれを湿度のせいにすることにした。自らを極限まで追い込むことが美徳だと信じ、同僚たちの前で失態を晒されることは社会人の洗礼なんだと思い込もうと足掻いてきたが、年を越そうとする頃、呼吸をしようとしないと呼吸が出来なくなり、自分が次第に透き通っていくような感覚に陥った。季節が一巡する頃、一人前の社会人になっているはずだった僕は僕自身を完全に失っていた。唯一、花粉だけが、鼻腔の粘膜を通じて僕の意識を容赦なくかき混ぜてくる。身体が不調であることは生きていることと等しい。
ご乗車ありがとうございます。
這うように家を出てタクシーらしきものを捕まえる。恐らく長身であろう運転手は、僕がひどい花粉症である事を見て取ると嬉しそうに話し出す。
「来年はねぇ、年明けくらいに病院行きはったらよろしいわ。ほんでね、なんやったかな…忘れたけどなんか治療してもらうんですわ。グー療法やったかな、チョキ療法やったかな…。」
言葉が耳の周りを風のように流れていく。
ハズレのタクシーを引いたと言いたいところだが、不思議と悪い気はしない。
「お客さん、南極の氷、知ってはりますか?
いや、こないだ行ったバーでね、ウイスキーを飲んだらね、ロックが南極の氷でしたんや。あれ、パチパチ音が鳴りますねん。空気が弾けとるんですわな。閉じ込められた古代の空気ですわ。南極の氷が白いのも、閉じ込められた空気のせい、ですな。」
「ほんでね、南極はずーっと寒いでっしゃろ。でもね、氷は層になっとるんですわ。じーっとしてるだけの氷が層になってますねん。あれってね、地球の気温の変化で層になるらしいんですわ。寒い年、ましな年がありますやろ。じーっとしててもね、しっかり年月(としつき)が刻み込まれとるんですな。後からみたら、あぁ、この年はしこたま寒かったんやな、とかわかるんです。後から振り返るとね。」
僕の反応を伺うことなく、運転手はどこか頓珍漢な話を滔々と続ける。
「お客さんのことね、実はちょこっと前から知ってますねん。」
「今はね、お客さん寒い時期や、思いますわ。でもね、しっかり経験は刻み込まれてる。きっと沢山の経験を身体に含んでええ色がついて、ええ音鳴りまっせ。ホンマですよ。知らんけど。いや、料金は要りませんねん。好きでここまで送っただけやさかい。」
何を言っているのか理解は出来ないのだが、少なくとも料金を取らないのなら客と呼ばれる筋合いはないだろう、との言葉がかろうじて口をつく。
そしてそんなことよりも、僕は一体何色人間で、一体どんな音を奏でるのだろう。静かな車内で、そんな想いに囚われる。
「いや、ほんまですね、お客さん、ええとこ気付きはるわ。ほな、客やのうて…」
「同乗者、ということにしときまひょか。」
✳︎
〈第三章〉
几帳面な私にも、靴紐の縦結びに気が付かない日はある。あの朝がそうだった。浮かれていたのかもしれないし慌てていたのかも知れない。若しくはその両方か。大事な約束だった。そして私は寝坊をしていた。
昨晩、慣れない服選びに大苦戦をし、挙句に目が冴えて眠れず、眠れないはずなのに寝坊をするというこの体たらく。冷静な判断を欠くであろう一日の始まりとしてはもう十分だったろう。
私は体が弱く、長くはこの世と繋がりを持たないであろうことを前提に過ごしてきた。それ自体は何とも思わない。与えられた時間は人それぞれで、歩む速さも違う。生きることは、有限であるという点において至極平等で、故に誰にでも等しく次の季節が巡ってくるだなんて迷信といってもいいのだろう。勿論、年月を重ね続ける事は喜ばしい。しかし今日一日に納得出来るかどうかは漫然と長い年月を重ねるよりも高い価値があると私は信じている。
慌てて駆け出す私の後ろから、馴染みのあるエンジン音が聞こえてくる。
あいつだ。ツイてる。
「なんやデートかいな。恋愛に割く時間に価値が見出せませんとか、むずがゆいことゆーてたお前が恋に慌てとるやなんて、全然イメージないな。ちょっと滑稽やし、なんかオモロいわ。」
「そうだな、私も意外に思っていて正直取り乱しているところなんだ。先を描くこと自体に慣れないし、それは恐れでもある。ただ、自らの衝動的な感情は新しい発見なんだ。もし、万が一、彼女との間に意志を持った未来が歩みを始めるだなんてことになれば、私はきっと未練の塊となって漂い続けるだろう。これは心配という名の未来だ。」
「いやぁ、お前の考え方はホンマ特殊やで。まぁ、誰かて特殊やし、皆がドラマを生きてるんやけどな。ボクはそんな人らの話を聞くのが大好きなんや。おもしろーて堪らん。君のその未来とやらはボクが面倒みるよ。時々やけどな。大丈夫や。任しとき。」
年季の入ったエンジン音が響く騒がしい車内で私は声を張り上げて彼に感謝を伝えた。そしてチカラを込めてスライドドアを開け放ち、私は、未来への一歩を踏み出した。
あいつの声が背中から追いかけてくる。
「いつか静かなクルマの中で喋ろうや!」
「ほんで靴紐、縦になってるで!」
いいんだ。
階段を駆け上がる私は、ただ、前だけを向いていた。
✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎
〈解説〉
Podcast番組『お仕置き三輪車のエレクトリカルドライブ』の二周年企画、2,000字お便りのために書いた創作物語です。
🚙お仕置き三輪車生誕祭🚙
— お仕置き三輪車 (@oshioki3rinsha) March 4, 2022
小生がこの世に生を受けて丸2年、今年もやります生誕祭
昨年の生誕祭では狂気の1000文字おたより企画を実行し大好評を博しました。今年はそれを上回る2000字おたよりを募集!合わせておしおたベスト3も開催します。
みなさま奮ってご参加を!https://t.co/LVElmJIsYA
以下、作品の流れを解説します。
三輪車さんなので、三章構成、各章は私の大好きなPodcast番組『スカシウマRadio』の書き出し小説大会で挙げられたものを使用しています。
ここで挙げられた書き出しのうち、私が感銘を受けたものは当時tweetしていました。
木曜午後0時、電車がトンネルに入った薄暗い車内で、耳を澄ませるボクは下ろしていたマスクを慌てて上げたが、遮光素材の帽子を目深に被り直すべきだった…
— chicagocoffeee (@abovethesea2) February 24, 2022
『縦結び』が好き
『1LDK1OBK』が対抗馬
『透明人間』にグサリとくる
素材が最高過ぎてヤバい#スカらじ
https://t.co/Gr1d7gaa7f
時間軸を遡る構成で、
〈第一章:現在〉実体のない僕が、おしさんに認識してもらう話
〈第二章:一つ過去〉花粉症の僕が、おしさんとの会話をきっかけに自分を取り戻す話
〈第三章:更に過去〉私がおしさんに未来を託す話
登場人物整理
■第三章の“私”→第一章の“実体のない僕”
■第三章の“未来”→私の忘れ形見で、第二章の花粉症の僕であり、第一章のAであり“同乗者”の名付け親
■“おしさん”→第三章で、私を拾い、第二章で未来を助け、第一章で私との約束を果たす
の三人。
時間軸を正すと、“私”はおしさんに未来を託し、未来である“色を失った花粉症の僕”はおしさんに助けられ、自らを取り戻すが、心配した“私”は現在も実体のないまま未来の周りを漂っている。そして、おしさんに大丈夫だと言ってもらえて、自分の実体がない事に気づく、それがおしさんとの約束「次は静かなクルマのなかで喋ろう」だったことを思い出す、という物語です。
おしさんの視点に立つと、几帳面な“私”を旧車デリボーイで拾う、私の忘れ形見の“花粉症な未来”を電気自動車で助けてあげる、いつまでも漂ってる僕に約束通りお喋りして、ちゃんと未来を見守っていることを伝えてあげる、という流れです。
ちなみに第一章の“漂う僕”が車窓から眺める街の景色は第三章でおしさんと離れた“私”がその後の人生を回想するのも兼ねてます。出会って、彼女と歩み出す、希望と心配とが混在する人生です。
遡る時間軸は映画『ちょっと思い出しただけ』に着想を得ています。とても素敵な映画でした。時間が遡るので最初は何が起こっているのか分からない、というところが斬新に感じました。
何度も読める物語ってどんなものだろうといつも考え続けてます。
とても難しくてとても楽しいです。
お仕置き三輪車さん、最高の企画をありがとうございました。
