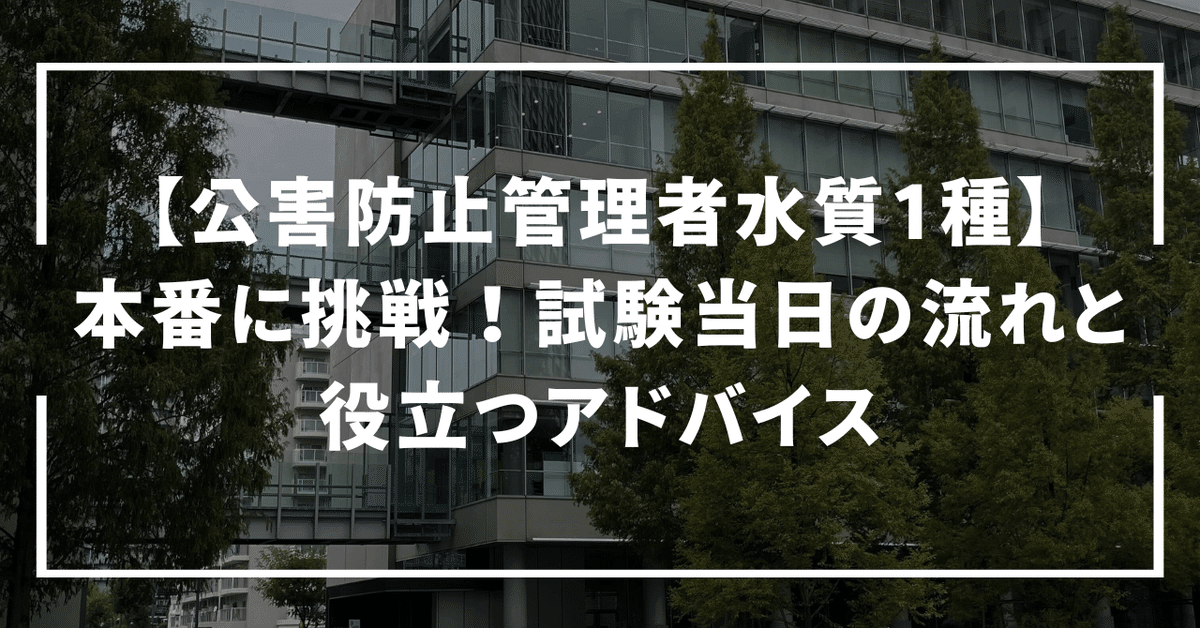
【公害防止管理者水質1種】本番に挑戦!試験当日の流れと役立つアドバイス
先週、公害防止の試験を受けてきました!
私自身、いろいろ資格試験を経験しましたが
いつも会場に着くとそわそわするし
慣れない環境で力を出し切れるか不安になります・・・
公害防止の試験は1年に1回だけ。
同じように思う人は多いのではないでしょうか。
でも、本番の様子や注意点がわかっていれば
初めての人でも安心して試験に取り組めるでしょう。
そこで今回は2024年に公害防止管理者試験を受験した
私の経験をもとにまとめました。
試験会場や試験中の雰囲気は?
試験当日の流れってどんな感じ?
受験時の注意点やアドバイスは?
初めて受験する人に
本番のイメージをつけてもらって
少しでも合格に近づくよう役立ててもらえればと思います。
序章:まず受験地を知っておこう

何気に注意なのが受験地です。
例年、だいたい9都市(エリア)しかありません。
受験地は次の主要都市(札幌市、仙台市、首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県を含む)、愛知県(名古屋市を含む)、大阪府(大阪市を含む)、広島市、高松市、福岡市、那覇市)とその周辺都市となりますが、会場の確保が困難な場合には他の市、府県で実施します。
受験地は限られるので
私のような田舎者は一番の近場であっても遠征です・・・
幸い、公害総論は大気1種で取得済みなので
2科目目からのスタートでした。
それでも朝6時台には家を出ましたが 汗
地方の人は朝イチの科目を受けるなら
前泊が必要になるかもしれません。
試験会場ってどんなところ?

片道3時間以上かけて最寄りの受験地に到着。
芝浦工業大学(豊洲キャンパス)に着いたのは10時くらいでした。
都会的で洗練されたキャンパス、建物の高さにびっくり。
すでに落ち着きません。
キョロキョロしてると
係員のお兄さんが「公害防止試験の受験者ですか?」と声をかけてくれて
スムーズに誘導してくれました。
会場で差があるかもしれませんが、
今回はキャンパス内に係委員の人があちこちに立っていて迷わずに
目的の建物につきました。
試験会場の雰囲気

会場の教室棟に入ると
3F〜5Fの多くの部屋が受験会場になっていて
「どの教室も水質一種?」と思うくらい水質一種の受験者が密集してました(試験区分ごとで会場分けてるんですかね??)
受験票に書いてある通りの教室に入ると、
3人がけの長机がズラズラ並び
真ん中は空けて、両端に座るスタイルで
適度に受験者同士の距離は保たれてました。
机の右上には受験番号シールが貼ってあるので
受験票と見比べて間違いないことを確認して座ります。
ちなみに
これまで3回、公害防止の試験を受けた経験上、
教室内は意外と閑散としています。
その理由は、
公害防止は科目合格が認められているので
受験対象の科目のみ受ければ良いからです。
例えば今回私が受けたのは4科目でしたが、
いずれも教室内は定員の半分ぐらいしかいませんでした。
資格によっては受験者が詰め詰めの状態の時もありますが
公害防止は比較的ゆったりした雰囲気かと思います。
試験当日の流れは午前2科目、午後3科目

科目ごとの試験時間は例年こんな感じです。
午前は2科目
9:35〜10:25 公害総論
11:00〜11:35 水質概論
午後は3科目
12:45〜14:00 汚水処理特論
14:35〜15:25 水質有害特論
16:00〜16:35 大規模水質特論
大気1種はさらにもう1科目ありますが、
水質1種も一日がかりの試験です。
最後は疲れもたまり、集中力を維持するのが大変でした。
試験中の雰囲気は?

どの科目もスタート15分前から試験官より注意事項の説明があります。
このタイミングで説明に沿って解答用紙に氏名と受験番号を書き、
毎度このルーチンが終わると開始まで沈黙が続きます。
「それでは、始めてください」の発声でスタート。
少し経つと試験官が受験票の顔写真を見ながら
本人確認したり、その辺を巡回してます。
試験終盤に、
「試験終了まで10分です。名前と受験番号の記入漏れがないか
確認してください」とアナウンスがあります。
個人的にはどの科目も時間が余りました。
途中退室NGなので
マークミスがないかチェックしたり、
自己採点用に問題用紙にも解答漏れがないかチェックしてました。
休憩の時や試験後の雰囲気は?
科目間の休憩時間でトイレに行ったり
次の科目の勉強をしたり、
知り合いと来てる人とかは教室の外で雑談したり基本自由です。
午前の科目が終わると1時間くらい休憩時間があるので
ここでお昼ご飯をとる人が多いです。
自分の席や教室の外で食べたり、
近くの店に行く人など様々ですが、
昼食を取りつつも
午後の科目に向けて勉強している人も多かったです。
私の場合は、会場に来る前に
コンビニでプロテインバー買って
試験教室の自分の席で食べつつ、次の科目に備えてました。
試験終了後は
一斉に受験者が帰り出すので、廊下は大行列になります。
結局、最寄り駅まではそれなりの集団のままでの移動でした。
注意点とアドバイス

持ち物は要確認
受験票に持ち物の一覧があるので、事前にチェックしておきましょう。
直前に忘れ物に気づいて大慌て、ということが無いようにしておきたいですね。
私は別の試験で腕時計を忘れたことがあります。
試験本番で残り時間が分からないのはかなりの恐怖でした。
会場によっては部屋に時計がありますが、
無い会場もよくあります(今回の教室は時計無しでした)。
筆記用具とか受験票のような基本的な持ち物は
忘れないと思いますが、
あると便利系(電卓、時計)も確実に持っていくようにしましょう。
会場は合ってる?
公害防止の試験会場は大学になることが多いです。
大学名だけでなくキャンパスの場所まで確認しておきましょう。
大学名は合ってるけど、別キャンパスだったということ事がないように。
あと、試験会場は毎年変わるケースもあるので
しっかり受験票を確認しておきましょう。
試験開始15分前は着席しておくこと
受験票にも書いてありますが
どの科目も開始15分前には着席しておく必要があります。
理由は注意事項の説明があるからです。
今回の教室では説明の途中で入ってくる人が2人いました。
全体説明後、試験官は遅れた人に対して個別に説明しに
回るのでバタバタ忙しそうでした。
ちなみに別試験で富山大学に行った時は
係員による誘導は一切なく、表示も最低限でした。
工学部の教育研究棟の場所が分からず迷子になりました 汗
時間に多少余裕もあり、何とか集合時間前に着きましたが
それ以来、初めての試験会場にいく時はより慎重になりました。
終わったことは引きずらずに次の科目へ
これは自分の反省点です。
今回、水質概論に自信が持てず、
終わった直後の休憩で答えを調べて一喜一憂の繰り返し。
結果は変わらないし、精神的にも良いことは殆どなく。。。
無駄な時間でした。
次の科目でしっかり得点できるように
気持ちの切り替えや最終確認をするなど有意義に休憩を過ごすよう
アドバイスしておきます。
まとめ
今回は初めて公害防止を受験する人向けに
これらの内容を中心にお伝えしました。
試験会場や試験中の雰囲気は?
試験当日の流れってどんな感じ?
受験時の注意点やアドバイスは?
本番は緊張するかもですが
力を出しきって、合格を勝ち取りましょう!
