
AWS EBSとは?初心者向け超入門から活用術まで
AWS(Amazon Web Services)のサービスを利用していると「EBS(Elastic Block Store)」という名前をよく耳にするかもしれません。このEBSは、AWSが提供するクラウドストレージの一つであり、EC2(仮想サーバー)と組み合わせて利用されることが一般的です。
この記事では、EBSの基本的な仕組みから具体的な活用方法、注意点までを分かりやすく、そして丁寧に解説していきます。初心者の方でも、この記事を読み終えたときにはEBSの主要な機能を理解し、実際のプロジェクトに活用できるようになるでしょう。
1. EBSとは?
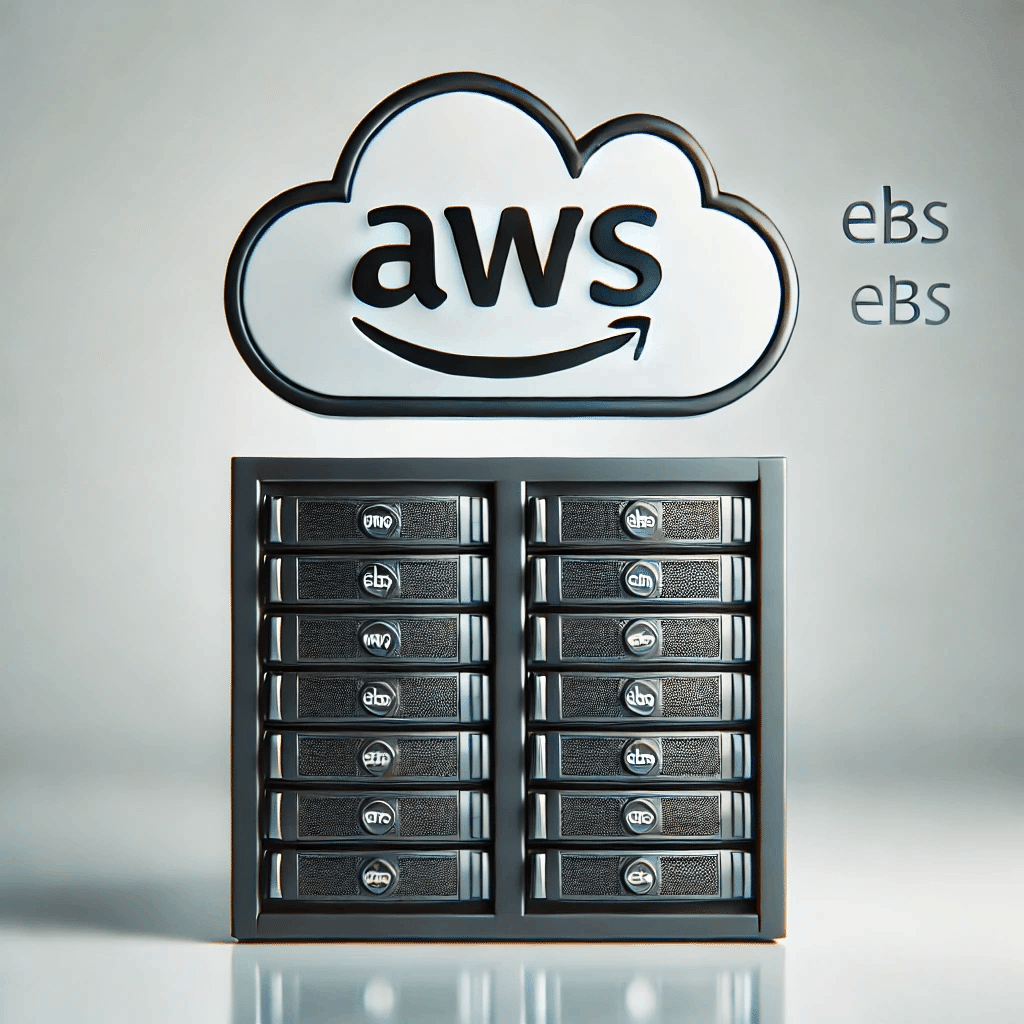
まずは基本から説明します。EBS(Elastic Block Store)は、その名前の通り、「ブロックストレージ」の一種です。「ブロックストレージ」とは、データを小さなブロック単位で保存・管理する形式のストレージを指します。これにより、高速なデータ読み書きが可能となり、コンピュータシステムにおける処理速度を向上させる役割を果たします。
EBSの主な特徴は以下の通りです:
AWS EC2との連携
EBSは主にEC2インスタンス(AWSの仮想サーバー)に接続して利用されます。EC2に「ハードディスク」を取り付けるイメージで、ストレージとして機能します。高い可用性と耐障害性
EBSは設計上、データの可用性を高めるよう最適化されています。データのバックアップや復旧機能が充実しているため、安心して利用できます。柔軟なスケーラビリティ
必要に応じてストレージ容量を拡張できるため、小規模なアプリケーションから大規模なデータベースシステムまで幅広く対応可能です。
例えば、個人ブログ用の小規模なウェブサーバーから、数十万のユーザーを抱えるeコマースサイトの基盤構築に至るまで、EBSは多様なシナリオで利用されています。
2. ボリュームタイプの詳細と使い分け

EBSにはいくつかの「ボリュームタイプ」がありますが、それぞれが異なる用途に最適化されています。このセクションでは、ボリュームタイプの違いや特徴を詳しく解説します。
汎用SSDボリューム(gp3, gp2)
このタイプは最も一般的で、多くのユースケースで使いやすいのが特徴です。高いパフォーマンスとリーズナブルなコストのバランスが取れており、初心者にもおすすめです。gp3:最大IOPS(1秒あたりの読み書き回数)が16,000、最大スループット(データ転送量)が1,000MiB/秒と高性能。特にデータベースのように高いIOPSが必要なシステムで利用されます。
gp2:gp3に比べ性能はやや劣りますが、多くの標準的なアプリケーションで十分対応可能です。
高性能SSDボリューム(io2, io1)
高い耐久性とIOPS性能を備えたタイプです。io2:0.0001%という極めて低い年間故障率が特徴で、ミッションクリティカルなシステムに適しています。
io1:性能面ではio2に近いですが、耐久性はやや低め。こちらも高度なパフォーマンスが求められる環境向けです。
スループット最適化HDD(st1)とCold HDD(sc1)
大容量データを低コストで保存したい場合に適しています。ログファイルの保存やバックアップに利用されることが多いです。st1:スループット性能が求められるアプリケーションに適しています。
sc1:最低限のスループット性能で十分なデータアーカイブに向いています。
3. スナップショット機能の活用術
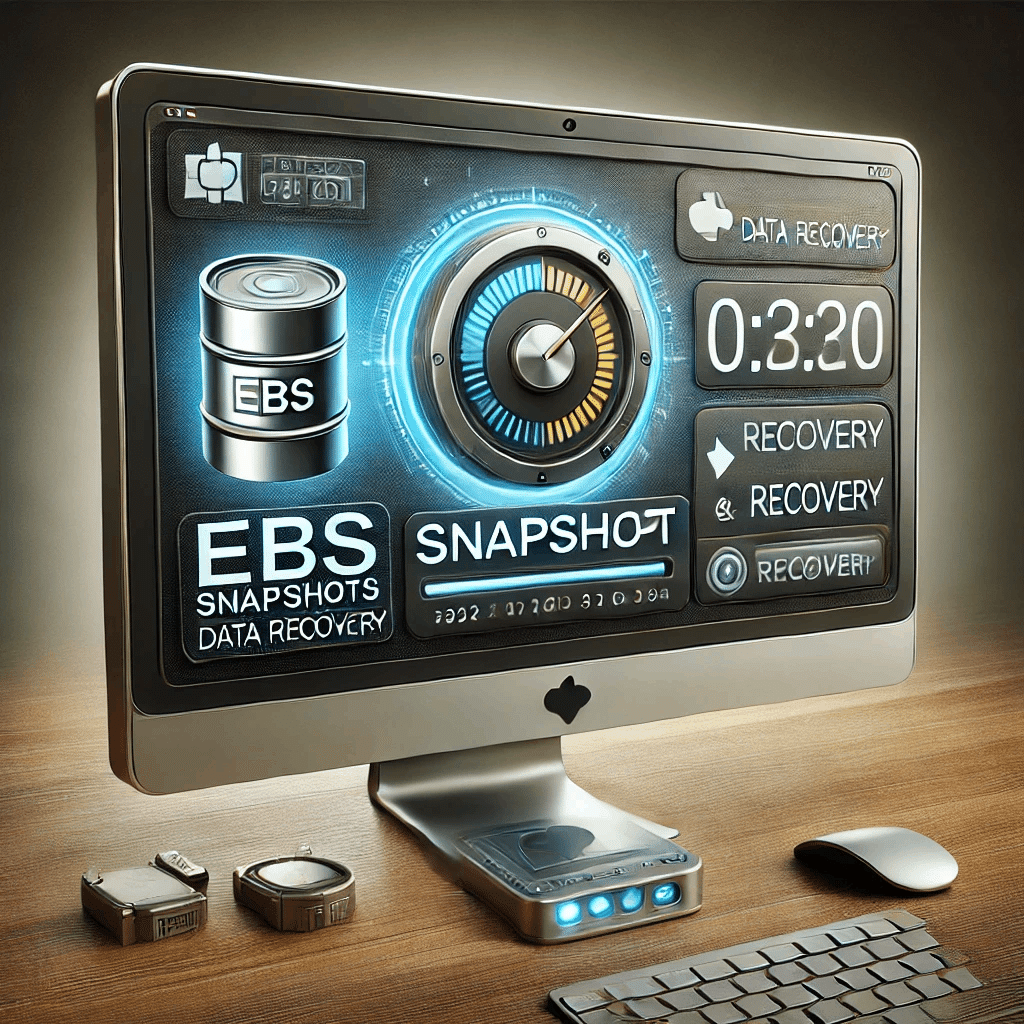
EBSの便利な機能として「スナップショット」が挙げられます。これは、ボリュームの現在の状態を保存し、必要に応じて復元できる仕組みです。
スナップショットの仕組み
初めて作成するスナップショットは「フルスナップショット」と呼ばれ、ボリューム全体のデータを保存します。その後に作成されるスナップショットは「増分スナップショット」となり、変更部分のみが保存されます。これにより、ストレージ容量を効率的に使用できます。
スナップショットのメリット
データ保護:データの破損や誤操作が発生しても、スナップショットから簡単に復元できます。
環境の複製:本番環境のコピーを作成し、開発やテスト環境として活用可能です。
低コスト運用:増分スナップショットによりストレージコストを削減できます。
4. データセキュリティを強化する暗号化の活用
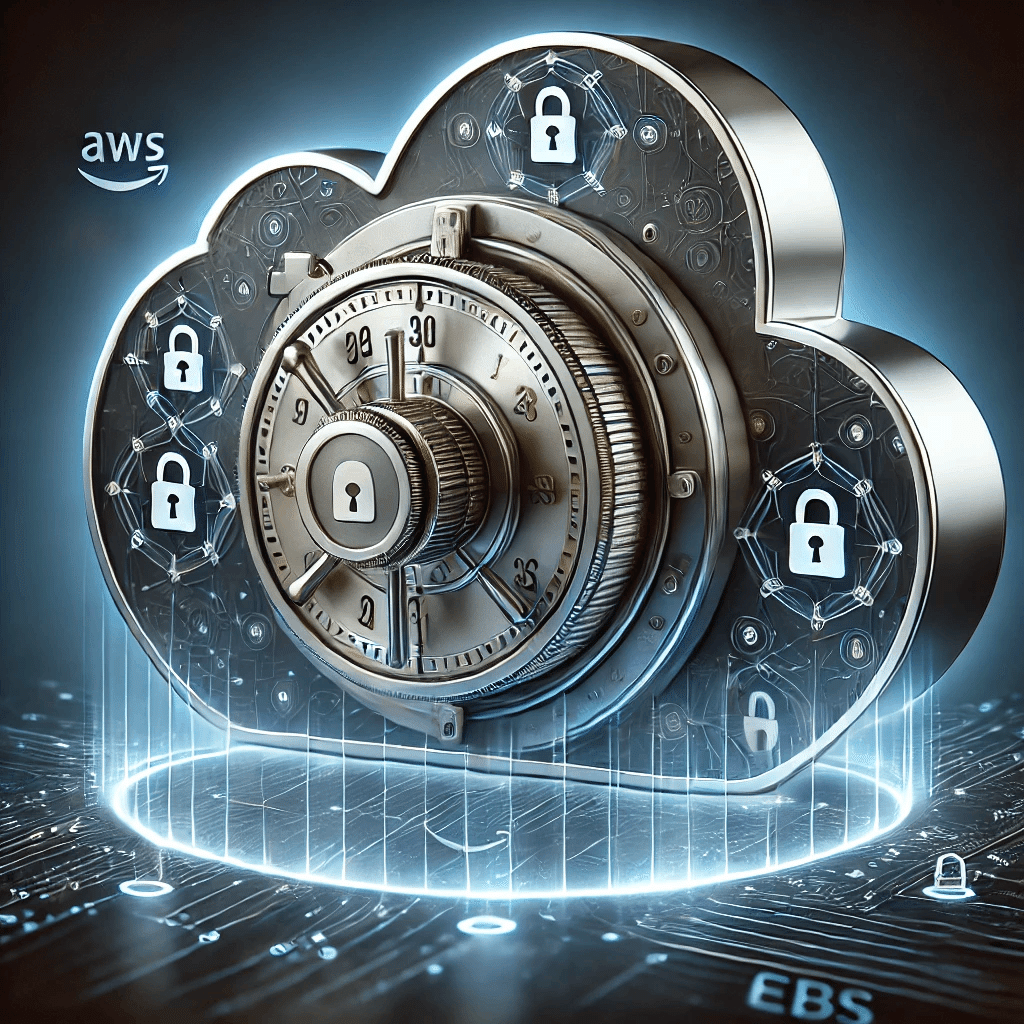
クラウドストレージを利用する上で、データの安全性は非常に重要です。EBSでは暗号化機能を活用することで、機密性の高いデータを保護できます。
KMS(Key Management Service)の利用
AWSが提供するKMSを使用すると、暗号鍵の管理を自動化できます。これにより、データ保存時や転送時のセキュリティを確保しつつ、管理の手間を最小限に抑えられます。
暗号化が必要な具体例としては、以下が挙げられます:
医療記録や金融データなど、法規制に基づいて保護が必要なデータ
社内の重要なプロジェクトファイルや顧客データ
5. 自動化で効率化を目指すDLM
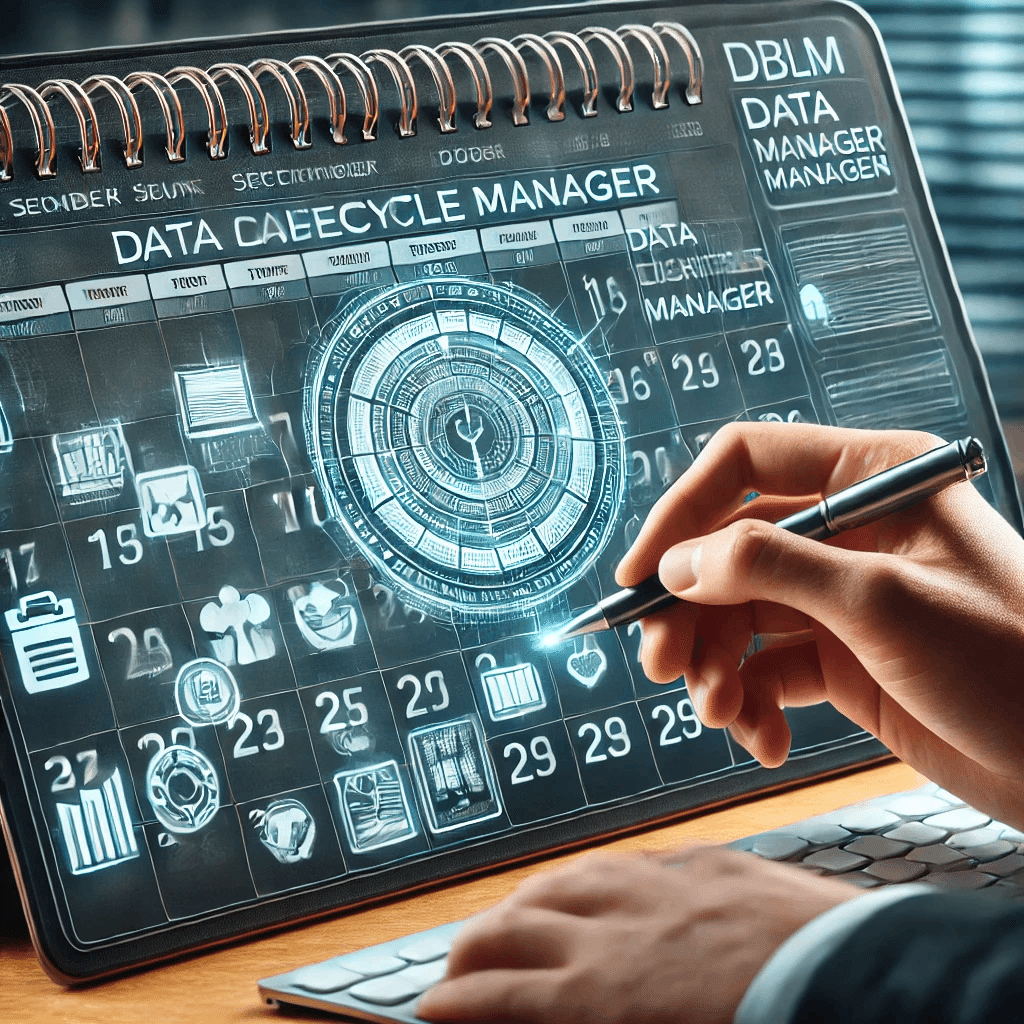
EBSの運用をより効率化するために、「Data Lifecycle Manager(DLM)」を活用しましょう。DLMは、スナップショットの作成・保持・削除をスケジュールに基づいて自動化するツールです。
例えば、毎晩深夜にスナップショットを作成し、30日以上経過したスナップショットは自動削除する設定が可能です。これにより、運用コストを削減しつつ、管理を簡素化できます。
6. RAIDでさらなる冗長性を確保

RAID(Redundant Array of Independent Disks)は、複数のEBSボリュームを一つの論理ストレージとしてまとめ、冗長性や性能を向上させる技術です。
RAIDの構成例
RAID 1(ミラーリング):同じデータを複数のボリュームに書き込むことで、1つのボリュームが故障してもデータを保持可能。
RAID 5/6(ストライピング+パリティ):データを分散保存しつつ、冗長性を確保します。
7. まとめと次のステップ
EBSはAWSクラウド環境を支える強力なツールです。適切に利用することで、システムの可用性、耐障害性、安全性を大幅に向上させられます。
次は、EBSを実際にセットアップし、スナップショットの作成やRAIDの構築を試してみましょう。EBSの活用に慣れれば、クラウド運用がさらに快適になります。
クラウドの勉強をするならAWS SAAに合格しよう

AWS SAA(ソリューションアーキテクトアソシエイト)とは、Amazon社が運営する資格の一つです。
クラウドの勉強を体系的にするなら、AWS SAAの取得を目指した方がいいと言われています。
※AWS SAA試験の合格方法についてもまとめていますので、宜しければご覧ください
