
ワイヤレス通信と認証の基本を学ぼう:私たちの毎日を支えるテクノロジーの裏側
みなさん、こんにちは。
私たちの生活を便利にしてくれるワイヤレス通信。スマートフォンでSNSを楽しんだり、家のWi-Fiで動画を見たり、カフェでノートパソコンを使ったりする場面で、この技術に助けられています。しかし、その仕組みや安全性について考える機会は意外と少ないかもしれません。
この記事では、ワイヤレス通信の仕組み、利用される周波数帯、進化を続ける規格、そして重要なセキュリティと認証について、日常生活に即した具体例を交えながら、わかりやすく解説していきます。
1. ワイヤレス通信とは何か?その基本を押さえよう

有線通信との違い
ワイヤレス通信は、LANケーブルや光ファイバケーブルといった物理的な接続を必要とせず、電波を利用してデータをやり取りする通信技術です。有線通信と比べると、次のようなメリットがあります。
配線が不要で設置が簡単:家の中やオフィスで、わざわざケーブルを敷設しなくても利用できます。
モビリティの向上:電波の届く範囲内であれば自由に移動しながら通信可能です。例えば、スマートフォンで動画を見ながら部屋を移動しても接続が切れません。
物理的な制約が少ない:壁や家具でケーブルが邪魔になる心配がありません。
しかし、ワイヤレス通信には弱点もあります。それは「電波の性質による制限」です。たとえば、壁や床などの遮蔽物があると、電波が届きにくくなることがあります。
電波の干渉と通信の安定性
ワイヤレス通信には、電波の干渉という問題もあります。例えば、隣の部屋で電子レンジを使うとWi-Fiが遅くなる、なんて経験はありませんか?これは電子レンジがWi-Fiと同じ2.4GHz帯を利用しているために干渉が発生してしまうためです。
また、ワイヤレス通信は基本的に「半二重通信」と呼ばれる方式を採用しています。一度に送信と受信の両方を行えない仕組みで、同時に複数の端末が通信を行うと衝突(コリジョン)が発生することがあります。
2. ワイヤレス通信の周波数帯の特徴を理解する

ワイヤレス通信には、主に 2.4GHz帯 と 5GHz帯 の周波数が利用されています。それぞれの特徴を知ることで、最適な環境を整えるヒントが得られます。
2.4GHz帯の特徴
長所:
障害物に強い:壁や床を越えても電波が届きやすい。
機器の互換性が広い:古いデバイスも対応している場合が多い。
短所:
電波干渉を受けやすい:電子レンジやBluetoothデバイスが同じ周波数帯を使用しているため、通信速度が低下する可能性があります。
5GHz帯の特徴
長所:
電波干渉が少ない:利用されている機器が少なく、安定した通信が可能。
高速通信が可能:Wi-Fi 5(IEEE802.11ac)やWi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応しており、高速データ転送が可能です。
短所:
障害物に弱い:直進性が高いため、壁や床を越えると信号が弱まります。
周波数の選び方
自宅のWi-Fiを選ぶ際には、「2.4GHz帯」と「5GHz帯」の両方をサポートするルーターを選ぶのがおすすめです。障害物が多い場合は2.4GHz帯を利用し、安定性が必要な場所では5GHz帯を活用しましょう。
3. ワイヤレスLANの進化:規格の歴史を知ろう

ワイヤレスLANの技術は進化を続けています。その代表的な規格をいくつか見ていきましょう。
Wi-Fi 4(IEEE802.11n)
2009年に登場した規格で、2.4GHz帯と5GHz帯の両方に対応しています。最大通信速度は600Mbpsと、当時の基準では非常に高速でした。
Wi-Fi 5(IEEE802.11ac)
2014年に登場した規格で、5GHz帯専用です。最大6.9Gbpsの高速通信を実現しました。この規格では、「MIMO(複数アンテナで同時通信)」や「チャネルボンディング(周波数帯を束ねる)」といった技術が導入され、さらに効率的な通信が可能になりました。
Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)
2020年に策定された最新規格です。2.4GHz帯と5GHz帯の両方に対応しており、最大通信速度は9.6Gbps。加えて、多くのデバイスが同時に接続しても通信が安定するよう、技術が改良されています。
4. ワイヤレス通信のセキュリティ:見えない危険から身を守る

なぜセキュリティが必要なのか?
ワイヤレス通信は、有線通信に比べて盗聴や不正アクセスのリスクが高いです。電波は特定の範囲に届くため、その範囲内にいる悪意のある人物に盗聴される可能性があります。
データの暗号化
通信内容を暗号化することで、第三者に内容を読み取られないようにします。AES(Advanced Encryption Standard)は現在の標準的な暗号化方式で、強力なセキュリティを提供します。
認証の仕組み
ワイヤレスLANの認証方式には以下のようなものがあります:
事前共有鍵認証(PSK認証):簡単に設定でき、家庭用Wi-Fiに最適。ただし、パスワード漏洩のリスクがあります。
IEEE802.1X認証:企業でよく使われる方式で、ユーザーIDやパスワードを用います。
Web認証:駅やカフェなどで見かける認証方式で、ブラウザを使ってログインします。
Open認証:基本的に認証を行わない方式。他の認証方式と組み合わせて使うことが推奨されます。
5. WPA3:最新のセキュリティ規格
2018年に登場したWPA3は、これまでの脆弱性を解消し、以下のような特徴を持っています:
SAE (Simultaneous Authentication of Equals):暗号化の強化により、データが漏洩しても過去の通信内容が解読されるリスクを防ぎます。
辞書攻撃への耐性:パスワード試行を制限する機能が追加されました。
Wi-Fi 6対応の機器では、WPA3の導入が必須です。
6. ワイヤレスLANコントローラ:効率的なネットワーク管理を実現
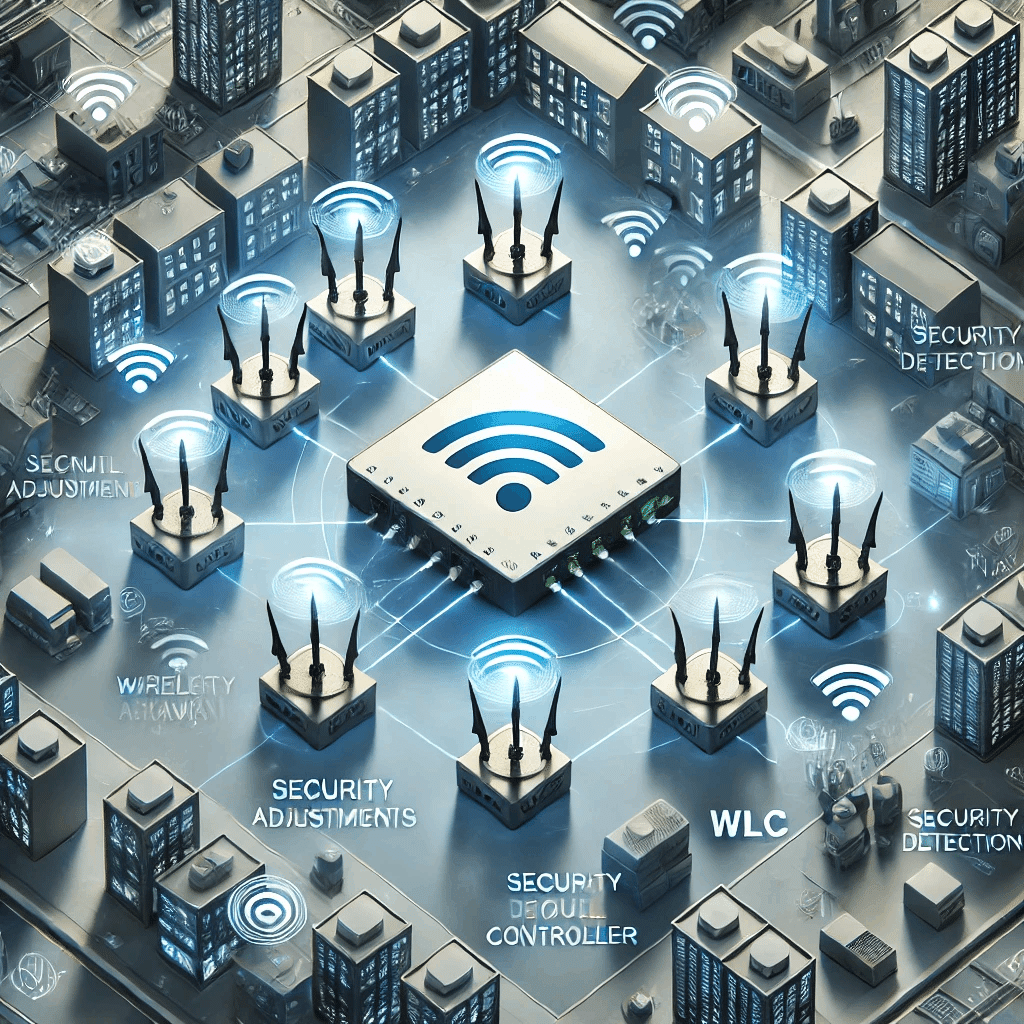
中規模から大規模なネットワークでは、複数のアクセスポイントを効率的に管理するために、ワイヤレスLANコントローラ(WLC)が活用されます。
WLCの主な機能
アクセスポイントの自動調整:電波の出力や使用する周波数帯の設定を自動で最適化。
不正アクセスポイントの検出:セキュリティを強化。
FlexConnectモード:WLCとの接続が切れてもアクセスポイントが独立して動作可能。
これにより、大規模ネットワークの運用が容易になります。
7. ワイヤレス通信の未来へ向けて
ワイヤレス通信の技術は日々進化しています。より速く、より安全な通信を実現するためには、新しい技術や規格に対応したデバイスの導入が重要です。また、セキュリティをしっかりと意識し、適切な設定を行うことで、安心してネットワークを利用できます。
次にWi-Fiの設定を見直す際には、この記事の内容を参考にしてみてください。ワイヤレス通信の裏側に隠された技術と安全性への工夫を、身近に感じられることでしょう。
ネットワークの勉強をするならCCNAに合格しよう

CCNAとはアメリカのネットワーク機器ベンダの最大手のCisco(シスコ)システムズが運営する資格の一つです。
ネットワークの勉強を体系的にするなら、CCNAの取得を目指した方がいいと言われています。
※CCNAの最短合格方法についてもまとめていますので、宜しければご覧ください
