
ネットワーク技術の基礎:EtherChannelって何だ?
皆さん、こんにちは!今回は、ネットワークエンジニアとして押さえておきたい「EtherChannel(イーサチャネル)」について解説していきます。
「複数のケーブルを1本にまとめる?」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。これがまさにEtherChannelの基本的なイメージです。
そもそもEtherChannelって何?

EtherChannelは、複数の物理リンクをまとめて1つの「論理リンク」として扱う技術のこと。
具体的には、スイッチ間やルータ間の通信を複数のケーブルでつなぐ場合、通常の設定だと以下のような問題が出るんです。
帯域幅が活かせない:STP(スパニングツリープロトコル)によってループを防ぐため、一部のリンクがブロックされちゃう。
冗長性が不十分:1本のリンクが落ちたとき、切り替えはできるけど帯域が減る。
EtherChannelを使うと、これらの問題を解決できます!
複数の物理リンクをまとめて1本の論理リンクにすることで、帯域を最大限に活かしつつ、リンク障害時の冗長性も確保するわけですね。
EtherChannelのメリット
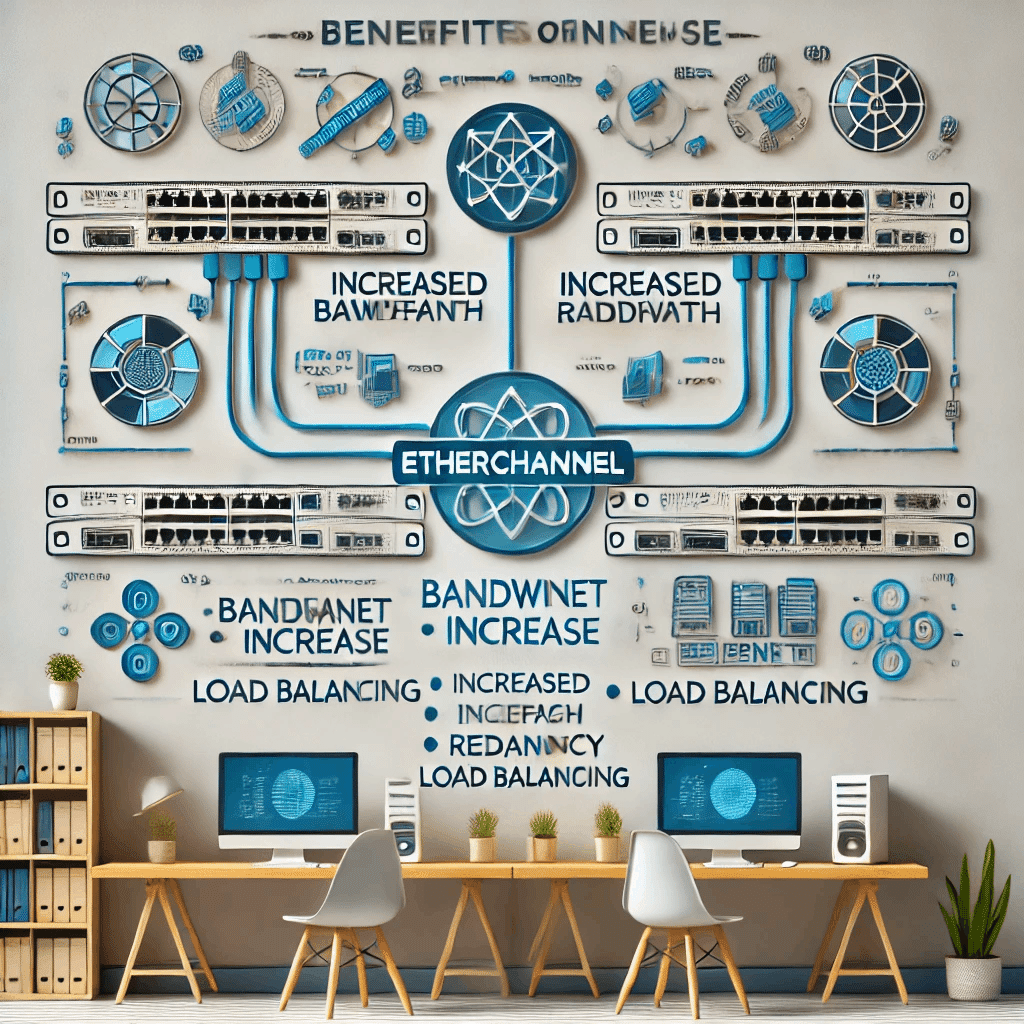
EtherChannelを導入すると、主に以下のメリットがあります:
帯域幅の増加
たとえば、100Mbpsのリンクを2本束ねれば、理論上200Mbpsの帯域が確保できます。
※もちろん、実際の帯域幅は設計や負荷状況によりますが、効率的な通信が可能になります。冗長性の確保
1本のリンクが落ちても、残りのリンクで通信が継続されるので安心。スイッチ間の負荷分散
トラフィックが複数のリンクに分散されるため、1つのリンクに負荷が集中しづらくなります。
EtherChannelの設定方法

EtherChannelの設定には、大きく分けて以下の2種類があります。
1. Static(スタティック)
手動でリンクをまとめる方法。あらかじめ設定したポートをチャネルグループに割り当てることでLAGを構成します。
特定のプロトコルが不要なため、シンプルな構成で実装したい場合に便利です。
2. Dynamic(ダイナミック)
プロトコルを使って動的にリンクをまとめる方法。以下の2つのプロトコルが使えます:
PAgP(Port Aggregation Protocol):Cisco独自のプロトコル
LACP(Link Aggregation Control Protocol):IEEE標準で、マルチベンダー環境にも対応
動的設定で気をつけるべきポイント
動的設定では、プロトコルの動作モードによってLAGが組めるかどうかが決まります。
たとえば:
両端ともactiveならOK!
一方がactiveで、もう一方がpassiveならOK!
両端ともpassiveだとNG…。
この組み合わせ、覚えておくとトラブル対応のときに役立ちます。
設定時の注意点

EtherChannelを構成する際は、以下の点に注意してください。
インターフェースの設定を統一すること
たとえば:Duplexモード(half/full)
Speed(10/100/1000 Mbps)
VLAN設定(トランクならAllowed VLANを統一)
チャネルグループのルールを守る
1つのインターフェースは1つのチャネルグループにのみ参加可能。
まとめ
EtherChannel(またはLAG)は、ネットワークの信頼性とパフォーマンスを向上させるための重要な技術です。
複数の物理リンクを論理リンクとして扱うことで、帯域幅を増やし、冗長性を高めることができます。
設定の際には、StaticかDynamicのどちらを選ぶか、またプロトコルのモードに気をつけることが大切です。
あなたのネットワーク構築・運用スキルをさらにアップデートするため、ぜひこの技術をマスターしてください!
ネットワークの勉強をするならCCNAに合格しよう
CCNAとはアメリカのネットワーク機器ベンダの最大手のCisco(シスコ)システムズが運営する資格の一つです。
ネットワークの勉強を体系的にするなら、CCNAの取得を目指した方がいいと言われています。
※CCNAの最短合格方法についてもまとめていますので、宜しければご覧ください
▼CCNAの最短合格方法はコチラ
本日もブログを閲覧下さりありがとうございました!
