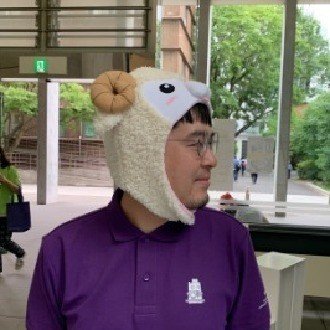第296号(2025年2月17日) 走り出したトランプのウクライナ停戦政策(だが、どこへ?)
【お知らせ】クラファン、順調です!
民間インテリジェンス組織DEEP DIVEのクラウドファンディングが順調に進んでいます。最初の1週間で730万円ものご支援をいただきました。本当にありがとうございます。
目標金額まであと少し。皆様の引き続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。
【インサイト】走り出したトランプのウクライナ停戦政策(だが、どこへ?)
軍事フェーズからついに政治フェーズへ?
今週に入り、ウクライナをめぐる情勢に大きな転換が生まれつつあるように思います。個々の動きについては以下で述べていきますが、全体的にこの戦争をめぐる決定的要因が軍事から政治へと移りつつあるのかもしれない、ということです。
これまでのほぼ3年間、ウクライナをめぐる問題の核心は主に戦場の中にありました。ロシア軍は本当に侵攻するのか(2022年)、ウクライナ軍の反転攻勢は成功するのか(2023年)、東部戦線は維持できるのか(2024年)などなどです。
一方、この間における政治の影は(少なくとも表面上は)薄く、交渉による停戦は極めて悲観的であると私は見てきました。詳しくは前回のメルマガに書きましたが、要はロシア側の要求はウクライナが受け入れるにはあまりにも大きなものである、ということです。したがって、トランプ政権が早期停戦を掲げるにしても、それはなかなか難しいのだろうかということをやはり前回のメルマガで述べました。
しかし、トランプは力づくででも主導権を軍事の領域から政治の領域に移そうとしているようです。今回のテーマである停戦交渉の動きがものすごいスピードで進んでいるのは、トランプ政権がかなり本気であることを示すものでしょう。多少めちゃくちゃに見えてもとにかく俺がリーダーシップを発揮して話をまとめるんだ!という点は、終始優柔不断であったバイデン政権のウクライナ政策とは対照的ですし、それはそれで一概に悪いことではないと思います。
ただ、主導権をもぎ取ったトランプはどこへ向かって走って行こうとしているのか。なんとなくの方向性は見えてきたように思いますが、本当に走り出すことはできるのか、具体的なゴールがどこなのかはやはりまだ、明確になっていません。
トランプの停戦外交とロシアの要求
まずは事実関係をザザッと把握しておきましょう。
トランプ政権によるウクライナ停戦の動きが表面化したのは2月12日のことです。この日、トランプ大統領はロシアのプーチン大統領と電話会談を行ったと明らかにしました。ウクライナとの電話会談はその後なので、先に米露で話をつけてから結果がウクライナに言い渡されるという開戦前の構図が復活した形になります(この戦争中は基本的に米国とウクライナが話し合いの主体であって、ロシアとの交渉が行われるとすればバックチャンネルを通じてであった)。また、この電話会談に合わせてロシア側は拘束していた米国人男性を解放しており、これを機に米露の和解ムードを演出したいとの狙いも伺われます。
さらにその中身について、トランプ大統領は次のように述べています(日本ではNHKが内容を詳しく報じています)。
・プーチンは停戦を望んでいる。早期の停戦が可能だろう
・近いうちにサウジアラビアでプーチンと会うことになるだろう
・ウクライナのNATO加盟はロシアが許さないので現実的ではない
・ウクライナが2014年以前の領土を回復するのは難しいと思われる
このうちの後半部分、すなわちウクライナのNATO加盟と領土回復は実現困難であるとする声明は、昨年6月14日にプーチンが外務省幹部の前で行った演説の中の「停戦交渉開始の条件」とかなり符合します。より正確に言えば、この時にプーチンが主張したのは「2022年にロシア側が「併合」を宣言したウクライナ4州の行政境界線外にウクライナ軍が撤退すること」と「ウクライナがNATOに加盟しないと約束すること」でした。
トランプの声明は「現実的ではない」「難しい」という言葉でこのロシア側の要求を暗に認めているように見えます。
これとほぼ時を同じくしてブリュッセルで開かれたウクライナ防衛支援国会合(UDCG:いわゆるラムシュテイン会合)に出席したピート・ヘグセス米国防長官も、「主権を維持し繁栄するウクライナを望む」としつつ、「2014年以前の国境を回復すのは非現実的である」「このような幻想的な目標を追求すれば戦争が長引くだけだ」と主張。さらに「ウクライナで再び戦争が起こらないよう強力な安全保障が必要だ」とする一方で「かといってウクライナのNATO加盟が交渉による解決の現実的な結果であるとは思われない」と述べました。
その他、ウクライナへの平和維持部隊はNATOの枠外でやるべきであり米国が部隊を派遣することはない、などとも主張したヘグセス演説の評判は非常に悪いわけですが、全体として見ると、私はそこまで変なことを言っているようには感じませんでした。
もはや米国が欧州とインド太平洋正面の両方で抑止を丸抱えすることはできないんだ、欧州がもっとしっかりしてくれないといけないんだ、というのがメッセージの本丸であり、これは国防次官となったエルブリッジ・コルビーの持論にかなり影響されたものでしょう(というかスピーチ原稿を書いたのは彼なのでしょう)。さらに言えばウクライナの領土奪還が困難であることもその通りであって、それを「非現実的だ」と呼ぶこともわからないではない。
こうしたメッセージは、翌日にブリュッセルで開催されたNATO国防省会合におけるヘグセスの演説でも繰り返されました。
それでも不安が残るトランプ政権の対ウクライナ政策
ただ、問題は、そのような現実論がロシア側のナラティブと微妙に噛み合ってしまっている、という点です。すでに述べたように、ウクライナの領土放棄とNATO不加盟はロシアにとって「停戦交渉開始」の条件であって、停戦そのものの条件ではありません。
とするならば、開戦当日から現在に至るまでロシアが求め続けてきた停戦そのものの条件、言い換えるとウクライナの降伏条件も、トランプ政権が認めてしまうのではないかという危惧がどうしても生まれてきます。これも前回取り上げたことですが、要はロシアの要求はウクライナの属国化です。ウクライナがロシアのコントロール下にないことがロシアにとっては屈辱でもあり、脅威でもある、というナラティブをロシア側は過去3年間、繰り返してきました。だから6月14日演説では政治・軍事・対ロシア外交のあり方全体についてロシアの強い影響力を認めよということが主張されてきたわけです。
で、今回のトランプ=プーチン会談ですが、プーチンは「戦争の根本原因に対処する必要がある」とトランプに主張したようです(上記NHK記事)。ここまで述べたことからすれば、「戦争の根本原因」とは要するに「ウクライナが主権国家であること」でしょう。ヘグセス(なのかコルビーなのか)はそこまでは許さないんだ、というメッセージを割と明瞭に発していてこれはいいのですが、問題はトランプもそうなのか、あるいは言葉だけでなく行いによってウクライナの主権維持を支援するのかどうかです。
ここが見えてこない限り、やっぱりトランプの対ウクライナ政策には不安が残ります。
大荒れのミュンヘン国際安全保障会議
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?