
プレオンラインツアーを開催しました
空き家になっていたアンティーク日本の心を、街角サードプレイスにリノベーションするプロジェクトを今年3月中旬からスタートして2ヶ月半が経ちました。手探りですがこの間、片付けや掃除、物の譲渡に取り組んできました。
次の段階に向けて、サードプレイスのビジョンやコンセプト、コンテンツをつくります。それに向けて、地域の方や関わってくれる方とコミュニケーションを取りたいと考えました。
そもそも、理想の街や地域とは何か、この街や地域にはどんな資産や課題があるのか、こういったことをオンラインでお話してきましたので、レポートとしてまとめます。
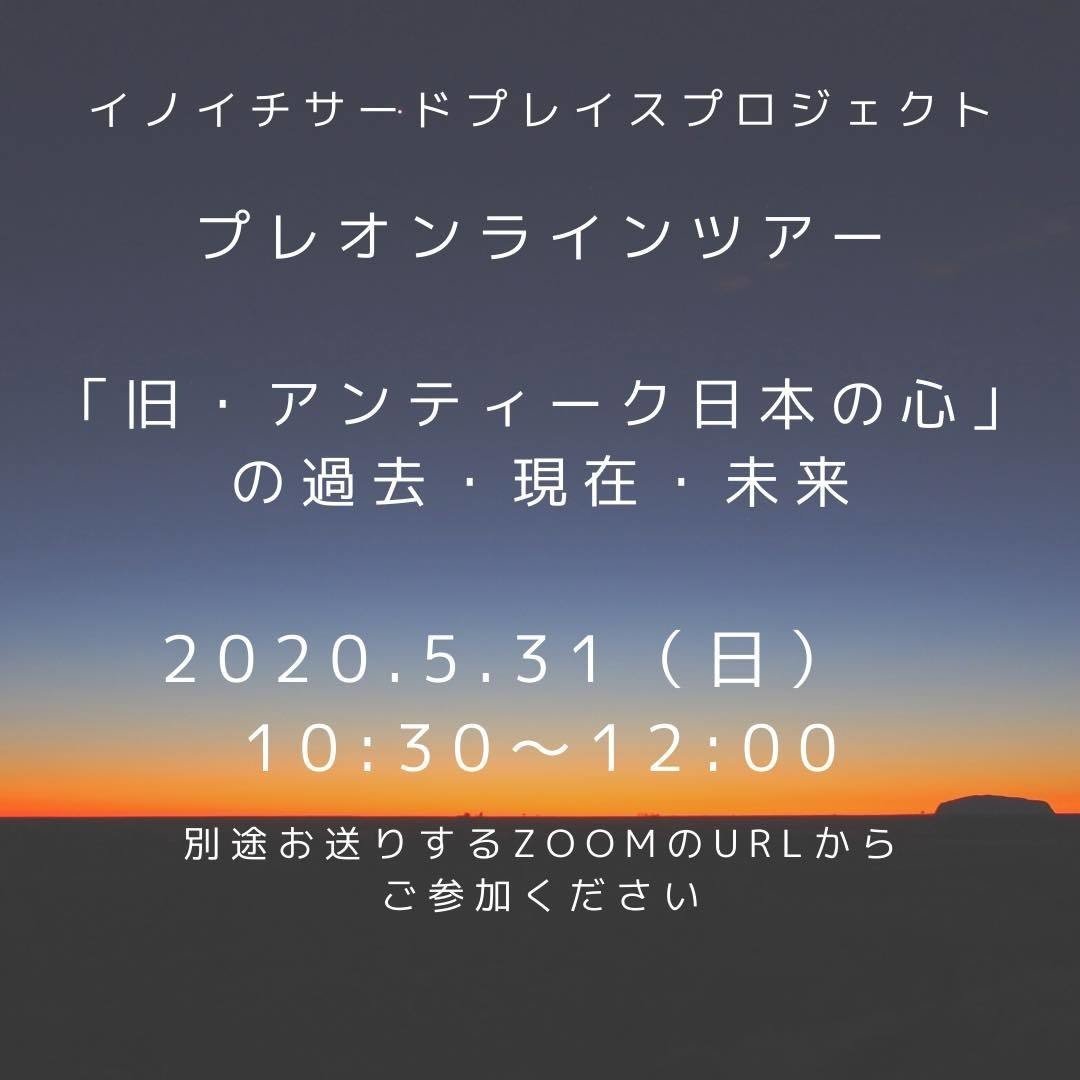
<参加者>
竹上さん 井の頭一丁目町会長
横山さん 井の頭地域在住
岸本さん 井の頭地域在住
加藤さん 井の頭地域在勤
Sさん まちづくり会社元スタッフ
舟橋 牟礼地域在住
みんなのブックカフェ
はじめに、参加者それぞれの自己紹介を含め、直近の活動や関心について聞いてみました。
竹上さんはご主人が転勤族だったこともあり海外と日本を転々とされていました。15年前に三鷹に落ち着き、何か自分らしい活動ができないかと考え、地域の居場所づくりを始められました。
それが「みんなのブックカフェ」です。今年で12年目になります。三鷹台児童公園内の井の頭東部地区公会堂で、隔週の火曜日に開催しています。(コロナ感染拡大予防のため、しばらくお休みしています)
絵本や紙芝居の読み聞かせ、昔遊び、工作、シニア向けヨガなど、多世代が気軽に楽しめる場所です。
コロナ禍においてもできることをやっていこうという、前向きで柔軟な発想とスピーディーに実行に移す行動力が井の頭一丁目町会にはあります。
外出自粛が続く中、「電話でおしゃべりプロジェクト」「Facebookカバー写真コンテスト」「ミニトマト鉢プレゼント」などの町会事業に矢継ぎ早に取り組みました。
井の頭一丁目町会の活動の様子はこちらのブログやFacebookをご覧ください。
ナナメの関係
横山さんはお子さん2人の4人家族で、井の頭地域に住んで今年で8年目です。ご夫婦ともに地方出身ということで、当初は地域に頼れる人がいませんでした。
子育てするにあたり、自分たち親以外にも、地域で暮らすたくさんの大人と関わる機会が欲しいと常々思っていました。
そういった「ナナメの関係」をつくれないかと、数年前に竹上さん相談をしに行きます。そこから、この記事の後半に出てくる「いのいちリビング」といったイベントの誕生につなげていきました。
自分たちと似たような思いを持っているファミリーも増えてきた、と横山さん。街ですれ違った時に、ちょっと挨拶できる関係性を増やしていきたいと考えています。
オンライン教育
岸本さんもお子さん2人の4人家族で、井の頭地域に住んで5年になります。井の頭地域におばあさんが昔住んでいたこともあり、この地域には元々馴染みがありました。
今年度から、お子さんが通われている小学校のPTA役員をやるようになりました。コロナ禍においてもzoomで会議をしたり、インターネット上で総会の議決を取ったりと、工夫してPTA活動を続けられています。
3ヶ月間もの間休校となってしまった学校が多いです。時間や場所にとらわれない「オンライン教育」のゆくえに関心を寄せられています。
ピンチの時にでもつながりを
加藤さんは地域福祉の仕事をされつつ、子育て中でもあります。特に、シニアが地域社会につながっていくために、どんなことができるか考え、実践されています。
コロナ禍においてナーバスになっているシニアがたくさんいます。今までは地域に対して面で関わることが多かったけれど、個々の不安や困りごとに対して関わっていくことが必要と考えています。
さまざまや世代がいての地域であり、ピンチの時にでもつながりを保てる地域を作っていきたいです。
地域の活動はまとめちゃいけない
Sさんは私が以前プロボノ(ライター)として関わっていたまちづくり会社の元スタッフです。現在は別の会社で、エリアマネジメントやまちづくりに携わっています。また、新しい活動を始められた人からいろいろ相談を受けたりされています。
地域の活動はまとめちゃいけない、地域で自分が生きている心地がしないのはよくないこと、とSさん。東日本大震災以来、まちづくりの仕事を始めてからそうしたことを実感しています。
地域に足がついている人たちで、協力して街や地域を良くしていければいいです。
理想の街や地域とは
次に、「理想の街や地域とは」というテーマで、それぞれのアイデアや考えを出してもらいました。
zoomのホワイトボード機能を使って、参加者全員が一枚のホワイトボードに書き込みました。

「ちょっとした困りごとはお互いさまで支え合える地域」 竹上さん
「多世代が交流して、いつまでも住み続けたくなる街」 〃
「ナナメの関係」 横山さん
「楽しい、楽ちん、気が楽」 岸本さん
「それぞれの人がそれぞれの温度でゆるやかに集える、つながれる」 加藤さん
「困ったときは気軽にSOSが出せる、気付きあえる」 〃
「良いことも悪いことも(楽しい時も困った時も)共有できる」 Sさん
「サードプレイス、ソーシャルグッドプレイス」 舟橋

それぞれの目線から見えている理想の街や地域が言語化されたことで、目指すべきビジョンのイメージが、クリアになってきました。
こうした理想の街や地域を実現するうえで、これからつくるイノイチサードプレイスプロジェクトのコンテンツが、少しでも貢献できるものになっていけばいいです。
直面するハードルや阻害要因を洗い出し、課題を設定し、具体的な解決に向けてPDCAを回していくことが重要だと考えています。
井の頭や三鷹武蔵野の資産とは
3つ目のテーマは「井の頭や三鷹武蔵野の土地固有の資産とは」です。
この街や地域で暮らしているからこそ見えてくる、その土地ならではの歴史や自然、文化、人など、有形無形の資産を、ざっくばらんに話し合いました。

小規模店舗の存在
馴染みの小規模なお店がまだ残っているのがいい、と岸本さんは言います。井の頭3丁目にある「栗原ストアー」や「島長」(鮮魚店)など小規模店舗だからこそ、顔の見える関係が築け、安心して買い物に行けます。
配達もしてくれるという便利さや、子どもが一人でも気軽に買いに行けるという安心感があります。
栗原ストアーを入って奥に島長があります。店の外からも注文できます(写真左の小窓から)。

せっかくなので私も買ってみました。大型スーパーにはなかなか無いラインナップでした。

井の頭公園通り沿いにある「マルナカ」は2017年に閉店しましたが、規模縮小して再開しています。
野菜や果物、豆腐など必要な食料品はだいたい揃っています。とりあえずあそこにいけば何かある、と感じるお店が近くにあることは、生活する上で大きな魅力の一つです。

店主の高齢化と後継者不足
一方でこういった小規模店舗が必ずといっていいほど直面する問題が、店主の高齢化と後継者不足です。
2018年度商店街実態調査によると、商店主の退店(廃業)理由の1位は「商店主の高齢化、後継者の不在」(74.0%)、商店街が抱える問題の1位も「経営者の高齢化による後継者問題」(64.5%)とあります。
一方で、後継者問題に対して対策を講じていない商店街が大半(91.2%)です。
井の頭1丁目にも、惣菜も売っていた肉屋があったが現在は閉店している、と竹上さん。
店主の高齢化と後継者不足は根深い問題としてありつつも、三鷹台駅前や井の頭公園駅前の飲食店は比較的新しいお店も多く、すぐ地域に慣れている様子です。
いのいちリビング
住宅街にしては珍しく広く緑豊かな公園である「三鷹台児童公園」ではこれまで、井の頭一丁目町会主催でキャンドルナイトや春のお祭り、フリーマーケットなど、様々なイベントが実施されてきました。

2018年6月には、音楽ライブや子ども店員カフェ、昔遊び、お下がり交換コーナー、綿飴、青空囲碁・将棋、子育て情報マップといった盛り沢山なイベント「いのいちリビング」が加わりました。
発端は、横山さんご夫妻が「プレーパークがやりたい」と提案したことからでした。
じゃあみんなで考えよう、ということで4月に「三鷹台児童公園を考えるワークショップ」を開催しました。公園をこんな風に使いたい、こんな施設にしたいと夢を語り合い、まずは「すぐにできること」をやってみようということになったのでした。
いのいちリビングは、これまで4回にわたって開催されてきました。昨年7月に開催された第4回には三鷹台駅前の鉄板焼き店「サブライム」にも出店してもらい、じゃこカツバーガーや焼きそばは大好評でした。

若い世代を受け入れる懐の深さ
子育て中の若いメンバーが企画を考え、町会の運営委員や防災を考える会のメンバーなどがそれをサポートする、という信頼関係が背景にあります。
「アウェーの人たちをすんなり受け入れる雰囲気が(井の頭には)ある」と横山さんは言います。
若い世代の考えたアイデアに対して、長く住んでいる方たちが快く協力してくれる、様々なお願いにも気軽に応じてくれる、という懐の深さや気風があります。
「(今までも少しずつ動いてきたが)横山さんご夫妻が2年前くらいから町会活動に関わってくれるようになってからさらに楽しくなった、町会活動も捨てたもんじゃない」と竹上さん。
井の頭一丁目に住むおもしろい人を発掘
井の頭一丁目町会では「井の一 リレーおもしろ講座」と題して、町内の魅力ある多才な方々のお話を聴いたり、パフォーマンスを披露してもらう会を開催しています。
これまで、南極観測船「宗谷」乗組員だった高尾一三さんやカナダ人和紙研究家のポール・デンホードさん、心理学者で口笛名人でもある山口実さんを招きました。
今後は、「イタリア人に学ぶコミュニケーション術(仮)」を近々開催予定です。街や地域にはおもしろい人がたくさんいらっしゃいます。そうした人たちを発掘して、オープンなコミュニケーションが取れたら素敵です。
最近のイノイチサードプレイスプロジェクトの進捗
4番目として、私からイノイチサードプレイスプロジェクトのこれまでとこれからについて、プレゼン資料を元に情報共有しました。
3月の初日から比べればだいぶ片付けや掃除が進んできました。顔馴染みの方も増えてきました。昔のアンティーク日本の心の様子を話してくれたり、当時の写真を見せてくれたり、とあるインフルエンサーの影響で思わぬ方が訪れたり、多くの方が譲った食器や物の写真を店前に貼ったり、着実に前進している実感があります。

自宅以外でテレワークできる場所の必要性
子育て中のファミリーは共働きがほとんどです。突然の外出制限や休校、テレワークなどにより、家庭には相当な負担が生じています。学校から山のように出された課題を見つつ、食事の用意もして仕事もするというのは、困難を極めます。
コロナが一旦落ち着いたとしても、第二波や第三波の懸念は払拭されていない状況です。仕事効率化の観点だけではなく、危機管理の文脈からも、テレワークは有効であることが、今回のコロナ禍で半ば証明されました。
しかし、小さい子どもが自宅にステイホームしている中、自宅で仕事をするのは難しいこともわかりました。
夫婦2人がテレワークだとすれば、1人が子どもの面倒を見て、もう1人が近所のテレワーク施設で仕事する、ということができれば負担はいくらか減らせます。もちろん「新しい生活様式」など、感染予防に対する配慮をしたうえで。
空き教室や空き家など、街や地域には、以外と空いている(ように見える)スペースが点在しています。こうした遊休空間を有効活用できればいいです。
イノイチサードプレイスプロジェクトとして、モバイルルーターの整備などにより具体化できるか、今後考えていきます。
最後に一言
「zoomがとても便利なツールで、世代も場所も違う人たちとコミュニケーション取れるのが良かった」 竹上さん
「(井の頭地域にある)企業の社員寮や学生寮に住む若い社会人や学生が、引き続きこの地域に住みたくなるような、または関わりたくるような地域をつくっていきたい」 横山さん
「大人にとっても子どもにとっても、人とつながる機会が身近な場所にあることはとてもいい」 岸本さん
「老いても地域で何か楽しいことに関わったり、役割をもてたり、多世代に気軽に(オンライン含め)つながれる場があるって大事」 加藤さん
「街や地域はそこにいる人たちのものだから、皆さんの好きなように、楽しいようにつくっていってほしい」 Sさん
まとめ
30分近くオーバーしたオンラインミーティングでしたが、生のご意見や声がダイレクトに聞けたことは大きな収穫でした。世代も性別も職業も趣味も抱えている課題もバラバラな人たちとのコミュニケーションは、発見や気付きを得られるばかりでなく、自分の考えを相対化できる良い機会です。
多くのヒントが得られましたので、咀嚼して、次のアクションや仮説検証につなげていきます。
イノイチサードプレイスプロジェクトのInstagram
イノイチサードプレイスプロジェクトのLINE公式アカウント
いいなと思ったら応援しよう!

