
国内TCGのジャッジ裁定について思う事
皆様こんにちは、カードランドです。
noteの執筆は久しぶりですが、近頃の国内TCGに対して少々思うところが
あったため、筆を取った次第であります。
それは…
近頃の国内TCGのジャッジ裁定厳しすぎませんか?
です。
今回はそう思った経緯と、ジャッジ制度の始祖と言えるMTGにおけるジャッジ裁定に関する歴史と、今のジャッジ裁定に思う事に関して綴らせて頂きます。
1.このnoteを書こうと思ったキッカケ
「プレーヤーを守るためにルールがある」
— Naoya Kihara/木原直哉 (@key_poker) February 4, 2025
と考えるのがアメリカ含む多くの地域での根本的な思想なんだけど、日本では
「ルールを守るためならプレーヤーの損に繋がってもしょうがない」
という思想が強すぎるといつも思う。
ポーカーに限ったことじゃなくあらゆる界隈でそれを感じる。
Xのタイムラインを見ていると、このようなポストが回ってきました。
ポスト主の木原プロは、日本を代表するポーカープロの先駆者のような存在で、かくいう私も木原プロが出演されたTV番組を拝見し、憧れ、ポーカーに触れた一人です。
このポストを見て、日本のTCG環境にも当てはまってるなと感じたと同時に、近年思っていた「国内のジャッジ裁定について思う事」の言語化が出来るかもしれないと思い、このnoteの執筆に至りました。
ポストにある「ルールを守る為ならプレイヤーの損に繋がってもしょうがない」という思想は、今の国内TCGのジャッジ裁定における根源的な思想にも通ずると感じております。
特に近年ではプレイミスに対する裁定や、スリーブの状態に対する処分が非常に重くなっていると感じています。
2.TCGの大会というのは何のためにあるのか?
ここで一度考えたいのが、
「TCGの大会とは何のためにあるのか?どうして開催するのか?」
という前提の話です。
これは恐らく主催者側の立場によって変わる話で、
例えばカードショップが開く場合は
・ユーザーの来店動機を増やし、売上向上に繋げたい
・参加費として参加費の徴収や商品の購入等を促す
これが個人主催の非公認大会になる場合は
・主催者の知名度等を広めたい
・ユーザーのプレイ環境を広めていきたい
大体このような理由だと思います。
では、メーカー側が大会を開く理由は何でしょうか?
理由は1つに集約されると思います。
・そのコンテンツの売上を増やしたい
これが最大の理由になるでしょう。
何故ならば、メーカー側は商品の売上を上げることが最優先事項であり、
メーカー主催の公式大会やその他施策は、全て安定的な売上向上を促す為に行っているのです。
あり得ない仮定の話ですが、仮に大会の有無が売上に一切繋がらないのであれば、少なくともメーカーが大会を開催することはないだろうと思います。
しかし近年、このメーカー側のイベント開催理由と実際の大会シーンでの
ジャッジ裁定の厳しさが、結びついていないと感じることが多々あると感じております。
3.MTGにおけるジャッジ裁定の歴史
※筆者は本格的なMTGプレイヤーではなく、TCG業界の勉強の為に文献等を読み漁って得た知識となります。もし間違った内容があれば恐縮ではございますが、ご指摘頂けると幸いです。
TCGにおけるジャッジという存在を語る上で、やはり"マジック:ザ・ギャザリング(以下:MTG)"の存在は欠かせません。
MTGは今から約30年前の1996年、プロツアーと呼ばれるいわば世界大会がスタートしました。
では、この時代の裁定とはどうだったのでしょうか?
とある文献では「暗黒時代」と揶揄されるレベルで、相手の不備やプレイミスを指摘し合う文化が存在していたと言われています。
少しでもコストを支払う意思を見せたら巻き戻しは出来ず、わずかでも宣言が間違っていた場合は、もはや難癖というレベルで、指摘した側が有利になる裁定が出ることが多かったという時代だったようです。
この時代に関しては例に持ち出すこと自体が議論の極端化を招く可能性もありますが、しかし昨今の国内TCGの実情も似たような状況になってきていると感じる所もありましたので、ご紹介させて頂きました。
そのような暗黒時代を抜け、現在ではどのようになっているのでしょうか?
4.「TCGは揚げ足を取るゲームではない」
現在のMTGは、プレイミスや宣言ミス等に関して、競技的な大会であっても、良く言うと非常に大らかに、悪く言うと緩くなっています。
有名な所で言うと、昔はパクト死(契約死)という概念がありました。

ある程度TCGの経験がある方ならばルールを知らなくても読み取れると思いますが、このカードは平たく言うと「その場ではノーコストで使えるけど、次の自分のターン開始時にコスト払えなかったら負ける」というカードです。
何故"パクト死"という言葉が存在するのかというと、ターン開始時にこの処理を失念し、山札からカードを引いてしまった時点で、コストを払わなかったとなってしまい、ゲームに敗北となります。
例えコストを支払えていたとしても、カードを引いてしまったら負けてしまいます。
MTGが暗黒時代から緩和し、ルールに関して寛容になりつつあった後も、このパクト死自体は存在し続けていました。
各プレイヤーは山札の上にダイスを置いたりし、カードを引く前にコストを払うことを失念しないように努力していました。
では、現在はどうなっているのかというと、失念による過失でのパクト死は存在しなくなりました。
近年のMTGでは「TCGは揚げ足を取るゲームではない」という前提の元で動いていると聞いたことがあります(どこかのblogで見た記事だったかと思うのですが、文献が見つけられませんでした)。
暗黒時代を得て、30年のノウハウの蓄積が示した先は、賛否両論がありながらも「揚げ足取りはさせない」という理念にたどり着きました。
これが前述した木原プロのポストにある「プレイヤーを守るためにルールがある」にも通ずる考えなのだと思います。
そして、この理念を象徴とする裁定に「決定の撤回」という概念が存在します。
これは簡単にまとめると「非公開情報を得てない限りは、誤ったプレイを巻き戻すことが出来る(ジャッジ判断)」といった趣旨です。
国内のTCGだと、"シャドウバースエボルヴ"が「選択の撤回」を大会ルールで採用しております。
選択の撤回について
プレイヤーは、ゲーム上における自身の選択について、通常は撤回することが出来ません。
しかし、当該のプレイヤーがその選択を行った後に「ゲーム上における新しい戦略的な情報」を得ておらず、更に「ゲームが進行した」と認められない場合、その選択を撤回することが可能です。
この場合の「ゲーム上における新しい戦略的な情報」とは、「カードを引く」「カードのプレイ」「能力のプレイ」「攻撃やターン終了の宣言を行い、対戦相手がクイックを持つカードを持っているかの判断情報を得ること」「ターンの終了」「対戦相手のリアクションからの類推情報」「対戦相手からのゲーム情報における指摘」などを指します。
5.現状の国内TCGではどうか?
では、現状の国内TCGではどうでしょうか?
仮に先ほど挙げたMTGで言う「~~の契約」のような処理のカードが存在していると仮定します。
それでターン開始時の処理を失念していた場合は、恐らくゲーム自体の敗北の処理が進められると思います。
国内のTCGでは、原則として"巻き戻し行為"が認められておりません。
対戦中に、ルール上問題の無い行動を取り消すことは、原則としてできません。対戦相手が断りなく 操作を修正しようとしたときは、ジャッジ(またはスタッフ)を呼んで対応をしてもらいましょう。
ワンピースカードゲームでは、2025年2月より"公認ジャッジ"制度が始まりました。
現在、フラッグシップや8パックバトルに関しては、店舗での公認大会だとしても、公認のジャッジが派遣されるシステムとなっております。
そしてワンピースカードゲームに限らず、国内のTCGにおける裁定では、前述のエボルヴを除き、「決定の撤回(巻き戻し)」に関しては容認されることはありません。
特に競技的な大会においては「過失でもルールをミスった側が悪い」となるケースが大半です。
これが「ルールを守るためにはプレイヤーが損をしてもしょうがない」という思想が適応されている最たる例だと思います。
ここでいう"プレイヤーの損"というのは、ゲーム上の展開もそうですが、その後の感情にも付随します。
"イベントに参加した上で不快な思い"をして帰る事に繋がりかねません。
それは果たして「そのコンテンツの売上を増やしたい」というメーカーの開催理由と合致するものでしょうか?
「カードゲームの大会とは誰の為に存在するのか?」という根源の本質的な部分だと思います。
その上で先日、当店で起こった事例をご紹介します。
先に申し上げますが、公認ジャッジ様を否定する意図は一切ございません。
来店していただいたジャッジ様には非常に感謝していますし、ジャッジ様個人を批判する内容ではないことを予めご理解いただけると幸いです。
起こった事例は以下のものです。
①"パワー6000"のキャラに"パワー9000"のキャラが攻撃を仕掛けた。
②それに対し、防御側は"カウンターで3000分のカード"を捨て、防御した。
③本来であれば攻撃側の"パワー9000"に対し防御側も同値の為、このままでは攻撃が通ってしまうが、お互いのプレイヤーはそれに気づかずにゲームを進行した。(この時点では攻撃側は守られたと感じ、防御側は守ったという認識)
④防御側のターンに移り、ターン開始時の処理が終わったタイミングで、攻撃側のプレイヤーが前のターンの攻防で防御値が足りていないことに気づき、ジャッジを呼ぶ。
このような流れでジャッジが呼ばれ、ジャッジから下された内容は
「攻撃は通ったものとして防御側のキャラはKO、使った防御札は戻ってこない」という処理でした。
私は横でその裁定を聞き、率直に「厳しい裁定だな」と感じました。
基本的に手札が無条件で2枚失うということは、ゲームロスに近い裁定とも言えます。
まずこのケースでは攻撃側も防御側も、防御に使ったカードの詳しい内容はお互いで確認が取れています。
そしてターン開始時の処理まで進めている以上、巻き戻して追加でのカウンターを認める処理は難しいとは思います。
その上で、本来ゲーム上誤った処理を進めているのは、それを誘発した側は防御側でもありますが、攻撃側にも一定の落ち度があるように思えます。
この場合、もし私個人が大会のジャッジとして運営を行っていた場合は、「ゲームが進んでる以上、その場面巻き戻すことは出来ないのでそのままKO、防御で誤って使用したカウンターは戻す。ただしこの事態を誘発した防御側のプレイヤーにはペナルティとして注意」という判断を下していたと思います。
繰り返しになりますが、公認ジャッジの場合はマニュアル等があると思いますし、ジャッジの方針がある以上、厳しい裁定になるのも致し方ないと思います。これは裁定に対しての批判・否定の意思によるものではなく、あくまで相違点として捉えて頂けるようお願いいたします。
6.ルールミスを誘発するカードデザインの数々

ことワンピースカードゲームに限った話をすると、画像のような「次の相手のターン終了時まで~」という効果が多数存在します。
画像の2枚も、現時点の環境でバリバリ活躍しているメジャーなカードです。
先日の日本一決定戦の配信中も、左側の緑紫ルフィ側が自身のパワーを失念し、カウンターで使用したカードを変えるという光景がありました。
私自身色々なカードゲームをプレイしてきましたが、ここまで「次の相手のターン終了時まで~」という効果が乱発されるカードゲームは見たことがありません。
何故このような効果が一般的に少ないのかというと、やはり"当事者同士で揉める"事が非常に多いからだと思います。
本来常駐効果を除き、ターンを跨ぐ誘発効果が発動する場合は、カードの上にカウンターの乗せ、目印とすることが多いと思います(+1/+1カウンター等)
しかしワンピースカードの場合、このような効果を発動するにおいて、カウンターを乗せるといった処置は義務ではありません。
悪く言うと「忘れた側が悪い」という構造になっています。
人は誰しもミスをします。
それこそ、日本一決定戦という強豪プレイヤーがひしめく舞台であっても、効果の失念は起こっていることから、どうしても起きるミスでもあります。
こちらの当店での裁定はあくまで公認ジャッジ制度が始まる前での裁定の指針ではありますが、当店では前述の「ゲームが進行していない場合での選択の撤回」を認め、このような事態をお互いのプレイヤー同士で防ぎ合おうという方針を取っておりました。
7.公式大会とは何なのか?ジャッジとは何なのか?
果たして公式大会において、ルールに関して「忘れた側が悪い」という思想は正しいのでしょうか?
現状の絶対の答えはありません。このnote自体も"これが正しい!"という趣旨ではありません。
あくまで近年多発している事に対する"問題提起"と"私が思うこと"を書き綴っています。
多発している問題としては、近年"スリーブによる失格"も多く発生しております。
もちろんマークド行為や、作為的な積み込みは許容されることではなく、明確な確証があれば一発で失格にするべきだと思います。
しかし近年では、意図的とは思いにくいスリーブの不備に対して、ゲームロスや受賞資格の停止等も多く発生しております。
この失格を含む厳しい裁定が当たり前になりつつある状態は、非常に悪い流れだと危惧しており、一種の「暗黒時代」と言っても差し支えがないように思えます。
もちろん過度な汚れ等は許容できないかもしれませんが、スリーブは消耗品です。
毎試合毎に交換するのは現実的ではありませんし、大会のたびに変えるというのも少し過剰に思えます。
そして、このスリーブ論争の行き着く先は、悪意ある者による"武器"にもなり得ます。
具体的には負けそうになった時、ダメ元で相手のスリーブの不備を指摘するという行為に使われる可能性です。
本来、正しい行為である"指摘"が、行き過ぎた取締りとも言える大会環境の中では"武器"に代わり得ます。
近年のスリーブ不備のペナルティの取り方は、このような事態を既に引き起こしている節が僅かではありますが、見受けられます。
当店でも競技性かつプライズ性の高い大会を運営している最中に、「相手のスリーブをチェックしてほしい」という旨のご要望をもらうことは稀にあります。
具体的に「〇〇に作為的な要素を感じる」といったご指摘があれば良いのですが、中には高額な賞品の為に、対戦相手の失格(ジャッジキル)を狙ってそうな指摘だと感じることもあります。
繰り返しになりますが、これは積み込みや、マークド行為への擁護ではありません。”武器”に変わりつつある”指摘”に対しての危惧であり問題提起です。
以上を鑑みて、今一度
・大会イベントとは何なのか?
・ジャッジとは何なのか?
という本質をメーカーも小売りもユーザーもジャッジも、考えるべきなのではないと愚考する次第です。
8.私が思う理想とこれからの危惧
最後に、私が思う理想を書き綴ると、
大会は「一人でも多くの人に楽しんでもらい、皆が不快な思いやモヤモヤを残さずに帰られる事、その上で悪質なプレイヤーには悪・即・斬の精神」
ジャッジは「"正確"ではなく、"正常"なコミュニケーションゲームに近づけるための補助的要素」
となることです。
本来「そのコンテンツの売上を増やしたい」大会で、不快な思いをさせたり、遺恨が残るような体験をされることは、容認されるべきではないと思いますし、コンテンツの未来の為に、極力減らしていく方針であるべきだと思っております。
ジャッジも、正確さだけを求めるのではなく、正常なコミュニケーションでゲームを本来進むべきであった結果へ進むようにする役割が、本来求められることなのではないでしょうか?

正確さだけを求めた先に何があるのでしょうか?
それは揚げ足取りするプレイヤーが是とされ、増加する結果になっていきかねません。
例えば画像左側のシャンクス、多くの方が相手の攻撃に対し
「リーダー効果とカウンターを切ります」という宣言で処理していると思います。
しかし、正確には「リーダーかキャラ1枚までを」なので、そのバトルに参加していないカードも対象に取れますし、対象を指定しないこともできます。
ですので「リーダー効果の対象を宣言していないので0枚解決で、攻撃通ります」という揚げ足取りも出来なくはありません。誰も言ってないだけで。
そんな馬鹿な事が、と思うかもしれませんが、このゲームでは画像右の子供ルフィ達の宣言問題が登場以降問題となっています。
宣言した時点でパワー上昇を適応しないケースは絶対にあり得ないのですが、「リーダーの指定がなかったので、0枚対象で」という指摘が起こってますし、それが公式大会でもジャッジの裁定で適応されることもあります。
シャンクスのケースはこのような指摘がまかり通っていってしまう果てにある事例になっていくと思います。
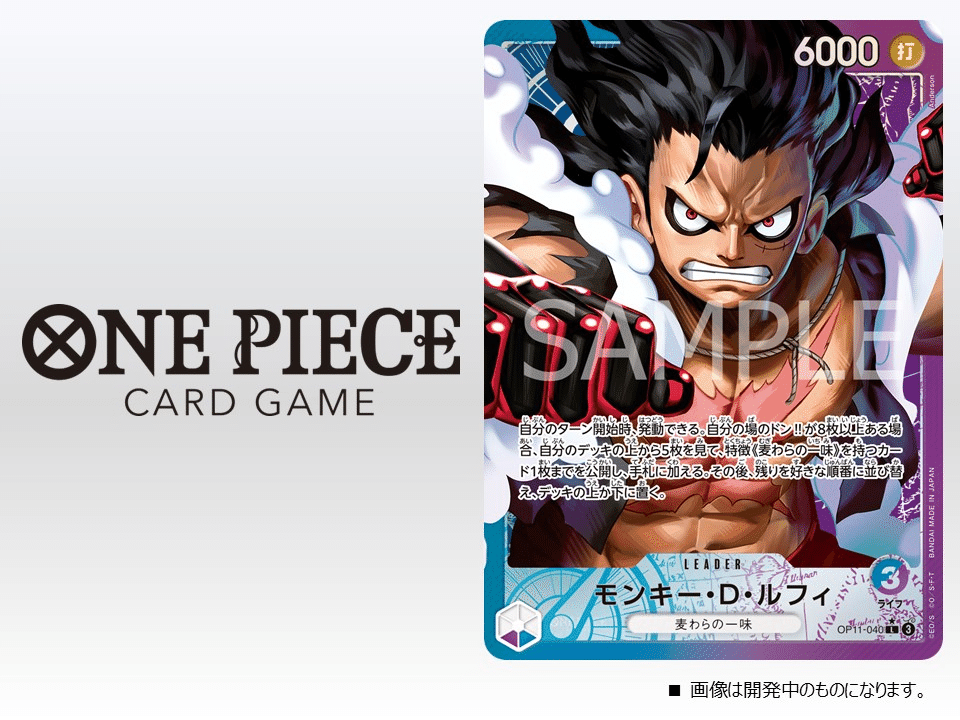
11弾収録のリーダールフィも、これから誘発忘れが多発する1枚になるでしょう。
このカードの効果は「自分のターン開始時、発動できる。」となっている為、"発動しない"という選択肢を取ることが出来ます。
そして、ワンピースカードゲームにおいて、自分のターン開始時とは、リフレッシュフェイズに属します。
6-2. リフレッシュフェイズ
6-2-1. 「ターン開始時まで」と表記されている、現在まで適用されてい る効果が無効になります。
6-2-2. 自分または相手の「ターン開始時」と表記されている効果が発動します。
6-2-3. 自分のリーダーエリア、キャラクターエリアのカードに付与(6-5- 5-1.参照)されているドン‼カードすべてをコストエリアに戻します。
6-2-4. 自分のリーダーエリア、キャラクターエリア、ステージエリア、コ ストエリアに置かれているレストのカードすべてをアクティブにしま す。
リフレッシュフェイズ中であれば、解決が前後しても解決可能だと思われますが(フェイズ中にも解決順が決められているなら話は変わります)、その後のドローフェイズやドンフェイズまで進んでしまうと、発動しないと選んだとなります。
もちろんドローフェイズまで進んでカードを引いてしまっている場合は、そうなってしまうのは致し方ないとは思いますが、恐らく各地でジャッジ案件が発生するリーダーになりそうだなとは思います。
そして仮定の話ですが、リフレッシュフェイズの処理順が「ターン開始時効果誘発→ドン戻し&ドン追加」という順で解決が義務付けられているのであれば、「ドン追加したのでターン開始時効果誘発のタイミングを逃すので不発です」という"武器"にもなりかねません。
このまま相手の宣言漏れや誘発忘れ、それを逆手に取った番外戦術と言っても良いようなジャッジへの申告が横行するのであれば、そしてワンピースカードに限らず、それが国内TCGにとっての当たり前として定着してしまったら、それはMTGにおける「暗黒時代」のような時代に戻ってしまうのではないでしょうか?
MTGが30年前に通った道を、国内TCGは今通っている最中なのかもしれません。
このnoteが、その道を少しでも舗装できればと思います。
今回の内容は賛否が分かれるものだと思います。
「間違えた方が悪い」「忘れた側が悪い」という方も、もちろんいらっしゃると思います。
しかし私は、
「ルールでプレイヤーの損を許容する」世界よりも
「ルールでプレイヤーを守る」世界であってほしいことを願っています。
以上です。
長くなってしまいましたが今回の記事を読んでくださり、ありがとうございました。
