
AI時代に求められること - 人間にしかできない3つの力
前回のnoteでは、AIの進化について見てきましたが、今回は「私たち人間にしかできないこと」について考えていきます。
前回、最近のAI(生成AI)は使い方のコツも変わってきていますと書きましたが、そもそも今のAIが得意なことから見ていきましょう。
AIって、こんなことが得意なんです
AIは、私たちの「お助けサポーター」として、こんなことが得意です。
一般的な知識をサッと教えてくれる:例えば、「かぼちゃの栄養って何?」と聞くと、すぐに答えてくれます。
正解を素早く見つけてくれる:「運動会のプログラムの時間配分、これでいいのかな?」というような計算も、あっという間!
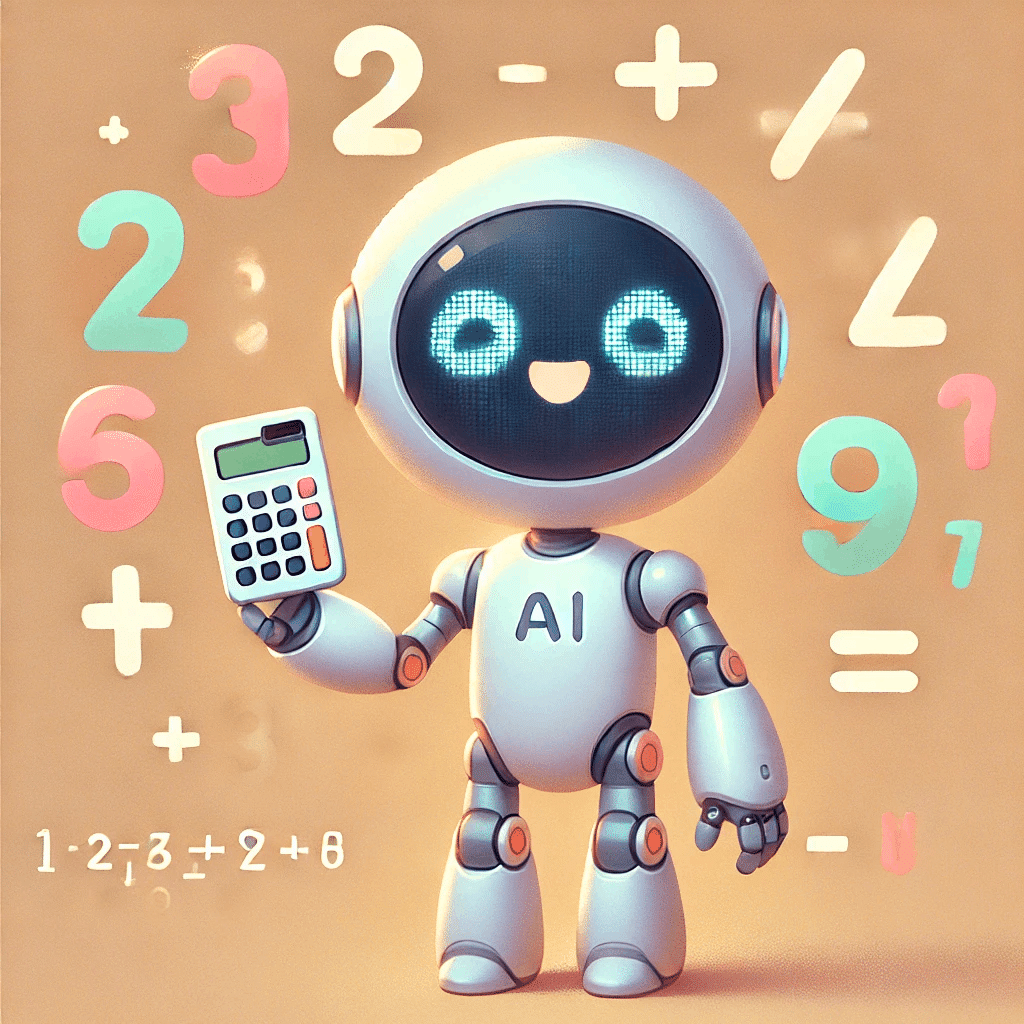
つまり、AIは「これまでの知識を探して答えを出す」のが得意なんです。でも、例えばこどもの成長も「正解」なんてないですよね。「どんな答えが必要なのか?」を考えるのは、やっぱり私たち人間の仕事。だからこそ、次に紹介する「人間にしかないもの」が大切になってくるんです。
でも、人間には素敵な「持ち物」があります!
AIが持っていない、私たち人間だけの「特別な持ち物」があるんです。

それは...
「いつか○○になりたい!」という夢
「やってみたい!」という欲求
「なんでだろう?」という好奇心
「これが好き!」という情熱
子どもたちが砂場で夢中になって遊ぶように、私たち人間には「夢中になれる力」があるんです。
AIがどんなに賢くても、「何に応えるのか?」という 「問い」がなければAIは応えようがありません。
そして、「問い」を生むのは、好奇心とか情熱とか夢中になれる力だと思っています。
AI時代に光る3つの「すごい力」
では、最後にこれからのAI時代に何が人間に求められるか、それに合わせて伸ばしていきたい力を考えてみます。これは会社経営に携わり、このような若い人と仕事したいと僕なりに考えた力です。
もちろん、勝手に僕だけが考えたものでは意味がないので、国が出しているはじめの100ヶ月の育ちビジョン、第4期教育振興基本計画、「令和の日本型学校教育」の構築を目指してなどを参考にしながら乳幼児期の教育と重ねてまとめてみました。
1. 夢中を探求し、個性を発揮する力
園庭で、ある子は虫探し、別の子は鬼ごっこ、また別の子は砂遊び...。それぞれが違うことに夢中になれるのは、素晴らしい個性の表れですよね。
2. 問いを生み出し、経験から学び続ける力
「どうして空は青いの?」「なんで雨が降るの?」
子どもたちが投げかける「なぜ?」という質問。実は、これこそが人間の大切な力なんです。AIは答えを出すことはできても、問いを生み出すことは苦手。だから、問いを立てられる私たち人間の出番なんです!
3. 多様な人々と協働し、豊かな人間性を育む力
運動会の準備や、お誕生日会の計画...。みんなで力を合わせて何かを作り上げる時の喜びは、AIには真似できません。
AIは確かにすごい力を持っています。でも、私たち人間にしかできないこともたくさんあるんです。子どもたちと過ごす毎日の中で、この3つの力を意識しながら、共に成長していけたらいいですね。
2回に渡り抽象的な話が多くなりましたので、次回はもう少し具体的にAIをどのように保育・幼児教育で活かすかという点を深掘りしたいと思います。
