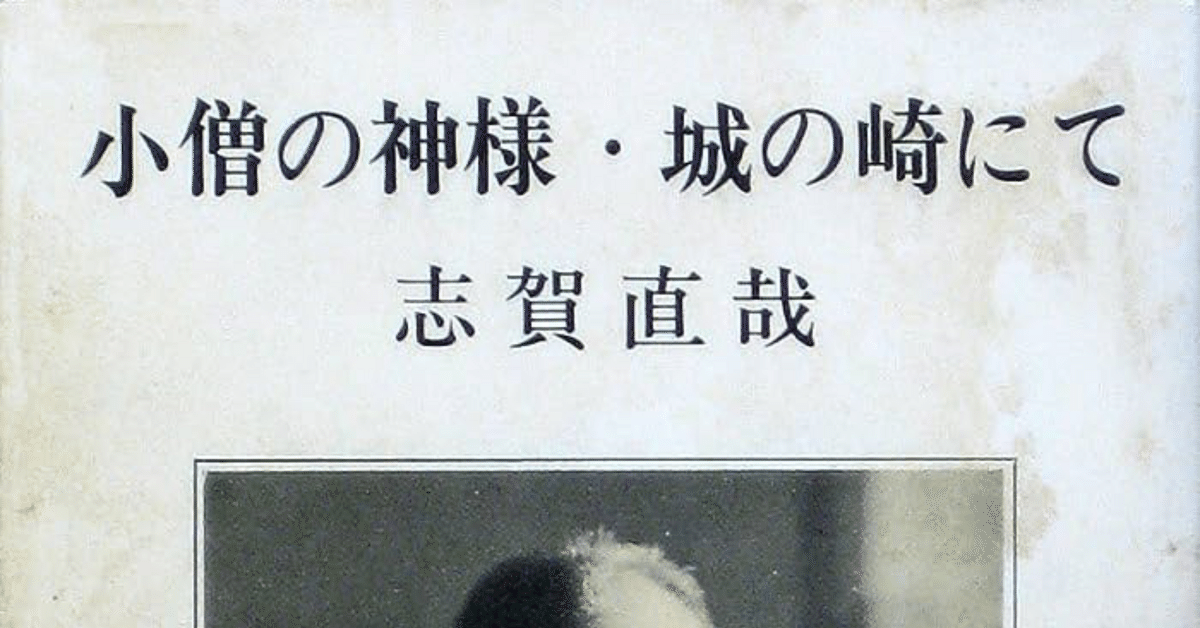
志賀直哉『小僧の神様・城崎にて』(新潮文庫)
とにかく要心は肝心だからといわれて、それで来た。──(『城崎にて』)
2020年、コロナ禍に入り仕事を取り上げられ、やることがなくなると不安も焦りもなくなり、生きていく目的を探すために罪悪感だけが強調される毎日に陥っていった。秋口にもうずっと悪かった父が亡くなり、いよいよ僕の心と身体は死よりも空しい暗渠へ流れ出し、今どこを漂っているのか平静の地上からは窺い知ることが難しくなった。そんな暗闇の中で、たまたま「入門書」のつもりで買っておいた志賀直哉の短編集を手に取った。漱石は『草枕』の読後感を曲に書いてしまう(イタイ)ほど好きな作家なので、新潮文庫のページを巡り、『佐々木の場合』にある端書きに掠め取られて、気がついたらひと息もつかずに読み切ってしまった。今思い返すと、完全に病気してたと思う。
僕はあんまり一気読みとか一気観にステータスみたいなものを感じないので、場面や段落ごとにいちいち立ち止まって考え込んだり、いらぬ連想を抱いていたりしてなかなかページを巡らないので、電車で隣の席の人に読んでるふりだと思われちゃったてたら恥ずかしいなくらいは気が散りながら、できれば文鎮でページをおさえて腕組みしながら読みたいくらいなのだ。それでもすらすら読めてしまう小説は僕はあんまり面白くない。
二回目以降は筆者の狙いにのって、なるべくリズムにのって読むようにする。僕はまだ一回目からそれができない。ときどきできる文体もあるけど、やっぱり自分の世界が割り込んできてしまう。仕事でやっている、楽譜の読み方とそう変わらない。
明治や昭和初期の生活やそこに付随する感触は今のものとまるで違う。最近では心の距離なんていうものはほとんど(笑)扱いである。しょうがない。
でもだからこそ、そのまま読むだけでSFくらい僕の日常との飛躍を感じる話もたくさんあるし、海外のものになるととにかく想像することに力を注ぐ。文体が、とか、技術的な勉強にもなるけど、それよりも実態と想像との距離が遠いので、とにかくきちんと読むこと──書かれていること、その周りにあるものに集中しなければならない。
そののち文豪を横ばいにいろいろ読むようになって、志賀直哉がどれだけ読みやすい作家だったのか思い知ったけど、とにかくなにも難しくない。素朴で、簡潔で、美しい。小細工のない美しさに準えて、和の心や骨董美術品の話に繋げることもできるけど、それは各々が志賀直哉の著作に触れて感じることだと思う。
志賀直哉の入門書として、最適だった。
