
「リスク社会における危機管理」慶応義塾大学法学部2018年
(1)問題
次の文章は、現代社会のリスクに我々がどのように対処すべきかを記したものである。著者の議論を400字程度でまとめた上で、それに対するあなたの考えを、具体例にふれつつ論じなさい。
① 第一に、リスクを取ってでも事業をおこなおうとする決定者とそれにより損害を被る被影響者とのあいだでのコミュニケーションのあり方を詳細に検討すべきである。この点については、ニクラスールーマンがシーラ・ジャサノフのいう「完全に同化されることのない対話」に着想を得て提案している「了解」のあり方が参考になる。
② ルーマンによれば、「了解(あるいは「説得されないままに進捗する了解」という言い方もしているが)とは、「了解しあわなければならない者を、その信念から引き離したり、改心させたり、あるいはどんなかたちであれ変えさせようと試みたりはしない」かたちでのコミュニケーション様式をあらわす。これは以下のような特徴をもつ。
③ (1)リスキーとされる事象についての評価を含めて、一般にある出来事や状態についての記述は、客観性を装って「他人を強制的に同意させるだけの十分な、唯一正しい知」を駆使しようと振る舞ってはならない。というのも、こんにち観察や記述そのものが、誰によってどのような利害関心にもとづいておこなわれているのかという、第三者からの観察にさらされざるをえないからである。またその際、上記のような態度を相対主義だと批判してはならない。なぜならこの場合、相対主義ではない何かを望むことはできないからである。
④ 要するに了解の過程は、同調圧力から解放されなくてはならない。決定者と被影響者のあいだでなされるコミュニケーションは不安定で揺らぐことを宿命づけられている。ある時点でひとつの解決案が受け入れられたとしても、その場その場での取り決めでしかなく、あくまでも暫定的なものであり、つねに問い直しに関して開かれている必要がある。
⑤ (2)了解の過程では「道徳」を持ち出すことは慎まねばならない。了解の基本原則は、みずからの道徳と合致しない者の「排除」ではなく、道徳を禁欲することによって得られる「包摂」でなくてはならない。つまり、対話への参加者を制限する動きは、可能な限り制止されるべきである。さらにいえば、参加者は「賢い市民」である必要もない。参加は強制されないのであり、対話の機会ごとに関心のある者が参加でき、しかも参加できるときに参加すればよい。逆に、体制/反体制という図式を持ち出し、教条主義的に決定者(体制側)に対して非難することも慎むべきである。
⑥ 現在、「参加」や「審議」に軸を置いた民主制のあり方が模索され、その具体的な姿として、調査に協力する人々が討論を通じて問題点や論点を把握した上でアンケートに答えるデリベラティブ・ポリング、あるいはデンマークや日本でのコンセンサス会議が注目されているが、そうした場における討議のあり方を考えるうえでも、この「了解」のあり方は示唆に富む提言である。
⑦ 第二に、専門知への不信や不安という問題への対処も視野に入れておかねばならない。近年の高度な科学技術のもたらす多様なリスクは、科学への信頼を問題化するきっかけとなっている。専門知や科学への信頼の問題に対して、どういった対処法を展望すればよいのか。
⑧ この点については、人間と自然の関係性の様態から環境問題を分析する「社会的リンク論」の議論が傾聴に値する。鬼頭秀一によれば、今日の高度な技術は、我々の経験によって飼い慣らすことも、また経験にもとづいて信頼を付与することもできなくなっている。そこで特定の地域や文化に歴史的に蓄積されている固有の知識(ローカル・ナレッジ)や生活知を援用したり活用したりする必要があるとする。つまりこの知識や生活知によって技術を飼い慣らし、経験にもとづく信頼を獲得して、科学技術の不確実性に由来する不信を補ってゆくべきだというのである。それは、見えない技術を見えるものへと転換することである。さらにそれは、自分たちの手に負えなくなったリスクを再び自己責任で利用できるものへと差し戻すことでもある。自分たちで技術を制御する術を身につけることで、皆でリスクを分かち合い、相互の支え合いにもとづいた社会の構築へと向かうことができるのである。
⑨ 信頼は自分が「あえてする、リスキーな」行為の選択に深く関わっている。そこでは、自分たちの行為とその結果との関わりが可視的になることが必要である。
⑩ たとえば水害についていうと、かつて日本には地域住民の自治によって水害への対応をはかる「水害予防組合」が各地に多数存在し、これが水防活動の主力をなしていた。この組合は、受益者負担の原則にしたがって、住民がその土地所有面積や建物の同定資産税額、水害頻度等に応じて組合費を拠出し、これをもとに河用環境の整備や堤防の改修等をおこなった。しかし、1958(昭和三32)年の水防法の改正をきっかけにして次々と解散し、市町村の予算で行政によって運営される「水防事務組合」へと編成替えされていった。現在残存する「水害予防組合」は全国でわずか十前後であり、これらの組合も、活動内容が形骸化しているケースが多く、該当する地域内住民がその存在すら知らない場合もある。
⑪ そうなってしまった原因として、都市化の進展や組合費の負担に関わる住民間の紛争の深刻化などがあるが、主たるそれはダムや堤防に代表される治水技術の著しい進展である。水害防御のための専門知に依存することにより、人々は水害のリスクをあまり心配せずに日常生活を送ることができるようになった。他方、あたかもそのリスクが存在しないかのようにさえ認識された結果、川ヘの関心が薄れ、水害に備えるための伝統的な知恵も失われ、いったん水害が起こると甚大な被害がもたらされるようになってしまった。水防と治水の分離として語られる事態も同様である。
⑫ 水害を完全になくすことは不軒能である。必要なことは、ふだんから水害とつきあい、水害リスクを地域で分かち合ってゆくことである。これが水害への対応の基本となる。高度な治水技術を駆使して大洪水が発生しないようにすることは重要であるが、大きな被害が出ない程度の水害ならば適度に氾濫・遊水させて、ふだんから水害の体験やその被害を軽減する方法を訓練することが必要である。こうした考え方は、現代の高度な技術の効率性を生かすだけでなく、「住民のための技術」から「住民による技術」に重点をおいて、住民にとって可視的かつ参加可能な「コミュニティ技術」として地域社会に組み込んでゆくことであり、リスク管理のために崚要な考え方である。
⑬ かつてウルリッヒ・ベックは、リスク社会における「危害の貧困化」という表現を用いて、リスクや危険の定義が専門家に独占され、被害を被りうる当事者の直接的な経験の意義が低下し、当事者がいわば「管轄外」になってしまう事態を指摘した。同様のことをルーマンも、リスクが過剰に、あるいは過小に評価されることで、リスク言説が先鋭化したり日常生活の不安が煽られたりする傾向を、システム分化・役割分化の進展および経験の抽象化によって説明している。上述の「住民による技術」の議論は、こうした「危害の貧困化」を緩和する術として評価できるだろう。
⑭ 第三に、新しいリスクとのつきあい方について信頼を軸に考えていく際には、信頼についてのより詳細かつ緻密な理論を展開する必要がある。
⑮ たとえば、「信頼」と「不信」を先鋭に対立させる思考方法から一定の距離を保たなくてはならない。確かに、信頼と不信は対照的な関係にある。地域住民間の信頼関係の意義を力説する議論にしばしば見られるように、信頼は倫理的・道徳的に「善」であり不信は「悪」、あるいは信頼が「原則」で不信は「例外」といった想定が、暗黙標に入り込んでいることが多い。より多くの信頼を獲得し、不信を極力避けようとする議論の背景には、不信が非効率であり逆機能的であるという仮定が存在する。しかし、信頼社会かさもなければ相互不信社会かといった二者択一しか用意されていないと考えるのは、単純にすぎる。むしろ信頼と不信は、(とりわけ近代的な条件のもとでは)相互に強化しあう関係にあるものとして捉えられるべきである。不信の概念にも、信頼の概念と同程度の目配りが必要である。
⑯ まず、信頼するということの「観点」が分化していることへの冷静なまなざしが必要ある。どの観点で人や集団を信頼し、どの観点では信頼しないのか、という観点の特定化を組み込んだかたちでの議論が必要である。
⑰ また、政治や科学への信頼とか不信とはいっても、どのレベルでの信頼であり不信なのかを正確に区別する必要がある。たとえば政治システムについていえば、それを多くの層からなるひとつの「玉葱」のようなものとして考えるなら、その一番深いところにある政治的コミュニティや民主制そのものへの信頼や不信と、そのひとつ表側にある現行の諸制度に対する信頼や不信、さらには、もう少し表面に近いところの、ある特定の政策や政党や政治家に対する信頼や不信などを一括して議論することはできない。ロジヤー・カスパーソンらが指摘するとおり、より「深い層」での(たとえば民主制への)信頼が確保できていれば、「表層」での不信はむしろ有益なものであるかもしれない。
(中略)
⑱ 社会が、全体として信頼社会になったり不信社会になったりすることはありえない。社会が複雑化してゆけば、不信と信頼が相互に強化されてゆく。ある一定レベルの「不信」であれは、将来的損害の可能性を早期に発見するうえで機能的に作用することもありうる。問題は、信頼をいかに最大化するかよりもむしろ、信頼と不信とが社会のなかでどのように絡み合っているかを見極めることである。
⑲ 過度の不安に煽られて「監視社会」の到来に手を貸すのではなく、また、専門知や政治に身を委ねて安心に浸りきり、リスクがないかのような生活を送るのでもなく、現代型リスクといかにつきあい、皆でいかに分かち合ってゆくのかを考えることこそ、リスク社会に生きる我々の課題である。
小松丈晃「リスク社会と信頼」(今田高俊編『社会生活からみたリスク』岩波書店、2012年)。試験問題として使用するために、文章を一部省略・変更した。
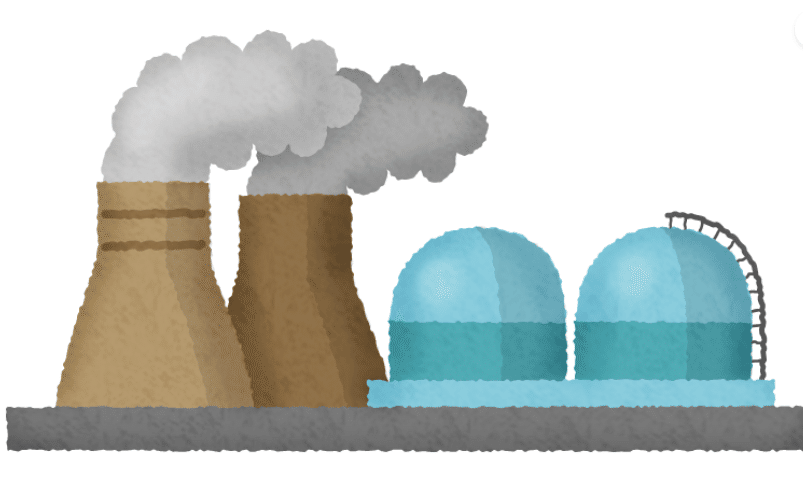
(2)解答例
現代社会におけるリスク管理は、第一にリスクを引き受ける者と被影響者との了解の在り方である。リスクの評価や事象の記述は客観性を装って絶対的な正しさを強制してはならない。了解の過程は、同調圧力を避ける。議論は開かれている必要があり参加を強制されない。解決案に対してつねに問い直しをする。第二に高度な技術の進展による専門知については、特定の地域や文化に歴史的に蓄積されている固有の知識や生活知によって技術を自己責任で利用可能とし信頼を回復する。リスクの因果関係の可視化を行い住民がリスクの相互分担・相互扶助基づいた社会を構築する。第三に新しいリスクの信頼性について詳細・緻密な理論を展開する。信頼社会・相互不信の二分法を取らず信頼と不信は相互に強化しあう関係にあると考える。人や集団に対する信頼性を観点ごとに仕分け、政治や科学に対してはシステムの階層ごとに信頼性を評価する。信頼の最大化よりは信頼・不信の社会における構造的連関を見極める。
原子力発電所の安全性について考える。原発の放射能は目に見えないために恐怖を増幅させる。核物理学の難解な記述や数値基準は国民の理解を越えているために、専門家に対する過度な信頼や不信の両極端の反応を招く。いきおい賛成派と反対派は感情的な言説の応酬に陥り、原発への拒絶か依存という極端な二分法に囚われて議論が平行線をたどる。
原発の問題は放射線に対するリスクである。太陽光には放射線も含まれて、自然界には常に放射線が存在する。放射線=危険という図式は単純な理解である。レントゲン検査などで私たちは恒常的に放射線の照射を受けており、徹底した管理の下では私たちは放射線と共存できる。原発のリスク管理は事故防止の厳密な安全基準の作成と原発稼働後の事故対策も含めた放射線の評価と管理に収斂される。
原発は絶対に安心という「原発安全神話」は福島第一原発の事故で崩壊した。だからといって、安全性に対する精緻な議論を抜きに原発絶対反対を唱えるのも教条主義の批判を免れない。原発の建設や再稼働に際しては、情報の透明化を進め、専門家にまかせることなく、広く国民的な議論に展開させるべきである。
福島第一原発の事故を契機に、情報公開や専門家集団と市民社会のリスク分担の適切な在り方などの問題を考える端緒としてゆくことを強く望む。(987字)
👇慶應義塾大学法学部入試小論文のオンライン授業はココから
(授業時間60分+添削2回)
書き方だけでなく、豊富な知識で政治・経済、社会問題を詳しく解説。もと予備校政治経済講師だからできる納得授業。
