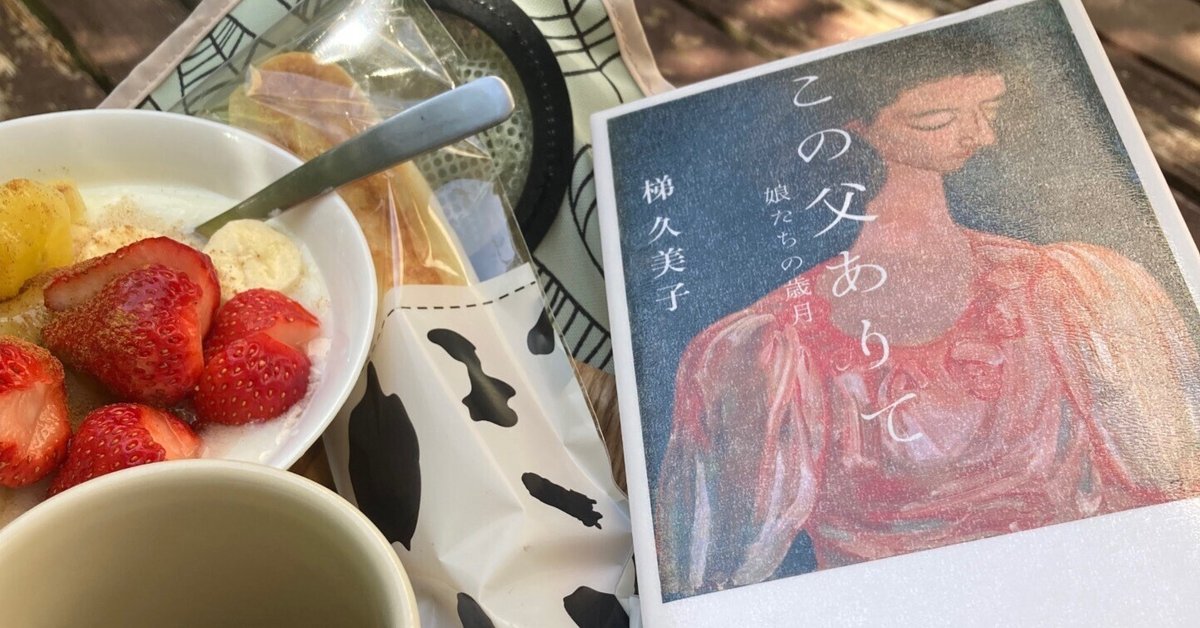
「この父ありて」梯久美子著〜9人の書く女たちの父とのダイアローグ
目の前で父親を虐殺された渡辺和子さんの、壮絶なエピソードから始まる9人の書く女たちのライフヒストリー。父親という、客観視することが容易でない存在を書くには、半世紀以上の時間の濾過を必要とする。私自身が50歳を過ぎ、ようやく父の存在を一人の人間として客観視できるようになった今、この本と出会えたことは意味深い。
作者の人の描き方が、まるで本人の眼を通して見ていたかのように心情に訴えかけてくるので、これまで何度か関心を持ってきた「ナラティブ」に再度関心を持った。今後何らかの企画に「ナラティブ」をテーマにしたものを組み込みたいと思った。
9人の書く女たちの生き方にはライフワークや仕事としての「書く」があった。女性が働き、自分の意見を言うこと自体大変だった時代。そんな時代だったからこそ、彼女達は書いたのではないだろうか。書くために立場を明確にする必要はあまりない。必要なものは紙とペンと、批判を恐れない心、そして書かずにはおられない「どうして」「なぜ」のような探究心。
問いを立てることはそれに答えようとすることでもある。今自分が置かれている状況に「なぜ」を感じない限り、人はその答えも知ろうとはしないのではないだろうか。彼女たちは果敢に挑戦し、人々の心を動かす存在となった。彼女たちが現在の女性の生き方に与えた影響は計り知れない。
私の父は組合運動で家にはほとんどいなかった。私が高校生の時、久しぶりに授業参観に行こうとして中学校に行くような父だった。父が与えてくれたもの。それは父の書棚の本。小学校時代は学校の図書館の本を端から端まで読むほど本が友達だった。中学生時代には子ども向けの本に飽きてしまい、父の本棚の本を端から順に読んだ。父は不在だったが、本はいつもそこにあった。端から順に読んだのは、何が書かれているか予想がつかなかったからだと今になって気づく。
本棚の本に書かれていたことが世界のすべてではないと知ってからは、父に愛されたい、認めてもらいたいと思いながら、そうではない人生を歩んだ。今振り返ってみて父との関係で学んだことは、本を読むことと、ディベートのスキル、お酒の嗜み方だったように思う。
議論するには相手の存在が不可欠。しかも自分と同程度以上のディベートスキルがなければ議論しても面白くない。そして最後には論破しなければならない。ずっとそう信じてきたが、今は違う感覚でいる。議論というのは同じ目的を共有しながら行わなければ闘争に発展する。そして戦いは敗者を作る。グローバル化が進んだことでかえってスモールワールドになってきた現代において、勝ち負けを決めるだけの議論に未来はない。大量消費の時代も、貨幣主義も、学歴だけの評価も、性差や国籍、障がいの有無でのランクづけも、終焉を迎えようとしている。
今あるものをうまく分け合い、お互いに幸せでいられるように調整する力。そしてその調整によって生み出される利益を、これまた調整能力で分配するリーダーシップが求められているのかもしれない。
過去を振り返ってみれば、クーデターや選挙、デモによって変革を迫られた出来事はこれまでも沢山あった。この本にも冒頭から時代に翻弄された父親達が登場する。しかしそれは世界規模の変革に連動するものではなかった。今はそれが世界規模で起き、一度戦争が起きれば人々は難民となって大移動を迫られる。いわば地球規模の難民社会が始まったのかもしれない。
どこに行けばいいのか、わからない。誰がリーダーなのか、わからない。予定調和も予測も不可能。そんな時代を私たちは生きている。
この本に出てくる娘たちはみんな父を愛し、敬っている。しかしそんな父親たち、娘たちばかりではないだろう。
今この世界で繰り広げられている戦いに向かう父達に、娘達の言葉は届いているんだろうか。そんな世界は欲しくない、私はあなたのものではない、もうここから出て行きます。そう娘は言っていないだろうか。
強さでも力による支配でもなく、生きることの素晴らしさを対話によって気づかせる、人間としての本質的な豊かさ。それを9人の父親が持っていたことが、彼女たちの生き方をつくった源なのだと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
