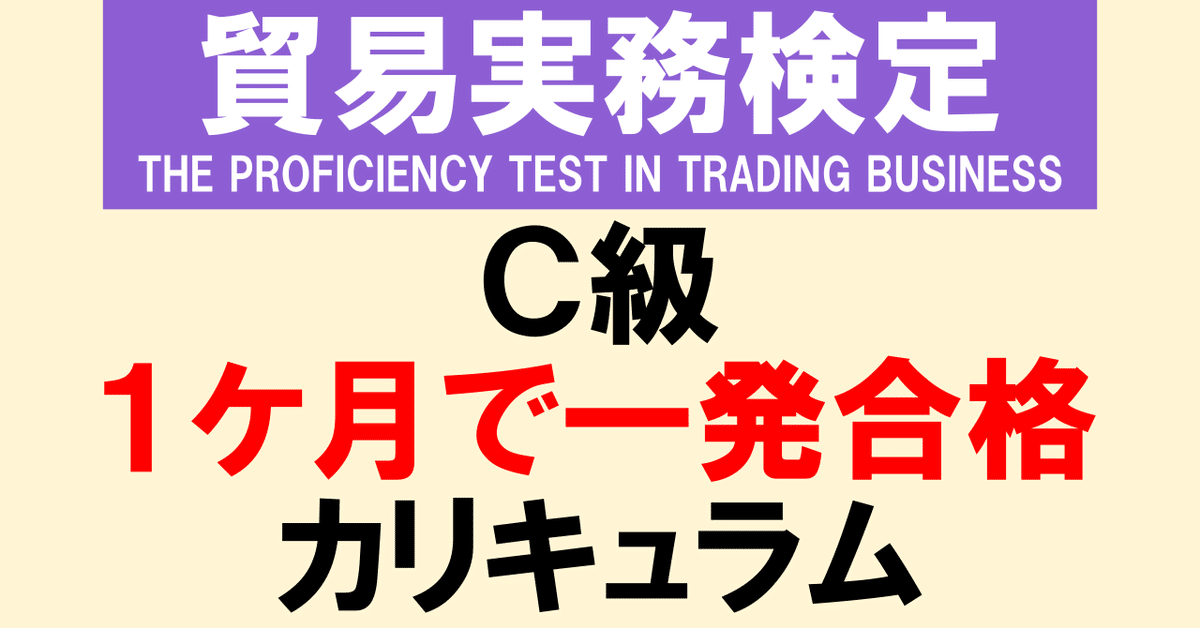
貿易実務検定C級※100%一発合格できる過去問集とテキストがこれだわ!
まず、最初に断言しておきますが、
貿易実務検定C級は1ケ月間の勉強で一発合格できます!
えっ、えっ、えっ?
一ヶ月間の勉強で貿易実務検定C級が一発合格できるって???
理由は???
根拠は???
って、
思わせる方がほとんどだと思います(=_=;)
理由、根拠、それは、こちらです!!!


そうです!
合格証書ですね!
一枚目の合格書
Grade B
Japan Trading Business Assciation
は、貿易実務検定B級の合格書です。
貿易実務検定B級は、1~3年以上の貿易実務経験のレベルなので、一発合格は無理かなと思いました。
一方、貿易実務検定C級は、1年程度の貿易実務経験のレベルなので、貿易実務検定C級から取得しようと思い、参考書と問題集を買いました。
そして、12月の第一週の日曜日に行われる貿易実務検定C級の試験に向けて、10月の中頃から勉強を進めていくのですが、10月の下旬に、「私の勉強のやり方だと、C級は100%合格する。」と思うようになり、「ならば、レベルを上げてB級を受験しよう」と方向転換しました。
結果、10月下頃から試験当日の12月8日まで約1ケ月ちょいの勉強で、貿易実務検定B級を合格することができました。
ですので、『貿易実務検定C級を1ケ月間で一発合格』ってのは、私の勉強のやり方(カリキュラム)では、当たり前のことなんですよね(^o^)V
ちなみに、
二枚目の合格証書
国家資格の通関士試験合格証書です。
はい、これも、私の合格証書です。
通関士を取得するのに、独学で4ケ月勉強しました。
結果、通関業法、関税法の2科目は自己採点で合格。
しかし、通関実務のほうが輸入申告書、輸出申告書の出来が悪く、1回目の受験では不合格に終わりました・・・
2回目の受験は、通関士試験(毎年、10月の第一週目の日曜日)の1ケ月前に、『通関士試験・通関実務 輸入申告書、輸出申告書の対策講座』の授業を受けて、見事、2回目で合格しました。
通関士、貿易実務検定B級を取得している私だからこそ、どこを重点的に勉強すれば、限られた時間の中で合格できるというのが分かります。
私の勉強のやり方(カリキュラム)というのは、世間に出回っている参考書・問題集から無駄なものを取り除き、1ケ月間の勉強で一発合格を目的にしたカリキュラムになっています 。
貿易実務検定C級の合格率は?
貿易実務検定を主催している日本貿易実務検定協会の公式サイトで発表している『第一回から直近までの累計の合格率』は、54.84%です。
まぁ、悪くない合格率ですね。
ただ、気になるのは、勉強時間ですよね・・・
いろいろな人に聞いてみたり、ブログやネット書込みなど見ていると、
・勉強期間はだいたい3ケ月位だったと思います
・1日30分を2ケ月間(60日)続けました(これだとトータル勉強時間は30時間)
・2ケ月間、週末の休みの日だけ1日3時間勉強した(これだとトータル勉強時間は48時間)
っていう感じでしたね。
やっぱり、みなさん、2、3ケ月は勉強されている感じですね。
そして、2、3ケ月の間、1日に〇〇分とか、休みの日に〇〇時間とかを続けているようです。
私の勉強のやり方(カリキュラム)というと
10時間程度の勉強で一発合格が基本になっています。
各々の生活スタイルに合わせ、隙間、隙間で、時間を確保してもらってトータル10時間を勉強するやり方(カリキュラム)になります。
「仕事帰り、18時から30分くらいお気に入りのカフェでちょこっと勉強しましょうか」みたいな、その方の生活スタイルを聞きながら、こんな場所で、これくらいだけ勉強してみましょうとアドバイスもさせていただいております。
だって、仕事や学校で身体も精神的にも疲れていて、「あぁ~、やっと家に帰ってきた・・・」という状態で、食卓の上で、勉強なんかできます???
仮に、初日の一日だけ頑張れたとしても、以降、絶対に勉強を続けられないですからね・・・( ノД`)
だから、あえて、お気に入りのカフェとか、前から行きたいと思っていたカフェなどで、家に帰る前に、『30分だけ勉強』をすると、とても集中できて勉強もはかどりますからね(^_-)-☆
貿易実務検定C級の勉強している人だけに限るわけではないですけど、意外と、先々の計画を立てられないという方が多いなぁと思います。
例えば、1000問の問題があるとします、これを30日間で終わらせるには、
1日に何問を解けばいいのか?
1問を解くのに何分でこなせばいいのか?
じゃ、このペースで進めていけば、30日間で1000問の問題が解き終わるねって計画を立てられない人が多いんですよね・・・( ノД`)
こういう勉強の計画を立てられるように、あなたの生活スタイルを聞きながら、あなたの生活スタイルに合わせ、隙間、隙間で、時間を確保してもらってトータル10時間を勉強できるようにアドバイスもさせていただいております。
簡単な計画を立ててみますと、
1000問 ÷ 30日間 =33問/1日に解く問題数
じゃ、1問を解くのに、1分くらい時間をかけようかなとすると、
33問 × 1分/1問を解く時間=33分/1日に33問を解く時間
ということになります。
ねっ、1日30分程度の勉強をするだけで1000問の問題が解けます。
1000問も解けば、貿易実務検定C級は間違いない合格しますからね。
貿易実務検定C級の科目と配点について
既に、知っていることだと思いますけど、今一度、確認していきますね。
科目は、貿易実務と貿易実務英語の2科目です。
貿易実務:150点満点(試験時間:1時間30分)
問題1
正誤式(○×式) 10問 ×各3点 = 30点
問題2
2択式 15問 ×各3点 = 45点
問題3
語群選択式 10問 ×各3点 = 30点
問題4
3択式 15問 ×各3点 = 45点
貿易実務英語:50点満点(試験時間:45分)
問題1
語群選択式 10問 ×各2点 = 20点
問題2
3択式 10問 ×各2点 = 20点
問題3
3択式 2問 ×各5点 = 10点
という問題形式です。
2科目合計200点で、合格基準点は80%の160点です。
後ほど、実際の問題を見てもらいますが、答えを書きだすという記述問題はなく、○×式、2択式、3択式、語群選択式なので、ほぼ、問題分の中に答えがあります。
それで、「あぁ~、どっちだったかな?」と、選び出すだけなので、暗記するという勉強法ではないので、勉強としてはかなりイージーですからね。
「なんとなく、こうかな」という感じで勉強を進めていくだけで、十分に合格基準点は80%は取れますからね。
それと、貿易実務、貿易英語、いずれも時間にはかなり余裕がありますので、タイムアタック的な訓練は必要ないですからね。
1ケ月間の勉強で貿易実務検定C級を一発合格していただくために、過去4年間の本試験に出題された問題を分析に分析を重ね、出題傾向の高い問題を選りすぐり、この問題にさえ慣れ親しんでおけば大丈夫という1000問(教材問題集)を厳選しております。
この教材問題集(1000問)の『質』が気になる方も多いと思いますので、本試験で毎度、毎度、繰り返し出題されている重要な問題を無料公開しています。
実際に、問題と非常に分かりやすいと定評のある私の解説を読んでみて、「わりと有益だな」と思ったら、教材問題集(1000問)の購入をご検討いだたけたらと思います。
1000問(教材問題集)を無料公開しています
まず、本試験では、初めの問題として、【問題1 / 正誤(○×)式】次の記述について、正しいものには〇印を、誤っているものには×印を解答欄にマークしなさい。という問いで、10題x各3点 30点分が出題されます。
では、以下より問題と解説になります。
例題1つ目
【問題】輸入する郵便物の場合には、課税価格が30万円以下のものであっても、税関長に対して輸入(納税)申告が必要である。
【解説】解答:× 解説:これは、通関知識の輸出入申告の方法・内容という出題範囲になります。輸入する郵便物の場合には、課税価格(貨物を輸入しようとするときには、輸入貨物の価格又は数量を課税標準として、これに税率を掛けて、関税や消費税が課されます。 原則として、輸入貨物について買手から売手に対し支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に、運賃等の所定の費用(加算要素)を加えた価格。)が20万円以下のもの及び寄贈品である場合、税関長に対して輸入(納税)申告は不要である。難しく書きましたが、簡単に言いますと、額が小さいもの(20万円以下)やプレゼント(寄贈品)は、税関長に対して輸入(納税)申告しなくてもよいということです。ポイントは、『20万円以下、寄贈品、輸入(納税)申告は不要』の箇所です。
例題2つ目
【問題】外国為替相場において、商品の売り手である日本の輸出者が有利になるのは、円高傾向にある場合である。
【解説】解答:× 解説:これは、外国為替の外国為替とは?という出題範囲になります。外国為替とは、遠隔地(例えば、日本とアメリカ)にいる買主(輸入者)と売主(輸出者)がお金のやり取りを金融機関を通じて決済する仕組みのことです。外国との貿易において代金決済をする場合、円を外国の相手国の通貨に交換しなければいけません。しかし、通貨によって、その価値はまちまちですから、異なる通貨同士を交換する場合、一定のレート(交換比率)が決められています。外国為替という言葉は、このレートを意味することもあります。円高、円安という言葉は、円の価値が高くなる場合を円高といいます。逆に、円の価値が安くなる場合を円安といいます。例えば、アメリカの通貨US$を例にすると、究極の円高は1円=1$です。しかし、現在は、110円=1$です。日本の言い分としては、「なんで、1$と交換するのに110円も払わないといけないのか・・・」ということになります。でも、110円だったのが、90円になると、日本としては、「よしよし、1$と交換するのに90円だけでいい」となり、110円の時と比べ、円の価値が高くなっているので円高といいます。この逆で、110円だったのが、130円になると、円の価値が安くなっているので円安といいます。この円高と円安ですが、輸出者、輸入者、立場が変わると、メリット、デメリットも変わります。下部の例をご覧ください。
【輸入のメリット】100$のものを輸入する場合、110円=1$だと、110円x100$=11000円です。円高になり1100円=1$が90円=1$になると、90円x100$=9000円です。輸入の場合は、円高のほうが同じ100$でも11000円ー9000円=2000円も安く買えるというメリットがあります。
【輸出のデメリット】100$のものを輸出する場合、110円=1$だと、110円x100$=11000円です。円高になり110円=1$が90円=1$になると、90円x100$=9000円です。輸出の場合は、円高になると、同じ100$でも11000円ー9000円=2000円もらえるお金が少なくなるというデメリットがあります。なので、日本の輸出者が有利になるのは、円安傾向にある場合です。
では、ポイントは、『円の価値が高くなる(1$100円が90円に)場合を円高、円の価値が安くなる(1$100円が110円に)場合を円安』の箇所です。
例題3つ目
【問題】ハウス・エア・ウェイビルは、利用航空運送事業者が個々の荷主に対して発行するものである。
【解説】解答:○ 解説:これは、航空貨物という出題範囲になります。エアウェイビル(Air Waybill/AWB)は、航空輸送の際に、航空会社(または航空貨物代理店)が発行する書類です。「誰が(どこから)」「誰に(どこに)」「何を」運んでいるのか記載された航空貨物専用の運送状です。航空輸送の手配には、① 航空会社またはその代理店に直接申し込む方法と、② フォワーダー(利用運送事業者/混載業者)に依頼する方法があるのですが、一般的に商社や貿易会社は②の方法で航空輸送を手配することが多いです。というのも、②の方法は、フォワーダーが複数の会社(荷主/輸出者)からの貨物を大口貨物にまとめ、フォワーダー自身が代表荷主となって航空会社または代理店に輸送を依頼するのですが、フォワーダーは航空運賃の規定(安く仕入れる制度)に詳しく、①よりも運送料を抑えられる(可能性が高い)というメリットがあるためです。この②の方法で航空輸送が手配されたときに登場するのが、「マスターエアウェイビル」と「ハウスエアウェイビル」です。フォワーダー(利用航空運送事業者/混載業者)を利用して航空輸送を行う場合、フォワーダーは、複数の会社(荷主/輸出者)の貨物をまとめて大口貨物に仕立て、代表荷主となります。その代表荷主であるフォワーダーが航空会社から発行されるエアウェイビルが「マスターエアウェイビル(Master Air Waybill/MAWB)」です。マスター(master)は「元の」という意味がありますので、「元の航空会社のAir Waybill」=「Master Air Waybill」になります。その後、フォワーダーも、それぞれの輸出者(小口荷主)に対してエアウェイビルを発行します。これを「ハウスエアウェイビル(House Air Waybill/HAWB)」といいます。ハウス(house)は「~を包む」という意味がありますので、「それぞれの輸出者(小口荷主)を包むAir Waybill」=「House Air Waybill」になります。これら2つのエアウェイビルは全く同じものではないため、通常エアウェイビルは「マスター」なのか「ハウス」なのか、書面上に記載されています。
では、ポイントは、『マスター(master)は「元の」という意味で「元の航空会社のAir Waybill」=「Master Air Waybill」、ハウス(house)は「~を包む」という意味で「それぞれの輸出者(小口荷主)を包むAir Waybill」=「House Air Waybill」』の箇所です。
