
【恒例年末洋楽企画#2】Boonzzyの選ぶ2020年ベストアルバム: 20位〜16位
2020年もようやく最終週。今週はもう仕事も終わりでお休み、と言う方も多いのでは。さてこの年末恒例洋楽企画、第2弾は私ことBoonzzyが独断と偏見で選ぶ、2020年のベストアルバムのカウントダウンです。年末は音楽メディアのみならず、音楽ブロガーの皆さんもよくやっている企画ですが、自分の場合の年間ベストアルバムを選ぶにあたっての条件というのを決めていて、それは「自分でフィジカル(LPまたはCD)を購入したアルバムの中から選ぶ」というもの。「え、そんなの当たり前じゃん」と思われるかもしれませんが、最近はストリーミングでいろんなアルバムがフィジカルを買わずとも手軽に聴けてしまう時代。でもやっぱり自分は古い人間なのか、ストリーミングでもいろいろ聴きますけど、気になったアルバムはやはりフィジカルを買うんですよね。逆にストリーミングで聴いても引っかからないやつは買わない。ある意味ここで一次選別が行われているようなあんばいです。もちろん、全ての新譜を把握しているわけではないので、リリースされたのに知らず、年が終わってから巡り会って「あー、去年のうちに聴いてたら絶対上位に入れたのに!」というのもままある話。でも、それも音楽と付き合う面白さの一つと割り切って、毎年自分が目一杯張ったアンテナにひっかかった作品のうち、自分が年間通じてよく聴いて、かついろんな意味で心に残った作品を選んで、こうしてカウントダウンしています。なので、音楽メディアのランキングと重なるもの、全く重ならないもの、いろいろありますのでそういう観点でこのカウントダウン、楽しんでもらえればいいなあ、と思ってます。
ではさっそくBoonzzyが選ぶ2020年ベストアルバム、その20位から行ってみましょう。
20. Songs / Instrumentals - Adrianne Lenker (4AD)

2020年を語るにあたって欠かせない視点が「コロナ禍で音楽活動、特にライブが制限されている中で、アーティスト達はどう対応してきたのか。それは彼らの作品にどのような影響を与えたのか」というもの。そうした視点の背景になっている今年のコロナ禍の状況に、個人的な状況を重ね合わせて作られた今年の作品の中で、特にその表現方法や曲の内容においてシンプルに、かつ直接的に表現されたことで結果として心に残る作品になっている、というのが、昨年大きくブレイクしたインディ・ロック・バンド、ビッグ・シーフのボーカル兼ギタリストのエイドリアン・レンカーによるこのアルバム。
何しろ全編彼女のボーカルとアコースティック・ギターの弾き語りだけでアルバムが進行し、このアルバムが録音されたマサチューセッツ州西部の小さな山小屋の庭先から聴こえる木のざわめきや、鳥の声などが時折聞こえる他は彼女の演奏だけという潔さ。ちょうど昨年『U.F.O.F.』と『Two Hands』という音楽メディアにも高く評価された2枚のアルバムでブレイクした後のプロモーションとツアーでクタクタになっていたという彼女の疲労感と、今年に入って付き合っていたパートナーと別れたことによる失望感が、3月にコロナ禍でのヨーロッパ・ツアーがキャンセルした頃はどっと出て何もする気がしなくて件の山小屋に妹と移り住んでいたらしい。でもその新しい環境が為せる技だったのか、自然と曲が生まれてきたので知り合いの録音技師を呼んでその小屋で録音したのがこのアルバム。
アルバムを通して感じるのは、夢見るように頼りなさげに聞こえる彼女の独特のボーカルが存在感を持って迫ってくること、彼女のギターワークの素晴らしさ、そしてどの楽曲もシンプルながら曲としてのクオリティが高くて、自然の音のバックドロップも含めて思わず聴き入ってしまうこと。ちょうどこのアルバムがリリースされた9月から10月にかけて、コロナの第二波が出ていて秋のメランコリーな雰囲気に拍車がかかっていた頃に、本当にこのアルバムが耳にしっくり来たものです。彼女のお祖母さんが描いたという、とっても味のある水彩画のジャケも、レコードをかけながらディスプレイするととってもいい気分。そして、このアルバムは実は2枚のアルバムが一つになっていて、2枚目は20分近くの長尺のインストゥルメンタル曲が2曲入った『Instrumentals』というもの。こちらは件の山小屋でのセッション中に録りためたエイドリアンのギター演奏をつなぎ合わせたりミックスしたりして作られた、アコギと自然音とのミュージック・コンクレートのような作品。これを聴いていると、ある時はアンビエント・ミュージックのようでもあり、ある時はリオ・コッケとかのアコギ・マスターの作品のようでもあり、そしてある時はその昔のプログレッシヴ・ロックのアルバムのようでもあるという、一種不思議な世界に遊ぶことができる、そんな2枚め。おそらくコロナがすべての人の創作活動へのアプローチを全く変えてしまった、そんな今年だからこそ生まれたアルバムなんだと思う。それくらい今の我々の気持ちにピッタリ寄り添ってくれる、そんな感じなのが妙に愛おしい。
このアルバム、やはり話題のビッグ・シーフのフロント(ウー)マンによるブレイク後初のソロ作ということもあってかなり評判になって、音楽メディアのペイスト誌9位、ピッチフォーク誌11位と、今最も先進的なメディア2誌からのしっかりとした評価を受けてます。今の寒々しい季節にもいいサウンドトラックになるので、ジャケも含めてお勧めです。
19. Mama's Boy - LANY (Polydor / Interscope)
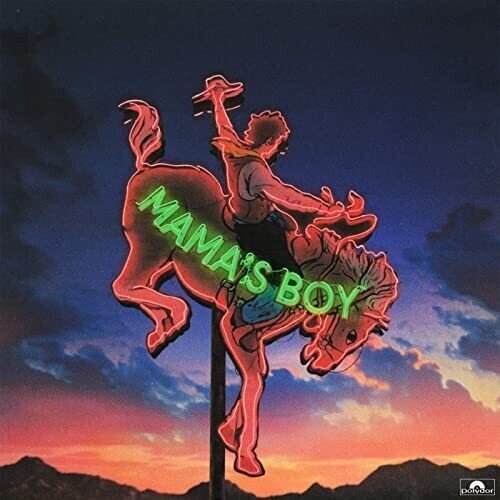
先ほどのエイドリアン・レンカーのアルバムが、2020年にコロナ禍の物憂い雰囲気を作風に巧みに活かして伝統的な演奏アプローチで作られた作品類型の典型だとすると、このロス出身の3人組、LANY(LAとNYの合成語なんだけどレイニー、って読むらしい)の3作目にあたる『Mama's Boy』は、正に今風の打込みやエレクトロ・サウンドを駆使して思いっきりメインストリーム・ポップな作り方をされた作品類型の典型。このバンドは正直このアルバムまでまったく知らなかったのだけど、このアルバムが10/17付のBillboard 200の7位に初登場してきたので、毎週ここnote.comで書いてる「今週の全米No.1アルバム事情」の記事を書く関係でアルバムを聴いてみたところ、一発で気に入ったという、こういう洋楽発進活動してなかったらきっとなかなか出会えなかった作品。こういう今時ポップど真ん中な作品は音楽メディアでもなかなか高い評価を受けるのも難しいだろうしね。その時の記事がこれです。
その時も書いたけど、初期コールドプレイとかキーンとかに通じるようないい感じのスケール感のあるエレクトロなメインストリーム・ポップ・ロック感がこのバンドの信条のようで、アルバム冒頭いきなり壮大な感じ(しかし大仰ではない)で始まり、これはいいんじゃないかという予感を与えてくれる「You」から「Cowboy In LA」そして「If This Is The Last Time」とか正に珠玉のエレクトロ・ポップ・ワールド。ボーカルのポール・クライン君のドリーミーでちょっとチャーリー・プースとか、ヴァンパイア・ウィークエンドのエズラっぽい感じの聴いたら耳に残る魅力的なボーカルがかなり効果的ではあるのだけど、洗練されたフックを持ったメロディといい、気持ち良く聴ける楽曲構成といい、はっきりいって今年のメインストリーム・ポップ・アルバムの一二を争うクオリティの高い作品だと思う。
何でもこの前に2枚のアルバムをリリースした後、こちらも昨年デビューEPをリリースしたばかりのロス在住のロシア系アメリカ人女性シンガーソングライター、サッシャ・スローンと知り合って意気投合したらしく、このアルバムではボーカルのポールとサッシャがほとんどの楽曲を共作しているから、この素晴らしくポップな楽曲群はその有機的化学反応の結果なのかも。うーんこうなるとそのサッシャの作品も気になるところです。また、ポールも単なるラブソングばかり書いてるわけではなく、カントリー界の実力ソングライターであるシェイン・マクアナリーとの3人の共作で、バックにクワイヤを従えたゴスペル・バラード調の楽曲「I Still Talk To Jesus」なんて曲もやってておっと思わせます。この曲は「天国ってものがあるなら行ってみたいけど/多分僕はダメ、ルール破りすぎだし/聖書にやっちゃダメだって書いてあること全てやってるから/僕はちょっと飲み過ぎかもだし/何度か恋に落ちたこともある/ママには嘘ついてマリファナ吸ったし/たいてい自分のやりたいことをやってきた/でもね、信じられないかもしれないけど/まだ今でもイエス・キリストにお話してるんだよ」という、恐らくこのバンドのファンである若手のリスナーたちには無茶苦茶共感を呼ぶんだろうな、うまいな、やられたな、って感じでニヤリとする感じ。
何しろこんな素晴らしいポップ・アルバムが今のところどこの音楽メディアでもあまり取り上げられてないのはホントもったいない。これだけクオリティ高い楽曲が満載なのに、なぜかシングルヒットが一曲もないのも解せないところ。前述の初期コールドプレイとかキーンとか、あとボーカルの感じでチャーリー・プースとかショーン・メンデスとか好きな人、是非聴いて見てほしい。あともう一つ。このアルバムのヴァイナルについて来るデジタルダウンロード・コードで、このアルバム全曲のボーカル抜き(そ、カラオケ)のトラックが一緒にダウンロードできます。このカラオケトラックを聴いて改めて感心したのは、ポールが歌うメロディのリードのようなトラックは一切なく、バックトラックはとってもシンプルな打込み中心で構成されているのだけど(ラスト曲「Nobody Else」はアコギですが)それがそれだけでも充分鑑賞に値するくらいのクオリティだということ。このバンド、要注目ですね。
18. Hearts Town - The War And Treaty (Rounder)

自分の音楽的嗜好の2大柱はブラック・ミュージックとルーツ・ミュージックなんですが、時々その両方をカバーしてくれるアーティストやアルバムに出会うとハマってしまうことになります、当然。そしてこのマイケルとタニヤの黒人夫婦デュオのザ・ウォー・アンド・トリーティのアルバムもそのいい例だったというわけ。アメリカ中南部出身の二人で、かつナッシュヴィル録音なんで、ベースはゴスペルやブルースなのですが、楽曲のスタイルやリズムの取り方がR&Bやゴスペル、といった感じではなくいわゆるロック系の感じで、何となくメンフィスやマッスルショールズ・スタジオで録音したロック・バンドのレコード的なグルーヴを漂わしているのが特にオールド・スクールなサザンロックやスワンプ系ロックのファンには何ともいえない魅力。詳しくはここnote.comでやってる「新旧お宝アルバム!」で先日レビューしてますのでこちらをご覧下さい。
上記のレビューでも書きましたが、アメリカーナ系の有力アーティスト達が客演してるのもこのアルバムの魅力で、「Beautiful」で客演しているアメリカーナ・ロックの今や中心人物、ジェイソン・イズベルや、「Hustlin'」ではドブロの達人、ジェリー・ダグラスとアメリカーナのスーパーバンド、パンチ・ブラザーズのギタリスト、クリス・エルドリッジと共演するなど、自分の2つの音楽嗜好のツボをぐいぐい突いてくるのです。でも、このアルバムのベストトラックは、メンフィス・ソウルのノリで気持ち良く歌ってくれてる「Five More Minutes」でしょう。とにかく、サザンロックやメンフィス系R&B風ロック、はたまたスワンプ系等がお好きな向きには無茶苦茶おすすめのアルバム。実は10月頃にこのアルバムポチってるんですが、まだヴァイナルが届かず、仕方ないのでストリーミングでずっと聴いてるのが残念なところ。早くレコード来ないかなあ。
17. XOXO - The Jayhawks (Thirty Tigers / SHAM)
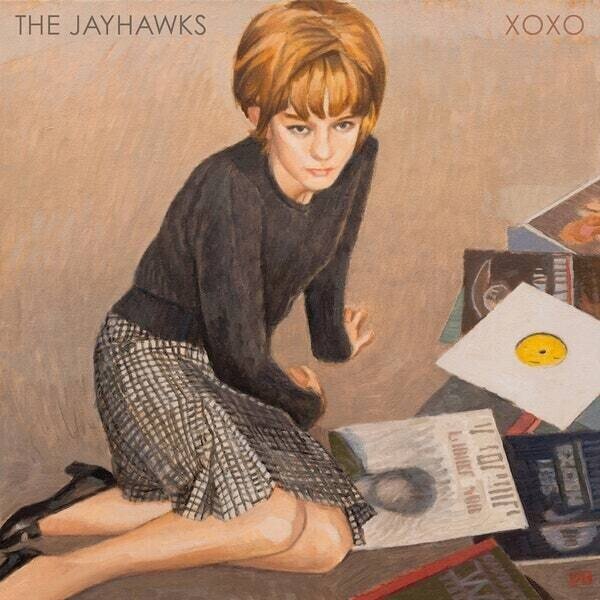
アメリカーナ大好きな自分なんで、ジェイホークスのアルバムは出たらほとんどの場合その年のトップ20には自動的に入るんです。唯一の例外は、2016年の『Paging Mr. Proust』で、R.E.M.のピーター・バックをプロデューサーに迎えて、バンドの今やメイン&オンリー・ソングライターであるゲイリー・ルイスがいろいろ新しい曲作りのスタイルやサウンドに挑戦しよう、という意気込みは買えるところだったんだけど、いかんせん僕らがジェイホークスに求めるものとは微妙にずれてて、あまり馴染めなかったんです。
もうバンド結成して35年目のバンドだし、オルタナ・カントリー・ロックというスタイルで、アメリカ中西部あたりの原風景を思わせるような甘酸っぱくも切ない曲を聴かせるというややもするとマンネリに陥りかねない立ち位置なので、いろいろと目先を変えてみるのも必要な時期に来ているのは確か。かつての盟友マーク・オルセンも今はいないし、そうした課題を一人で担うのはゲイリーに取ってもある意味プレッシャーなんだろうな、とは思います。そういう意味で前作の『Back Roads And Abandoned Motels』(2018)はなかなかいいアイデアの作品でした。ゲイリーが過去に他のアーティストに提供または共作した曲を、ジェイホークスという自分のバンドでセルフ・カバーすることによって「ああ、やっぱりゲイリーが書く曲はジェイホークスでしっかり落ち着くのだなあ」と思わせてくれた、ちょっと気持ちのいい変化球アルバムだったので、自分の2018年の年間アルバムの10位に入れてました。
そして今回の新作『XOXO』。特にパブリシティもあまりなしでリリースされたこのアルバム、タイトルや家でレコードを広げてくつろぐ女性のジャケに示唆されるように(「XOXO」というのは海外でメールやレターの最後に書かれるスラングで、「Hugs and Kisses(抱きしめてキス)」という意味)おそらくこのコロナ禍での憂鬱を少しでも晴らしてもらいたい、というバンドの気持ちがこめられたアルバムだと受け取りました。聴き始めてみると冒頭の「This Forgotten Town」からもうあの耳にすっと入ってくるジェイホークス節炸裂の哀愁のアメリカーナ・ナンバーで、うんうん、これこれ、これだよ!と頷きながら聴くといきなり60年代後半のビート・バンドっぽい「Dogtown Days」でえ、ジェイホークスこんな曲もやるんだ、でも結構いいじゃんこれ、と思ってクレジットを確かめて気が付いたのが、今回のアルバムはゲイリーだけじゃなくて、ドラムのティムも、キーボードのカレンも、そしてベースのマーク(・パールマン)もそれぞれ単独で書いた楽曲を収録していること。これまで彼らの曲はゲイリーとマーク(・オルソン)の共作かマーク(・オルソン)が脱退してる時はゲイリーがもっぱら書いてて、他のメンバーがゲイリーと共作に参加することはあっても、他のメンバー単独の楽曲というのは2003年の『Rainy Day Music』で3曲ほどあった以外はほとんどなかったんです。それが今回はティムが3曲、カレンが2曲、マークが1曲と、全12曲中半分がメンバーの単独曲で、しかもそれらは作者がリードボーカルを取るという、ある意味ジェイホークスの歴史では画期的な企画だったんです。
しかもそれでアルバム全体が散漫な印象になることもなく、むしろかえってジェイホークス「らしい」魅力に包まれた作品になっているのがファンには嬉しいところ。カレンのアンニュイな感じが心地よい「Ruby」「Across My Field」もいいし、先述のビート・ロックっぽいティムの「Downttown Days」や「Society Pages」もなかなか新鮮。マークPのドノヴァン風60年代後期チェンバー・ポップな「Down To The Farm」もなかなかいい。そして要所要所をビシッとジェイホーク節炸裂の「Living In A Bubble」(これなんかはコロナへの直接言及ですね)や「Homecoming」で締めるゲイリーのソングライティングもさすがの一言。残念ながら商業的には前作同様はかばかしくないですが、このクオリティの作品を出し続けてくれるんだったら、自分はずっとジェイホークスについていきますわ。
16. Lianne La Havas - Lianne La Havas (Warner)
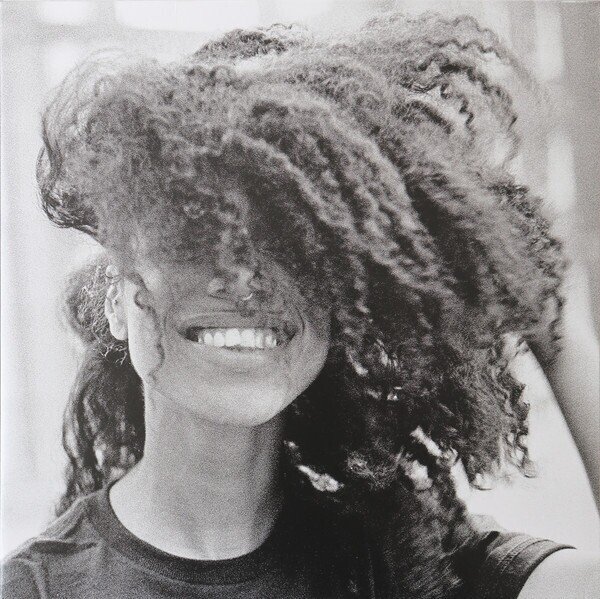
イギリスのリアン・ラ・ハヴァスも、自分としてはデビュー作『Blood』(2015、自分の2015年間ランキング10位でした)でぶっ飛んで以来気になって動向を追っかけているアーティスト。その『Blood』は「新旧お宝アルバム!」をnote.comに場を移す前の自分のブログでも熱いレビューをポストしてました。
ソウルやR&Bのいいものは最近はUKから来る、っていうのがここんとこの自分の信念ですが、彼女とかジョージャ・スミスとか正にそういう自分にとってストライクなアーティスト。その彼女が5年の沈黙を破ってコロナ禍まっただ中の7月にリリースしたのがこのアルバム。だいたいアーティストがセルフ・タイトルでアルバムを出す時ってのは、それなりの決意を持って重要な意味を持たせているケースが多いんですが、このアルバムも、彼女が『Blood』以降関係を持った相手と別れたことをきっかけに作られたらしく、アルバム全体の構成も「男女関係の始まりと恋の盛り上がり」〜「男女関係の終わり」〜「一人でいることの喜びと寂しさ」という三部構成になっているとのこと。そのアルバムのオープニングの「Bittersweet (Full Length)」はいきなりエモーショナルにリアンが恋することのほろ苦さについて絞り出すように歌うちょっとアシッド系の香りを漂わせるR&Bバラード。この曲はアルバム最後にも再び登場して、アルバム全体を総括するような役割のようですね。
『Blood』でもそうでしたが、彼女の楽曲は単純なR&Bではなく、ジャズやフォークなどの影響を色濃く感じさせながら独得のムードを持ったネオ・ソウルとでも言えるようなものが多いですが、その中には今回のアルバムを録音するきっかけになったという、レディオヘッドのカバー曲「Weird Fishes」のような曲も含まれていて、彼女の間口の広さを感じさせます。男女関係への言及はさておき、いずれの楽曲も『Blood』で自分を虜にしたリアンの作品よりも更に深みを増して、更にエモーショナルに迫ってくるものが多いように感じますし、やはり彼女でないと作り出せない独得のグルーヴを持ったものが多く、90年代アシッドジャズとかに親しんだ方であれば間違いなく気にいると思います。音楽メディアの評価もやはり高く、モジョ誌(49位)、ペイスト誌(47位)、スラント誌(38位)といったところの2020年年間アルバムランキングにも顔を出してます。リアンの名前をまだご存知なかった方は、『Blood』と併せてお聴きになることを強く、強くお勧めしますよ。
ということでBoonzzyの選ぶ2020年ベストアルバム、その20〜16位でした。引き続き15位以上もポストしますのでお楽しみに。
