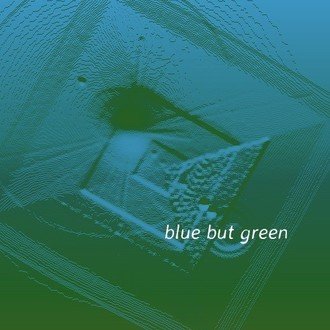旋法④
昨日はスコットランド民謡が「ヨナ抜き長音階」との親和性が高い、という話を途中で書きました。
「蛍の光」なんていい例ですよね。全然違う歌詞を付けて別の曲のように振る舞っていますが(笑)。
ただ一方で、西洋から音楽が持ち込まれる時代というのも長くは続かないんですよ。
日本人が西洋に行って、音楽を身に付けて帰ってきて、日本の音楽を制作するようになります。
こういう方たちはヨナ抜き長音階が普通だなんて考えていなかったんですよ。西洋音楽を学んで、導音なしで音楽を作る、という発想にはなかなかなりません。
実は昔の旋法を使っている作品でも、「ヒポ」に実質的な意味が無くなってからは、旋法にない主音の半音下からの上行終止を使っている作品もあります。
それ位「導音」の力は強力なんですよ(笑)。
だからこそ、戦前では「ヨナ抜き長音階」が日本の音楽だ、という主張は成り立ちませんでした。
これが変わったのは戦後の話です。
戦後に日本が飛躍的な成長を遂げる中で、都市部への人口集中が発生します。
実際東京の人ってほとんどが地方出身者ですから。
ちなみに自分の先祖は江戸時代から江戸に住んでましたが、やはりその前は地方から来ています。
で、そういう人達にとってはいかにも西洋音楽、といったような音楽より、昔聴いていた音楽に対する意識の方が高かっでしょう。
やはり故郷が懐かしいんでしょうね。自分の場合そういう感覚はありませんが...。
で、そこで出てきたのが「演歌」なんですよ。意図的に「ヨナ抜き長音階」で作られている作品が多いと思います。
「演歌は日本の心」って言う方がいるでしょう。これは単に宣伝の一種でしかありませんが、ある意味正しいんですよ。いい悪いといったような価値観とは関係ありませんが、田舎の日本。
実際には日本音楽のメインストリームとは言えない、周縁部の音楽でしかなかった「ヨナ抜き長音階」がこうして「日本の心」になった訳です。
少なくとも、高度成長期を支える機能として一定の役割を果たした、と言ってよいと思います。
で、それだけならまだ良かったのですが、これがある意味「想像の共同体」的なものを形成してしまい、本当に「ヨナ抜き長音階」を日本の音楽と考えることが一般的になってしまいました。
自分自身演歌は聴きませんし、興味もないのですが、これは演歌を否定するために言っているのではありません。ただ、このことがこれを使えば「日本的」だという認識の誤りを作りだすことになったきっかけになった訳です。
まあ、それを本当のことだと信じてしまうミュージシャンも情けない限りですが。
一般的に「ヨナ抜き長音階」は日本だけのものではなく、同時進行的に他の地域でもありますから、「日本の心」でも無ければ「日本の音楽の特徴」でも何でもない、たかだか数十年の間に起きた現象です。
いわゆる本来の意味での「邦楽」を聴いて育ってきた人間からすると、少なくともミュージシャンを自称する人がこんな認識で音楽制作を行っているようでは、もはや終わりとしかいいようがありません。
やや長くなりましたが、これが「日本の心」と呼ばれる音楽の正体です。
明日は元に戻って教会旋法のその後について書いてみたいと思います。
いいなと思ったら応援しよう!