
Ig Nobel Prize 2024 生理学賞 「お尻が呼吸する能力」とは?
新年あけましておめでとうございます🍾
新しい年になりましたが、皆さんは今年の目標とか立てられましたか。ビビは、今年も自分が嬉しいこと、楽しいことをするって決めました😆。忙しいと何かと日々の生活に流されがちなので、ちっちゃな幸せを探していきたいと思います。
もちろん、noteを書くのも楽しいことの一つなので、今年もお付き合い頂けますと嬉しいです!🍀
さて、今回はIg Nobel 賞についてです。サイエントークでも語られていましたが、毎年10件の研究に贈られる賞ですね。その中で私の大好きな1分野(生理学賞)だけですが、ご紹介したいと思います。(なんて、エゴ…….🤭)
受賞したのは日本人の研究者🧪 めちゃめちゃ視点が興味深い研究です。
遅くなりましたが、武部貴則先生、おめでとうございます💐
🦋Ig Nobel 賞とはどんな賞?
Ig Nobel賞について、みなさんもなんとなくご存知だと思いますが、Nobel賞とはどう違うの?思う方もいらっしゃるかもしれません。
Nobel賞は、ダイナマイトの発明者であるアルフレッド・ノーベルさんの遺言により1901年に始まった、ノーベル財団によって「人類に対して大きな貢献をした人物」に贈られる賞です。毎年10月ごろに発表されますね。
単語の意味だけを考えると、Nobelが「高貴な、名誉な」という意味を持つことに対して、Ig Nobelは「不名誉な」といった意味合いを持ちます。
Ig Nobel賞は、1991年に始まり、「人々を笑わせ、そして考えさせる驚くべき業績」を称えるために作られました。珍しいものを称え、想像力に富んだものを称え、科学、医学、技術への人々の興味を喚起することを目的にしています。
運営は、多くのノーベル賞受賞者を含むImprobable Research編集委員会によって行われています。選考枠に入るには、自薦・他薦による応募が必要で、毎年、自薦は10-20%程度ありますが、受賞確率は高くないようです。やはり、他薦してもらえるくらいインパクトがある研究ネタでないと審査員の心は掴めないのかもしれません☺️
この賞の受賞の連絡を受けた人は賞を辞退するオプションも与えられますが、今までにほとんど辞退した人はいないそうです。さらに、授賞式も自費で参加しなければなりませんが、多くの皆さんが忙しい研究の合間に自費で駆けつけているということは、研究者にとって受賞は、とても「名誉な」ことに違いありません。
今回、このnoteを書くのに初めてIg Nobel賞のWebサイトを訪問したのですが、「科学、医学、技術への人々の興味を喚起する」ための仕掛けがたくさんあることに気づかされました。サイエンスをいろんな視点で楽しみ、興味を持ってもらえる環境を作り出すのって大事だなって改めて思いました。
日本の理系離れも言われて久しいですが、最近はSNSでの研究者のアピールや情報提供もあり、少しは身近に感じてもらえるようになっていると嬉しいです。
もともと、理系と文系で分ける必要はないんじゃないのかな? 生物が好きでも物理苦手な理系の人も山ほどいますしね😆
🦋2024年の生理学賞は、武部貴則先生!
さて、今年の生理学賞は、みなさんも既にご存知の通り、武部貴則先生です。受賞理由は、ブタなどの動物に「お尻から呼吸する能力があることを発見した」ことです。
武部先生は、日本の複数の大学(大阪大学、横浜市立大学、東京科学大学(旧東京医科歯科大学))だけでなく、米国のシンシナティにも研究拠点を置かれている最先端の研究者です。31歳で横浜市立大学の教授に着任し、その後、爆速で成果を出されていますが、若くして医学部の教授になられたことで余計な苦労もされているのではなかろうかと、アカデミアをチラッと垣間見た私は勝手に思うのです。研究界隈が、そんな不要な苦労をしなくて良い、若い優秀な研究者がどんどん活躍できる世界になってほしいなと、いつも願っています。
そんな先生の主な研究分野は再生医療で、臓器オルガノイド(ミニチュア臓器)などでは他の研究者と異なる着眼点から研究を進め、素晴らしい成果を出されています。武部先生の研究については、ビビの再生医療のnoteでも少しだけ取り上げていますので、宜しければ読んでみてください☺️
🦋「お尻が呼吸する能力」とは?
この研究に関する最初の研究報告は、2021年5月にされました。コロナ渦の中での発表だったので、私もとても興味を持ったことを覚えています。
研究のひらめきは、ドジョウの腸呼吸にあるようです。
ドジョウは魚ですので、エラ呼吸が基本ですが、酸素が不足してきた非常事態には、補助的な呼吸手段として腸呼吸を使うことができるそうです。腸を満たしている水に溶けている酸素を体内に吸収するのです。しかしながら、哺乳類が同様の機能を持つかは知られていませんでした。
そこで、武部先生の研究チームは、マウスでも腸呼吸ができるか調べたのです。酸素ガスあるいは酸素を高濃度で溶解したパーフルオロカーボン(手術等でも使われる酸素溶解性の高い液体)のいずれかを腸内に投与したところ、どちらの方法でも血中の酸素量を著しく改善することに成功しました。
その後の研究で、ブタでもパーフルオロカーボン法で血中酸素濃度を改善することができました。また、腸管を通る静脈血の酸素濃度が上昇していることも分かりました。
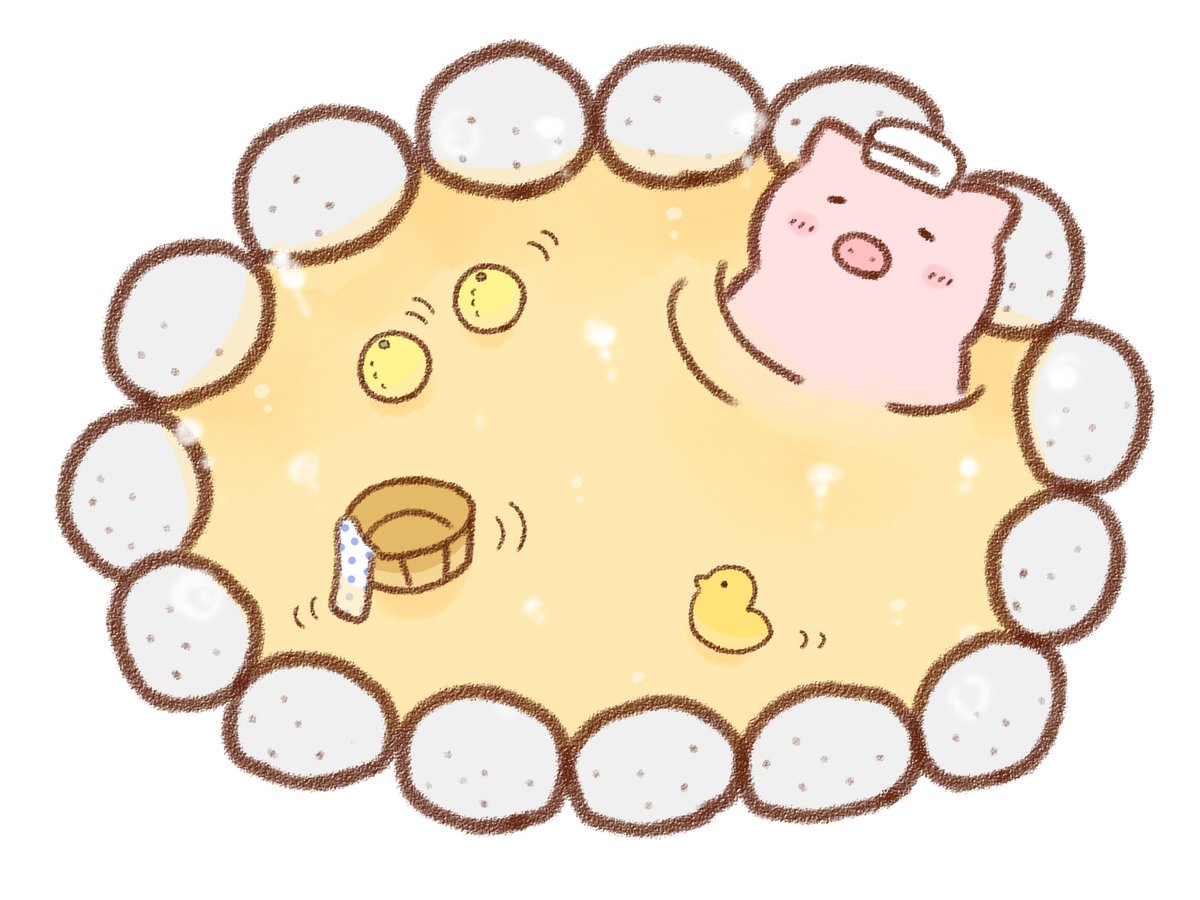
腸管を通る静脈血の酸素濃度が上昇
ヒトでも同様に腸呼吸ができ、血中酸素濃度が安全に、かつ十分に上昇するかはまだ試験途中です。解決すべき課題もたくさんあるかもしれませんが、ぜひ治療法として確立してほしいです。
🦋腸呼吸が注目される理由とは?
コロナの最中、肺機能の低下により血中酸素濃度が下がりすぎてしまい、重症化する患者さんが増え、ECMO(人工肺とポンプを用いた体外循環による治療)が注目を集めました。当時、機器の不足も話題となりましたが、何より専門の医療チームの付きっきりの対応が必要であることや、血液を取り出して体外で処理することによる患者さんへの負担やリスクが高いことも取り上げられました。
当然、体力の弱っている患者さんには、より負担の少ない治療法が求められます。
このアイデアは、医療の現場を知っている研究者ならではの発想だと思います。
今回のECMOのように、既に確立されている他の疾患に対する治療法の中でも、まだまだ十分でない方法はたくさんあるでしょう。お医者さん=研究者、あるいはお医者さんと連携した研究者がもっと増えると良いですね。
🦋EVANGELION
武部先生はこの研究をもとに、株式会社EVAセラピューティクスを創立されました。社名の由来には、液体で満たされるイメージからも連想される某アニメが念頭にあったとか・・・☺️
このスタートアップでは、既にいくつものパイプラインが走っており、中にはPhase Iを開始したものもあります。グローバルを視野に入れたProgramも多く、期待が膨らみます。
ぜひ皆さんも関心を寄せていただけると嬉しいです。
🦋最後に・・・
この研究がIg Nobel賞を受賞したニュースを知った時、え?Ig?なぜ?と一瞬混乱しました。私にとっては、最初のリリースからこの研究は早く臨床に上がるといいいな!としか思わなかった、ガチな研究だったからです。でも、この受賞のおかげで、世界中の注目を集めることができたのは、今後の開発を進める上で大きなプラスになるのではないでしょうか。
このお話は、ポッドキャスト(サイエントーク)をもとに書かせていただいています。研究者のレンさんとOLのエマさんの楽しいトークもぜひ聴いてみてください😆
サイエントーク
145. ブタはお尻で呼吸する?
関連資料他
1. improbable research
2. えら・皮膚・腸?謎だらけのドジョウの呼吸
3. 「腸呼吸の応用により、呼吸不全の治療に成功!」
4. 「 大動物を用いて腸換気法の有効性を概念実証 」
5. 株式会社EVAセラピューティクス
