
遠藤正二朗 完全新作連載小説「秘密結社をつくろう!」第3話 ─俺たちのアジトで旗揚げしよう!─Chapter1-2
鬼才・遠藤正二朗氏による完全新作連載小説、第3話が開始!
「魔法の少女シルキーリップ」「Aランクサンダー」「マリカ 真実の世界」「ひみつ戦隊メタモルV」など、独特の世界観で手にした人の心に深い想いを刻んできた鬼才・遠藤正二朗氏。

▼遠藤正二朗氏の近況も含めたロングインタビューはこちらから
『Beep21』では遠藤正二朗氏の完全新作小説を毎週月曜に配信中!
主人公の山田正一は、ある時『鍵』という形で具現化された強大な力を手に入れる。その力を有効活用するため、主人公のマサカズと弁護士(伊達隼斗)は数奇な運命を歩むことに。底辺にいる2人が人生の大逆転を目指す物語をぜひご覧ください!
前回までの「ひみつく」は
▼第1話を最初から読む人はこちらから
(Chapter01-02)【※各回一章分を無料公開中!】

【第1話あらすじ】
ある日、手にした謎の「鍵」によって無敵の身体能力を手に入れた山田正一(やまだ まさかず・28歳)。彼はその力の使い方に戸惑いながらも、同じ現場で危機を乗り越えた若き弁護士の伊達隼斗(だてはやと)の助言を得て、つけ込まれていた半グレ集団との縁を断つことに成功する。敵との死闘の中、鍵は一部が壊れてしまったが、その使い道について2人は本格的に考え始める。
▼"鍵"の予期せぬ使い方と急展開の事件が描かれる「第2話」はこちらから【※2話も各回冒頭の一章分を無料公開中!】
【第2話あらすじ】
敵との死闘の際、鍵は一部が壊れてしまったが、その鍵の修復を試みる中で、思わぬ使い方が判明する。伊達はその使い道について、事業計画書を書き始める一方、マサカズはアルバイト先の後輩、七浦葵(ななうらあおい)との距離が近づいていく。だがある日、日常を一変させる事件が突如起きてしまう…。
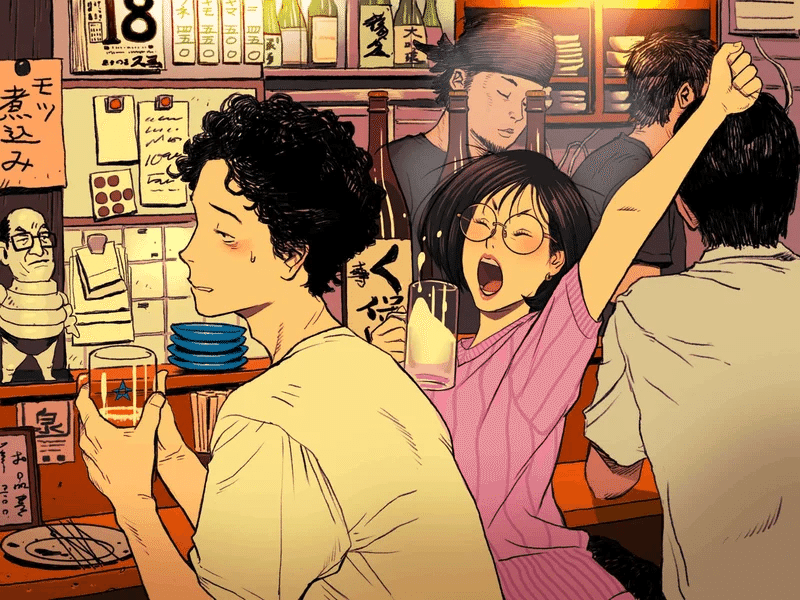

※本記事はこちらから最後まで読むことができます(※下の「2023年間購読版」もかなりお得でオススメです)
◆お得な「年間購読版」でも読むことができます!
※『Beep21』が初めてという方は、こちらの『Beep21』2021〜2022年分 超全部入りお得パックがオススメです!(※ご購入いただくと2021〜2022年に刊行された創刊1号・2号・3号・メガドライブミニ2臨時増刊号すべての記事を読むことができます!)
※初めての方は遠藤正二朗氏の「シルキーリップ」秘話も読める「無料お試し10記事パック」を一緒にご覧ください!
大きな痛みをともなう事件を経て、マサカズと伊達は新たな道を進み始めます。第3話もぜひお楽しみください!
第3話 ─俺たちのアジトで旗揚げしよう!─ Chapter1
アップライト筐体のモニターには、戦場を縦方向に進む兵士が映し出されていた。たった一発の敵弾で、兵士は大地に果てた。すると場面は幾分か巻き戻り、二人目の兵士が戦場に現れた。彼は今しがた果てた兵士と、うり二つの容姿だったが、同一人物かどうかはそれを操る側の想像力に任されていた。レバーを手にした伊達は兵士の行動を八方向から選択し、自動小銃で敵兵士を排除し、ここぞという局面においては数に限りのあるとっておきの手榴弾を投擲した。
「日本兵じゃねぇな」
背後からかけられたしゃがれ声に、ゲーム台と向き合っていた伊達は「たぶん、米兵です」と答えた。
「じゃあ相手はドイツか」
「です。おそらく」
最後の兵士が敵兵の銃弾に倒れると、スーツ姿の伊達は椅子から立ち上がり、ネクタイを締め直し、初老の男に振り返った。
ゲームセンター『エンペラー』は高田馬場の神田川に沿った路地にあり、所属する法律事務所から歩いて五分もかからなかった。店舗の特徴としては、八十年代以降の古いビデオゲーム筐体や基板を良好な稼働状態で維持し、提供しており、いわゆるレトロゲームの聖地としてマニアからの支持を集めていた。伊達にとっては“行きつけ”であり、今日も井沢との待ち合わせ場所として利用していた。
ゲームセンターを出た二人は夕暮れの中、神田川を望む歩道で肩を並べた。井沢は使い込まれた牛革のビジネスバッグからA4大の茶封筒を取り出すと、それを伊達に渡した。
「七浦の件だけどな。ありゃなんだ?」
「自分に聞かれても……」
伊達は困り顔を作った。この古豪に自分の動きが見抜かれていることは、これまでの付き合いでわかってはいたが一応そうしてみた。
「知ってるんだろ? 一課や科捜研の連中もハテナ出しっぱなしだぜ」
「いや、だから俺にわかるはずもないです」
あくまでも頑なな伊達に、井沢は鼻を鳴らすと川に目を向けた。
「まずな、人間じゃあり得ねぇ手口だ。ゴリラじゃねぇと、あんな殺しはムリだってよ。そして観覧車だ。山田がいたゴンドラにどうやって乗り込んだか、だ」
「彼も驚いていましたよ。一体どうやって地上百メートルまで登ってきたのかって」
マサカズはあの雨の夜、確かに七浦葵の出現に驚いてはいた。しかしその手段については確かな心当たりがあった。伊達の言葉には真実と虚構が入り交じっていて、井沢はそれに対して頷くことなく鋭い眼光を向けていた。井沢はかつて捜査機関で警部を務め、現場で長年に亘り叩き上げられた、もと敏腕捜査官である。人を値踏みする経験が豊富なこの古豪は、嘘を見抜いているはずである。それはわかっているものの、それでも伊達は鍵の異能について明かすことをしなかった。
「まぁいいや。あとな、“池ドラ”についちゃ、ありゃそもそも吉田が個人的に動いているだけで、組織としちゃ山田については認知してねぇようだ」
“池ドラ”とはマサカズを脅迫し、タタキを依頼した吉田が所属する反社会的グループ『池袋ドラゴン』のことである。伊達は頷いた。
「瓜原使って脅迫なんざ、吉田は本格的なアホだな。ありゃいつかしくじるだろうよ」
「珍しいですね、井沢さんが人物評なんて」
「山田正一絡みは、さすがに俺もクビを突っ込みがちになっちまってな」
井沢はそう言うと、被っていたハンチング帽を脱いだ。
「あー、お前さんの言う通りだ。確かにらしくねぇ。年甲斐もなくワクワクなんてしたら、コケちまうだけなんだよな」
「あぁ……」
伊達は井沢の言葉に軽く驚き、そして納得した。そう、自分もマサカズに対して関心だけではなく、期待を抱いている。経験を積み、大抵のことでは動じないはずの井沢でさえ、自身をつい見失うほどなのだ。三十は超えたもののまだまだ若造に類する自分など、冷静な判断を保てる自信もない。だとしたら、これからどうあのちりちり頭の青年と関わればいいのだろう。ネオンに照らされた七夕の夜空を見上げた伊達は、小さくため息を漏らした。
法律事務所まで戻った伊達は、自分のデスクについた。彼はパソコンをスリープ状態から復帰させると、あす法廷で争う、ある詐欺事件の資料を確認した。手口としてはある老人の息子になりすまし電話をかけ、金銭トラブルの懇願をしたのち、その被害相手を装った別の者が現金の振り込みを要求するといったものである。いわゆるオレオレ詐欺と言われている、最近となっては珍しくなった古い手法だったのだが、告げられた事態にうろたえた被害者は三百万円を振り込んでしまった。息子役であり、今回の顧客である二十代の男は犯行の全てを認めていた。通信履歴から足が着いてしまい、逮捕されたのだが、彼はネットでの闇バイトに応募したに過ぎず、犯行を指示したグループは別にいる。伊達にはそれに対しての心当たりがあり、連中が逮捕された際、おそらくこの事務所の誰かが弁護を担当することになることが予想できる。そこまで考えた伊達は、眼鏡を外して目薬を差した。
今回の依頼について、決して安くない弁護士費用は依頼者の父親である建築会社の代表が支払っていた。なんとか無罪、悪くても執行猶予でお願いできないか、などと彼は頼み込んできたが、どう努力しても実刑は免れないケースである。自分にできるのは、動機に凶悪性が薄く、再犯の可能性も低く、今後は両親のもと更生していく、といった主張を裁判所に対して訴え、できるだけ量刑を軽くするだけである。無論、これらの主張は全て自分の描いた物語でしかなく、拘置所での接見でこれまで知り得た依頼人の、法令を軽視する発言や態度から判断すると、あの青年は再び道を踏み外すだろう。だが、だからと言って依頼を請けた弁護人としての責務は全力で果たす必要があった。
所長の柏城は「ウチがこんなクズ共を弁護するのには理由がある。あいつらの金で潤ったぶん、恵まれない連中に救いの手を差し伸べるんだ」と語っていた。そう、すべては持たざる者たちに法律の加護を受けさせるためだ。伊達は改めてその基本的な理念を「仕方ねぇんだよな」と言い換え、つぶやいた。
「なにが仕方ないんだよ」
デスクの脇までやってきてそう尋ねてきたのは、所長の柏城だった。伊達は眼鏡をかけると、わざとらしく下唇を突き出した柏城に身体を向けた。
「あ、いや、なんでもありません。ただの独り言です」
「ならいいんだけどな。明日はしっかり頼むぞ」
「それなんですけど、一応聞いておくべきだって思ったんですけど、そもそもこの案件ってどういったルートでウチに来たんです?」
「父親がな、アッチと繋がりがあってな。どうやら仕事で関係しているって話だ」
柏城は苦笑いを浮かべ、立てた親指を自らの肩越しに後ろへ向けるとそう言った。“アッチ”とはこの事務所とも契約を交わしているある暴力団のことである。所長の様子からそう察した伊達は、「あー」と漏らし納得した。
「俺らの稼業は人のつながりで仕事が回ってくる。お前も時間のある限り人脈を作るといい。いずれ独立するときの財産になるぞ」
「それ、もう三度目ですよ」
「四度だって言ってやるぞ」
「そもそも独立なんて考えてませんよ。まだまだ半人前ですから」
「あのな、客観的に見りゃ、お前はもう独り立ちしてもおかしくない実績を積んでるんだぞ」
「いやぁ、全然ですって」
伊達の言葉に柏城は額の皺を深め、彼の肩に手を当てた。
「冗談抜きで言わせてもらうけどな、自己評価の低いヤツはこの稼業に向いてないぞ。今のお前の態度、ただの謙遜だと受け止めておくからな」
そう言い残すと、柏城は所長室に戻っていった。
弁護士としての能力は決して低くない。伊達はそう自覚していたが、独立について現実的に考えたことはなかった。そして、その理由について考えを深めたことはなかった。
飯田橋のマンションまで帰ってきた伊達は、鞄を置くと真っ先にシャワーを浴びた。Tシャツとスウェットに着替えると、彼は冷蔵庫からビール缶を取り出し、ソファに腰掛けた。井沢から受け取った書類に目を通しながら、伊達はビールを勢いよく呷った。
書類は、井沢が独自のルートで手に入れた七浦葵についての捜査資料を取りまとめたものだった。ゴンドラの外側には葵の指紋が僅かだが検出されていたため、マサカズの証言は裏付けられたが、どうやって地上百メートルはあるそこまで達したのか、手段については明記されていない。監視カメラの映像から葵が行ったと断定された二件の殺害についても、遺体が強大な暴力によって撲殺されたといった検死資料はあったものの、彼女がいかなる方法でそれを実現できたのかという点については、やはり記載はなかった。いずれにしても犯人は既にこの世に無く、今後については被疑者死亡のため不起訴となる。そうなれば犯行の手段について法廷で述べる必要もないため、検察が司法警察へ捜査の深掘りを要求することもないはずである。だが、これまでの被疑者死亡のケースとは異なり、あまりにも奇妙な事件の経緯に対して、興味を示す者が現れても不思議ではない。それがもし一定以上の地位にいる場合、自分では想像が及ばぬ手段で一連の犯行について調査を始める可能性がある。葵の遺品にはマサカズから盗んだあの鍵もあるはずだ。ありふれたものなので注目されることもないはずだが、今後は懸念するべき点ではある。
資料を読みながら、仏頂面の伊達はこの件についてこれ以上考えるのが無駄だと感じた。彼はビールを飲み干すと、二缶目を冷蔵庫から取りだした。
伊達はテレビとゲーム機の電源をつけた。ゲーム機には六十本のゲームタイトルがプリインストールされていて、伊達はその中から一本のパズルゲームを選んだ。
ゲームパッドでカラフルな宝石を模したブロックを操作しながら、伊達はマサカズとの今後について考えを巡らせ、口元に笑みを浮かべた。
第3話 ─俺たちのアジトで旗揚げしよう!─ Chapter2
ここから先は
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?

