
A piece of rum raisin 第12章 新橋第一ホテル(3)
第 12 章 第一ユニバース:新橋第一ホテル(3)
1978年12月24日(土)
12月1日に新橋第一ホテルで勤務を始めた。これはかなりキツかった。朝、大学に行き、夕方、京王井の頭線の駒場東大前から渋谷に行く。渋谷から山手線で新橋へ。だいたい、午後5時頃に新橋第一ホテルに着く。タイムレコーダーを打ち込んで、従業員食堂で早めの夕食をとる。午後6時に12階のバーに行く。バーは昼間も開いているので、昼間出庫してしまった酒、ソフトドリンク、つまみ、軽食用の食材の在庫を確認する。不足するものを地階の倉庫に取りに行き、バーのパントリー内の倉庫に補充したり、バーの酒棚に並べたりする。客の目に触れるビン類は濡れ布巾、乾いた布巾でピカピカに磨く。バーカウンターの下にソフトドリンクを補充しておく。生ビールの樽の残量をみて、交換したり、樽を取りに行ったりする。それを午後7時前くらいに終わらせると、だんだん客が増えてくる。フロアに出て、注文を受ける。バーテンに注文を伝える。伝票を作ったり、書き加えたりする。78年なのだから、すべて手書きだ。酒やカクテル、つまみを持っていき、伝票を客のテーブルの隅におく。
午後11時頃になると、だんだん客足が落ちてくる。その頃から、バーの閉店時間の午前1時を見込んで、たまった洗い物を少しずつこなしていく。パントリーも掃除し始める。午前1時にバーは閉店。その頃には、最後の客のテーブルの後片付けをしたり、あまり仕事は残っていない。床掃除は、早朝にホテルの清掃係が行う。
午前1時から1時間ほど、バーのスタッフで寝酒を呑む。スタッフは、正社員のバーテンダー2名ほどとアルバイト2名ほどだ。寝酒は、アルバイトが作ったりする。みんな飲むのはウイスキーのロックとか水割りだから簡単なものだ。その時、カクテルを試しに作らせてくれたりする。ステアの使い方とか、シェイカーの使い方をバーテンダーが教えてくれる。
みんな話すことは、土日の競馬や競輪の予想とか、世相の話とか。バーテンダーによるが、そこで客に見せる手品の練習をしたり、皮のダイス(サイコロ)カップでダイススタッキング(数個のダイスをカウンターに並べて、カップを振りながらダイスをカップの中に入れていき、ダイスを縦に積みあげる遊び)の練習をする人もいる。
午前2時頃にお開きとなり、バーテンダーと私たちバイトは仮眠室に行く。従業員階に仮眠室はあった。ホテルの客室と似たようなレイアウトになっていて、アルバイトの部屋は2段ベッドが設えてある。洗面所とシャワー室もある。午前2時なので、顔をさっと洗ったら寝てしまう。山手線の新橋駅の始発時間は午前5時頃。4時半にホテルを出て、駅に向かい始発に乗る。5時過ぎには原宿駅に着く。家に戻るのは6時少し前。それから午前中の大学の講義がない時は寝てしまう。9時からの講義がある場合には2時間ほど仮眠する。
ローテーションでたいがいが土日は休めるが、土日出勤の場合もあった。ここ第一ユニバースの体は20才。むこうの第三の39才の体よりはタフにできているが、それでも睡眠不足はどうしようもない。土日は寝溜めをした。
そんな生活なので、メグミにもあまり会えない。土曜日の早朝、私が家に帰るとメグミがいることが多かった。玄関を入るとメグミがいて、「おかえり、疲れたね」と言ってくれる。「うん、疲れたけど、面白いよ。今度手品を見せてあげるよ。習ったんだ」「どんな手品?」「まだ、簡単なやつだけど、逆さにしたコップの上に100円玉を置いて、バンっと叩くと硬貨がコップの中に入っている、とかね」
「あら、面白そうね。暇な時にやってみて。あ、そうそう、この前、教授のお使いで本郷に行ったら、理学部1号館で小平先生をお見かけしたわ。もちろん、声はかけなかったけど。それがね、あちらじゃあ、52才の先生の姿に慣れているじゃない?こちらでは32才よ。若いのよ。禿げてなかった。私だって、39才の感覚でいるけど、鏡を見れば20才の小娘。まだまだ慣れないわよねえ」
「そういえば、私も駒場で湯澤の姿を見かけたよ。確かに、あいつも20才で若い。自分もそう他人にはうつっているんだろうなあ」
「このバイト、来年まで続けるのよね?」
「湯澤が洋子にしたヒアリングでは、79年6月13日に落雷があるそうだ。洋子の第一の記憶はそう言っている。ホテルの彼女の部屋で私と一緒の時、落雷があって、記憶転移が起こるということだ」
「そのホテルの彼女の部屋に明彦と一緒というのが、私には非常に引っかかりますが?」
「私の責任じゃないよ、メグミ。だから、このバイトは来年の6月13日までは続けないといけないんだよ」
「仕方ないわね。でも後6ヶ月間も明彦は忙しいままなのね」
「その間、私たちの資金運用は任せたよ」
「先週の時点で3千万円ほど増えたわ。明彦の指示通り、野村證券の担当者と打合せをしながら運用してる。担当者の佐藤さんがね、なぜこんなに投資が当たるんだって不思議に思っていたわ」
「う~ん、勘付かれてはいけないから、証券会社を増やして分散させるかな?」
「その話は、明彦が睡眠を取ってからにしましょうね」
「そうだな、眠いよ」
「朝食を作っておいたわ。食べて。でもなあ、あと半年我慢しなきゃあいけないんだね。寂しいなあ」
「あと2ヶ月で絵美も合流する。そうしたら、分担できるよ」
「ときどきね、この数億円を持って、明彦と南米にでも夜逃げしたくなるわ」

「おいおい、私たちの双肩には、あちらの65億人の運命がかかっているんだからね。それと数兆、数京の生物の運命も」
「冗談です。冗談。でも、辛いなあ」
「まだ、序の口だよ。あと、30年くらい頑張る必要があるんだ。21世紀になれば、私たちに必要な科学技術も半導体も手に入るんだから。それまでに、資金を増やしておく、コネクションを作り上げないとね」
「わかってます。わかってますよ」
12月1日から三週間もバイトしていると業務にはだいたい慣れてきた。そして、クリスマスイブ。大学生にとっては、クリスマスは特別な日。サービス業にとってはかき入れ時。私にとっても今日は特別な日である。旧友との再開の日だった。だが、彼女はそれを知らない。
バーのチーフの吉田さんが、「明彦、クリスマスイブは絶対に休むなよ、終わったらロイヤル・ハウスホールドを際限なく飲ませてやる」と言う。ロイヤル・ハウスホールド(Royal Household)、英国王室御用達のスコッチの絶品。バランタイン30年よりもさらにさらに洗練された味。バーのアルバイトは普通飲ませて貰えない。とりあえず「う~ん、え~、まあ、いいですよ」と誤魔化しておく。クリスマスイブにここにいるためにこのバイトをやっているのだ。休めるわけがない。
ということで、24日午後5時に出勤。いつものごとく、社員用のレストランで夕食を取る。ホテルの社食だからこれがおいしい。クリスマス特別メニューで、ローストビーフ、ヨークシャープディングなどディッケンズの小説で出てくる料理がいっぱいで、楽しめた。
ホテルのバーは見かけよりもずっと忙しい。アルバイトだって、カウンターの中で酒を作ることもあれば(正社員のバーテンダーが休憩とか食事の時とか)、ボーイ役でバーの中を歩き回る。バーの後ろの隠れたパントリーで、カットオレンジやメロン、牛肉のタタキを作っていたり(カットと飾り付けだけ)、キッチンに素材を取りに行ったり、グラスを洗ったり。
このグラスを洗う、というのが重要だ。洗剤をいっぱい使ってゴシゴシ磨けばいい、などというものではない。
まず、シンクにぬるま湯を満たす。洗剤をほんのちょっと入れる。そして、数十個のクリスタルグラスを種類毎に漬ける。それから、スポンジに適度に洗剤をつけ、丁寧にグラスの底まで洗う。洗ったグラスは別のシンクで洗剤をすすぎ、さかさにして並べる。普通の家庭ならここまでだろう。
ところが、いくら丁寧に洗っても、クリスタルグラスには油脂分が付着している。乾くと曇る。
そこで、次に、シンクに熱湯を満たす。熱湯はホテルのセントラルの給湯システムから80℃の高温水が蛇口をひねれば出てくる。そこにひとつひとつグラスを浸して、熱湯と同じ温度になるまで待つ。同じ温度になったら、乾いたタオルで親指をグラスの内側に入れて、外側内側をキュキュッと磨く。そこまでしないとクリスタルグラスの表面の曇りは取り除けない。もちろん、場末の街場のバーでこんなことはしない。
バーのかき入れ時は8時から11時頃までだ。今日は普段の客の2倍以上が訪れる。注文を訊く、バーテンに伝える、バーカウンターの横のパントリーでメロンをカットしハムを盛りつける、飲み物と食い物を客に届ける。
シャンペンを注文する客、シャンペンクーラーを準備する、シャンペンをあける、ワイン、カクテル、時間が進むに連れて、強い酒が多くなる。ジャック・ダニエル、オン・ザ・ロックスをダブルでとか、マティニをシェイクしないで軽くステアして、ウィスキーグラスでオン・ザ・ロックスにして頂戴、なんて客もいる。4シートの席で、おのおの面倒なカクテルを頼むグループもいる。こっちはもう慣れた。いくらカスタマイズした注文でもすらすら復誦できる。「・・・と、以上のご注文でよろしいですね?」という私。間違いがないのに驚く客。毎日やっているんだよ、こっちは。客のカスタマイズドカクテルなんて、たかが知れたもの。
10時半を過ぎた。吉田さんが、「明彦、俺、飯食ってくるから、カウンターやってよ」と言う。私は年上でフーテンのアマネさん(本名をホテルの会計係以外誰も知らないし、アマネの由来も誰も知らない、私と同じアルバイトだ)に、「アマネさん、カウンターやってくるからフロアはお願いします」とフロアを預けて、カウンターに入った。
カウンターだって忙しい。生ビールの樽を入れ替えたり、氷を割ったり、グラスを磨いたり、カウンターを拭く、客が何とかビルはどこかね?という問いに答える、はさみある?なんてプレゼントを開くので訊く客、カクテルを作る、ウィスキーの水割りを作る、客の雑談に答える、ミリオンダイスにつき合う、シンクの洗剤をそそぐ、自分の蝶ネクタイを直す、外人の客に英語で答える、泣きべそをかいている女性客にティッシュを渡す・・・、やれやれ、無限に仕事は存在する。だから、それなりにアルバイト代はいいわけだ。
11時になって、急に潮が引くように客がいなくなっていく。外の銀座の風景が美しい。第1次オイルショックの時はネオンも消えて寂しかったが、今回のオイルショックでは、あまりネオン自粛の声も聞かれない。
カウンターには客が一人もいなくなった。フロアのアマネさんも暇そうにしている。
階段を降りてL字型に座り心地の良さそうな樫の木づくりの10席ほどのカウンターが有り、そこから建物の端までは2席から4席のテーブル席が設けられている。
アマネさんとフロアを見てよそ見していた私に、急に「ピンクジンを頂戴、タンカリー、ダブルで」とカウンターから注文が来た。いつの間にきたのか、チェアを引く音が聞こえなかった。「いらっしゃいませ。ピンクジン、タンカリーベースでダブルですね」と私はカウンターに目を戻して復唱した。待ち人が来た。私にとっては彼女と会うのは8年ぶりである。それもむこうで39才の彼女と会ったのが最後だった。

島津洋子が現れた。ビジネススーツを着ている。下がパンツなのかスカートなのか、カウンターからは見えない。非常に美しい。今の洋子は、彼女が第一から受信した記憶では26才のはずだ。ネイビーブルーのビジネススーツはオーソドックスだが、シャツは白のフリルがついているかなり高価そうな代物。プラチナの揃いのピアスとネックレス。四角いダイアモンドのペンダント。カウンターにおいた手には結婚指輪はない。バーテンは瞬時に客層を見るもんだ、と吉田さんが言っていた。
ミキシンググラスにロックアイスを入れ、タンカリーのダブルを注ぐ。ちゃんとメジャーグラスで計って注いでから、ちょっとハーフをグラスから足し増す。このおまけが客には重要だ。売り上げが上がる。
中指と薬指を折り、親指と人差し指、小指でミキシングスプーンを支えて、軽くステアする。アンゴスチュラ・ビターズを数滴。ミントの葉を2枚。ピンクジンの出来上がり。彼女の前にコースターをだし、グラスをそっとおく。我ながら流れるような作業だ。
「おいしいわ」と彼女。私もつられてニコッと笑う。
「クリスマスなのに大変ね?」と彼女が私に言う。「忙しいですが、イブにバーが閉まっていたらお客様がお困りになります」と私。
「お若そうね?」「え~、大学生なんです」「あら?ここに勤めているのじゃないの?」「夜だけですよ」私はグラスを磨きながら答える。
「いいわねえ、イブなのにやることがあって・・・」と彼女。心のなかで、イブにやることは君と会うことだよ、とつぶやく。「ハイ?」と素知らぬ顔で答えた。「イブなのに、ホテルのバーでやることもなくピンクジンを一人飲んでいる寂しい女もいるのよ」と彼女が言う。「今日も大変だった、クライアントと打ち合わせして、その後、食事。2次会も適当につき合って、ホテルに帰ってきたの。金沢から出てきたから知り合いもいないのね、あ~あ」と彼女。「うん、ゴメンごめん、愚痴が思わずでちゃったわね」と彼女はニコッと私に微笑みグラスを掲げて言った。「それは大変だったですね」と私はグラスを拭きながら言った。素敵な笑顔だ。
「キミ、仕事が終わった後はどうするの?終電もないでしょ?バーが閉まるのは1時よね?」と彼女が訊く。「ホテルの従業員階の一室に二段ベッドがおいてあって、バーの従業員は始発まで仮眠できるようになっているんですよ」と私。
「へぇ、そぉ?」と彼女が言う。ちょっと考えて、多少躊躇しながら彼女が小声で言った。「私ね、部屋が9階なの。903。ほら、この鍵」と真鍮のキーホルダーとキーを私に見せる。「キミ、その仮眠室、抜け出せるの?」と彼女。「え~、誰がいつ出て行った、なんて、同室のバーのバイト連中は気にしませんから。昼間まで寝ているフーテンもいます。ここを寝場所にしているようなものですよ。寝た後は誰も起きません」と私。
「そぉ、だったら、私の部屋にこられる?寝酒をつき合うっていうのはどう?」と彼女。おいおい、あの島津洋子が自室にバーのアルバイトを誘うのか?メグミの言うように、湯澤のヒアリングで女性が正直に全部話したわけじゃあなさそうだな、と思った。
ホテルの従業員はそういうことをしてはいけない、という理性の声も聞こえる。しかし、「問題ありませんよ、2時頃でもよろしいですか?」と平然と答える私。「2時ね、シャンパンを注文しておくわ・・・あなたが届けるんじゃないでしょうね?」「あのフロアに突っ立っている男が届けますよ」「そう、じゃあ、ピンクジンは部屋につけておいてね。それから、クリュッグのノンビンテージを冷やして部屋に持ってくるように手配してね。キミ、このお酒でよろしい?」と彼女。「了解致しました」と私。私は、伝票を書き、彼女に部屋番号と氏名、サインを求めた。
サラサラとサインすると、彼女は「じゃあ、あとで。メリークリスマス!」と小さく言い、さっさと立ち上がって、左手のエレベーターの方に消えていった。後ろ姿を見送る私。スカートだった。シームの入った黒のストッキング。やれやれ。
「アマネさん?」とフロアにいるアマネさんに言う。「なんだい?」「今のお客さん、903号室、部屋にクリュッグのノンビンテージを持ってきて欲しいそうですよ。グラスは2つ」と私。そう、グラスは2つ必要だろう?
「わかった、フロアの向こうにいたのでよく見えなかったが、美人だったな」「部屋に行ったらゆっくり鑑賞できるでしょう?」「はは、じゃあ、持っていくから、フロアも見てくれよ」とアマネさんはいって、パントリーからワインクーラーを取り、ワイン庫からシャンパンを持ってくると、私が用意した伝票を持って、エレベーターの方に向かった。入れ違いにバーテンダーが帰ってきた。素晴らしいタイミングだ。
「ハイ、ただいま。もう、客も引けたな?」と彼。「これから泥酔状態の一団がなだれ込んでこないとも限りませんよ」と私。
案の定、泥酔状態の5人組がなだれ込んできたのは12時だった・・・
「2時か・・・」
今晩、仮眠室はアマネさんと私だけだ。アマネさんは、いつもバーが閉まってからのバー仲間の一杯を、安ウィスキーを半パイントほども飲んで寝てしまう。寝たら絶対に起きない。この前など、情けないことに寝小便までしていた。この人の人生はなんなのだろうか?
「ま、いいや、メリークリスマス」と私は誰にともなく言った。
泥酔状態の5人組は適当に酒を出して、1時前には丁重にお引き取り願った。「お客様、当バーは午前1時までの営業となります。そろそろ閉店の時間なのですが・・・」と私。へべれけの5人組は素直に勘定をして出て行った。バーの入り口を閉ざす。5人組以外は客が居なかったので、洗い物も片づけも終わっていた。5人組のグラスを洗うともうやることもない。
「全部終わりましたが・・・」と吉田さんに言う私。「お!終わったか、じゃあ、約束通り、ロイヤル・ハウスホールドを飲めよ」とバーテンが言う。「ありがとうございます」とロイヤル・ハウスホールドの瓶を棚から取って、グラスに注ぐ。何も足さないで飲む。ノドを何の抵抗もなく落ちていく。素晴らしい。
「まあ、今日は忙しかったな。明日って、今日か、クリスマスだな。どうするんだ?」と彼が訊くので、「オフにさせてください、ちょっと約束があるので・・・」と答える。
「イブに仕事させたからな、女の子とでも約束があるんだろうな」「そうなんですよ・・・ああ、そうそう、部屋を取って頂けませんか?ダブルの部屋を」「なんだ?女の子と泊まるのか?贅沢なヤツだなあ、ホテルに部屋を取るなんて」とバーテンがうらやましそうに言う。
78年は、学生がシティーホテルに泊まるなんてことはまずなかった。たとえクリスマスイブだろうが、なんだろうが、そういう文化はまだ形成されていなかった。
「まあ、いいや、宮部の名前で取っておいてやるよ、特別料金だぞ、安くしておくから」と彼が言う。「ありがとうございます」と私。
アマネさんは、ウィスキーをストレートでガブガブ飲んでいた。カウンターの隅に坐って会話には参加しない。つくづく変わった人だ。
「さて、1時半じゃないか?お開きにするか?」と吉田さんが言った。「おい、アマネ、飲み過ぎたか?」とアマネさんにバーテンが訊く。「大丈夫ですよ」とアマネさんが答えるが、呂律が回っていない。最近酒にめっきり弱くなったようだ。「明彦、部屋まで一緒に連れて行ってくれ。それと寝小便をされちゃ困るからな、トイレをすませてから寝させてくれよ」と言われた。
私はアマネさんの腕を肩に回して、従業員用エレベーターで従業員階まで降りた。ベッドにアマネさんを放り出すと、もう彼はグウグウ寝ている。「アマネさん、トイレに行かないと・・・」と揺り起こすがダメだった。しょうがない、制服のままだが、制服はいつもクリーニングされて一式予備が支給されるので、明日は予備を着ればいい。毛布を掛けて寝かしつける。
私は、部屋に付属する小さなシャワールームで手早くシャワーを浴びて、私服に着替える。そっと部屋を抜け出し、客用エレベーターに乗った。2時5分。2時頃に、と言ったのでいいだろう。9階に上がる。
903号室は階の隅にある。そっとノックをする。ドアが静かにあけられた。「キミね?」と隙間から覗く彼女。「ちょっと待っていて。ドアチェーンを外すわ」ドアが閉まり中でガチャガチャやっている。「さ、入って」と彼女が言う。「おじゃまします」と小さな声で言う私。
ベッドは乱れていなかった。窓際のテーブルにアマネさんの届けたシャンパンクーラーがおいてあった。彼女はグレイのニットのミニドレスに着替えていた。ストッキングははいていない。素足だ。あちらの世界でも美しい女性だったが、彼女を性的対象として見ていなかった。こちらの世界の26才の彼女は若々しくさらに美しかった。むこう(第三)の意識が、記憶は39才だが、お前は20才の男性なんだぞ、彼女は26才の年上なんだぞ、と警告する。
「さ、坐って。寝酒をつき合ってくれてありがとう」と彼女は窓際のソファーを指差した。ソファーに座りながら「ご招待頂きありがとうございます」と私。彼女は壁に備え付けのデスクの椅子に腰を下ろした。

「キミ、制服じゃなくって私服だと確かに学生なのね」「だって、学生ですから」「トラッドが好きなのね」と彼女が言う。チノパンツにボタンダウンのシャツ、フィッシャーマンズセーターを私は着ていた。靴はデッキシューズ。「名前は?」「宮部明彦といいます」「じゃあ、明彦くんでいいわね?」とウインクする。洋子にウインクされるのはおかしな感覚だった。白衣を着たビジネスパンツでテキパキと物理学の講義をこなす彼女とイメージがダブってこない。
「ちょっと飲んじゃった」と彼女。「遅れてスミマセン、片づけがあった物ですから・・・」「仕事ですものね、シャンパンをどうぞ。それとも強いお酒がいい?」「いえ、シャンパンを頂きます」と私はシャンパンクーラーからボトルを取り上げ、タオルで結露した瓶の表面を拭ってグラスに注いだ。彼女のグラスにも残り少なかったので継ぎ足した。
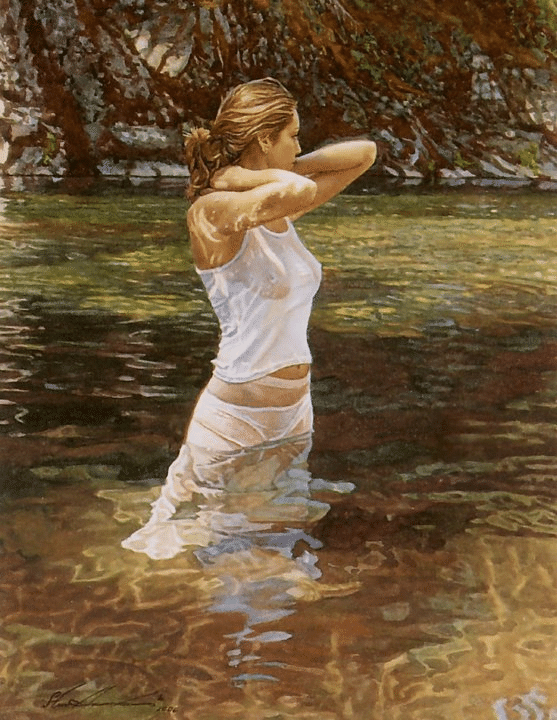
クリュッグのノンビンテージを頼むなどこの世界の洋子は趣味がいい。モエ・エ・シャンドンが日本人にはよく知られているが(ドンペリニョンはこの社で作っている)、クリュッグの味には負ける。ビンテージは、何年ものとか呼ばれる。その年のブドウからしか作られない。いわばシングルモルトのようなものだ。ノンビンテージは、さまざまな年のワインをブレンドして作られる、シャンパンのブレンデッドウィスキーだ。個性はビンテージが強いが、まよらかな味ならノンビンテージだ。むろん、高価だ。78年当時で3万円もする代物だった。ホテルのチャージがかかるので、いったいいくらになるのか?
「やっぱり、シャンパンはおいしいわ」と彼女が言う。「クリュッグのノンビンテージはあまり出ません。ご存じの方が少ないので。外国の方がよく飲まれるんですよ」「フランスにいた時、こればっかり飲んでいたわ」「フランスにおられたんですか?」「ちょっとね、はくつけで留学していたようなものよ」「へぇ~、パリですか?」
「モンペリエよ、南フランスの大学。パリはね、好きじゃなかったわ」と彼女が言う。「法学を学んだのよ・・・ところで、ね、キミの専攻は何なの?どこの大学?」と彼女が訊く。「本郷の大学です。物理科です」と私。「物理?変わっているわね?」「変わっていますかね?」心のなかで、むこうの第三ユニバースでは洋子だって素粒子物理学の権威じゃないか、とつぶやく。
「だって、工学部とかならいっぱいいるけれど、物理学専攻という人にはじめてであったわ」「そんなに希少価値がありますかね?」「上野の動物園のパンダ並じゃないの?」「それほど珍しいかなあ・・・」自分だって、第三ならパンダの仲間じゃないか?
「彼女いるの?」「いませんよ」とウソを付く。いや、メグミは彼女なのか?戦友みたいな同士なのか?
「イブにバイトしているくらいですから・・・」「それはお気の毒」「不躾ですが、あなたはどうなんですか?」「いないわよ、もう適齢期もすぎちゃったわ」なんてたわいない話をしばらくした。78年当時は、晩婚という現象もなく、26才でも適齢期を過ぎた、という感覚なんだろう。
急に真顔で「ねえ、何時までいられるの?」と彼女が訊く。「このシャンパンを持ってきた男が起きるか、朝の電車の時間の5時頃ですね」「その人、早起き?」「たいがい、昼近くまで寝ていますよ」「じゃあ、5時頃まであと3時間ちょっとあるけれど、私につき合う?」「いいですよ、明日は予定はありませんから」と私が言う。彼女は、椅子から立ち上がるとベッドに腰をおろした。
「キミ、何をしたい?」と彼女が言う。私は洋子の脚を見ていた。バーにいる時は、彼女の席はバーカウンター。脚がよく見えなかった。「ねえ、キミ、私の脚を見ているでしょ?」と彼女。「え?ああ、きれいな脚だなあ、って、島津洋子さん・・・」「あら、私の名前・・・」「伝票に書いてあったでしょ?それで覚えていたんですよ」「そぉ・・・」と自分の脚を見ている。

洋子が、「じゃあさ、試しに私のスネを触ってみて」と刺激的なことを言う。「え?」「だから、そんな離れたソファーじゃなくて」とバンバンと自分の座っているベッドの左横を叩く。「ここ、ここに座って」私は、ソファーから立ち上がりベッドの彼女の左に座った。洋子は太腿を押し付けてくる。彼女のミニドレス越しに彼女の体温が伝わってくる。メグミにお仕置きをされそうだ。
彼女は私の手を持って、彼女のスネに押し付けた。「どう?」「スベスベです」「私は毛深いほうじゃないから、ムダ毛処理も簡単に済むのよ」「へぇー」という会話になって、「キミ、女の子が毛深いか毛深くないか、どうやったら簡単に見分けられる?」などと質問する。
彼女が言うには「もみあげから顎、うなじにかけて産毛が多い女の子っているでしょ?そういう産毛が多い子は毛深いのよ」と持論を述べる。しかし、それが本当なのかどうか?調べないといけない。「キミ、女性のあそこの毛だって、もみあげから類推できます、キッパリと言いきれます」とか言う。これも調べないといけない。でも、誰相手に?メグミにでも訊くのか?
「私、そんな産毛が多くないでしょ?毛深くないのよ。ホラ?」と長い髪をかきあげて、耳ともみあげを見せる。確かにそうだ。産毛はない。「ね?今晩じゃないけど、今度じっくり私を確認してもいいわよ」とニヤッと笑って、彼女はシャンパンを飲み干した。
「さて、キミ、私と何をしたい?」と彼女が言う。「ええっと・・・キスを・・・」「キス?私と?」「ハイ、洋子さんとキスしたいです」「明彦くん、よく言った。いいわよ。私もキミとキスしたい」と洋子は唇を近づけてきた。
洋子はキスがとても上手だった。
【マガジン】
● A piece of rum raisin(note)
目次ー小説一覧
https://note.com/beaty/m/mc0c2a486fc74
● A piece of rum raisin オリジナル(note)
目次ー小説一覧
https://note.com/beaty/m/mc0c2a486fc74
● フランク・ロイドのエッセイ集ー記事一覧
https://note.com/beaty/m/m2927b9ba7a08
● お気に入りの動画・画像
https://note.com/beaty/m/m13bc6805ec47
いいなと思ったら応援しよう!

