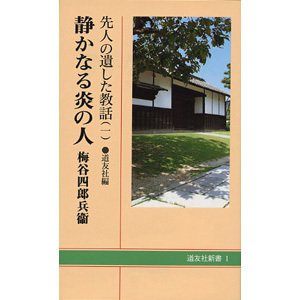明治二十年陰暦正月二十六日の物語
いつ引っ張られても構わん者ばかり、かかれ
教祖中山みき様が現身をお隠しになられた明治二十年陰暦正月二十六日の様子が、二代真柱による『ひとことはな志』その二に、お屋敷の青年づとめ第一号といわれる高弟、高井猶吉からの聞き書きとして記されている。
あの日の昼頃、管長さん(初代真柱)から「いつ引っ張られても構わん者ばかり、かかれ」とお話しあって、居合わした者でかかりました。誰と誰とであったか覚えんが、つとめ場所を出て甘露台の所でおつとめしました。その日はご命日(今で言う月次祭)であったので、たくさんの参詣人があったが、みな外へ出て参拝していた。それでも後から後からと、門からも押し入って来るので、竹で結界のようにしてあったのが、押し折られてしまった」
ご命日の参詣者は、一旦つとめ場所へ上がっていたのであるが、おつとめ始まるについて一度にドッと外へ押し出し、あまり広くもない庭は、その人たちで一杯になり、さらに内から雪崩入いる人々と押し合う様を想像下さい。記録には「参詣人数千人」とあり、また「竹が細かく割れたり」とさえ記されてあります。(中略)
「いつ引っ張られても構わん者ばかり、かかれ」
との言葉の裏には、必ず、おつとめ中途で中止されるもの、との予感があったのでしょう。
この聞き書きの「いつ引っ張られても構わん者ばかり、かかれ」との部分について、『稿本天理教教祖伝』では次のように記されている。
眞之亮から、おつとめの時、若し警察よりいかなる干渉あっても、命捨てゝもという心の者のみ、おつとめせよ。と、言い渡した。一同意を決し、下着を重ね足袋を重ねて、拘引を覚悟の上、午後一時頃から鳴物も入れて堂々とつとめに取り掛った。
「いつ引っ張られても構わん者ばかり、かかれ」『ひとことはな志』
「命捨てゝもという心の者のみ、おつとめせよ。」『稿本天理教教祖伝』
と、文言に若干の違いはあるが、どちらの文章からも、その時”おつとめ”をつとめることが非常に困難な状況にあったことが偲ばれる。
『御伝』で記される「命捨てゝも」という表現に、大仰さを感じる方もいるやも知れぬが、当時のお道を取り巻く環境、ことに官憲がお道に対して行った”弾圧”ともとれる行為をつぶさに見る時、それが決して大袈裟でないことは明らかだ。たとえば、
心勇組(敷島の前身)の講中が門前の村田長平方の二階でてをどりをしたためと考えられていますが、それは契機でありまして直接的には『御守の中に入れたる文字記してある「キレ」出でしより、其品を証拠として教祖様及び真之亮を引致したり。桝井と仲田ハ屋敷に居りし故引致せらる。
との理由で教祖が引致された「最後のご苦労」を終え監獄からお戻りになった際の
帰宅ハ旧正月二十六日に。おかいり後、もどりてから今日で十二日目になる。夫レより毎日、ねふどふし、耳ハ きこへず、めへハとんとみへず。
との文章からも、最後のご苦労を終えた教祖の、尋常ではない消耗ぶりが分かる。


老いて、傷つけられ、衰えゆく教祖のお身体を間近で拝し続けてきた眞之亮が、「これほどまでに衰弱された教祖が、再び拘引されるという最悪の事態に及んだならば、社としてのお身体がもう耐えられないだろう」と危惧したのは当然であろう。
教祖は”神のやしろ”として常に人々をお護りくださる存在であったが、眼前の衰弱しきった教祖は、初代真柱中山眞之亮にとって、自らの命に代えても護るべき存在であった。
かてて加えて、この時期「天理王は多人数を寄せ追々増長している」という報告が、所轄分署から奈良署(今でいう県警本部か)へなされており、警察が取締りを更に強化しようとしていることを、眞之亮は察知していたと思われる。
それゆへ、教祖から再三厳しく”つとめ”を急き込まれようと、逡巡し続けたのだ。「命捨てても」という眞之亮の言葉は決して大げさではなく、リアルな緊迫感をもって高弟たちの胸に迫ったであろう。
【註】ちなみに教祖が度々拘引されたのは、「違警罪第一条第九項」の
「神官、僧侶ニアラズシテ他人ノ為メニ加持祈祷ヲナシ、又ハ守礼ノ類ヲ配授シタル者」
という罪目に該当するという理由からである。お道はこの違警罪と違警罪即決令という天下の悪法に苦しめられることになったのだが、違警罪制定以前にもその前身である違式詿違条例によって厳しく取り締まられてきた。
(※その辺りの消息は松谷武一氏による『ひながたとかぐらづとめ』-国家権力の弾圧と近代法制資料-に詳しい)
そうした中を、数千人といわれる参詣人が詰めかけていたのだ。眞之亮の緊張と不安は極限まで高まっていたはずだ。
しかし、何事もなく無事おつとめをつとめ終えることができたことで、お屋敷の人々はもちろんの事、参詣人の喜びも大きかったであろう。
「これで教祖もご回復してくださるに違いない。おつとめをつとめたことをお喜び下さるだろう」と、誰しもが思った。
しかし・・・・・・25年の命を縮めて、扉は開かれた。
中山たまへ(11歳)の場合
ここで、当時11歳であった中山たまへによる明治二十年正月二十六日の懐旧談に目を通してみよう。
『稿本天理教教祖伝』と重複する箇所もあるが、11歳のたまへの視線で描かれている貴重な資料だと思う。

おつとめを終わってからよしゑさん(飯降よしゑ・当時22歳)に手を引かれて、つとめ場所の上段に祀ってある神床に参拝した。
〝おばあさま(教祖)は、もうようなって下さったやろか。ご飯もあがって下さるやろな〟と話しかけると、よしゑさんも〝そうでしょうとも〟と言っておられた。そして八畳間の入口まで送ってもらって、よしゑさんは帰った。
私は八畳の間へ入ったが誰もいなかったので北へ廻って、いつものように恐々ソッと障子から中を覗いた……
(二代真柱による補足)おつとめさえ勤めれば、教祖の身上はよくなって下さるものと信じておられたのであります。「扉開いて」とお願いした人々も、同じ心であったことは言うまでもありません。
ソッと覗くと、いつの間に来ておられたのか、お父様(眞之亮・二代真柱の父)はもう来ておられて、真っ赤な顔をして〝嬢(いと)、早よ来い〟と大声で言われたのや。おばあさま(教祖)が寝ておられるのに、あんな大きな声を出してと、ちょっと変には思ったが、それでもまさか、ご昇天になっているのだとは思わなかった。
〝嬢ちゃん。おばあさまがこんなになられた〟
と姉やん(梶本ひさ・初代真柱眞之亮の姉/後の山澤ひさ・教祖の最後のご苦労に付き添われた方。当時25歳)が私の手を、おばあさま(教祖)の顔に持っていったが、それでもまだ、息を引き取ったとは思わなかったが〝冷たいんやな。おばあさまは、もの言いはらへんねがな〟と言われて初めてそれと知って〝わァ〟と大声で泣いたので〝泣くな〟とお父様に叱られたのを覚えている。
それからお父様は〝皆に話してくるから、嬢、おばあさまの側を離れてはいかんで〟と出て行かれたが、その時には叔母やん(中山おまさ/教祖の長女・当時63歳)も居たように覚えている……」
「後になってから姉やん(梶本ひさ・眞之亮の姉)に聞いた話やが、皆がおつとめに出た後で、叔母やんと姉やんと二人でお側に居たんやが、陽気なおつとめの声を聞いて、おばあさま(教祖)は心地よさそうに、スヤスヤとおやすみになった。そこで、その時まで始終お側にいた叔母やんが〝おひさ、そこに居て。わしはちょっと拝んでくるから〟と言って、十二下り目にかかったと思われる時に出て行かれた。ちょうど、大工の人も揃い来たという最後のお歌が終わる頃、おばあさま(教祖)は、ちょっと変な素振りをされたので〝お水ですか〟言ったが何ともお返事がない。それでも水を差し上げたところ、三口召し上がった。〝おばあさま(教祖)〟と重ねてお呼び申したが、何ともお返事がないので大いに驚いて「誰かいませんか。早く眞之亮さんを呼んで来て下され」と大声で呼んだが、そこに誰かおったか、いなかったか知らんが、やがて叔母やんも、眞之亮さんも来たのや。誰かおって、呼んできてくれたのか、叔母やんが帰ってきて、眞之亮さんを呼んできてくれたのか、その辺はハッキリと記憶せぬが、おばあさま(教祖)のご昇天になる時に、お側におったのは私一人(梶本ひさ)との話や」
(以下二代真柱による補足)母様はここまで話されて、今なおまざまざと、その時の事が思い出されるように、座敷の一方を見つめられました。
〝今にも天地が闇になる〟かと思いながら〝まだ明るい、明るい、と思った〟との、子供らしい記憶を追うておられるようでありました。
やがて、長らく締め切られていた、上段の間と次の間の襖が開けられたが、そこには桝井(伊三郎)さんと梅谷(四郎兵衛)さんが、泣きこけておられたそうでありますが、もっともな姿と言えましょう。
これが幼いたまへの目に映った陰暦正月二十六日である。
眞之亮、中山おまさ、梶本おひさ、梅谷、桝井らの嗚咽や歯ぎしりさえ聴こえてくるような気がした。
梅谷四郎兵衛(41歳)の場合

さて『稿本天理教教祖伝』には正月二十六日当日の記録として、おつとめの役割が記されている。
その人々は、地方 泉田藤吉(47歳)・平野楢蔵(42歳)
神楽 真之亮(22歳)・前川菊太郎(22歳)・飯降政甚(24歳)・山本利三郎(38歳)・高井猶吉(27歳)・桝井伊三郎(38歳)辻忠作(52歳)・鴻田忠三郎(60歳)・上田いそ(50歳)・岡田与之助(宮森与三郎)(31歳)
お手振り 清水与之助(46歳)・山本利三郎(38歳)・高井猶吉(27歳)桝井伊三郎(38歳)・辻忠作(52歳)・岡田与之助(31歳)
鳴物 中山たまへ(琴 11歳)・飯降(永尾)よしゑ(三味線 22歳)・橋本清(つゞみ 年齢不明 20代から40代か?)
家事取締 梅谷四郎兵衞(41歳)・増野正兵衞(39歳)梶本松治郎(30歳)であった。
当時まだ幼少であったたまへも、孃(いと)、今日はお前もおつとめに出よ。との、眞之亮の言葉によって、つとめに出た。
家事取締りに当ったのは、梅谷四郎兵衞、増野正兵衞、梶本松治郎。以上総計十九名。(年齢はBeによる付記)
とある。この記述はみなさん何度も目にしてきただろう。
ここで注目したいのが、おつとめの役割に続いて書かれている「家事取締り」というお役に、梅谷四郎兵衞、増野正兵衞、梶本松治郎の三名がつかれている部分だ。
「家事取締り」とは如何なる役目なのか。
この「家事取締り」に当たった梅谷四郎兵衛は、明治十四年、左官業の弟子巽徳松の父親と雑談中に大和の生き神様の話を開き参詣を決意し、同年二月二十日、初参拝し、取り次ぎの先生の話を聞いて即日入信。大阪に帰ってその有り難いお話を知人や近隣に伝えて回り、十日後には八名を連れておぢばに帰り、三度目には同行者三十名という団参を果たす。入信直後からおぢばへ伏せ込み、同年、明心組(船場大教会の元)講元となった。入信から十ヶ月以内という驚異的な早さで講を作り、講元となっている。
明治十六年、「御休息所」の「壁塗りひのきしん」を勤めるが、この時におきた出来事が、『稿本天理教教祖伝逸話篇』123の「人がめどか」という逸話に記されている。
教祖は、入信後間もない梅谷四郎兵衛に、「やさしい心になりなされや。人を救けなされや。癖、性分を取りなされや。」と、お諭し下された。生来、四郎兵衛は気の短い方であった。明治十六年、折りから普請中の御休息所の壁塗りひのきしんをさせて頂いていたが、「大阪の食い詰め左官が、大和三界まで仕事に来て。」との陰口を聞いて、激しい憤りから、深夜、ひそかに荷物を取りまとめて、大阪へもどろうとした。足音をしのばせて、中南の門屋を出ようとした時、教祖の咳払いが聞こえた。「あ、教祖が。」と思ったとたんに足は止まり、腹立ちも消え去ってしまった。翌朝、お屋敷の人々と共に、御飯を頂戴しているところへ、教祖がお出ましになり、「四郎兵衛さん、人がめどか、神がめどか、神がめどやで。」と、仰せ下された。
この逸話はご存じかと思う。
『稿本天理教教祖伝逸話篇』には梅谷四郎兵衛に関する逸話が十三篇収められており、全登場人物の中で最多回数を誇る。それは熱心にお屋敷に伏せ込んだ証ともいえよう。
明治二十年五月十六日、本席より「息のさづけ」を授けられる。
明治二十二年一月十五日、船場分教会設置の許しを得て、初代会長となる。
一九一八(大正七)年四月、二代真柱教育委員。
大正八年五月二十九日出直し(享年七十七歳)
当時、「教理は梅谷四郎兵衛か桝井伊三郎に聞け」と言われていた。「純教理の梅谷」とも呼ばれていた。
入信は明治十四年なの教祖から直に仕込まれた先人の中では信仰歴は浅い方だが、天理大学名誉教授の高野友治は、明治二十年当時、前年に五十六歳で出直した仲田儀三郎を含め、桝井伊三郎(三十八歳)・山本利三郎(三十八歳)・梅谷四郎兵衞(四十一歳)の四人は、教祖から直接、そして最も教えを聴いてきた高弟であると述べている。
その四人の中で、出直した仲田を除き、桝井・山本の二人は正月二十六日のおつとめに出た。しかし梅谷四郎兵衛だけはおつとめに出ず、家事取締りの任についている。
そもそもこの日、”神楽”と”ておどり”の手は足りていたが、”鳴物”の手は揃っていなかった。男鳴物にいたっては橋本清がつとめた小鼓のみであるというのに、梅谷四郎兵衛がかんろだいの前に不在であったことが不思議でならなかった。
実はこの日、梅谷四郎兵衛は二十六日の午後の一時二十分前よりつとめにかかることが決まるや否や、早速おつとめ衣に着替え、なんとしてもこのおつとめで教祖のご身上を御守護いただくのだと、勇みに勇み、火の玉のようになって甘露台へ一旦は向かっていた。けれども、おつとめに出たという記録は残されていない。何故か?
その謎は教祖がお隠れになった翌日に、四郎兵衛が大阪の妻たねに宛てて綴った手紙を読むことで明らかになる。
手紙は陰暦正月二十七日に送ったものと二十八日に送ったものの二通である。まず、教祖お隠れという大事件の速報とも言える一通目の手紙には
【原文】梅谷四郎兵衛より たね宛
前文御免、さて御教祖儀、昨日廿六日午後の二時十分頃にお迎い取になりました。このことを聞いた事ならば、誠に心配をする事であろうけれども、何も心配することはいらん。そのつもりでどうぞ/\我が顔にも出さずに確かりしてくれますよう。飯降伊蔵様へお願い致しましたら、いままでに充分聞かしてあるとの事でした。これから道がころっと変りて、さあ/\これからや皆の者、揃うているか、これしっかりと聞き分け、とのおさしづでした。教祖の御葬儀は何日やら今日では、わかりません。そのつもりで大阪より参詣人は壱人も、私が帰るまで取り止めて下さる様に。
一番大切な用向きがすみましたら、直ぐ大阪へ一度帰ります。それまでは、たねの胸に仕舞って誰れにも言わぬようにして下さい。
(後略)たねどの江
梅谷四郎兵衛より
明治二十年陰暦正月二十六日、お屋敷はあたかも太陽が墜ちたごとき混乱の坩堝と化し、人々は悲嘆にくれていたが、現場に居あわせた四郎兵衛がしたためたこの文面からは、百十五歳定命と仰せられていた教祖が眼前で現身を隠されるという驚天動地の出来事のさなかに、動揺しながらも要点を外さない手紙を送っていることに驚かされる。
たとえば、この時、おつとめに出た平野楢造について、高井猶吉が次のように証言している。
「(教祖お隠れの報に接して)わしはそれから御休息所の方へ行きました。その時には、わしより先に幾人か御休息所へ行っていました。わしが行くと、郡山の平野(平野楢蔵)は、八畳の間の東側の縁に座り、片足を下げて、頭をかかえて考え込んでいました。
〝何してんねや〟
と尋ねると
〝俺は家へ帰れん〟
と言いよった。
〝何で去ねんねや(いねんねや/帰れないんや)〟
と尋ねたら
〝教祖は百十五歳が定命やと仰った。それで俺は、めったに神様のお話に違いはない。きっとよくなって下さると信じていたし、また人々にも話してきたんや。もし違(ちご)たら、俺の首やろ、とまで言ってきたんや〟
と言っていました……」
と伝えている。豪胆な平野楢造ですら茫然自失していた。
あるいは、教祖のお守り役であった増井りんは卒倒し、臥せってしまった。
事ほど左様に、教祖に薫陶を受けた高弟たちが一様に哀しみに打ちひしがれるばかりだった中で、梅谷四郎兵衛は
「何も心配はいらない」
と家族を励ましつつ
「これから道がころっと変りて、さあ/\これからや皆の者、揃うているか、これしっかりと聞き分け」
とのおさしづを正確に伝えると共に、向後の心構えと対応について、細やかに記した手紙を送っていたところに、四郎兵衛が稀代の高弟といわれる由縁を見る思いがする。
そして二日後に送った二通目の手紙。ここに四郎兵衛がおつとめに出ていない理由が記されていた。
【二通目の手紙原文】
ちょっとあらかじめ申し送ります。此の度の教祖長々の御身の悩みと云い、又はその上にお社まで捨てゝのお働きは、世界中皆何処までも、六じに踏みならすとのおさしづです。
(中略)
さあ/\しっかりと聞いて真実の心変らぬよう、さあこれからは道は、速いで/\、世界を六じに踏みならすと聞かしてあるで、これ一ツ忘れぬよう、とお聞かせ頂きました。それ故に今迄の道とは違い、社を聞いて世界六じに踏みならすとのおさしづでしまいでした。
どうぞその心得で今までよりも、真実厚くして、迷い疑う心は少しも持たぬよう。この事はくれぐれもしっかりと頼みます。自分は、とうてい二月中には大坂へ戻る事は出来ないと今日現在では思っております。
それ故にあらかじめの事を筆にて書き送ります。又私の事はこの度の御教祖の身上悩みに付き、正月廿六日に本づとめが勤まりました事に付ては、前日廿五日の午後六時にお地場へ到着いたしました。それより直ぐに談じ合いの中へ有難くも加わりました。
いよ/\廿六日の午後の壱時二十分前よりつとめにかゝられる様子になりました。私は心も勇みに勇んで黒衣を着して、甘露台へ向かおうという事になりましたら、内より梅谷/\と呼び声高く掛りましたので、見ますと、神様の次の間で、飯降様、梶本様の二人が顔色を変えて、我等二人は教祖の前に残り、あとは皆々高山(警察・監獄)へ行けば、我等二人でこの大切な御教祖を何としよう、どうぞ/\神様を大切と思うならば、何とぞ/\増野、梅谷、平野と三人は内へ残ってくれと、それは/\顔色変えてきびしく申し付けになりましたので、四郎兵衛心を取り直しまして、教祖の前にてふんばりました。増野と四良兵衛と二人だけで、平野はつとめに出られました。
あとの先生は、残らず無事で一座のつとめがすみやかにつとまりました。四良兵衛は廿六日の朝勤めには出さしてもらいましたのです。一寸此様子を申し送ります。
だん/\と御道はかわりて、真に頼もしき事になります。初めから聞かしてもらった通りの道になって来ました。十分思案して見なされや。
この屋敷一度は燈火が消えたような日があると聞きました事があります。
正にその通りであります。これからは教祖は、世界中を駆け回られるとの事です。
他にも詳しく申したい事も澤山ありますが、何分にも右の用事を申し送り度く、又後便にて詳しく申し送ります。
どうぞ/\心変る事のなきょう/\くれぐれも頼みます。
御母様を大切にして下さる様に。次に子供四人の事もよろしく頼みます。
二月廿日
たねどの
梅谷四郎兵衛
本席飯降伊蔵と、初代真柱の実兄である梶本松治郎から「何とぞ何とぞ増野、梅谷、平野と三人は内へ残りくれ」と名指しで命じられた、といよりも”懇願”された三名は、余人をもって代え難い信頼を本席から得ていたのだろう。
もしもおつとめに参加した者すべてが官憲に拘引されてしまうようなことになったならば、衰弱し切った状態の教祖はどうなってしまうのか。さらに万々が一、教祖が息を引き取られるという事態に及んだならば、残った飯降伊蔵、梶本松治郎とおまさ(中山おまさ/教祖の長女・当時六十三歳)・ひさ(梶本ひさ/眞之亮の姉・当時二十五歳)だけで対応するのは甚心許ない。また、もしも起き上がることもできない教祖が力尽くで拘引されるようなことになった場合、我が命に代えて阻止しなければならない。本席飯降伊蔵はそうした最悪の事態まで想定し、梅谷四郎兵衛らを引き留めたのであろう。
事態の急変にも臨機応変に対応できる者として、知恵と胆力と機転を兼ね備えた梅谷四郎兵衛、増野正兵衞、平野楢造ら三名が選ばれたことは必然であったと思われる。
これが梅谷四郎兵衛がおつとめに出ていない理由だ。「家事取締り」とは教祖の御身、「神のやしろ」を守るための最後の砦であったのだ。
「家事取締り」を命じられた三人の内、平野楢造だけは本席と梶本両人の懇願を振り切って決然とおつとめに参加している。
今際の際にある教祖の側に侍り、そのご容態の急変に対応しようとするのも大切な役目であるが、平野楢造は「おつとめさえ勤めたなら教祖は必ずご本復くださる。今優先されるべきは、お側でご容態を見守ることではなく、おつとめをつとめることだ」と瞬時に読み切ったのだろう。教祖に感化された元博徒、恩智楢ならではの黒白の選択過たぬ真っ直ぐな信仰と言えよう。
梅谷四郎兵衛とて、二月二十日付けの手紙に記される
「四郎兵衛心を取り直しまして、教祖の前にてふんばりました。増野と四良兵衛と二人だけで、平野はつとめに出られました。」
という、読む者にして落涙禁じ得ぬ短い文面からも、つとめに出ることができなかった無念さと切なさがにじみ出ている。胸の内に吹きすさぶ嵐に四郎兵衛は耐えたのだ。
その中で、家族はもとより、やがて教祖のお隠れを知るであろう明心組の信者に対して、二日後の二十八日には、いち早く「お道は益々伸び盛る。これからは教祖が世界中を駆け回ると仰せなのだから」と、教祖の思いと信者への対応の仕方を、妻に向けて的確に指示した四郎兵衛の揺るぎなき信仰に、心の震えるような感動おぼえる。
古い文献によると、この時おつとめに出ることができなかった梅谷四郎兵衛は、「柱にしがみついて男泣きに泣いた」とされている。きっと歯を食いしばって妻への手紙をしたためたのだろう。四郎兵衛の教祖を慕う一途な気持ちと堅固な信仰が胸に迫る。
四郎兵衛同様、再び立ち上がった多くの先人たちの強靱な信仰と一条心あればこそ、お道が今日に続いているのだと痛切に感じる時、その日から百四十年後の今を生きる私たちは、先人のご事歴や足跡、そして何よりもその精神を次代へと引き継ぎ、語り繋がねばならない。
それぞれの陰暦正月二十六日の物語
教祖がお隠れになった翌日の明治二十年陰暦正月二十七日にお屋敷の前で撮った集合写真を見ると、遠方で間に合わなかった方を除いて、教史に名を残す多くの先人が参集していたことがわかる。
だが、ここには明治十二年から教祖のお守役をつとめていた増井りんが写っていない。
増井りんは大縣大教会の礎となった方で、女性として初めて本部員に登用されれた方だ。りん以降現在にいたるまで、女性本部員は一人も誕生していない。
りんの入信は明治七年。失明寸前のところを御守護いただいた話は有名だが、他にも『稿本天理教教祖伝逸話篇』44 「雪の日」なども印象的な逸話なのではないかと思う。
明治十二年六月頃には
「用に使うとて引き寄せた。直ぐ、直ぐ、直ぐ。早く、早く。遅れた、遅れた。さあへ楽しめ、楽しめ。」
とお言葉があり、その日から教祖のお守役としてお側に仕えるようになった。当然明治二十年正月二十六日にもお屋敷にいらっしゃったが、教祖のお隠れに衝撃を受け、卒倒してしまい、そのまま寝込んでしまったのだ。その哀しみはあまりにも深く、六日後の陰暦二月一日につとめられたお葬儀にも参列できないほどだった。おりんさん、どれほど無念だったことだろう。
また船乗り卯之助こと、撫養大教会の初代、土佐卯之助は明治十七年頃には阿波真心講として六十余の講元や周施方を擁し、阿波一国に千戸の信者を擁していたが、止むに止
まれぬ不本意な決断をせざるを得なかったことによって、本部から「謀反人」と誤解を受け、お屋敷に近づくことさえできなかった。その結果、教祖のお隠れに立ち会えなかったのみならず、葬列に加わることすら許されなかった。その詳細については別の機会にゆずるが、土佐卯之助や増井りん。あるいは高井猶吉や平野楢蔵にも正月二十六日の物語があったように、教祖の親心と謦咳に触れた先人一人ひとりに『明治二十年陰暦正月二十六日の物語』はあったのだろう。
さあこれからは道は、速いで/\
いま、明治二十年陰暦正月二十六日から間もなく百四十年が経とうとしている。お隠れに接して、悲嘆に暮れるそばな者に対して、本席飯降伊蔵を通して下ったおさしづ、
子供可愛い故、をやの命を二十五年先の命を縮めて、今からたすけするのやで。しっかり見て居よ。今までとこれから先としっかり見て居よ。
あるいは
さあこれからは道は、速いで/\、世界を六じに踏みならすと聞かしてあるで、これ一ツ忘れぬよう
とのお言葉通り、教祖お隠れ後の百四十年間で、人間を取り巻く環境はめざましい進歩を遂げた。現在では、教祖ご在世中には存在していなかった電気、ガス、水道などの生活基盤となる設備や道路、鉄道、港、空港などの交通網。また、電話やインターネットなどの通信網や病院や公園といった公共施設までもが整えられている。
そしてなによりも、明治二十年当時、数万人程度であった信者数は、その後燎原に火を放つがごとく増え続け、明治二十五年、豊田山新墓地への教祖改埋葬の際は十数万の信者が馳せ参じ、明治二十九年には信者数三百万を数えた。百年祭以降減少が進んでいるとはいえ、今この瞬間も百万を超える人々が教祖ひながたの道を辿るべく、その歩みを進めている。
これらの歴史的事実を俯瞰する時、やはり教祖はお隠れ後の百四十年間、明治二十年陰暦正月二十六日以前にも増して、休むことなく世界中を駆け巡ってくださっていたことに改めて気づく。
今までとこれから先としっかり見て居よ。さあこれからは道は、速いで/\
とのお言葉に、いささかも嘘はなかった。
教祖のお言葉通りの世界。梅谷四郎兵衛が心に吹きすさぶ嵐に耐えてしたためた妻への手紙通りの世界に、いま私たちは身を置いている。いま私たちは身を置いている。教祖年祭の旬は、今も世界を駆け回ってお導きくださる教祖の親心にお応えする旬であるが、その旬に教祖ひながたの同行者として苦難の道中を歩まれた先人の信仰と、その面影に思いを馳せることも、決して無駄ではないだろう。
よって件のごとし。
ではまたいずれ。
関連記事
■明治二十年陰暦正月二十六日 「家事取締り役」梅谷四郎兵衛の手紙
■春季大祭を迎えるにあたり-明治二十年陰暦正月二十六日のおさしづ割書から-
■(続)春季大祭を迎えるにあたり-『御教祖御臨終のおさしづの考察』より-
【お薦めの本】
松谷武一著 『ひながたとかぐらづとめ』-国家権力の弾圧と近代法制資料-

天理教道友社編『静かなる炎の人・梅谷四郎兵衛』