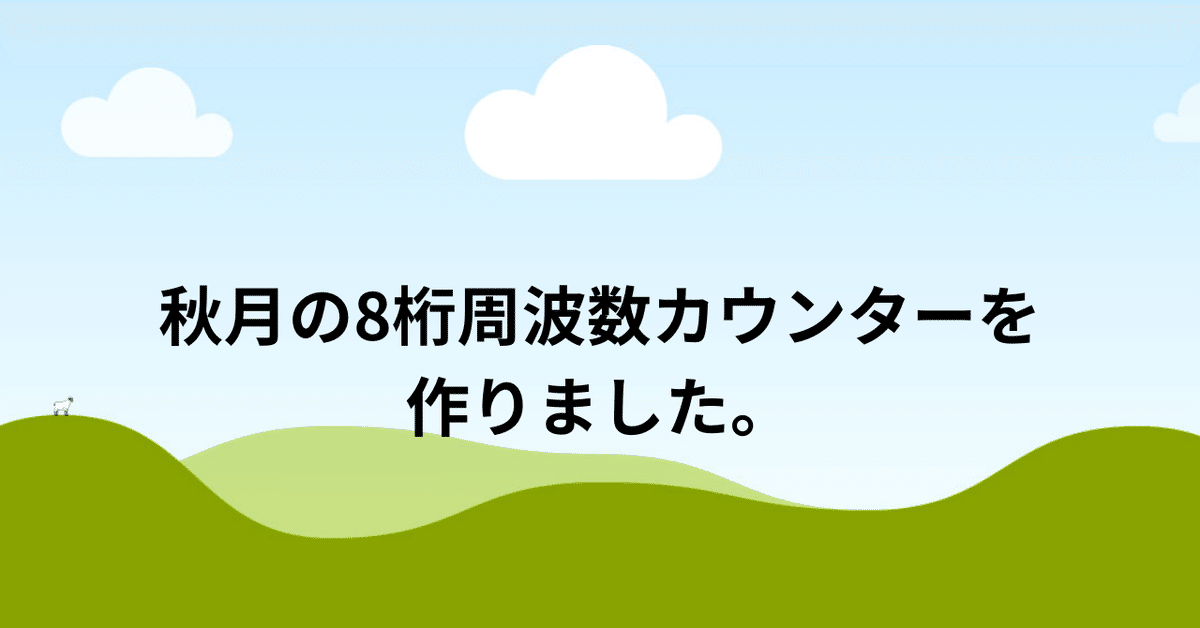
秋月の8桁周波数カウンターを作りました。
初めに
今、アナログレコードからの信号のハイレゾ化を試みていて、どんなオーディオインタフェースが良いか? 録音、編集はAudacityを使用してハイレゾを実現できないか、あれこれ考えています。
そんな中で、自作の低周波発振器(出力周波数と出力信号の大きさを変えることができます)を使用しているのですが、正確な発振周波数が知りたくなりました。今まで周波数カウンターを使って校正したことはありませんでした。

右上のつまみで出力信号の大きさを変えます。
そこで、秋月通商で、4年ほど前、低周波を測れる「1Hz~50MHz 8桁表示周波数カウンタキット」を買ったなと思い出し、取り出して来て製作した次第です。
ちなみに、この8桁表示周波数カウンターは、2024年8月現在でも、秋月通商で販売しています。型番は AE-FCOUNT3で4980円となっています。私が購入した2020年頃は3800円でした。秋月通商のwebページには、マニュアルもありますので、正確な事を知りたい方は、そちらをダウンロードして、読んだ方が、私のこの文書を読んでいるより確実です。
ちなみに、画像に出した自作の低周波発振器は、サトー電気さんの組み立てキットを使ってます。中身は、電球を使って増幅率の制限をしているウィーン・ブリッジ発振回路です。
わりと綺麗な正弦波(歪率が0.03から0.05%)が0.5Vぐらいで出力されます。出力電圧は可変できます。発振器の基板と部品の値段は1920円でした(値段に、こだわりますが)。2024年8月現在、まだ、サトー電気さんで売っています。
製作
マニュアルに従って、部品を基板に半田付けしていきます。20個ほどの部品です。
マニュアルに1つ間違いがあってC6は、47μF 35 Vではなく、10μF 50Vです。
なお、この基板はLEDと制御するタクトスイッチ3つ、測定モードを切り替えるDIPスイッチ、赤色LEDが乗っている表示部と、実際に信号を入力して処理、計測する計測部の2つに分かれています。(表示部、計測部は、私が勝手にそう言っているだけです。)表示部を計測部から切り離して、垂直に立てる(パネルなどに実装する)ことができます。しかし、切りはなすと表示部と計測部を23本の導線で接続しなければならないので、切り離すことはやめました。
電源
電源は、DC6Vから9Vです。容量は300mA以上が推奨されています。今回は、単3電池4本で6VにしてDCコネクタのところに直接、半田でつないで使っています。
火入れ
電池を4本セットして、電源投入です。オープニングメッセージ「FCount-3」が表示されました。すぐに消えましたが、無事、動作しているようです。

測定モード
秋月のWebで公開されているマニュアルのセットアップのところを読んだ方が早いですが、一応、さらっと書きます。
セレクトスイッチというDIPスイッチ(スライドスイッチが2つあります)が表示部、7セグメントLEDの下にあるのですが、2つのスライドスイッチの組み合わせ4つで4つのモードを設定させます。モード毎に入力するポートがあり、全部で4つのポートがあります。
以下に簡単に書きます。
・HFモード(スイッチ1:ON,スイッチ2:ON)、高周波アンプ入力、HF端子使
用、入力周波数 100kHz~50MHz、
感度700mVpp@50MHz 正弦波
・CH1モード(1:ON,2:OFF)、プリスケーラ接続入力用、CH1端子使用、
入力周波数 0Hz~50MHz、TTL入力
・CH2モード(1:OFF,2:ON)、オフセット値設定入力用、CH2端子使用、
設定オフセット値0~99.999999MHz、
入力周波数 0Hz~50MHz,TTL入力
・LFモード(1:OFF,2:OFF)、低周波アンプ入力、LF端子使用、
入力周波数 約50Hz~200kHz程度、
感度200mVpp@20kHz 正弦波
HF,端子とLF端子の入力は、±5V以内。CH1端子,CH2端子はTTLレベル(最大5V)となっています。
今回、一番使いたいのは低周波発振器の発振周波数ですから、スイッチを2つOFFにして、LF端子に5V以内の低周波信号を繋ぐことがメインとなります。
初期設定(セットアップ)
実際に使う前に初期設定をします。これもさらっと書きます。
・HFモード(1:ON,2:ON)にします。
表示部の7セグメントLEDの下にあるSET、HOLD、GATEのタクトスイッチ
を使って設定します。
・まず、SETスイッチを押します。LIGHTと表示されGATEスイッチか、HOLD
スイッチを押すことでLEDの明るさを調整します。
・またSETスイッチを押します。BPSと表示されTX端子から出力されるデータ
のボーレートを設定します。実際の測定とは関係がないです。
・さらにSETスイッチを押します。L*(*は1~9の数字)と表示されます。HF端
子をショートします。基板上のVR2を回して、7セグメントLEDがバーグラ
フになるので一番大きいところに持っていきます。これで、感度が最高に
なります。
・さらにSETスイッチを押します。GPSモジュールからのIS信号を使用しての
基準発振器を正確に校正する機能です。関係がないので飛ばします。
・最後にSETを押します, HFモードの測定の通常表示に戻ります。この時点で
各設定は保存され、次回電源ON時に、この設定で起動します。
なにか誤動作が起こった場合は、計測部にあるResetボタンを押します。電源投入時の状態に戻ります。(ファクトリーリセットではありません。)
低周波の測定(LFモード)
SELECTスイッチを(1:OFF,2:OFF)にして、LF端子に自作低周波発振器の出力をつなぎます。入力は±5Vまで許されているので、発振器の出力は、テスターで測って交流0.53Vにしておきました。
発振器のツマミを左にしぼって、最低周波数にします。最低発振周波数は、45Hzでした。

出力を1000Hzに正確に合わせることもできます。

発振器のレンジをHighにして、ツマミを右に回し切り、最高周波数を出力させました。最高周波数は、23447Hzでした。人間なら聞こえるか、聞こえないかというところでしょうか?

また、出力を下げていきました。テスターで測って2599Hzで0.014V(14mV)で安定に測れました。マニュアルには、200mVp-p@20kHz 正弦波とあるので、それよりもかなり小さい信号で安定して測れました(周波数が異なっていますが)。
高周波の測定(HFモード)
SELECTスイッチを(1:ON,2:ON)にして、高周波の測定モードにしました。私は、高周波発振器を持っていないので、HF端子にYAESU FT817NDというトランシーバーの出力を直接接続しました。トランシーバーのモードをAMにして0.5Wの出力をHF端子に入力させました。本来ならインピーダンスマッチングを考えなければならないのですが無視しました。回路図をみると入力にISS352(高速スイッチングダイオード)がプラスマイナスに入りクランプしているので大丈夫かと思いHF端子に直接入力しました。

アマチュア無線用のトランシーバーなので、まずは低いバンドの1.9MHz付近を入力させました。1.954998MHzとでました。

FT817NDの表示では、1.95500MHzと表示されていたので、0.000002MHz(2Hz)の違いです。これは、8桁カウンターとFT817NDの使っている基準発振器(水晶)のわずかな違いと言ってよいでしょう。2ppmの差といったところでしょうか。
3.5MHz、7MHz、10MHz、14MHz、18MHz、21MHz、と各アマチュア無線のバンドの周波数を入力させ、順調に表示することができました。
28MHzの時の表示が、28.199731MHz。FT817NDの表示では、28.19976MHz(7桁表示)。
0.000029MHz(29Hz)の違いとなっています。1.9MHzの時から、出力周波数が1桁上がっているので、違いも1桁あがりました。

8桁カウンターの測定周波数の上限が、仕様では50MHzです。アマチュア無線の50MHzバンドの上限周波数54MHzを入れてみました。FT817NDは賢くできていて、それぞれのバンドの周波数の上限を超えて出力しようとすると「TX ERR」と表示し、出力しません。50MHzバンドでは54MHzが上限周波数となります。FT817NDは、144MHz,430MHzと出力できるのですが、54MHzが今回、上限です。
8桁カウンターは、53.999945MHzと表示しました。

FT817NDの表示は54.000000MHzです。0.000055MHz(55Hz)の差でした。8桁カウンターの基準周波数発振器も、FT817NDの基準周波数発振器も誤差がありますから、どちらが悪いとも言えません。いつもFT817NDの方が高くでて、差は数ppmという結果になりました。
8桁カウンターは、仕様では50MHzが上限ですが、それ以上にカウントしました。どこまでが上限なのかは、54MHz以上を出力する発振器がないのでわかりません。
まとめ
・自作の低周波発振器の発振周波数は、45Hzから23447Hzでした。
・8桁カウンターの低周波の測定上限周波数は分かりません。仕様では
200kHz程度と書いてあります。
・8桁カウンターの低周波の入力感度は、14mVでした。
仕様では、200mVp-p@20kHz正弦波と書いてあるので、それよりもはるか
に優秀でした。
・高周波では、1.9MHzから54MHzまで0.5Wの入力で安定して、測りまし
た。仕様では、100kHzから50MHzまで、とあるので、上限は50MHzを超
えていました。どこまで測れるのは、わかりませんでした。下限の100kHz
も確かめることはできませんでした。
・高周波の入力感度についてはFT817NDを0.5Wから絞ることができないの
で、下限を確認することはできませんでした。
感想
・秋月の8桁周波数カウンターは、アマチュア無線のHF帯、50MHzバンドと
良く売っているトランシーバーの周波数帯で使用することができるもので
した。使えます。
また、高周波モードの下限が100kHzということであれば、高速OPアンプ
の試験にも使えるかなと思います。
・低周波は、下限45Hzから、今回確認できませんでしたが200kHzまで測れ
るとなると、オーディオ装置、ハイレゾでもPCMで192kHzのサンプリング
周波数が、今、通常上限となっているようですので、そこら辺でも使える
でしょう。
・別の話なのですがHFモードの時、アナログ信号が、ロジック信号に変わる
ところに、74VHCU04というインバターICが使われています。私は、この
一番基本的なロジックICが1秒間に54MHz(5.4千万回)で、実際ON/OFFし
ているのを考えると感心してしまうのです。
以上、最後まで、お読みくださりありがとうございました。
秋月の8桁周波数カウンター作りたくなりましたか?
いいなと思ったら応援しよう!

