
テレビの世界の話⑥「開局」の二文字に隠された想いとは・・・
普通の人ならばそうそう関わることのない「放送局の開局」。ところが昨今はyoutubeを始めとしたSNS上での動画の配信サービスを始めるということを「開局」と呼ぶならば多くの人が自分事化できるでしょうね。今回は「放送局の開局」のお話です。
最近、案外「開局」ラッシュ!
「開局」という言葉の響きには、道なき道を歩み始める勇気と不安な心持ちを感じます。果たしてSNS上における動画の配信のスタート時に、既存の放送局で行われる「火入れ式」に似た「はじまってしまうよ、続くといいな」的なノスタルジーを感じるかどうかはわかりません。でも、未来永劫続ける(予定の)放送事業における「開局」は特別な感情を抱くものだったのです。
振り返れば、今から67年前のNHKテレビ、日本テレビの開局が1953年。新しいところで平成新局の最後発が21年前の「とちぎテレビ」で1999年。この頃、衛星放送局も開局ラッシュでした。その後、暫く「開局」から遠ざかったかなと思いきや、「Channel4K」「スカパー4K」「ケーブル4K」「ひかりTV4K」など4K局の開局ラッシュが続きました。そして2018年12月には新4K8K衛星放送がスタートしています。

「開局」はメディアの自浄作用?
こうしてみると、放送業界は常に「開局」という「ハレの儀式」を積み上げることでメディアとしての自浄作用を働かせているのかもしれないと感じます。一方、ハレの裏には開局前夜のスタッフの血のにじむような努力があるのです。私自身も2000年のBSデジタル放送(映画専門放送局)の開局、今は亡き「ベネッセチャンネル」の開局前夜は、ぎりぎりまで番組制作を続けた思い出、はたまたChannel4K開局に際しては、そもそもだれも作った事の無い4Kの放送番組を模索したことなど、開局前夜の生みの苦しみを味わったひとりです。
民放第一声は名古屋のCBC
昭和26年1951年9月1日午前6時半「JOAR、こちらは中部日本放送、1090キロサイクルでお送りします」という宇井昇アナウンサーの第一声で開局したCBC中部日本放送。名古屋にあるこの局は、実は民放で始めて放送を出した局なのです。「民間放送史」には開局のその日を知る手掛かりがあります。
「前夜までの暗澹たる焦燥感と、スタジオ内の火の車ぶりをよそに、電波は淡々と定時番組「朝の調べ」「服飾講座」と続く。(中略)七時にはじめて服部時計店寄贈のテープ自動送出時報装置がテーマミュージックに続いて「ピンカラ、ポンカラ、ピィーッ」と民放特有の時報音を入れた。それは永くNHKの「ポッ・ポッ・ピーン」になじんでいた聴取者に“民間放送の音”を印象付けた。」(※1)
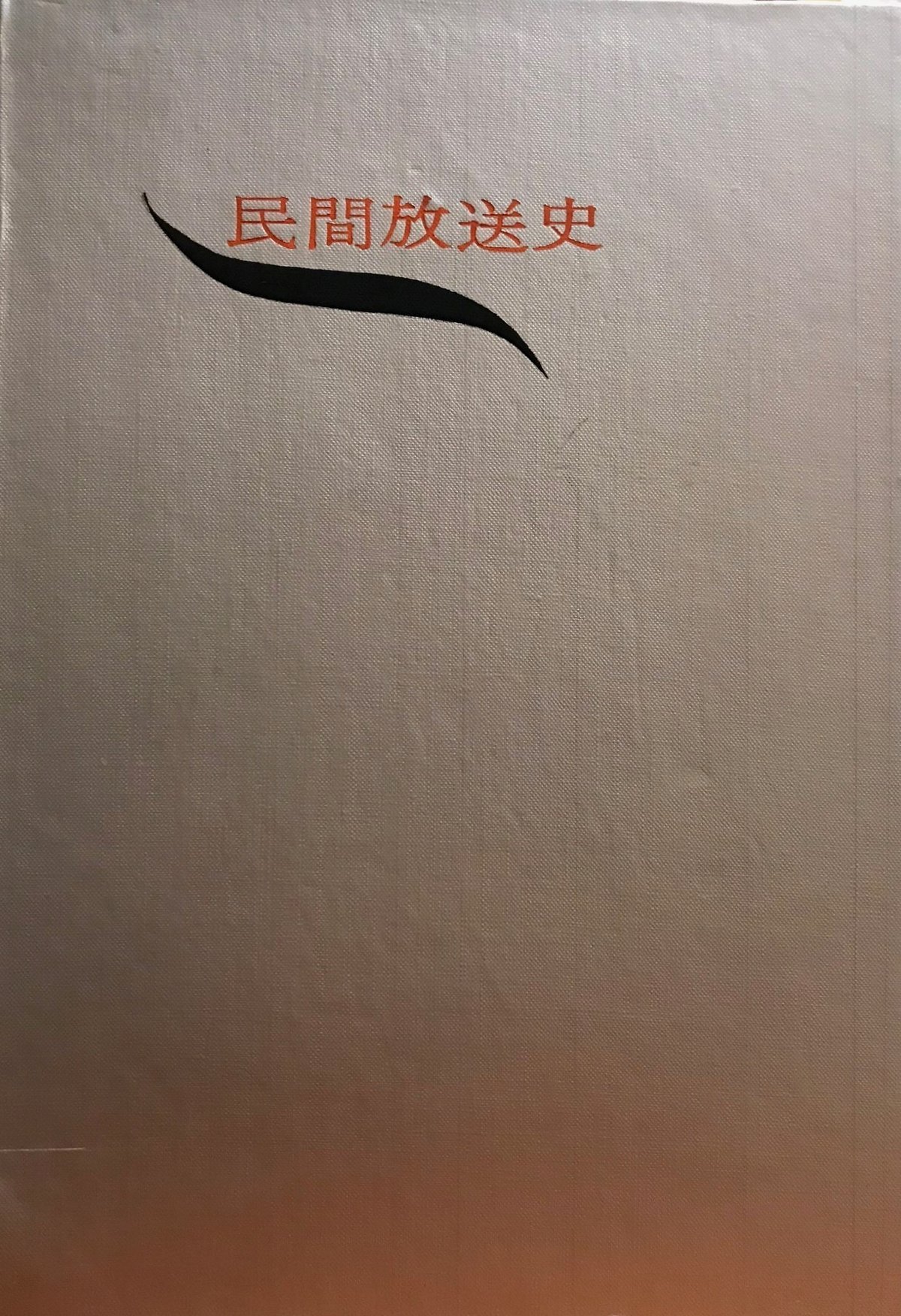
放送前日までにたった3日分しか番組のストックがない状態で、1日14時間余りの放送を開始した混沌のなかにあっても、制作番組のみならず「時報」に至るまで民放らしさを追求し、開局に挑んだ先達の想いの強さには尊敬するものがあります。
「われわれは明日、NHK島に敵前上陸する。北から南に日本列島をおおているNHKの電波の層は厚い。いやしくも水際で倒れるようなことがあってはならぬ。見事上陸して敵中深く進入しよう。」(※2)

当時、CBCの常務取締役であった小嶋源作は、開局前日全社員を前に檄を飛ばしています。そこに見え隠れするのは、小嶋自身の民放にかけた想いです。
「自らを商業放送のパイオニアを以て任じ、日本で最初の新しい電波媒体に対する大きな期待を胸に秘めて、未知への挑戦というロマンに生き、それに取り憑かれていたのではないだろうか」(※2)
開局前夜のドラマには、我々が時に忘れがちな放送/メディアの本質に触れることのできる思想が数多く詰まっています。「開局」へのハードルが下がった、規制が緩和され放送事業の参入も比較的容易になったといわれる状況ですが、それはあくまで物理的な側面にすぎないのです。
実は、放送局を「開局する」ということは、大きなイノベーションを起こし、新しいイデオロギーを構築することなのです。
だから、今になっても「開局」は、大変さが目に見える傍ら、なぜか「ワクワク」するものなのかも知れません。
※1「民間放送史」(中部日本放送編著/1959年)
※2「CBCとともに 小嶋源作遺稿集」(小嶋源作著/1990年/非売品)
※ヘッダー写真 くろてんさんによる写真ACからの写真
