
コーヒーと生成AI――現場で感じる未来のツール
コーヒーに携わる私たちは、日々「どう伝えるか」に頭を悩ませています。曖昧な表現ではなく、確かな経験則とエビデンスをもとに情報をお伝えすることを大切にしてきました。そんな中、最近注目しているのが「生成AI」です。ChatGPTのようなツールは、私たちの仕事に新しい可能性をもたらしてくれています。

経験とエビデンスで伝える大切さ
生産地、バリスタ、競技会、そしてコーヒーの最新トレンドについては、これまで自らの経験をもとにお伝えしてきました。しかし、いざ誰かに教えるとなると、どうしても表現が曖昧になってしまうことがありました。そこで、確かな根拠や具体的なエビデンスを示すことに努めています。そんな私にとって、生成AIは非常に心強いツールとなっています。たとえば、メールや告知文、PR文書の添削を依頼すれば、意図を伝えるだけでほぼゼロから文章を作成してくれるのです。
質問への回答力はずば抜けて優れてます。
先日「World Barista Championshipに出場して、勝ちたいです」とアドバイスを求めた際、生成AIからいただいた回答を画像で確認できるようにしましたが、その内容と応用力に感動しました。




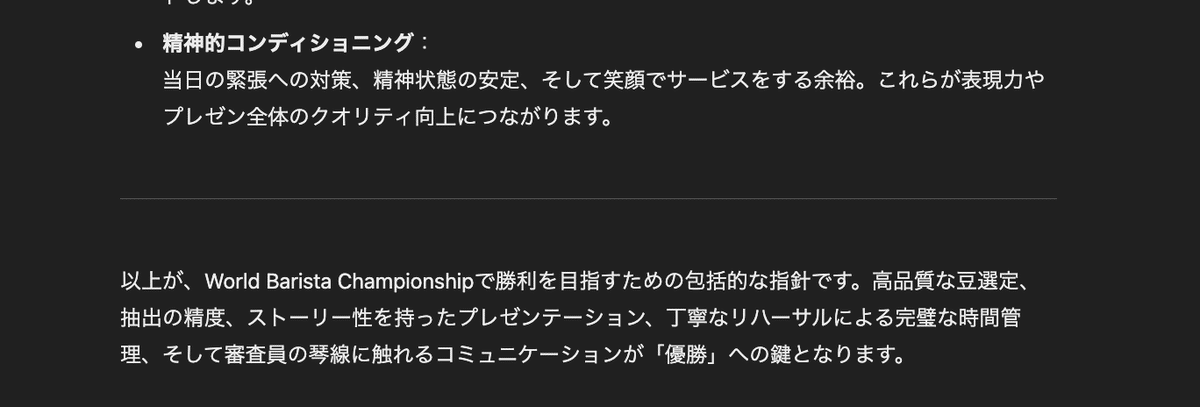
経験者であれば、かなり重要なポイントが列挙されており、初めて見るには十分な資料となりえることはわかるでしょう。
私なら「たしかに!これも伝える資料に入れよう!」という自分の教育における「抜け」や「漏れ」の網羅には、十分使えそうです。
生成AIの可能性とその活用方法
もちろん、生成AIはまだ完璧ではなく、関係者であれば上記のWBCの回答も、推論に基づく曖昧な回答や間違いが含まれることもあります。そのため、自らの経験値と、やはり内容について再調査/確認すること、そして、どの生成AIを使うかという選択も重要です。
市場にはさまざまなツールが存在しており、自分のニーズに合ったものを見極めることが必要です。
また、生成AIを最大限に活用するためには「質問力」が鍵となります。どんなに優れたツールでも、聞き方が不十分だと、期待している回答が得られません。私たちがコーヒーについて深く掘り下げた知識を持っているからこそ、生成AIから得られる情報の精度は格段に向上します。
ここで、生成AIを活用する際のポイントをまとめます。
ツール選び:自分のニーズにあった生成AIを選ぶことが大切です。私の1番のおすすめはChatGPTのPlus/ Proモード(ともに有料)ですが、無料で使える中国製のDeep seekなどもあります。FeloやGeminiなども非常に使えるツールです。詳細はまた別記事にします。
質問の仕方:具体的かつ、自分の専門知識を背景にした質問を心がけると、より的確な回答が得られます。違和感を感じたらそれを指摘し、再度、質問意図を明確にしましょう。「わかりやすく」「箇条書きで」「クリエイティブに」「ステップバイステップで」など、付け加えると、回答の内容がまったく変わります。これを「プロンプト」と言います。
検証の重要性:生成された情報に憶測や誤りがないか、自らの経験や知識でしっかり確認することが必要です。経験のない分野であればあるほど、鵜呑みにしないことが重要です。
実務への応用:メール、告知、PR文など、外部に発信する文章の質を向上させるために活用できます。
コーヒーの世界と生成AIが交わる未来
このように、生成AIは一見コーヒーの世界とは無関係に思えるかもしれませんが、実際には日々の業務の効率化や情報の質向上に大いに役立っています。大手チェーンの皆様などは、会社が推奨するマニュアル以外のことを学ぶ機会が少ないでしょうから、そういった多くの方々にとっても、生成AIの活用は新たな風を感じさせるものになるでしょう。
また、コーヒーマニアやファンの皆さんも、ぜひ自分の興味のあるキーワードで試してみてください。思わぬ発見や、新たな視点が得られるかもしれません。私自身、生成AIを上手く活用することで、これまで気づかなかった効率的な方法や、深い洞察を得ることができました。
先日、日経新聞でもこのような記事が掲載されていました。
生成AIが今後もさまざまな業界に与える影響について報じられています。これは、コーヒーの世界にとどまらず、あらゆる分野で大きな転換期を迎えていることを示しています。
まとめ
私たちが日々追求する「真の味」や「正確な情報」と、生成AIが提供する新たな視点は、一見別々のもののように感じられるかもしれません。しかし、どちらも「より良いものを提供する」という共通の目標に向かっています。曖昧な情報を排除し、確かなエビデンスに基づいた伝達が求められる現代において、生成AIは心強いパートナーとなるでしょう。
ぜひ皆さんも自分の得意分野から生成AIの活用を始めてみてください。新たな発見と、業務の効率化につながる大きな一歩が、そこにあるはずです。
