
変人類学序説①:はじめに

本稿でぼくは、みなさんを「変」をめぐる旅にご案内したいと考えている。いや、より正確にいうのなら、「変」をめぐる旅へご同伴願いたいと考えている。この旅は始まったばかりで、まだ目の前には深く霞がかかっているし、これから旅に出ようとする世界の地図がキレイに描けるようになるためには、まだもう少し時間がかかりそうだからだ。
ただ、この「変」をめぐる旅が、小さな気づきの連鎖を繰り返しながら、最終的には発想の転換や、これまで抱えてきた世界認識の変容や拡張を、少なからず生み出していくのではないかという期待感と確信のようなものがある。そのような旅である。みなさんはぜひぼくがウンウン唸りながら紡ぎ出した言葉の旅を傍目で捉えながら、次々とツッコミを入れながら、自身の足元を見直しながら、一緒に歩んでいって欲しいと願っている。あまりに馬鹿げていたら、サイトを閉じてしまって構わない。
とは言っても、この段階で何も伝えたいということがないというわけではない。ぼくのもつ確信について、少しだけ話させてほしい。
その一つに、「ぼくらはみんな、すべからく、変である」という前提がある。ともすれば「変人」という名の下に、他の人を侮蔑したり、もしくは崇敬の眼差しを向けたりということを、ぼくらはしてきた。また、他者から「変」「変人」であると言い放たれ、悲しくなったり嬉しくなったりしてきた。しかし、この営為は、どうやら間違っていたようだ。「変」「変人」は特定の人物だけが冠することのできるタイトルではないのだ。そう、ぼくらはみんな「変」なのである。全ての人間は、必ず「ズレ」を生じさせてしまうような、不完全で曖昧で、境界的な存在なのだ。この境界内的な存在もしくは現象として、「変」「変人」を扱おうというのが、本書の前提だ。このことをもって、本書のタイトルは「ホモ・ヘンデス」とした。ホモ・サピエンスは「賢い存在としての人間」、ホモ・エコノミクスは「経済的存在としての人間」、ホモ・ルーデンスは「遊ぶ存在としての人間」。そして、ホモ・ヘンデスは、「変である存在としての人間」ということである。もしくは「変であることを前提とした人間像」ともいえよう。
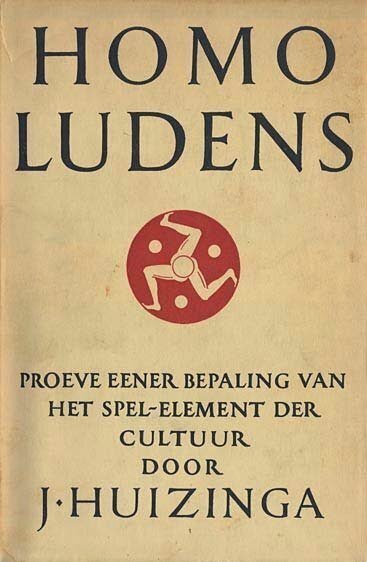
とはいっても、本稿は、「変(変人)とは何か」を明らかにするような、「変」を明確に定義するようなことはしない(「変」の非本質的特性)。ただ、「なぜ<変>が生まれるのか」を関係論的に捉え、社会的に構築されたものとしての「変」に込められた意味やそのメカニズムを読み解くことで、私たちが安易に陥ってしまう脆弱な「正しさ」や「常識」から少しでも自由になるための手続きを踏んでいきたいと考えている。少しずつ、着実に。
もし「変(変人)」になりたくないという人がいるとするならば、それはまずもって前提が間違っているのだ。繰り返すが、ぼくらは生まれてからこのかた、ずっと「変(変人)」だったのだ。そこで起こっていることは、「ズレを生じないよう(変にならないよう)に努力している」や「ズレていること(変な特質や状況)をひた隠しにしている」「ズレていないことを信じようとしている」「自分が<まとも>であることを確信するために、ズレている人や現象を排除している」だけのことだ。
本稿では、このような人々の努力やマインドセットが、社会を閉塞的・排除的なものにし、活力を失わせ、発想力を低下させ、創造性を奪い、他者に対する寛容性を減退させていることを突き止めたいと考えている。逆にいうと、自身が「変(変人)」であることを前提として引き受けていく環境(変人環境=Henvironment)は、社会を開放的なものにし、活力を復活させ、発想力・想像力を高め、社会をより包摂的(インクルーシブ)なものにしていく、ということだ。「変」が他者との関係でしか生み出されない現象ならば、そして誰もが「変」な特質を持っていて、「変」な現象(=「ヘーン現象」)を生み出す存在ならば、いっそのこと自他の「変」を愛そう。認め合おう。面白がろう。きっとぼくらが作り込んできた「変ではない」状況だって、ちょっとしたきっかけで「変」なものになってしまうのだから(文化とは常に恣意的なのだ)。
次の記事:変人類学序説②:「変」をめぐるイマージュ
