
京大・緊縛シンポの研究不正と学術的問題を告発します④吉岡洋氏報告について
本記事では、緊縛シンポ第2報告、吉岡洋氏「縄と蛇」について短く取り上げます。本記事で言いたいことは、シンポ登壇者の1人・吉岡洋氏は緊縛研究会のメンバーではなく、緊縛を研究したことはない、ということです。
1.吉岡洋氏報告「縄と蛇」について
第1報告のY氏・F氏報告は、先行文献を剽窃していたうえ、その文献が、アメリカの縄師によって書かれた正確ではない内容であり、学術的どころか、偽史を作り上げ流布させる、有害な報告であったと言えます。
第2報告の吉岡洋「縄と蛇」(広報されていた「現代アートとしての緊縛」から当日改題された)も、実は緊縛研究であったとは言えません。緊縛とは関係のない内容で、注連縄や蛇の話でした。内容だけみれば面白い話だったとは思いますが、なにせ緊縛と関係ないので、緊縛を学術的に研究したことにはなりません。本報告については内容よりむしろ、なぜ吉岡氏が報告をしたのか、という点を問題にしたいと思います。
緊縛シンポは、出口氏が2019年に立ち上げた緊縛研究会(当日は緊縛の哲学研究会と称されてもいた)の成果報告である、と説明され、登壇した研究者は全員研究会メンバーなのだろうと聴衆が理解するような紹介の仕方がされていました。ところが違いました。
吉岡氏はTwitterとブログをやっており、2020年11月12日のブログ記事「「緊縛」を縛るものは何か?」(最終閲覧日2021年1月10日)において、氏が緊縛シンポでの報告をすることになった経緯が書かれています。
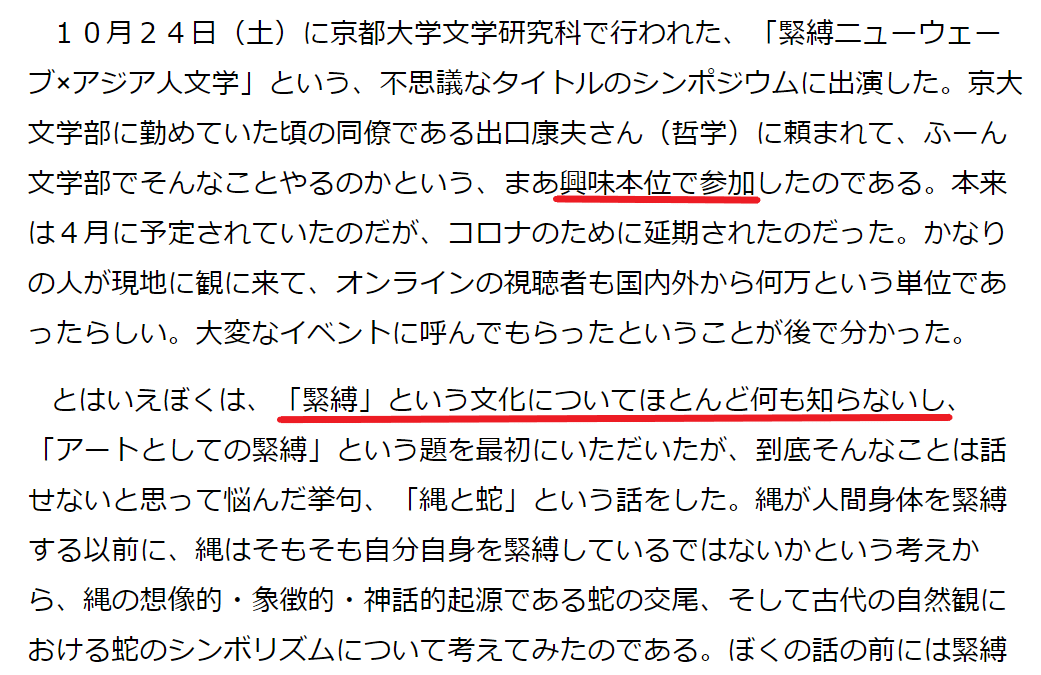
吉岡氏は、出口氏から頼まれて、シンポジウムに興味本位で参加したと述べています。そして、緊縛という文化については何も知らず、「アートとしての緊縛」というテーマでは話せないため、悩んだ挙句、論題を変更し蛇のシンボリズムについて話したということです。
つまり吉岡氏緊縛研究に関しては門外漢だったうえに、緊縛研究会のメンバーでさえなかったということです。
なぜ研究会メンバーに報告をさせず、まったくの門外漢に報告を依頼したのか、理解に苦しみます。以下は私の単なる邪推ですが、吉岡氏の「京都大学こころの未来研究センター教授」という肩書が必要だったのかもしれません。
しかし、研究そのものにとっては、肩書よりも内容の方が大切です。
今回、吉岡氏は、自分の知らないことについてうかつに話さない、という、ある意味での研究者の見識を示されたと思います。しかし、一般に、教授クラスの門外漢に緊縛についての講演を依頼すれば、結果として研究会の若手メンバーの成果を横取りするような形になった可能性もあったのではないかと想像します。
ただ、Y氏・F氏報告の内容が、1冊の、しかも研究書ではない一般書からの丸パクリだったことを考えると、そもそもこの緊縛研究会がきちんとした学術的研究活動をしていたのかかなり疑問ではあります。出口氏に後ろ暗いところがないのであれば、いつ、どこで、どのような活動をしたのか公表してほしいものです。
次の記事では、主催者である出口康夫氏の報告内容について検討します。
