
【振り返り】2024年2月
こんにちは。東です。
さて、2024年2月を振り返っていきます!
【臨床】今月の臨床
テーマ|わき腹の痛み
半年ぶりにお見えになられた患者さん。
以前から右肩の痛みを訴えていました。
今では指先までピリピリ痛むし、なんならヘバーデン結節で指先も腫れてきたという。
仕事が終わると無性にからだが痒くなる。
今日一番つらいのは、わき腹の痛み。
どうやら、背中からわき腹にかけて痛む。
息がなかなか吸えない。
かかりつけの医者に相談したところ、「それは心配だから大きい病院に行ってくれ」と自宅からほど近い総合病院へ行く。
レントゲンと血液検査。
膵臓と腎臓のトラブルを懸念しているとのこと。
1.胸脇苦満|きょうきょうくまん
鍼灸院ではこのように、病院で検査をした上で来院される患者さんはとても多いです。
この場合に鍼灸師の立場としてやらなければいけない事は、西洋医学的な検査は西洋医学に任せて、鍼灸の力を最も発揮できるように、東洋医学的に診察して、東洋医学的にアプローチをすることです。
この患者さんの症状は、脈診所見と腹診所見を判断材料として、肝気上逆による胸脇苦満と診定めました。
2.心下満|しんげまん
使用したツボは、足厥陰肝経の指先に位置する大敦穴(たいとんけつ)。
指先は井穴(せいけつ)と呼ばれるツボが並び、「心下満(しんげまん)」を主治するツボとされています。

とても古い『難経』という書物の中で、六十八難という所に出てくる主治法方になります。
治療後には、痛みもつっぱる感じもなくなっており、鍼灸治療ができない期間のケアとして、漢方薬を飲んでみることを提案。
連携医師兼漢方医を紹介して、お帰り頂きました。
めでたしめでたし。
【教育】東塾
腰痛の治療
今月は15,20日の2回やりました。
内容は「腰痛」です。
1.腰痛の物語 西洋篇
腰痛を一つとってみても、思索をめぐらすことが沢山あります。
まずは、現代医学でいうレッドフラッグ徴候があるかどうか。
あればすぐに病院へコンサルしないといけません。
次に、現代医学的な内臓疾患の潜在があるかどうか。
元より検査をしていたら、その情報を共有して頂きます。
直近で伺って頂けていたら情報の新鮮度が高いので、尚可、ですね。
鍼灸師は、整形外科医でもなければ内科医でもありません。
それでもこれは危ないのではないか、という危機感は常にもって鍼療に臨んでいます。
2.腰痛の物語 東洋篇
外気の変化
精神的な変化による循環物のよどみ
食事による循環物の変性
それを症状やこれまでの経過といった言葉による情報。
脈診や腹診といった手で診る診察や、面色や舌診といった目で診る診察、声色や言葉選びは耳で診て、体臭(からだの代謝状態)や香水の好みなどを鼻で診て、五感を駆使して情報収集します。
収集した情報から、今の患者さんのからだの状態は、いったいどのような日常生活から生じてきたのだろうか、と想像できるのか。
多くの病気は、変哲もない日常から生まれます。
震災や事故でもない限り、いきなり大きな病気になることはありません。
その患者さんの日常を、どれだけ想像できるか。
ここが臨床の生命線の一つかなと思っています。
【研究】医学史の講座①
テーマ|ナイチンゲールに学ぶ、東洋医学と西洋医学に共通する「普遍的ケア」とは?
知る人ぞ知る東郷俊宏先生による医学史の講座が始まりました。
第一回目は、『看護覚え書』を記したナイチンゲールです。
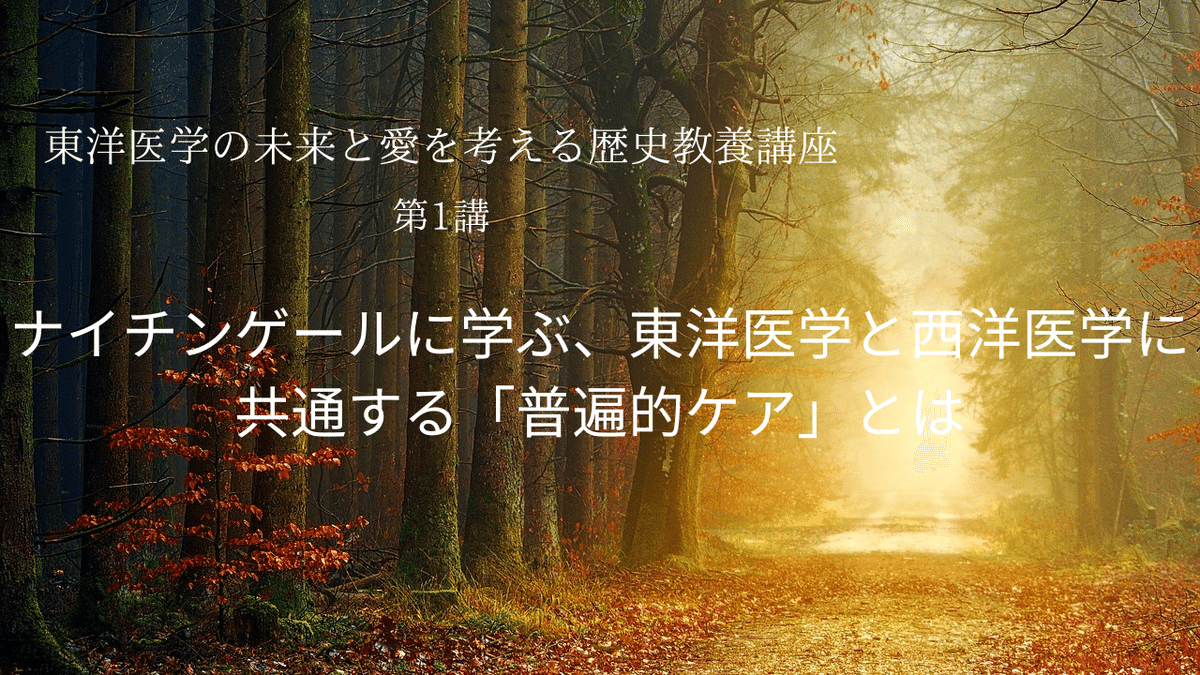
「白衣の天使」、「ランプの貴婦人」と呼ばれ、戦場で献身的な看護をしたと言われるナイチンゲールですが、その実際の顔は極めて実践的、合理的な思考を併せ持ち、今日のリハビリテーション医学の考えをもつ先見的な看護師でした。
そして西洋医学が「実験室の医学」へと傾いていく中で、東洋医学とも通じる生命観(自然治癒力)を持ち続けた人でした。また1859年に著した『看護覚え書』は、医の東西を問わず、「患者さん中心のケア」をする上で本質的な学びを与えてくれる名著です。
本講では19世紀の医学を振り返りながら、なぜナイチンゲール看護論が現代日本の医療、介護の世界で必要なのかをわかりやすく解き明かします。
1.東郷先生と私
私としては、なかなか感慨深いです。
私が2020年に東洋鍼灸専門学校で非常勤講師として、東洋医学の歴史を担当させて頂いた際に、東郷先生には近代医学の歴史について何度も会食のお時間を賜りながらご教示頂いた過去があります。
私にとっては医学史の師匠になります。
(東郷先生との会食の前には、できるだけクリティカルな質問ができるように、数十本の論文を読んでから臨んでいました)
(会食のつい先ほどまで、入念にキー論文を読んで新鮮な記憶で臨んでいる私ですが、東郷先生ははるか昔に読んだであろう論文の内容をまるで暗唱しているように淡々とお話していました)
(私は『あ、この話はこの論文の内容だ。あ、この話はあの論文の内容だ。へ~、そこがそう繋がるのですねっ!』みたいに、「門前の小僧」よろしく、耳学問をしながら医学史を学ばせて頂きました)
2.本講座への所感
ナイチンゲールの講座内容の詳細は、東郷先生の講座に参加してみて頂きたいのですが、私の率直な感想は二つ。
一つは、「大きな看護と小さな看護」の感覚
二つは、「東洋医学の現代語版」と思しき観察記録
「大きな看護と小さな看護」については、かつて記事にした「人類の普遍性と個人の千差万別さ」という感覚と似ているのかなと思いました。
▼みんな同じで、千差万別という価値観
人類に共通する治療室の環境づくりやスタッフが働きやすい環境づくり。
その上で患者個人を観察し、自然界の日内変動と個人の代謝サイクルの整合と、小さな彩(いろどり)の変化がもたらす治癒効果など、東洋医学の鍼灸師として学ぶことがたくさんありました。
3.日程
次回は3月17日(日)の21:00~22:30。
期間は、2024年2~12月の全10回。
毎月、第3週の日曜日の21:00~22:30までやっています。
中途参加でも、過去のアーカイブを視聴することができます。
興味が出た段階でご参加頂いても全く問題ありませんので、ぜひ申し込みしてみて下さい!
▼申し込み|歴史の講座
講座の詳細はこちらからも見られます。
「東洋医学の未来と愛を考える歴史教養講座」 第1講 「ナイチンゲールに学ぶ、東洋医学と西洋医学に共通する 「普遍的ケア」とは?」 を開催しました。 申込者、なんと80名(単発受講3名を含みます)! 主催者の私が一番信じられずにいます。 お...
Posted by Tosh Togo on Sunday, February 18, 2024
【連携】地域医療連携カンファレンス
鍼灸師が医療機関やケアサービス等と関係した症例の報告、及び検討を行っています。
概要
鍼灸師が臨床上経験した医療連携に関するカンファレンス。
医師を始めとした医療従事者らと症例についての意見を交わし交流を持つことで
①共通言語の学習
②それぞれの役割や専門性の学習
③鍼灸院の患者の抱え込みや疾患の見落としによるインシデントの予防
④地域での鍼灸院の役割の再定義
を目的として毎月行っている。
テーマ|10代 女性「心療内科と鍼灸治療を併用した頭痛・不安感・倦怠感・傾眠傾向の一症例」
今回は参加できなかったのが残念。
1.参加資格と日程
参加資格は、鍼灸を加えた地域医療連携・多職種連携に興味のある医師・コメディカル・介護・医療従事関係者、鍼灸師、及び学生です。
講座形態は、動画配信(ライブストリーミング配信)ですので、全国どこからでもご参加いただけます。
毎月、第2・月曜日の20:00に行っておりますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせ下さいませ!
▼申し込み|DAPA
▼DAPAカンファレンス
【開発】新作鍼
ふふふ。


▼木目金の鑱鍼
今回も読んで頂きありがとうございます。ISSEIDO noteでは、東洋医学に関わる「一齊堂の活動」や「研修の記録」を書いています。どんな人と会い、どんな体験をし、そこで何を感じたかを共有しています。臨床・教育・研究・開発・連携をするなかで感じた発見など、個人的な話もあります。
