
1月7日は七草粥の日 さくっと分かる七草粥の魅力3選
1月7日は何の日?
1(い)7(な)だから・・・
稲川淳二の日。
・・・ではありません。
(のっけからすべってますけど、それが何か?)
1月7日は『七草粥』を食べる日ですよ~。

だから何?
って・・・
『七草粥』って体には良さそうだけど
そんなに興味ないんですって方。
モッタイナイよ~。
体にも良いんですが
日本の伝統文化でもあり、
とっても縁起の良いものでもあるんです。
いつもはスルーしているそこのあなた。
今年はハードル下げまくってでも
お試し体験してみてはいかが?
それでは今日は
さくっと分かる七草粥の魅力をご紹介します。
七草粥の3つの魅力
1.七草粥は縁起が良い開運レシピであること
おせち料理にも意味があるように
七草にもちゃんと願いが込められているんです。

【春の七草に込められた意味】
■ せり:「競争に競り勝つ」の意味
■ なずな(ぺんぺん草):「なでて汚れを取り除く」
■ ごぎょう:人形を表し、仏のからだとされ縁起物
■ はこべら:「繁栄がはびこる」の意味
■ ほとけのざ:仏様が座っている座のような葉っぱ
■ すずな(かぶ):神を呼ぶ鈴に見立てられた
■ すずしろ(だいこん):「汚れのなき清白」の意味
7つ合わせると・・・
邪気を祓い
神や仏の力をお借りし
繫栄や勝利へと導いてくれる
という開運レシピという感じでしょうか。
例えれば
7つのボールを集めると願いが叶うみたいな?
(それは明らかに違う)

やっぱり新年になったばかりですし
運気アゲアゲでいきたいじゃないですか。
そんなときは
季節の縁起物を取り入れていくってのは
上昇気流に乗るための一つの策だと思います。
だから七草粥は良いんです。
さらに、身体にも良いことから
健康運もあげてくれるアイテムとも言えるんですよ。
2.七草粥が内臓ケアにピッタリ
7種はそれぞれ色々な効能をもっていて
主にこんな効果が言われています。

【春の七草の効果】
■ せり:食欲増進
■ なずな:解熱作用・利尿作用
■ ごぎょう:風邪予防
■ はこべら:ビタミンAが豊富で腹痛によいとされた。
■ ほとけのざ:食物繊維が豊富
■ すずな:消化促進、便秘解消。ビタミン豊富
■ すずしろ:消化を助け、風邪予防にも。
特に胃腸の働きを助けてくれる栄養素たちがたっぷりときた。
年末から年始にかけ
暴飲暴食が続くと胃腸が弱りますよね。
すると胃腸が熱をもって便秘になったり
消化機能が弱ったりもする。
こうなるのは時期的に仕方ないとして
今は弱った胃腸を助けてあげればいい。

そんなときにピッタリな奴らが勢ぞろいしています。
消化の良いお粥と組み合わせることろも憎い!
(お粥は消化が良いとはいえ、
よく噛まないと逆効果になるから要注意)
特に冬は寒さで生命力が落ちてしまうもの。
だからこそ、緑の野菜がもつ
ビタミンと芽吹きの生き生きとしたエネルギーを
体に取り入れることで
邪気を払い、元気を取り戻そうという
季節に合わせた日本人の智慧が
七草粥なんでしょうね。
何より、今みたいに
栄養素がどーのとかではなく
昔の人は
この時期に一番必要としているものを
体と感覚で自然と選び取ってこの形になった
というのがすごいことだな~と思います。
まさに智慧の結晶である七草粥。
3.子供に日本の伝統を伝えるチャンス
七草粥の習慣は
もともとは中国から来た風習で
3月3日の桃の節句
5月5日の端午の節句
7月7日の七夕
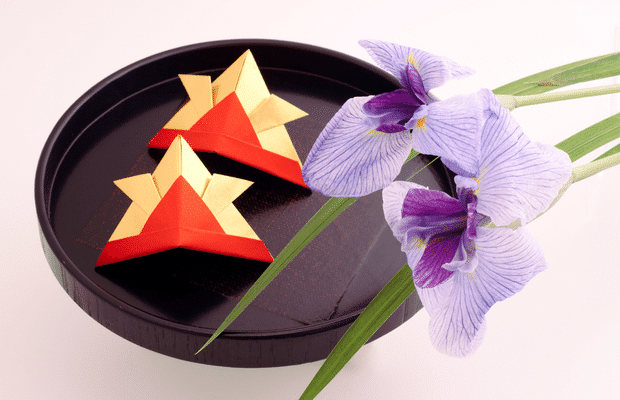
などと同じ節供の仲間。
中国の唐の時代に
1月7日は人日(じんじつ)の日と呼ばれ
7種類の若菜が入った汁ものを食べ、
無病息災を祈るという風習があったそうです。
(七種菜羹(ななしゅさいのかん)と言います)
それが日本に伝わるのですが
ただ伝わっただけじゃなく
日本の土着の文化と融合し
今の形になったというのがポイントです。
もともと日本には
・若菜摘み:年明けに若菜を食べる
・七種粥:7種類の穀物でおかゆを作る
という風習がありました。
ちょうどそれが中国から来た
1月7日の風習とがっちゃんこ。
そして無理なく
日本人に馴染む文化として
七草粥という風習が爆誕。

外からの文化を柔軟に受け入れ
日本ならではのものにして取り込む
日本人らしさが
こういうところからも感じ取れますよね。
そして日本人は自然そのものを神ととらえ
感謝や祈りというものを大切にしてきました。
七草粥も
その年の豊作と無病息災を願って食べる
祈りの気持ちがこもった大切な慣わしの一つ。
大切な大地の恵みであるお米と
自然界の恵みの青菜の組み合わせ。
七草粥を食べることで自然と
感謝の気持ちにもつながります。
こんなところからも七草粥を通して
子供たちに日本文化を伝える
チャンスではないか思います。

ただお粥にちょっと葉物を散らすだけでも
違うと思うんですよね。
口で説明するだけより、
目で見て、食べてみること。
体感するってことが大切なんだろうなと。
多少本物とは内容が違っても
絶対この方が伝わるし、心に残るはず。
日本の風習や文化をつなぐチャンスが
七草粥の日には待っていますよ。
ということで七草粥です。
食べましょう。
火曜金曜更新中
綺麗道こと古川綾子でした。
オリジナル マイ七草粥はこちらの記事で↓

冬におすすめ記事↓
◆カサカサ肌がかゆい・唇が荒れるのは【胃腸からの悲鳴】かもしれない。こんなサインに気を付けて!(1/7七草粥)
◆ずぼら薬膳的お餅の食べ方選手権。あたため・デトックス・美しさあなたはどれを選ぶ?
◆冬土用開運フード5選・季節の流れに乗った過ごし方で健康+開運を手に入れよう(1/17~2/3)
いいなと思ったら応援しよう!

