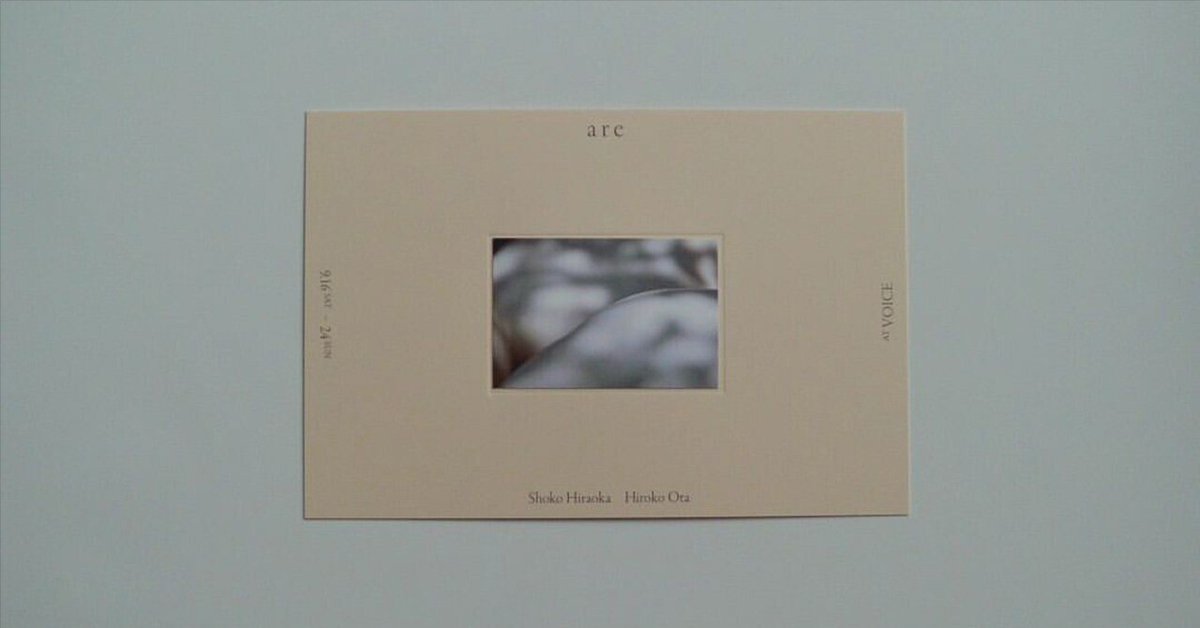
Behind what we are
写真家 平岡尚子と陶作家 太田浩子の出会いは2021年秋に遡る。平岡は、太田自身の「ニュートラルで潔い存在感」に、彼女のアトリエに置かれていた焼成過程半ばの、釉薬を用いない滑らかな陶に通じる魅力を感じたという。
〈質量〉として空間に存在する被写体と自分自身との三次元的・情緒的な関係性を、図像としてフィルムに留めることを目指している平岡。そして陶という物体を通じて、質量の軽重や流れを感じさせながらも、輪郭を持ち、かつそこから広がるものをつくる太田。媒体は違えども相通ずるもので繋がったふたりによる、約一年の歳月をかけた造形と撮影の交換を重ねる協働が始まった。
太田が制作する作品は、臍や尻など具体的な身体の部位を彷彿とさせるオブジェから、用途が明確なプロダクト寄りのものまでと幅広い。「釉薬を施した陶」というように主語述語の関係として物体が見えるのではなく、釉薬をも含めて「そのもの」としての実体感を目指す。とはいえ終始意識されるのは、不動の中にある動。たとえば「アイスクリームのもったりとした柔らかさに感じる重み」「落語家の軽やかな身体の動かし方」といった具体的なイメージがデフォルメされて、陶の表現に落とし込まれている。
しかし平岡が魅力を感じたのは、用途やイメージといった〈理(ことわり)〉から離れた裸の陶である。凹凸や気泡といった素材感が抑えられているため、平岡曰く、太田の作品は「写真におさめても動き続ける」。カメラをとおして捉えられた世界からは、観る者によってはミクロとマクロ、壮大と等身大、物語性と即物性といった両義性が垣間見えるかもしれない。この性質は天地左右を限定しない写真集の造本にも現れているだろう。しかも陶作品の全体ではなく、あくまで表面や接面の接写、陰影を捉えたものがほとんどである。
いわゆる「物撮り」を写真家に期待する陶作家としては、想像の斜め上を行く事態である。太田の中には、平岡の姿勢を理解しようとする気持ちと、全体を撮らせたいという欲とのせめぎ合いがあったという。そして思わず「接写される陶の表面に嫉妬してしまった」と述懐する。
対話を重ねながら方向性を掴んでは見失い、再び掴む過程を繰り返した結果、太田はさらに原初的な「丸い物体」を追求するようになる。自然に生じたかのように存在する物体を作りたいという思いから制作は進められた。
あまりの単純さゆえ、造形の加減によっては自然な存在としての物体から離れる要素となり得る。「何か」を意識した瞬間にその存在が〈理〉として浮かびあがる。ましてや釉薬を用いない焼成は修正が効かない。こういった葛藤と対峙しながらも太田は次第に、これこそが自身の原初的な制作動機であることに気づく。
これが、平岡も当初から直観していた太田の魅力だったのだろう。人間の皮膚のように写真としておさめられる自作に、もはや被写体が陶である必然性すら疑う瞬間もあったという太田の傍らで、平岡は接写を貫き通した。部分を撮りながら全体を捉える - 太田の作品はそれが実現できる。「そこにあるだけで美しい」平岡はそう繰り返し伝え続けた。〈理〉から離れて存在する太田の作品でないと捉えられないものがある、とも。
かねてより平岡は自身の制作ステートメントで「質量」という言葉を用いているが、質量をもってそれぞれが存在する事実をまっとうしなければ、世界には距離すら発生しない。一連の作品は、その事実をしかと感じさせる。
戸惑い揺らぎながらも造形を変化させていった太田、そんな彼女をやわらかく見守りながらも頑なに直観を信じ、シャッターをおろし続けた平岡。陶という物体、写真という図像、それぞれの〈ことば〉によって同じ実体をとらえ、為された対話をとおして築かれた関係。互いの輪郭を押し返しあいながら、作品に昇華していった過程がここにあらわれている。
9月16日〜24日にVOICEにて、これまでも作品について寄稿文を書かせていただいた写真家の平岡尚子さん、陶作家の太田浩子さんの作品展「are」が開催されます。本展示に寄せて、お二人への取材をもとに構成したテキストの日本語・英訳文が会場内にて掲示・配布されています。
「 are 」
PHOTO & OBJECT EXHIBITION
平岡尚子 (写真家) 太田浩子(陶作家)
@hiraoka.shoko @hiroko_utouto
会期 | 2023年9月16日~24日
会場 | VOICE
住所 | 東京都渋谷区神宮前3-7-11
開館時間 | 13:00~18:00
*休館日 | 9月19日
@voice_flower.jp
写真家 平岡尚子
多摩美術大学環境デザイン学科を卒業後、写真家上田義彦に師事。2020年独立。存在するすべての現象を被写体に、空間と質量の関係性を写真・映像表現を通じて捉えている。
平岡さんは2022年初春に開催された展示会「matters」でもテキストを寄せています。こうやってある表現者の定点観測を言葉をとおしてできるのは有り難いです。
陶作家 太田浩子
多摩美術大学工芸学科を卒業。2019年京都にて初個展を開催。
身体をモチーフにささやかな起伏を捉え、柔らかさや流れをもった陶のオブジェを制作。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
