
3人の「ふみ」プラス1
今回も別ブログなどで既出の記事をアップデートして掲載する「蔵出し」です。
旭川で2度暮らした日本を代表する歌人、齊藤史(さいとう・ふみ)については、これまで2本の記事を掲載していますが、今回も彼女の関連です。
旭川の文化史を調べていると、たくさんの「ふみ」に出会うというお話です。
********************
◆ 歌人の「ふみ」

写真1 齋藤史(1909-2002・17歳のころ・齋藤宣彦氏蔵)
最初に登場する「ふみ」は、その齋藤史です。
ご紹介していますように、旭川には、父親で軍人歌人と呼ばれた瀏(りゅう)の転勤に伴い、小学生時代と女学校卒業後の2度、暮らしました。
そして2度目の旭川滞在中、瀏を尋ねてきた歌人、若山牧水に作歌を勧められ、それが、彼女の将来を決めるきっかけとなりました。
その史は、歌だけではなく様々な随筆も残しています。
その語るように平明で、しかも背筋はしっかり伸びた文体には、いつ接しても新鮮な感動を覚えます。
次に紹介するのは、旭川で経験した大正の終わりの時期について書いた文章です。
「十二月に入ると、いよいよ北海道らしい激しい吹雪がつづいた。日がな一日絶え間なく降る雪の窓をうつ音は、眠りの際までも耳につき、時に浅い夢の中にまでひびいた。(中略)
土地に生れ育った人々が、落ち付きはらって冬に籠り、当り前の事として毎日の雪を眺め、平気に凌いで行くのが羨ましかった。(中略)
折から、大正天皇御不例の報が、しきりにきこえて、伝導の仕どころの無い毎日の屈んだ心の中に、かなしく積ってゆくのであった。
神去りました知らせを受けた夜は、殊に寒く、絶えず父の勤めさきから、かかる電話を待って、誰も寝るどころではなく、膝をかたく黙りあって座って居た。馬橇の鈴の音ひとつ聞えない、くらい夜であった。
(齋藤史 散文集「春寒記(しゅんかんき)」から「師走の思い出」より)
いかがでしょうか。
大正の終わりの日は12月の押し迫った時期でした(なので昭和元年はわずか7日間しかありません)。
その緊迫した雰囲気が伝わってくる名文です。
なお彼女の関連本で「ひたくれなゐに生きて」という本があります。
俵万智(たわら・まち)ら3人の女性歌人が、先達である史にインタビューした対談本です。
これも「ふみ節」ともいえる彼女独特の「語り」の魅力がつまった本です。

写真2 晩年の史(「原型 2003年4月 齋藤史追悼号」より)
一方、本人が実際に話している様子は、公開されているNHKのアーカイブス映像で見ることが出来ます。
魅力いっぱいの「ふみ節」を、肉声で味わうことができます。
◆ 作家の「ふみ」と詩人の「ふみ」、そして尾崎翠

写真3 林芙美子(1903-1951・「林芙美子全集」より)
続いて紹介する2人目の「ふみ」は、「放浪記」で知られる作家の林芙美子(はやし・ふみこ)です。
あまり知られていませんが、齋藤史と林芙美子は親しい間柄でした。
齋藤史の随筆には、戦時中、長野に疎開していた林芙美子が当地での様子を史に伝えたことが書かれています。
「そのような中で、林芙美子はご主人の関係で早めに、信州角間温泉に移り、時々東京へあらわれる。お手伝いさんが、お湯の出る便利さに、「温泉は、だれが沸かしているのでございますか―」と聞いた話や、「鶏一羽ぶら下げてくれば、どこの家でも喜んで泊めてくれるよ―」といって、わたくしたちをうらやましがらせた」(齋藤史「遠景近景」収録「林芙美子のこと」より)
空襲がさらに激しさを増したため、昭和20年3月、史は、父の故郷であり、芙美子がひと足早く過ごしていた長野に一家で疎開します。
あくまで推測ですが、一刻も早く東京を引き払うよう芙美子が強く史に勧めたのではないかと思われます。
下関生まれで、生まれながらの放浪生活から這い上がってきた林芙美子と、東京生まれで、職業軍人の一人娘である史。
生まれ育った環境は全く違いますが、お互いさっぱりとした気性だったことで、ウマが合ったのかもしれません。

写真4 林芙美子の来旭を伝える記事(昭和9年6月3日・旭川新聞)
その林芙美子は、昭和9年6月、旭川を訪れています。
写真はその時の新聞記事です。
「旭橋に驚嘆」、「アイヌ部落で子熊欲しがる」、「林芙美子さんぶらり来旭」などと書かれています。
実は、5月から6月にかけての北海道・樺太旅行の合間を見て、芙美子は旭川にいた旧友を訪ねたのです。
それがこちら・・・。

写真5 林芙美子と松下夫妻(旭川新聞より)
柱にもたれているのが林芙美子です。
子供を抱いているのが芙美子の友人で、3人目の「ふみ」こと、松下文子(まつした・ふみこ)です(間にいるのは、文子の夫で、林学博士の眞幸)。
松下文子は旭川出身。
東京に出て日本女子大学に通いましたが、そのときに寮の同室だったのが、のちに小説家となる尾崎翠(おざき・みどり)でした。
翠は、モダニズム小説の傑作とされる「第七官界彷徨」などで知られています。
その後、それぞれの事情から大学をやめた2人は、一時期、東京のアパートで同居します。
その頃、2人と知り合ってアパートをよく訪ねてきていたのが、まだ無名だった林芙美子でした。
その後、松下文子は結婚し、ドイツに留学した夫に同行。
2年後、帰国して旭川に住みます。
文子の結婚後も芙美子、翠との友情は変わらず、芙美子が初めての著書である詩集を出版するとき、その費用を文子が工面しました。
芙美子は自伝の中で文子の名をあげ、「この人の友情がなかったら、自分は本を出版できなかった」と書いています。
また健康を害し、故郷の鳥取に戻って創作活動から離れた翠とも、生涯、親友であり続けました。

写真6 尾崎翠(1896−1971・「尾崎翠全集」より)
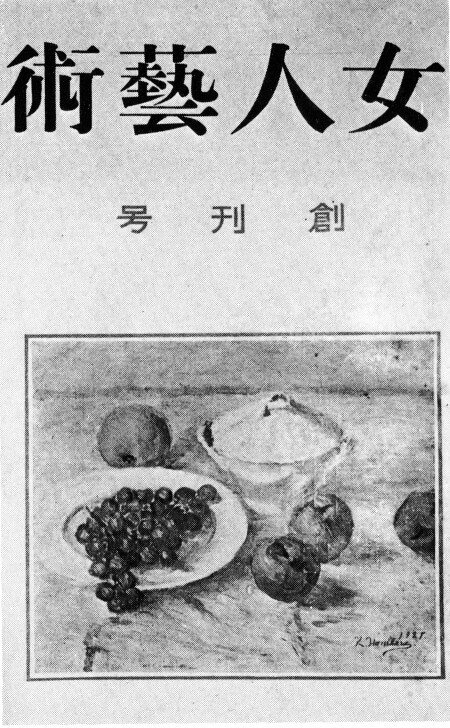
写真7 「女人芸術」創刊号(昭和3年)
なお松下文子も当時から詩を書いており、芙美子、翠とともに小説家の長谷川時雨(はせがわ・しぐれ)が主催していた雑誌「女人芸術」に作品を発表しています。
また故郷旭川でも地元の詩誌に寄稿するなど、創作を続けました。
旭川の詩人、東延江(あずま・のぶえ)さんの著書「続・旭川詩壇史」に彼女の詩が掲載されていますので紹介します。
暮春の圓 松下文子
春の夕まぐれ
水仙は地上に
黄珠を連ね
桃花 遥におぼろなり
風なく 音なく
暮色 若色ゆ立ち上る
突如
軍鶏 一羽
血ぶるひ立ちて
雄姿を運ぶ。徐に。
あゝ その下に
碎くる 珠花の片々

写真8 尾崎翠と松下文子(「尾崎翠 モダンガアルの偏愛」より)
◆ プラス1=社会活動家の「ふみ」

写真9 佐野文子(1893-1978)
せっかくのですので、紹介した3人との接点は確認できませんが、もう一人の「ふみ」についても紹介しておきましょう。
戦前から戦後にかけての旭川で、社会活動家として大きな実績を上げたクリスチャン、佐野文子(さの・ふみこ)です。
彼女は、1893(明治26)年、島根県の熱心なキリスト教信者の家に生まれた女性です。
1909(明治42)年、旭川で病院を経営していた義理の兄を頼って家族で北海道に移住、文子は小学校教諭となります。
ほどなく地元の実業家、佐野啓次郎(さの・けいじろう)と結婚しますが、9年後に夫は病死。
これをきっかけに彼女はさまざまな社会活動に身を捧げるようになります。
文子がまず取り組んだのが、働く女性への支援です。
同志とともに託児所の設置活動を始め、1924(大正13)年、旭川初の託児施設、旭川愛児園が誕生します。
次いで取り組んだのが遊郭で働く女性=娼妓(しょうぎ)を救う廃娼運動です。
旭川に曙(あけぼの)遊郭が置かれたのは1898(明治31)年。
9年後、これとは別に、陸軍第七師団の近郊に中島(なかじま)遊郭が設置されます。
文子はこれらの遊郭の敷地内に単身乗り込み、ビラをまくなどして活動の存在を知らせるとともに、実際に娼妓を逃れさせるなどの支援に奮闘しました。
時には遊郭の用心棒に刃物を突き付けられることもありましたが、文子はひるまず、彼女の支援を受けて廃業した女性は10人を超えるとされます。

写真10 旭川中島遊郭(絵葉書)
旭川の歴史を見ていきますと、石川啄木、金田一京助、若山牧水など、別々の時期に旭川の地に足跡を残した人が、実は密接な関係にあったことが分かるなど、思わず、「へーそうなんだ」と思うことがあります(啄木と金田一、啄木と牧水はそれぞれ友人で、いずれも旭川を訪れています)。
旭川という土地の奥深さを感じるのは、そうした時です。
