
第69回 ACE Tokyo Meetup イベントレポート
本記事はアトラシアン公式ブログからの転載です。
みなさん、こんにちは。アトラシアンでコミュニティマーケティングを担当している新村です。今回は1月23日に開催された第69回 ACE Tokyo Meetupの様子をレポートしたいと思います。ACE Tokyoはアトラシアンの公式コミュニティで東京を中心に活動しています。今回から分科会形式での開催となり、初回はAdmin分科会ということで、管理者の視点からJira Service ManagementとConfluenceを導入し、全社展開していくまでのお話をフリー株式会社の稲村さんに紹介いただきました。
リーダーからの乾杯とACE Tokyoの紹介からスタート!

今回が初めてのAdmin分科会ということで、ACE Tokyoのリーダーであり、Admin分科会のリーダーである高橋さんから乾杯の挨拶とACE Tokyoの紹介がありました。ACE Tokyo Meetupはまず乾杯から始まるカジュアルなイベントです。各々、フード&ドリンク スポンサーのリックソフトさんから提供された飲み物を側に置きながら、高橋さんからの説明を聞いていました。

管理者必見!Confluence/JSM 全社導入展開、ナレッジマネジメント成功の秘訣 〜freee社の事例〜
フリー株式会社 稲村さん

今回は複数のセッションを設けずに、フリー株式会社の稲村さんからナレッジマネジメントの観点でConfluenceとJSMの全社導入を行なった際の一連の流れと、苦労話や工夫した点をじっくりと紹介いただきました。下記に講演のサマリーを紹介します。
フリーでCulture IT部というチームを率いています。Culture Infraというチームではナレッジマネジメントの強化に取り組んでいて、Corporate ITチームではネットワークやデバイス、アカウントの管理などのITインフラを担っていますが、共通して「良いツールを入れて、良いルールを決めて、会社のカルチャーを強くしていく」ということを大事にしています。加えて、一般的に求められる「安心・安全・安定」だけではなく、「freeeらしいアソビゴゴロ」も大事にしています。
現在はJiraとConfluenceとJira Service Management(以下JSM)を利用していますが、今回はこの中でConfluenceとJSMを全社導入する際の検討の話と、導入後の浸透の話をしたいと思います。
JSMの導入
フリーの社員数はここ数年急速に成長しており、2022年以降に入社した社員が70%以上を占めるような状態です。そういった状況で情報共有をしっかりできるようにするという課題がありました。そこで、2022年の11月にaskAnyという社内問い合わせの一次受け窓口を構築し、「誰に聞いたら良いかの解決」、「たらい回しの撲滅」、「ナレッジベースの整備」の実現を目指しました。最初は問い合わせ窓口をMeta社のWorkplaceで、ナレッジ管理をスプレットシートでクイックに構築しましたが、そもそもの目的が違うツールで構築してしまったので、3ヶ月程度で限界に達し、次の一手として検討の対象となったのがJSMでした。JSMを選択した理由はライセンス費用がエージェント分しかかからないこと、すでに一部で使用されていたConfluenceと親和性が高かったからです。
導入が決まってから、まずはaskAnyの窓口とITヘルプデスクのポータルをJSMで構築しました。ポータルは既存の問い合わせ内容やGoogle Formなどに設けていた申請フォームから検討・移行し、初期設定を行いました。そして、既存のWorkplaceなどのチャンネルは閉じ、問い合わせ窓口をJSMに一本化しました。また、スプレットシートに蓄積していたナレッジはConfluenceに移行しました。
Confluenceの全社導入に向けての動き出し
2023年の後半には、CSIRTや経理チームがJSMを利用し始め、その後ビジネス部門で問い合わせを受けるようなチームもJSMの利用を開始し、社内でJSMの利用が拡大し始めました。それに伴い、Confluenceの利用も徐々に増加してきました。
一方でこの時期、ナレッジマネジメントの領域ではまだ各部門が自分たちの使いやすいITツールを選択しており、社内で利用しているツールが事業部で異なる状態でした。そのような状態で「コミュニケーションツールの分断は、人の分断になる」という思いを抱えており、WorkplaceからSlackへの統合も進めていたところに、社長から「ツールは統一していくべき」という掛け声もあり、Confluenceの全社導入に向けて動き出すことになりました。そんなタイミングでACE Tokyoのリーダーの高橋さんに声をかけ、いろいろと教えてもらうことができたことも非常に有益でした。
Confluenceの導入決定後
2024年の前半にはConfluenceの全社導入を短期間に進めていきました。パイロットチームが立ち上がり、先行利用の進んでいた開発組織には1月から本格導入を開始し、さらに3月には全社員分のアカウントを発行しました。この時点では、使えるけど、使いこなしてはいないという状態でした。
4月にはCulture Infraチームでナレッジマネジメント専任の担当者を採用して、利用部門と一緒になって積極的活用とナレッジの整理を実施していくスピードが上がりました。その後、2024年後半には全社のOKRにナレッジマネジメントが含まれることとなり、全社員がツールを使いながら、ナレッジマネジメントを実践するフェーズに移行してきています。
全社への浸透
JSMの浸透にあたっては、問い合わせをしてもらう観点からは古い窓口を閉鎖し、JSMに一本化することが必須でした。また、さまざまなチームにポータルを作ってもらってナレッジマネジメントを確立していくにあたっては、Culture Infraチームのメンバーがそれぞれの組織に出向いてナレッジの整理などの作業を代行するといったことを行いました。
また、「JSMを導入する→askがデータで可視化される→必要なナレッジを整備する→ナレッジの閲覧件数の上昇とともに自己解決率が高まり、askが減少する」というサイクルに「askAnyモデル」と名付けて、さらにJSM導入の手法をパッケージ化することで、それぞれのチームでの導入のハードルを下げることができました。
Confluenceの浸透にあたっては、Slack全社統合で得た経験から、もはや規模的に「全社で同じやり方」は通用しないという点を前提に進めています。
組織ごとに業務もカルチャーも異なるため、活用の仕方も異なれば、あるべき浸透のさせ方も異なります。組織のキーパーソンが各チームのルールやガイドラインを自律的に整備しているところもありますが、基本的には「やらされる」というムードにならないよう、導入することによって得られる恩恵を丁寧に説明したり、場合によってはそのチームに入り込んで一緒に積極的活用とナレッジ整理を行なっていくということもしました。
まとめ
ツールの導入はスモールスタートで実績をつくり、モデル化を行なってから全社展開へと移っていくのが鍵だと思います。ただし、ツールの導入そのものをゴールとするのではなく、「良いツール・ルールと当たり前にツールが使われるカルチャー作り」を目的に、導入から活用展開を行っています。
また、浸透させていくためには従業員に対する理解が不可欠です。単にツールを届けるのではなく、相手のメリットを説明し、最大限のサポートを行なっていくことが必要だと思います。

(追記)当日の発表資料も公開いただきました。
2回目の乾杯と懇親会
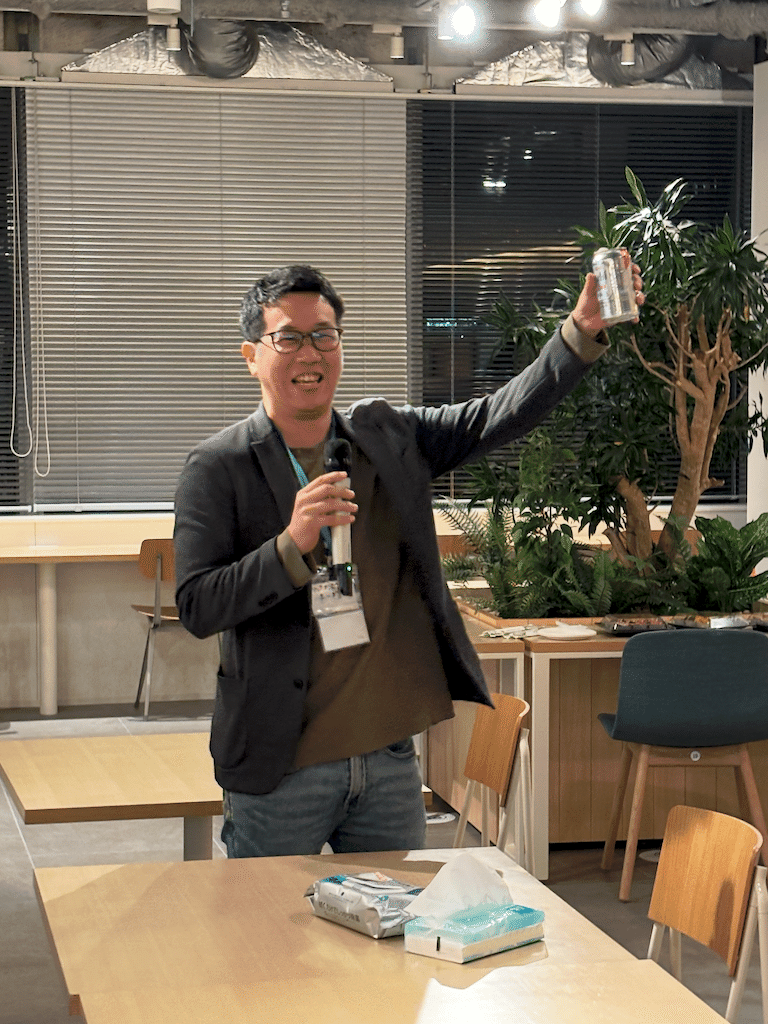
乾杯のご挨拶はドリンク&フードスポンサーをしていただいたリックソフトの大薗さんです。今回もたくさんのドリンクと美味しいフードを提供いただきありがとうございました。
懇親会でも議論の熱量が高く、あちこちで議論の輪ができていました。今回のテーマはみなさんが抱えている課題と同じような話だったようで、セッション中も首を縦に振られている方が非常に多かったです。そのままの勢いで懇親会となったので、議論の方もかなり盛り上がっていました。
最後は恒例の集合写真です。今回もたくさんの方にご参加いただきました。また次回も3月の開催を予定しています。決まり次第ご案内しますので、ACE Tokyoへの会員登録をぜひお願いします!

なお、当日はライブQ&Aを予定していましたが、事例セッションが盛り上がりすぎて実施することができませんでした。そのフォローアップとして頂いた質問への回答をするイベントを2月20日にオンラインで開催いたします。ぜひ、ご参加ください。
