
大河べらぼう/何故蔦屋重三郎が主人公なのか?
2025年1月からNHKで放映される大河ドラマ「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)〜」
主人公は、蔦屋重三郎という歴史上の人物。
「…誰?」
と思う方も少なくないはず。
蔦屋重三郎こと蔦重は、葛飾北斎、喜多川歌麿、東洲斎写楽など…世界的に有名な浮世絵師を発見し世に送り出してきた、江戸の浮世絵プロデューサーです。
文化・芸術の発展に大きく貢献した出版業者であり、浮世絵、黄表紙、洒落本などの出版を手がけ、後の日本文化に深い影響を与えました。
表舞台にはなかなか出てこない、江戸サブカル界隈のフィクサーといったところでしょうか。
しかしながら、大河ドラマなのに、大きな戦もない時代の彼が、なぜ主人公なのか?
そう思いませんか?
その理由を深掘りしていく中で、「令和の世」と「江戸後期(化政文化)」の多くの共通点に気付かされました。
答えは蔦重の人生にあります。
早速紐解いていきましょう。
ちなみに、「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺〜」の概要については、以前まとめた記事がありますので、興味のある方はぜひ読んでいただけると嬉しいです。
生まれと幼少期
蔦重は寛延3年(1750)に、江戸郊外にある吉原(現在の東京都江東区)の貧しい庶民の子に生まれました。
7歳で両親が離婚。
吉原で水商売を営み盛業だった親戚に引き取られて、引手茶屋(遊客を遊女屋に案内する茶屋)の養子になりました。
その後は、本屋(貸本屋)を経て、出版業を始めました。
吉原は愛欲の街。
「女を描けば右に出るものなし」と言われる喜多川歌麿を見出す素養は、幼少期から培われていたのですね。

蔦重・前半生の時代背景
蔦重が生きた時代は、現代・令和の世と共通点がたくさんあります。
江戸幕府の武士・田沼意次(渡辺謙)が政治の実権を握り、特大好景気で身分の上から下まで贅沢三昧!
利権をめぐって役人と商人との癒着が顕著となり、ワイロが日常化して社会的風潮にさえなった拝金主義全盛期でした。

今で言うバブルってやつですね。
一方、地方では火山の大爆発や大地震、大水害、そして「天明の大飢饉」が発生。
農政の不在により農村の荒廃がすすみ、地方の貧しい農家たちは次々に村を離れて都市の下層社会に流入…。
国民の幕府に対する不満はどんどん高まり、都市の社会秩序も大きく揺さぶられていきました。
さらに地方に残った農民は、打ちこわしや百姓一揆を全国で起こし、幕府の危機が訪れていた時期でもありました。
あれ…なんかこの感じ、今の日本に似てると思いませんか?
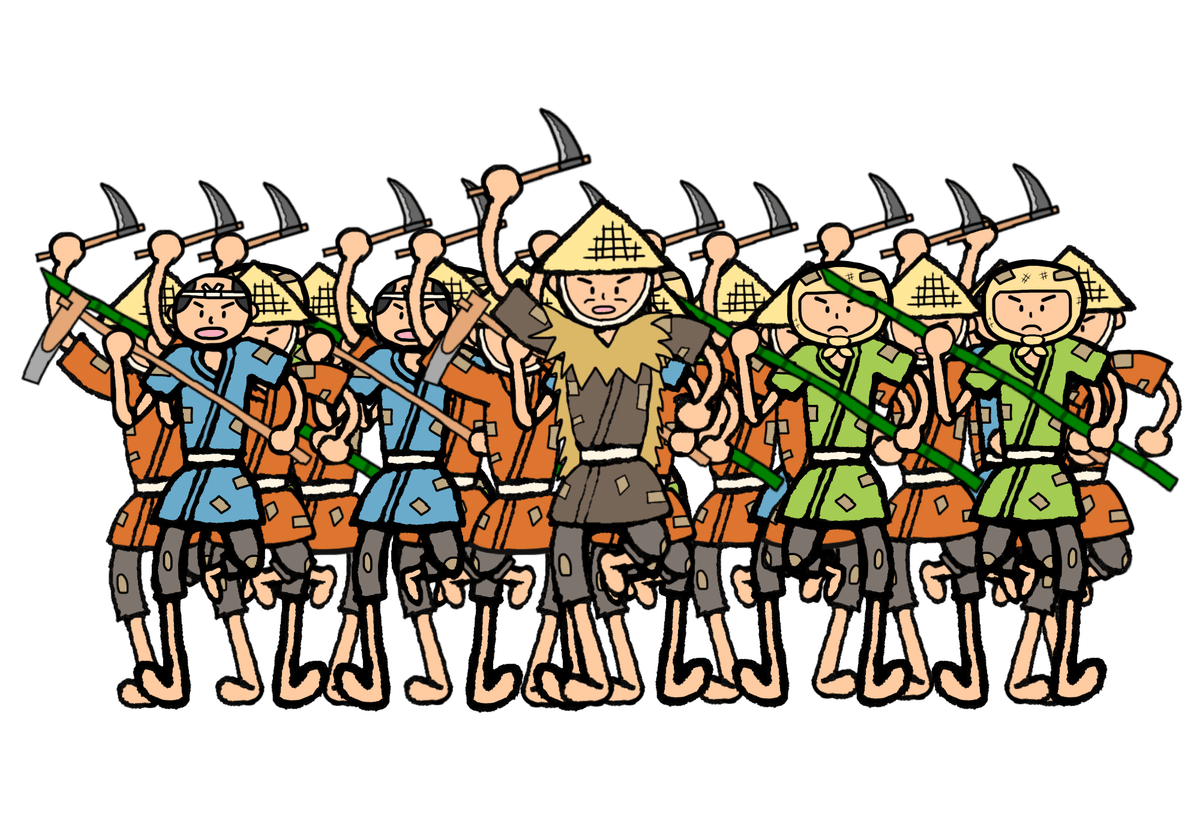
出版で頭角を表してきた蔦重
そんな右肩下がりのご時世に、のうのうと本を売っているだけではとても成功できそうにない…そんな状況に追い詰められた蔦重。
そこで蔦重は、浮世絵師や戯作者に目をつけました。
当時、本の小さな挿絵程度でしか活かすことができなかった浮世絵を、大きな一枚の紙に堂々と刷り、まるで絵画やブロマイドのように売ることに成功したのです。

さらに浮世絵師たち自体を、大ヒット作家として世に輩出しました。
喜多川歌麿に東洲斎写楽。
世に出る前の曲亭馬琴に十返舎一九、葛飾北斎たちも蔦重のお世話になっています。

蔦重・後半生の時代背景
時代は、絵師や出版業界にとって喜ばしくない状況に陥っていきました。
田沼意次の贅沢政策は崩壊していき、この難局を打開するため、白河藩(現在の福島県あたり)の松平定信が、将軍・徳川家斉から強力な推薦を受けて政治の中核を担うことになりました。
ここがめちゃくちゃ重要ポイント。
松平定信の寛政の改革が始まります。

これがクリエイターにとって非常に厄介な政策でした。
何をやったか簡潔にまとめますと…
とにかく超節約(倹約令)
Uターンに力を入れて農業再生(農村政策)
防災に力を入れるため備蓄米を制定(都市制作)
…現代の日本とおんなじ政策?
倹約令が化政文化へ転換のきっかけに
この倹約令というのが、江戸の文化に大きな影響を与えました。
倹約令を簡単にいうと…
とにかく贅沢するな。質素に暮らせ。
ってことです。
田沼意次の商業主義で華やかな江戸文化が花開いた反動から、華美な風俗や文化にに極めて厳しい弾圧を行いました。
特に出版への締め付けは厳しく、黄表紙(きびょうし:政治を滑稽に風刺した絵入りの小説)、洒落本(しゃれぼん:当時の粋な遊びを題材にした短編集)はすべて発行禁止。
さらに朱子学以外の学問を禁止する思想統制までスタート。
こうした文化・学問への弾圧は、庶民の楽しみや知的好奇心まで奪ってしまいました。
この倹約令をきっかけに華美で贅沢な文化は次第に、質素で粋な文化に移り変わっていったのです。
これが化政文化の始まりです。

蔦重の最後
寛政の改革時に、これらの本や浮世絵を出版した蔦重は、財産の半分を没収されました。
その6年後48歳で亡くなってしまいます。
まとめ
いかがでしたか?
蔦重の人生と時代背景を、現代と比べてみると、多くの点が共通していることがわかりました。
蔦重の人生をドラマとして描くことで、現代の私たちが共感する事がたくさんあるのではないかと感じます。
きっとその共感を狙って打ち出した企画なのではないかと考察しました。
作者の森下佳子さんは、『おんな城主 直虎』、『大奥』など、数多くの有名ドラマや映画を担当した脚本家さんです。
令和を生きる私たちに、多くの共感と感動を届けてくれることを期待しています!
放送予定は2025年1月5日(日)です!
気になる方は公式SNSもチェックしてみてください!
今後も、「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の情報や考察を発信していきますので、気になる方はぜひチェックしてくださると嬉しいです!
