第15回JESO一次予選解説・感想等
はじめに
初めまして、元IESO日本代表の黄鉄鉱と申します。2022年12月の第15回日本地学オリンピック一次予選の解説・感想とコメント・考え方などを書いてみようという気になったので書きました。問題を解いた後に、ご自身の解答に至るまでの考察過程と照らし合わせながら読んでいただくと良いかと思います。皆様の地学学習の一助になれば幸いです。
JESO公式ホームページはこちらから→https://jeso.jp/index.html
問題・解答→https://jeso.jp/jeso/pre.html#exam
解説
知識があればすぐに解けるものの、知識がなくても考えれば解ける場合がある問題は、その時の考え方なども適当に書きました。
※個人の考え方なので「これが正しい」というものではなく、間違った記述もあるかもしれませんが、です。
【地質】
第1問 ④
(下から順番に)石灰岩、火山岩脈、泥岩、凝灰岩、砂岩までが断層に切られていて、その上の礫岩は切られていないので、砂岩→断層→礫岩 の順に形成されたとわかる。
第2問 ①
石灰岩は火山岩脈に切られ、火山岩脈は泥岩層に切られているので、石灰岩→火山岩脈→泥岩 の順。また、下から順に泥岩→凝灰岩→砂岩 となっているので(地層は逆転していないことから)地層塁重の法則よりこの順で地層ができたとわかる。
火山岩脈の2.5億年前は古生代と中生代の境界、凝灰岩の6600万年前は中生代と新生代の境界。
よって、石灰岩は古生代以前、泥岩は中生代、砂岩は新生代の化石、となるものを選ぶ。
第3問 ③
〇③川の蛇行と三日月湖の説明になっている
×①V字谷の説明
×②扇状地の説明
×④何の説明かわからなかったが斜面ではなく土砂も崩壊してないので違う
第4問 ③
×③縞状鉄鉱層は先カンブリア時代の20〜30億年前に光合成が始まったことにより海中の鉄イオンが酸素と結びついて堆積したもの。
〇① 正しい記述
〇② 隕石の衝突の衝撃により津波が発生
〇④ ユカタン半島のチクシュルブクレーター
第5問 ③
×①海洋プレートに周期的に隆起したり沈降したりする性質はない。
△②少しはその影響もあるだろうが、大陸氷床の拡大・縮小の影響のほうが大きい。
×④海氷はもともと海に浮かんでいる分、その質量と同じだけに相当する海水を押しのけているので、海氷の量が変化しても海水準は変動しない。
第6問 ①
火炎構造で、降り積もった火山灰や泥などの未固結の層の上に地層が堆積してその層にくいこんだもの。荷重痕の一種である。下の層の上部が変形しているので上下方向がわかる。
第7問 ②
〇②チャートは二酸化ケイ素SiO2でできている。放散虫の殻など。
×①石灰岩…炭酸カルシウムCaCO3。有孔虫の殻など。
×③礫岩
×④砂岩
第8問 ④
示準化石…その産出する地層の年代の特定に役立つ化石。
×④個体数が多い方が年代を比較しやすい。
〇①広く生息する方が離れた地域の地層の年代を特定できる。
〇②進化の速い種の方が、その化石が出てきた時に相対年代が狭い範囲に定まる。
〇③硬い組織をもつ方が化石として残りやすい。
第9問 ③
×①ホモ・サピエンス
×②ホモ・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人)
×④サヘラントロプス・チャデンシス
第 10 問 ②
〇②全地球が氷河に覆われた、という言葉のイメージから(知らなくても)正解だと判断しやすかったと思う。
×①原生代にマンモスはいません。というか多細胞生物もほぼいません。
×③シアノバクテリアは寒冷な地域にしか住んでいないというわけでは全くないのでこれでは判断できない。
×④縞状鉄鉱層は海中で光合成が行われた証拠にしかならない。
第 11 問 ③
パンゲアが形成されたのはペルム紀末。中生代ジュラ紀に分裂が始まった。
【固体地球】
第 12 問 ③
マントルの深さは約0〜約2900km、地球の半径は約6400km。6400-2900=3500より、マントル以外は(3500/6400)^3×100=約20%。よってマントルは残りの約80%。外核は液体である(横波であるS波が中を伝わらないことから。知識問題)。
第 13 問 ①
モホロビチッチ不連続面は、地震波の伝わり方が急に変わる面であり、岩石の密度(≒種類)の境界(not柔らかさの境界)。
×②グーテンベルク不連続面と呼ばれる。
×③そんなものはない。マントルとリソスフェアは示す範囲が重なっている。
×④名前がついているのかもよくわからない
第 14 問 ①
「沈み込んでいる」と書いてある時点 で(知らなくても)収束境界というのは選べる。フィリピン海プレートが沈み込んでいるのは駿河トラフ・南海トラフ。
第 15 問 ④
内陸地震は直下型地震とも呼ばれるもので、その名の通り人類の住む陸のある大陸プレート内で発生するものである。
震源の深さが700㎞にもなる深発地震は、沈み込んだ海洋プレート(=スラブ)内で起こる。大陸プレートは厚いところでも100㎞程度しかないので、大陸プレート内の地震はこの深さには成りえない。また、プレート間の地震も同程度の深さにしかならない。
第 16 問 ③

動く方向を考えればわかる。
海洋プレートは大陸プレートへ向かう方向に沈み込んで、大陸プレートは普段は一部が固着して引きずり込まれているが、できれば引きずり込まれたくないので、耐えきれなくなると固着が剥がれ、その逆方向に動いて地震が発生する。(この図で)上下・左右・前後からかかる応力を比べると、左右からの圧縮の力が最も強く上下方向に押される力が最も弱いので逆断層になる。(相対的に言うと、「左右から押される」)
第 17 問 ④
マグニチュードは2大きくなると1000大きくなるんでした。
1大きくなると√1000倍≒32倍。なので3大きくなると1000√1000倍。
※「1大きくなると32倍」と覚えている人もいるようですが、2大きくなっても当然1024倍にはなりません。
第 18 問 ①
石基と斑晶→火山岩
橄欖石と輝石→苦鉄質岩
あわせて考えると玄武岩。
第 19 問 ②
×②粘性の「低い」溶岩ですね。アア溶岩も併せて覚えておきましょう。
〇①正しい記述。
〇③デカン高原とか。
〇④柱状節理。選択肢を読んで「場合がある」と書いてあるものは大体あります、実際考えてみれば起きそうな現象ですよね。
第 20 問 ①
覚えていれば一瞬。
粘性が低い→粘性が高いマグマに比べてガスが抜けやすい。揮発性成分が抜けやすいということは穏やか。逆に、粘性が高いマグマで揮発性成分が抜けにくい場合、中にガスがたまって一気に耐えきれなくなって吹っ飛ばすわけですから、爆発的な噴火になります。
第 21 問 ②
×②近畿地方の一部は「20㎝」と書いてある等層厚線があるが、これは火山灰などの堆積物が降り積もった厚さが全部あわせて20㎝ということであって、20㎝もの大きさの火山弾が降ってきたというわけではない。普通に考えてこんな遠くまで飛んで来たらかなり怖い。
〇①「北東方向にふいていた」風は南西→北東の風で、「南西の風」と同じであることに注意。
〇③分布限界は宮城・山形県あたりまで。
〇④東京では0~20㎝と読み取れるので、10㎝程度の層厚でもおかしくない。
第 22 問 ③
×③水蒸気爆発は「爆発」とあるように激しい噴火。マグマが地下の水に触れて急に水蒸気になって爆発を起こす。当然人的被害は大きい。
〇①考えたらありそう。実際、1926年、十勝岳で融雪型火山泥流が発生した。
〇②火山ガスの90%以上は水蒸気。
〇④雲仙普賢岳の噴火時など。
第 23 問 ②
覚えておくしかない問題。
「10万年は最近」だと思ったのに…。自分はそれで間違えました。1万年以内らしいです。
イの誤選択肢の50は、日本で常時観測されている活火山の数ですね。
【海洋】
第 24 問 ②
×②「この塩類だけ蒸発しやすい!」とかはないわけだから、塩類の組成は降水や蒸発分布に無関係で一定。
〇①塩分は水に比べて蒸発しにくい。
△③塩類は氷からはほぼ排除される。(少しは氷の中にも入ってしまう)
〇④海水は塩類の希薄水溶液だから、凝固点降下で海水の方が純粋な水よりも凍りにくくなる。(この説明は化学。地学だけやっている人は覚えておくといいでしょう。)
第 25 問 ④
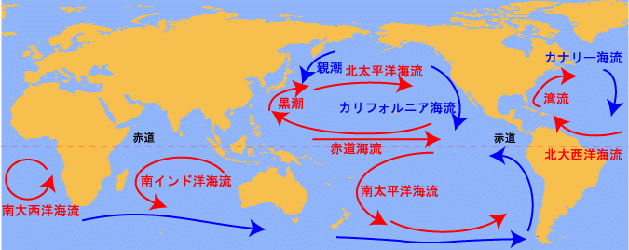
問題に答える話をすると、①と②は、内容から互いに互いのことが言えるのでどちらも同じ側(「間違っている」側)として消せる。
③について、海流の回転中心の偏りは地球の自転(緯度によるコリオリ力の大きさの違い)が原因なので北半球でも南半球でも向きは同じだという考え方ができる。
第 26 問 ③
エルニーニョ現象が発生している時は、貿易風が弱いとき。③以外はすべてラニーニャ現象の時のことを言っているので、この3つが同じ場合に及ぼされる影響のことを言っているのだとわかればどっちがどっちか覚えていなくても解ける。
〇③エルニーニョ現象時には貿易風が弱くなるので暖水域があまり西に押されず、それに伴う「赤道上の活発な降水域」も通常時より東寄りになる。
×②貿易風が強くなるのはラニーニャ現象。
×①東から西に吹く貿易風が強くなると、表層の暖かい海水が大きく西に移動した分を補填するように深層からおこる湧昇流が強くなる。
×④貿易風が強くなると、暖かい海水が西に通常時よりも押し付けられるのと同時に、南北にも広がる。
第 27 問 ④
0度付近には常に上昇気流があり、低圧帯で、降水が蒸発より多い。熱帯雨林などがあることからも想像がつく。30度付近は高圧帯で、降水量が蒸発量よりも少ない。砂漠がここらへんの緯度で多いことからも想像できる。イが降水量、アが蒸発量。
全体的に、左側(ウ)の方が蒸発量・降水量が多い傾向が読み取れるので、ウが、大陸が少なく海が多い(よってたくさん蒸発してたくさん降水する)南半球だと読み取れる。
第 28 問 ②
アorイは覚えるしかない。深層では海水温は一定で、5℃を下回るらしい。
ウorエでは、表層(深さ0m)の密度に注目すると、ウは約1000kg/m^3となっているので、これは純水とほぼ同じなのでさすがに密度が低すぎておかしい。海水には約35‰塩類が溶け込んでいる。
第 29 問 ②
親潮は黒潮と比べて栄養塩類が多いため(だから海洋生物を多く育み、「親」潮と呼ばれる)、それを栄養とするプランクトンが多く発生する。よって透明度は低くなる。親潮は寒流、黒潮は暖流なので、温度が低い親潮のほうが酸素が溶けこみやすいから溶存酸素量が多いのか、と自分は考えた。
それが理由かは知らないが、覚えるのには役立つだろう。
【気象】
第 30 問 ①
日食は、太陽、月、地球の順にほぼ一直線に並ぶ時に地球上の一部で太陽が月に隠されるように見える現象。宇宙から見ると、太陽の光を月が遮ることによってつくられる陰が地球の一部に映っている。月食だったら、太陽、地球、月の順に並んでおり、月に地球の陰が映っているので月の出ているところならどこからでも観測可能である。
月の公転、地球の公転、地球の自転の中で最も速い回転は地球の自転なので、陰の移動方向はこれに支配される。地球の自転方向はbであり、相対的に陰はaの方向に移動していく。
第 31 問 ①
北半球なので、停滞前線の北側が寒気、南側が暖気。温度が低いものほど白く表されるため、より白い北側の雲の上端の方が温度が低い、つまり北の雲の方が高層の雲だということがわかる。よって、「北側ほど雲頂が高い」。
ゆるやかな上昇流なので、(見てもわかるように)層状の雲が出来ている。
強い上昇流だったら積乱雲が発生して雲頂が高い雲が前線に近いところにだけ連なって発生するはずである。
第 32 問 ①
〇①地球のほうが表面温度が低いので、より波長が長い電磁波の放射が最大。地球放射は赤外線、太陽放射は可視光線が最大強度である。
×②むしろ逆。可視光に対してはほぼ透明で、地球放射(最大強度は赤外線)のほうが大気に吸収されやすい。
×③夜間には太陽からの放射はほとんど受け取れないが、地球は夜間でも(熱のある限り)電磁波を放射している。
×④そんなわけがない。雲を構成する水蒸気は太陽放射でも特定の波長を吸収するし、地球放射でも特定の波長を吸収する。
第 33 問 ④
Aは窒素、Bは酸素、Cはアルゴン、Dは二酸化炭素。
〇④火星表面には、二酸化炭素の固体であるドライアイスが存在する。
×①金星の大気の主成分は二酸化炭素。
×②これも主に二酸化炭素。最近話題になっていて問題になっている強い酸性雨は、工場などから放出されたNOxやSOxも溶け込むことによって発生している。
×③CaCO3(石灰岩)にHCl(塩酸)をかけるとCO2(二酸化炭素)が発生する。
結局選択肢は全部二酸化炭素でした〜。つまりは、二酸化炭素はA~Dのどれか、という問題だったということ。
第 34 問 ②
圧力(Pa)の定義は、単位面積あたりにかかる力。
Pa=N/m^2=kg・(m/s^2)/m^2からもわかるように、
大気の質量m(kg)×重力加速度g(m/s^2)÷面積S(m^2)が気圧。
第 35 問 ②
表層混合層はせいぜい幅数百m(海の深さは、最深のマリアナ海溝チャレンジャー海淵でも約10000m=10kmなのでどう考えても最も薄い)、対流圏は大体11~50kmなので幅約40km、大陸地殻は50~100kmくらい。
第 36 問 ④
a:誤

このように気温が高度とともに低下していくか上昇していくかによって圏が分かれている。対流圏の気温は全く一定ではない。一時的には対流圏界面の少し上で一定にはなる。
b:誤
成層圏界面ならほぼ地上と同じ温度なのでまだしも、中間圏界面は、気温の極小高度なので地表付近より高温なわけがないことはわかるであろう。
第 37 問 ③
上空で等圧線に沿って地衡風が吹いて、それに伴って水蒸気が流入している。よって、九州を通っている等圧線上の②か③であるとわかる。
その次に、風の向きを考えると、地衡風はコリオリの力と気圧傾度力が釣り合って吹いており、コリオリの力は北半球では進行方向の垂直右向きにかかるため、高気圧→低気圧の向きの気圧傾度力とこれが釣りあうように、③から北向きに吹いていることがわかる。
第 38 問 ④
フェレル循環に騙されて間違えた。実際のことも考慮してよく考えなければならない。
コリオリ力の向きを考えると、Cは貿易風であり東風で、Dは偏西風であり西風。その上空のAは西風、Bは東風となるが、「フェレル循環」は実際には存在せず、南北に蛇行しながら全体としては西風となるロスビー循環があるので、Dの上空のBでも西風が吹いている。
よって、A,B,Dで西風が吹く。
第 39 問 ①
×①やませは確かに北東から吹いては来るが、それは日本の北西にあるシベリア高気圧から吹き出す風ではない。寒流の親潮の上を通ってくるので冷涼な風になる。
〇②オホーツク海高気圧が南下するとそういうこともある。
〇③台風の最終時期は秋雨前線の時期と被るので、そういうこともある。
〇④「秋が深まり」→ほぼ冬なので冬型の西高東低の気圧配置になることもあるだろうし、そうなると地衡風が、コリオリの力が気圧傾度力と釣り合うように吹くので北寄りの風になる。木枯らしと呼ばれるらしい。
どちらにせよ①は絶対に違うのだから最も適切でないものは選べる。
【天文】
第 40 問 ①
赤道儀望遠鏡の極軸は、北半球では天の北極の方向(ほぼ北極星の方向)に合わせる。つまり北の方角36度。普段から望遠鏡を覗いている天文屋なら簡単だったでしょう。
第 41 問 ③
南半球で空を見上げた時に星の回転中心が見えるのだから、南方向を見ていることがわかる。地球の自転はどこでも西から東なので、星はどこでも東から西に日周運動をする。南を向いているとき、左が東、右が西。よってAの向き。
第 42 問 ③
赤道では、秋分の日には太陽が天頂で南中する。(平均太陽時と視太陽時との均時差があるから正午に天頂「付近」であってちょうど天頂というわけではない)
地軸が向いている方向は一年でほとんど変わらないのであるから、恒星の南中高度が夏至だからといって変わるわけがない。
※歳差運動により約2.6万年周期で少しずつ地軸が回転する
第 43 問 ①
水素の核融合。ヘリウムなどが出来ている。
×②これは原子力発電。
×③超新星爆発したらもう寿命が終わっている。しかも太陽程度の質量だと超新星爆発しない。
×④これは燃焼。
第 44 問 ④
原子番号が小さい順に水素→ヘリウムと多く存在する。イメージとして、宇宙では小さいものから順に作られたと覚えるとよい。原子核が1個の陽子の水素→それが集まって原子核が2個の陽子と2個の中性子合わせて4個で出来ているヘリウム、という感じ。(同位体はここでは気にしていない)
これらの元素の原子核はビッグバン直後に作られた。「原子」になったのは直後ではなくて38万年後(宇宙の晴れ上がりの時)なのだが、まあこれは直後にいれていいだろう。ほとんどの水素・ヘリウムがつくられたのは恒星内部ではないし。
選択肢について、Big Bangなので多分ビッ「グ」バンです、ビッ「ク」バンではなく。
第 45 問 ①
×①火星と木星の間の小惑星帯ですね、恋アスを読んで(見て)いる人ならわかるでしょう。
〇②正しい記述。
〇③正しい記述。
〇④そうでしょう。燃え尽きたものはただの流星ですね。
第 46 問 ④
④は、地球から見ると①を反転したみたいな形に見えます。絵を書いて太陽の光が当たっていない半分をぬりつぶして地球の方向からみるとわかりやすいです。
第 47 問 ②
実際に2022/11/08の皆既月食を観測された方なら簡単だったでしょう。
×②皆既中にも赤く輝く月が見られましたね。赤い光は地球の大気中をあまり散乱されずに伝わるので、地球の大気で屈折して、地球の陰に入っている月にも僅かに届きます。
〇①地球の公転と月の公転を比べると、速いのは月の公転。→この動きが主となって月食がおこる。月が公転して西から東に動くので、東側から欠けます。
〇③実際そうでした。
〇④第30問参照。
第 48 問 ②
写真やその天体の名前に目が行くかもしれませんが、注目すべきポイントはただ一つ。
ア「星雲」イ「銀河団」ウ「銀河」
ア星雲(銀河の中にたくさん分布する)<ウ銀河<イ銀河団(銀河の集まり)
よりこの順に小さいとわかる。
第 49 問 ③
定義ですね。語源を考えると、Habitable Zoneということで「生息可能な領域」、つまり生命体が存在可能な領域(≒液体の水が存在できる領域。地球でも海で生命が誕生した)ということです。
【総合】
第 50 問 ①
いきなり時事問題を突っ込んできました。一年前は、ついに地球科学の分野からノーベル賞受賞者が出たかと話題になっていましたね。他の選択肢の方々も過去の日本人ノーベル物理学賞受賞者です。
第 51 問 ②
こんなに増えたか、人口。これ絶対地学の問題じゃないやろ。
第 52 問 ②
自分は日本に期待しすぎて30%を選んでしまいました。
水力8%、その他再生可能エネルギー10%くらい、合わせて約20%らしいです。
地理の問題みがありますね。
第 53 問 ①
②、③、④の国はプレートの沈み込み境界の周辺なので、火山も多く地熱発電に適しています。①のインドは北部のヒマラヤ山脈のあたりがプレート境界ですが、大陸プレートどうしの衝突境界なので地熱発電には適していません。
第 54 問 ④
化石燃料は植物や動物の死骸が原料なので、植物に取り込まれやすいC12の割合が大気中よりも高い。よってこれを燃やすことはC12の割合を増やしてそれ以外のC13やC14の割合を減らすことになる。
第 55 問 ②
「のみ」に注目。知識問題。③は1960年チリ地震の時とかのことですかね。
第 56 問 ④
南極の「春」にオゾンホールが出現。南半球なので日本での「秋」の時期なことに注意。
第 57 問 ①
これらのうち大気中に含まれる量が圧倒的に多いのが水蒸気。普段よく見る「大気中の気体の割合」は乾燥大気のもので、実際の大気には水蒸気は2〜3%くらい含まれます。水蒸気も実は温室効果ガスです。メタンは二酸化炭素よりも強力な温室効果ガスとして有名です。
第 58 問 ③
チバニアンは約77万年前〜13万年前。更新世は約260万年前〜1万年前。
第 59 問 ①
今回からのテーマであるSDGsをここで出してきました。そんなことは気にせず、覚えていることを適用するのみ。淡水は約2.5%と覚えておきましょう。しかしその大半は大陸氷河のため、人間が利用できる淡水はもっと少ないです。
第 60 問 ③
×①都市の中心部からしだいにその郊外に人が移り住んでいくこと。地理用語かい!
×②脊梁山脈を湿った風が超えるとそのあと吹き下ろす風が熱風になっている現象。
×④貿易風が強くなる現象。
感想
最後の競技科学でした。(地学オリンピック以外に参加していないですが)
初心に帰ったようで、数年前のことを思い出し、こんな頃もあったなと懐かしく、書いていて楽しかったです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
