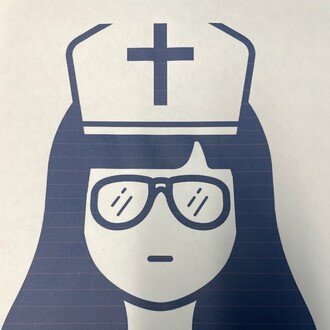ナースあさみと学ぶ、前提条件としての麻酔の話
最近、やたらと無痛分娩の話題を見かけるようになりました。
同時に
全然、無痛じゃないじゃん!!
という意見をネットでもリアルでもよく聞きます。
無痛分娩、無痛だと思ってた(1/8)
— 真船佳奈@テレ東の漫画家 (@mafune_kana) March 25, 2024
#正直出産ってどうだったか教えて#漫画が読めるハッシュタグ pic.twitter.com/9dbi97QGFm
私の出産した病院は無痛分娩平日9時〜17時の間しかやってなくて、土日や夜間に陣痛来ちゃったら普通分娩で産むしかない恐怖でメンタルやられたし、いざ出産は一応無痛分娩できたが、無痛なのは産む瞬間だけの話で、数時間後には麻酔きれて会陰切開とかの痛みが壮絶で一ヶ月寝たきりの地獄だったよ!1/6 pic.twitter.com/T4V0Vi40SW
— 峰なゆか (@minenayuka) May 8, 2024
無痛っていうから
無痛分娩にしたのに……なぜ……?
と、多くの方が感じるのでしょう。
ただ、医療従事者目線で言うと
うん……無痛って表現がイマイチだよね、普通に痛いと感じる人はいると思うよ……だって……
という曖昧なものになってしまいます。
無痛と言うからには、麻酔のようなものをすること、皆さんも想像がつくと思うんですが
じゃあ、その麻酔って何なんでしょうか?
どういう理屈で、痛みを取るのでしょう?
全身麻酔で、意識を失ってしまうのはなぜ?
このあたりの前提知識がないと、無痛分娩の「無痛」だけが独り歩きしてしまうような気がしています。比較のしようがありませんが、無痛分娩なら排便みたいな感覚で産めると思っている方もいるでしょう。
もちろん、他の麻酔も然りです。
まったく痛みを感じずに、周手術期を乗り越えられると思っていたのに!と言う患者さんもたくさんいました。
そこで、今回は
麻酔ってなんなの?
麻酔の種類
薬の種類
麻酔をしてくれない医者は、ひどい医者なの?
あたりを解説してみようと思います。
時間のない人は、目次だけでも読んでみてくださいね。
これから全身麻酔で手術を控えている方、部分的な処置を控えている方、無痛分娩で出産を考えている方あたりに読んで頂けると嬉しいです。
もちろん、それ以外の方も。
では、まいりましょう。
麻酔って、なんなの?
麻酔とは
薬を使って局部(全身)の知覚を一時失わせること
となっています。
この「一時」ってのがポイントですね。ずーっと知覚を失ってしまうと、それはもう障害になってしまいますから。
ここでいう知覚は、痛覚、触覚、視覚、味覚など。
みなさんおわかりのとおり、1番大事なのは痛覚ですね。
痛みをとってほしい、だから麻酔をする。
しかしながら、医療従事者側からみると、痛みをとる以外にも
・手術や処置をするので、身体が動かないでほしい
・組織を切ったり縫ったりするので、そのあたりがやわらかくなっていてほしい
・患者が痛みや不安を過度に感じると、いろいろ不都合なので意識が飛んでいてほしい
こういう目的もあります。ベテランの医者であっても、手技の実践や操作のしやすさに勝る環境調整はありません。暴れてる人にメスを向けることはナンセンス。本来切るべきところではないところを切ってしまうかもしれませんから。
整理しておくと、麻酔の目的は
痛みをとること=鎮痛
手術や処置をする部位が動かなくなり、筋肉がやわらかくなること=筋弛緩
意識を飛ばしておくことで痛みや苦しみ、不安などを感じないような状態にしておく=鎮静
この3つになります。
麻酔にはどんな種類があるの?効く範囲についての話
ここでは、麻酔の種類についてお伝えしていきます。
これは効く範囲で分かれています。
ひとつずつ、みていきましょう。
全身麻酔
基本的に静脈麻酔薬でおこなうものです。ときに、吸入麻酔を併用することもあります。血液にのって、呼吸にのって、脳の中枢に薬を作用させます。そのため、意識がなくなり身体が動かなくなります。
いわゆる麻酔といえばコレ、というもの。
おなかをきったり、腰をきったりするときに使うものですね。
薬の作用によって、意識が飛ぶ&呼吸抑制(呼吸が弱まったり止まったりすること)がおこるので、人工呼吸器管理が必須となります。
このあたりは、のちほど詳しくお話しますね。
腰椎麻酔(脊髄くも膜下麻酔、もしくはルンバール)
腰椎から薬をいれると、下半身全体に効くようなタイプの麻酔です。脊髄と脊髄液で満たされた「くも膜下」という部位に一発ぴゅっといれるようなイメージ。迅速かつ強烈な鎮痛効果が持ち味です。
かわりに、投与した部位から下の運動神経も麻痺してしまうため、薬が効いてるあいだは足を動かせなくなります。
一番使うのは、帝王切開かな。
他にも、鼠径ヘルニアや肛門の手術、全身麻酔をかけるにはハイリスクな症例に適応されることもあります。
硬膜外麻酔
全身麻酔後の術後疼痛管理として使われることが多いものです。腰椎麻酔と違うのは、おなかだけ、足だけといったように、局所だけに鎮痛効果をもたらすことができること。
腰椎麻酔では、腰から下が全部ふにゃふにゃになってしまいますが、硬膜外麻酔の場合はそれが起こりません。そのため、薬を投与されながら歩行することも可能です。
無痛分娩でも、この麻酔が第一選択になることが多いとされています。
静脈麻酔
静脈から麻酔をするものです。点滴と同じルートから投与されます。こちらは術前・術中も使いますし、術後の疼痛管理でも用いられることがあります。胃カメラや大腸カメラ、組織の生検のときも使用しますね。
ただ、のちほど説明しますが、こういう検査のときに使う薬は厳密に言えば全身麻酔のときに使うような強い薬ではありません。そのため、使うと眠たくなる、ボーッとする、痛みがちょっとマシくらいのイメージのほうが良いかもしれません。
PCA(Patient Controlled Analgesia)についても説明させてほしい
手術中も痛いんでしょうが、患者さんが痛いのは、術後。
特に、起き上がって最初に歩くとき、なんです。
(よっぽどのことがない限り、翌日から歩くことが推奨されます)
術後にも、手術中に使っているくらい強い薬で疼痛管理ができたらいいよね、患者さんの痛みが増大したとき(寝返りをうつときとか歩くときとか)に自分で薬を追加できたらいいよねってことで導入されているのが、PCAという仕組みです。
医師の判断で使用されるかどうかが決まります。消化器の病棟にいたときは毎日のように見てましたが、整形外科の病棟で大腿骨頚部骨折の患者さんを見ていても、あんまり使用されていない印象です。
硬膜外麻酔で硬膜外PCA
静脈麻酔でIVPCAと略したりします。
(IVは静脈っていう意味ね)
全身麻酔で手術を受けたあとに、術前に挿入しておいた硬膜外麻酔のルート、もしくは静脈ルートから薬を投与します。
ひとつ、事例をあげてみましょう。
1時間あたり4ml投与がデフォルトの設定。
患者さんが痛いときに手元のボタンでワンプッシュすると追加分としてもう4ml追加することが可能、ただし次のワンプッシュまでのタイムラグは〇〇分、痛いからと連打しても薬が都度投与されないようになってるよ、だって強い薬だから連続でたくさん投与すると副作用が出ちゃうじゃん!!
という仕様になっています。
量や時間はあくまで例ですよ。
よろしくお願いしますね。
PCAの場合、ポンプといって投与量を管理&記録する機械がついているので、一目瞭然。
一度もワンプッシュしていないということは、デフォルトの設定量だけで痛みを抑えられているんだな
数回ワンプッシュしているということは、痛みに応じて自身で積極的に使用できているな
ワンプッシュが一晩で80回…?タイムラグを待てずにボタンを連打しているな、ってことは相当痛いんだな、デフォルトの量で足りていないから麻酔科医に相談して他の痛み止めも検討してもらうか…それとも、少しでも夜間眠ってもらうために睡眠導入剤の使用を担当医に相談すべきか……本人の痛みの閾値が低いこともありそうだけど、それはもうしょうがないよね
といったような評価をすることができるんです。
IVPCAの場合は、ポンプと呼ばれる機械ではなく、ふとっちょ注射器もどき or 医療用風船ばくだんみたいなものを使うことが多いです。もう何を言ってるかわからないと思うので、気になる人は下記のサイトで実物をみてください。
電気を使用せずに、空気圧で薬液をルート内に押し込むことができる優れものです。追加のワンプッシュもある程度時間が経ってボタンがせり上がってこないと押せないようになっています。
腹腔鏡下胆嚢摘出術とか鼠径ヘルニアの手術、膝の手術に使ってくることが多い印象ですかね。手術の翌日、もしくは翌々日までもてばいいという狙いだと個人的には思っています。
その頃には、口から飲み薬を飲めるような状態であることのほうが多いので、わざわざ点滴からの投与だけを考えなくても大丈夫ってわけです。
局所麻酔
患部に細い針で薬液を注射して効果を得る方法ですね。歯医者での治療とか、どこかを切ったときに縫う場合の時とか。おそらく、一番受けたことのある人の多い麻酔だと思います。
残念ながら、点滴や採血と同じくらいの侵襲度(患者さんへのダメージ具合)なので、この針をさすときに緩和するアイテムはありません。我慢するのみ。耐えてね。
ここで触れておきたいのは、あくまでも鎮痛しかしないということ。たとえば、処置の際に患部を思いきり引っ張ったり押し込んだりするときの感覚は残っています。触られてる感覚も残るんですね。だから、これを「痛かった」と捉える人はゼロじゃないということ。
麻酔扱いではなくなりますが、処置の前に痛み止め入りのゼリーを患部に塗っておく、透析の患者さんが針の穿刺部位に前もってリドカインテープや塗り薬タイプの痛み止めを塗っておく、という疼痛管理方法もあります。
いずれも、患者本人の希望ではなく、安全に処置を行なうために医師が指示するパターンが多いように思います。ゼリーを塗らずにおこなう人も、痛み止めを使用せずに透析の針を刺す人もいますからね。
この辺りは、ほんと人によります。
全身麻酔の流れを見てみよう
ここから先は、全身麻酔にフォーカスをあてます。
いわゆる手術といえば、全身麻酔でおこなうもの。
なのに、あまり知られていません。
眠ちゃっててよく覚えてないんだよね……
という人がほとんどなんですが、その寝ている間こそ麻酔の真髄がよくあらわれる場面なのです。いい面も、そうでない面も含めて。
これから全身麻酔で手術を受ける方は、ぜひ読んでいただきたいです。
手術室には歩いていく
わたしたちは入室と言います。
手術室に入ること。
緊急手術の場合は、ストレッチャーやベッドごと入室しますが、多くは予定手術。
この日に手術しましょうと予め決めておいて、それに合わせて入院したり前処置を終えてきている場合には、歩いて手術室に入ります。
これ、よく驚かれますが歩いていける人は歩いていきます。車椅子もストレッチャーも、自分で歩けない人が使うものです。歩ける人は歩く。
点滴をしていることもあります。これは、病気や術式、患者の状態によるので人によりますね。
その後、本人確認をおこないます。
信じられないかもしれませんが、間違うことがあるんです。
横浜市大で起こった患者取り違え事故以降、手術室での入室確認が厳密になったと聞いたことがあります。
以前いた病院では
・麻酔科医
・担当医
・手術室看護師
・病棟看護師
・患者本人
この5人でせーの!で確認して、承認するようなプロセスになっていました。
それから、左右のある臓器の手術の場合(乳房とか大腿骨とかヘルニアとか)は、患者さんにもどちらを手術するか、口頭で述べてもらっていました。あなたが落としたのは銀の斧ですか?金の斧ですか?的なテンションで、あなたが手術するのは、右ですか?左ですか?って。
ここまで確認して、やっと手術室の中に入ります。
病棟看護師はここでお別れ。
麻酔導入の準備
手術室に入ったら、手術台の上に横になります。いわゆる、病室のベッドよりかは寝心地が悪いはずです。あくまで、術者(執刀医や助手)にとって都合のよい作りになっているためです。
ここで、横向きになって背中を丸めるようなポーズをします。胎児のような、茹であがった海老のようなイメージですね。ここで硬膜外麻酔のルートを挿入します。
いきなり挿入するのはお互いに厳しいので、最初に局所麻酔薬を皮膚に何ヶ所かちゅっちゅっと注射して、皮膚が麻痺してから本ルートを差し込む流れです。これは、中心静脈ルートや胸腔ドレーン挿入時なども同じですね。
いきなり本番は厳しい。
この挿入、背中を押される感じと言ってた患者さんが多いですかね。静脈に刺すときよりも、差し込むちからが大きいので。
ちなみに、硬膜外麻酔のルートは入れたあと、テープで固定するだけです。点滴と同じような留め方ですね。皮膚に縫ってこないので、引っ張ったり背中のテープを無理やり剥がしたら、簡単に抜けてしまいます。
ぜひとも、触らないようにしましょう。
(硬膜外麻酔のルートが抜けてるところを発見してしまったら、関係者はインシデントレポートです、ドンマイ!)
これを留置できたら、仰向けに戻っていよいよ全身麻酔の開始です。麻酔科医が静脈からの麻酔、吸入の麻酔を組み合わせて、患者さんが3秒くらいで意識を失えるよう調整します。
だいたい、さん、にー、いちと数えるのですが、いちではもう意識のない人がほとんどですね。変なたとえですが、整うとかキマるよりもすごい。
患者さんの記憶はここから先はありませんが、このあと、どういうことがおこなわれているか見ていきましょう。
人工呼吸器の装着
患者さんが意識を失ったあと、ついでに失うものがあります。それは、自発呼吸。普段、人が無意識におこなっている呼吸のことです。
全身麻酔は、中枢=脳に作用します。痛みや記憶をなくしてくれる。ありがたい。けれども、いつもは無意識にやってくれている呼吸の機能も失ってしまうんです。こいつは困った。
がんを完全に切除しました
でも、呼吸が長時間止まっていたせいで患者が死亡しました
これじゃダメですね。手術というリスクを負った意味がない。だから、呼吸を補う補助として人工呼吸器の装着が不可欠になります。
これがね、いろんな処置の中で、個人的に最もつらいと思っているものです。男性の尿道カテーテル挿入よりも。
意識を失ったあと、吸入のマスクからはめちゃめちゃ酸素が流れるようになります。空気中の酸素の配分はいつもだいたい20%くらい(理科で習いましたよね)、これを100%にして酸素を流します。超酸素状態。これから、無呼吸に近い状態になる挿管という処置をおこなうためです。

これを喉の奥に挿入して、ぐいっと喉を広げて、挿管チューブというものを挿入します。意識があると嘔吐反射が起こってしまう人も。無理やりウェッてされてるのと一緒なので。
もう読んでるだけで苦しいでしょ。
ね?だから、意識がなくて患者もしあわせ、医師もしあわせ。
術前に食事ができないのも、このためです。
挿管の際に、患者が嘔吐したらいろいろマズイ。
きちんと気管に挿入できたら人工呼吸器をつなぎつつ、チューブを口元にテープで固定します。人工呼吸器と患者本人の呼吸が同調し、有効な換気が軌道にのったらOKです。他にもいろんなことを確認して、最終確認(タイムアウト)をして手術開始です。
ここまででだいたい30分前後ですかね。
1時間近くかかることもあります。
患者さんからすると、手術室に入った時間から退室するまでが手術時間だと思われるんですが、関係者からするとタイムアウト(手術開始)からサインアウト(手術終了)までが手術時間という扱いのことのが多い印象。
人工呼吸器をつけるまでは、手術の前準備という認識なんです。
全部で5時間くらいだけど、手術自体は3〜4時間ってところかな
なんて言い方をする担当医がいるのも、このためです。ちなみに、ここまでは麻酔科医の管轄。担当医は着替えて、手術的手洗いをして、手をあげた状態でこの時間くらいに「麻酔どんな感じ?」って入室してきます。
全身麻酔をするにあたっての条件の話
ここまで、全身麻酔の流れをみてきました。
勘のいい人ならお気づきかもしれませんが、要所でいろんな条件をクリアしないといけません。全身麻酔を使って手術をすることで、助からないといけないから。手術は、もっと長く生きるためにすることだから。
当然、いろんな理由で全身麻酔をかけることができません、手術することができませんと言われる患者さんも出てきます。高齢社会の昨今、以前よりもこのケースが増えているように感じます。
ここから先は、全身麻酔を受けるにあたって必要となる条件についてお話していきます。
とにもかくにも心臓と肺
全身麻酔を受ける予定の患者さん、全員に受けていただく検査が「心機能検査」と「肺機能検査」です。
最悪のケースの場合、脳が死んでもどうにかなりますが、心臓と肺がどうにかなったら死んでしまいます。手術が死因になってしまうのは、関係者全員にとって不幸ですよね。
こういう理由で、これらの検査は必須です。そんなに痛みを伴うような検査ではないので、そこまで抵抗はないかと思います。
どういう機能をみるかの詳細をここで語ることはしませんが
・心臓なら、本来の機能であるポンプとしての機能
・肺なら、空気を吸って排出するという換気機能、そして酸素と二酸化炭素がうまく循環する機能
どちらが欠けてもダメ。
全身麻酔や手術そのものの安全性に大きく寄与するからです。
肺機能は、どうせ人工呼吸器をつけるからいいじゃん!という人もいるんですが、まったく良くありません。
人間の呼吸は、自発呼吸が一番効率的で安全です。人工呼吸器も改良はされていますが、基本的に外から空気の量や圧で押す仕組み。一方、人間の呼吸は、横隔膜を使って空気を中へ引き込む仕組み。
肺胞という、肺を構成する要素であるぶとうの房みたいなもののふくらみっぷりが全然違うんです。人工心肺や血液透析の機械を見ても思いますが、臓器が持つ機能を人間が作ると、あんなにも大きくなってしまうのかとびっくりします。わたしよりデカいもの。ほんと臓器ってすごい!と尊敬します。
喫煙の習慣がある人は、術前2ヶ月くらい禁煙してもらうことが多いですね。
つらいでしょうが、呼吸が苦しい術後を過ごすよりかはマシだと思います。肺機能が悪い中で手術をすると、再挿管となる人もいますし、意識がある中で首から気道にチューブをぶっさす処置をする人もいました。気管切開ってやつですね。
喫煙中の人が人工呼吸器をつけると、痰は多いは、肺胞のふくらみは悪いは、酸素がうまく入っていかないわ、マジでいいことが何もありません。
明日、息子がパートナーを連れてくる!っていう前日に、家の中で焼肉をするご家庭、いないでしょう?だいたい、掃除して整理整頓してお酒も控えるんじゃないでしょうか。綺麗にしますよね?
そういうマインドで手術、全身麻酔にものぞんでいただきたいと思います。
あなどれない血糖値
生活習慣病といえば、高血圧、高脂血症、肥満などいろいろありますが、全身麻酔で手術を受ける方にとって一番敵に回したくない病気1位は、糖尿病だと思っています。
詳しく知りたい方は、上記のnoteをご一読ください。
手術を受ける人は、傷は治るものという最低条件の前提を持っていると思うんですが、糖尿病があるとこの前提が揺らぎます。
傷がくっつかないんです。
細胞に流入すべき糖が血中にとどまってしまうのが、糖尿病です。糖というと糖質制限などの影響で悪者のイメージもあるかもしれませんが、細胞の代謝を語る上で欠かせない栄養素。糖が枯渇すると、細胞の新陳代謝が落ちると思ってもらって構いません。
山田さん、すぐに手術してもいいけど、俺や教授がどんなに丁寧に縫っても、糖尿病のせいで傷がひらいてきてしまうと思うよ。それでもいいなら、明日手術するけど、どうする?
こういうセリフを聞いたのは、一度や二度じゃありません。それくらい、血糖値が高い状態のまま、身体に大きな傷をつくってしまうのはリスクしかないんです。
そのため、通常よりも早めに入院してもらい血糖コントロールというものをおこないます。いつも内服している薬がある人はそれらを使いながら、注射薬であるインスリンの投与もおこなっていく、というものです。
いつもよりも、血糖値を低く保ちたいという感じでしょうか。でも、低血糖は困るのでいい塩梅、糖尿病じゃない人くらいの血糖値の推移が理想だと思われます。
このコントロールの難しさは
・術前術後は食事をしないので、点滴のみでの糖摂取になること
・糖尿病じゃなくても、身体に大きな傷がつくと、人間の血糖値は上昇するという前提があること
もう、食べてないのに血糖値が乱気流みたいに上がったり下がったりします。高くなったらインスリンを投与しますし、低すぎたらブドウ糖注射液を注射します。そうやって、なるべく血糖値を一定水準にキープするのです。
それでも、傷が開いてしまう人はいます。もちろん、糖尿病だけではなくいろんな要因が重なって、ですが。入院期間は伸びますし、毎日の処置や観察が続きます。場合によっては、追加の処置がおこなわれることもあります。
痛い、苦しい、つらいが比較的わかりにくい糖尿病ですが、ことこういう場面になるとそのタチの悪さをいかんなく発揮するなと感じます。普段怒らない人がブチ切れる、みたいな感じですかね。
肥満でいいことは、ひとつもない
さきほど禁煙をお願いすると言いましたが、手術までにダイエットをお願いする人もいます。だいたい、手術予定日まで数ヶ月単位で時間があることのほうが多いですから。
肥満だと、余計な脂肪細胞のために貴重な血液や酸素を使うことになります。手術は、麻酔薬があるおかげで医療処置扱いになっていますが、身体からしたら命の一大危機なわけです。切って取って縫ってくる。
臓器ファーストでやりたいのに、脂肪細胞がたくさんいると、そちらにも血液や酸素をわけなくてはならない。手術における生産性が悪い状態になってしまうんです。
それから、猟奇的な言い方になりますが、肉は縫えても脂は縫えません。
皮膚や筋肉は縫うことができますが、脂は難しい。脂は融点が低いですしね。ロース薄切りをまとめてお鍋にいれると全部くっついてしまうと思うんですが、豚バラ薄切りをまとめてお鍋にいれると、脂がとけてハラハラわかれていきますでしょ?あんな感じ。
以前、BMI35を超える肥満の患者さんの傷が開いてしまうことがあったんですが、ガーゼに融解した脂肪が付着していてびっくりしたことがあります。傷口が血よりも脂にまみれているんです。テカテカ。
わたしは、ガーゼ交換をしながら豚の角煮を思い浮かべてしまいました。
補足情報になりますが、手術室に勤める友人が、手術においてデブは凶器と話していました。わたしを含め耳が痛くなった方は、ダイエットがんばりましょうね。
みんな、歯医者さん行ってる?
さきほど、全身麻酔をする際には人工呼吸器が必要、そのとき「挿管」という処置の話をしたこと、みなさん覚えてますでしょうか?
肺は、とてもきれいな場所です。菌がいません。注射なんかもそうですね。必ず皮膚を消毒してから、菌のいない血中に未使用のきれいな針を刺す。
なんとなくイメージがつきますよね。
ですが、挿管はちょっと違います。
気管という場所に口から挿管チューブを留置するため、口唇、歯、舌、咽頭にチューブが触れてしまいます。これらはすべて粘膜、なんらかの菌がいる場所になります。
皮膚の上にも、表皮ブドウ球菌やアクネ桿菌、黄色ブドウ球菌なんかがいるので人間の細胞の近くに菌がいること、そしてそれらに触れてしまうことは、仕方のないことという認識のもと、挿管という処理をおこなうのです。
ただ、ここにも限度というものがあります。
長年放置している虫歯があるとか
年単位で培った歯石があるとか
いまにも抜けそうな歯があるとか
こういうことは、仕方のないことではありません。
患者自身のセルフケア不足、と言われてしまうものです。
虫歯の菌が肺に入ってしまったら、もう感染まっしぐらです。包丁とまな板に便がついたと思ってください。包丁とまな板だったら処分して新しいものを買い直せばいいかもしれませんが、人間の臓器は替えがききません。
ひとつしかないものを、ずっと使い続けないといけないのです。
他にも、挿管の刺激で歯石や歯が気管支へ、そして肺の手前までうっかり入ってしまうようなことがあったら、場合によっては手術中止です。呼吸そのものの安全に関わります。
こういうリスクがあるため、術前に必ず口腔外科の受診をするよう言われます。
・虫歯がないかどうか
・度が過ぎた歯石がたまっていないだろうか
・抜けそうな歯がないかどうか
重度の虫歯があったり、抜けそうな歯がある場合には、そちらの治療が優先されます。挿管時にガッとやってあっ!みたいなことがあるより、全然マシだからです。
抜歯のために、手術のスケジュールそのものをリスケする、という人もいます。
大人で健康保険に加入している人なら、歯科検診のお知らせが5年おきくらいに届いているはずです。もしもの際のリスクを減らす意味でも、日頃からかかりつけの歯医者さんにいっておきましょう。
忘れられがちな膀胱周り
よほど短時間の手術でない限り、全身麻酔を伴う手術では膀胱留置カテーテル(バルーンと呼んだりします)というものを挿入します。これ、麻酔がかかったあとでやる処置なので、安心してくださいね。羞恥心とか痛みとか、いろいろ感じない状態でやるので。
なぜバルーンを挿入するかというと、手術という特殊な環境に陥ると尿閉といって尿がまったく出ない状況になってしまうから。尿は作られているのに出せなくなる、ここがポイントです。
環境が整い麻酔薬を使っている状態とはいえ、身体からしたら大きなストレスがかかっているのと同じ状態。オリンピックの決勝戦みたいな感じです。そんな環境の中で、トイレいきたいんですけど……と言える人は稀ですね。だいたい、ストレスと緊張で気を張っている状態なので、排泄への欲求は弱くなるはずなんです。
しかしながら
手術中は、必ずなんらかの点滴が投与されています。脱水予防もありますが、手術中は血液をはじめいろんな体液を失うリスクが高い。そういう理由もあって常になんらかの点滴が持続投与されています。しかも、通常の飲水ペースよりも早いペースで。
ということは、尿が出せないのに、いつもよりも尿が作られてしまうという矛盾した状態が作られてしまうわけです。
ここを打破するのが、膀胱留置カテーテル。膀胱まで管を留置してしまえば、サイフォンの原理で勝手に出てきます。
くわえて、手術中に失禁してしまうなどのアクシデントを防ぐことができます。尿が出ちゃった!くらいなら、こちらもなんとも思わないんですが、尿がいま切り開いているその部分にかかる or 垂れるなどは、手術の操作的な意味でも人としての尊厳的な意味でもあってはならないですね。
ちなみに、便はあんまり聞かないかな。出そうな人とか大腸〜直腸の手術の人は前もって浣腸をかけさせてもらうことが多いですかね。あとは、手術前日から絶食+点滴パターンが多いように思います。もう、便を作らせない強い気持ち。術中にまみれるくらいなら、術前に出しておこうというリスクヘッジ。
ちょっと話が飛びますが、この膀胱周り。術前に尿検査をして腎機能とか尿の成分をチェックしておくことは済ませておくんですが、実際の陰部から膀胱までの環境はチェックしないことが多いです。術前の人のパンツをわざわざ下ろす作業は、どの医療機関でもしていないはず。
ですが、いざ手術が始まってバルーンを挿入しようと下半身を露出させた状態にしてはじめて、こちらが知る問題やリスクがあったりします。
尿検査は完璧ではないのです。
・陰部がただれている→菌やウィルスがいる場合、バルーン挿入の刺激で膀胱内にそれらを運んでしまうことになります、膀胱炎のリスク
・性感染症がありそう→上に同じ
・膀胱脱がある→出ちゃってんじゃん!という
・重度の包茎がある→バルーン挿入の刺激で絶対的に出血します。消毒&挿入の際にめっちゃ剥きますから
・前立腺肥大がある→膀胱内まで入りずらい、場合によっては挿入を断念するレベルの人も
・膀胱内にトラブルがある→なんかおかしい
こうなると、全身麻酔の前にこの段階でつまづいてしまうことになります。
実際にわたしが体験した事例でお話すると、バルーン挿入をしようとした患者さんが、重度の包茎&膀胱結石で手術が予定よりも3時間、延長した人がいました。
最初の消毒とカテーテルをぐりぐり入れるところで時間がかかり、やっとカテーテルが膀胱内に辿り着くぞと思ったら、なぜかその先に進めません。泌尿器の先生を呼んで膀胱鏡(尿道からカメラを入れる処置)で見てみたら、膀胱の入り口から膀胱内まで結石だらけ。あとで写真を見せてもらったら、鍾乳洞みたいになっていました。もはや、ちょっとキレイ。
ひとまず、カテーテルを挿入できるレベルまで鍾乳洞を削り、その後やっと全身麻酔→手術の流れに移行しました。この人の場合、大腸がんの手術だったのですが、もう大腸よりも膀胱だね!ってことで、早々に泌尿器科の病棟へ転科していきましたね。
尊厳や羞恥心への配慮が大切なこと、それは重々承知ですが、こと手術においては術者も患者も安全であることの優先順位が高いです(もちろん100%の担保はできないのですが)
心配事や懸念点があれば、担当医でも術前の手術室看護師との説明場面でも病棟看護師でもいいので、事前に伝えてもらえるとありがたいです。
じゃあ、緊急手術ってなんなの?
これまでは、予定手術(待機手術)といってあらかじめスケジューリングされている手術の話をしてきました。
麻酔科医
担当医
執刀医
器械出し看護師(メス!って言われてシャッと渡す担当)
外回り看護師(ガーゼカウント、体位変換、点滴や輸血の管理など全体的なバックアップ担当)
これらの人員のアサインが済んでいる状態の手術です。どういう術式でどういう器械を使って、どんなふうに進行するのか、共有済。
一方で、緊急手術というものもあります。交通事故や外傷、突然の危機、災害や事件に巻き込まれた患者におこなうものです。
こういう手術は、前もっての人員のアサインはありません。事前の打ち合わせもありません。そもそも、どういう手術をするのか、術者もぼんやりとしたまま始まることだってあります。
これまで説明した事前の条件を、すべて調べられないまま手術が始まってしまうからです。なんかいろいろわかんないし不安だけど
いま手術しないと死んじゃう
だからやるんです。
放っておいて死んでしまうくらいなら、手術という方法で抗ってみても悪くないよね?というスタンスです。緊急手術を受けた人、その家族であれば
これから手術をするけれど、死んじゃうもしれない。
でも、放っておくと確実に死んじゃうので、手術します!
という説明を必ずされているはずです。まぁ、本人は意識がすでになかったり朦朧としていたりするので記憶がないかもしれませんが……
実際にやってみて、助かる人もいれば残念ながらそうでない人もいます。手術室で亡くなる方や、病棟まで帰ってこれたけど24時間以内に亡くなる方もいます。
実際、臨床の最前線はこれくらいシビアなんです。
そのため
高齢者でメジャーな大腿骨頸部骨折とか腰椎圧迫骨折とかは、緊急で手術しないですね。救急車で運ばれても、ひとまず数日安静にして1週間後くらいに手術というパターンが多いのではないでしょうか。
「こんなに痛いのになんですぐに手術してくれないんだ!」と激昂される患者さんもいますが、激昂できるだけ元気な証。足や手が折れてようが、いのちに別状はありません。医療従事者からみた具合の悪い人は、基本喋れないし、意識がありませんから。
肛門異物、膣異物、電池飲んじゃった系は割とすぐやりますかね。放っておくことでのリスクがあるためです。
おしり関連が気になる方は、こちらもぜひ。
ここで、緊急手術にまつわる医療体制の話にも触れておきましょう。
夜中でも緊急手術をしれくれるような医療機関の当直体制、だいたい麻酔科医が2名、各領域の外科医が2〜3名、手術室看護師は3人くらいです。本当に、最小限でシフトを回していること、おわかりいただけるかと思います。
そのため、緊急手術が1件でも入ったら、外科医たちはそこへ全員集合です。ということは、その科の救急外来が止まりますね。
ついでにもう1件、緊急手術が入ります!となると、もう現場は限界です。医者の人数はこれ以上増えません。みなすでに激務をこなすなかで、当直のシフトにも入っているわけですから。
ただ、手術室看護師はちょっとだけ増えます。オンコールと呼ばれる仕組みがあるからです。オンコールとは、「電話をかけたら30分以内に手術室まで来れる状態で自宅待機しててね体制」みたいなものです。仕事のような、仕事じゃないような。ネトフリ見ながらダラダラしててもいいけれど、お酒は飲んじゃダメ、長時間のお風呂もダメ、そんな時間。
もし、その時間内に呼び出しがなければ出勤する必要はありません。けれども、1回でも電話がなれば出勤です。手術室についてはじめて、どういう患者がどういう手術をしているのか、すぐさま情報収集して動かないといけない。それゆえ、ある程度の臨床経験のある看護師が選ばれます。
ちなみに、わたしがいま勤めている二次救急の病院では、夜間の緊急手術はありません。夜は医者が全部で2名しかいませんし、麻酔科医もいません。そのため、そういう患者さんそのものが救急車で運ばれてこないようになっています。
麻酔のときに使うくすりの話
ここから、おくすりの話をしていきます。
このnoteの一番はじめに、麻酔には鎮痛、鎮静、筋弛緩の要素が必要であると説明しました。
出汁入り味噌みたいな感じで、ひとつでこれらを賄える薬があればいいのですが、そんなうまい話はありません。症例によって、患者によって、どこを強く作用させるか、させないかのコントロールができなくなってしまいますしね。
したがって、いろんな薬を混ぜて使っています。
では、どんな薬をどう組み合わせているか、みていきましょう。
まずは合法的な麻薬から
いわゆる、医療用麻薬と呼ばれるものですね。緩和ケアや終末期医療の領域、がん末期の患者さんに使っているイメージがあるでしょうが、一番消費が多いのは手術室だと思っています。
手術室なんて基本、麻薬と劇薬と毒薬しかありませんから……
今回、このnoteでは麻薬、劇薬、毒薬に関する詳しい説明は省力しますが、興味のある方はこちらの動画をどうぞ。
下記は、厚生省が出している医療用麻薬を適切に使用するための説明書
150pもあります。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/2012iryo_tekisei_guide.pdf
さすが麻薬というだけあって、医療用麻薬の扱いはたいへん厳しく
処方できる医師が決まっている。麻薬施用者免許が必要、研修医や特定行為看護師は医療用麻薬の処方を出せない。
薬は鍵のかかる持ち出し不可の金庫に保管。使用時以外は金庫に鍵をかけておかねばならない。
注射薬、内服、貼付薬、坐薬、すべて使用時は看護師でダブルチェックが必要、開けたアンプルやバイアル(薬液が入っていた瓶)はすべて回収&数の管理、施設によっては内服や貼付薬の薬包(空袋ですね)の数も管理する
医療用麻薬を紛失した場合は、インシデントレポートの作成が必須(もはやアクシデント)
医療用麻薬を床にこぼしてしまった場合は、ガーゼでふきとり、そのガーゼをビニル袋にいれて薬局へ返却。ゴミ箱に捨ててはいけない。
旅行や出張で国外の持ち出す場合、必要書類を提出しなければならない
という感じです。
そのため、どの検査室&病棟にもおいてあるものではありません。必要時は、薬剤室へ取りに行くスタイルです。手術室&ICUには常備していますが、もちろん鍵管理、その鍵を時間帯の責任者が常に携帯しているのがデフォルトです。スタッフであっても、誰でもいつでも持ち出せるものではないのです。
準麻薬という種類の薬もあります
こちらは、麻薬ほどではないけれど、麻薬の次くらいに強い薬シリーズ。
麻薬ほどの厳密な管理を必要としません。
胃カメラにしろ、大腸カメラにしろ、医療従事者が求めているのは鎮痛よりも鎮静です。だって、施術側は痛くないから。とにかく、患者に暴れないで静かにしててほしいんです。ポリープ切除もそう。痛みを感じないはず。だって、粘膜に痛みを感じる神経は通っていませんから。
後述しますが、胃カメラや大腸カメラそのものは手術ではありません。
検査もしくは処置に留まります。
それよりも、不安や恐怖で患者が取り乱す or 暴れてもらっては困るので薬を使うというマインド。
消化管の中を見るだけにしろ、細胞を取ってくるにしろ、なんらか処置をしてくるにしろ、やってる最中に動かれたらスコープが臓器を突き破るかもしれません。
(過去に突き破る→緊急手術になったケースを知っています……アーメン)
この準麻薬、ほぼすべての検査室&病棟に置いてあることがほとんどです。
ただし、絶対に鍵管理、数の出納はすべて記録に残すことになっています。
一般の人が、これを麻酔薬だと思い込むのは、胃カメラや大腸カメラの際に、この準麻薬の鎮静部分を強く感じるからだと思っています。くわえて、ここに眠くなる&落ち着かせる効果を狙った抗精神病薬と併用して使用することが多いから。
準麻薬それ自体は、眠くなる成分がメインではありません。痛みを緩和させる効果のほうがむしろ高いです。ですが、実際に準麻薬と抗精神病薬を同時に投与されると、麻酔薬みたいな効果を与えることができるんです。みなさん「ぼーっとしてきてそのまま寝てしまった」と言います。この検査をはじめてやった人なら、これを麻酔だと感じてもおかしくありません。
抗精神病薬と聞いてびっくりする人もいるでしょうが、臨床では割とメジャーな薬です。精神疾患の有無に関わらず、暴れている人を落ち着かせたいときに使うことが多いように思います。
病棟の鍵のかからない引き出しに定数として管理されていますし、急変時に使う救急カートの中にも入っているものです。
よく使うのは、アタラックスPとセレネースあたり。
ただ、これらも人によっては呼吸が弱ってしまう(場合によっては止まってしまう)呼吸抑制というものが起こることがあるので、いつでも補助換気(顔にマスクをあてて風船みたいなものでぷしゅーと空気を送っている画像、みたことありません??)ができる状況で使うことが多いです。

そのため、たとえばクリニックでの採卵で麻酔をしてくれなかった!という人がいるのは、この辺りの薬を使うための条件が揃っていなかったんだなと、わたしは解釈します。最低、3人はいないと呼吸停止のような急変時に対応できませんから。
痛いのがつらいのはわかるんですが、それは意識があるから。外科的サイコパス看護師の一意見になりますが、本当に痛かったら人は意識を失います、薬を使わずとも。こっちのほうが、いろいろなリスクが少ないと判断される臨床の場面も少なからずあるんです。
ここでちょっと整理しておくと、麻酔といっても
麻酔の種類 ✖️ 薬の種類
これらの組み合わせで、その効きっぷりや患者本人の麻酔してもらった感には、個人差が出ます。
インターネットにはいろんな人の療養記がありますが、その体験や内容が多種多様なのは初体験だから。意外と麻酔の種類、薬の種類の組み合わせにはセオリーがあるので、こちらから見ると「あ、そのパターンを選択したのね」と思います。
専門的な資料になりますが、麻酔薬の一覧や細かい名称が知りたい方はこちらもどうぞ。
麻酔をしてくれない医者は、ひどい医者なのか?
さきほど、クリニックでの採卵で麻酔をしてくれなかった!というエピソードに触れましたが、そうでなくても
先生が麻酔してくれなかった!
痛み止めを追加してくれなかった!!
という患者さんからの訴え、わたしも毎日のように臨床で聞いています。
これは、医者のいじわる……
ではありません。
麻酔をすること、薬を使うことのメリットとデメリットを天秤にかけ、総合的に判断しているだけなんです。
これはどの薬にも言えますが、薬には薬効と呼ばれる薬を使うことでの効果のほかに、副作用と呼ばれるデメリットが必ずあります。
例として、コロナのときにもお世話になったであろう人が多い解熱鎮痛剤のロキソニンをみてみましょう。
上記は添付文書と呼ばれる、薬の取説です。みていただくと、薬の効果よりも先に禁忌対象者の記述があります。それくらい、薬の副作用はメジャーなもの、かつ注意すべきものなんです。
ちなみに、ロキソニンの場合は腎機能が悪い人、胃腸が弱い人、アレルギーがある人には原則処方されません。透析患者さんとか、胃潰瘍の人には、別の薬を処方する傾向がありますね。
もうひとつ、麻酔の際に使われるポピュラーな薬、フェンタニルという医療用麻薬もみてみましょう。
https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00068271.pdf
禁忌の前に、警告という表記があります。やはり強い薬なので扱うときには注意が必要だよ!という意味ですね。ロキソニンは薬局で買えるようになりましたけど、フェンタニルが薬局で買える未来は日本だと絶対にありえないでしょう。
ちなみに、文書の右上が赤く鉤括弧で染まっています。これは、この薬の使用によって亡くなった人がいることを示しています。
こう聞くと怖くなってしまう人もいると思いますが、手術室や救命センターで使う効果の強い薬は、その分強い副作用やショックをもたらすものでもあります。リスクをとってリスクをつぶしていく。ゼロリスク信仰の強い人には馴染まないでしょうが、これが臨床での戦い方のひとつなのです。
ここからは、麻酔薬の使用によって起こりうる副作用について説明していきます。ひとつひとつの薬を説明してたらキリがないので、概論だけ。
呼吸抑制
人工呼吸器のところでもお話しましたが、呼吸が弱くなったり、場合によっては止まってしまうこともあります。歯を抜くだけ、組織をとってくるだけ、ポリープをとってくるだけ、というような状況で、呼吸が止まってしまうかもしれない薬を使うかどうか、施術側だったらどういう判断をするのか、みなさんも考えてみてくださいね。
血圧低下
基本的に、麻酔薬は患者の筋肉をゆるめて、眠らせ意識を飛ばすものなので、バイタルサイン(体温、血圧、脈拍数、呼吸数など)と呼ばれるものは全体的な傾向として下がっていきます。めちゃ深い睡眠状態と同じような感じです。
ただ、まれにこれらが下がりすぎて循環不全を起こす人もいます。脈が止まっちゃうのはダメですし、血圧が下がりすぎると身体に血液が巡らなくなるので、これまた死の淵がみえてしまいます。ダメですね。そのため、血圧をあげる薬や脈を早くするような薬を併用して使っていきます。
ちなみに、大量出血の場合における血圧低下はこの限りではありません。ありとあらゆる薬を使い、輸血もします。輸血も点滴のぽたぽた速度では間に合わないので、機械を使ってぼたぼたぼたと投与したり、注射器を手でぎゅーっとおして投与することもあります。
下記のこういう現場では、上記のような対応をしているはずです。
消化管運動の低下
スーパーでお肉を買ってきて、そのお肉が動いたら困りますよね。手術も同じ。これから切るところは、あんまり動かないでほしい。じっとしててほしい。これから胃を切るのに、ギュルギュル動いていたら困っちゃう。
というわけで、麻酔の効果のひとつとして、消化管運動の低下があります。臓器たちが静まるんです。ただ、完全に止まるわけではありません。そろーりそろーりとは動いています。
しかしながら、これが術後はデメリットになります。おなかがそろーりとしか動かないので、吐き気が出現したりごはんを食べても吐いちゃうんですね。
術後、痛みが強くなかなか離床が進まないためPCAの薬を増やしたら、今度は吐き気&嘔吐でグロッキーという患者をたくさん見てきました(すごく遠い目)
もうこればかりは、運ですね。
薬との相性が良くなかった、としか言いようがない。
痛み止めがいい感じ効きで吐き気もなく、予定よりも早く回復して退院していく患者さんもいますから。
他にも、いろいろ副作用はありますが、基本的に
強い薬をたくさんは、あんまり使いたくない
手術や処置、分娩にかかる時間は短くしたい
が医療従事者サイドの基本モットーだと思います。わたしもそうです。セレネースやアタラックスPを使用した患者が寝始めたら、呼吸抑制が心配で30分おきに見にいっちゃいますもん。
手術も臓器が空気中に露出するなんて普通はありえないことなので、できるだけその時間を最小限にしたいんです。早く終えることも、医療安全の要項のひとつだと思っています。
無痛分娩における麻酔管理の難しさ
はい、やっとここから無痛分娩のお話です。
悪いですが、妊娠の経過や普通分娩についてはご自身で調べてみてくださいね。いろいろ載ってますから。
無痛分娩は、自然分娩を疼痛緩和目的で緩和しながらおこなうもの、という認識で良いと思います。産婦の意識はあるし、いきむこともできるし、赤ちゃんが出てくる感覚もわかる。麻酔の種類でいうと、脊髄くも膜下麻酔、もしくは硬膜外麻酔ですね。
いろんな症例があるとは思いますが、帝王切開への移行の可能性が高い場合には、最初から脊髄くも膜下麻酔(腰椎麻酔ね、足にも麻酔がきいて動かせなくなるやつ)を導入することが多いのかな。
下記のPDFが、無痛分娩の手順としてわかりやすいと思います
(一般の人が読んでもちんぷんかんぷんかもしれませんが……がんばって!)
https://www.hmedc.or.jp/media/manual_ns_2.pdf
ここまで読んでくれた方なら、無痛分娩における麻酔管理の難しさが容易に想像できると思います。ざっくりいうと、天秤にかけるものが多すぎる。
分娩の痛みを緩和しつつ
でも、娩出の感覚は残し
いきみにかける力の感覚も残し
麻酔薬の副作用の出現を最小限におさえ
分娩進行を妨げないように
分娩後は、子宮復古(子宮が収縮し元のサイズに戻ること)の妨げにならず
悪露(おろ、と読みます)の出血量になるべく影響せず
母子共に無事であることが大前提だし
日本では保険適応外の処置なので患者が100%費用を負担しているという背景
これらを背負った麻酔管理、いまの日本でスタンダードに提供できる医療施設はそう多くないと思われます。
それなら、腰椎麻酔の帝王切開で約30分の分娩を終わらせたほうが、安全だし使う薬の量も時間も短くて済む、と外科畑のわたしは考えてしまいます。
自然分娩だといつ産まれるかわからないじゃないですか。けれども、帝王切開として手術管理にすると、ある程度時間が読めるので1日に何件もお産がとれます。安全性も効率の良さも、どっちも守れる。
無痛分娩では、痛みをゼロにすることはできません。あくまで、緩和です。物理的に鼻からスイカがでてくるようなプロセスですもの。手術と同じ。
医療用麻薬を使って療養しているがん患者さんだって、痛みをゼロにおさえこめてる人は稀です。無痛分娩も疼痛緩和分娩と名称を変えたらいいのでは?なんて思ってしまいます。
無痛分娩にお金をかけるべきではない、という意見もありますが、痛みを緩和軽減することは、日本の医療のお世話になっている者として、みなが持っている権利だとわたしは思うんです。
歯を抜くときだって、おなかがいたときだって、こんなん我慢できるよ!とか、お前は痛み止めを使うべきじゃない!なんて誰も言わないじゃないですか。医者の判断や助言のもと、本人が決めますよね。
無痛分娩もそう。使う使わないの判断は、それぞれの産婦の自由と責任の中にあれば、それで良いと思います。
その他の無痛分娩のQ&Aに関しては、以下を参考にしてみてください。
こちらもおすすめ。
あくまで麻酔は、目的ではない
ここまで長々と麻酔について話をしてきましたが
麻酔は、調整です。ゴールではありません。
料理でいうと、下ごしらえ。
その先の手術や処置が、本番です。
そのため、本番を優先することが多々あります。
切羽詰まっているときは、調整を省くでしょう?
みなさんだって、蒸すのめんどくさいからレンジでチンしたり下ごしらえを端折ったり、出汁をとるのがめんどくさくて濃縮タイプの出汁を使ったり出汁パック使うでしょう?
それでも、そこそこおいしい食卓になっているんじゃないでしょうか。
医療でいえば、手術や処置が安全におこなわれること
料理でいえば、あるていどおいしく食べられる状態で食卓に並ぶこと
これらがゴールです。
その上で、どういうプロセスを辿るのかは、関係者間で状況を共有し、合意がとれていれば、なんだっていいとわたしは思っています。
できるだけ薬を使いたくないタイプの人もいるでしょうし
ガンガンいこうぜ!のテンションで薬を使う人もいるでしょう
医療でいうと安全という項目の優先順位が高くなりますが、どれをとっても100%の安全を保証することはできません。
リスクをとってリスクをつぶす現場なんです。
ゼロリスクでは、なにも進まない。
そして、手術や麻酔ははじめての人が多い領域です。はじめての場所で、はじめて食べるものをいただくような状況です。
気にいるかどうか
おいしいかどうか
落ち着くかどうか
みんなも気にいるかどうか
これらは、やってみないとわからないのです。
人によっては、全然おいしくなくてアレルギーのような症状を引き起こすことだってあるでしょう。
では、そのお店や料理は、悪なんでしょうか?
ネットや書籍で他人の体験記を読むことそのものを否定するつもりはありませんが、個人の体験は、個人のものです。共感や共鳴をすることはあっても、その人と同じ体験をすることはできません。
Aさんがいいって言うからと、同じ処置や手術を選択しても、それがあなたにとっていいかどうかは、やってみないとわかりません。そして、よくない状況になったとき、責任をとってくれるのはAさんではありません。
医療従事者がプロたる所以は、リスクのある行動を取ることを国の認可のもと許されていること。くわえて、第三者としていろんな症例を知っていることです。
患者の体験記には載っていない、実際の薬の投与量とタイミング、3ヶ月分の患者の採血データ、体験記には載せなかった家族関係のトラブルなど、客観的に他者へ証明&立証できる情報をたくさん持っています。
これから受ける医療に対して不安なことがある際は、どうか目の前にいる医療従事者を頼ってください。
麻酔を含む薬やケアを用いることで
患者さんがなるべく痛くなく、つらくなく、苦しくなく
処置や手術を終えてほしいとみなが願っていますので。
参考文献
いいなと思ったら応援しよう!