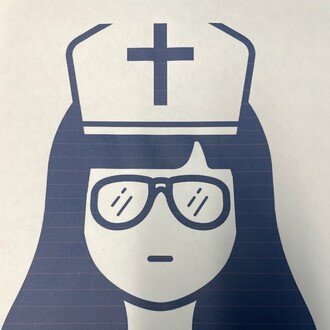読むという行為
先日、書くことと読むことについて考える機会があったので、わたしの頭の中をここに残しておきます。
学生の頃から、そこそこ本を読んできた私からすると、読むという行為は、そこに書かれていないことを地に足が着いた想像力を駆使して補填すること、だと思っています。
この、「補填すること」に自分の語彙力や文章力を用いるから、読むことと書くことは表裏一体、なんて言ったりするんでしょうね。
わたしの中で、読むことが楽しいと思ったきっかけは読書。
最初にハマった作家さんが、はやみねかおるさんと赤川次郎さんだったんですが、もうね、途中からお二人のことをすべて知らないと気が済まなくなってしまって
当時発売されていた書籍をすべて読んだんです。(500冊くらいだったはず)
図書館の人にも、あの子は書庫にある古い本を予約して取り寄せる変わった中学生として覚えられていました。
ファンクラブにも入ったりして、とにかくそれぞれの作家さんの思考回路と背景をすべて知りたかったんですね。
書籍の中や世に出ている情報からある程度はお二人の全体像を把握することが出来ましたが、当然すべてはわからないわけで。
そこから、補填することを覚えていきました。
いま、わたしがやっている看護という仕事に置き換えると、アセスメントや解釈と言えるかもしれません。
目の前にある情報から、ありとあらゆる可能性のベクトルを掬いあげ、より現実的な最適解を導くプロセス。
おふたりの頭の中は、きっとこんな感じ。
だから、ああいう作品が生まれるんだ…!
納得するようになりました。
だから、文章を読むときは目の前の文字の羅列を読むことはもちろん、文章として表現されなかった余白や背景にも意識が向かいます。
ここで、地に足がついた想像力と表した理由をお話させてください。
頭の中で想像してると、どうしてもひとりよがりになってしまって、対象のことを疎かにしがち。
実は、こんな苦い経験をしたことがあるんです。
以前、担当していた車椅子の患者さんが病院から自宅に外泊するとき。
担当看護師だったわたしは、介護タクシーを手配し、家の中の介護物品を揃え、ケアマネージャーに連絡して…
万全の体制でその患者さんを送り出しました。
完璧…!と思っていた、その2時間後。
その患者さんが病棟に戻ってきました。
いや~…玄関前にあった段差が曲者でね。
この車椅子じゃ、どうしても上がれなかったんだ。妻とタクシーの運転手さんもうんしょ、うんしょって手伝ってくれたんだけど、どうにもダメで…帰ってきちゃったよ…
もう、不甲斐ないやら申しわけないやらで奈落の奥底に沈みましたよね、わたし。
結局、患者さんが自宅のベッドに横になるまでの具体的な導線を想像出来ていなかったんです。
玄関前にあった約10cmの段差が障壁となり、その患者さんの外泊は実現しませんでした。
わたしが行った調整は、看護師目線からの対応になっていたんです。実際に動き、生活する患者さんの視点での調整になっていなかった。
患者さんの生活を読めていなかったんです。
以来、患者さんの生活を読むことに人一倍敏感になりました。
トイレと食事がひとりでできるのはわかった。でも、ひとり暮らしするっていっても、誰が買い物とゴミ出しするの?ネット使えないでしょ
とか
手すりがあったら歩けるけど、台所にも玄関にも手すりないんでしょ?どうするの?
とか
湯船に毎日入りたいって言っても、高低差30cmある湯船をひとりでよいしょって出入りできるほどの関節可動域がないじゃん…なのに、介護されたくないとか無理だよ…
これ以上、骨折させる訳にはいかないから訪問入浴にしようよ…寝てるだけでいいんだよ…
など、Google Earth並の解像度の高さで患者さんの生活を想像しています。
そうすると、患者さんもいろんなお話をしてくれるんです。これは、情報提供にあたります。
私たちを信頼してくれるから、伝えてくれること。これがひとりよがりでは、患者さんたちだって、私たちに伝えてくれません。
これが、地に足のついた想像力とさせてもらった理由。ふわふわしたままじゃ、現実で実践できない。
いい書き手には、いい読み手がいて
いい読み手が、また書き手を育てる。
そんなことを考えた夜でした。
いいなと思ったら応援しよう!