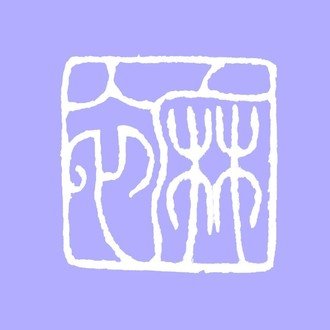ロータスⅡ
1.
いつのまにか道に迷っていた。
電車は目的の駅に着く様子がない。車窓を流れてゆく景色も妙によそよそしく、見覚えがない。不安になって、次に停まったところで降りて、ホームの反対側に滑りこんできた車輌に乗り換えた。駅名も、行き先も何も確かめなかったことに、ドアが閉まってから気づいた。
先刻までは窓から空が見えていたのに、この銀色のボディの電車は地下鉄のようだ。いつ地下に潜ったのか、まったくわからなかった。車内を見回すと、毛羽だち、色褪せた臙脂色の座席に、濃紺のブレザー姿の少女が並んで腰掛けていた。クラスメイトだった。ああ、そうだ、あの制服を着て、毎日この電車に乗っていた。学校へ行くために。
学校? 学校へ行こうとしていたのだろうか。もう、とっくに卒業したはずなのだけれど。とっくに大人になって、うんとうんと歳をとったように思っていたのだけれど。
制服の少女たちが立ち上がって降車する。あわてて、後についていってしまう。何も考えず出口を出ると、青い空がどこまでも高い。
家に帰ろう、と思う。帰らなければ。でも、どこへ? あまりにも色々な家を転々としたから、どこが自分の帰る家なのかわからない。家路を急ぐ学生たちとすれ違う。かつての恋人の顔をした男の子たちが、詰襟に身を包んで歩み去ってゆく。
歩いているのはどこでもなく、よく知っている場所だった。何度もたどった。坂を上って、猫のいる踏切を渡り、色とりどりの花が咲く庭、延々とつづくブロック塀。細い道が複雑に入り組む路地の曲がり角を、何度でも間違えた。魔法にかけられているように、同じ袋小路に何度もぶつかる。近くまで来ているのに、正しい道が見つからない。
ああ、今もまた。ここはどこなのか、もう、わからなくなってしまった。
いつまでもさまよっていた。五十年以上歩いていない、けれど記憶の中では何度も何度も訪れた、道を。
……夢を見ていた。子どもの頃から繰り返し、繰り返し同じ夢を見る。
閉じられた瞼を囲む深い皺が、目尻から滲みだした涙で濡れた。ベッドの脇に佇んで、柘榴はじっと老いた寝顔を見ていた。眠りながら泣いているとき、彼女はひどく頼りなく、あどけなかった。いつか見せてもらった若い日の写真の、ぱっちりした大きな瞳、丸顔のふっくらした頬にえくぼをつくって笑っていた女の子の面影が重なる。
柘榴は手にしていた蒸しタオルで彼女の目許を拭った。身じろぎもせず眠りのなかにいる老女に話しかけるために、軽く息を吸って声を張る。
「桃重(トウエ)さん。……おはよう、桃重さん、起きて」
体に手をかけてそっと揺すると、桃重はぼんやりと目を開いた。まだ遥か遠くをさまよっているような瞳で、彼女は言った。
「……ああ……あたし、またあの夢を見てた。なんだか悲しい夢」
「夢?」
「それがねえ、……目が覚めると、全部きれいに忘れてしまうのよ。いつもそう。……とっても悲しい、っていうことしか覚えていないの」
言いながら、桃重はうっとりと眠りの国へ戻ってしまいそうだったので、柘榴は更に大きな声を出した。部屋の外では、母たちが慌ただしく動きまわっている。
「桃重さん、もう起きて。支度をしなきゃ」
「あれ、柘榴ちゃんじゃないの。どうしたの、学校に行かなくていいの」
たった今気がついた、というように桃重は柘榴の顔を見た。柘榴は小さく溜め息をついた。柘榴が大学を卒業してもう十年経つというのに、桃重はときどきその時間の経過をなかったことにしてしまう。今がいつなのか、ここがどこなのか、桃重のまわりの世界はぼんやりと霞みはじめていた。
「あたしはもうとっくに学校へ行ってないよ」
「ああ、そうか。またあたし、わからなくなっちゃった」
「……ね、桃重さん、ごはんを運んで来ていい?」
「もうそんな時間なの。なんだか今日は早いんじゃない?」
大儀そうにゆっくりと体を起こす桃重に手を貸してやりながら、柘榴は静かに告げた。
「……父さんのお葬式だから」
桃重の表情は能面のように動かなかった。伝わっていないのだろうか、と柘榴が訝っていると、やがて桃重は寂しげにゆっくりと微笑んだ。
「……そうだったね。あの人、逝っちゃったんだったねえ」
2.
夕食のあと、食器の片付けを終えた沙羅が手を拭いて振り向くと、伯母の椿が物言いたげにすぐ背後に立っていた。
「あ、ごめんなさい。流し、使う?」
「うん、お茶淹れようかと思って。沙羅も飲むでしょ?」
「ありがとう」
椿は電気ケトルのスイッチを入れ、ティーバッグを二つ取り出した。伯母は何をするにも手軽さを最優先する。
「……沙羅、ごめん。そろそろ、匿ってあげられなくなりそうだよ」
ティーバッグを湯に浸けたままのマグカップを沙羅に手渡し、紅茶の色が出るのを待たずに口をつけながら、椿は硬い声で言った。やっぱり、と沙羅は思う。もっと早くに追い出されていてもおかしくなかった。今日は大丈夫だったけど、明日はだめかも知れない、と寝る前に毎晩思っていた。
「柊(シュウ)にバレちゃった。たぶん、もう茉莉花(マリカ)さんにも伝わってると思う」
柊、というのは椿の双子の弟で、沙羅の父の柊二(シュウジ)のことだ。沙羅には建前上「お父さんにもお母さんにも内緒で」ということにしてあったものの、実際には沙羅が転がりこんできたその日に椿は柊二に連絡を取り、しばらく預かるから心配要らない、と伝えてあった。母親の茉莉花にも、とにかく安全な場所にいるから本人の気が済んで帰ってくるまで待つように、と柊二を通して言い含めてあったのだが、予想以上に茉莉花も気を揉んでいたのだろう。そっちへ乗り込むと言い出して止められない、夫婦仲まで微妙になりそうだ、と柊二が泣きついてきた。柊二が口を割るまでもなく、沙羅が身を寄せられそうなのは椿のところぐらいしかない、と茉莉花も感づいていたに違いない。
そういう事情をもちろん椿は口に出さなかったが、沙羅は十代の鋭さで薄々察していた。独身を通しているせいか、同い年で、しかも便宜上は姉のはずなのに弟である父より若く見える椿は、近くに住んでいることもあって昔からしょっちゅう家に遊びに来ていた。自分の子のようにかわいがってくれ、母よりは気さくにつきあえる伯母に沙羅は幼い頃から懐いていた。たまに椿の家に預けられることがあると、嬉しくてたまらなかった。
母との関係がこじれだしてからは、沙羅の気持ちはますます椿に傾いた。椿は茉莉花とも仲が良かったが、時折、遠慮しているような態度も見せるので、あまり甘えすぎてはいけないとわかっていながらも、沙羅は茉莉花と衝突する鬱憤をつい椿にぶつけてしまうのだった。
どんなに他愛ない会話も口論になり、柘榴と揃って専門学校を受験したい、と打ち明けたあたりからは、沙羅は茉莉花と顔をあわせるのも苦痛だった。結局、沙羅も柘榴も親と教師の猛反対にあって系列の女子大に内部進学することになったのだが、沙羅と茉莉花の溝は深まった。そして五日前、茉莉花と大喧嘩した沙羅は衝動的に家を飛び出してしまったのだ。
沙羅はまだ帰りたくなかった。無理やり連れ戻されるのも癪に障るし、母と冷静に話をするためにはもう少し時間が欲しい。けれど、こうして椿にはっきり宣告されてしまった以上、わがままを言うわけにもいかない。
柘榴の顔が脳裡を過ぎった。閑静な高級住宅街の豪邸には使われていない客間も幾つかあったし、沙羅が住んでいるマンションのリビングほども広さがある部屋を柘榴はひとりで使っていたから、物理的には沙羅ひとりぶんの空間を確保するぐらいわけはないだろうが、柘榴は自宅を嫌っていた。初めて遊びに行ったとき、緊張で体ががちがちになり、ふかふかのソファの応接間で出されたお茶にもろくに手をつけられなかったことを沙羅は今でも覚えている。時代がかった探偵小説の舞台になりそうな、今時珍しく家族以外の人間の出入りも多い家だった。あまり積極的にお世話になりたい環境ではなかった。そもそも今、沙羅は柘榴に気安く「泊めて」などと頼めない。同じ演劇部で、中等科の頃から沙羅がいちばん親しくつきあってきた柘榴だったが、冬休み明けから二人のあいだにぎこちないものが漂いはじめ、進学試験が終わって授業が休みになってからはほとんど連絡をとっていない。
行けそうなあてはなく、マグカップを見つめて沙羅は黙り込んだ。わかった、明日帰る、と言わなければいけないのに、口を開いて言葉を発することができずにいた。椿がぽつりと言った。
「……蓮(レン)さんの家がわかれば……」
蓮。その名前は何度か聞いたことがあった。こっそり盗み見た、母と父の結婚写真の後列に、花嫁と花婿よりも濃い存在感で立っていたひとだ。データを持ちだして何度も眺めたから、実物を見なくてもありありと構図を思い浮かべられる。茉莉花はその話をしたがらなかったが、椿は蓮のこと、蓮と一緒に物語の衣装のような服を着て集まっていたときのことをよく話してくれた。
「あの人はよく女の子を家に泊めてあげてたから。今でもひとり住まいのままなら、あんたのことを居候させてくれるんじゃないかなあ」
「でも、わたしは会ったこともない人だよ。椿さんや母よりも年上なんでしょう?」
「そうだね、……十歳、もっと離れてるかな? あたしとは十六、七歳違うかも。……そうか、蓮さんももう、七十近いのか。想像がつかないな」
「椿さんが最後に会ったのは、いつなの?」
「いつだろう……もしかしたら、沙羅が生まれるか生まれないか、っていう頃かも知れない。オンラインではたまにメッセージを送りあったり、ブログを読んだりしてたから、ずっと繋がっている気がしてたよ」
椿は懐かしげに目尻に皺をよせた。
「ブログを読んでいた限りでは環境が変わったっていう気配もなかったけど、さすがに昔のままではないのかなあ。どうもあの人だけは、歳もとらずにずっとあのままという気がしてしまって。あ、」
急に椿は大きな声を出した。
「茉莉花さんと蓮さんは同じ学校の卒業生だったはずだよ。ええと、何だっけ、お嬢様校の……」
「えっ、華胥の出なの?」
つられて沙羅の声も大きくなった。
「ああ、沙羅も同じとこ通ってるんだっけ? 卒業生名簿とか、持ってないの? 住所を探せるかもよ」
「卒業生名簿……」
そういうものが家のどこかにあっただろうか、と思考をめぐらせはじめた沙羅に、椿は一転あらたまった口調になった。
「いやいや、駄目だ、こんなこと教えて沙羅の家出が長引いたら茉莉花さんに縁を切られちゃう。忘れて、忘れて」
翌日、身支度をして沙羅が「お世話になりました」と頭を下げたときも、
「いい、昨夜の話はあたしの戯言だからね。あんたはこれからまっすぐ家に帰りなさいね」
と玄関先で椿は念を押した。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?