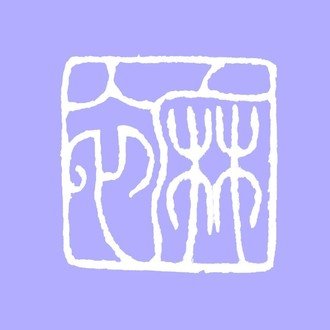シスター
1.
人ごみに見慣れた背中を見つけて紫苑が足を速めようとしたそのとき、視線に引っ張られるように三つ編みを揺らして菫子(スミレコ)が振り向いた。気づいてくれたのか、と手を振ろうとした紫苑を、しかし菫子は見ていなかった。読みさしの本を片手に持ったまま、白昼夢を見ているような目で、少し首を傾げて何もない空間を注視している。ふいに宙を見つめて静止してしまう猫みたいに。
いつだってそうだった。菫子は遠い彼方のもの、そこにないものばかり見ている。すぐ傍にいる紫苑の頭を、彼女の眼はいつも飛び越してゆく。
小さく溜め息を吐き、紫苑はゆっくり菫子に歩み寄った。ぽん、と肩を叩くと、菫子は一瞬まるく見開いた瞳を糸のようにして笑った。駅の構内を行きかう人々ごと風景は連続写真となって流れ、紫苑には菫子しか見えなくなる。
土曜日の午後のサンシャイン通りは人でごった返し、パフェテラス「ミルキーウェイ」にも少女たちの賑やかな笑い声が溢れていた。席に案内されて向かい合うと、菫子はメニューに目もくれずに口を開いた。
「やっぱりわたしは修道院に入るべきなんだよ」
ああ、まただ、と紫苑は秘かに思う。昨夜、切羽詰まった声の電話がかかってきたときからなんとなく予想はしていたが、ここに連れて来られた時点でそれが確信に変わった。星をモチーフにしたメルヘンな趣味のこの店は菫子のお気に入りなのだが、ヴォリュームたっぷりの甘いパフェをおやつに食べるのは体重に一喜一憂する女子高校生には勇気が要ることでもあり、学校帰りに気軽に寄る店ではなかった。店員が注文を取りに来ると、菫子はようやくメニューをちらりと見て「蠍座のパフェ」を指差した。菫子は蠍座なのだ。紫苑は魚座だが、同じものを頼んだ。
菫子がここに来るときは彼女にとって大切な話があるときであり、それはほぼ毎回「修道院に入りたい」から始まる。紫苑はその展開をこっそり「尼寺の場」と呼んでいた。勿論オフィーリアのように恋人から「尼寺へ行け!」と罵倒されたわけではなく、これは菫子が失恋したときの決まり文句で、次にくる台詞もほぼ決まっている。
「あのひとも……、結局はただの男の人だったんだもの」
予め書かれたシナリオのように毎回同じだ。菫子の恋は「今度こそ本当に見つけた」から始まり、「他の人と同じ、ただの男の人でしかなかった」で終わる。この世に「ただの男」でない男などいるものか、初めのうちは紫苑もそう言った。何度も何度も、お節介だと気が引けるのをこらえて、菫子のためなら自分は嫌われても構わない、と覚悟さえしながら、ほとんど叱りつけるような強い調子で言ったこともあった。けれど紫苑の言葉は菫子を通り抜けてゆくばかりで、「そうだね、本当に紫苑ちゃんの言うとおりだと思う。わたしが馬鹿だったんだ」と神妙に頷きながら、菫子はすぐにまた繰り返す。だから紫苑はもう何も言わない。同じことを繰り返しているのに、いつも初めてのように傷つく菫子をこれ以上見たくないという紫苑の願いなど、菫子には思いもよらないのだろう。紫苑はただ、菫子の受けた傷のケアに集中することにしている。菫子が傷ついていることに、自分も傷つきながら。
菫子は紫苑よりひとつ歳上で、初等科の頃に同じ図書委員だったことがきっかけで親しくなった。交換日記が流行り、紫苑も菫子を含めた四人ほどでノートを回しあっていたのだが、紫苑と菫子以外のメンバーは直ぐに飽きてしまい、いつのまにか二人だけのやりとりになった。菫子は学業も委員会活動も優秀で、きょうだいのいない紫苑は、出来の良い姉を持ったような気持ちで菫子を慕い、あとをついて歩いたものだ。真面目でしっかり者の菫子。それがこと色恋の話になると、途端に危なっかしく頼りなく、どちらが歳上だかわからなくなってしまう。
「……そうですか……」
運ばれてきたパフェの、星型のビスケットを口に入れて紫苑は菫子の今回の相手を思い出す。確か菫子が通う予備校の講師だった。十以上も歳が離れていて、物腰が柔らかく穏やかで、どこか世間離れしたところがあり、妻子か、或いは長く連れ添った恋人がいる男。容貌や職業、肩書きなどが変わってもこの条件は菫子の片想いに一貫して引き継がれていた。本人は気づいておらず、何かのはずみで相手が妻帯者だったと判明するたび菫子はひどく落ち込むのだった。「あのひとが今度のひとなの」と遠目に紹介される男の左手を、紫苑は真っ先に確認し、薬指のつけ根がきらりと光るのをみとめ、心の準備を始める。菫子には言わないでおく。言ったところで「光の加減だ」とか「お洒落でつけてるだけで、意味なんかない」とか散々に否定されたあげくむっつり黙りこまれるだけだからだ。
あれは菫子が、産休代理で一年だけ演劇部の顧問を務めた理科教師に想いを寄せていたときだったか、紫苑は「先生はご結婚されてるんですか?」と菫子の目の前で抜け抜けと訊いてやったことがある。若いのに感情の起伏の少ない教師は珍しくうろたえ、「ああ、これですか」と照れたように自分の左手を見て、わざとらしく髪を直した。シルバーの細い指輪が填められた手は、中性的な雰囲気に似合わず節がしっかりして大きかった。奥さんどんな方なんですか、いやいや勘弁してください、紫苑が教師と会話をしているあいだ、菫子は表情を失くして立っていた。唇の両端を何とか引き上げようと努力しているのが伺えたが、その微笑は能面に似ていた。メドゥーサに睨まれて石化していくように、直立の姿勢のまま菫子の体が強張ってゆく気配が伝わってきた。
その日、部活のあとの帰り道で、山手線の改札口で別れるまで菫子はひとことも口をきかなかった。現実をはっきりわからせたくてしたことだったけれど、軽率だった、と後悔しながら、挨拶すら切りだしにくい空気を無理やり破って「それじゃあ……」と紫苑が立ち去ろうとしたとき、菫子が面を上げた。
「あのひとは実験や数式や、元素や化学反応にしか興味がないように思ってた。女の人とか、そういうこととは関係がない気がしてた。そんなはずないのにね。ただの男の人だったんだね。どうして気づかなかったんだろう」
菫子は今にも泣きそうな顔で笑っていた。
迷子の子どもが心細いのを押し隠して知らない大人に媚びてみせるような菫子の泣き笑いは、紫苑を途方に暮れさせる。相手がいようと関係ない、奥さんや恋人よりも菫子のことをもっと好きになるかも知れない、と必死で考えた慰めを口にしたこともあったけれど、菫子は力なく首を振るばかりだった。パートナーのいる男しか好きにならないくせに、パートナーがいるとわかった途端に菫子の恋心は消滅する。相手の男の意志は関係なく、他人の持ち物ばかりが良く見えて欲しがるというのとも違うようなのだった。
なるべくそんな顔をさせたくなくて、紫苑は菫子を積極的に現実から庇ってやるようになった。何も気づかず、遠くから見つめるだけの淡い片想いのままでいれば、菫子は幸せでいられる。だから今回の予備校講師のことも、何も言わずにひたすら浮かれはしゃぐ菫子の話を聞いていたのに、菫子はまたしてもあの泣き笑いで、捨てられた犬か猫のように紫苑を見つめているのだった。
「結婚してたんですか? ……ええと、風間先生」
そう、風間という名だった。菫子のことだからどうせそうだろうと高を括る反面、紫苑は今回はもしかしたら、とも思っていた。万が一の間違いで菫子の恋がうまくいくかも知れない、という胸騒ぎめいたものは常にあるのだが、それだけではなかった。一度だけ、菫子にせがまれて教室に潜り、一緒に風間の授業を受けたことがある。風間の担当教科は数学だった。ただでさえ苦手なのに一学年上の内容など理解できるはずもなく、落ち着いたトーンの解説を外国語か何かのように声だけ聞いていた紫苑が、その講義で唯一覚えているのが、眼鏡の位置を直した風間の左手に指輪がなかったことだった。あれっと思ってチョークを持つ右手にも目を凝らしたが、やはりそれらしきものはなかった。今度の相手は独身で、今度こそ見こみがあるのだろうか。不安に似たざわざわした気持ちが紫苑を揺らした。
けれど、菫子は紫苑の問いをあっさり肯定した。
「子どももいるって」
「……菫子先輩、それ直接聞いたの?」
「まさか。わたしがしょっちゅう質問に行ってるから、全然関係ない先生にばれたみたいで」
菫子は溶けて崩れかかっているパフェのデコレーションをスプーンで突ついた。
講師室の風間の席にはいつも質問の列が出来ていた。菫子もその列に並んでしょっちゅう質問をしていたが、後ろで順番待ちをしている生徒の前で余計な雑談ができる雰囲気でもないので、用が済むとお礼もそこそこにその場を離れるのが常だった。
けれどその日はたまたま、質問をしに風間を訪れたのは菫子だけだった。風間はいつになく丁寧に、徹底的に菫子の疑問につきあってくれた。それだけで十分すぎるほど満ち足りて、深々とお辞儀をして立ち去ろうとした菫子を、風間は呼びとめたのだ。
「いつもこのくらいちゃんと説明してあげられるといいんだけど、ごめんね」
「いえ……そんな」
「君、どこを狙ってるの」
菫子は言葉に詰まった。彼女が紫苑とともに通っているのは、幼稚舎から大学までの一貫教育を誇る私立の名門女子校、華胥女子学院だ。そのことと、とりあえずは内部進学できればいいと思っていることを、たどたどしく説明した。
「ああ、そう言えば華胥の制服だね。そうか、お嬢さんなんだな」
風間はくつろいだ様子でマイルドセブンを取り出し、ゆったりと火を点けた。近くの席にいた講師が、立ちあがって出て行った。風間が煙草を吸うのは意外でもあったが、新鮮だった。彼のくだけたところを菫子は初めて見た。どきどきした。
雲の上を歩いているようにふわふわした気分で廊下に出たところで、菫子は声をかけられた。
「いいことを教えてあげようか。……風間先生のこと」
先ほど席を立った講師が、壁に凭れていた。上から下まで黒ずくめの服を着て、背が高く、現代文のテキストと赤のサインペンを手にしたまま腕を組んでいる。授業を受け持たれたことはなかったが、知っている人だった。
なぜあの人がこんなところに。
会釈して通り過ぎようとした菫子の背中に、講師は低く呟いた。
「彼は独身だけど子どもはいる。離婚したんだよ」
思わず菫子は足を止めて振り返った。乗っていた雲が切れ、虚空を落下していくような感覚に膝の下がすうっと冷えた。
「英語の清水先生に訊いてごらん。彼女が詳しいから」
講師は広げたテキストの影で笑っているようだった。
「……何なの、そいつ。知り合いなの」
細心の注意を払って触れている硝子細工を、無造作に掴んで乱暴に扱われたような出来事に紫苑は憤慨した。けれど菫子はそれに答えずに、
「子どもがいる、というのは構わないの。過去に結婚していたというのは……まあ、ショックだったけど、お父さんだというのはそれはそれで風間先生らしい気がするの。だけど……」
菫子は唇を噛んだ。手をつけていないアイスクリームが、皿ですっかり溶けてしまっている。
「現在進行形で女の人とつきあっているなんて」
「だけど、そんな得体の知れない奴の言ってること、どこまで本当か怪しいですよ。まるまる信じることないんじゃないですか?」
「わたしもそう思った。でも、清水先生のことは本当だと思う……、同じような話を、クラスの子からも聞いたから」
紫苑はテーブルの上で微かに震えている菫子の手をとってそっと開いた。掌をあわせて、指の腹でそっと撫でる。紫苑の為すがままにまかせながら、菫子はあいている手で頬杖をついた。
「わたし、ずうっとずうっと同じことを繰り返してるよね。紫苑ちゃんに何回も怒られて、それでもまた懲りずに同じことして。こうして、だめだったってなってるときは、わかるの、みんなただの男の人なんだ、って。……好きになると忘れちゃうんだよね。今度こそ見つけた、このひとは絶対に違う、って思いこんじゃうんだよね……」
「なに、どうしたんですか急に」
「紫苑ちゃんは、わたしが人の話を何にも聞いてないと思ってるんでしょう」
「う……うん」
話が思いもよらない方向に転がって、紫苑はびっくりして手を止めてしまった。菫子は掌を返して自分の手を上にし、指を絡める。
「今度という今度は本当に思い知った。わたし、今度こそ諦めなきゃいけないと思う。これ以上無駄に希望を持ちたくないし、失望して傷つきたくない。……疲れたわ」
紫苑は思わず菫子の手をぎゅっと握ってしまった。菫子は自然に握り返してくる。熱くて、子どもと手をつないでいるようだと思う。
「……だからって、いきなりシスターは……極端すぎる」
「だって、誰とも恋をしないでいるには神さまと結婚しちゃうのがいちばんだと思わない?」
通りに面した硝子張りの窓越しに差し込む陽が柔らかく菫子を照らした。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?