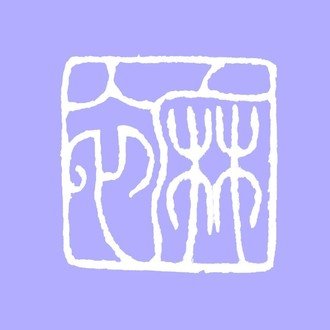リリイ
1.
開けた箪笥の抽出に肘をついて凭れかかり、裸のまま、ゆりのは迷っていた。
着けていくランジェリーを決められない。熱いシャワーを浴びて火照った肌は、すっかり冷たくなりかけている。
今日はきっと、久しぶりで下着姿を人に見せることになる。レースのかわりにふわふわのフリルをあしらった白の無地が清楚でいいだろうか。いや、白イコール清楚という発想は安直すぎる。桃重(トウエ)が肌によく映えて色っぽいと褒めてくれた、アンティークゴールドの地に紫紺の繊細な刺繍が施されたブラジャーを合わせてみる。色っぽいというより、過剰にいやらしく見えて怖じ気づき、慌ててゆりのはそれを戻した。一時期大人っぽくなれる気がして集めていた黒も、避けたい気分だった。
桃重はいま、どこで何をしているのだろう。今でもあの店、ブーケドゥリスで働いているのだろうか。かつてのゆりののような、自分のバストサイズもろくに知らない少女に、ぴったりのブラジャーを見立ててやって、それから、……そうだ、あんなことがあったのだからあの店は辞めてしまったかも知れない。もしかしたら再婚している可能性もある。
……そして、蓮実は。蓮実はどうしているだろう。
抽出に詰まった、色とりどりの花畑のような下着。眺めていると、遠い夢のような時間が次々に思い出される。それは、特別な記憶など何もなかったかのように、何食わぬ顔をして日々を送っている現在のゆりのを、瞬く間にのみ込んだ。
桃重に出会うまで、つまりブーケドゥリスに足を踏み入れるまでゆりのは自分で下着を買ったことがなかった。母に任せていた。さすがに高校生の頃には、いい歳をしてお母さんにパンツを買ってもらっている、というのも気恥ずかしく思っていたが、下着売り場に入るのはそれ以上に気恥ずかしかった。
華胥女子学院の中等科と高等科に通う生徒の半数以上は池袋駅を経由する。ゆりのも乗り換えのために下車する池袋で日課のように寄り道をした。行き先は大抵、カラオケ・ボックス、ゲームセンター、そうでなければ西武百貨店の本店。十六歳から入会できるクレジット機能のないクラブ・オン・カードを持つのがクラスで流行って、ゆりのも十六歳になってすぐカードをつくった。隙あらばそれを使いたくてとりあえずは西武に行くのだが、実際にはそれほど買い物をするわけでもなく、ひたすら店内をうろうろして満足していた。よくまあ毎日飽きなかったものだ、とゆりのは自分でも苦笑してしまう。
しかもゆりのや、ゆりのが親しくしていた友人達はお洒落に熱心な方ではなかった。だからデパートに来たところで、洋服や服飾雑貨、化粧品なんかのフロアは素通りして、専らリブロで立ち読みをするか、WAVEで新譜の発売日をチェックするか、なのだった。
最上階のWAVEと、地下のリブロを行き来するために延々エスカレーターを乗り継いでいると、必ず三階でインナーウェアの売り場の近くを通る。ゆりの達と同年代、かつ、ゆりの達より垢抜けた、茶色い髪で化粧もしている女子高生が、楽しげにランジェリーを広げている様子が嫌でも目に入る。ゆりのはそれを他人事のように見ていた。
「ああいうところ、入ったことない」
二階へ下りるエスカレーターのベルトに凭れながら、ゆりのは呟いたことがある。
「あたしもない」
一緒にいた喜久恵も同調した。同じ演劇部で、贔屓の劇団や役者などの好みが似ている喜久恵とはよくつるんでいた。
「ないけど、近寄って値札見たことはあるよ。ああいうところのパンツって三千円ぐらいするんだよね。ビックリした、あたしなんかダイエーで五枚千円なんだけど」
「ええっ」
正直、ゆりのは当時自分がはいているショーツがいくらぐらいなのか把握していなかったが、それにしても三千円は素直に驚きだった。
「だって……パンツなんて毎日はくものだし、汚れるし」
「穴もあくしね」喜久恵が笑った。「消耗品だよね」
「大体、誰に見せるわけでもないのに」
「ねえ。見えないところにこだわるのが真のオシャレ、とかなのかも知れないけどさ、でも三千円あったら安い席ならお芝居一本行けちゃうよ」
「CDも買えるし、文庫本だったら十冊買えちゃうもんなあ……、いや、十冊は無理か」
「無理でしょ。今時消費税込み三百円はいくら何でもそうそうないよ」
そんな話をして笑いあった喜久恵が一年後、偶々通りかかった丸井のインナーウェアセールで、古本を物色するような慣れた手つきで色とりどりのショーツを選びはじめたとき、ゆりのはぎょっとした。二人とも、系列の女子大に内部進学していたが、学部が分かれ、滅多に顔を合わせなくなっていた。前期試験が終わって夏休みに入ったばかりで、会うのは入学式以来だった。
「キク、いつのまにそんな高いパンツ買うようになったの?」
喜久恵が手にとって眺めているショーツの値札、赤字で書かれた「sale 1980」をさりげなく見やって、からかう口調でゆりのが言うと、喜久恵は色違いに手を伸ばしながら生返事をした。
「や、普段は相変わらずダイエーだよ。……なんかねえ、九月のあたまに旅行するかも知れなくて、彼と」
かれ、という代名詞に撲たれたような気がした。いつのまに? 気になる男の子と言ったら、漫画の登場人物か架空の名探偵だった喜久恵に、恋人? そしてそのとき、それまで深く気にすることもなく聞き流してきた「勝負下着」という言葉の意味を、ゆりのは初めて諒解したのだった。思ってもみない事だった。見慣れたはずの喜久恵の横顔に、目や鼻や口を福笑いのパーツのように一度ばらばらにして置き直したような、へんな違和感をおぼえた。置いて行かれたというショック、いつのまにか自分の知らない世界へ踏み出していた喜久恵への疎外感、何も知らず、何も考えずいつまでものんきに子供の感覚でいた自分への居たたまれなさがごちゃごちゃになってゆりのを襲い、やっとのことで「そうなんだ」と呟いた。
喜久恵と食事をしていて、はずみで恋人とラブホテルに行った話を聞かされたこともある。「服を脱がせてくれるじゃない、ストッキングがいっつも大変そうなんだよね、伝線しないようにそろそろーって。自分で脱いだって引っかけるときあるし、一本や二本気にしないよ、って言うんだけど」ナシゴレンに卵を混ぜながらあっけらかんと喜久恵は笑った。
ああ、男の人とつきあって、一緒にベッドに入るということはそういうことか、無理やり笑おうとしながらゆりのは思った。性的なことへの過剰な嫌悪感はわたしにはない、とゆりのは思っていた。「体を求められると思うと怖くて男の子とつきあえない。体じゃなくて内面を、本当の私を見て欲しい」と潔癖な顔で言う少女たちを、ゆりのは軽蔑していた。純情ぶって。そういう女に限って、舌の根の乾かぬうちに平気な顔して男とホテルへ行ったりするくせに。そんなことは、わざわざ大仰に言いたてるまでもなく、多かれ少なかれ思春期には誰でも思うことだ。素裸になって体に触れられ、異物を挿入されるという未知の行為が、少しも怖くないという方が奇特ではないか。怖いか怖くないかと問われればそれは怖いに決まっているけれど、だからといって、わたしはとくべつ清純なのよ、なんてポーズをとったりは絶対にしたくない、厭らしい。そう思っていたのだ。
その夜、喜久恵と手を振って別れ、地下鉄に乗るためにひとり新宿駅の地下道を歩きながら、思わずゆりのは身震いをしてシャツの衿元を強くかき合わせた。辛いエスニック料理で体は温まっていたし、寒い季節ではなかったのに、そうせずにはいられなかった。胸元に伸びてきてボタンを外す手を思い浮かべたら、泣きたいくらいの嫌悪感が込み上げた。忙しない足どりのビジネスマン風の男の右手が、すれ違いざまゆりのの太腿にぶつかる。誰かの手で服を脱がされるなんて想像するのも嫌だ。喜久恵と「抱かれたい俳優ランキング」を発表しあい、わたしの一位は永遠に福山雅治だね、などと無邪気に言っていた自分が思い出され、恥ずかしい、バカみたいと唇をかんで俯いた。涙がこぼれそうなのを必死で堪えた。
その翌年の夏だったろうか、ゆりのはひとり、池袋の西武百貨店の夏物在庫一掃セールをのぞいていた。サンダルを選び終え、靴売り場から三階の洋服を見に行こうとして、高校生のときいつも横目で見ていたインナーウェア売り場の横を通った。何故か足が止まった。どの売り場も人でごった返していたのに、そこだけが無人だった。あたりを窺うようにして、ゆりのはセールのワゴンにそっと近づいた。
何の気なしに拾いあげたのがお尻の部分がほとんど紐だけのソングで、ゆりのはぎょっとした。振り返ると、ハンガーに吊られたスリップは透け透けで、ブラジャーにはレースがぎっしりついている。見られることを前提にしたデザイン。その目的に思考が到達した瞬間、いつかの嫌悪感が生々しくよみがえった。
わたしにはどうせ必要ない。……見てくれる人だっていない。ゆりのは踵を返し、早足で立ち去った。急いで最近お気に入りのショップへ走り、Tシャツを一枚買った。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?