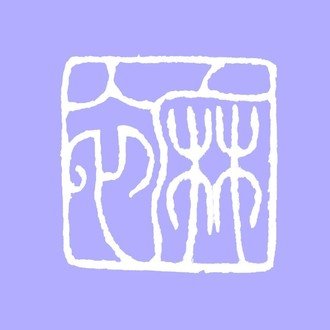リップスティックのL
1.
校舎の裏手のフェンス越しにカテドラルの尖塔が見える。あれが自分の通う学園のチャペルだったらいいのに、と渡り廊下から桐(キリ)はいつも思いを馳せた。物語のなかの寄宿学校(ギムナジウム)に通う少年たちは、あんな屋根の下で朝ごとに讃美歌を合唱しているのだろうか。ブラウスの衿元にタイを結び、半ズボンをサスペンダーで吊り、靴下どめでハイソックスを留めている少年になって、遠く聞こえる笛の音や号令、器楽の練習曲を背に、午後の授業をエスケープする気分を楽しみながら桐は旧講堂へ向かったものだ。二人だけの秘密の場所で友だちが待っている。学業に秀で、運動神経も抜群、優等生の資質を持ちあわせていながら教師には従順に振舞わず、大人びて不良じみた翳のあるきれいな相棒。
李里(リリ)そのものだ。
桐は我に返る。旧講堂でいま桐を待っている李里、そこで李里に告げなければいけないこと、そうした現実に引き戻されたのだ。鉛のかたまりが重苦しく胸につかえているこんなときでさえ、いつもの夢想を巡らせる自分をほろ苦く思うと同時に、桐は束の間なぐさめられた。
無意識に唇にふれる。ろくに手入れもしていないので、カサカサに乾いていた。薄い皮膜を引き剥がしたあとが微かに痛む。舐めると血の味がした。
渡り廊下の向こうにひっそりと佇む旧講堂は、二人が最も長くともに過ごした場所であり、はじまりの場所でもある。そしてこれから、終わりの場所になる。
2.
桐が中等科にあがった頃、まだ香山記念ホールは工事中だった。新しいホールが完成してから、式典や行事はほとんどがそちらで行われることになって、それまでの講堂は急速に存在感が薄れ、専ら演劇部の稽古場として使われるようになったのだった。現在の旧講堂で行われた入学式は、桐たちの代で最後だった。
華胥女子学院は幼稚舎から大学までの一貫教育を誇る私立校だ。卒業、入学と大仰な式をやったところで、変わるのは背景の校舎だけで役者の顔ぶれはさほど変わらない。
そのなかで李里は最初から鮮烈だった。座っていることに退屈しきってあくびをかみ殺した桐の目の前を、見知らぬ顔の妙に唇の紅い少年が横切っていった、ように見えた。はっとして目で追いかけたが、後ろ姿は紺色のプリーツスカートの群れに融けてしまって、刹那の印象を確かめる術はなかった。ショートカットのすっきりした衿足と、うなじの潔い白さだけが目に残った。
同じクラスの生徒だということはすぐにわかった。中等科を受験して入ってきた李里は、連綿とつづく同じ環境・同じ関係のなかで皆顔見知り、昼休みには昔からのしきたりのように机の島が出来上がる教室で、近づきがたい横顔を見せていた。誰かと寄り集まることも、誰かに擦り寄ることもなく、自然にひとりでいた。
初等科の六年間を通じてとうとう周囲に溶け込むことができず、このままあと同じだけの月日を同じ環境で過ごすのか、と牢獄に繋がれるような失望とともに中等科にあがり、生粋の内部進学生であるにも関わらず孤立していた桐は、馴染まないことに何ら苦痛を感じていない李里の佇まいに、強く惹かれた。
二人が近づく最初のきっかけが生まれたのも、旧講堂でだった。入学式から一週間ほど経った放課後、演劇部の新入生歓迎公演を見学しようと桐が講堂に行ってみると、入り口から澄んだピアノの音色がこぼれていた。ショパンの「夜想曲(ノクターン)」だ。おそるおそる中を窺うと、堂内はがらんとして、舞台の袖近くに置かれたグランドピアノが鳴っているほかに人影はなかった。予想していた光景と違うことに首を傾げつつ、桐はそっと中に入った。きし、きし、と歩くたびに木の床が小さな音をたてる。
演奏者は李里だった。またしても一瞬少年に見えて、息をのむ。徹底した男子禁制を敷き、年老いた男性教師が数人、肩身が狭そうにしているだけの学院内に少年などいるわけがないのに、或いはだからこそなのか、ともかく李里に少年の姿を幻視する自分が不思議で、桐は鍵盤に向かう横顔をじっと見つめた。銀縁の眼鏡の奥の細く涼しげな眼のせいか、「白皙」という言葉を想起させる額のせいか。意志の強そうな薄く紅い唇のせいか。
ピアノが止んだ。凝視されているのを感知した李里が、切れ長の瞳を見開いて桐を見ていた。桐が慌てて視線を逸らすより早く、李里は目を伏せた。
「……すみません。使うなら退きます。誰もいないのをいいことに、勝手に弾いていたから」
初めて聞く李里の声は容貌に反して柔らかい。桐を級友だと認識していなさそうな態度に、桐はうろたえた。
「違うんです、違うの、あの……そうじゃなくて、……演劇部の、劇を、」
新入生歓迎公演を観に来たのだと、桐はしどろもどろに説明した。
「そろそろ時間のはずなのに、誰もいないから……」
桐が持っていたチラシを広げると、李里はピアノの前を離れて歩み寄って来、頭を近寄せて覗きこんだ。ブラウスの衿元に結ぶことになっているはずの臙脂色のリボンがなく、ボタン二つぶん胸元が開いている。
「これ、明日の日付だよ。一日間違えてる」
李里が愉快そうに公演日時の欄を指差した。桐は思わずあっと声を上げ、頭を抱えてしゃがみこんでしまいたくなった。李里は真っ赤になっている桐に構わず、失礼、と藁半紙を取り上げた。触れた長い指先が冷たい。
「ふうん、『小鳥の巣』を演るのか」
「読んだことあるの?」
「あるよ。萩尾望都は好きなんだ。君は?」
桐はかぶりを振った。
「ないけど、面白そうだなあと思って」
あれは初等科の一年生だったか二年生だったか、自らも華胥女子学院出身の母に連れられて、中等科と高等科が合同で行う文化祭に出かけたことがあった。詳しい経緯は覚えていないが、母の校友の姪だかが出るというので、演劇部の発表を観たのだ。その芝居はまだ十歳にもならない桐にもひどく印象的だった。確か、ヨーロッパの寄宿学校の少年たちの物語だった。話の筋は忘れてしまったが、舞台に立っていた部員たちの中にひとり、群を抜いて格好良く少年役を演じていた長身の生徒がいて、桐は子どもごころにときめいた。その人のことはずっと忘れられなかった。
それを話すと、李里は興味深げにふうん、と言った。
「去年、文化祭を見に来たけど、そういえば演劇部は見なかったな。見ればよかった。……面白そうだね、良かったらおともさせてくれない?」
「もちろん!」
その場でぴょんと飛び上がりそうな勢いで、桐は即座に答えた。こんなふうに李里と親しく口をきくチャンスができるとは思ってもみなかった。正直、ひとりで行くことには少々気後れしていたので、一緒に行く仲間が出来るのは頼もしくもあった。
「あ……そういえば、ごめんね、邪魔しちゃって」
「全然。先生かと思ってちょっとヒヤッとしたけど」
「上手だね、ピアノ。好きなの?」
「親の言いつけでずっと習っているだけ。でも、たまに弾きたくなるから、嫌いじゃないんだろうね。何も考えずにいられるし」
李里の、ほんの僅かに口の端が歪む笑い方と素直でない物言いが、桐には大人びて見えた。もっと話をしたかったけれど、それ以上は話すことがなかった。
「……じゃあ、明日」
「うん、また」
李里は何事もなかったかのようにピアノに戻り、桐はそのまま李里を眺めながら曲を聴いていたい、という思いを振り切ってその場をあとにした。
翌日、二人が連れだって同じ時間の同じ場所に行くと、舞台には緞帳が下ろされ、パイプ椅子が並べられて既に十人ぐらいの生徒が席を占めていた。
『ポーの一族』の一挿話を縮めて脚色した新入生歓迎公演は、教室から借りてきた机と椅子を並べ替えて場面転換を行い、照明もボーダーライトとホリゾントのみの簡素な芝居だった。ただ、原作はうまくアレンジされており、演技もよく練習してあった。ブレザーにリボンタイの制服に身を包み、「きみ」「ぼく」と言い交わし、薔薇を口にする少年たちの世界に桐はすっかり惹きこまれた。スカートの少女たちが群れる学院内で、舞台の上にだけ存在を許される少年たちの世界は魅力的だった。
特にひとり、他を圧倒する存在感の「少年」がいた。すらりと背が高く、掠れたような低い声の、キリアン役だ。ズボンをはいて男言葉を使ってもなかなか「少女」の要素が抜けず、演技でそれをカバーしている部員たちのなかにあって、演技はそれほど巧くないにも関わらず「彼」は少年らしく見えた。その感じは、李里を初めて見たときの感覚に通じているように思え、桐は途中で隣に座る李里を何度か盗み見た。李里は背筋を伸ばし、膝の上に両手をきちんと揃えて目の前の芝居に集中していた。
熱のこもった拍手を受けて劇は終わった。カーテンコールで、下りた幕の前に一列に並んでお辞儀をした役者たちのなかにキリアンはいなかった。続いて行われた入部説明会でも、喋ったのは主に小柄で声がよく通るアラン役の生徒だった。このアランを演じた藤緒(フジオ)という高等科の三年生が部長で、後日、桐と李里の入部届を受理してくれた。藤緒と同級で、副部長の杏名(アンナ)がエドガー役だった。この二人も息の合った演技を見せ、ワルツのシーンなど客席をかなり湧かせた。
それでも、桐と李里の話題はキリアンに終始した。
「格好良かったねえ」
「格好良かった。本当に女の人? と疑ってしまうくらい」
二人は同時に溜め息を吐いた。
「あんな感じだったんだ。子どものときに見て、格好良いなと思った人も」
「案外、本人だったりしてね。高校生とは思えない大人っぽさだったし」
「まさか。……似ているような気はするけど」
桐と李里が新入部員として演劇部に加わった最初の日の活動は、部室での顔合わせだった。クラブ活動は中等科と高等科の合同で行われることになっており、演劇部の活動部員は各学年五人前後で、総勢三十人弱。部員たちは順々に自己紹介し、新入生歓迎公演のキャストは「『小鳥の巣』ではマチアスを演りました」といった具合に、自分が演じた役名を付け加えた。役をもらっているのはほとんどが高等科の部員で、中等科の部員は一部の三年生をのぞいて概ね裏方に徹していた。
そのなかにもキリアン役はいなかった。『小鳥の巣』を見て入部を決めた一年生のうち、「彼」に魅了されていたのは桐と李里だけではなかったようで、何人かがもの言いたげにもじもじしている。その様子を察して藤緒が何かを言いかけたとき、ドアが開いた。
「ごめん、遅くなった」
長身を黒一色に包み、サングラスをかけて現れたその人に、あ、と全員が声にならない声を上げ、それが呼吸を合わせる合図だったかのように「蓮実先輩、こんにちは!」と上級生たちが声を揃えた。
「こんにちは。申し訳ない、よりによって顔合わせに遅刻するなんて。……初めまして、八十七回卒業の蓮実です」
蓮実は新入部員に向かって軽く頭を下げ、サングラスを外した。年齢が一つ二つしか違わない中等科の上級生たちでさえ大人びて映る一年生の目には、高等科の部員は手が届かないほど大人に見えたが、蓮実はさらに別次元で、外見こそ学生たちに交じっていても違和感がないものの、完全に大人だった。
「うちは顧問の先生は相談役みたいな形で、実際の練習では主に卒業生の方に監督・指導していただいてます。蓮実先輩は特によくいらしてくださるので、皆さんもこれからお世話になる機会が多いと思います」
副部長の紹介を受けて、蓮実は自嘲的に呟いた。
「暇なだけだよ、私は」
「もう皆さんお気づきかも知れないけど、先日の新歓公演にも蓮実先輩に特別出演してもらっちゃいまして……」
「こら藤緒、そればらしちゃだめだって言ったろうに」
蓮実が部長の頭を軽く叩いた。叩かれた藤緒は嬉しそうに、すみません、と舌を出す。
「キリアン……ですよね?」
一年生のひとりがおずおずと聞いた。それは蓮実が入ってきた瞬間に皆が気づいていたことを、念の為に確認する問い掛けだった。蓮実は苦笑まじりに頷いた。
「おかしかったでしょう。いい歳をした大人が、現役の中高生に交じって十代の男の子の役をやるなんて」
「全然ですよお! 毎回客演してほしいぐらいです」
はしゃいだ声を出したのは、中等科二年の梨世(リヨ)だ。その能天気な調子に杏名が少し慌てて、本来キリアンを演るはずだった部員が公演当日に三十八度の熱で寝込んでしまい、その日の朝急遽頼み込んで蓮実を代役にたてた、という経緯を説明した。
「キリアンの台詞が入っているのが蓮実先輩だけだったので、無理を言ってお願いしたんです」
そもそもこの『小鳥の巣』を脚色したのは蓮実であること、現役の時にも蓮実は一度キリアンを演じていたことを、桐はあとから知った。中等科一年のときに、当時高等科三年の蓮実のキリアンを見て入部したという藤緒は、このハプニングをむしろ幸運と捉えているふしがあり、もともとのキリアン役の部員は居づらそうにしていた。ただし宣伝という面だけから見れば蓮実の効果は抜群だった。桐は、例の子どもの頃から忘れられない男役が蓮実だったということを、ほぼ確信し、あらためて蓮実に惹かれていた。李里も同じだったらしく、二人は蓮実への憧れを共有し、わかちあうことで思いを深めた。
「いつもワイズかギャルソン着てるよね。いいなあ、黒が似合って」
「あと十年経ってもあんなに格好良くなれる気がしないよ」
「なれるよ、きっと」
「ほんとォ? リイ君ならなれるかも知れないけど」
桐は李里のことを「リイ君」と呼んだ。李里には、「リリちゃん」などとは呼ばせない硬質さがあった。「リイ」という響きが連想させるオリエンタルな異国情緒も、李里に似合っていた。
二人は中庭を横切っていた。薔薇の花壇に目をやった李里が、蕾のひとつを指差した。
「――食べておしまい。その開きかけたやつ」
「えっ?」
「キリ、もう忘れちゃったの? この前の『小鳥の巣』のエドガーの台詞じゃないか。エドガーとアランが、温室の薔薇を折った埋め合わせに蕾を買って、植える場面」
「よく覚えてるね」
「覚えるくらい読んだ。萩尾望都の『ポーの一族』、それも『小鳥の巣』を演るなんて、お手並み拝見、原作を台無しにしてたら途中で椅子を蹴って帰ってやるつもりで君について行ったんだよ。……そうしたら逆に取り込まれてしまった。あのキリアンは反則だよ」
李里はなにげない手つきで薔薇の蕾を手折った。
「あっ、花どろぼう」
「――どうぞ、ぼくはきみからもらう」
蕾を桐の眼前に差し出して、李里が言う。先刻の続き、エドガーに応えるアランの台詞だ。瞳をのぞきこまれて、脈拍が速くなるのを感じながら桐は差し出された蕾を受け取った。物語を忠実になぞって、李里は桐にふわりと抱きつき、くすくす笑いながら桐の肩に顔を埋めた。李里の髪から薔薇の香りがした。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?