
クリエイティブ小山 ✔︎✔︎︎︎︎
ライブの開演5分前、出順が三番手ということもありながら、緊張と暑さでのどが乾いた。その日のライブは『オリーブゴールド』というマセキ芸能社のオーディションライブ。動画審査と最終選考を通して出させてもらっている大事なライブ。出番に遅れるなんて許されないが、のどが乾いた万全でない状態で出る気もサラサラなかった。しかし買ってる途中でライブははじまるし、三番目とは言っても尺はそれぞれ4分、そんなに時間はない。覚悟を決めて急ぎ足でコンビニへ向かった。
会場を出て40秒、太田プロ所属一年目コンビ「サイヤング」の小さくてへんな方 クリエイティブ小山 が向かいから歩いてくるのが見えた。自分は見た目が派手である以上無視できないし、サッと挨拶してすぐコンビニへ向かおうと思った。
「おざす(お疲れ様ですの略)」
『おー!ありゃまー!何してるの?』
「ライブで」
『オリーブゴールド?』
「そすね」
計画は失敗した。こっちは歩いていたのに、たくさん話しかけてきた。こうなったら最短で満足させよう。
「小山さんもライブすか?」
『そうねー、このあと疾風迅雷』
「すげー!肉食の上のやつ!がんばって下さい!」
『うーん、ありがとう、ありゃまはどこ行ってるの?』
おだてて会話を終わらす作戦 失敗
もっと質問してきた。
ぼくは焦っている。
「そこのコンビニで、飲みもん買おっかなって」
『おれは今そこのケバブにしようか、コンビニにしようか迷ってるんだよね』
「おれ飲みもん欲しいんでコンビニ行きます」
『んー、どうしようか』
「じゃーコンビニ行きましょう」
立ち話からはやく逃れたかったため下したこの決断が大きく間違っていたとのちに知る。
何を食べようか悩んでいる小山くんを置いていこうと自分の置かれている状況を伝える。
「おれ結構時間ギリなんすよね」
『じゃあそっちの方が近いよ』
たしかにぼくが行こうとしていたコンビニより会場に近いコンビニを教えてくれた。しかし小山は離れなかった。すぐさまコンビニに駆け込んで、ぼくは迷う暇もなく炭酸ではないウェルチのグレープジュースを手に取った。ここで自分の思慮の浅さに落胆する。
ふつうに新宿のコンビニはすごい混んでいた。ぼくが並んでいる間に小山くんは''チキンをバーカーみたいにして挟むタイプのパン''と''なんかの茶色いおかずが入ってそうな弁当''を手にとってぼくの後ろに並んだ。ケバブを食べようとしていた男の食い意地はすごい。相方の芸名が『BIG RICE』なだけある。そんなことはどうでもいい、ぼくはとても焦っている。だからこそ小山くんがニコニコしながらゆっくりパンにチキンを挟む未来が目に浮かんで、小山くんのその選択を決して肯定したくなかった。いま食べるものに悩んでいる小山くんのその選択に他の意見を言ってしまうと小山くんはさらに悩んで決めあぐねてしまう。そんな未来は耐えられない、ぼくは何も言わずただ列が前に進んでいくのを待っていた。何回も『どうしようかなー』みたいな音がしたが、ぼくには全く聞こえなかった。
小山くんの後ろに別の客が並んだ時、もう小山くんが食べるものは、その''チキンをバーカーみたいにして挟むタイプのパン''と''なんかの茶色いおかずが入ってそうな弁当''に確定したと思っていた。
『ありゃまー、お願いがあるんだけど』
何も聞きたくない。
『このパン戻してくるから弁当持っててくれる』
ここで小山くんがパンにチキンを挟む世界線が消えた。
「あ、いいっすよ!」
その時 弁当のおかずを確認することも出来たがその時のぼくはそれどころではなく、「もう出番が来てしまっていて、柴助がひとりで登壇する最悪の未来」が見えていた。
待ちに待ったお会計、ぼくはこの状況に置いて随分と無駄な癖で小山くんにレジをゆずってしまった。
『この弁当、あたためおねがいします』
この時、ぼくが最も聞きたくなかったセリフを言い放つクリエイティブ小山。
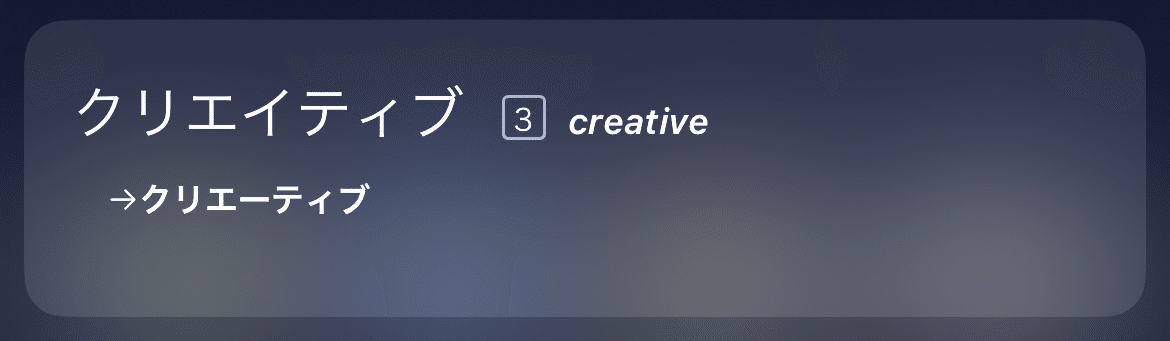
ぼくは何も言わずそれの全てを目で訴えながら、ウェルチのグレープジュースを小山くんに突きつけた。
『なんかー、あんまよく分からんけど』
「すみません、ありがとうございます」
『ありゃまは同期だからね』
「ちょっと、マジで時間やばいんで、すみません」
ぼくは小山くんに見える範囲で小走りをして、感謝を背中で表現した。角を曲がってから六倍速で会場へ向かった。もう出番はじまってたらどんなセリフで誤魔化そう、スタッフやMCに止められようとぼくは必ず舞台に立ってやるぞ、全力で走った。
ウェルチのグレープジュースをひといきに流しこみながら舞台裏に駆け込むとそこには一番手の「雨夜の分岐点」さんと喋っている柴助が居た。ぼくらは三番手、まだはじまってない。よかった。と安心しつつも時間は開演から15分過ぎている。
すこし息切れしながら''雨夜''の西堂さんに聞いた。
「え、開演おそくないですか?」
「いや、オレら終わっていま二番手のサイハテだよ」
「じゃあぼくらもう袖におらんとやないですか!!」
柴助は何も気づいていなかった。ここにもクリエイティブ小山がいた。柴助の手を引っ張って袖に向かった。ぼくは急いで結い直したボサボサな髪とダラダラの汗をかいたままスタンバイし、一旦深呼吸をした。
状況を飲み込んで、ぜんぶの汗が引いた。

教師を辞めてくれて本当によかった