
【現役銀行員×中小企業診断士ゆーき】成長のカギを握る内部環境分析の極意~売上高編~
今回は、ゆーきさんから寄稿いただいた14つ目の記事をご紹介します。
私の自己紹介記事も、ぜひあわせてチェックしていただけると嬉しいです。
「うちの売上って本当はどこが強みなんだろう?」
「日々の経営で、数字を見ているつもりなのに、どこを伸ばすべきか分からない…そんなモヤモヤを抱えてはいませんか?」
現役銀行員×中小企業診断士のゆーきです。
私はこれまで、多くの経営者の方々とお話してきましたが、事業計画を立てるときの“数字”への向き合い方に戸惑う方が少なくありません。中には「経理担当に任せている」「毎月の売上はなんとなく確認しているけど、深堀りしていない」とおっしゃる方も。そしていざ新しく事業計画書を作ろうとすると、「数字がよくわからない」「売上の伸ばし方が具体的にイメージできない」という声が上がってきます。
もしあなたも、そんな不安や疑問を抱えているのなら、本記事がきっとお役に立てるはずです。では、始めていきましょう!
Xでも、私の考えを発信しています。
https://x.com/yuuki_sanbou
導入

まずは、今回の記事の目的をはっきりさせましょう。それは、
「事業計画書を作るために必要な内部環境分析の一つである“売上高分析”を、しっかりと理解してもらうこと」
です。事業計画書を作成する際には、多角的な分析が求められます。前回の記事までで「外部環境の調査」について触れましたが、今回はその“内部編”。自社の数字がどのように成り立ち、どこに強みと弱みがあるのかを把握するために、「利益を出す×継続性」という軸をキーワードに分析を進めていきます。
実は、この「利益を出す×継続性」という軸はあらゆる企業にとっての必須条件です。どれほど画期的な商品やサービスを提供していても、利益が出なかったり、すぐに継続不可能な状況に陥ったりしては、ビジネスは成立しませんよね。これまでの私の記事をご覧いただいた方はご存じかもしれませんが、この軸に立ち返ることで、いざ分析や調査で迷ったときにもブレにくくなるのです。
今回の記事では、内部環境分析のなかでも「売上高」にフォーカスして、基本的な考え方や分解の手法を説明していきます。
1.まずは売上高を分解してみよう

前回の外部環境分析でも、“利益を出す”という言葉を具体的に分解し、どの部分に注目して行動を起こすべきかを探りました。覚えている方も多いかもしれませんね。今回は、“売上高”を分解することで、数字をより立体的に捉えられるようにしていきましょう。
「売上高」と一口にいっても、実にさまざまな要因で構成されています。例えば、業界やビジネスモデルによっては、
時間軸(年度/月/平日休日など)
商品別・サービス別
数量と単価
顧客層別(法人/個人、年齢層など)
販売チャネル別(店舗販売/ECサイト/卸売など)
地域別(国内/海外、エリアごとの売上)
時間別(年度・四半期・月・週など)
といった切り口に分解することが可能です。あなたのビジネスがどの切り口で分析すると分かりやすいかを見極めるために、まずはざっくりと全体の構造を俯瞰し、その分類をするとどのような改善策が打ち出せるのか?を考えながら進めるのがポイントです。
2.売上高を分解して何がわかるのか?

「分解した結果がわかったとして、それがどのように役立つのか?」
こうした疑問をお持ちの方もいるかもしれません。しかし、売上が伸び悩んでいるとき、どこに強みと弱みがあるのかをつかむ手がかりになるのがこの分解なのです。
たとえば、地域別に分解してみて、思いがけないエリアの売上が高いと分かった場合、そのエリアに今後リソースを集中投下することを検討できます。顧客層別であれば「シニア層からのリピート率が高いので、店舗のバリアフリー化やサービス強化を進めよう」などの施策が見えてきます。他には、ある一定の取引先や地域の売上高に依存していたら、リスクが高いと判断できます。最終的には「利益を出す×継続性」を実現するために、どこに力を入れるべきかを考えるヒントが得られるわけです。
感覚的に分かっているかと思いますが、具体的に数字で把握することで、10良くすればいいのか?100良くすればいいのか?が分かります。それによって、取るべき行動が変わりますよね?
3.なぜ売上高分析が「利益を出す×継続性」につながるのか

ここで改めて、「利益を出す×継続性」という軸に立ち返ってみましょう。事業計画書の作成にあたっては、自社が将来どのように利益を得て、どのような形で継続的にビジネスを回していくのかを明確に示す意味があります。
■利益を出すため
売上高がどのように構成されているのかを知ることで、利益に大きく貢献している事業や、逆に足を引っ張っている事業を炙り出すことができます。リソースの再配分や新事業への投資を考える際にも、この分析結果が重要な指標となるでしょう。
■継続性を確保するため
ある特定の収益源だけに頼っていると、市場環境の変化や外部リスクが起こったときに大きなダメージを受ける可能性があります。売上高の構成要素を把握し、いざというときにどこでリカバリーできるかを知っておくことで、事業の継続性を高められます。
4.売上高分析を進めるステップ

「実際にどうやって売上高分析を進めればいいの?」という疑問に応えるため、ステップを簡単にご紹介します。
1.分析の目的を明確にする
新規顧客を増やしたいのか、既存顧客のリピート率を上げたいのか、あるいは地域の知名度向上が狙いなのか。目的によって分解の切り口や調査ポイントが変わるため、まずはゴールを設定しましょう。
2.必要なデータを収集する
試算表、販売実績データの2つで十分かと思います。販売データがない場合は、紙から拾う必要があるかもしれません。ただし、すべてを完璧にやろうとすると膨大な時間がかかるので、やらないことを決めることも重要です。
3.売上高を分解する
先ほど例示した通り、商品別・顧客層別・販売チャネル別など、多面的にチェックします。
自社にとって、重要度が高いと感じる切り口を優先していきましょう。
4.分解した結果を比較・分析する
「どの部分が伸びているのか」「どの部分が落ち込んでいるのか」を可視化します。前年や過去数年分の推移、または市場の推移との比較も有効です。
一番わかりやすいのは、決算書の売上高10年推移を見て、変化があったところを深堀していくのがいいです。なぜ変化が起きたのか?どの製品?取引先?販売チャネル?などを明確にします。
5.改善策やアクションプランを立てる
分析結果を踏まえて、「この商品・サービスを強化しよう」「この地域への営業を増やそう」「新しい販売チャネルにチャレンジしよう」など、具体的なプランを作ります。ここで投資コストや必要リソースを予測し、利益や継続性との兼ね合いをしっかり考慮しましょう。
5.ここで重要なポイントがあります

「分析を進めていたら、気づけばデータだらけ。やりたいことが次々に増えて優先順位がわからなくなった…」
データに埋もれることが多々あります。つい欲張ってしまうと、本来のゴールを見失います。ここで重要なポイントがあります。それは、「あなたの企業が『利益を出す×継続性』を実現するうえで、いまどの数字がボトルネックとなっているか」を常に意識することです。
具体的には、まず一番フォーカスすべき売上構成要素を選び、優先度の低い部分は思い切って後回しにしましょう。たとえば、店舗販売で収益を重ねている企業なら、まずは店舗販売の客単価や客数の変動をじっくり深堀りするといったように、主要な収益源の“中身”を徹底的に分解・分析するのです。そうすることで、必要なデータや施策が明確になり、次のアクションにスムーズに移れます。
簡単に言うと大きな数字から取り組みましょう!ということ。
6.まとめ ~売上高分析が導く、あなたの次の一手~

ここまで読んでくださったあなたは、すでに「売上高分析がなぜ必要なのか」「分解の仕方とその活用方法」「どんな疑問が生まれ、その答えが何なのか」といったポイントをひととおり押さえられたはずです。
そしてもう一度強調したいのが、「利益を出す×継続性」という軸。事業計画書を作る際も、日々の意思決定においても、この軸に立ち返ることで迷いがぐっと減るはずです。
売上高を分解することで、自社の強みと弱みを具体的な数字の面から理解する。
具体的なアクションプランにつなげるために、分析結果をもとにどこを強化すべきか・どこを見直すべきかを検討する。
外部環境だけでなく、内部環境の状況を把握することで、現状のリソースや予算の使い方にメリハリがつけられる。
さあ、ここまで「内部環境分析の売上高」を軸にお話してきましたが、まだまだ内部環境分析には多くの要素が存在します。人材の活用や設備の状況、在庫やキャッシュフローなど、挙げればキリがありません。
しかし、すべてを一度に網羅するのは至難の業。だからこそ、あなた自身が「いま必要な分析は何か」を見極めて、優先度の高いものから取り組んでいくことが大切です。
判断に迷う際は、気軽にご連絡くださいね。
次回の記事では、引き続き内部環境分析のほかの要素にも触れていきます。分析を進めていくためのヒントをお届けしますので、どうぞお楽しみに。
XのフォローやDMでのご相談もお待ちしております。
https://x.com/yuuki_sanbou
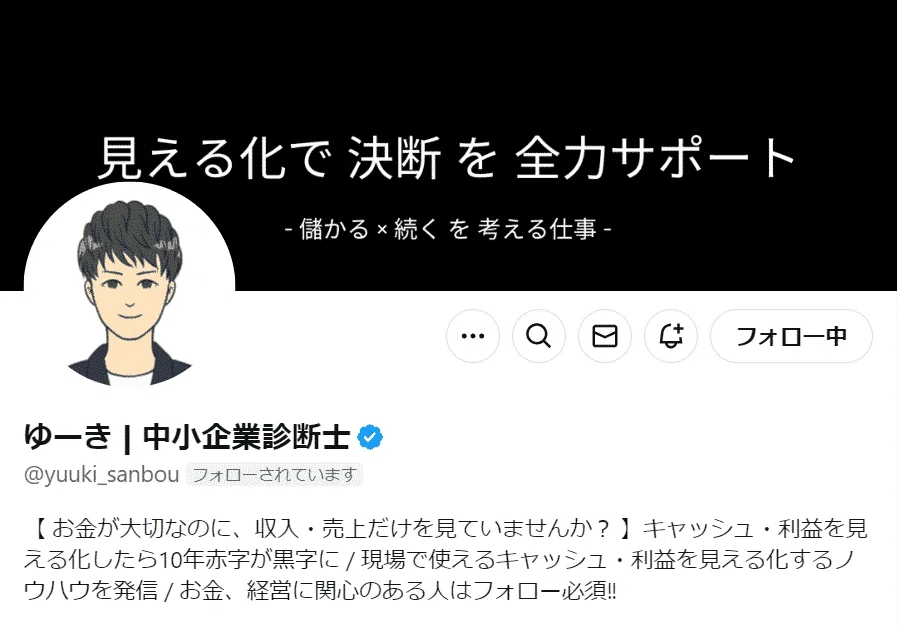
私、谷本もXで日々発信を行っています。
ぜひnote、Xについて今後もフォローをお願いします。
https://x.com/arriba0519
相談に関する質問については、以下の記事でお答えしています。
お問い合わせは、DMもしくは問い合わせフォームからお願い致します。
※氏名・社名・業種・Facebook URL・メールアドレスなどを添えてお問い合わせください。
主に銀行融資関係(資金調達)のコンサルを行っています。
資金調達が出来た際の成功報酬は基本的に頂いておりません。
理由としては・・・
・1度融資を利用する企業は、その後、2回目、3回目と利用があります。
・長いお付き合いをすることで、お互いの信頼関係を築くと共に、今後の資金繰りについて責任を果たすためです。
ですので、契約先とは最低でも毎月1回は定例でコミュニケーションを取らせて頂き、その都度、資金調達のタイミングや事業方針などについても議論をしております。
社長の望む調達金額を受けられる決算書の作成を得意とします。
銀行融資にはいくつかポイントがあります。
粉飾などによらず、目指す決算書にたどり着くよう、決算月の約半年前からすり合わせを行います。
このすり合わせとは、紙面による数字との睨み合いに留まりません。企業における営業活動など、包括的に関わっております。
これは、税理士や一般的なコンサルタントでは分からない分野です。
お客様によりますが、御社での私の名刺を作ってもらい、銀行対応全般をお任せ頂いております。
銀行対応において、代表者や責任者の方にご同席頂くのは、基本的に初面談時と契約時のみです。
融資実行までの中間の交渉は、全て私がお引き受けします。
(金融機関や個別対応でお受けできない場合もあります。)
CFO的な立ち位置で長きに渡りお役に立てればと思います。
創業融資のお問い合わせも多く頂いております。(R3年実績30社程度)
創業計画書の書き方にお悩みではないでしょうか?
大口の資金調達のコーディネートも行います。
これから事業が大きく成長する中で、どのように銀行と付き合おっていくべきかお悩みではないでしょうか?
収益物件購入、不動産業者、保険営業マンからのご相談もあります。
ご自身では分からない銀行のこと、たくさんあります。
銀行内には独自のルールや文化が満ちあふれています。
現在、お付き合いを頂いている企業は東京が主ですが、リモート対応も可能です。場合によっては出張も致します。
事業を頑張る経営者の皆さまのお役に立てる記事をこれから書いていきたいと思っております。
初回30分無料相談もお受けしています。
