
【現役銀行員×中小企業診断士ゆーき】事業計画の第一歩。自社を知る。-企業概要の書き方とは?
今回は、ゆーきさんから寄稿いただいた9つ目の記事をご紹介します。
私の自己紹介記事も、ぜひあわせてチェックしていただけると嬉しいです。
「この会社、面白い!」
と一瞬で思わせたいのに、どうも伝わりきらない…。
そんなジレンマに悩んだことはありませんか?
こんにちは。中小企業診断士×現役銀行員のゆーきです。
これまで事業計画書の書き方をテーマに解説してきましたが、今回はその『入口』とも言える“企業概要”に焦点を当てます。
前回はサマリーの書き方についてでした。前回までの記事を見ていない方は、是非ご覧ください。
Xでも、私の考えを発信しています。
https://x.com/yuuki_sanbou
なぜ企業概要が重要なのか?

まず、企業概要は事業計画書の中でどんな役割を果たすのか考えましょう。
事業の全体像を簡潔に説明するセクション
企業概要は、事業の全体像を簡潔に説明するセクションです。この部分を読むだけで、「何をする会社なのか」「どのような価値を提供するのか」「どこに向かっているのか」が一目でわかるようにする必要があります。簡単に言うとあなたは何者なの?ということです。
実際に金融機関でも、最初に目を通す部分が企業概要であることが多いです。なぜならば、どんなことをやっている会社なのか理解できなければ、融資の判断はできません。事業の実態を把握する為に、まず、あなたの会社は何者なの?を理解しにいきます。
自社の事を振り返るきっかけにもなる
また、自社の事を振り返るきっかけになります。歴史やビジネスのモデルを再確認することで、自社の強みや弱みを再認識できます。分かっているつもりになっているだけで、日常の業務に追われ、意外と忘れてしまっていることも多いと思います。
こうして自社の基本情報を整理することは、次の項目である“具体的な内容”をスムーズに組み立てる基盤となります。それでは、企業概要の中に具体的にどのような要素を盛り込むべきか見ていきましょう。
書くべき内容とその順番

それでは、実際に企業概要に盛り込むべき要素を見ていきましょう。
① 経営理念
会社の存在意義や意思決定をする際の考え方の軸になるものです。何を考えて経営をしているのか?どのような情熱があるのか?を見ます。
自分が担当する先では、形骸化してしまっている企業も多く、見直すきっかけになったこともあります。基本手金は、企業の目的である「顧客の為に」「従業員の成長」「地域への貢献」の3つが含まれていることが望ましいと考えます。最近ではMVVと言ったりしますね。
② 基本情報
ここでは企業の基本的な情報を載せていきます。具体的には、設立年月日、住所、沿革、役員、主要取引先。特に沿革と主要取引先は重要なポイントです。沿革は、会社の歴史です。
どのようなことに力を入れて、どのような危機を乗り越えてきたかなど成長の過程を示すことで信用度が増します。また、主要取引先を見ることで、どのような事業をやっているか、売上増減のイメージがわきやすくなります。
③ 拠点情報
拠点情報は、基本情報の中に組み込めれば組み込んでしまっても大丈夫です。例えば、店舗がたくさんある、物流拠点が複数にわたる、製造拠点が多岐に渡る…こんな場合は、地図とともに示しとくといいでしょう。
経営改善の場合は、どの拠点を閉めるべきか?という論点もありますので、しっかりと整理することをお勧めします。
④ 所有設備
所有設備は、自社の強みをアピールする重要なポイントです。
また、取得時期や修繕履歴を明確にしておくと、投資判断の基礎資料にもなります。ここで、自社の設備情報をリストアップして整理してみてはいかがでしょうか?
⑤ビジネスモデル俯瞰図
これは金融機関がしっかりと見ます。これを見ることで、収益構造が見えてくるからです。
書き方は、図解が見やすいです。記載する内容は、使用材料、主要仕入れ先、主要外注先、自社の加工工程、物流、主要販売先、エンドユーザーと仕入から販売のフローで図解すると理解が進みます。
⑥取扱製品
自社の取扱う主要な製品を写真付きで載せると伝わります。製品・サービス名、年間の売上、販売先などの項目があれば良いでしょう。
⑦組織図
経営改善では、組織図を一番に最初にもらいます。それほど重要です。どのようなチームで戦っていくか?会社の意思決定はどのように行われているか?キーマンはどこにいるか?などヒアリングを元に紐解いていくことが多いです。名前まで載せる必要はありませんが、各部門の名前や人数、年齢、勤続年数などあると良いでしょう。
これから、人手不足になります。どの部門にどのような人財を補充する必要があるかなど検討する材料にもなります。
⑧株主資本図
実質的な支配権は、誰にあるかを確認します。株は恐ろしいです。年に1度の株主総会でこの株を活用して、決定できることが多数あります。特に中小企業だと親族間で持ち合っていることが多く、重要なことを決める際にネックになることもあります。
実際、自分が担当する会社でも有力な役員が少数株主であったため、追い出されてしまう。そんなことが起こったケースもあります。戦略的に株をどこに集約すべきか?を考えることはとても重要です。
重要なポイント

多くの人が陥りがちなミスは、「自分の視点」で書いてしまうことです。企業概要は読む人に価値を伝えるもの。そのためには、「相手の視点」で考え抜くことが大切です。
例えば、場合と顧客に向けた場合、金融機関に向けた場合、従業員に向けた場合では、強調すべきポイントが異なります。顧客には具体的なサービス内容や価値、金融機関には会社の儲けの源泉を分かりやすく、従業員には会社の基本的な考え方や今後の会社の方向性を示しましょう。
まとめ
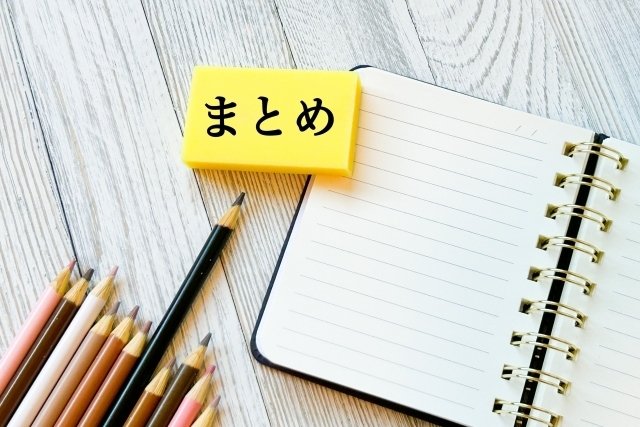
企業概要は、単なる形式的な情報の羅列ではありません。会社の本質を短時間で伝え、相手の心を動かす「入り口」です。また、自社を振り返る良い機会となり、新たな発想が出てきます。
これを読んだあなたには、ぜひ次のアクションをしていただきたいと思います。今すぐ、現行の事業計画書を開き、企業概要に記載した内容を確認してみましょう。次の1週間で以下の3つを実践することをおすすめします。
①情報のアップデート
②専門家や同僚の意見を取り入れる
③読み手視点でわかりやすい構成を追求すること
判断に迷うことがありましたら、いつでもご相談ください。では、次回は“ 財務状況 ”のセクションです。お楽しみに!!
XのフォローやDMでのご相談もお待ちしております。
https://x.com/yuuki_sanbou

私、谷本もXで日々発信を行っています。
ぜひnote、Xについて今後もフォローをお願いします。
https://x.com/arriba0519
相談に関する質問については、以下の記事でお答えしています。
お問い合わせは、DMもしくは問い合わせフォームからお願い致します。
※氏名・社名・業種・Facebook URL・メールアドレスなどを添えてお問い合わせください。
主に銀行融資関係(資金調達)のコンサルを行っています。
資金調達が出来た際の成功報酬は基本的に頂いておりません。
理由としては・・・
・1度融資を利用する企業は、その後、2回目、3回目と利用があります。
・長いお付き合いをすることで、お互いの信頼関係を築くと共に、今後の資金繰りについて責任を果たすためです。
ですので、契約先とは最低でも毎月1回は定例でコミュニケーションを取らせて頂き、その都度、資金調達のタイミングや事業方針などについても議論をしております。
社長の望む調達金額を受けられる決算書の作成を得意とします。
銀行融資にはいくつかポイントがあります。
粉飾などによらず、目指す決算書にたどり着くよう、決算月の約半年前からすり合わせを行います。
このすり合わせとは、紙面による数字との睨み合いに留まりません。企業における営業活動など、包括的に関わっております。
これは、税理士や一般的なコンサルタントでは分からない分野です。
お客様によりますが、御社での私の名刺を作ってもらい、銀行対応全般をお任せ頂いております。
銀行対応において、代表者や責任者の方にご同席頂くのは、基本的に初面談時と契約時のみです。
融資実行までの中間の交渉は、全て私がお引き受けします。
(金融機関や個別対応でお受けできない場合もあります。)
CFO的な立ち位置で長きに渡りお役に立てればと思います。
創業融資のお問い合わせも多く頂いております。(R3年実績30社程度)
創業計画書の書き方にお悩みではないでしょうか?
大口の資金調達のコーディネートも行います。
これから事業が大きく成長する中で、どのように銀行と付き合おっていくべきかお悩みではないでしょうか?
収益物件購入、不動産業者、保険営業マンからのご相談もあります。
ご自身では分からない銀行のこと、たくさんあります。
銀行内には独自のルールや文化が満ちあふれています。
現在、お付き合いを頂いている企業は東京が主ですが、リモート対応も可能です。場合によっては出張も致します。
事業を頑張る経営者の皆さまのお役に立てる記事をこれから書いていきたいと思っております。
初回30分無料相談もお受けしています。
