
【前編】建築家と土地を探すことのメリット〜安いけど癖がある…そんな土地をうまく住みこなす建築事例をご紹介します~
こんにちは。
アラウンドアーキテクチャー(以下、AA)の久保田です。
家のかたちは、それが建つ土地のかたちや立地、およびその場所にかかっている法律に大きく左右されます。
それゆえ理想の広さや間取り、空間を実現するためには土地選びが非常に重要で、そういった意味では「土地選びの段階から既に設計は始まっている」とすら言えるかもしれません。
また、ほとんどの人はその後何十年と腰を据える場所を選ぶわけですから、エリアも非常に重要です。
だけど希望のエリアだと、予算に見合った土地が見つからない……でもせっかく建築家に設計を依頼するのならば、可能な限り建築にも多くのお金を回したい……。
そんな方も多々います。そうなった場合、思い切ってエリアを変えてみるのももちろん一つの手ですが、
この記事では、「少し特殊(ワケアリ)な土地を買う」という選択肢があることをお伝えしたいのです。そして、そんな特殊な土地でこそ建築家の本領が発揮されることもある、と。
前置きが長くなりました。
本記事では、まず「特殊(ワケアリ)な土地」がどんなものかを整理したうえで、弊社が実際にかかわった建築事例を三つご紹介します。
建築家との家づくりにどんな可能性があるのか、その一端をお見せできたらなと思います。
土地の評価基準~一般的に「良い」とされる土地とは~
そもそも、土地の価格は何を根拠に決められているのでしょうか。
弊社の仕事は買主側の仲介がメインではありますが、売却のお手伝いをすることもしばしばあります(住み替えをする方の旧宅や、相続したものの処分に困っている土地など)。その際は、物件の査定をしなくてはなりません。
査定の方法はいくつかありますが、中でも最も一般的な方法が「取引事例比較法」です。近隣の類似の取引事例を収集し、いくつかの評価軸を基準に比較をして価格を決める方法です。
評価のポイントは、例えば以下のようなものがあります。
用途地域→建ぺい率、容積率が大きいほど〇
接道方位→南向きが〇
土地の間口→広いほど〇
土地の形→整形地ほど〇
前面道路幅員→広いほど〇
駅距離→近いほど〇
まあそうだよなと、納得していただけるかと思います。
これらのポイントには、「流通性」、つまり売ろうとした際にどれだけ売りやすいか(=他の人が欲しいと思うか)という考え方が通底しています。
つまり、この評価軸からはずれるほど物件の価格は安くなる、というわけです。

特殊な土地でこそ建築家の本領が発揮される
しかし、だからといって安い物件が必ずしも悪い土地というわけではありません。
上記のような評価はあくまで土地単体で見たときのものであり、そのうえに建つであろう建物の、建築的な可能性は含まれていないのです。
一見マイナスに見えるような土地の特徴も、設計の工夫次第ではプラスとして捉えることもできます。
その土地ならではの特徴や周辺環境を読み解き、それらを生かしながら豊かな空間を立ち上げること。それこそ現代の建築家が最も得意とするところではないでしょうか。
さて、ここからは具体例をご紹介します。
いずれも弊社が土地の仲介、住宅ローンのサポートを行った物件です。
事例①:2700(設計:IGARCHITECTS)

こちらは弊社・安藤が担当した物件です。
若い夫婦ふたりのための住宅で、設計者はIGARCHITECTSの五十嵐理人さん。
この土地は下の図の通り長方形の角地ですが、長手方向が約16mあるのに対し、なんと短手は約2.9mしかありません。そう、「超細長い」のです。
そのため、大通り沿い・駅徒歩10分という好立地にもかかわらず、比較的安価な価格で購入することができました。
■「都市計画道路」に切り取られた土地
そもそもなぜこのような超細長い土地が生まれたのか、不思議ですよね。
これには敷地南西側の「都市計画道路」が関係しています。

都市計画道路とは、市街地の道路状況の改善や計画的な都市づくりのために、都市計画によって計画された、地域内の交通・通行の中心となる道路のことをいいます。要するに、幅が広くて車がビュンビュン通るような道のことです。
(参考:https://iqrafudosan.com/channel/cityplanning-road)
都市計画道路はたいていの場合、既存の道路を拡幅することでつくられますが、その建設予定地を行政が各所有者から買い取ることで進められます。
この土地は、売りに出される以前は丁度今の倍くらいの横幅がありました。
しかし、南側の都市計画道路の拡幅のために土地のおよそ半分が収容されることとなり、結果残ったのがこの細長い土地だった、というわけです。
■細長さを豊かさに変える建築
では、こんな細長い土地の上に建築家・五十嵐理人さんはどのような住宅を設計したのでしょうか。この住宅はタイトルの通り、横幅が2700mm(=2m70cm)しかありません。
そのため、普通の家でいう廊下のような移動のための空間が、同時に生活空間を兼ねています。各部屋を明確に区切らず緩やかにつなげることで、面積以上の広がりを感じられるよう設計されているのです。



またこの家の一階の上部には、周囲が開けているという立地を生かして、四周に渡って横長の窓が設けられています。そしてその高さが一定である一方で、床は奥に進むほど高くなるようにつくられています。つまり、立つ位置によって窓との距離が近かったり遠かったりするわけです。
横幅が狭いことで強調される「奥行」と、移動に合わせて刻々と変化する空間の質(天井が高い/低い、明るい/暗い、開けている/閉じている、など)とそのリズム。
この豊かな空間は、この土地でしか獲得しえなかったものだと思います。
※より詳しく知りたい方は、以下のリンクよりIGARCHITECTSのHPをご覧ください!


さて、この土地を更地の状態で見たとして、こんな素敵な家が建つなんて誰が予想できるでしょうか。
実はこのプロジェクトでは、お施主さんがこの土地を購入する前に、前もって五十嵐さんからアドバイスをもらっていました。この土地ならこんなことができて、例えばこんな感じの家がつくれるだろう、と。下の二枚は購入前に五十嵐さんがパッと作成したラフ案です。
このような特殊な土地は、物件探しの段階から建築家に関わってもらうことではじめて、安心して買うことができるのだと思います。


■住宅ローンを組む場合は注意が必要
この家も一般的な家と同じように住宅ローンを組んでおり、弊社はそのサポートを行いました。しかし、実はその銀行選びは難航してしまいました。
金融機関から住宅ローンを借りる際、一般的にはその対象となる土地や住宅を担保に入れる必要があります。万が一借主が返済できなくなってしまったときに、その物件を売りに出して債務を回収するためです。
そのため、担保となる物件はある程度の価値が認められている必要があります。そしてこの担保評価もまた、前述した「流通性」という価値基準のもとでなされます。
この物件の場合、その形状が特殊すぎることから担保評価ができない(=価値が見込めない)という金融機関が多数でした。
とはいっても、担保評価の基準は金融機関ごとに異なります。
そのため、たとえ一つの金融機関がダメでも諦めないこと、私たちのような専門家の視点から、しっかり金融機関とコミュニケーションを取っていくことが非常に重要です。
弊社では様々な金融機関にヒアリングをし、結果として、無事に融資を受けられる銀行を見つけることができました。
※建築家住宅でローンを組む場合、気をつけなくてはならないことは他にもあります。以下の記事で詳しく書いてますので、気になる方はぜひこちらも読んでみてください。
後半に続きます。

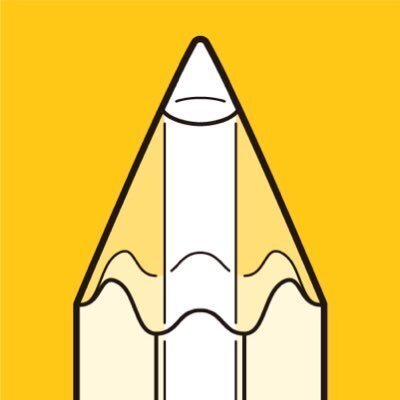
P.S.
この「2700」は、土地購入後の設計段階においても、数々の荒波を乗り越えて完成したプロジェクトです。というのも、この家は当初は鉄骨造で設計されていたようなのですが概算見積もりが合わず、その後木造での検討を経て、最終的にRC造に辿り着いたようです。建築設計はお施主さんの要望や、昨今の高騰する建設費など、さまざま事柄を調節しながら進めていく必要があります。
一般の不動産会社は、物件の契約・引き渡しが終わったらそこで仕事完了、以降その家づくりに登場することは基本的にはありません。しかし弊社では、土地の引き渡し後も建物が完成するまで、全体のお金やスケジュールのマネジメントなどのサポートを、建築家の設計と併走しながら行います――これについてはまた、別の機会に記事にしようと思います。
