
【イルミネーションスターズ】はこぶものたち【シャニマス】【まとめ・感想】
アイドルマスターシャイニーカラーズのユニット、イルミネーションスターズのイベントコミュ【はこぶものたち】についてのまとめと感想です。
様々なコミュについて無限にネタバレをします。その上に偏見も多い。
今後読む気がある人は公式を楽しんでからどうぞ。特にそうではない人は読んで興味をもってくれたらいいな。
挨拶
こんにちは。
イケメン天才最強モテモテイケイケ社会人存在、ありれるれんです。皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
進級が決まったり、受験が終わったり、人事の問題が決まったり、引っ越しに忙しなかったりしましたか?
新規のイベントに歓喜したり、限定が引けなくて泣いたり、大吉こがたんの環境破壊力に呆然としたり、天井を叩いたり、高山に脱衣を要求したり、……していますか?
きっとご機嫌な毎日をお過ごしのことでしょう。
そんなご機嫌なあなたであれば、きっとこの長々とした記事を読むだけのあらゆる類の「余裕」があるはずだ。
この記事は比較的長いと思われる。皆に要求される余裕として、例えば、絶対に共通する時間のことだけ取り上げてみたい。日本人が文章を読む速度が平均800文字/分(ソースなし)であるらしいことから計算すると、この記事を読むには平均で1時間30分程度かかるらしい。
これを読んで「とりあえず読んでみるか……?」となったあなたは人生の才能がある。自信を持って生きて良い。「読むかよ!長いんじゃい!」となったあなたは、やはり人生の才能がある。大いに自信を持って生きると良い。
ただ、この記事は僕が2022年の2月の休日を費やしたものでもあるのだ。個人的な思いとしては、折角なら見ていって、そして「スキ」して、さらには共有してくれても悪くないんじゃないかと思わないでもない。
そして僕自身がこういうことだろうという自信を持っているとはいえ、これは厳密にはただの感想であり、個人的な解釈であることも併せて述べておく。
それではどうぞ読んでいってください。
前提とする知識
1. 主体と客体について
主体と客体の対立は『アイドルマスターシャイニーカラーズ』という作品の根幹的主題である。物語というもの一般の骨子でもある。
私たちの自意識は、存在を主体と客体で認識している。主体とは自己の意志によって行為する存在であり、客体とは主体の行為の対象となる存在である。
この主体と客体の認識はあらゆるところに表象化する。
その端的な例を挙げると、「人の目を気にして」という慣用的な表現がある。「人の目を気にし」た人間は、他の主体による「見る」という行為によって、自らを「見られる」客体にされ、その客体化によって自分の意思に基づく行為が制限されている。
もう一つ例を挙げると、シャニマスには一部界隈で「大丈夫教」と呼ばれるものがある。彼らは、一部のアイドルがシャニPの「大丈夫」という言葉に依存しているのではないかと主張している。彼女らは、様々な理由によって不安を感じたとき、シャニPの「君は大丈夫な存在である」という客体化を受けることにより安心を得ている。これらは、主体と客体の対立関係の一部始終を指している。
例えば【ノー・カラット】では、緋田美琴やダンサーたちに「見られる」客体的な存在として焦りを感じる七草にちかを、「見る」主体的な存在として七草にちかを思い遣れない緋田美琴をそれぞれ象徴的に描いた。
2. 実存主義
実存主義は、サルトルによると普遍的・必然的な本質存在に相対する、個別的・偶然的な現実存在の優越を本来性として主張、もしくは優越となっている現実の世界を肯定してそれとのかかわりについて考察する思想である、とされる(「実存は本質に先立つ」)。
西洋哲学としての実存主義
近代科学が発達して以降の西洋においては、様々なものが科学にによって革新的に進歩した。
科学技術や産業構造に対してもそうであったように、特にキリスト教を代表とする宗教的思想に基づいた彼ら人間存在の精神に与えた影響は甚だしものであった。特に、いわゆるインテリジェンスデザイン説を根本的に否定することになったダーウィンの『進化論』などの影響は大きかった。
これを受けて彼らの宗教に基づいた思想習慣であり存在証明である人間性に対立する動物性の否定という論理は、動物性と人間性が対立するものではないという近代科学の結論により致命的な破綻をきたした。
そして神は絶対的に正しいわけではないという事実が明らかになったことにより、彼らの考えるキリスト教世界における絶対善というものも絶対的に正しいものではなくなった。獣性を罪、あるいは悪魔とし、それを懺悔するという思想習慣から本質的な(少なくとも彼らにとって普遍的な・必然的な)正当性が失われたのだ。
絶対善という安心をもたらすための目標が失われたことによる彼らの不安は、二度の世界大戦によってより大きなものになった。
絶対的であるべきキリスト教の隣人愛という発想に真っ向から矛盾する西洋国家群同士の破壊的衝突や、キリスト教に代わり台頭した進歩主義の発明による進歩的大量破壊、故郷としての国家の崩壊、あるいは軍事行動により家父長などを失うのである。
これによって、彼らの存在を承認していた様々な存在が失われる。彼らの存在証明にについての不安は更に大きく膨らんでいった。
諸君、嵐は終わった。にもかかわらず、われわれは、あたかも嵐が起ころうとしている矢先のように不安である。
そのような状況を背景に成立していった思想の大系が実存主義である。
この哲学における思想家は、近代科学によって失われた本質という不確かなものよりも、存在することが確からしい現実の存在に彼らの拠り所を求めた。
実存主義の考えには、「発生した事象の中にある絶対的真理としての本質よりも、むしろ実際に発生した個々の事象そのものが常に優先されるべき事象である」としていることが共通している。
例えば、 「セッ!」に及んだとしよう。
多くの場合で、いわゆるSとMに分かれるだろう。しかしSも実際にはMの要望に応えている点ではMであるし、MもそうやってSにSであることをを強いてる点ではSだとも言える。 これをどう捉えるかに従来の「本質主義」と実存主義の違いがよく出ている。
「あくまでもSは行為する人間として主体であり、Mが行為される人間としての客体である」とかすることで、何とか定義しようとするのが従来の本質を重視する考えである。彼らは根本的な意味においては、あるいは普遍的な意味においてはどう定義することができるのか考えてきた。
一方で、「いやSもMも、実際にはSでありながらMじゃんね」と言ってしまうのが実存主義である。 現実に存在する事象そのものが本質よりも重要であると考えている。
本質的思想と実存主義は時折対立し、個人によっては受け容れられないことがありもする。
いわゆるカップリング論争においては「逆カプNG」という発想があるらしい。これは実存的に否定しきることができない可能性の提起を通して、「原作」という彼らの存在証明が揺らぐことにより発生する不安によって起きるものである。これもまた本質的思想と実存主義的思想の対立の類型であると言える。
彼ら彼女らは、思想的かつ言論的な宗教戦争を行っているのである。

日本における実存主義と葉隠
西洋の実存主義の雑解説にならって、本邦においての解説も雑にしてみたい。
本邦の支配と人間の精神生活の領域においては、君臨する主体としての天皇が常に存在していた。政治的実権は藤原氏や平家の台頭、源平の合戦などを経て、様々な実存上の変化を経験したが、天皇の名の下に任命される役職によって支配を行うという点において、天皇の権威による支配が本質的かつ綿密に連続していた。
いつの時代にも天皇を本質的主体、民衆を本質的客体とし、さらに相互に積極的干渉が行われないことによって、天皇の存在と民衆としての存在証明は自然に安定している。
そして私たちは天皇の名のもとに安穏な承認を受ける臣民として、時にお祭りに殺到してみたり、文化に現を抜かしてみたり、天災で酷い目に遭ってみたり、小粋に戦などをしてみたり、天の下に覇を唱えてみたり、歌を詠んでは割腹したり、……していたようである。
この国家の権威の――天皇の権威の――危機は応仁の乱くらいのものである。ここでは二人の天皇がそれぞれに自らの正当性を主張することで、朝廷が南北に分裂し、本質的な権威が曖昧になった。
つまり本質が不確かになることで「官軍」、「賊軍」が不明になってしまい混乱を来たしたのだ。この時代においては現実的存在としての損失もそうであるが、それよりもむしろ人々の精神世界において大きな破壊と荒廃を経験している。
天皇の存在によって、西洋の人間と比較したときの私たちは、それほど大きな不安を経験せず、つまり認知が破壊的に歪むほどの複雑かつ強力な支配や、その喪失による不安からは自由であったようだ。
それでも、私たちの精神世界は、大陸から伝来した哲学的側面を多分に含む仏教や儒学、実存的政治と軍事を担うことになった武士の影響や、産業構造などの基本的な状態をも反映している。
そうして、私たちの精神生活と支配においては、主体としての天皇という単純な国家の本質と、個人の範囲に及ぶことになる貴族や武士が実行する政治や単純なままではない産業と生活の変化などという実存が矛盾していた。
当時の私たちも、この矛盾には人間に処せる程度の不安を抱いたことが窺い知れる。
承認する本質的で極めて単純な権威である天皇というものが明確な肉体を持って存在しているという確かさと、実存的な支配者としての政治を行う幕府、そして平和な時代の中で構築された複雑な実存を形成することとなった社会、それらの蜜月である江戸の時代には、様々な哲学・思想についての本が執筆されている。
その中には、人間にとっては余りにも複雑化した社会を形成している世界に生まれ落ちた今日の私たちにも通用する『葉隠』という、本質と実存の接点について書かれた隠居老人による居酒屋トーク本がある。
ここでは葉隠的な実存の解釈があることを先に断っておく。

概要
本イベントコミュは、複雑な社会における本質的な善悪は実存的事象に優先しないことを示し、それでいて倫理を重要なものと主張する。さらにそうすることで私たちが晒されることになる不安や苦しみの中で、それでも全力で生きる勇気を持つよう説く。
本質的かつ明確に肯定あるいは否定可能で絶対的な「善悪」、あるいは同じく明確に肯定あるいは否定可能で純粋な「主客」というものは、現実世界には存在しないことを主題とているという点において、本質および物語を否定しているとも言える。
これは物語というよりむしろ生きることについての話である。
ユニット『イルミネーションスターズ』の彼女らが仕事で関わることになったフードデリバリー企業とサッカーチームの運営に焦点を当て、炎上という事件を通して彼女らの成長を描く。
特に風野灯織に焦点を当て、人間の自然な防衛機制が引き起こす不自然な行動や、客観的に不健康かつ主観的に健康な精神と、その回復を描く。
登場人物
イルミネーションスターズは、アイドルマスターシャイニーカラーズの初期ユニットの一つである。通称「イルミネ」。
純真無垢な櫻木真乃をセンターに、元気いっぱいな八宮めぐる、クールな風野灯織で構成されている。
これまでの彼女らは、それぞれに抱えた人との関わり方や孤独に関する苦しみを、アイドル活動やユニットメンバー、プロデューサーとの相互関係の中で解決してきた。
今回の彼女らは、これまでに提示してきた存在証明に関する問題から発展し、現実的な人間社会の軋轢を経験する。
(風野灯織のSSRを非常に引けていないため私は彼女についてよく分からない。個人への言及は割愛する。)
まとめ
ここからはコミュの内容について順を追って解釈しながら振り返る。
オープニング:漕ぐ人
オープニングでは、他のユニットメンバーがレッスンや仕事に精力的活動している時期にあって、風野灯織は自身が活動の機会を持てていないことに不安を感じている。また彼女自身の意識の取り扱いが不器用であることが描写される。
今回のイベントコミュにおいて重要な主題である不安というものと、「はこぶものたち」というモチーフが提示される。
風野灯織は一人バスに乗っている。仕事やレッスンに打ち込む櫻木真乃や八宮めぐるとは別行動をしているようである。彼女はSNSであるアカウントを眺めていた。


風野灯織が追っている「兄やん」と呼ばれるアカウントは、個人へ委託する形式の食品配達業(「Ub〇r Eats」のようないわゆるフードデリバリーサービス、以下フーデリ)を生業として働いている。
風野灯織は「兄やん」に思いを馳せた。

そしてその裏では、トレーナー達とのレッスンと食事などで賑やかに過ごす八宮めぐるや、仕事を頑張る櫻木真乃が描写されている。そんなときに風野灯織はバスで一人、自転車を漕ぐ見知らぬ男の姿を追っている。
一時は配達依頼が来ないことに退屈して犬の写真を撮るなどしていた「兄やん」であったが、ピークタイムを迎えると配達を要請する通知を受け取り駆けずり始めた。
そんな彼を見て、彼女は「いいな」と口にする。
バスを降りると、大きな仕事が無事に終えた櫻木真乃がイルミネのメンバーに向けてメッセージを送っていた。八宮めぐるがいつものような陽気でその成功を喜ぶ文面を見て、風野灯織もそれに同意する。

そして、事務所にはピザやたこ焼きがあるから寄らないかという八宮めぐるの提案に「ごちそうだ」と喜ぶ風野灯織の声は弾んでいる。
しかし彼女の顔は物憂げだった。
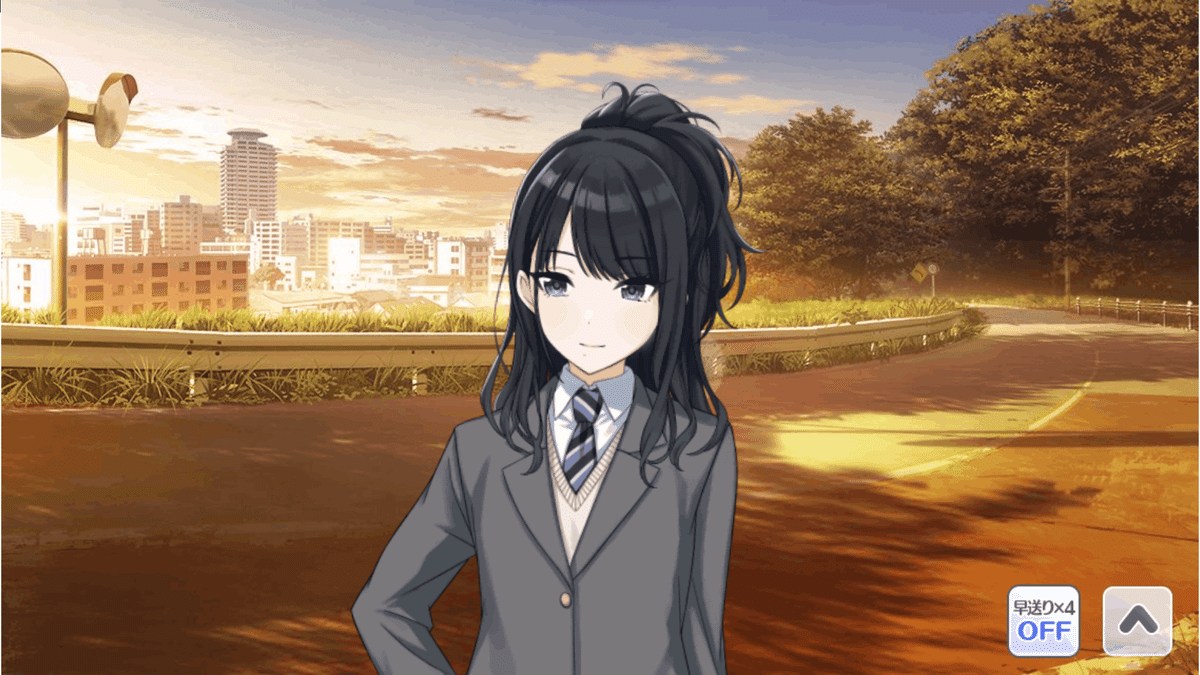
風野灯織の不安
オープニングでは、風野灯織が直面した不安という主題を提起する。
彼女が感じている不安というものは、存在証明の危機による不安である。言葉自体が持つ昨今の印象を恐れずに言えば、この不安は承認欲求として表出した。
彼女が持つ彼女自身の存在証明(僕は彼女のSSRをマジに持っていないため詳しくないが)にとって、「イルミネーションスターズのメンバー」であるという観念による客体化、つまり「櫻木真乃と八宮めぐるの隣にいる」自分という承認が非常に大きなものとなっている。
それ故に、この時間軸において、イルミネの他メンバーのように仕事に恵まれず、かと言って八宮めぐるのように誰かと睦み合うことで他の承認を得られない埋められない風野灯織は、自分がイルミネのメンバーに相応しくないという観念に直面することで不安を感じてしまっていた。
そして彼女は「兄やん」と呼ばれるアカウントに思いを馳せることで不安の解消を図っている。

彼はフーデリで働いていた。彼の発信する内容は必ずしも常に恵まれたものではない様子である。ただし彼は大変な厳しい道のりであろうと、安い報酬であろうと、自転車を漕ぐ。重いリュックを背負って、重たいペダルを踏み続ける……。twitterに発信される投稿の前向きな様子が変わることはない。苦しくても辛くても……それなら頑張る理由は自分がそうしたいからだというところに求められるのではないか?
ここではイベントコミュ【アイムベリーベリーソーリー】の「ぼくらが走る理由」が引用されている。
即ち、彼女は、『「兄やん」が自ら働く自己の主体を確認できていると想像している』ことを暗喩している。

他者の主体的行為を通して自己の主体についての意識が高まることは作品を通して描写されている。
風野灯織は、自身の主体意志を確認することができれば、「必要とされない自分」でも、つまり現在の「イルミネに相応しくない自分」であったとしても、この大きな不安に苦しむことなくいられるはずだと無意識下に主体たることを試みる。
しかし、「誰かの笑顔に近づいて」と考えたところで、彼女は新たな仕事の通知を得た「兄やん」の様子に意識を向けた。

ここでは、主体意志に基づき行為することの難しさが発生している。純然たる主体として行為しようと考えたとしても、その行為が誰かに望まれるものであることに気付いてしまえば、その認識により行為は「望まれた行為」として客体化されてしまう。
彼女は自己の主体を確認することに失敗してしまった。
――そもそも「兄やん」は主体として走ることができているのだろうか?
僕はイルミネの彼女らのようには優しくも賢明でもないので彼の様子を振り返ろう。
フーデリで働く彼は、SNSで頻繁に発信を行いつつ働いている。仕事を始める前の「おはピ」という挨拶から始め、働き始める前には「オン!!」と言う。そしてそんな彼を応援する誰かがいるようだ。

それだけでなく、自転車を漕ぐ間にも発信を欠かさない。時間に余裕がない配達で道路を横断する手段を見つけられないような状況にも関わらずSNSでの発信を止めない。配達依頼がない時間にも自転車のメンテナンスなどには集中せずにSNSに夢中だ。
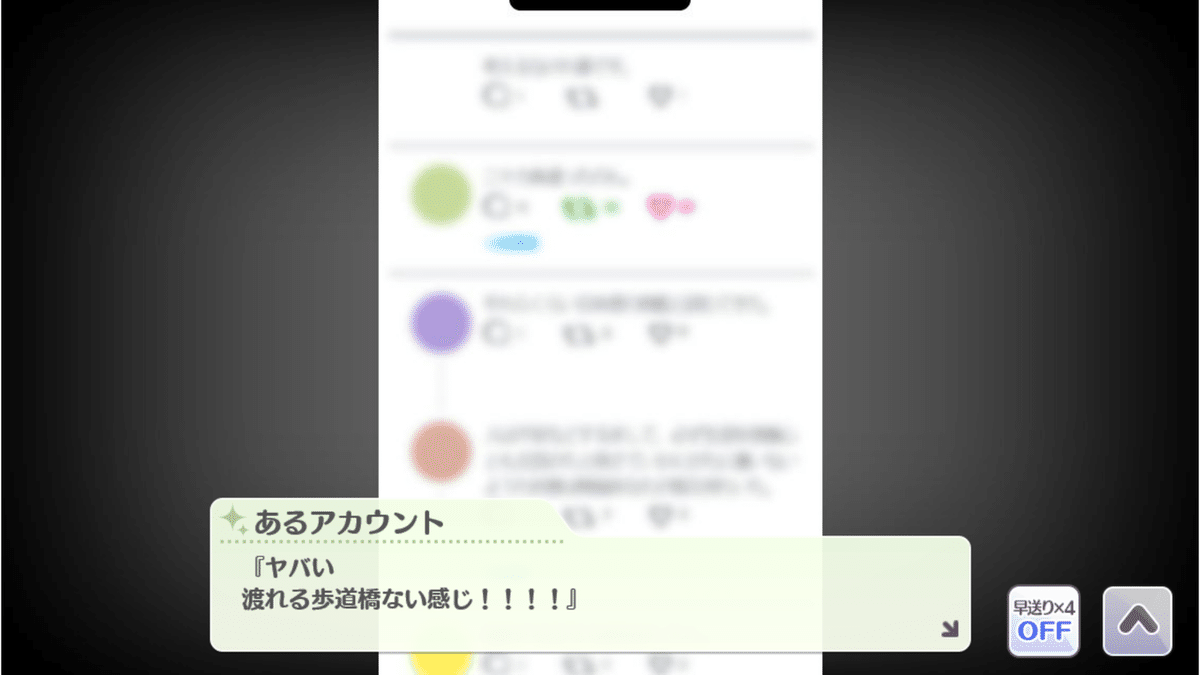
少し考えてみよう。フーデリ一般の雇用形態に準じてみると、彼は個人事業主として働くことのできる高校生以上だ。
いい歳をした男が、「おはピ」などという恥知らずの挨拶をし、「兄やん」などという軽薄な渾名で気安く呼ばれることを許し、感嘆符を滑稽なほどに付け、自分の行為に「オン!!」などと叫ぶ。さらに応援にいい気になってますますSNSにのめり込む。……このような人間はSNSにおいては実に頻繁に見られる人間である。
彼は客体化されたいという欲求、つまり承認欲求に従い、それを解消しようとしているのだ。
――風野灯織は美しく働く彼を想像した。いつか走りたい自分の心を信じられた櫻木真乃のような、そんな彼でいることを信じた。しかしながら彼はそうではなかった。彼は確かに300円の報酬のためには走っていなかったかもしれない。けれど彼はその代わりに注目という承認の甘い飴を求めて走っていた。

ここまでの一連の表現が暗示するものは風野灯織の防衛機制の失敗である。
風野灯織は意識の表層においては自己主体の確認を志向しているが、無意識下で彼女が避けた本当の精神的営為が存在する。
それは風野灯織が承認欲求を求めていることだ。彼女は「兄やん」に自己を投影することで自らの承認欲求を代替することを試みているに過ぎなかった。

彼女は意識して自分の主体の確立を志向したものの、自分のためだけに行為することができないという実存上の避けがたい失敗を経験し、「兄やん」という明らかに客体に寄った自意識を持つ存在には分不相応な主体的動機が存在することを期待する。ちなみに不在の主体に理想を重ねるという精神的営為は典型的な恋愛の実存の一類型でもある。
そして彼女はピークタイムを迎えて引っ切り無しに仕事に呼ばれる「兄やん」に羨望を口にした。風野灯織は無意識のうちに自らの承認欲求に収攬されてしまっている。

バスを降りた後には、彼女が承認欲求を意識することを避けた無意識の理由が暗示されている。
フーデリ企業の大きな仕事をプロデューサーと共に終えた櫻木真乃や、トレーナー達との楽しいレッスンと次の仕事への打ち合わせから帰った八宮めぐるからメッセージが届いた。
彼女はメッセージに返信する。画面の向こうに自分の本当の様子が伝わらないように。ほの暗い赤く湿った思いから、問題のない感情だけを取捨して意識するように。
例えばそれは櫻木真乃の仕事が上手くいった様子であるという単純な感想であった。あるいはたこ焼きやピザがごちそうであるという単純な感想だった。
彼女の無意識は、承認されないただの風野灯織が充実しているイルミネの彼女らを意識して想像することを恐れた。皆と違う自分を意識して比べることに耐えられるはずがなかったのだ。彼女が求めるのは彼女たちの隣にいることであればこそ、彼女の抱える感情は発見されるべきものではない。
それならば……――仕事がもらえる彼女たちへの後ろ暗い感情は赤い空だけが知っていればよかった。

第1話:小さな夜
この話ではイルミネーションスターズが定期的に行っている報告会を通して、仕事に恵まれない風野灯織の現状に対する周囲の反応を描写する。
そして人間関係においてはそれぞれに異なる様々な動機や形態の客体化が存在することが示唆される。
風野灯織の自意識の状態はひどい。
午後八時、イルミネのメンバーが画面越しに定例の報告会を行っている。個人個人の仕事が増えてきて会う機会が減ったであろう彼女らであったが、このような場を持っているようだ。

報告会では各々の一日について報告している。どうやらこの報告会は毎日しているものらしい。
報告は櫻木真乃から始まった。フーデリ企業の広告塔という大仕事の始まりを無事に終えた彼女は、「応援」をしてくれたユニットメンバーに感謝を伝える。
緊張に対する応援の効用とは、客体化の競合的阻害による緊張の緩和である。
緊張とは、これから発生する激しく複雑な客体化を予期しての肉体および精神的拘縮である。身近な他の何者かによる励ましという単純な客体化によって緊張を抑制することが期待できる。
イルミネの二人による、極めて単純な「やれるよ」の言葉による客体化である応援は実際に役に立ったのだろう。

報告会は、次に八宮めぐるの番に移った。彼女はあるファッションブランドのモデルとして「すごい服」を着せてもらうことになったらしい。
彼女は服を着せられることを喜び、そしてそれが「すごい」ことであると信じて疑わない。

風野灯織はそんな彼女に「不安はありませんか?」とおどけて尋ねている。
ここでの彼女は深刻に聞いているようには見えないが、しかしこれは画面越しである。オープニングからの画面越しと意識の関係、そして他者への自己投影という防衛機制をそのまま引き継いでいる。
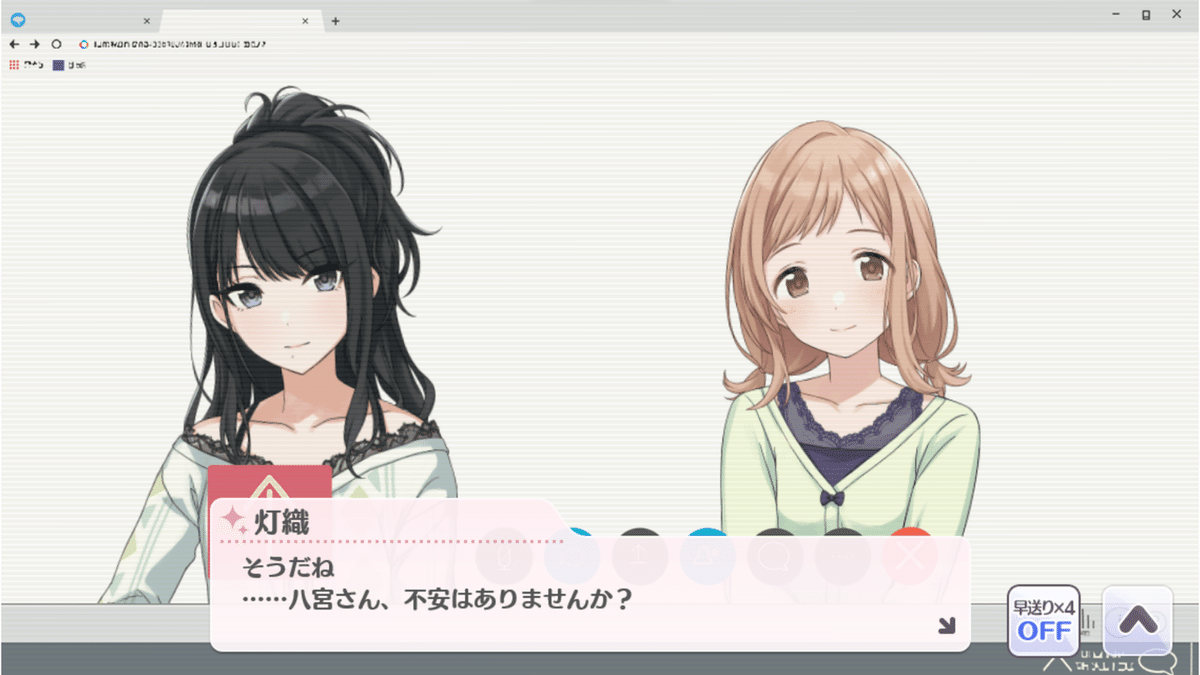
そしてそれに対して八宮は「楽しみだ」と答える。
のみならず、彼女を起用したクライアントが語った「ありのままの」八宮めぐるでいいらしいという言葉を返す。
ここでは、ありのままの風野灯織が自分と彼女らのために押し込めた後ろ暗い感情の存在と、元気な「ありのまま」である八宮めぐるを対比する。

しかしながら、八宮めぐるの「ありのまま」もまた、混血児としての生い立ちがもたらした自己の存在証明における不安を含むものである。これは必ずしも「アイドル八宮めぐる」の印象とは一致しない。
ここで八宮めぐるついて説明する。
例えば、彼女個人としての性質に触れた
イベントコミュ、【Star n dew by me】の第5話:invent laughter はそのタイトルがニーチェからの引用である。
“Perhaps I know best why it is man alone who laughs; he alone suffers so deeply that he had to invent laughter.”
「孤独な人ほどよく笑う最も大きな理由は、不幸によって余りにも深く苦しんだために笑うことを思い至るしかなかったからなのだろう(意訳)」という言葉をコミュタイトルに掲げている。
ここでは八宮めぐるが孤独への恐怖によって笑顔や陽気さを獲得しなければなかったことが端的に示されている。
また今回のお話のコミュタイトルである「小さな夜」は彼女のpSR【小さな夜のトロイメライ】八宮めぐるからの引用だと考えられる。
【小さな夜のトロイメライ】では、一つ目のコミュで、ある番組の企画で画面から消えてしまう可能性に慌てる八宮めぐるを描写する。二つ目では学生時代の旧友と遊ぶプロデューサーが偶然おつかいに出ていた八宮めぐると行き会い、彼は学校の同級生に出会ったような想像を抱く。そしてTrueEndコミュにおいては、仕事の帰りに疲れて眠る八宮めぐるを描写する。
そんなコミュ内容を踏まえて【小さな夜のトロイメライ】という題名を振り返ろう。まず「トロイメライ」からだが、これはTrueEndコミュて眠る八宮めぐるが示されたように「夢見ること」を意味する独語の"träumerei"である。
そして二つ目のコミュ内容において、彼女に同級生のような感覚を抱いたプロデューサーの様子から、これはシューマンの有名な楽曲『träumerei』をその一部に含む作品の邦題が『子供の情景』であることにも関連付いてる。
西洋音楽についての前提を踏まえた上で「小さな夜の」という言葉に触れると、このフレーズは一般的な類型であり「小夜曲(serenade)」とされるものである。また、モーツァルトの有名な楽曲『Eine kleine Nachtmusik』のように、独語でそのまま「Eine kleine nacht――」としても良い。
しかしながらこのコミュの題名は【Eine kleine Nachat träumerei】でも【子供の情景の小夜曲】でもなく、【小さな夜のトロイメライ】なのだ。
この題名が示唆するものは、当然ながら八宮めぐるの混血児としての生い立ちであると思われる。
コミュの内容を振り返ると、直接的にそれを示す事象はない。しかし一つ目のコミュでは、テレビの画面から消えることで注目の機会を失うことへの――承認されないことへの――不安が描写されている。
以上のことから、この【小さな夜のトロイメライ】というタイトルは、浮動した彼女の存在証明とそれが齎す不安を暗示していると考えられる。

今回の仕事では「ありのまま」の八宮めぐるを求めたクライアントであったが、彼らは真にありのままの八宮めぐる――孤独に怯え、寂しい思いをするのが怖くて仕方がない臆病な少女――を求めてはいないだろう。
クライアントに求められた「ありのまま」は、臆病な自分を守るためにどう見られるのかを気にして頑張るいつものアイドルの、「すごい」八宮めぐるなのだ。(真にありのままの彼女を承認した者は友達にさえいなかったが、櫻木真乃という「彼女の特別」はそれをしたと言えるだろう。なんだこれは、尊いなあ。)

さて、無知がもたらしたという点において決して避けられないが、ありのままではない「ありのまま」を求められたことには気付かなかった。
「すごい服」を着せてもらえる八宮めぐるの仕事の話を聞いて、またもや風野灯織は「八宮めぐるがその服を着ている様子を見たら、きっと私は気持ちが良く感じる服なんだろうと思うだろう」という、やや不自然な感想を口にする。ここでは仕事を貰えて服を着ている八宮めぐるの姿を意識することで、仕事が貰えない自身を意識しないよう無意識に振る舞っている。
さらに櫻木真乃が仕事に臨む八宮めぐるに対して、自分がそうしてもらったようにと「やれるよ」というのを見て、風野灯織はそれに同意するように追従した。
風野灯織はイルミネのメンバーに相応しい。なぜなら、八宮めぐるのようにメンバーの成功を純粋に喜び、櫻木真乃のようにメンバーの仕事を無垢に応援している。そんな素晴らしい彼女は、イルミネの素晴らしいメンバーと同じように、紛れもなく十全に素晴らしい存在なのだ。
少なくとも彼女の意識の上においては。

その裏では、プロデューサーがまだ仕事をしていた。
忙しくなり始めた櫻木真乃の仕事に八宮めぐるが控えたモデルの仕事についての業務を抱えて残業をしているようだった。
そして彼は、ユニットメンバーの中で一人だけ仕事がない風野灯織を思い遣った。彼は彼女の不安を思い、けれど学生の彼女が通わなければいけない学校の存在や、必ずしも望ましいとは限らない仕事の存在についても考える。
そして彼は彼女に仕事を用意するべく営業をかけることにしたようだ。
ここでは無意識のうちに「ありのまま」の「すごい」八宮めぐるを求めることになったテレビの画面の向こうにいる者としてのクライアントと、無意識を含めたありのままの風野灯織を思い遣ることができている対面する者としてのプロデューサーを対比している。

そして報告会はついに風野灯織の番に移った。
彼女はいつも通りの一日を報告する。学校とレッスンというイルミネのメンバーたちにも共通する日常について語っている。
しかし、八宮めぐるは、話したいような面白いことが――櫻木真乃や私のように充実した特別な出来事はなかったのか――聞いてしまう。
これは無知による残酷な追及である。

ここで風野灯織の脳裏に浮かんだのは「兄やん」であり、自分のことですらなかった。
そして、彼女はイルミネのメンバーとしての承認の要件を満たすために、見ず知らずの泡沫SNSアカウントの話をするべきではない。
そうして彼女は、イルミネの皆に共通する学校とレッスンについて詳細に振り返った。化学の小テストがいつもよりできたこと……レッスン室が乾燥していたこと……。
――あまりにも些細で決して特別でないこんな日常は、特別な仕事の話をした彼女らには不釣り合いだ。それならば、この日常はイルミネの彼女らに釣り合うだけの大きな事件であるべきだった。
そうして、彼女はどうとでも対策できるレッスン室の乾燥に、「気を付けたほうがいいかもしれない」と無意味な警告を行っている。

怪訝な様子であったが、櫻木真乃と八宮めぐるは真剣に取り合っている。
しかし風野灯織はそんな二人を笑って、イルミネーションスターズのメンバーに相応しいものと思われる「応援」という行為に及んだ。

……風野灯織のもとにプロデューサーからの連絡が来たのを機に、櫻木真乃と八宮めぐるはしりとりを始めた。
すぐに戻った風野灯織は「しりとり」に対して「リヤカー(はこぶものモチーフの提示)」と答える彼女らに合わせて笑う。
そして風野灯織は「海岸」という言葉を続けてしりとりに負けてしまった。
ここではしりとりという簡単な勝負に臨むという目標が、イルミネで自分だけが違うという観念に客体化され損なわれてしまっている様子を暗喩している。
しかし画面越しの彼女らは、そんな彼女の気持ちて知ることもできず楽しげに笑った。
風野灯織は笑って彼女は報告会を終えた。笑いきって終えることができた。
一息ついた彼女は、「兄やん」が仕事をもらえたことを報告していることに気付いた。彼女が自己を投影した彼が、「夜遅くの1056円の仕事」に恵まれた様子を見て彼女は喜ぶ。
そんな彼女は一見すると微笑ましく映るのかもしれない。
しかし、彼女はそれ以上にすごいはずのイルミネの二人、あるいは夜遅くまで自分のために働くプロデューサーにはそれほどの喜びを感じただろうか?
彼女は、自分がイルミネに相応しくないのではないかという観念がもたらす強烈な不安を避けて、無意識に自己投影に走ってしまった。その結果として歪めた自己の認知によって客観性を失っている。
ここでは、周囲の人間に対して無垢で素直な感謝ができなかったという精神的失敗が描かれる。
これによって、イルミネに相応しい自分でありたいという願望と、イルミネに相応しくない自分を守ろうとする精神的営為とが強烈に矛盾したことが提示されている。

「兄やん」に向かって頑張ってと呟いた彼女は、「頑張ろう」と、もう一度全く同じ意味の言葉を繰り返した。

第1話では、様々な防衛機制によって自分の感情を押し隠そうとする風野灯織の言動の苦しさを示す。
また、演じる客体から逃れることのできない現実や、無知によって、あるいは致し方のない無意識の存在から、不意の衝突や無自覚の残酷が発生せざるを得ない様子が描かれた。
そして、それから逃れようと願っても、客体から逃れられない風野灯織はやはり承認を得るために現実の機会を待つしかなかった。
この小さな夜の闇は、小さな彼女にとってはあまりに大きい。
第2話:みんなは頑張っている
ここではそれぞれの思いを抱えて努力する人々の姿を描写する。
その思いは行為における思いでもあり、そして認識する人間としての思いでもある。
彼女たちは私たちと同じように主体として活動する行為者であり、客体化する認識者でもある。そして彼女らも同時に認識され、そして評価される客体でもある。
この話ではそんな彼女たちを客体化する様々な「応援」や「おまじない」が行われる。
この話は、前話で連絡していた打ち合わせから始まる。
学校での時間を終えた風野灯織がプロデューサーの車に乗る。車は冷えきっていた。待っていたプロデューサーは車――人間を乗せてはこぶもの――のエンジンを切っていたらしい。環境への配慮から励行されたアイドリングストップを実践している。
彼女は日直のために遅れてしまったと謝罪をするが彼は不器用に世間話を始めようとした。しかしその不自然な様子を逆に彼女に心配されてしまう。(本当にダメな人――。)
彼はやや腰砕けなものの、かえって彼女の緊張を解くことに成功して本題に入った。

一方の事務所では、仕事が忙しくなり始めた櫻木真乃が、風野灯織と同様に冷え込んだ事務所にやってくる。そこにはプロデューサーこそいなかったが、七草はづきが用意してくれていた台本があった。
風野灯織と同様に誰かの思い遣りに触れることができている。

そして櫻木真乃は見えない努力を始めた。誰かのいないところでの誰に見せるためでもない練習であった。
彼女は「初回送料無料」の文言が自然に言えない。
どのように聞かれるか意識すると、あるいは何かをやらされると……つまり行為に客体的自意識が関与すると、人間はただ文言を読み上げることさえ難しくなる。そういった客体への意識を行為から排除するために必要なのが、練習・訓練である。
練習とは意識的行為の無意識化である。
彼女のする孤独な音読は練習というものの原型でもある。

そのときプロデューサーは本題を始めていた。
風野灯織に仕事の意向を尋ねる。「もっと増やしたいとか、どんな仕事がしたいとか」と聞いている。学校や体力の問題を考慮するという目的を踏まえた質問であるが、その実、仕事の少ない彼女が悩んではいないか聞こうとする婉曲的な確認であった。
第1話で、はっきりと直接的な質問で追及してしまった八宮めぐると対比して、彼はデリカシーに満ちた言葉選びで会話を進める。
風野灯織は、最近仕事がない様子を指して「ペースが落ち着いているので落ち着いて仕事ができている」と強がりながら、「もっとやれる」と仕事が欲しい旨を伝えた。
プロデューサーは仕事がないのが不安だとは言えない彼女に対し、「無理して欲しいわけではない」と答えている。あくまでも仕事がなくて不安であるという実存的無意識と、それにやや矛盾する彼女の意識的認知を踏み荒らさないよう振る舞う。
その上で、仕事がないことを「落ち着いてる」と表現した彼女に倣い、さらに彼女が希望する仕事についての情報を探ろうと試みる。

しかし彼女はやりたい仕事を見つけることができない。
彼女は主体としての遊ぶ心もちを持てていない状態であり、そんな状態の人間が自身のやりたいことを確認することはできない。
彼女はやりたいことを考えるよりも前の段階で、そもそもの自己の意志を確認することに失敗し続けているのだった。
そして彼女は、その代わりに自分の無意識が秘匿し続けた、必要とされている櫻木真乃と八宮めぐる、そして必要とされていない自分の比較に思い当ってしまう。
思わず口に出してしまった自分にやや後悔を感じながら、彼女はプロデューサーの返答を待った。
ここからプロデューサーは頑張る。
まず彼は思い遣り――イルミネの二人と比べて仕事が少ない状態にあり、それを心配することでイルミネの中で浮いているという認識によって彼女を客体化したこと――について謝罪し、実直な解答をした。

そしてすかさず謝罪の体を装ったフォローを行う。このフォローはとても上手だ。
彼が直ちに防ぐべきことがあるとすれば、風野灯織の「私はイルミネに相応しくない」という観念に対して、客観的妥当性を与えてしまうことである。
そこで彼は、イルミネではない第三者として「みんな、本当に仲がいい」という承認を与えることに注力した。
そして、そのために「『少しの状況の違い』(かなり婉曲的な表現)を心配をしたのは、本当に仲がいいと客観的に感じるからである」というやや難のある論理を振りかざしている。
さらに、この不可解な言葉を受けて考え込みそうになった彼女を「失礼だった」という言葉で強引に制した。
そうして彼は、彼女の中で形成されかけた「客観的にイルミネで浮いている」という認識を「客観的にイルミネは仲がいい」という認識にすり替えることに成功した。
彼女は一旦の落ち着きを取り戻す。毎日の報告会や応援し合うイルミネの一人としての無意識の演技をやり通したことがその自己認知に有利に働いているようである。
……――あなたは……スーツも……折り目正しく……美しい……ああ(略)。

……しかし、それでも彼女は「二人が忙しい時に私が応援できる方がいい」と分かるようなよく分からないことを言う。
詳しく追及することが許されない無意識との不調和が産み落とした、なりそこないの論理を展開してしまったのだ。
この場においては、彼はこれ以上のことを何もできなかったが、それでも不明瞭な何らかへの「ありがとう」の言葉――おまじない――によって不安定な風野灯織にせめてもの客体化を行う。
そして、何かやりたいことがあれば言うこと、「応援」という婉曲的な言葉を用いて客体化を要請することを躊躇わないことを言い渡す。
しかし、彼女が思い起こすのは自己投影した「兄やん」の、承認欲求から生じた「オン!!」の言葉であった。当然ながらそこには一切の救いを見出だせずに彼女は黙り込む。
そんな彼女の様子を見て、彼は「仕事を探すから」と直接的に勇気付けることになった。
これまでに示してきた非常に上手な思い遣りは、しかし細やかながら完全な失敗に終わってしまう。

ここで、七草はづきが櫻木真乃のために少しの思い遣りで出力したキャンペーンの文言によって上手くいった櫻木真乃が描写される。
これにより、素晴らしいイルミネに相応しくない存在としての風野灯織の観念が対比的に強調される。

また、服を仕立ててもらう八宮めぐるも描写されている。
服を仕立ててもらう彼女が感じる「嬉しさ」というのはファッションの喜びである。
ここで説明すると、ファッションの喜びというものは、「被服」という単語が表す通りに着せ「られる」喜びなのだ。
寸法を測られる喜び、誰かに思われながら服を作られる喜び、服を注目される喜び、誰かに褒められる喜び……。ファッションは徹底的に客体に結び付いている。
そういう意味において、この世界で最もファッションらしいファッションとは、その集団の一員であるという承認を与える制服なのだ。
ごく一部の例外として原始ロリータファッションなどが存在するにしても、古今東西ファッションの喜びは決して客体と分かつことのできぬものである。
機能性のみを求めたダウンやスニーカーですら、「服飾に興味を示さない私」の自己認識とは実存的に不可分であり、野戦における迷彩服ですら軍団の一員としての認識や、状況に対応する存在としての客体化がある。
ごく一部の例外であるロリータファッションにしても、主体としてのファッションたることができたのは一番初めに実践した人間の初めの一回のみであり、二回目からは習慣による客体化があり、ロリータファッションの追従者にはロリータファッションという体系に連なる者としての客体化が発生する。
従って、「ありのまま」と嘯き主体を標榜するアパレルブランドは、見られる自分を飾ることを否定した「おまじない」を掛けているのであるが、その実「おまじない」が服を飾っている以上は、凡て「おまじない」ありきである。
これらのキャッチコピーは、いわば捻くれただけの化粧であり、つまり「ありのまま」という彼らは大噓吐きであると言って何ら差し支えない。

さて、そのような服飾というものに関わるデザイナーに、さらに採寸のための拘束――身体的自由の制限という強い客体化――をされながら、八宮めぐるは今回の仕事の打ち合わせを楽しげに振り返る。
今回の仕事では、クライアントは「エシカル」というものをコンセプトにしているとのことであった。
アパレル産業は大量の廃棄物をもたらすというのは有名な話だ。現在の業態上の宿命でもある。ここではそういった話からの引用がある。
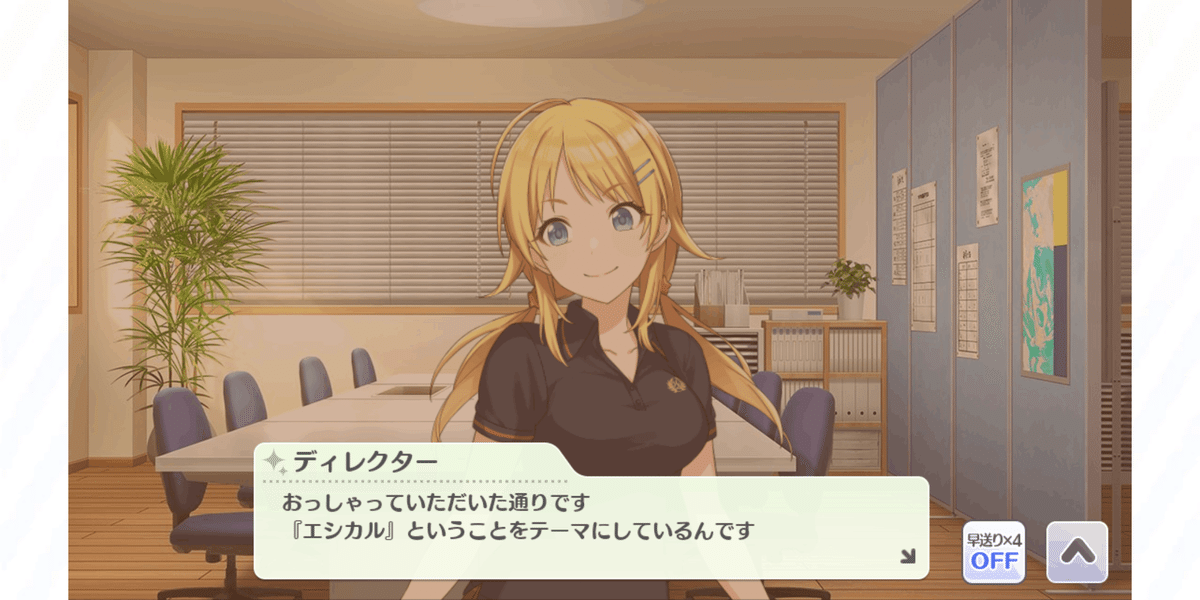
大量の廃棄物を出すという点において、アパレル産業は環境保護の観点から明らかに悪い存在である。
環境保護という観点においては、種々の酸化化合物や産業廃棄物、地域において「環境破壊」があるかによって、明確で単純な善悪が裁定される。
善悪による単純で二元化された客体化を受けることに、人間の客体は惹かれてしまう。人間は考えることを元来好まないのだ。
そして八宮めぐるは――自身の根源的定義に係る人種というアイデンティティの曖昧な混血児として生まれ、その孤独により笑顔を発明せざるを得なかった不安な人間――は、行動に明確な善を定義することができて、不安を感じずに済むらしい、そんな魅力的な「おまじない」に好意的な興味を持った。

ちなみに、作中のアパレル産業の主張する「エシカル」のキャッチコピーは、「天然素材」と「丈夫な良いデザイン」によって(化学合成繊維を減らし?、)廃棄物を減らし、環境負荷という神の前に悪とされるアパレル産業を善なるものにしようとする試みらしい。
ここには様々な欺瞞が含まれる。
まず、彼らは「環境に優しい天然素材」と言ったが、「環境に優しい」も「天然素材」も曖昧な言葉である。それを主張するだけの総合的かつ具体的な評価を著しく欠いている。他にも「丈夫で良いデザイン」にすることで長く着れると主張しているが、「良いデザイン」という評価の基準が何なのかは曖昧だ。例えば、今日では滑稽の象徴と化した肩パッドや派手な色のスーツも、バブル期にはきっと最先端のお洒落として流行した「良いデザイン」だったろう。もし長期的に「良い」と称されるデザインがあるとすれば、服飾においては機能性という一面にそれを求められるだろう。今日、最も機能的に優れていると思われるのは例えばダウンやスニーカーといったものであろう。その素材には往々にして化学繊維を用いている。価格の高いものを含むのであればいわゆる「天然素材」でも十分な優位な機能を有するものがあるだろうが、機能を評価するのであれば価格も重要な指標になる。そう考えたとき、少なくとも「環境に優しい天然素材」で作ったこの服が「丈夫で長く着られる良いデザイン」のものであり得るかは甚だ疑わしい。
挙げ始めればきりがないくらいに、「エシカル」の欠陥や指摘することのできる欺瞞は多い。
そもそも、彼らが環境保護のお題目を掲げたのは、根本的にアパレルブランド同士の商業的競争を考えてのことである。当人が否定したとして、これを客観的実存上否定することは不可能である。
実際に彼らが行っているのは何か説明すると、環境保護という宗教において悪とされるアパレル産業の中で、自ブランドは他ブランドよりも相対的に善なるものであるとしているのだ。
つまり、彼らは環境保護の御名にあやかることを選んだことで、「アパレルブランド各社は相対的に私たちよりも悪である」という客体化を必ず行っている。
無礼もいいところだ。
そして質の悪いことに、この思想による認知的客体化においては、彼らは客体化する行為者として主体の自覚がない。彼らは他者を客体化した存在としての責任を果たすことを放棄しているのだ。
このときに私たちが感じる絶望に近い怒りは、例えば、強権的な父親が会社で頭を下げてヘコヘコしているのを見た思春期の子が感じる怒りであり、あるいは自分たちとの試合で勝ち上がった相手チームが痴情から発生した問題で出場資格を失ったときに感じる怒りだ。
彼らのことを、敢えて彼らの方法で評価するならば、御為ごかしに振り切った彼らは、生きる人間として何らの評価にも値しない巨悪であると言っていい。
八宮めぐるは、その生い立ちから人一倍客体化を欲してしまうが故に、この「おまじない」に興味を惹かれてしまった。
彼女は自身を採寸するデザイナーに、「エシカル」とは何なのかと質問する。
彼女を採寸する――彼女の肉体を定義し、彼女に服を着せ、そして彼女を動かないように拘束すらするという強力な客体化を行う――存在であるこのデザイナーは、彼女に説明することにした。
しかし彼女が語ったのは、クライアントが振り回す美辞麗句としての「エシカル」ではなく、倫理というものについてであった。

彼女がする倫理の説明は、言葉自体の説明であるが故に一般性を保っている。
自分の雇い主が声高に叫ぶ汎用商業的外注宗教としての「エシカル」とは違い、倫理というものは世界には様々な生命や人間が存在するということへの理解であると語っている。
そう言って彼女は採寸の終わりを告げた。つまりここまでが客体化、つまり「おまじない」である。
このおまじないの意図は、デザイナーが作り八宮めぐるが着せられる服が、商業的「エシカル」の産物ではなく、せめて個人の規模においては倫理というものを目指したものになることを祈るものである。
デザイナーは八宮めぐるの中に形成されかけた「『エシカル』は良いもの」という認識を「倫理はデザイナーに肯定されている」という認識で上書きしている。
そして彼女は八宮めぐるに、彼女が着る服が良い服になるようにおまじないを掛けるよう言う。

そして八宮めぐるは言われたように「おまじない」をかけた。
単純で無思慮な正義を掲げた「環境に優しい」服ではなく、これまで通り相変わらず所在ない不安を伴っても「みんなのこと考える」服になーれと。

ここでは他者による認識を上書きする客体化、つまりデザイナーから「おまじない」を受けて成功した八宮めぐるを描くことで、プロデューサーの「おまじない」を受けてもなお自意識的危機を解決できない風野灯織を対比的に強調している。
櫻木真乃の描写と同様に、「イルミネに相応しくない存在」としての風野灯織という観念を累加した。
さて、無自覚ながら非常な危機にある風野灯織の状態を改善するには、「応援」あるいは「おまじない」では足りなかった。
言葉によって彼女の苦しみの本質である不安を緩和できたとして、苦しみの原因である仕事がないという彼女の実存的状況は改善しない。
プロデューサーはやはり実際の仕事を探すしかなかった。
そして彼は営業をかけ始めた。
他の仕事の合間にしか時間を取れないのだろうか、明らかに出先のオフィスや暗くなった道、夜更けの事務所でとにかく営業の電話をかけた。
当然のことであるが、彼は「仕事を寄越せ」などとは言わない。なぜならそれは明らかに不躾であるからだ。
彼らは社会人であり、つまりそれぞれの仕事をそれぞれに行っている。唐突に命令という客体化を加えるという振る舞いなどは、相互に主体であるという暗黙の了解を覆すような礼儀を欠いた行為だ。
電話をする彼は、例えば世間話の体を装う。客体化は相手が望んだ場合に行い(恐らく相手も仕事話に含まれる相互の客体化を許容することを示すために分かりやすい自慢のようなことを言ったのだろう)、折り返しの電話があれば相手に行為を強いる客体化を働いたことに謝罪と感謝を伝え、お互いの交流を名目に仕事の話をしたいと申し込む。
社会という私たちを不断に客体化する怪物に対し、ある種の諦念を抱えて生きるプロデューサーの彼は、しかしアイドルには主体としてあることを祈っているらしいことが様々なコミュから見て取れる。
そのために、彼は芸能関係者が用いる軽薄な礼儀によって、自らが客体化されることに受け容れているようだ。
彼がアイドルに抱く理想とそのための努力の動機が、主体として生きたいという彼自身の願望をアイドルに投影するために行われている可能性を否定するというのは公平ではない。大袈裟な彼の礼儀は痛々しいものであるかもしれない。
しかし、実存として彼は苦しむことを選んでいる。客体化を受ける苦しみから逃避していないことは確からしいし、多忙な毎日の一息吐くような時間の全てを使って、夜遅くまで社会の人間として働いている。
痛々しくとも努力する彼の姿は魅力的だ。



一方で風野灯織は引き続き、SNSの「兄やん」に自己投影を行っていた。
「兄やん」や彼らのコミュニティに属する人々はプロデューサーなどと比較して不躾だ。
彼らが話題にした稼いでいる金額の話というものは、非常に多義的かつ複雑な客体化を招きかねない。このような下衆の勘繰りは古来より忌み嫌われ戒められてきたものだ。
しかし、これをSNSの彼らはやる。意識してか意識せずか。
対面する可能性を持つ相手に対しては、相手への、あるいは相手からの不断の客体化を無意識に知覚し、それに相応しいデリカシーを発揮する一方で、画面の向こうの存在である彼らは「フォロワー」に対して余りにも放埒な言動をする。
しかし「フォロワー」は「フォロワー」で、「稼いですごい」という褒め言葉という客体化――おまじない――をただ単純に喜ぶだろう。
なぜなら、彼らの関係は実際の社会の中で対面することを前提にしていないため、褒め言葉が引き連れる嫉妬による攻撃や金の無心に遭うことを心配する必要がないからだ。

しかし、一方でこの不躾な客体化を行う存在に溢れたSNSという環境では、当然不快な客体化も発生する。
風野灯織は、フーデリ従事者の中に、社会規範にそぐわない行為をする者がいることを乱雑に批判するアカウントを発見する。

風野灯織は、自己投影の対象である「兄やん」がいつかの櫻木真乃のように主体としての「走る理由」を知っている素晴らしい存在であると信じている。それだけでなく彼は周囲の承認を受けている。「兄やん」は、イルミネの素晴らしいメンバーに相応しい理想的な存在なのだ。
そのため苦しげに彼女は呟いた。「兄やん」は違うと。
彼女は誰かのことを思っているように見えるかもしれない。しかし彼女は彼女のために努力する身近な人の存在を見逃していた。

この話では、誰かを客体化することについて様々に表現した。
時に、「応援」、「おまじない」などの言葉で表し肯定的に描くが、「エシカル」という商業的運動が知ってか知らずか行う善悪という客体化を文脈から暗示的に否定する。
そしてSNSで発生する、非常に乱雑かつ幼稚で、何より自己の言論が粗野である様子に無意識である客体化をもって話を締め括る。
風野灯織の不安は解消されても、不安を生み出す実存的状況は何ら解決されることがなく、自分を守るために依然として続けざるを得ない自己投影によって、彼女の自意識と認知は損壊が続いている。
彼女に気付かれなかったとしても、あるいはむしろ気付かれないように祈りながらも、大人であるプロデューサーは相互に客体化される苦しい社会で努力している。
みんなは頑張っている。
頑張る誰かを応援して、頑張る誰かを思い遣って、頑張る誰かにおまじないをかけている。自分が走る理由を知らなくても、誰かに走る理由を見つけてほしくて走っている。SNSのあの人もきっとみんなペダルを漕いでいる。みんなは頑張っている。
わたしは頑張っていない。
第3話:車輪
この話では、誰かの努力が生み出した実存的な成功が承認への飢渇と不安を健全に満たす様を描写する。
しかしその一方で、実際の現実と同様に、誰かの成功は必ずしも他の誰かを幸せにするわけではなく、不安の引き起こした批判の的になり得ることも示す。
プロデューサーは、風野灯織にサッカーの試合を振り返る番組コーナーでの「ナビゲーター」という仕事を取ってきた。
その仕事の内容はサッカーの試合を見て、彼女が気になったところを振り返ることおよびそのコーナーの進行らしい。ナビゲーターから偏見のない素直な疑問を引き出し、視聴者と一緒に楽しもうという趣旨のコーナーであるとのことだ。
風野灯織は、自身がサッカーについてほとんど知らないため、自分が不適格なのではないかと躊躇う。しかしプロデューサーの言葉や、何よりイルミネに相応しい自分にという観念に押されて、彼女はこの仕事を受けることにしたようだ。
そして番組スタッフに「カタい」と緊張を指摘されながらも撮影が始まる

ちなみに、プロデューサーが風野灯織にした説明はやや怪しく、つまり「おまじない」の可能性があるように感じられる。
まず、このナビゲーターの仕事は当初登用されていた人間のキャンセルありきで回ってきたものだ。
さらにこの番組はサッカーの専門番組らしい。また番組内ではチーム名で呼ぶことはなく、「ホームチーム」と呼んでいることから総合的なサッカー番組のように思われる。(解釈の余地あり)
例えば、特定のチームにフォーカスした番組であれば、彼氏の趣味に付き合ったり「イケメンな選手」の熱心な追っかけをするファンなど、サッカー自体に興味がない人もこの番組を見るだろう。
特定のチームに偏らないのであれば、サッカーそのものの情報番組になるわけであるが、このような番組を視聴するのがライト層である可能性は低いように思われる。
さらに彼女の請けた役回りの名前は、主体的にコーナーを先導する「ナビゲーター」である。一人でも進行が可能である程度の知識が要求されると考える方が自然だ。
然るに、彼女が請けた仕事で本来期待されたのは、それなりの知識を持った人間によるそれなりの進行なのではないか?
そうでなかったとすれば、このコーナーは視聴者を「サッカーファン」として客体化する試みである可能性がある。
この番組の視聴者は、理解の足らない「若くて可愛いだけのアイドル」を見て、無意識の中でサッカーにおいては少しばかり詳しい自分が相対的に優位にあることを確認するだろう。
すると、自分を気持ち良くしてくれるものである「サッカーファン」という肩書を自身に刻み付けるだろう。
自己の存在証明に「サッカーファン」を含めるようになったこの存在は、己の存在を守るためにサッカーファンであることを証明するようになるだろうし、そうするとサッカーにのめり込むことを周囲に認めてもらいたがって周囲に広めたり、サッカーという興行を持続するためにお金を落としたり、このコミュニティから離れまいと熱心な応援をするようにもなるだろう。
こういった商業的な狙いを持った「ファン」にするための客体化は、いわゆるエンタメ業界には普遍的に見られる。

風野灯織はこの有り触れた、少しばかり巧い詐術のために利用されている可能性がある。こちらの可能性の方が高そうな気がする。
そして忘れてはならないのは、この詐術は人々に「所詮アイドルだな」という認知や、時には誹謗中傷とも取れる発言を期待することなのだ。
この起用が故意であるか、不意であるかは分からない。「オッカムの剃刀」など様々な警句もある。僕には分からない。ただ疑おうと思えばいくらでも疑えるということたけは確かだ。
さて、撮影が始まった。
風野灯織が取り上げたのは「オフサイド」の裁定であった。サッカーを詳しくないものにとっては最も理解し難いルールであると言っていい。
そして、この反則は非常に文句が出易いものであるというのも特徴的だ。
なぜなら、この反則が指摘されるのは得点に直結する場面が非常に多く、さらに判定自体も見る人によっては異なるような微妙な反則だからだ。
ここでは、「オフサイド」という微妙で文句の出易い反則を通して、絶対的かつ単純明快な客体化に人が誘惑される理由、つまり「エシカル」をはじめとした客観的に明らかな御為ごかしが、有効な支配を実現する理由を暗示している。
絶対的で簡潔なルールがあれば――絶対に正しいものが保証されてさえいれば――人は不安を感じることや不安が生む争いにも、苦しまずに済むように感じてしまう。
宗教の実存的魅力はここにある。
一方で、反則の笛を吹いた審判に対して、アナウンサーは「勇気ある」判断であると言及する。当然これも客体化だ。審判の現実は分からない。無理筋が許されるのであれば、アウェイのチーム側の罵倒を面倒がったのかもしれないし、ホームチームへの私怨があったのかもしれないので、厳密にはアナウンサーの彼も間違ったことを言っている可能性が否定できない。
しかし、審判の彼にとっては、オフサイドの指摘によりホームチームから批判されることは確実に予想されることである。それならば、微妙ながらも自分の判断を信じてプレーを止めたこの審判は、少なくともホームチームからの批判分の勇気を示したように思われる。
まず彼は副審である。主審よりもその責任は軽いように思いなされるような名前である。
そしてこのコーナーの名前である「VAR」というものは、裁定を客観的に提示するものだ。ビデオによる検証は、審判を客観的結果映像により客体化する。つまり「厳密な裁定で試合を成立させた素晴らしい審判」か、「決定的な得点機会を奪い、試合を左右した価値のない審判」かの二択に追いやる。
それならばなおのこと、この裁定は反則の有無に関わらず勇気を示すものだ。
仮に審判の彼が笛を鳴らさなければ、VARが行われるかは分からない上に、仮に何らかのチャレンジ制度のようなものでVARが行われ、そこでオフサイドが指摘されたなら、それは絶対に正しい裁定によるものとして観客は渋々ながら、あるいは嬉々として納得するだろう。
それに対して、審判の彼がオフサイドを指摘したことで得られるものは、アウェイチームがVARを要求する権利を喪失する可能性や、公正に試合が行われていないのではないかという観客や選手が抱くかもしれない不安を減らすという結果であり、つまり試合を公平に運営する審判という職務における彼自身の誇りくらいのものだ。
彼が歓迎されるのかは全く分からない。だからこそ彼は「笛を吹く理由」を知っていたのだろうと考えられる。
彼が白痴か、あるいはここまで考える存在がいることを見越した上での功名心を持たないのだとすれば、あるいは持っていたとしても、彼の行為には勇気があると言っていいと僕は思う。少なくとも腰抜けの誹りを受けることはない。

「風野灯織のVAR」――認知が歪むことによって客観性を失った女の子の客観的な裁定――で、彼女は主体を確認できているらしい審判という人間の存在に気付いていない。
この審判が、「兄やん」よりも信じられる存在であるのはきっと間違いではない。しかし彼女は示された勇気の存在に気付けないのた。このVARの対象は明確に風野灯織である。
ここでは「風野灯織のVAR」というコーナー名と物語の展開によって、後述する今回のイベントコミュ全体の主題である主客の混在についても暗喩している。シャレオツぅ!

彼女の審理はキャスターからのアドリブに促された。
彼女はオフサイドによって試合の勝敗が左右される状況に「ドキドキ」したか問われるか、彼女の回答は歯切れが悪かった。
なぜならドキドキ――緊張というものは客体化についての不安がもたらすものだ。
この番組において彼女を客体化しているのは、「イルミネに相応しい自分でいることができるのか」という観念なのだ。このような私事にのみ専心している存在が、この番組に相応しいはずがあるだろうか。
「ナビゲーター」としての彼女に許されることが確からしい本来の緊張とは、サッカーが好きな自分として試合の行方に対して抱いた緊張か、あるいは番組の製作者というチームに対する緊張か、あるいは百歩譲ってアイドルとしての視聴者に対する緊張くらいのものだ。
しかし、風野灯織はどうだろうか。彼女はサッカー好きとして試合の行方に興味を持てず、番組制作者として視聴者を気持ち良く相対化する無知な可愛い女の子に徹することもできず、アイドルとして彼女のファンに応えようという意識もありはしない。
繰り返すが、彼女が緊張しているのは、今、「自分はイルミネに相応しい存在でいることができているのか」という私事だ。
彼女を客観的に評価したとき、その本質は「ナビゲーター」として余りにも不適格だ。
ここで、物事に客体化された人間の性質について話をしておこう。
人間にとって、自分と異なるものに客体化された人間ほど奇妙で、動物的忌避感と危機感を惹起するものはない。
例えば、今日におけるキリスト教徒とイスラム教徒、資本主義と共産主義などのイデオロギー闘争の原動力は、己とは異なる思想に客体化された集団への危機感にあるのだ。
観念や他者に客体化された存在というのは、何を考えているのか分かりにくく、さらに主体的発想からは思いもよらない歪んだ認知を感じさせる言動をとる。
そして同一物に客体化された人間同士は排他性や話題の共有などといったことから結束しやすく、一人一人の危険人物は危険な集団になりやすい。
同じものに客体化されていない人間から認識すると、彼らは不気味に過ぎる。
余計な偏見と悪口を言えば、昨今の西洋社会における「多様性」の主張は、この客体化された存在への忌避感――精神における負の走性――という動物的体験を、彼らの存在証明に深く根付いた宗教に基づく原罪の思想習慣により悪魔化した結果の産物である。
彼らが存在証明における安心を得るためには、この動物的忌避感は絶対悪である必要がある。従って、多様性を肯定しない存在は絶対的悪魔の崇拝者であり、つまり存在することを認めらない。
そして結果として、その実存において多様性を認めていない。
僕は「小学生でも分かる矛盾を起こしているので、彼らは認知が歪んでいるのかもしれない」と一定の偏見を持つことにより、この奇天烈な集団のことを「一般性の保たれた論理の範疇にある点においては自己と変わらぬ同一物である」として客体化しているが、それでもやや不気味である。

風野灯織の初収録は破綻こそしなかったものの、芳しいとはとても言えない結果に終わった。
だが、プロデューサーは、初めに「よく頑張った」と客体化を行う。
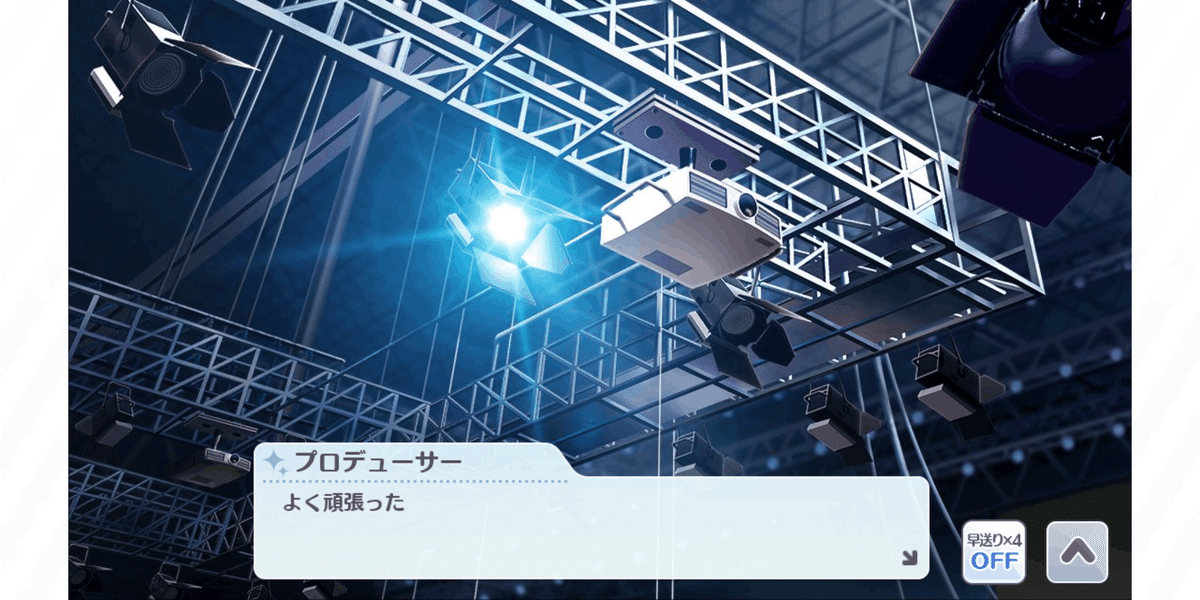
ここから風野灯織の意識と無意識の苦しい対立にプロデューサーは客体化をもって介入しようと押し合いが始まる。
彼はあくまでも彼女の存在証明における危機がもたらした承認への飢渇を解消することを期している。
一方の風野灯織は、自分が不安を抱えて承認を求めていることに気が付いていない。真面目な態度から客観性を持っているが、彼女が失敗したという実存は揺るがないため自罰的な思考に陥いっていた。
失敗の自覚がある彼女は、その不安な気持ちを解消しようという無意識から、彼に客観的評価を求めている。
これは彼女の意識の上においては第三者視点での批判を求めているようでいて、無意識においては、イルミネに相応しく十分に仕事をこなすことができていたという承認をこそ望んでいる。

プロデューサーは、彼女の不安を理解した上で、あくまでも事実らしい様子基づき彼女自身が仕事の結果を肯定しやすいよう伝えることを試みた。
出演者として求められる要件をまるで満たしていない緊張状態を指して、「少しかたくなっていた」と評し、自意識の不安定から台本に寄る辺を求めた様子を「進行に安定感があった」と褒める。
これは風野灯織の無意識が求める客体化であったが、風野灯織の意識はあくまでも成長したいという衝動を有した主体性のある存在として、この番組の後においては懲罰的な批判を求めている。
彼女の無意識が快い安心を得たいと思いながらも、意識はその快い安心を求めることを良しとしない。そしていずれにしても不安な自分の心を持って、外部から客体化を求めていることには変わらない。
そんな彼女の客体に偏る自意識の苦しみは、正しく主体を確立することによって多少緩和されるものであるが、直接的に主体であることを促すということは不可能である。
何かを命令したり勧めたりするという行為には実存的に何らかの客体化を発生するため、外部からの介入によってはほとんど実現しない。

そんな様子を受けて、プロデューサーは彼自身で彼女自体を客体化することを打ち切る。
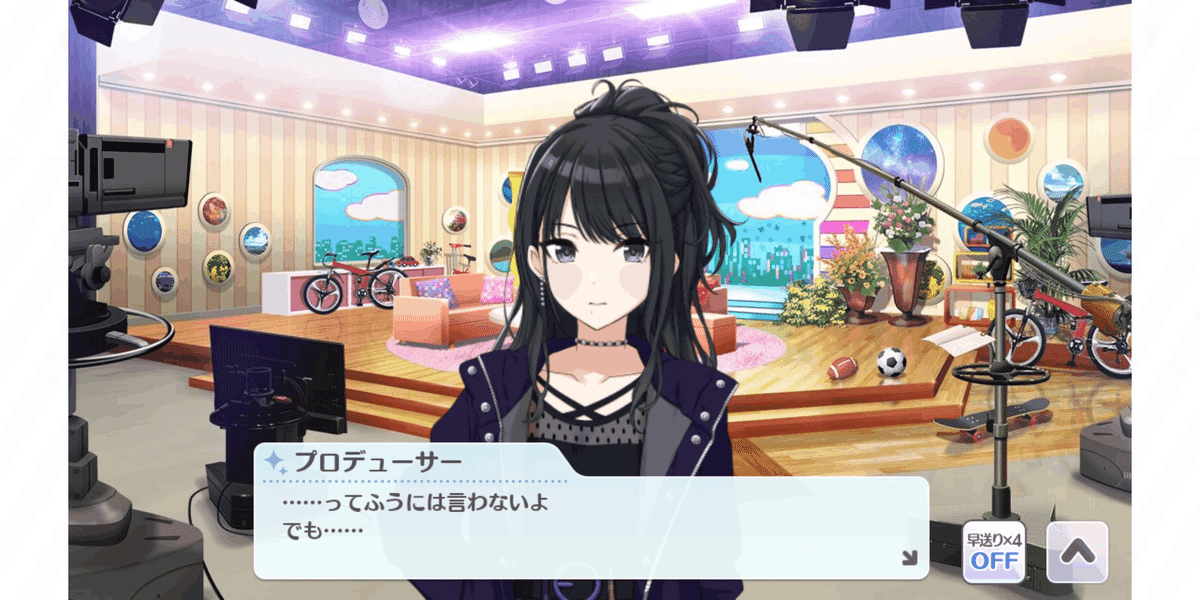
代わりに、「チームがいる」と告げた。そしてまたこの番組に出ることを望むのなら彼女自身も「チームにならなきゃ」いけないことを指摘する。
ここまでの彼女は、自己の意識と無意識の対立に耐えること、あるいは自己投影の「兄やん」と彼の自意識に終始していた。
ここでプロデューサーは、番組の出演者の存在に頼ることと、そして暗示的に彼女を取り巻く存在、つまりプロデューサーやイルミネーションスターズのメンバーが努力をしておりそれを頼ることを告げている。
これはある程度認知能力が発達している人間にとっては残酷な発言でもある。周囲の存在を認知していなかったという指摘とそれが事実であったという客体化はそれはそれは残酷だ。デリカシーのある男はこんなことを言わない。
しかし彼もそういうことを指摘しないといけないという覚悟を、あるいは勇気を示している。

そして「灯織も、チームにならなきゃ」との言葉を投げかけたとき、番組のADが挨拶に来た。出演者のアナウンサーやコメンテーターとは挨拶を交わしている様子は描写されない。
テレビ局の人間であるADは挨拶を求めても、番組の出演者にとっての彼女は番組のメンバーではなく、「『283プロダクション』とやらの一度だけ出演した事務所が推すアイドル」でしかないようだ。
プロデューサーの言った「チーム」とは、そこにいる集団の一員として承認を得ることであり、この番組における「チーム」というものが「サッカーとテレビ番組というものに客体化された存在の集団」である以上は、やはりそこに、自ら客体化を求める意識の介在が必要になることを伝えている。
個人的な苦しみに専念することだけでは実際の問題が解決することはなく、他者から差し伸べられた手を意志の高潔だけで振り払えばいいというものでもない。
実存的な問題には絶対的な解答が存在しない。この世界の事象の実存は、主体と客体をもって世界を認識する私たち人間にとっては常に複雑だ。

そして事務所で二人、生放送の風野灯織を見守っていた櫻木真乃と八宮めぐるは、出演者の衣装である「ユニフォーム(制服と衣装という客体のモチーフを合わせたもの)がよく似合っていた」、「かっこ良かった」と、彼女の精神的内面に反した感想を述べる。
また、イルミネーションスターズにおいて非常に頻繁に用いられる模倣行為のモチーフによって、イルミネーションスターズの一員として風野灯織を客体化、つまり承認する。
ここではオープニングから引き続き、画面の向こうに、まるで番組に相応しくない風野灯織の気持ちは伝わっていない。

そして、二人が行ったSNSの投稿によって、自分がイルミネの一員として承認されたことについては、仕事をしたという事実に基づき意識の上でも納得できた。
ここでようやく彼女は素直な喜びを見せる。

風野灯織は番組への出演という仕事を受けたことで必要な承認を得ることができた。
そして彼女は今日が櫻木真乃のCMが放映される日であることを思い出して言及する。
これは、従前の彼女が自己の納得を伴うイルミネーションスターズの一員としての承認を得られず、メンバーの仕事について同意するような振る舞いや単純な感想に限局したことだけを意識することに徹していたことと対比している。
承認を得られたことで初めて櫻木真乃の様子を意識する余裕を取り戻すことができたのだ。
そしてこの自然な発言こそ、イルミネに相応しい、素直な主体としての行為であり、イルミネーションスターズの彼女らにとっての「応援」なのだろう。
第2話の車中でプロデューサーに告げた「二人が忙しいときほど応援しないと」という、論理が存在しない不安な言葉が改めて否定される。
名実共に彼女はイルミネの一員になれた。

そして街には櫻木真乃のCMが流れている。
――「走れご飯!送料無料キャンペーン実施中!」「お届けちょっきり20分」「食べる人にぬくもりを、作る人につばさを、届ける人にきぼうを」「わたしたちがフードデリバリーの明日を応援します」。
プロデューサーが取ってきて、クライアントに雇われて、七草はづきの思い遣りで身に付けて、そんな誰かの思いを運ぶ、明るい希望に満ちた言葉は、誰にでも届くようにと簡単な言葉で書かれたおまじないで、生きる人々に向けた応援だった。
――しかし風野灯織が眺めるSNSには、フーデリで働く人々の大きな不安が形になっていた。
この応援は誰かからの応援を期待するもので、このおまじないは、無視してしまったのかもしれない誰かに呪われていた。

この話では、人間であるならば客体化を受けることを肯うよう求める。子供でも分かる社会のルール、「仲間に入れて」、あるいは「郷に入っては郷に従え」を描く。
また、その一方で、サッカー番組に出演する前にサッカーやテレビ番組に客体化を受けていないという本質的な状態は、決して同じ番組に出演したという実存に優先しないことが示される。
例えば、このシナリオの文脈に準じて言えば、物語的分りやすさとして描写されてこそいないものの、やってきたADの挨拶を皮切りにして出演者との挨拶は交わされただろう。
また、イルミネの二人や彼女らのファンはもちろん、サッカーファンの一部(あるいは大勢)にすら「風野灯織のVAR!」のコーナーは間違いなく肯定的に捉えられたものであったろう。
実存は本質に優先するのだ。
気持ちより行為が先にある。彼女がサッカーが好きかどうかという本質は、あるいはサッカーが好きであるべきだという正義に基づけば悪である彼女の感情は、サッカー番組に出たという実存に優先しない。ここでの本質、気持ちは後から付いてくるものだ。
この哲理が暗示するものは、「結果が全て」というような救いのない現実である。今回の話において、プロデューサーに仕事を取り付ける能力があったから風野灯織の問題は解決したが、能力がなければ苦しみ続けたろう。この点については力のない弱者にとってはある意味救いのない現実的な様相である。
そしてそういった力というものは、持って生まれれば必要がなく、持たずに生まれたとすれば、実際の努力という行為の中にしか結実しないものであるという点において、属性的格差と本質の無力さが厳然と存在する。
これは生きることそれ自体の残酷な事象であり、必ずしも物語の事象ではない。
ただし、この残酷な描写は少なくとも現実において誤りではないという点において、弱者を仮初めの御為ごかしで救われたように見せかけて良いように利用し、その実責任を果たさずに置き去りにしていくような姑息なおまじないより余程爽やかではある。
最後に提示されたSNSでのフーデリ配達員からの批判は、フーデリというものが一般的に取っている個人事業主への業務委託という形式に見られる本質的主体尊重と実存的客体化という強烈な欺瞞について取り上げる。
またそれだけでなく、おそらく「送料無料キャンペーン」はフーデリ配達員の報酬にはさしたる影響を与えないよう設計されている可能性が十分にあるというところに、不安がもたらす危険が仄めかされている。
また、SNSの発達により相互に言葉を参照できるようになったことで、日夜発生している企業や運営と消費者あるいは従業員や参加者における主客の関係の更なる曖昧化および複雑化と、それに伴う錯誤の様子が描写された。
車輪は回る。
誰にも止められないこの回転は運命のように。車輪は回る。何かをはこぶために。車輪は回る。何をはこんでいるのかも知らずに。車輪は回る。軋む音に眉を顰められて。車輪は回る。あるいは気づかれないままに。車輪は回る。
僕達は誰もが車輪。
第4話:3つの夜
この話では、自意識上の危機的な状況を脱することで、ようやく正常な認知をもって自らのことを客観視することができた風野灯織を描く。
また、フーデリ企業のサッカーチーム経営の参入と彼らの試みによる彼女らへの影響についても言及し始める。
冒頭では櫻木真乃が広告を務めたフーデリ企業がサッカーチームの経営権を獲得したところから始まる。

櫻木真乃はピンクの帽子という制服(フーデリによる実存上の客体化を暗喩する)を被った配達員に、誰にも聞かれないが故に見返りを求めないことが確からしい「応援」を行う。

一方では、八宮めぐるは自身がモデルを務める「エシカル」な服の宣伝の一環として、服の作成過程を配信で紹介している。
八宮めぐるがインタビューを行いながら「エシカル」な服について様々な説明を受けていく。竹が原料であることや化学合成繊維ではないため土に還るなどの説明を受ける。廃棄手順を守るのであればどちらにしろ燃焼して廃棄することになる。例えばこういった製品を買う都市部の人間がコンクリに覆われた近隣の土地から離れて、遠路はるばる郊外まで服を一着不法投棄しに行く様子は是非とも見せてほしいものである。

そして、八宮めぐるは、スタッフに対してその服は倫理的な「いっぱい考える服」なのかと質問をする。
取材を受ける体の彼女は「素敵な言い方ー、いっぱい考えてるつもり」だとそこそこに答え、すぐに生産している服の売りである「環境への優しさ」についての説明を続けた。
八宮めぐるはそれに対して「環境のことを考えている」服だとただ喜ぶ。

配信の視聴者たちは、そのやり取りを受けて概ね好意的な反応を取っているが、コメントの中には否定的なコメントも見られた。

同じ時間に、風野灯織は以前から引き続き、サッカーの情報番組のコーナーに出演していた。
撮影の前にスタッフから矢継ぎ早に指示(客体化の基本に準じ、一時に多重に行われる点において方法としてドチャクソ下手であり、更には自然な笑顔という主体の領分となる行為を客体化によって実現しようとするという点で内容としても矛盾しており有効でない)が飛ぶ。
彼女が何かを修正できるわけもなく番組は進んだ。今回は生放送だった前回とは異なり収録であったが、前回の放送と何も変わらず台本から離れたサッカーの話は分からなかった。
蚊帳の外の彼女は番組収録後の撮影現場で、挨拶だけでもと出演者に近寄るが、彼らはサッカー業界の話で盛り上がっていた。彼らは好きであることに共通して客体化を受けている集団なのだ。
風野灯織は番組の話に参加できなかったときと同様の疎外感を覚え、彼らに話しかけることができなかった。
ここでは、八宮めぐるの広く一般的な対象に向けた配信と、サッカー出演者同士の内輪話を対比し、後者に参加できない風野灯織を描いている。

そんなこんなで一日を終えたイルミネーションスターズの彼女らは、定例の報告会を行っていた。
そこには、自分の一日を振り返って、配信を卒なくこなした八宮めぐると自らを比較する風野灯織の姿があった。
ここだけを見れば風野灯織は落ち込んでいるように思われるが、少し前までの彼女からすると精神状態において目覚ましい改善が見られる。
以前の彼女は、イルミネの彼女らと自身を比較することで発生する感情を恐れて、彼女らの感情や自分を意識することさえ避けていた。
しかし、ここでは自らを客観視して八宮めぐると比較し、口に出すことまでできるようになっている。

そして報告会は続き、櫻木真乃は持ち前の素直さで自らの何でもない一日――レッスンを受けて、学校に行き、そしてピンク色の帽子を被ったフーデリ配達員を見たというだけの一日――を何ら虚飾することなく話す。
彼女は、今日見かけた配達員が、もしかしたら以前ほんの少し話に上がっていた「兄やん」だったのかもしれないと面白くなったようだ。

そして「兄やん」について覚えていない八宮めぐるへの説明を通して、いつのまにやら風野灯織は独白していた。
彼女は自分が想像する「兄やん」のことを正直に話していた。彼がどんな景色を見ているはずなのか、どんな思いで走っていると感じているのか滔々と話す。
彼女が自分の理想の姿を投影したイルミネに相応しい素晴らしいはずの「兄やん」は……自分は、「すごく頑張っている」のだと呟く。
これは本当に辛い時期を終えてなお、彼女の真面目な意識が許さない弱音であり、無意識の不器用な告白であった。

今度の彼女らは、不器用な彼女の不自然な言動を追求しなかった。第1話からの対比がある。

その裏では、プロデューサーが仕事相手である広告会社の営業と一対一での飲酒を含む食事をしている。
後ほど分かるが、これは楽しみというよりは付き合い、いやむしろ商談でしかないようだ。
ここでは建て前という「おまじない」を提示している。

この広告会社は櫻木真乃が宣伝を務めるフーデリ企業の案件を担当しているらしい。
この営業は「283さんもすごい」、「フードデリバリー大手のあの企業は勢いがある」と、特に商談をまとめるために相手に言い分を飲ませる仕事をしている営業という職種に相応しく、仕事に役立つ「おまじない」を徹底する。
これは他者にだけでなく、自分に対してもこれは行われている。会話にはあらゆるところに場を和ませたり、自己を警戒させないための演技が含まれる。自己の卑下や、過剰な表現、間の抜けた伸びる語尾などを混ぜ、そして慎重な振る舞いができないようにと酒を飲ませるための断りにくい振る舞いを選ぶ。

彼はクライアントであるフーデリ企業からサッカークラブの話を聞いている立場にあることを伝えつつ、自分はその件についての関りが薄いのだという体を装う。
このクライアントは櫻木真乃を起用したCMに「予想外に反応が大きかった」ことを理由に、「イルミネみたいなクラス」をサッカークラブのハーフタイムショーに起用したいと考えているとのことだ。

検討すると答えたプロデューサーだったが、この営業はすぐにでも明確な答えを欲しがっているようだった。
そして、ハーフタイムショーにイルミネを起用するつもりであるという話は、実際にはもう詰まっていたらしいことが物語として明かされる。
広告会社営業の強引なやり方の背景には、この話がクライアントから持ち上がったのが開幕戦まで間もない時期であったことが予想される。
イベントの開催に当たって現場で実働するイベント会社のための準備期間や宣伝のための期間、チケットの販売期間……諸々の場所で働く関連各社の全てに共通する時間の要請に少しでも応えるために、広告会社としては出演依頼の要請と了承をもらうための待ち期間を用意することができない状況にあったと考えられる。

また、広告会社の営業から語られる話と、既に話が詰まっていたという状況から、フーデリ企業がどのような感覚でイルミネにハーフタイムショーを起用したがっていたかが暗示される。
まず、櫻木真乃によるCMの反響が予想外であったことから、アイドルとそのファン達というものについての市場規模や特性などをあまり理解していないということだ。
「アイドルのファン」というものは、押し並べてアイドルのファンであることを自分の存在証明の一部に持ち、アイドルという主体の活動を通して「何でもない自分の退屈な生活」が「推しのいる素敵な生活」になることに幸福を感じている。彼らはアイドルという存在に客体化されているのだ。
そんな彼らは、自己の「推しのいる素敵な生活」を送る幸せな自分を守るために、アイドルが主体として十全に活動できることを望んでいる。
そんな彼らは、アイドルの彼女が主体として存在できるように彼女の権利を十分に拡充するための奉仕活動を行うだろう。それは例えば、推しに次の仕事が入るようにと、推しの宣伝した商品を購入することでもあるのだ。
敢えてその実存に準じてはっきり悪し様に言うが、客体化された人間は金になる。これ以外にも様々な理由で客体は金になるのだ。広告社が、特に自意識において客体の占めるところが大きい傾向を持つ若年女性を指して「F1」層と呼ぶのにはそういった理由がある。
繰り返しになるが、ファン活動の喜びとは、推している何者かに客体化される喜びなのだ。それはいわゆる同担とのコミュニティでの楽しみも当然含む。
そして、推しのために、主体の権利を保障するための物質である金銭を放棄するという形態を取る「貢ぎ」行為は、極めて象徴的で、極めて大きな喜びをもたらす「推し事」の形態だろう。
「個人事業主への業務委託という主体尊重の形態を取りつつ(某フーデリ企業はこの個人事業主を「パートナー」と呼んで対等を主張しているらしい)も、制服を着せマーケティング戦略には一方的に巻き込み客体化するという実存的雇用関係を構築する」というやや込み入った詐術を弄するフーデリ企業であるにも関わらず、アイドルのファンというものがどれほどアイドルに貢ぐ存在であるかは理解していなかったようだ。
このことから、彼らはアイドル業界というものをほとんど理解していないことが推察される。
そしてこの無理解が前提にあることで、営業の言葉とは裏腹に、実際のフーデリ企業にとっては「CMでの予想外の反応が確認されたアイドルの女の子が所属しているらしいグループ」としてのイルミネーションスターズを雇おうというのである。
彼らはイルミネーションスターズのことなど何も知らず、取り敢えず一定の広告効果が見込めることが分かっている彼女らを場当たり的に起用したいという意図を持っている。
つまり、「おまじない」や「欺瞞」を駆使するこの営業が、さもクライアント側からの言葉であるかのように吹聴した「イルミネみたいなクラス」という言葉にまんまと嬉しくなってしまったオタクがいたはずだ。
君は、やや悪条件の仕事を取り付けることに全力を尽くす狡猾な男から出たお世辞であるという認識が甘くはなかったか?
「何か嬉しい」などとツイートしたそこのオタク、君はここまで散々繰り返されてきた「おまじない」あるいは「欺瞞」の表面が、少し自分にとり気持ちの良いものに変わっただけで騙されてしまう甘っちょろいオタクなのだ。
同じような状況で嬉しくなってしまった挙句に、良くない条件とタイミングの仕事を振られたら断れるか?「条件はあんまり良くないけど……まあOKしちゃお!」とならなかったと言えるのか?
少し反省した方がいい。
視点は戻り、イルミネーションスターズは毎夜の報告会を終えている。
そして風野灯織は心配されている自分を顧みて独り言る。
しかし、これは第2話の認知的不協和の結果が産み落とした発言である「二人が忙しい時に私が応援できる方がいい」からの対比であり、認知的不協和を解消し、客観的な視点を取り戻せていることを示している。
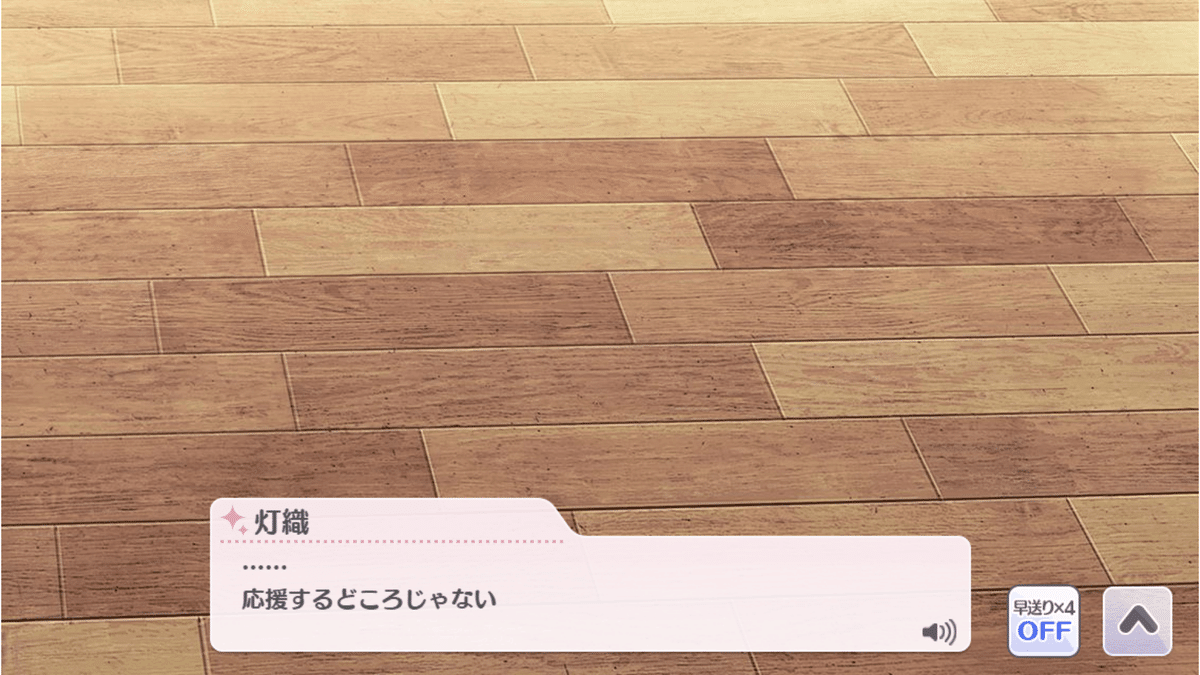
画面の上の私たち、画面の彼此の私、対面しあう私たち、皆それぞれに色んな誰かを思っていた。
だから、3つの夜は、幾つもの夜に繋がっていた。
第5話:みんなが
現地観戦と埋まるスタジアムと実際にサッカーに関わる人々を通して風野灯織の状態に大きな改善がみられる。
また、様々な批判を引き起こす行為者であるフーデリ企業の社長から、自らの行為についての所感が告白される。
そしてハーフタイムショーに出るイルミネを目当てに集まったアイドルファンとサッカーを目当てに集まったファンからの不満の言葉から、不安なファンへたちにより誹謗中傷が拡散することで炎上が発生する。
プロデューサーは、断ることが非常に難しい前話の仕事(ほとんど話が進み切っているこの話を却下すれば、当該営業の評価を大きく下げることになり、今後の仕事での優先順位が下がるなど差し支えがありかねない)を受けるのか、彼女らの意志を聞いている。
そしてイルミネーションスターズの彼女らは、皆が「他の二人が良いのなら仕事を受けても良い」と答えている。
いつもの彼であれば、「君たちの意見が全てだ」とか「嫌だったら断ってもいい」と必ず確認するところであるが、今回はそれを聞いている様子が描写されない。単なる省略であるか、それとも実際には断れそうにもない様子を反映してのことなのかは分からないが、物語的文脈からは個人的には後者だろうと思う。

広告会社営業からお礼の電話が来ている。
イルミネのハーフタイムショー出演により、チケットの売れ行きは非常に良いらしい。
この電話は、大いに喜ばしい結果への感謝とともに、今後の仕事も共関係を続けていきたいという意志表明である。
そして何より、状況から必要だったのかもしれないとはいえ、様々な「おまじない」を用いて半ば嵌めるような形で仕事を取り付け、プロデューサーひいては283プロダクション側の主体を大きく侵害したことに対しての言外の謝罪を含む連絡でもあるだろう。
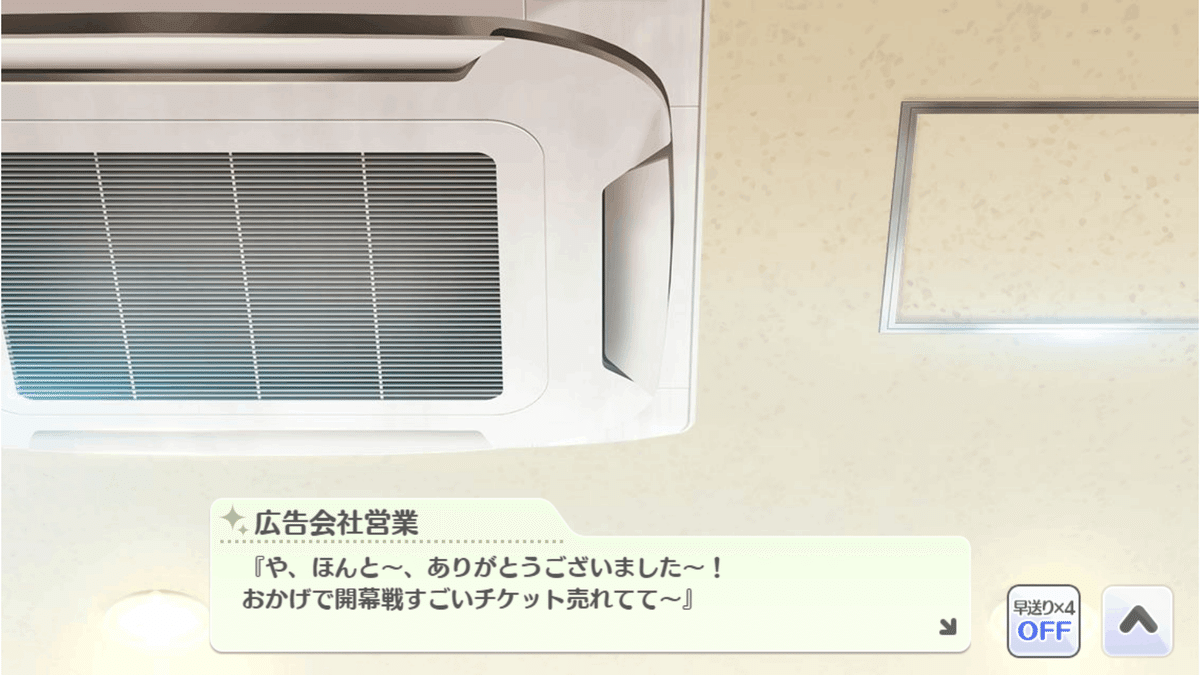
そしてこの広告会社営業は、この商談によって自分が確かに利益を享受することができたことを報告する。これは、他者であるプロデューサーの主体を侵害して、それでもなお何も得られなかったのであれば、それはただひたすらに無駄な犠牲であり、そこにはプロデューサーなどが不快な思いをした以外に何も残るものがないという状況になる。
この個人的な受益についての報告は礼儀である。何者かが確かに利益を得られたのだという報告は重要なものなのだ。
感謝というものは常に純粋無垢たるものではなく、往々にして謝罪ですらあり、虚無に対抗するためのものでさえある。
そして今回の彼の感謝は、今回の関係において自己が譲歩を強いたことを認め、今後の便宜を約束するものである。

プロデューサーはそんな広告会社営業に対して、自らも享受した利益を伝える。しかしこれは純粋な社交辞令であるように思われる。
櫻木真乃や八宮めぐるが別の仕事で忙しいにも関わらず、前話にて「丁度良いタイミングだ」と語っているように、彼は風野灯織の精神的苦境(イルミネに相応しくないという観念によるもの)が、彼女らの一人としてのパフォーマンスを行うことで解決することを期待したと考えられる。
しかし、以前からの受けていた「風野灯織のVAR」の仕事によって、肝心の彼女は出演できず、パフォーマンスをする二人と、遠くに離れた席で見ているしかできない風野灯織という構図が生まれてしまった。彼と彼のアイドルにとって、このハーフタイムショーは仕事が忙しい二人にさらなる負担を掛けるばかりか、風野灯織の疎外感を深めもするという良くない仕事になってしまっている。
そのため、今回仕事を受けたことについての彼の本音を言えば、この仕事は「いい機会」とは呼べないものとなってしまった。しかしながら、今後仕事で長く付き合いをしていくという意志を持つのであれば、ここで社交辞令の嘘を吐き、正直や誠実を偽っておくことは重要な礼儀であるのだった。

一方、当の風野灯織は公園でリフティングの練習をしていた。前話で描写された「サッカー番組に相応しくない自分」を変えるため行っているやや方向性が間違っていそうな行為である。

そんな彼女のもとに、元からの仕事に加えてパフォーマンスの仕事が増えてしまったイルミネの二人がやって来る。
彼女らは「ゲーフラ」というサッカーファンにはお馴染みの――サッカーファンであることを証明するような象徴的な――応援グッズを作ったらしい。そこまでする必要は必ずしもないのだが、その理由を尋ねると彼女らは「仕事だから」と答えている。
そして一方で「仕事に持っていくことのできない」風野灯織のゲーフラも作ったらしい。それから言葉の上でもお互いのことを「応援」していることを示し合う。

そして日々は過ぎ、開幕戦が始まった。
スタジアム現地は、広告会社営業の言っていた通りに、これまでの地味なチームにはなかった熱気に包まれていた。
放送席では風野灯織がいつもの番組メンバーたちと中継を行っている。スタジアム現地の感想を求められた彼女は「圧倒されている」と答える。
すると、これまで彼女とはろくにやり取りのなかった解説者(御大と呼ばれていることからサッカー業界の大御所と思われる)と初めての応答があった。「クラブが必死に運営してる」「スタジアムでの観戦をお勧めしたい」とのことだ。
ここでは、解説者もまた、アイドルに客体化されたファンと同様に、サッカーあるいはサッカー業界というものに客体化された者であり、サッカーチームが主体として安定して存続することを考えていることが端的に示される。
この応対による彼の微かな承認は、スタジアムでサッカーファンの自分と同じように熱気を感じた彼女への共感であると同時に、イルミネーションスターズというアイドルグループが確かにサッカー業界に寄与する可能性を認めた上でのことでもあるのだろう。


ハーフタイムショーのためにやってきた櫻木真乃と八宮めぐるは、沸き立つスタジアムにいつもの「イルミネーションスターズのライブ」との違いを感じている。
二人はいつもと違う緊張感を感じているが、そこに含まれる危険には気付かなかった。


そして、櫻木真乃は偶然通りがかったサッカーチームのロッカールームで監督と選手たちの言葉を聞く。
彼らは、将来の日程などではなく、純粋な目前の試合に向けて集中するのだと鼓舞し合っていた。
「今日、今、走れ」という彼らは、クライマックスを意識する人間と同様に、非常に主体としての自覚が強い。
ここでの彼らは主体の確認を行っているのだ。

一方の風野灯織もインタビューのために控室へ向かっていた。こちらのチームでもまた、監督が選手たちに目前の試合に集中することを促す。
こちらでは、主体として全力を尽くさなければ、試合に出場できなかった者を劣った者として客体化したことを納得させられないことを示す。
ここでは、行為者が暗に要請されている主体として存在するために全力を尽くすことが示される。
これは両者ともに、行為における自己の主体を確認し、行為において自己が主体として全力を尽くすということが、非常に多義的に、著しく重んじられ、あらゆる価値に富み、甚だしく強く願い願われるものであるということを、強く、強く、示唆するものである。

控室ではスタジアム用にといつもと違う濃いメイク(強い客体のモチーフ)を施された八宮めぐるがいた。ここでは、普段と違う舞台であることを通して観客もまた普段とは異なることを暗示している。
そして未だに戻らない櫻木真乃を探してプロデューサーは控室を出る。

さて、その後も控室への道に迷っている櫻木真乃は、偶然にもフーデリ企業の社長に出会った。
彼は広告を打つために雇ったアイドルの少女に対して、これまでのお礼や今回の急なライブのオファーについての通り一面の感謝を伝える。
これは社会人としての社交辞令に類するものである。このような目上の者からの挨拶に対する返事は、普通の場合には謙遜しながらやはり簡略な挨拶を返すものだろう。
しかし、櫻木真乃は純朴な真心によってこの社長に誠心誠意の感謝を伝える。
そんな純粋な彼女を見てきっと理解できないだろうと思ったのか、彼は一瞬ながら弱気な告白を始めてしまった。
そんな折、出会った彼らをプロデューサーは遠くから目撃している。

この告白は、他人の批判の言葉をきっと表面的には気にも留めていないように見せてきたのかもしれない彼が、しかし一人の人間としては当然ながら気にしていたことについてのセンチメンタルな告白だ。

プロデューサーは告白を始めた社長に何も言わなかった。
彼は、社会人として様々なデリカシーや暗黙の了解のもとに様々な欺瞞に巻き込まれ、何より主体としてのアイドルという彼自身の理想を欺瞞に満ちた「おまじない」という客体化に晒すことを耐え難い苦しみのうちにかろうじて受容しているような男だ。
そんな男が、このような欺瞞を強いた、欺瞞の権化とも言えるフーデリ社長の情けない告白を、激しい沈黙のうちに見守っている。

そして社長が続けるのは、大の男が語るには余りにも青く、身綺麗な流通の美学であった。
しかし、彼はフーデリ企業の社長である。欺瞞に満ちた拝金主義者のクソッタレとして実存上の従業員である個人事業主には苦しみを強い、SNSには仲違いを引き起こしている。そしてその実存を御為ごかしのおまじないで飾ることさえした!
彼が自らの事業にあるはずの耳触りの良い本質を語る資格はない。
彼がその事業を興し、運営し、そしてそれが多くの問題と欺瞞の中心になった以上、せめて彼にできるのは、常に明確な怒りの対象となることであり、彼らに欺瞞を強いた行為者であり続けることであり、そして何よりそれでも彼を信じて共に働く者のために己の行為に対して強く自信を持つことなのだ。
つまり彼は主体であることが「求められ」ている。
何をまかり間違っても、自らが正しいのだろうかなどと不安に思ったり、何者かに自らを承認されることを願うなどという甘ったれた態度は許されない。
誰かに弱気な姿を見られれば自らを信じた仲間たちがどれだけの不安に晒されるのか理解していればこそ、それが虚勢に過ぎぬとしても、男の姿は自信とエゴイズムで満たされていなければならない。

しかし、この純粋な心根の社長が並べる綺麗な言葉を聞いて、櫻木真乃は――今回、彼が自らの決して綺麗とは言えない事業に巻き込んだ明らかに無垢な少女は――彼が読み上げさせた綺麗事そのものである彼の本質的理想に思い当たる。
そしてこの悪人であるべき男は、暗い通路で人知れず救われた。
櫻木真乃はその素直と純朴から、この普段は傲慢と見紛わんばかりの自信と利己主義者を演じているのかもしれない男が、いつも感じているに違いない大きな苦しみについて理解できなかっただろう。
そして彼も、決してこの苦しみを感じるような弱さを認識されるべきではなく、そしてこの一幕を決して知られるべきではない。
プロデューサーもまた、許されざるこの瞬間の告白について彼の沈黙を貫くべきであった。それが「おまじない」や「欺瞞」に満ちた社会で、それでも生きていく者としての黙契であり、この秘密を守ることもまた礼儀なのだ。何より、それは未だかろうじて侵害されていない櫻木真乃の無垢に対して果たすべき責任でもある。
一通りの懺悔が終わった社長は、明るい控室に繋がる通路の角の前まで櫻木真乃を送る。
彼と彼女の邂逅は秘密でなければいけない。

そして視点は風野灯織に移る。
飲み物でも買いに行かないかというプロデューサーからの提案に彼女は一度頷きかけるが、自分でも試合の全てを見ておきたいと言って断る。先刻のサッカーチームが示した「今」というものへの集中に感化されたらしい。
ここでさりげなく風野灯織が今回の話で抱え込んだ大きな主題の一つが解決する。
即ち、現在への集中による主体意識の向上と、サッカー番組のチームに属するものとしてサッカーに集中するという条件が満たされた。
ここでは承認を得るために重要なのは、必ずしも承認欲求にただ従うことではなく、時に主体であることでさえあるという実存を示している。

アイドルと社会に生きる彼ら彼女らとの様子とはまるで関係なく、サッカーの試合はどんどん進み、スコアレスドローでハーフタイムを迎えた。
緊張感のある良い試合だ。
久し振りの、永らく待ち侘びたサッカー観戦。フロントが代わって不安と期待ではち切れそうな開幕戦だ。
スタジアムはいつもと違って満員で、熱気に満ちた観客席に座るサッカーファンは、試合の緊張感を共有している。
そしてそこに試合の展開に不安を含みながらも、観客席は良い試合に立ち会えた喜びと、このまま良い試合をしてほしいという願いに満ちているだろう。
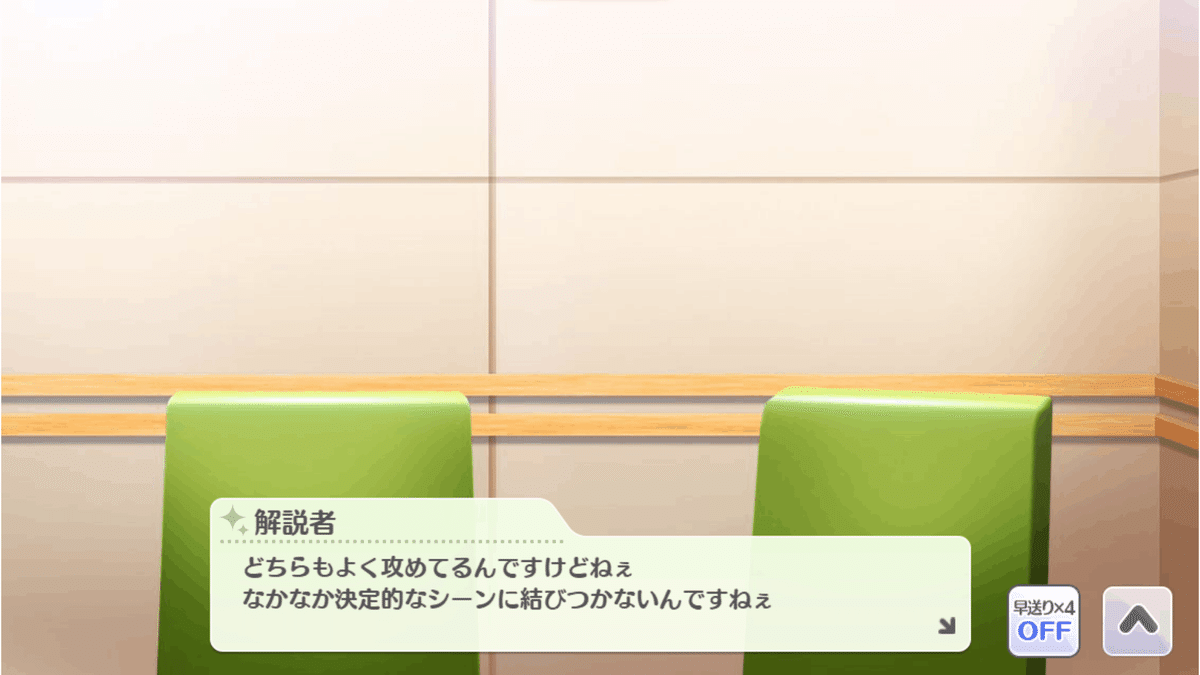
スタジアムの高まる空気を感じて、イルミネの二人はいつもとの違いを殊更に意識することになった。
この空気を感じて、八宮めぐるは「緊張がうつっちゃてるみたいな感じ」と評する。


これは彼女らの緊張が彼女らのものではないことを如実に示している。この緊張はサッカーの試合のために捧げられている緊張であることを。
そしてその危険を理解できないまま、彼女らはスタジアムに飛び出した。
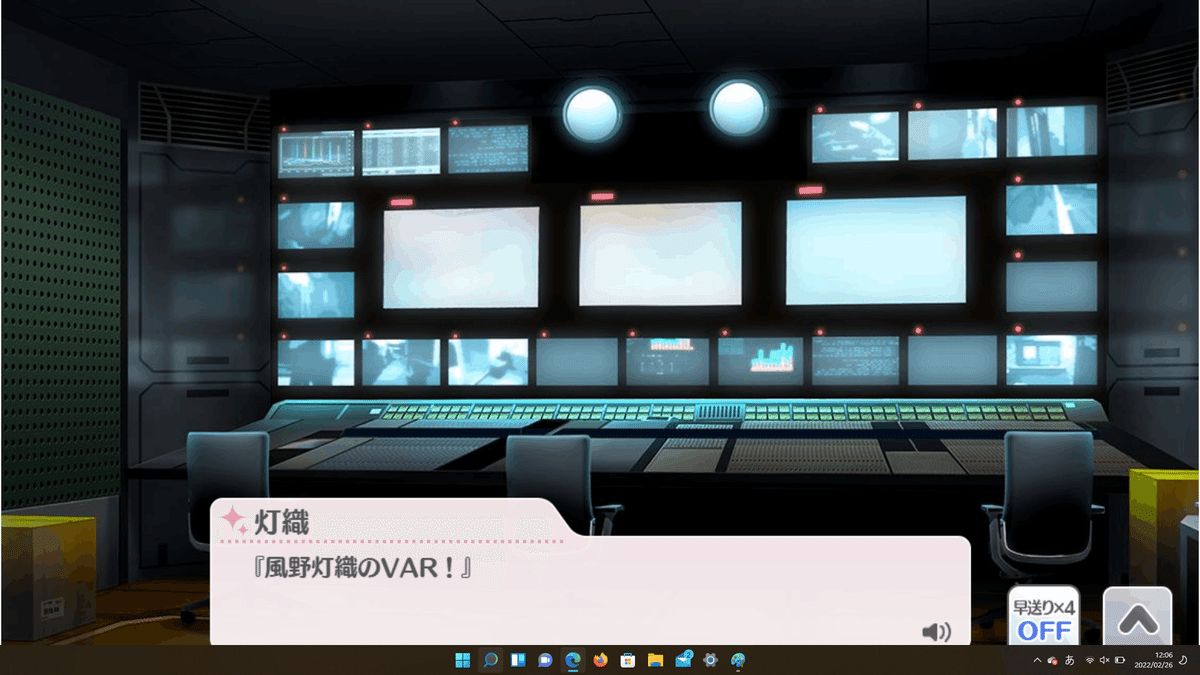
そしてスタジアムには心強い声援が響き渡る。「イルミネ」、「真乃ちゃん」、「めぐるちゃん」……あまつさえその場にいない「灯織ちゃん」の名前すら。
気高く走る男たちよりも高く、選手でもない彼女らの名前が呼ばれる。
スタジアムを包む心地良く張り詰めた勝負への緊張は、「キモい」オタクたちの大声で弾けてしまった。

ハーフタイムショーが終わり、やがて試合が終わった。
しかし描写されるのは炎上の様であった。
SNSに書き込まれる多数の匿名投稿は相互の集団への怒りに満ちている。サッカーの試合への緊張を台無しにしたアイドルファンという者たちへの怒り、そして自らの正当性と批判への反抗を示すアイドルファンたち、それを見て意見を表明する他チームのファンたち、そして何かを擁護せんとする多種多様の書き込み……。
風野灯織の番組出演にて僅かに仄めかされていた、異なる物に客体化された集団についての危機感が遺憾なく発揮された。
彼ら彼女らは雑然としていたが、彼らは共通して何かの「ファン」であった。そして彼らは共通して、自己の存在証明に係る彼らの主体が、少しでも安定して存続できるようにと試みる不安な者たちであった。
そして更に言えば、彼らは決して自らの主体など確認することをしていない。完全に客体化された存在として、彼らの主体が揺らぐのではないかという自らの不安を解消することにのみ専心している。
彼らの中で一体誰が、躍動する男たちの雄姿に、あるいは「推し」のパフォーマンスに目を向けているというのだろうか。そして彼らの「推し」の誰が、炎上などというものを望んでいるのだろうか。
SNSの、画面の向こうの彼らは、あるいは私たちは、乱雑で、同時で、不躾で、高度に、激しく、客体化を行い続けた。画面の向こうにある誰かのことを考えることもなく、お互いに及ぶ直接的な危険がないことに甘えて、どこまでも無礼に。
炎上とは、何らかの批判によって主体が消えてなくなってしまうのではないかという不安に支配された私たちの起こす、主体不在の臆病で無礼な争いだ。
炎上の構成要素に何らかの主体を確認できているらしい者は驚くほどに見当たらない。

みんなが何かのファンだった。みんなが弱い人間だった。みんなが強がっていた。みんなが臆病で、みんなが何かの救いを求めて、みんなが何かに耐えている。純粋な善人も純粋な悪人も、みんなが見つけられなかった。みんなが起こして、みんなが苦しむ事件だった。
第6話:きみの座らないたくさんの席
この話では、炎上を経験したイルミネの彼女らや周囲の人間たちによる人知れぬ反省と再起の試みが描かれる。
また、本作において通底していた風野灯織の成長も描かれる。
さらに否応なく他者を客体化する主体である人間として取るべき振る舞いについての主張が行われる。
プロデューサーは、八宮めぐるの撮影現場で仕事相手の何者かと通話しているようだ。電話の相手は彼と彼女らを気遣うことを言っているらしい。
後の描写から、彼は異なる相手に何度もこのやり取りをしていることが見て取れる。

電話が終わると近くにいたメイクスタッフが声を掛けてくる。「ごめんなさい聞いちゃって」と言いつつ、彼女は自己の視点から考えるイルミネの無罪をプロデューサーに伝えた。またそれだけでなく、サッカーファンサの友人による言葉を引用し、「一部のファン」こそが原因であると話す。
また、彼女は身近に発生したこの事件に興味を持ち、ネット記事まで探したらしい。小さなものが一つだけと語られるその記事に書かれているのは、「『デリバリー会社さん』が新規参入してきたから悪い」という内容であった。このレッテルを張るような記事に対して彼女は何も言っていない。
プロデューサーからは一連の炎上によって、イルミネの仕事には大きな影響はなかったことが語られた。
そしてこのメイクスタッフによる「283プロの関係者は悪くない」という旨の言葉にプロデューサーは安堵を覚えるが、そんな自分と、実際の行為に及びそして事件の中心になったイルミネの彼女らの精神を比較して自己嫌悪に陥るのだと言う。

ここでは、通話相手およびメイクスタッフによる「心配」あるいは「お節介」を描くことで、悪を定義することにより、自己の相対的善あるいは正義という客体化を得ようとする精神的営為が、日常的に、そして普遍的に、何より無意識に存在するものであることを描いている。
さらにこの日常的な思考方法と炎上という事件の実存における共通性を仄めかしている。
まず、メイクスタッフの彼女の思考においては、「一部ファン」を炎上の明確な原因としての「悪」と断じている。これと「デリバリー会社の参入」を「悪」とする小さなネット記事の主張との間に根本的な差異は存在しない。
炎上という事件においては、それぞれ異なるものに客体化された集団が、それぞれの集団を相互に自らの奉じる主体を脅かす「悪」であると客体化することで過激な発言に及んでいる。
そして、この発言の動機は主に自らが奉じる主体が揺らぐという不安を解消することにある。さらに、その不安を解消するためには一人一人が発言を取り止めることこそが重要であることは明らかであるが、不安のもたらす認知的不協和と不安そのものの大きさによって目前の安心を得るための発言を止められない。
また、このメイクスタッフは「サポーターである友人」の言葉を引用することで、彼女の主張において確認するべき主体の実存が曖昧であることを暗示している。
自らの主体の範疇においては、私たちは自分の言動についての責任を意識することになる。しかし、他者からの承認を受けることで、私たちは良く言えば大胆、悪く言えば放埒な物言いをする。
炎上における発言者は、自らの主体にファンとして、また自らの不安に支配された者として、さらには自らの信じる主体を脅かす「悪」に対峙した「善」なるものとして承認を受けている。
「メイクスタッフ」という演者を客体化するモチーフィックな存在による客体化という物語的構図および、炎上による複雑かつ激しい客体化を受けることで苦しい状況にありながらも心中を隠す八宮めぐるの撮影風景を描くことで暗示する。
ここでのメイクスタッフの彼女は、彼ら彼女らに演技を強いる炎上を暗喩する存在として描かれていると言える。

プロデューサーは、炎上を発生させたはずのそんな彼女の客体化の言葉に安心を覚えてしまう自己を嫌悪する。
「あなたは悪くない」として他者を客体化する――承認する――この言葉は、昨今SNSに氾濫する軽薄な言葉を用いるのであれば「ポジティブ」な言葉である。そしてこれは作中においては「応援」だとか、「おまじない」だとかと表現されてきたものである。
しかしながら、「あなたは悪くない」と言うとき、そこには必ず「悪」の存在を要求する。なぜなら、世界には「ネガティブ」なことが確かに存在するからだ。悪くない者が存在するためには、絶対に存在するこの「ネガティブ」な出来事を押し付けるための「悪」こそが欠くべからざる存在である。
「あの子たちは悪くない」という承認は、炎上という苦しい出来事の原因を押し付ける先の何かを暗黙の裡に必要としている。
そして、この悪魔化の手続きは、イルミネの彼女らにとって自身を苦しめ続ける炎上の原因そのものであり、彼女たちがライブを行った行為者として客観的かつ主体的な実存を持つ高潔さなどの理由から、受容することを許さないものである。
従って、ここでメイクスタッフがかける言葉でプロデューサーが覚える安堵とは、イルミネの彼女らとの相対化の中において、彼自身の行為者としての主体性が欠如していたという実存に直結している。
今回の仕事を受けた彼の判断についての経緯を振り返ると、広告会社の営業に流され、風野灯織に安心して欲しいなどと願っているばかりで、彼自身の意向や意志が十全に確認できていたわけでは決してなく、更には彼自身の信条であるアイドルの意志の尊重も曖昧であった。
そもそも社会で生きる人間は社会の構成要素として客体化されているという実存を一般に有している。そこで自分の純粋な意思を確認する機会などというものはまずない。仕事となればなおさらだ。
ここではそんなある種仕方がないと言わざるを得ない、彼自身の厳然たる現実と、主体として十全に生きるという人間の動物的理想は、現代においては果てしなく実現可能性が低いという現実が描かれている。

風野灯織は走り込みをしていた。夕方まで時間を忘れて走り込みをしていたらしい。
帰らない彼女を心配して探しに出ていたのか、プロデューサーに出会った彼女は、意外なほどに自分が落ち着いていると語る。炎上が自分を思っての行為から発生したにも関わらず、落ち着いていられる彼女は不思議がっている。

前話において、現在への集中を通して自己の主体性を高めるようになった彼女は、他者から複雑かつ激しい客体化を受ける炎上という出来事を経験した後でもなお落ち着いて、つまり様々な客体化による認知的問題を持たずに走り込みができている。
ここでは誰かに強いられてのものではない自己の意志で走っていることを通して、オープニングから繰り返されてきた「走る理由」を得ることができたことを描写する。
また、他者からの言葉や認知に左右されない現在の精神状態はこれまでの彼女からの大きな変化であり、そのことが彼女には不思議に感じられるようであった。

対外的には何でもない風に見える彼女らであったが、実際にはかなり気に病んでいるようである。
仕事を受けることを了承した彼女らは、全員が「他の二人がいいなら」と判断の過程に自分だけの主体としての意志を確認していなかった。このことが炎上という事件を反省する際に、炎上に至る原因としての他責の余地を生むことになっている。
そして、その他責という無意識下の防衛機制においては、やはり他者を「悪」と規定することにより安堵を得るという炎上に共通する精神的営為が見出される。
彼女らには持ち前の素直さはもちろん、炎上の中心となった当事者として感じることもあったのだろうか、彼女らが行う高潔な反省は難しいものとなっている。

そして櫻木真乃と八宮めぐるから彼女らの描写されない苦悩を経た反省として、炎上についての根本的な理由が提示される。
つまり「同一の空間に存在する様々な属性を持つ、即ちそれぞれ異なる物に客体化された集団が、それぞれに奉じる主体に及んだ曖昧な危機に不安を覚えることで、相手を絶対悪として客体化し安心を図るという防衛機制の連続的に発生し、いわゆる炎上が形成される」という現象について説明が行われる。

そして、今回のハーフタイムショーというサッカーファンとアイドルファンが混在する状況において、ファンに囲まれた――観衆が既に自身によって客体化され、ありのままの自己、つまり主体である自己が絶対善として肯定されている――普段のステージとの比較や、「ありのまま」でいいと言われたことなどを振り返り、八宮めぐるは「ありのままじゃわからないことばっかりだ」と悲しく笑う。そして「わかってたのにな」と反省する。
ここでは、孤独に耐えかね陽気な自分にならざるを得なかった八宮めぐるが、スタジアムに臨んだ自分の在り方を回想し、そしてその厳然たる現実を意識せずにいられた普段のファンがいるステージに恵まれていたことに気付く。
そして厳然と存在する苦しく不安な現実には、依然として対応しなければならないものであるとして、自らの手遅れを悔やむ気持ちにある中で、今の笑顔を保とうと試みている。

曇った女の子は可愛いけどー余りに不幸なのはちーがーうー大崎甘奈を曇らせてもー八宮めぐるを曇らせるなーああわれらのー八宮めぐるを曇らせるな高校
そのような様々な反省の中において、みんなが彼女らは自身に確かな過失があったことを認めている。
そして彼女ら、あるいはプロデューサーは「だから私が悪い」のだと言い及ぶ。

これは高頻に見られる他者を悪として客体化する行為への高潔な忌避と、自意識における軋轢の解消を両立する方法であり、しかし自己嫌悪の一つの類型である。
繰り返しにはなるが、これは自己嫌悪の例に漏れず、この行為においては自己を裁定する「真の自分」を作ることによって、実際の自意識的不安を解消しながらにして、悪であると認識する自己の罪の意識の分だけ真の自分が高潔な承認を得られる。これは自己に向けて行われる巧妙な詐術だ。
無意識に誰しもがやるし、自身を卑下するという点において高潔であると誤認してしまう。
例えば、キリスト教という集団がその教徒を客体化する際に用いている構造的原理は、不断に供給される動物としての感覚と欲求を罪として客体化することで自己嫌悪に陥らせる客体化である。近代科学の発展によってその存在可能性が無に帰した現代においても、なお根強く勢力を保っていることからもこの詐術は非常に強力な客体化を発生させていることが実証されている。
さて、「自分が悪い」と思い至ったイルミネの彼女らとプロデューサーであるが、「『みんな』で決めたことが重たい。」、「『みんな』を主語にするとあの子たちはそれが言えなくな」ると、ややまとまらないままの彼自身の高潔な感覚が語られる。
ここでは、自責という精神的営為は、不安を嫌って絶対悪を他者に押し付けないという点においては炎上の原理とは異なるが、仮定した真の自分によって自己を絶対悪として客体化する以上は、不安の解消のために何者かを絶対悪と規定するという原理において炎上との根本的な差異を認めない」ということがシャニマスくんから主張されている。

そして広告会社の営業からは今回の件についての直接的な謝罪などを含めた様々な言葉が提示され、プロデューサーはそれを意外なことだと感じている。
ここではさりげなく様々に行われるデリカシーは、例え対面していようとも、相互の認知機能の優劣や文化の差異によって必ずしも伝わらないことがあると暗示される。

そしてそのような表現を取るに至った振る舞いについての相互の謝罪を経て、社会人としての礼儀を保った話し合いに戻る。
そして、今回の炎上に繋がった企画においては、計画や告知などの運営に不備はなく、さらには観戦ルールには則って咎められることが妥当であると一般的に認識されるような振る舞いも発生しなかったことが確認される。またより細かな点に至るまで規定するルールという客体化は実現可能性が低いばかりでなく、「子ども扱い」という認知による客体化も行う無礼なものであることにも言及される。

そして広告会社営業の口から、改めて問題の根本的な原因が「違うやつらがいる」という状況における動物的忌避感によるものであることが示される。
また続けて、今回の過失についてはクライアントが勉強するべきところであると言う。
ここでは、広告会社に勤める人間である以上は、この営業がいわゆるクラスタが複数いる状態を避けるべきであることを知っていたことが予想される。即ち、今回の企画を発案し主導したのはクライアントのフーデリ企業側であり、特に社長の純粋な願いがもたらした失敗であることが暗示される。
またこのことから、広告会社営業の彼は仕事を行う存在として、やや不確かな炎上の可能性を把握しながらも自らの享受する見返りや発生する周囲の損害などを考慮し、それを諌めるだけの勇気を発揮しなかったことも示唆される。ここでは第3話でサッカーの試合にオフサイドの裁定を与えた「走る理由」を知る審判との対比がある。
そして、様々なデリカシーを示すことができるような広告会社の営業をもってしてこのような他人事としての態度を示さしむ様態からは、自己の行為における主体を必ずしも確認することができないという社会の現実を示してもいる。
現代の社会においては、かつての農業から家内制手工業あたりまでのように一人の手によって最初から最後までの産業が完結することがない。
陳腐な表現にはなるが、人間は社会の歯車として、あるいは社会の滞りのない供給の流れを担保する車輪として自らの実存を客体化されざるを得ないのだ。そして、そのような平和な社会にあるからこそ、私たちには自己の主体を確認するという現代社会においては難しい健全な個人主義が必要になったという背景が示唆されている。

そして場面は報告会に臨むイルミネの彼女らに移る。
彼女らは、プロデューサーから自責による自己の客体化によって、不安を解消することを戒められている。これは炎上と言う営為に共通した主体の放棄と自己の客体化による安寧の享受という点において根本的には悪魔化の手続きを取っているにも関わらず、自罰的な発想というものは当事者である彼女らにおいても客観的な妥当だと考えやすく、その妥当性を相互に承認する可能性があることを踏まえたものであると思われる。

しかし、風野灯織はこの炎上の原因をどうのように表現しようとも原因が変わることはないと言う。否定しようとするイルミネの二人であったが、彼女は頑なであり、彼女がそれを主張する以上は他者を客体化せんとする被害に遭ったばかりの彼女らがそれ以上に追及することもなかった。

そして彼女は彼女の知る範囲において、炎上という事件の原因――事象における因果関係においても、そこに通底する不安という精神的実存においても原因であった――イルミネに相応しくない自分という観念による自己の状態に思い至った。
さらに炎上を引き起こしたその日のハーフタイムショーに自分が出演することはなかった状況によって、批判される当事者としてさえ実存的に完全ではない自己を顧みる。
きっと炎上の中には、イルミネーションスターズというアイドルグループの全員が参加していない状況は、自身の応援するクラブがマイナーであるために見くびられたのではないかという不満の類を表明する意見もあったのだろうことを思わせる。
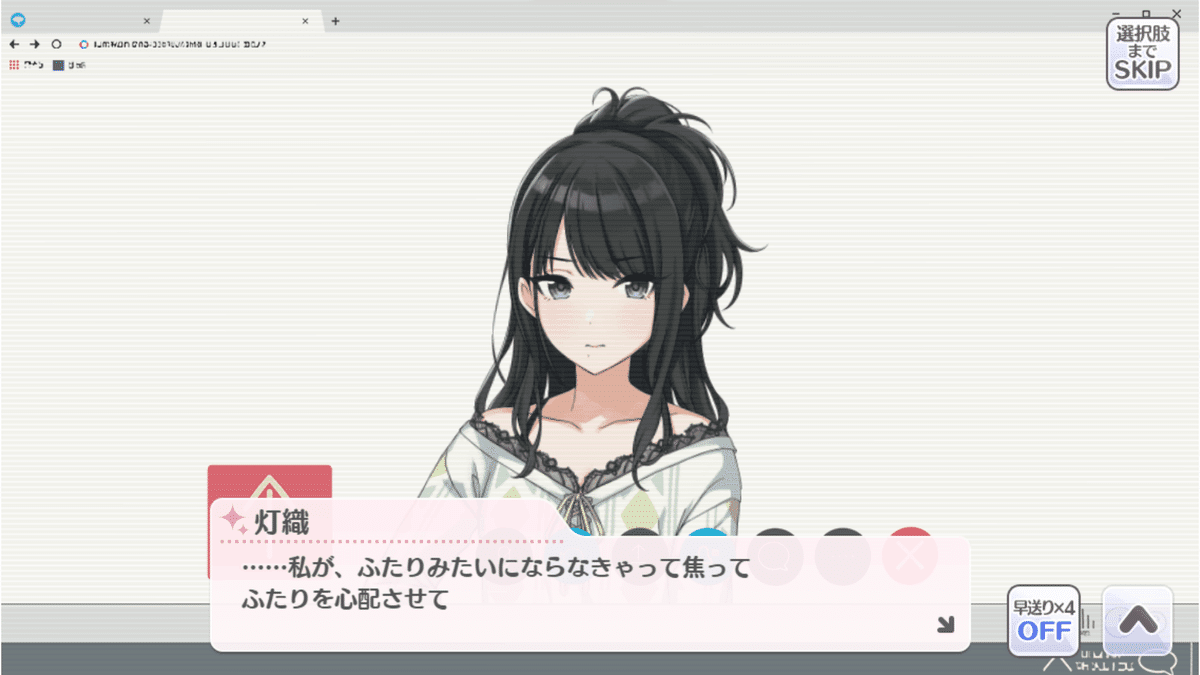
そして自己の主体を確認せずに仕事に臨んでしまった彼女らはそれを後悔する。
主体を確認することを疎かにした彼女らは、誰かに動機を委ねることは失敗した際の責任すら、実存的に他者に委ねることになるのだということを知った。
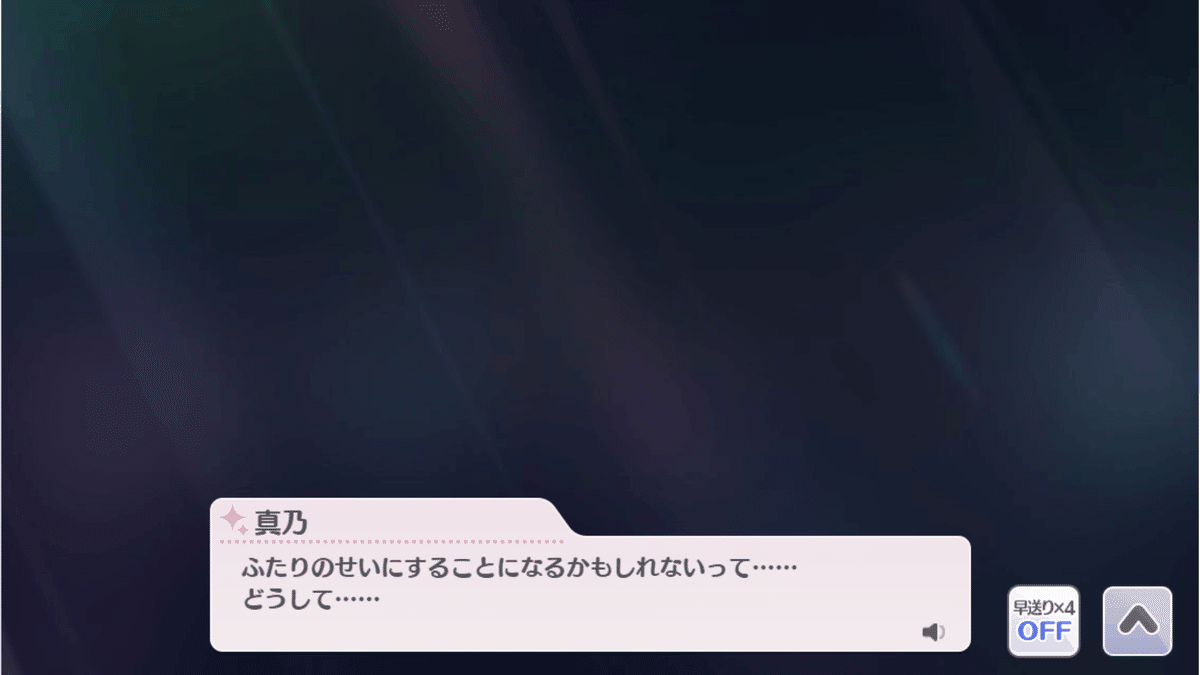
そして、広告会社の営業と話すプロデューサーは、ハーフタイムショーにおいて様々な存在のいる世界で、様々に客体化された存在が多種多様に存在する社会とその危険の片鱗を体験した彼女らは、その恐怖を知ってなお生きていかなければいけないのだという考えを述べる。
ここでの「未来」について補足すると、「未来」とはいつか来るものとしての未来ではない。これは実際に存在する現在という瞬間の積み重ねによって形成される私たちの人生において、現在から振り返ったある過去時点から、今におけるまでの現在の積み重ねを指している。
未来なんて実はどこにもないのだ。
即ち、彼が言っているのは、曖昧で細々とした未来に希望を抱くのではなく、実感を伴い存在する現在を、今回の反省をともに力強く生きていくということに他ならない。
また、ここでは再度、周囲の人間から彼女らは悪くないのだと言われる現状を説明している。
また、ここまでの主張から、この高尚な憐憫あるいは第三者によって行われる愛に満ちた同情というものには、「客観的にアイドルの彼女らに主体などを見出すことはできず、ただ従わされているだけの存在である」という認識を持つことが含まれ、つまり社会の参画者は主体であるという前提を満たしていないという認識を行っている点において、著しい侮蔑が無意識に含まれるという実存に即して同情というものを批判している。

そして広告会社の営業は、青いプロデューサーを「マジメだな~」と茶化しながらも、話には付き合っているらしい。やや礼を失したプロデューサーの言葉にも「え~」と返すばかりである。
彼が話に付き合っている理由には、今後の関係を見越し、炎上に繋がる危険性が高いと分かって強引に仕事を取り付けた自分の振る舞いに対する埋め合わせであることを否定できないのと同様に、彼の言葉が説く勇気などについて惹かれていないこともまた実存において否定ができない。

そしてイルミネの報告会では、誰かの前で歌うことが応援になるという魅力的な単純さに盲目であったことという反省が行われた。
そしてその反省は「誰かに何かを届けるのってとっても大変なこと」であるということを理解したことであり、明確な回答が出ないこととその明確な回答が出ない状況についての受容である。
そしてこれは今回のイベントコミュ【はこぶものたち】における、誰かに何かをはこぶものとしての彼女たちの、そして食事を運んだフーデリ企業の人々、仕事を運んだ営業、プロデューサーという社会の車輪でもある彼女たちの主題でもある。

そして、歌って踊ることで応援するという彼女らの活動は単純な「すごくいいこと」であるように思っていた彼女らであったが、「いいことって思ったより複雑みたい」という結論に至る。
特に「エシカル」に魅力を感じる八宮めぐるにとっては残念なことであるが、何らかの存在による客体化を前提とした「いいこと」というものは、実際の世界においては常により大きな枠組みにおける一構成要素に過ぎず、単純さ故に魅力的な「善悪」というものは単純な形態では存在しないのだ。
失意のもとにではあるが、彼女らはこの経験によって「主体を確認する」という、この世界において現代社会に生きる者としての全ての基本となる重要な教訓を得られた。

そしてそれを受けて、風野灯織も自分からこの仕事がしたいと確認することで自己の主体意志に即して仕事を受けるべきであったことが反省される。
これはイルミネのメンバーには関係ないただ一人の存在としての高潔さがあるべきだったという反省だ。

ここが主題であるためやや脱線して補強する。イルミネの彼女たちが主体を確認することを重要だとした考えた論理には、他責の余地が残る実存上の問題が中心にあるが、現代社会によって高度に客体化される私たちは、他にも様々な理由でこの考えが必要となる。
例えば人間は絶対的に「いい」存在として生きることなどできない。
生まれ育ちや能力の優劣など無数の巡り合いにより、私たちを客体化する存在は様々に異なる。そしてその客体化を行う存在の安定性や自己への客体化の強度などもそれぞれに異なる。
そしてそれらには、論理的破綻の有無による正誤や能力における優劣はあれど、本質的な「善」あるいは「悪」などというものは存在しない。
したがって私たちは快不快を問わない様々な事象に客体化を受けることからは決して逃れられない。そして私たちはそれでも生きようという主体でもあるのだ。主体として他者を客体化することで蹂躙することなど大小含めていくらでもある。例えば私は、過去に失恋した相手の名字がシャニマスに登場するアイドルと同じであることで心に残った柔らかい古傷が痛む。
他にも、実存や科学を追求した初期の西洋の人間の多くは、その矛盾と誤りの甚だしさという宗教的利点と表裏一体の当たり判定の大きさにを持つキリスト教によって「異端」の烙印を押されている。
私たちは道を歩けば草を踏むように、あるいは食事の度に動物や植物を物質に還元するように、私たちは、他の主体を侵害せずに生きることなど決してできはしない。
そんな私たちが他者に対して何かができる可能性がかろうじて残っているものがあるとすれば、他者を客体化してきた主体として、彼らを主体の不在という不安に晒さないことである。
そしてそうあるために強く安定してあることもまた、自己の主体を確認するという私たちの行為における精神の儀式に直結している。
そしてこの主体の確認においては、習慣による客体化を避けるべくして行われなければならならない。
そしてこの一回性を保証するための精神あるいは「けじめ」をつけることこそが本来の道徳なのだ。
余計な偏見を述べると、「人権道徳」などというのは有名無実であり、その実存は道徳を騙り広範にわたる世界の人間一般を客体化することで、無から普遍的な絶対善を創出しようとする規範における試みである。当然ながらこれは人権軽視の発想を悪としている点において、悪魔化の手続きを取っており従来の様々な存在と同様にそれ自体が絶対的な善や悪であることはありえない。
西洋社会の行ったキリスト教という規範による支配とその結果として高度に客体化された個人としての彼らが被っている精神生活の損失を思えば、人権道徳が私たちを幸福にするようには思われない。私たちを承認する存在はもっと確かに存在するものであるべきだと私は考える。それは必ずしも快い存在ではないだろうが、少なくともそこにおり、少なくとも現実の存在だ。
そして残る不安には耐える。そのための勇気こそが肝要なのだと考える。
さて話を戻そう。
広告会社の営業とプロデューサーが会話をしているそもそもの目的は、イルミネの彼女らから「スタジアムのボランティア」を行うという提案を受け入れてもらうためのものであったらしい。
このボランティアの希望は、イルミネの彼女らが、イルミネのメンバーとしてでなく、それぞが別々の個人として、自分だけの孤独な主体意志を確認するためのけじめであり、つまり本来の意味での道徳の実践なのだ。
然るに「ボランティア」という名称を便宜的に名乗りながらも、これは決して誰かへの奉仕ではなく、世界のためを思って行われる献身ではない。
ボランティアというものが雇用を奪っているというボランティア一般への批判を受けるかもしれないが、今回の彼女らはその批判よりも高い次元で道徳としての行為を実践している。

今回のボランティアが実現するまでの過程において、仕事に関係がないにも関わらず、広告会社営業の彼がこの話を先方へと取り次いだのは、先立ってプロデューサーに強引に仕事を取り付けた分への埋め合わせであり、この営業からフーデリ企業への取り次ぎが行われるのもまた今回の仕事についての埋め合わせなのだ。彼らは社会で生き仕事を通して誰かの思いをはこぶものたちとして描かれている。
そこに存在するプロデューサーと広告会社で営業として働く彼との間にある何らかの情緒は曖昧なままである。彼らはそこに不用意に踏み込まない礼儀という黙契を有している。

そして彼女らの回想が挟まれる。
冒頭から繰り返されてきたはこぶものの独白である。
風野灯織は、オープニングにおいてはバスに乗り、「兄やん」に自己投影を行うという思考における試みであったが、今彼女は実際に走っているようだ。同じ独白を繰り返す彼女には、やはり走る理由になるような何かは分からなかったらしい。

そしてそのまま「みんなのことをいっぱい考える服」についての八宮めぐる回想に移る。
当然ながら、「エシカルは欺瞞」であるという攻撃的な言葉を承認について敏感である彼女は真に受けていた。欺瞞とされるのも当然な「エシカル」の現状を知った彼女であったが、それならば「みんなのことを考える」という倫理的なものは不必要であるのかと悩んでいる。
それに対してプロデューサーは明確な答えを――他者により絶対的善であると認識される恐れがある何かを――与えないが、代わりに服の制作に携わった人々が何かを考えていたことが実際に服を着てみることで分かったのではないかと言う。
ここで彼女が来た欺瞞である「エシカル」な服について考える。「エシカル」な服というものそれ自体は無礼の集塊であるように思われるが、例えば彼らの本質的な発想においては純真であり、無知と失敗によって失敗したに過ぎないものかもしれない。
仮に彼らが環境保護を名目に同業他社を相対的に悪であると客体化した自身の無礼を理解した上で、商業的成功を狙ったのであったとしても、実際の仕事に携わった者、特に今回のコミュにおいてはデザイナーは、クライアントであるアパレル会社に雇われることで服をデザインさせられるという客体的立場にあってなお、服を制作する行為者としての自己の主体と責任を自覚し、彼女自身が全人的に取り組む仕事として考えて職務に当たっていたことが、お為ごかしに巻き込まれた世間知らずの幼い少女に行った倫理の説明などから見て取れる。
ここでは、「走る理由」を確信できないが走り出した風野灯織と、客体化を期する様々な事象に絶対善が存在しないながらも関わる人間の迷いや考えや、思いをはこぶものではあった「みんなのことを考える服」を着た八宮めぐるを通して、思考ではなく行動することにこそ何らかの活路が発見し得ることを示す。
また、その思いもまた行動する過程の中にのみ発生し、つまり行為に及ばなければ何も発生し得ないという知行合一の精神についての主張を行う。

そしてここでは、イベントコミュの題名【はこぶものたち】の含意が明示される。
平仮名で書かれたこの言葉は、「運ぶ者」として行為者である主体としての彼ら彼女らと、誰かにとっての「運ぶ物」として誰かのもとに届けられる客体としての彼ら彼女らの思いを示している。
行為や彼女らの存在には厳然と主客が混在することを主張する点において、これは本質あるいは物語を否定して実存あるいは生きることについて語っている。
また複数の人間を示す「達」により、彼ら彼女らの思いは客体化されているがしかし物質ではなく人格を有する人間であり、そこには様々で完全に客体化され切らない主体おしての思いの存在があるはずなのだというシャニマスくんのまあ大人っぽい情熱的なメッセージがある。
この素晴らしい題名が分からなかった人のために、敢えて簡単で冗長で野暮な表現に直すのであれば、「人々の思いを伝え、人々の思いに支えられ、人々のことを思うこと」とでもなるだろう。

そしてここでプロデューサーから、思いをはこぶものにして、はこばれる思いですらある彼女らについて、自分たちの思いを届け直してこそ、ようやく彼女らは次の活動に向かえるのだと語る。

そしてSNSには長らく更新が途絶えていた「兄やん」の、客体的動機によって働き、しかし同時に確かに自らペダルを漕いで「はこぶもの」の投稿があった。
彼もまた、物語によって決定的に否定されるべき客体的存在でありながら、生きることにおいては肯定されるべき主体的行為者なのだった。
彼は息を吹き返すようにこの作品に存在を証明する。

この話では、炎上を経験した彼女らが様々な反省とともに、この世界には単純な善も単純な悪も決して存在せず、また純粋な主体も純粋な客体も存在し得ないという本質および物語の否定が行われる。
そして代わりに提示されるのは考えることの重要性と、生きることに根差した数多くの爽やかな矛盾を当然のものとして是認する行動における哲学である。
これはごく簡潔に言って行動に即しており、今作においては行為において常に自己の主体を確認することと、まずは行為から物事から始まるという知行合一精神のもとの行動、そして生きる私たちが相互に主体であることを前提とした礼儀を中心としている。
実存における行為の圧倒的な重要性が示される。
よく分からんかったなら葉隠を読むとよい。
大変だろうから三島由紀夫が抜粋してまとめたやつでいい。
ヨドバシ.com - 葉隠入門(新潮文庫 み-3-33-新潮文庫) [文庫] 通販【全品無料配達】 (yodobashi.com)
葉隠入門 (新潮文庫) | 由紀夫, 三島 |本 | 通販 | Amazon
エンディング:運ぶ人
エンディングでは、ここまでに行われた様々な行為とそれについての懊悩に関してシャニマスくんからの結論が提示される。
またシャニマスくんは、シャニマスくんに関わる者を含む現代社会の僕たちは、頑張って生きていくべきなのだと主張する。
スタジアムでボランティアに勤しむイルミネーションスターズの皆から始まる。
八宮めぐるはスタジアムを一周しながらごみを回収してきたらしい。風野灯織と櫻木真乃も、誰の目に付くこともないロッカールームの清掃を終えた。

合流した彼女らは観客席を掃除する前に、そこで一服することに決めた。
誰もいない観客席は、試合が行われていた先刻までの賑わいもあり、彼女らには静寂そのものであった。

一方でボランティアに同行したプロデューサーは事務長への挨拶に向かっている。やり取りから、おそらくこの事務長はホームチームの事務長であると思われる。
彼が担当するチームの財政などを含めた業務を思えば、新規ファンの獲得や既存ファン安定にとって被害をもたらし得る炎上という騒動によって、最も大きな被害を被ることになった存在の一人と言えるであろう。


そんな彼に対してプロデューサーはまず謝罪する。
補足すると、大人の謝罪とは、主体としての自己が他者の主体を侵害したということについての明示的かつ相互の確認である。また大人の感謝についても、同様に自己の主体が他者の主体の行為によって受益したことについての明示的かつ相互の確認である。
ここで本当に関係なさそうな話をすると、子供の謝罪および感謝とは、大人による言いつけもしくは更なる自己の被害を減らすこと、あるいは更なる受益を得ることのみを主眼に置いた経験則や模倣からくる習慣に過ぎない。
ただし、感謝や謝罪、あるいは礼儀というものは、あらゆる場合においても客体とは実存的に不可分である。その点においては子供のそれであったとしても、それは等しく謝罪であり、感謝であり、あるいは礼儀である。
当然子供のした過ちに対して言われる「子供のしたことだから」というのは道理が通らない。客体一般がそうであるように、その謝罪には打算がいつも含まれて然るものである。
例えば、桜の木を切ったワシントンの子供が正直な謝罪を行ったとしても、彼には桜の木を再生させるバイオテクノロジーやそのためのあらゆる資源がない。
子供である彼は、大人とは異なり今後の関係の中での補填に係る能力や信用を持たない。
代わりに、そんなクソガキの彼にあるのは何か。それは桜の木のため誰かがした努力や救われた何者かの可能性をつまらない自分が破壊したという不安を、許容あるいは罰により解消したいという実存的打算である。
この話の結末は、少年がした正直な告白によって打たれることもなく許されるというものであるが、これを妥当に感じるのは、罪の告白により全ての罪が許されるとかいう客観性皆無のトンデモ理論を信じたがる面白集団である。彼らの告白万能論の破綻はナチスドイツに参画した人間たちに対して未だに行われる処刑行為が実証している。
ならば大人としてワシントン産のクソガキに行うべき行為は何か。それは間違いなく無惨な遺骸となった桜の木の下での、実存的正拳突きである。そうすれば桜に睦んできた人間も多少胸がすくだろうし、風雅な観覧者や正拳付きマンが感じることになる諸々の罪悪感や拳の痛みは、公共財を損壊させた取り返しのつかない子供についての監督不行き届きに関して甘受するべき大人の責任である。
そうやって一人の不安な子供の承認が痛みによって行われれば、他でもない彼自身の健全な打算通りに彼は安心を得て、そしてやはり彼自身の健全な打算によって、痛みを嫌うことでそれからはただのガキくらいにはなれるかもしれない。
この正拳突きは礼儀なのだ。このクソガキは打算を持つほどに一個の生きる主体としての人間であると認め、そしてその意思を仮初の優しさで歪めないための礼儀なのだ。

話を戻すと、炎上の件についてのプロデューサーの謝罪に対して、客観的に明らかに謝罪を受けるに値する事務長は謝罪は不要であることを伝えている。

プロデューサーは、仕事を行った主体としての誇りを伴う自己の責任を主張しようとするが、それを遮って事務長は自分が運営するチームについて簡潔に語り始めた。

彼が語るのは、自らが事務方の責任者として運営してきたチームは、観客やファンの規模として決して恵まれていなかったことだ。そしてそれだけにそのチームのファンである彼らは、例えば「僕が支えなければならない」という具合に高度に「チームのファン」として客体化されていることを語っている。
そして彼は自らのチームのファンを「うちの若いの」と呼んでいる。そして彼は謝罪に及んだ。

ここで彼が行ったチームファンについての謝罪行為は、彼の運営者という主体としての意識を如実に反映している。
彼はサッカーチームの運営者である。
第6話のメイクスタッフが言っていた通りに、客観的に炎上の行為者となったのは「一部ファン同士」である。更に言えば、今回の炎上の原因を受け入れさせた新たなオーナー企業についても彼らは責任を押し付け客体に甘んじることが客観的には可能である。彼らは、サッカーチーム運営という自身の行為において責任を押し付ける明確な存在を持っている。
そんな状況で、事務長の彼はサッカーチームの運営者として行った自らの仕事とその結果に対し、自らの責任を、つまり自らの主体を主張している。
なぜなら彼らのサッカーチームが試合を行い利益を受けたことは確かであり、ファンを増やすための行為があったかは別として、炎上を起こすほどに入れ込むほどに存在証明を自身に依存したファンを作ったのは確かである。
しかし、彼はサッカーチームの一員にして、集団の長として運営する行為者なのだ。ここでは彼は求められているという点において客体における要請ですらある自己の誇りを言葉の上ではあるが実践的に証明している。
また会長(サッカーチームのであろうか)もまた自己の行いについての誇りを持っているらしい。

そして今日のボランティアについてお世話になったことに感謝を伝えて退出していくプロデューサーに、先ほどの謝罪にそうしたように、彼は「こちらこそ」と感謝を返す。
そして事務長は、ボランティアとはいえ謝礼がしたいとのことで、オーナー企業の「フードデリバリーさん」から受け取ったクーポン券をプロデューサーに横流しした。
この行為からは、事務長の自意識についての処世術が垣間見える。
オーナー企業はすごく細やかながらも、サッカーチームに対して支払う給料以上の報酬である優待券を渡している。
この行為は一見親切なものであるが、その実、一般的な礼儀の範囲を越えた贈与を受ける彼らが持つ職務についての主体意志を侵害している。彼らは主体存在である社会人として、様々な理由から自らの誇りのもとに仕事をしているのだと胸を張っているのだ。
その長に相応しい誇りを確認することを少しでも難しいものにするような贈り物をしてしまうことで、オーナー企業は彼の誇りに対して逆説的な無礼を働いていると言える。
しかし、彼自身はフーデリ企業にとっての職務の本分そのものでもある贈物を受け取ることで、彼らの面目を潰さぬよう礼節を弁えている。
その一方で、職務に当たる自己の主体意志が確認できる状態を可能な限り維持するために、自分はその優待券を使用するつもりはない。
そして折良くボランティアを買って出たいという人間がやって来た。さらに彼らは今回の炎上騒動において、自分ほどには職務上の直接的被害が出なかった者であり、さらに都合の良いことに、彼女らはお節介なオーナーと同様に、今回の仕事で彼らに良い何かをしようとしたいらしいのだ。
彼女らの内面は別として、客観的にはボランティアというお節介でありつつも、しかし彼自身にも需要を感じる行為に対して、彼が事務長たる主体を維持しつつ彼女らのボランティアをしたいという主体を尊重するためには、それに相応しい程度の慎ましいお礼があるべきだ。
そしてそのとき、この優待券ほどその由緒を含めて適したものもあるまい。
この事務長は、誰かのためになりたいと願ったフーデリ企業から、誰かのためを願ったことを反省した彼女らへとクーポン券を運んでおり、そこでは彼自身の誇りや巡り合わせへの喜びといった思いも人知れず運ばれている。

そして彼は別れ際になって、炎上の最も大きな原因と目され、彼自身にもやや無礼な行為に及んでしまっているフーデリ企業の諸言動についても「よくしたいって思ってるだけなの」だという考えを口にする。ここでは倫理についての説明が繰り返される。
そしてこれは第5話のフーデリ企業社長による櫻木真乃へのセンチメンタルな告白から確からしいことが予想される。

一方イルミネーションスターズの彼女らは忘れ物の傘を見つけた。
しかし試合があったこの日は雨が降るような日ではなかったらしい。彼女らは不思議に思ってそこにどのような人が座っていたのだろうかと考える。

そして彼女らは傘を忘れた誰かがどんな人物だったか様々に考え始めた。
……雨が降りそうだっのかもしれない、そんな天気ではなかった、ぜーったい濡れたくないと思ったのかも……ホームチームの座席にいる……――この前も来てくれただろうか。
――どんな人なのだろうか。隣の人もその隣の人も、誰一人として同じ人間はいなかった。ホームチームを応援したことは確かなように思えるだけの彼か彼女かはどんな風に生きて何を思って生きているのだろうか。
彼女らは思いを馳せた。
今の彼女らは、誰かに幻想を抱いたりしない。
どんな人か決めつけて安心したり、自分を責めたりもしない。
ただ考え続けている。
考えている彼女らにはっきりと分かることなんて何もなかったけど――何も分からない世界は相変わらず不安な事ばかりだけど――、それでも彼女たちは考えて、自分も誰かの思いを運ぶ人で、誰かの思いで運ばれる人で、そしてサッカーファンの彼らも、社会に生きる誰もが、「はこぶものたち」であることを理解できた。
「それじゃあ椅子を拭こう」と彼女らは休憩を終える。あの日持っていなかった自分たち自身の確かな思いが、あの日に座った誰かに、そしてこれから座る誰かに届きますようにと祈りを込めて。
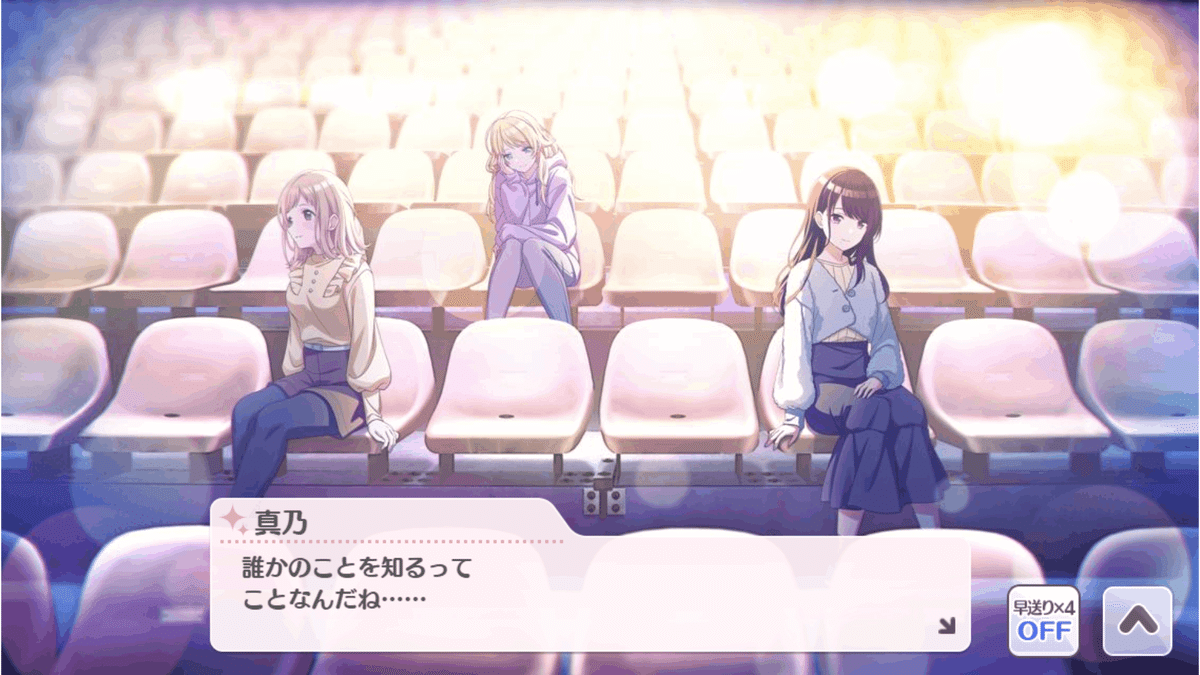
"美麗(パネ)"エイラスト"真剣感謝(マジアザッス)"。
シャニマスくんのイラストについては「"描(シバ)"いたのは……"神(オレ)"だぜ。」と言ってる姿を想像していた、高山が。"現実(リアル)"は「CYOCO」だからな?俺は失望したぞ、高山。責任を取って風野灯織のSSRが【WtW】と初期sSSRしか実装されていない疑惑がある僕のアカウントを修繕しろ。あと【LATE】緋田美琴を引かせない卑劣な限定ガシャによって鉱脈を完全に枯渇させたばかりか美琴さんと僕の思い出を半ば恒久的に引き裂いた人道上の罪を償え。
そうして彼女らは考えて、「ボランティア」を行為して、ようやく彼女らは自らの主体を確認し、自分の仕事を肯うことができた。
やがて帰途に就いた彼女らは道を行くフーデリ企業の配達員に気付く。そしてそんな彼に彼女らは「頑張ってー!」と応援する。
ここでは、現実世界に準じて描くことで暗示されていたフーデリ企業の一般の雇用形態――個人事業主への業務委託という主体尊重のような雇用形態を取りつつ、制服を着せ広告物として客体化している――という「おまじない」の象徴物であるピンクの帽子によって彼女らに応援される様子を描く。
ここでは、これら「おまじない」自体は他の善悪というものなどと同じく、それ自体が決して絶対的な純粋悪ではないことを暗示している。また、行為の実践によって考えもつかない幸運が発生し得ることも暗示されている。

前者においては語るまでもないことなので、後者の、色々な点においてアホ丸出しの楽観的希望論について語ろう。
私たちは生きることについて、自意識の強烈な矛盾を抱えざるを得ない。誰かのためになる仕事ですら、本当に誰かのためになるためには自分のためだと自分に確認し続けることが必要になる場合がままある。
しかし自分の主体を確認することは難しく、細々とした様々な努力が必要になる上に、このような過程を経た先にある行為や精神に伴う主体でさえも実存的には虚勢の域を出ない。
嘘偽りや詐術に依らずに自らの動機が自らのためだけのものであると言い切る高潔を維持し続けるのは容易いことではない。
そうすると僕たちは精神的な苦境に立つことになる。
完全に主観の与太話をすると、仏教というものは本来信仰ではなく思考に限局した実存哲学である。
他のいわゆる世界宗教が信者を客体化せんとする一方で、仏教は主客における実存についての理解によって主客の自意識を喪失することで、これら自意識の矛盾による軋轢を解消し、様々な苦しみをなきものにしようとする哲学の大系であると考えられる。
仏教が言うように、人間は自意識に矛盾が少ないほど苦しまずに済むのだ。
仏教ではこの矛盾を減じるために、時に究極的には人間の自然な欲求や矛盾を処理する機構である精神を発達させることを否定する。

続いて例え話をしよう。
桃色のお店において、「あなたはドMである」と言われたとする。
この行為はあなたをドMであると認識し、そして言葉にすることで客体化する行為である。
もし仮にあなたが誇りに満ちた一般理想成人男性であれば、この言葉に怒りを覚えるはずである。
なぜならこれは間違いなく侮辱であるからだ。あなたは社会で生き、友や上司、部下からの信頼篤く、家に帰れば愛する妻と子供たちがいる。彼の身の上は決して彼一人のものではなく、彼は主体としてあることを様々な状況に「強いられる」矛盾を抱えながら、それでも誇り高く生きている。
そんなあなたに投げられた「あなたはドMである」、つまり「あなたは客体に関する欲求の肥大した卑猥な存在である」という言葉は、自己の主体を確認し続けている高潔についての彼の試みを無に帰するような無礼な言葉だ。
一般理想成人男性の彼は、「要請された高潔」という矛盾に耐える人生の苦しみのもと、決して的外れではない彼女の侮辱に最もな怒りを覚える。
一方で、あなたが平均オタク男性であればどうだろうか?「あなたはドMだ」と言われたあなたは言うはずである。
「Exactly(そのとおりでございます)」と。
偏見ではあるが、長文に目を通そうなどと考える男性オタク存在は、幼少期の教育や躾よって十分以上に客体化されたにも関わらず、思春期に得られるべき女性からの客体化――特別な彼氏としての承認――には恵まれていない。
暗い部屋でtwitterを眺め、女の子と男女らしい話をしたのは二年前まで遡る。妻もいなければ彼女さえ当然のようにおらず、一人で行くと不審がられると夜の丘から都市の光を眺めることさえできはしない。時にtwitterを閉じてはすぐtwitterを開き、いいねを欲してはネタツイに走る。
そんな居場所のない僕らは主に客体化されたいという欲求が肥大しているのだ。
そんな存在であるあなたが「あなたはドM」である、つまり「あなたは客体に関する欲求の肥大した卑猥な存在である」という侮辱を受けた。この侮辱は当意即妙なのだ。客体化を欲した彼に与えられたのはこの上なく正しい侮辱というこの上なく正しい承認である。
さらに、平均オタク男性のあなたは選ばれることもなければ守るものも持たない孤独で不安なだけの男である。
――そんなあなたはこの侮辱にその通りだと言っあと、間髪入れずにこう叫ぶだろう。「この哀れなわたくしめにお慈悲を!」と。
そして飛ばされた鞭に嬌声が響く――。
もし彼に、自分が主体として生きる人間としての自覚があるのであれば怒るのかもしれないが、しかしその誇りすら承認されたいというセンチメンタルな感情と表裏一体なのだ。

さて、自意識の矛盾による軋轢が苦しみを生む様相は雰囲気で理解できたことだろう。
ここで改めて考えてみよう。
桃色のお店において、前者の一般理想成人男性と平均オタク男性のどちらがより幸福で、どちらがより苦しいだろうか?
問うまでもないことかもしれないが、桃色のお店においては、当然高潔な一般理想成人男性の方が苦しく、そして幸福でない。
一方で卑猥な平均オタク男性は苦しみがなく、そして幸福である。
俗に、そしてその中でも高潔に生きる人間と、人生を生きることを止めてされるがままの人間との比較においては、努力と幸福についての費用対効果の点において、「色々なことを諦めて投げ出してしまった方が良い」というような非常に悲しい状況が成立することが往々にしてあるのだ。
さて、自意識に矛盾を孕む人生には集積していく苦しみがつきものだ。
しかし、全てを諦めて俗世を離れ、山奥で安らかな死を待つのは違うと思うのなら、あるいは少しでも自分の存在を証明をしたいと感じたり、自分の存在を認めてほしいと思ったり、そうでなくても何かの役に立とうだとか、人間らしくあろうだとか言うのなら、有料苦行ガシャを回し続けることそのものである社会参画を行い、つまり、人生を生きる必要があるらしい。

そんな不都合に揉まれ続けるような人生をそれでも生きるに当たっては、楽観的であることが非常に重要である。
「何とかなるんじゃないか」、「何か良い感じになるだろう」などという根拠のないクソ適当な前向き精神構造を持つことこそ、努力の対価に苦しみを獲得する人生においては馬鹿みてぇに肝要なのだ。

真に重要な「ポジティブシンキング」は、「クソ疲れる上に報酬も安いし皆に白い目で見られれば、制服すらダサい」とかいうコスパ最悪の配達仕事の途中にあっても「めっちゃくちゃ可愛い女子高生のしかも三人組(実はアイドル)が応援してくれるかもしれないだろ!」というものである。
ゼロではないがほぼ絶無と言えそうな幸運の可能性に、気分良く賭けてしまえるのが重要な楽観なのだ。
実際には、この先に待ち受けるのが非常に長い不断の苦しみであることがほぼ確実であるため、この楽観はほとんど勇気だと言っていい。
そして、実際にはあり得ないようなことがあり得るのかどうかすら、本当に、本当にやってみなければ分からないのだ。
脱線した話を戻すと、ピンク帽子の配達員を見た彼女らは、ボランティアの謝礼にもらったささやかな贈物であるクーポンを使おうという話から、以前風野灯織が話していた「兄やん」の話に移る。
SNSに夢中になるような彼の態度から予想がつくことではあるが、配達中に交通事故を起こしていた。職務に当たっても客体としての意識が強く、主体としての単純な目標である交通ルールを守れなかったのだろう。そして彼はその怪我でしばらく配達ができなかったらしい。
復帰しても相変わらず恥知らずの「オン」という言葉を放つなどの言動は変わらないが、配達中は配達という自己の行為に集中することに決めたらしく、彼にもまた行為とその結果による反省が行われている。

孤独についての大きな不安を抱える八宮めぐるは、他者の存在を考える倫理というものがお気に召したらしい。
彼女は「兄やん」がどんな人なのだろうかと考えて、そのまま風野灯織に問いかけた。
「兄やん」に会ってみたいかと。これは場合によっては第1話のようにデリカシーに欠けた質問にもなり得る。

しかし風野灯織は少し考え込んで、そして否定した。
ここで彼女は、いつかそうしたように、彼女は青や茜色の空のもと駆けている「兄やん」のことを考えた。
そして「どこかで走って、頑張っている人がいるって、そう思うと、自分も頑張ろうって思えて……だから『オン!』だけでいい」と述懐する。

苦しい時期を過ごしていた時の彼女にとって、「兄やん」とは仕事のない自分の焦りや不安を慰めるために自己を投影する対象だった。
特にその不安においては仕事に恵まれず頑張る機会を持てなかったという状況が大きな実存を占めていた。
そのため、実際に仕事を受けてから働いている間に渡るまでの一部始終の情報は、かつての彼女にとって必要不可欠なものであったと言えるだろう。
彼女は自分の認知的不協和を解消してから、ここで初めて、自己投影のための幻想ではない「兄やん」という個人のことについて考えている。
そうして、いつか意識の上でそう思おうとした、「頑張る誰かの思いを感じることで自分も頑張れる自分でいられる」ことについて今は全人的に素直な納得ができた。
さらに実存は本質に優先することもここまで描写されてきている。「兄やん」の動機が承認を求める客体の中にあったとしても、行為に及ぶ主体でさえあることには間違いがないのだ。
だから誰かが頑張っているというただそれだけのことさえ分かったなら、もうそれだけでそれで良いのだ。
さらに、曖昧な後ろ暗い感情を自他から隠匿するためにかつての彼女は自分の認知を歪めざるをえなかったが、今の彼女は素直な自分の考えを述べることができている。
そして彼女は「『オン!』だけでいい」のだという爽やかな結論に至る。

そしてその裏ではプロデューサーがスゲェこと言ってる。
マ!?来るの!?!!??!?春!!?!???!?!!?

――風野灯織は独白する。
等身大で、行き当たりばったりで、自然な考え方で、まとまらない文章で、誰かに聞かせようとなんて思わないで呟いた。口を衝いて言葉が漏れる。




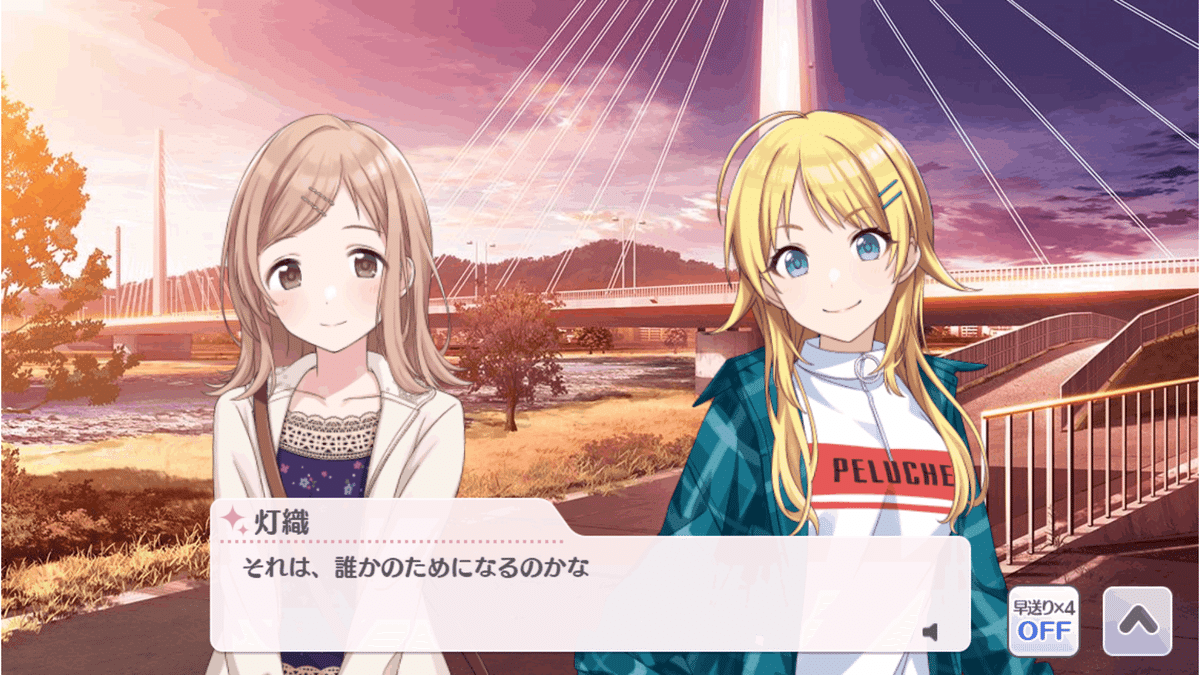
ぼくらが走るとき、きっとそこには実存的に確固たる理由がないのだろうと考えた。ぼくたちにできるのは、自分のためだと必死に強がるくらいで、それで精一杯だ。そのなかには、本当に自分のためだけに走ることができる人もいるのかもしれない。
そして、そんなぼくらの曖昧な気持ちには関係がない、何かをしたかどうかなんて次元で、この世界には色々な物が運ばれて、CMやアイドルの仕事っていう楽しくて幸せなことも、走る配達員の不安やスタジアムの炎上なんていう苦しくて辛いことも、差し引きがゼロになるのかも分からないくらいに複雑に、色んなことが起きている。
他の誰かがいることを考えられるようになった僕たちは、このまま何もしないで終わりを待つこともできるようになったのかもしれないけれど、それでも走って、生きてほしいと彼女は祈った。
彼女がそう言うように、自分のためだけの何かに始まっても、誰かの喜びに繋がって、そんな喜びも次の自分の力になるのなら……色んなことが純粋で簡単じゃないこの世界で、それでも生きていこうと思えたのなら、それは誰かのためになるのだろうかしら。
ここでプロデューサーの短い祈りが述懐される。
ひとりひとりが、複雑で強力な社会の客体化による不安の中にあってもなお、あるべき自分の主体を確認して、不安で苦しいこの人生を、それでも気高く生きる別々の人間として、大人になっていく彼女らを祈った。そして苦しむ彼女らが焦らぬように、焦りが何かを歪めてしまわぬようにと祈った。


そして風野灯織が口に出していた彼女だけの思案に対して、そして遠くどこかで祈るプロデューサーの祈りに対して、櫻木真乃とは八宮めぐるは、――かつて風野灯織の本質はどうあれ応援した彼女たちが――彼女たちにそうされたように、そしてそれをもってはこぶものたちであるのだと証明するように、風野灯織に「応援」をした。
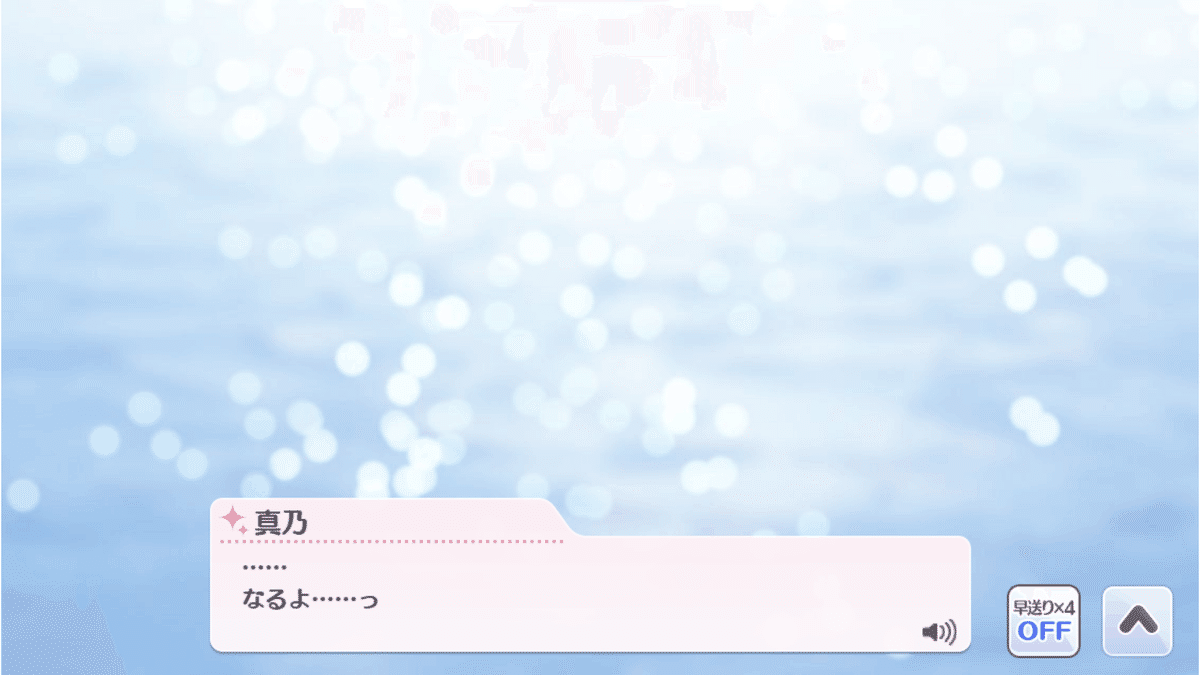
そうして自身にいつまでも不安の混じる思いに、彼女たちからの等身大の承認を得た彼女も、心の内で彼女自身の等身大の応援をする。
なおここではイルミネーションスターズにおける主体的な存在としての櫻木真乃と客体的な存在としての八宮めぐるという象徴的な両者からの応援であることからも物語としての性質も混在していると言える。

……それから、大きく話を逸れた自分たちを笑うように、そしてこれから生きる未来が、ご機嫌なものに違いないことを知っているかのように、風野灯織は今日のごちそうの話をした。
いつか、自分への意識を逸らすためだけに意識したごちそうが、今日の彼女は楽しみだ。

――そして彼女の心には、応援されて、応援する「はこぶものたち」としての彼女自身の意識が、彼女たちに支えられて、確かに息衝いていた。

感想
め い さ く
道徳的かつ哲学的な話だった。難しい話を難しいままに、複雑なものを複雑なままに肯う勇気についての話で、不安なことばかりの現代社会に生きる勇者たる人間についての話で、そして物語ですらある。
これは僕たちの話で、彼女たちの話で、ひいてはシャニマスくんからの話で、そして応援であった。
例えば、急に声をかけられるとびっくりするみたいに、それか、モテない陰キャの高校生が罰ゲームの告白を心から信じてしまうみたいに皆が過敏に反応してしまった。
シャニマスが去年炎上しがちだったのもあり、クラスタに属するほぼ全員が事件の当事者としての経験がある僕たちに炎上の話をするのは刺さりすぎていたかもしれない。
作品の感想のほとんどが炎上とその事態への所感に占められ、シャニマスくんの失礼スレスレのド直球エールや、頑張って作ったのはほぼ確実な内容自体に注目している人はあまり見られなかったのがやや面白いところだった。
スケジュールが分からないからそのロックな在り方については何とも言えないが、それでも、良かったぞ高山。
作品ではオープニングから中盤にかけて丁寧に物語を作っておきながら、終盤にかけて一気に物語というものそれ自体を否定する。
また、絶対的な善悪あるいは絶対的主客の不在というものを主題にすることをいいことに、作中では物語にとっていつも不都合な諸々の現実的矛盾への鬱憤を晴らすように書き殴っていた。
その分、明確な物語的モチーフや行間を埋める物語然とした分かりやすい主客の示唆が減っており、企業や人間の態度などについては現実の実存的様態に準じて考えることが必要になっている。そうして、作品を理解する上では、作品以外の一般的な洞察と照らして文脈を追うことが重要になる形式であった。
その形式の都合から、作品の内容には個々人の主観が入る余地が数多く存在することから解釈が必要になるところもそれなりにあった。
しかしながらそれについては大まかには記事にまとめた分で間違っていないだろう。
「難しい話になる」と話していた高山と、「きみの座らないたくさんの席を……」という予告から、当初は様々な規範に対して主体礼賛の傾向が強めの作品傾向を持つシャニマスくんにおける物語的妥当性と、最近になってtwitterを真剣に活用することへの迷いに決着を着けたように見えるシャニマスくんの運営態度との矛盾を避けるのが難しい、という意味での「難しい話」なのだろうかと推測していた。
しかし普通に理解するのが大変だということだとは思いもよらなかった。さらにもっと言うなら、バイアスのかかっている状態が普通である僕たちにとって、この作品が取り扱った主題は破壊的でもある。そういう人々にとっては内容が素直に受け容れられない場合もあることを指して、高山は「難しい」と言っていたと思われる。
ただし、「生きることは物語じゃない」らしいことから、丁寧に作れるとはいえシャニマスくんが物語にはあまり拘泥しないということについては、僕は理解あるプロデューサーくんであるべきだったのかもしれないなとも思った。
また、表情や仕草の作成など、spineだかを使った細かい仕事が様々に行われていて良かった。記事を作成するに当たってスクリーンショットを撮るために何度も再生することになり、見る回数が増えたことで気付くような演出や、彼女らの態度の変化の表現についての努力が垣間見えた。
また声優さんの演技が上手だなぁとも思った。硬くて上ずった声出せるのかなと興味を持ち、自室にて「風野灯織のVAR!」と三度ほど口に出す異常成人男性になってはみたが、僕の口からは羞恥心を多分に含む弱々しく低い声が漏れるだけだった。
演技もへったくれもなかった。声優さんすごいっす!
他にもauto再生機能やSEを使って作る物理的な間や、そこに敷き詰められた細かな仕草は文字や漫画のような媒体にはない特有の強みの一つなのだと思う。
記事を作成するときにこそ、お目当てのスクリーンショットを撮るまでの再生時間がブレることが腹立たしく思われたが、作品の出来に大きく寄与していると思う。
ここまで書いておいてなんだが、作品に最低限の敬意と面白みという動機から、敢えて作品自体を客観的判断基準のもとに良いとか悪いとか言ったりするのは控えるが、少なくとも読んだ僕はご機嫌な作品でした。
今回もお仕事お疲れさまです。ありがとうございました。
終わりの挨拶
内容があるような、ないような長い記事ではありますが、目を通してくださりありがとうございました。
最後に、シャニマスくん、ひいては『アイドルマスター シャイニーカラーズ』制作プロデューサーこと高山が、今後も引き続き頑張っていけるよう祈って本記事を終わりたいと思います。
風野灯織の追加分SSRが実装されていない僕のシャニマスアカウントの修繕と、とうとう全ての鉱脈を枯らしてみせた残酷な神様そのものの限定バレンタイン美琴さん、当時の貯蓄を破壊して全てを奪い尽くしながらついぞ姿を見せなかった梅雨の樋口円香、【ノー石・敗者フェイス】の屈辱を強いた正月冬優子などの限定SSRが滞りなく恒常になりますよう。
ありれるれん
