
【赤報隊に会った男】⑪ インタビューの結末
インタビューの開始からすでに2時間が過ぎていた。
鈴木邦男は本当に赤報隊に会ったのか――――。
この疑問に何としてでも答えを出してやろうと意気込んで臨んだインタビューだったが、それは簡単な仕事ではなかった。
これまでのやりとりを通じて、鈴木が過去に書いた赤報隊に関するエピソードの中に、数多くのフィクションが混入しているという心証は得られた。
しかし、その一方で、鈴木があくまで「実体験」だと主張するエピソードもあった。
朝日新聞阪神支局襲撃事件の後、差出人不明の手紙で呼び出され、指定された場所から2度3度と移動させられ末に謎の男が現れ、「中曽根康弘を全生庵で狙う」と予告されたという話。
また、同じく阪神支局襲撃事件の後、手元に送られてきた切符で関西の駅に赴くと、雑踏の中で謎の男に声をかけられ、後をついて行ってホテルの一室で夜を徹して話をしたという話。
鈴木は、この2つのエピソードに登場する謎の男は同一人物であり、こういう複雑な方法で何度か密会した、今でも彼が赤報隊だと思っている、と説明した。
しかしながら、この男と会った時期を尋ねると、彼は「忘れてしまった」と口を濁した。会った場所はどこか、関西の駅というのは何駅か、と尋ねても答えてくれない。
これでは話の信憑性を吟味することができないし、かといってフィクションだと切り捨てることもできない。
恐らく、鈴木はそういうことを計算したうえで、答えるべき質問と答えるべきではない質問の間に頭の中できっちり線を引いている。こちらが事実ともフィクションとも判断できないように。
彼はこれまでも、こうやって数多の記者たちを煙に巻いてきたのだろう。もしかすると、公安警察と長年渡り合ってきた活動家としての防衛本能なのかもしれない。

相手の目を見れば本当のことを話しているかどうかはわかる――――と言う人がいる。
しかし僕に言わせれば、これは自信過剰な人間の言葉だ。
確かに、世の中には「わかりやすい人」もいる。
しかし、ある程度以上の人生経験を積んだ思慮深い人間の腹の底というのは、そう簡単に見抜けるものではない。
これが、20年余りの記者人生で、僕が嫌というほど失敗を重ねながら学んだ教訓だ。
だから、物事の真偽を見極めようと思えば、とにかく多くのことを相手に語らせて、その内容を吟味していくしかないのである。
僕はしつこく問い続けた。
――――鈴木さんはかつて「赤報隊に会った」という記述の真意を朝日新聞の記者に問われて、「あれは文学的な表現」だと答えていましたね。でも、本当は鈴木さんの実体験だったということなんですか?
「そうなんですねえ」
――――週刊文春の取材にも「つい筆が滑っただけ」と答えていましたが?
「週刊文春にも言ってたっけ?」
――――この記事です。一水会元幹部のA氏としてコメントが紹介されています。
「A氏って俺?」
――――だと思いますよ。
このコメントは、週刊文春2003年新年特大号に掲載された特集記事〈朝日銃撃「赤報隊事件」 絞り込まれた9人の「容疑者」〉の中に出てくる。

改めて説明しておくと、この特集記事は、1998年に警察庁が作成した重要捜査対象者リストに全国の右翼活動家9人がリストアップされていたという内容で、そこにはこう記されている。
一水会元幹部のA氏は雑誌などで「私は赤報隊から《中曽根が許せない。ぜひやらせてください》と相談を受けたと発言。A氏は警察当局から116号事件への関与を最後まで疑われ、リストに残された。A氏はこう言う。
「つい筆が滑って書いただけです。僕の著書を読んで訪ねてきたり、取材と称して接触してきた人間のなかで、『こいつかもしれない』と思ったことがあるという程度ですね(略)」
――――この一水会元幹部のA氏というのは鈴木さんしかないですよね?
「うん。木村君もいるけども……」
ここで鈴木が名前を挙げた「木村君」とは、鈴木と長年活動をともにしてきた木村三浩・現一水会代表のことである。かつて「統一戦線義勇軍」という新右翼団体を率いていた経歴があり、鈴木と同じく警察当局から116号事件への関与が疑われた時期がある。
――――でも、木村さんは「私は赤報隊に会った」とは雑誌に書いてないですよ。
「そうですね、僕でしょうね」
――――この記事には「つい筆が滑って書いただけです」という鈴木さんのコメントが紹介されています。
「ははは……」
――――さらに「僕の著書を読んだり、取材と称して接触してきた人間の中で、こいつかも知れないと思ったことがあるという程度ですね」とコメントしています。
「ははは……逃げてますね」
――――これを読んで、そういうことなのかなと思っていたら、鈴木さんはその後、「公安警察の手口」や「別冊宝島」で再び「赤報隊に会ったんだ」と書いてくる。だから、やっぱりこれは鈴木さんの実体験なのかなと思ってしまう。実体験なんですか?
「なんでしょうね」
――――なんでしょうねって……。
「うーん、だから凄い人に会いましたよ」
どこまでもいっても、のらりくらりとかわされる。
こんなやりとりもあった。
――――彼はなぜ鈴木さんに接触してきたと思いますか。
「赤報隊についていろいろ書いているし、赤報隊の容疑者になっているから安心だったんじゃないですか。こいつに容疑が集中しているからって」
――――でも、鈴木さんに会うと公安に足がつく可能性があるわけでしょ?
「ねえ」
――――容疑者に会うというのはリスキーですよ。僕が赤報隊だったら絶対鈴木さんには接触しませんよ。
「そうねえ。そういう意味じゃ公安よりノウハウを持ってたんでしょう。唯一、公安を出し抜いたというのは彼らだけですね。僕にしたって僕の仲間にしたって全部公安に負け続けてますよ。彼らだけですね、公安に打ち勝っているというのは。そういう意味で僕はシンパシーを感じたのかもしれませんね」
――――鈴木さんが、赤報隊だと思うこの男のことをはっきり書かないのは、公安警察への恨みと、この男との信義ということなんですか?
「そうですねえ。僕を信じてくれた。だから、書くことによって彼らが捕まるというようなことはしたくない、というのはありましたね。一般市民としてはいけないことなのかもしれないけど……」
――――時効が成立した今も、その考えは変わらないんですか?
「いや、時効になったので何か書いてみたいとは思いますよ。特に言論の問題を含めて」
――――謎の男のことについては? もう逮捕される可能性もないんだから、公安警察への恨みという点を考えても、その男との信義という点を考えても、書くハードルは下がったと思うのですが?
「でも、知らないんですよ。家族構成も知らないし……」
――――鈴木さんがその男と会ったのは、関西のどこですか?
「どこでしょうねえ」
――――今、言ってもらうわけにはいかないですか?
「うーん……」
――――それは信義の問題で?
「うーん、まあ、それもありますねえ」
堂々めぐりの問答が延々と続いた。
このインタビューを通じて僕は繰り返し「すでに時効が成立した今なら詳細を明らかにしても問題ないのでは?」と水を向けたが、鈴木は頑なに態度を変えなかった。
どうしても赤報隊の正体を暴きたい、という僕の野心みたいなものを感じ取ったのだろう。鈴木は「僕からは彼らに会う接点が全くないし、似顔絵も描けないし。そういう意味でやっぱり協力できないと思います」とも話した。
そんなやりとりを繰り返す中で、ふと、鈴木が逆に問いかけてきた。
「時効になって何年経つの?」
――――時効成立が2003年だから、もう14年ですね。
「え、そんなになるの」
――――2003年の3月に116号事件関係の全ての犯行が時効になったんですよ。その時に鈴木さんは木村さんと一緒に記者会見していますよ。
「そうかあ……」
――――その翌年に鈴木さんは「公安警察の手口」を出版して、この中で再び赤報隊らしき男に会ったという話を蒸し返しているわけです。2004年の10月のことです。
せっかくだからと思って、僕は手元に用意していた「公安警察の手口」のコピーを読み上げた。
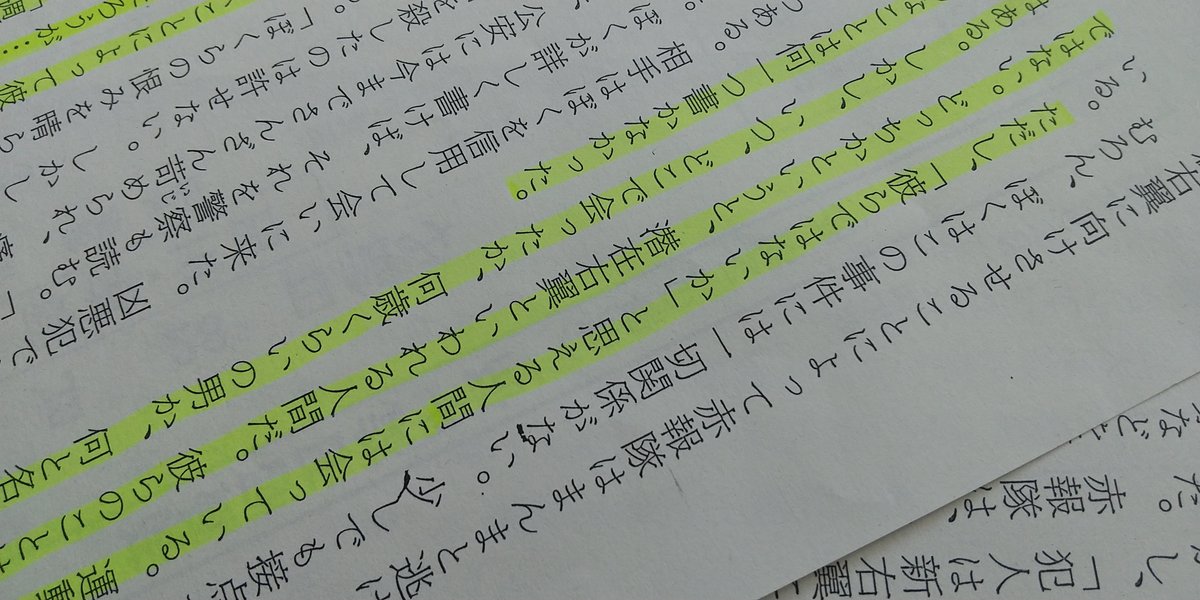
僕はこの事件には一切関係がない。少しでも接点があったら確実に捕まっている。ただし、「彼らではないか」と思える人間には会っている……
一度、ギリギリまで書いたことがある。「週刊SPA!」の連載にだ。そうしたら第一回目を書いた時点で、ガサ入れが来た。「赤報隊と会ったというから、メモや手紙があるはずだ」と。こいつらは馬鹿かと思った。せっかくギリギリまで書こうと思ったのに、「もうやめた。誰が教えてやるもんか」と思った……
知っていることを全て言う義務はないだろう。これまで僕は赤報隊のことについてはどこかでセーブして書いてきた。それは公安への〈恨み〉が動機になっている……
鈴木は目を細め、13年前に書いた自分の文章を懐かしそうに聞いていた。
朗読を終えた後、僕は淡い期待をこめて最後にもう一度だけ尋ねてみた。
「僕は公安じゃないんだから、もう少し教えていただくわけにはいきませんか?」
彼は穏やかな表情のまま答えた。
「それで全てじゃないですか」
結局、僕はこれ以上の言葉を鈴木邦男から引き出すことができなかった。(つづく)
つづきはこちら→【赤報隊に会った男】⑫(最終回)解けた謎と解けざる謎
※この連載では登場人物各位の敬称を省略させていただいています。このブログは「にほんブログ村」のランキングに参加しています。
