
社の前(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 20)
※縦書き画像でもお読み頂けます。
社の前
帰蝶が、信長の部屋にゆっくり入ってきた。
「今日は良いのか、無理をするなよ」
病にやつれ、弱っている帰蝶を労るように信長は声をかけた。
それなりに年は感じさせるものの、明智によく似た美貌に笑顔を浮かべて、帰蝶は長年の連れ合いである夫に寄り添った。
子は成さなかったものの、城の奥向きの要はいまだに帰蝶に頼る所が大きい。彼女は長年嫡子信忠の後見役としてあり、そして信忠はまだ正室を迎えていない。奥には必ず誰かしっかりと箍を絞める役割の女性が必要だ。
八月十五日、安土では相撲興業が行われていた。
奉行を津田信澄、堀秀政、蒲生氏郷ら、信長のお気に入りの若手が勤め、華々しく座を飾っている。また、婚礼を無事に終えた細川のやんちゃ坊主が妻を連れて挨拶に訪れることになっていた。帰蝶は明智の娘である珠子とおば・姪同士の縁戚だ。
「何とも愛らしい若夫婦でございました」
帰蝶は先に二人に会って様子を見てきた所だった。
「そうか、それは重畳」
「おたまに新婚の生活はどうですかとたずねると、こう、嬉しげに頬を染めて、にこにこしておりましたわ」
信長は一段と機嫌が良くなった。ではやはり、あのいたずら者の手前勝手な恋慕とわがままというわけでなかったのだ。
忠興が幼い時からあれほど切望する娘、求めに応じてやったはよいが、肝心の親である藤孝があの手この手を使っての再三の猛反対だ。あの時は多少むきになって押し切ったものの、何らかの理由があるのかもしれぬ、という一抹の不安は残っていた。
今や織田家中において押しも押されぬ重臣、明智の娘だ。石高や扱いの違いもある。もしや当の娘が望んでおらぬのを、藤孝は知っていたのではないか。
そんな心配を一掃する帰蝶の話だった。
忠興とその娘とは筒井筒の仲で、お互いに好きおうていたのであろう。小僧め、なかなか巧みにやっていたとみゆる。
信長は首をひねった。
(そうなるとなお、あの細川の親父の心底がよくわからぬ)
京育ちの連中はよくわからぬ遠慮の構えを取ることがある。気持ちと行動が裏腹なのだ。わしはそういうのは苦手だな。
◇
その肝心の「親父」は、忠興の嫁の輿入れの翌日、前日の酔いにも関わらずぱっちりと目を開いたとき、既に不安だった。
まだ一日目だ。婚礼は三日間続く。
藤孝は昨夜、夜を徹して酒を客にふるまい、精一杯のもてなしを行った。笑顔を見せて冗談を言い、ありとあらゆる知識を総動員して万芸を披露してみせ、場を盛り上げるよう気を使った。内心は心配でたまらない。初日からろくなことが起きない予感がする。
花嫁が現れたとき、その美しさに家中の気配が波のように動き、湧いた。
忠興が血相を変えて立ち上がりかける。その膝を藤孝は渾身の力をこめてぐぐぐっと抑えたが、おとなしく座らせるのにむやみに時間がかかった。怖い顔でにらみつけてやっとしぶしぶ力を抜いたが、まさかこの席で刀をぬき、ひと暴れするつもりだったのではなかろうな?
やりかねない。藤孝は身ぶるいをした。
抜けるように肌の白い花嫁の顔は冷静で、その美しい表情から何の感情も見て取れなかった。
藤孝は慌てて起きると身支度を整え、様子を伺いに裏屋敷へ向かった。
十兵衛から、いつも仲良くしていると聞いていたもののどうにも信じがたく、文の返事が来ないと忠興が悩んでいるらしいと聞いたときにはそれみたことかと思っているぐらいだった。
足早に侍女たちのもとへ行き、どうか?とひそかに尋ねると、年嵩の侍女頭は難しい顔をしている。
(だめか)
がっかりして肩を落とし、藤孝はすっかり気落ちした。
「やはりなあ。あやつがひどいのであろう。嫁御料は大丈夫なのか」
大得意の威張りくさった息子と、涙をこらえ、愛らしい顔を曇らせているよめごが目に見えるようだ。
二日目の朝に、新婚の二人は当主たる父母の前で挨拶をすることとなっている。さほど広くもない勝竜寺城の広間は、忠興の兄弟姉妹でぎゅう詰めになっていた。次男の頓五郎はともかく、キツい顔だちの伊也は最初から仲良くする気などありえないといった敵意を燃やしているし、七歳の三男は鼻たれをこすって落ち着きなく体を揺すっている。
あの壮麗な坂本城からこんな所にやってきて、しかもあんな奴と共に暮らさねばならぬとは、何の前世の因縁か?明智の家ではあやつもおとなしかっただろうし、お互いに幼い頃は、ようわからんかったろう。
藤孝はため息をついて思わず浮かんだ涙さえふき、気の毒な嫁をできる限り優しく扱おうと決心した。とはいえ、どうしても帰りたいと言われたならば、なんとしてなだめよう。この婚礼には上様もからんで居るし、尻ぬぐいは親の努めなれど限度がある。
そこへ声がかかって、忠興と珠子が共に、にこにこしながら部屋に入ってきた。うちとけて仲睦まじい様子だ。
へえっ?
藤孝はあてがはずれたような奇妙な心地がして、ぽかんとしながら息子夫婦の言上を受けた。
顔を上げた若い花嫁をごく間近に見て、ちょっとやそっとのことでは動じないつもりでいる藤孝も少しぼうっとした。
まばゆいほどの嫁ごだな。上様の寵愛といい、忠興はちょっと禍福の福が過ぎるようだ。
若い珠子が落ち着いているので、並んだ息子も別人のように立派に見えた。堂々と胸を張り、目は輝いている。
藤孝は、素直に喜んでいいのかやはり疑ったほうがいいのか、あれこれ迷った。うまくいかぬのを望んでいたわけではないが、どうもわしはこれまでの経験から、最悪を想定するのが癖になっておるようだ。
そこで思い出した。
この嫡男を、動乱の京のただ中に幼くして置いていかざるを得なかったとき、もう命はないものとすっかりあきらめていた。顔を見るたびに、背後にあの記憶がちらつく。後ろめたくもあり、やっと助かった命を失う怖さもあり、必要以上に情を移すまいと距離を取ってしまっていたようだ。
肝心の婚礼そっちのけですっかり思い出にふけっている藤孝を、妻の麝香が横からひじでどん!と突いた。思い切りみぞおちにはまり、藤孝はしばらく息が止まってしまった。
◇
当主への挨拶の次は一族への顔合わせだった。それから家臣たちの挨拶、祝いを述べに来た客たちの応対が待っている。気の強い妹の伊也が、頓五郎の背後から目を丸くして義姉を見つめていた。
忠興は得意満面でちらりと横を見た。そこには珠子が何一つ曇りない笑顔で寄り添っている。妻がただ美しいのみならず、堂々としているのが何よりも誇らしく得意で、忠興は幸福で体がいっぱいになった。
しかしデレデレした顔はいやだ。だらしない態度は見せたくない。そんなのは珠子に、わが妻にふさわしくない!
かといっていつものようにそっくり返って我が威を見せびらかすのも、子供っぽく思われた。というわけで忠興は、家中の全員がびっくりするほど殊勝な態度で頭を下げ、朗々とした声で立派に挨拶を述べた。
米田是政の父、宗堅が涙をふき、なんとご立派な!と声を上げたのを皮切りに、皆が口々に祝いの言葉を述べる。これは安泰じゃ。若殿もこれで落ち着かれた、などと囁き交わすざわめきの中には、心からの安堵と喜びが混じっていた。
◇
藤孝は挨拶と食事を終えると、小走りに走って行って、先ほど難しい顔で首を振っていた侍女を捕まえた。
「別にどうということはなかったではないか?」
侍女が語る昨夜の様子はこうだった。
部屋の外に控えた見守り役の侍女たちは、二人が床入りの部屋に入ってから、ずっと声をひそめて、何ごとか話している声を聞いた。ひそひそ声はずっととめどなく続いた。
それから一向に何か起きそうな気配もない。何をそんなに密談しているのやら、揺らめく灯火の光をたまに遮って蠢く影と、くっくっとたまに響く笑いに幻惑された侍女たちは、物の怪が若夫婦と成り替わっているのではないかと危ぶみはじめた。
数度目の忍び笑いを聞いたとき、厳格な老女のひとりが大きな咳払いをした。
すると、まさか新婚の床でそんなことが起きるなどと誰一人思ってもみなかったのだが、部屋の中から襖を蹴立てる勢いで血相を変えた忠興が飛び出してきて怒鳴り散らし、近習も侍女もみな、全員が部屋の近くから逃げ散ってしまったのだった。
「それから恐ろしゅうて誰一人局(部屋)近くには近づけませぬ」
やはりやらかしていたのではないか。
藤孝はゲッソリとして、肩を落とし、大きなため息をついた。
◇
勝竜寺に入って最初に新郎とその親が待つ部屋に足を踏み入れたとき、珠子の鋭い目は真っ先にこれから生涯の伴侶となるべき相手を探した。
眼と眼を見かわしただけで真っ赤になったのは、顔立ちの整ったすらりとした若者で、珠子の若い胸は喜びでいっぱいになった。
そこで姉や乳母がきつく言い聞かせていた嗜みなど忘れて、さっそく好奇心いっぱいに目を開き、まじろぎもせずにしげしげと相手の顔を伺ったので、忠興は赤い顔が今度は白くなり、完全に固まってしまった。
細くてきつい眉だ。前髪の下で暗くなるより、こうして剥き出しに晴れていた方がよい。同年代の少年たちに比べればどちらかといえば小柄だったが、鍛えられたからだは痩身で引き締まっており、顔立ちは上品で、育ちのよさも伺わせた。
あの小鬼がこんなにも育ったのか。
近くに座って顔を合わせてみれば、相手が激情のあまり、泣き出しそうなほど不安な顔をしているのをみて、かえって自分の不安が取り払われた。抱きしめて慰めてやりたい衝動にかられ、珠子はおそらくこの城の誰一人思わないであろう考え──彼はかわいいと考えた。
花嫁の視線を感じた忠興は、ぐっとこらえて懸命に正気を保っていた。
何と戦っているのか自分でもわからなかったが、生来の負けん気が、この花嫁の存在に打ちのめされ、屈服するのを拒んでいた。
そんな二人を鋭い目で観察していたのは、忠興の母、麝香だった。父親に負けないほどこの婚礼について心配している。
麝香は母親だけに、この息子が親の愛情不足に不満を抱いていることも、神経質であることも、不安が強く落ち着かないたちであることも充分にわかっていた。これまで麝香はずっと、雷を落として息子の暴走を止める以外は、見守るだけで黙っていた。結婚すれば、この暴発しがちな息子のすべてを正面から受け止め、支えるのはこの嫁となるのだ。武家の身代を支えるのに、容貌の良しあしなど関係なかったので、麝香は気にも留めなかった。
◇
盃を交わし、妻となった珠子と二人きりになると、忠興の頭の中から、何十回、何百回と直前までおさらいをしていたしきたりや述べるべき文言、作法などすべて消えてしまった。
珠子の瞳はきらきら輝いている。
どちらともなく寄り添い、肩を寄せ合ってくっついた。
すると二人は、仲良しの少年と少女に戻っていた。まだその頃を忘れてしまうほど大人になりきっていない。
外から咳払いが聞こえた。珠子はそっと忠興の膝に触れて(忠興は卒倒しそうになった)くちびるに指をさして襖を見る。そこにはある程度遠慮はしながらも、老女たちが控えて聞き耳を立てているはずだ。
忠興は若干、腹を立てた。
やっと会えて、やっと二人になれたものを、この世の中のどんな誰にも邪魔されたくない。まして聞き耳を立てられるなどと、実に不愉快だ。
気を取り直して横を見れば、すぐ傍に珠子がいる。つんとすましていると冷たくさえ感じるあの顔が、いたずらっぽい笑顔でいっぱいでいる。全身が熱く震えた。幸せがしみとおる。
珠子、珠子……。
忠興は目を閉じて、まずは唇を吸おうと顔を突き出した──。
「そなた、右府さまに頼んだの?」
予想外の質問が珠子の口から飛び出して、そんなことを聞かれるとは思ってもみなかった忠興は、あっけにとられてぽかんとした。
「な、な……何?」
「わたしと結婚するように頼んだのか?」
無理を言ってねじ込んだのがばれたのか?
それを確認してどうしようというのか?
応とも否とも答えることができず、この真っ直ぐな瞳の前で嘘をつくこともできない。
ぐるぐるめまいがして、天井が回りはじめ、忠興は一声、いやだ!と彼にしては元気のない声で怒鳴って、新床の上につっ伏してしまった。
いいところを見せようと気負っていた花婿として、あまり威厳のあるスタートとは言えなかったが、幼なじみの大好きな少女の声の前で、彼は急激に子供に戻っていた。
珠子は膝でにじりよると、もっと近くに寄り添って忠興の肩に手をかけて顔を覗き込んだ。
「何がいやか?」
「そ、そ……そなたに、嫌われるのがいやだ!」
最初は鈴を振る音が聞こえたと思った。
珠子が笑っている。笑い声が降り注ぎ、頭の上できらめいて散った。いやな気分ではなかった。声高くならないように押さえてはいるが、明るくて影の欠片もない、気持ちのよい笑い声だった。
多少元気になって忠興が居住まいを正して珠子の顔色を窺うと、満面の笑顔で珠子は手を差し伸べた。
「細川さま……義父上さまが何度も断ったと聞いたの。なのに、どうしてもわたしと結婚したかったのか?」
乗り出してきた美しい顔が目の前のすぐ近くにあるのを感じた。
「おれはそなたを誰にも渡しとうない。どうしても、どうしてもだ!手段など選ばぬ。おれは鬼だ!」
強気で威張ったことを言いながらも、内心ひどく心配な忠興が様子をうかがうと、珠子は考え深そうな顔でいた。弟たちに言って聞かせるように、少し大人ぶった口調で言う。
「殿方は娶るおなごが自分のことを好きかどうかなんて気にしないものなのよ。でもそなたは、わたしの気持ちも考えてくれる」
珠子は手を差し伸べた。
「私はそなたが好きです。何で嫌うものか。そなたでよかった。そなたがよい。おたまは幸せ!」
珠子の言葉は、忠興に劇的な効果をもたらした。
情けない姿を晒しても、許され、受け入れられたと感じて、全ての緊張が解けた。きつい顔立ちがゆるみ、眉がひらいて顔が輝き、彼自身の本来の姿が覗いた。
笑い声とさざめき、あやかしたちがどっと囃し、歌い、口々に祝う。鬼と蛇の婚礼だ。
何かの鍵がはまって開く音がした。
秘密は正しく開かれて、二人で神秘の社の前に立っていた。
瑞兆はわが手にある。二度と手放すまい。
そして生涯をかけて誓うのだ。
何があっても、わが心は常にひとり。そなた一人だと。
──その心を忘れなければ、家はいつ何時までも富み栄えるでしょう。
どこから響いてきたのか分からない。彼女の口から漏れたのだとも思えなかった。心の中から生まれてきたのかもしれない。
また咳払いの声が聞こえた。
◇
「右近!」
「お祝いに参ることができず、心苦しゅう思うておりました」
相撲興行のかたわら、忠興は謁見のために珠子を伴い、控えている間に次々に安土の小姓仲間や知己の者たちが祝いに訪れていた。
高山右近は丁寧に祝いの言葉を述べた。
「ご挨拶できて何よりでござる」
「なあ、なあ、すごい傷であろう」
他の朋輩が祝いの言葉を述べるたび、珠子をじろじろと好奇の目で見ると、いちいち血相を変えていた忠興だが、右近に対しては何の疑いも持っていない。
あまりにも有頂天だった忠興は、右近がひどく沈んだ、物思わしげな苦しそうな顔をしているのに気づかなかった。
「右近は自慢をしないのだ。何でも誇るようなやつは真の勇者ではない!礼儀正しく、静かで自然体で……」
「そんなことはありませぬ。常に迷いのただ中なのです」
珠子はその話の合間に、鋭い目で首から下がった南蛮数珠と十字架を見た。デウス如来と呼ばれる、西国の信仰を持っている者たちがいると聞いているが、それに違いない。
──南蛮教か。
少しだけ頭をあげて多少そっけない顔をした。
外部からやってきた宗教に対して疑いを持つ、信仰的には非常に保守的な父の影響を多分に珠子も受けていた。古い神々と仏を信奉し、重んずる。
「古新どのが参られたようです」
「何!?」
忠興は赤くなり、立ち上がった。
「だめだだめだ!」
「だめとはこれ如何に。他の皆さまがご挨拶なされているのに」
「あいつはな!」
声を低めて言った。
「よめごとするのがどうとかうらやましいとか、ろくな話をせぬ!珠子を見せたくない」
もう古新がそこまで来ていて、こそこそ話をもれ聞いてしまった。部屋の外から大声で言う。
「なんだお前はケチめ」
「そういうことじゃない!」
「古新どのとは池田恒興さまのご次男さま。殿はたくさんの方とお知り合いなのですね」
勝竜寺城にいるよりも元気そうで、生き生きしているように思える。安土城の中で珠子が見たのは、思いもよらない忠興の社交的な姿だった。
◇
「上様のお成り!」
小姓の浪々とした声が響き、みな頭を下げる。
錚々たる顔ぶれの中には舅となった明智の白い顔もあった。
待ちきれない信長は、細川の若夫婦に真っ先に声をかけた。
細川ずれに嫁ぐなど不満だったのではないかなどというどんな噂も吹き飛ばす、曇りのない輝くような少女の笑顔を見て、信長の機嫌はさらに上々になった。
嗜好による身びいきはあったが、信長は少年たちを近くに置いて愛し育てるのと同じくらい、幸福な夫婦を見るのが好きだった。我が事のように嬉しいと思う。
夫婦和合は美しいものだ。釣り合いのとれた連れ合いと添わせてやりたい。ハゲネズミ(秀吉)の奴は、通いづめに通うて口説き落としたという。見目麗しい者同士ならばなおよい。
悦に入ってお気に入りの少年の紅潮した顔を眺めた。
「祝言を無事終えたのだな。上々の首尾。両人ともたいそう喜んでいると聞いて満足である。沢山の子を成して織田家のために励めよ」
「無論でございまする!」
「よいか与一郎。わしが下しおいた宝をゆめゆめ、手放すでないぞ」
からかうような声に、どうだ、お前の望み通りになったぞという、信長の若干の含みがあった。忠興は敏感に感じ、畳に頭を擦り付けんばかりに誓った。
「必ず、必ず!このご恩は忘れがたく、上様に終生の御恩返しと奉公を誓いまする!命をかけて!」
満面に嬉しさの漂うその顔から、ぐるりと二人を見渡し、信長は笑顔を浮かべて思わず感嘆の声をあげた。
「これはまた何とのう、まるで男雛と女雛が並びたるごとしではないか!」
立派ないでたちのきりっとした顔の若武者と、落ち着いた白い肌の美しい少女を、信長はほれぼれと眺めた。この二人の姿が、これから作って行きたい国、信長が理想とする世界が体現している気がした。
信長は少しだけ長く、珠子に目を留めた。
噂であった明智が娘がこれか。
すっきりした卵形の顔立ちに薄い桜色の唇まで、すべてに文句のつけようがない。華奢な体つきだが弱さはいっさい感じない。何よりも静かで落ち着いた挙動に目を奪い心を飲み込むような匂い立つ色気がある。
眉、鼻梁、切れ長ながら黒目の大きな真っ黒のひとみに吸い込まれる。我が妹も絶世の美女と呼ばれ、また安土城の奧向きには、きらびやかな美人が揃っているが、こんな整い方は見たことがない。誰もがそうであるように、信長も動きが止まった。吸い寄せられて凝視する。
深い森の中には泉が潜む。
信長は淵のほとりにいた。見下ろして見極めようとしていた。
澄んでいるのに底が見通せぬ。あまりにも深く、昏いため、光さえ吸い込まれて戻って来れなくなるのだ。目を凝らせば凝らすほど、引っ張られるような感覚をおぼえ、思わず前にのめる。
危のうございます、と声が聞こえた。近習の蘭丸の声のようでもあり、眼前の忠興のようでもあり、明智の声と思えた。
耐えて意識を引き戻したのは、信長の恐るべき意志の強さによるもので、気が付いてから再度珠子に目をあてた。
与一郎は平気なのか?
若いからか?気づいてはいないのか。こやつもどこか特別なのか。
あれは魔だ。人とはとても思われぬ。
だが忠興に目を移すと、その魔性がふっと揺らいで薄れて消えるのを感じた。こちらはひたすら嬉しそうで、元気百倍、勢い千倍といった顔からは、この娘を嫁にすることができ天にも昇る心地であるという以上の違和感は伝わって来ない。
この魔性も与一郎の前では薄れるのか。これは最早相性なのかもしれぬ。
この娘がおなごとなり、子を産んでどんな風に変わっていくのだろうと信長はふと考えた。
第二十話 終わり
次回のお話 第二十一話「新婚生活」
画像(ルビつき・縦書き)
画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。




















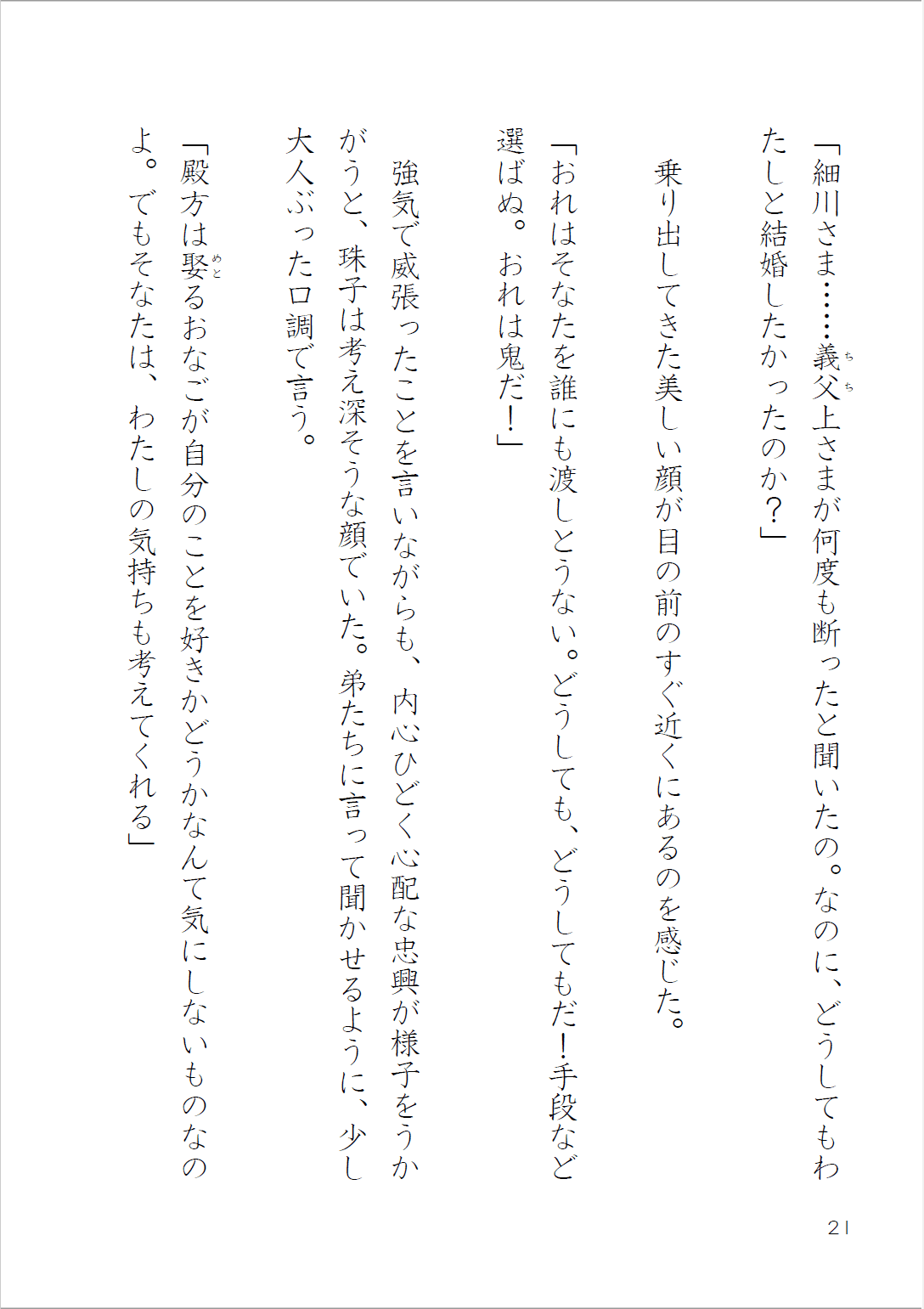




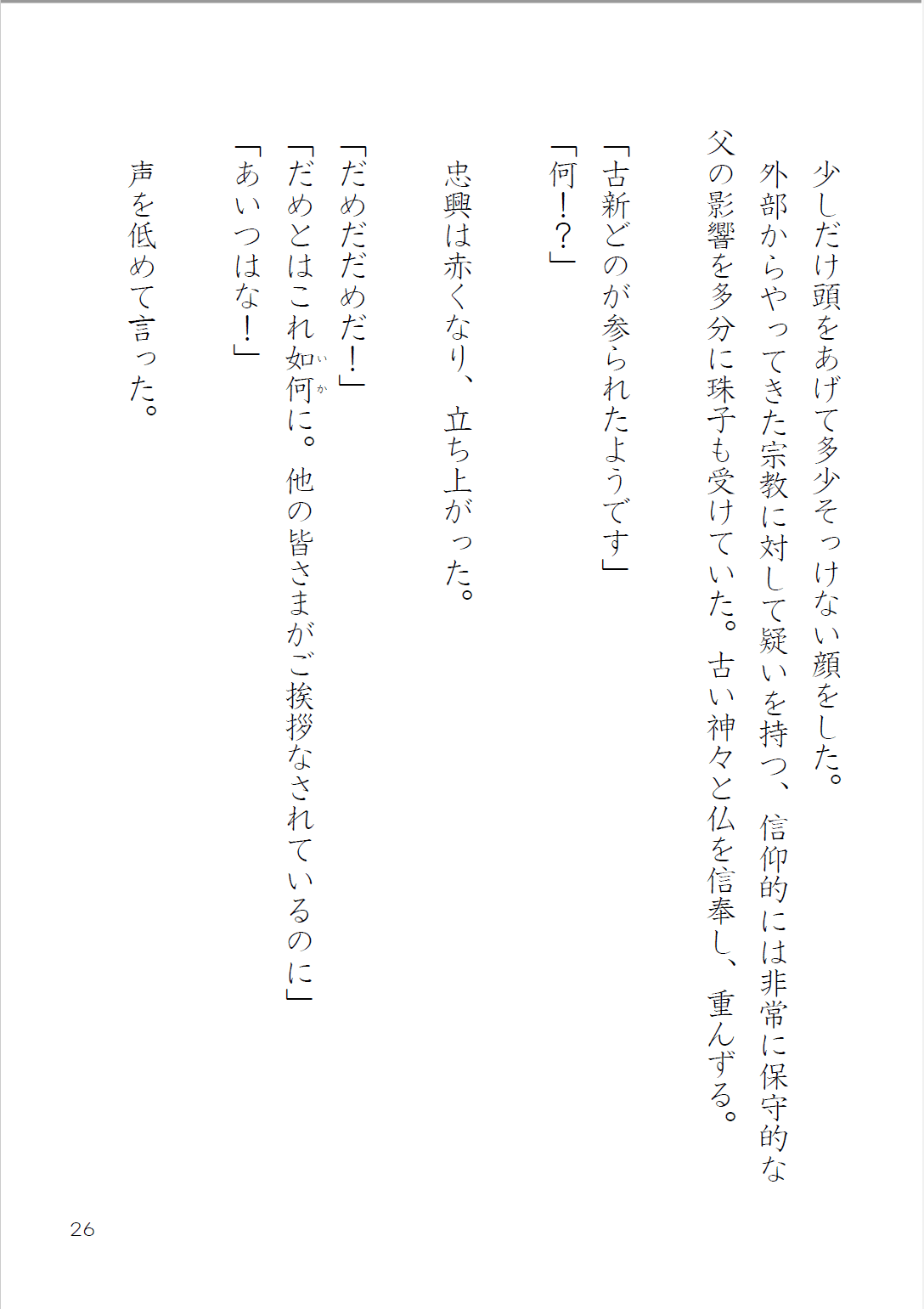








画像。本型。見開き版。


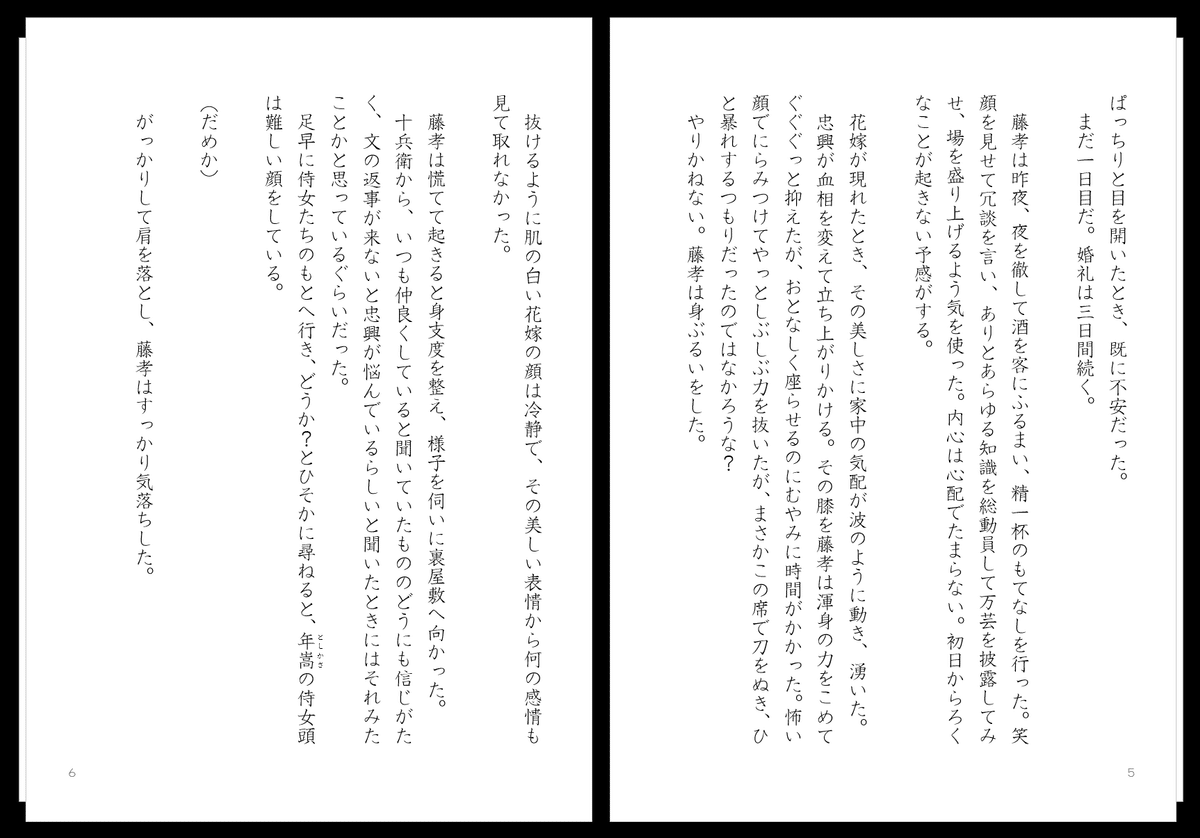






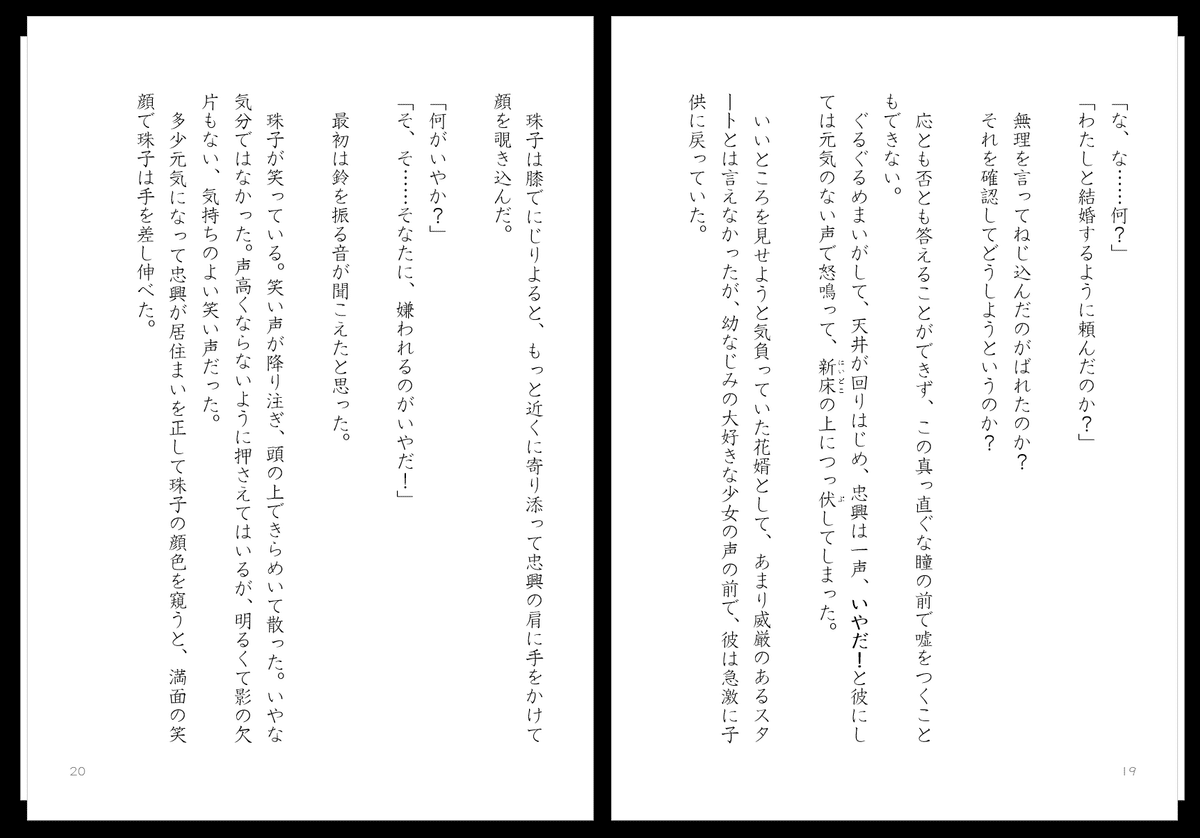







次回のお話 第二十一話「新婚生活」
いいなと思ったら応援しよう!

