
忠興生い立ち、または喧嘩上等・石合戦(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 4)
※「ルビつき・縦書き画像」をお読み頂けます。
忠興生い立ち、または喧嘩上等・石合戦
熊千代は京都一条の館で、細川藤孝の長男として生まれた。
のちに細川忠興となるこの少年の家系は、代々将軍の近習を勤める名家であったが、当時は貧苦と戦乱の中に喘いでいる。
将軍家の威光は風前のともしびであり、足利義輝は三好長慶と争いながら近江各地を転々としていた。やっと京に戻ったのもつかの間、長慶の死後すぐに永禄の変が起きて、義輝は戦死する。足利将軍家の命運は風前の灯となった。
幼い頃からずっと将軍義輝の傍に奉公衆として仕えていた細川藤孝は、兄の三淵藤英と共に、義輝の弟を将軍に立てようと必死に奔走する。
細川熊千代と、明智珠子が生まれたのは、そんな時分のことだった。
熊千代がまだ二歳(数え三歳)の年に、父の藤孝は新将軍擁立のため、六角氏を頼ろうとして兄と近江へ赴き、数少ない家人もすべて同行した。
母ともはぐれ、熊千代はひとりぼっちになった。
三好一党を避け、乳母は熊千代を抱いて、京都の外れに裏屋を借りて隠れ住んだ。中村新助という昔ながらの家人の妻で、夫本人はやはり藤孝と共に京を離れている。娘が三人おり、末娘がひとり共にいたというが、熊千代はほとんど覚えていない。
藤孝は六角氏の次に越前の朝倉氏を頼り、それから明智光秀と共に美濃の織田信長を頼り、ついに覚慶を足利義昭として担ぎ出すまでの丸二年間、熊千代は騒乱の最中の荒廃する京に取り残されていた。
隠れ住んでいる間、彼の名前は『宗八』であり、ただの町人の子供だった。
のちの熊千代が熊千代である証といえば、乳母に藤孝が与えた一振の守脇差だけだった。
◇
父母の顔を再び見た時の熊千代は四歳、母は生まれたばかりの弟を抱いていた。
「よう無事であった、熊千代」
そんな風に呼びかけられても不振が湧くばかりだ。無理もない。
これまでは「これ、宗八」「こっちに来なされ、宗八」と呼ばれていたのだ。
熊千代はこの見知らぬ父という人、母という人、弟という赤子にひたすら怪訝な顔をするだけだったと、そう乳母が語る。
そんなわけで、熊千代は父母への思いが幼少期から薄い。
荒廃した町屋の中で野放図に育ち、礼儀作法だの学問だの教養だのと、顔を見るなりいきなり押し付けようとする「親」になじめないままにいた熊千代も、そのうち六歳になった。
その年に、ちょっとした騒動が起きた。
京都では信長による、足利将軍の城、二条城の築城が始まっていた。
本圀寺で義昭が三好一党に襲撃を受けた事件を受けてのことだった。
◇
二条城の普請の現場で、奉公衆の足軽同士が口論をはじめたのだ。
始まりは上野清信の足軽と藤孝の甥である荒川輝宗の歩卒だったという。
そのうち、誰からともなく石を投げ合いはじめた。ぱらぱらと、最初は小石の雨が降るような音が周囲に落ちてきて、四方八方から従類眷属がかけつけ大乱闘に発展した。
普請を見物に来ていた熊千代の顔は、争う声を聞いてぱっと輝いた。
戦争だ!喧嘩だ騒ぎだ!
あっという間に乳母の手を振り払って駆け出した。
「熊千代さま!熊千代さま!」
乳母の必死の声が聞こえるが、危ない、お女中は下がれという声とともに遠くなった。
罵り合う連中の少し外側から、加勢に石を投げる者たちの中に紛れ込む。
真似をして自分も足元の石を拾い、渾身の力で思いっきり投げつけると、一人の額に命中し、相手がのけぞって後ろに倒れた。
「ようやるな、坊主!」
どっと笑う声に勢いを得て、また投げた。誰かが熊千代を狙ったのか、耳元近くを石が呻りをあげて過ぎていき、 大人はこんなにも力強く投げられるものなのかと驚いた。熊千代は降り注ぐ石礫から決して目を離さず、おそるべき動体視力でよけて進んだ。
数名、同じぐらいの年の泥まみれの小僧どもがいる。取っ組み合う侍、足軽、人足、下人どもの中に駆け入り、走り回った。
「餓鬼が何をしている!」
という声もするが、大きくて鈍い連中に踏まれるようなそんなばかだと思うのか。熊千代はせせら笑った。元来、小柄で身軽だ。すばしっこく手当たりしだいに走り回るうち、さまざまなものを見た。高台にある家の窓に鈴なりになって見物している連中、逃げ惑う食事係の下働きの女たち、さらに、どさくさに紛れて倉から様々な物を掠め取っていく奴もいる
賑やかに騒ぎまわっていた所、熊千代はいきなり腰を掴まれて、荷物のように持ち上げられてしまった
「離せ!離せ!」
相手は聞こえていないかのように、ゆっくりとした動作で歩き出す。熊千代は顔をひねって見て叫んだ
「万助か!」
有吉万助という、熊千代のお付きをしている家人の少年だ。
無口で鈍重なため、ものの役にも立たぬ奴と言われ、扱いにくい熊千代の相手をさせられている。
のんびりとした動作で何も言わずに熊千代を抱え、この大騒動の中を悠々と歩いている。これでもまだ十一歳なのだ。体が大きく、熊千代の盾になりつついくつか降ってきた石を手で払い退けて小動もしない姿に、熊千代は感心して暴れるのをやめた。
もともと熊千代は選んで小高い場所を走っていた。石を下へ投げ付けるのは楽だが、下から投げ上げるのは力がいるからだ。万助はその小高い丘をさらに上へ上がり、熊千代をすとんと降ろすと腰を下ろして争乱の方を見下ろした。
「大将は大勢の動きを見ろということか?」
熊千代が聞いても、万助はじっと黙って座っているだけだ。
二人はその場に座り込んで、右往左往の大騒ぎを観察した。まるで屏風絵のようだ。人の動きがよく見える。こんなわけのわからぬ暴動にも、そこかしこに大将株の者がおり、先導者がいる。戦いの流れが見える、よく見える!
熊千代は声を立てて笑った。
頬は自分のものか他人のものかもわからない血と泥に汚れている。
◇
熊千代は父に大目玉のすえ、家に入るのを禁じられ、寺に入れられてしまった。
寺の坊主に混じって修行をし、少しは反省しろというわけだ。この頃の寺は、初等教育から大学院まで成る、寄宿舎つき学校のような役割を兼ねていた。
寺に放り込まれるまで、熊千代があまりにも暴れたので、若は少しおかしいとか、たわけかもしれぬと囁く者たちさえいた。
「乳母があの戦乱の中に失うて、どこぞで拾うて来たのでは?」
「ばかいえ、拾うならもっとおとなしいのにするわ」
松井が血相を変えてひどく叱り付けているが、藤孝もあまりにごもっともと思うので怒る気にもなれない。
父母と一緒になってから一年もたたずに寺に入れられた熊千代は、また親と離れ離れになることとなった。
「無用な争いに自らを投じて、いらぬ恨みを買い、また命を損じたらどうする」
ふて腐れた熊千代を、寺の和尚は窘めた。
まだ若い和尚だ。若くから仏門に入った藤孝の弟で、熊千代の伯父にあたる。
熊千代はこの玉甫紹琮和尚のことは好きだった。上から押さえつけるようなことをせず、ただじっとそばにいてくれる。
熊千代は母と離れたのも、たいしてつらいとは思っていなかった。
母はいつも、背中を向けて、その手は赤子で塞がっている。
頓五郎が離れたかと思えば伊也が膝にまとわりつき、怒られる以外に熊千代と接するすきなどどこにもない。
おれをまともに見てくれる人など誰もいない、と熊千代は考える。
おれはおじと有吉がいればそれでよい。
自らも若くして父母と離れたこの和尚は、荒れている熊千代の気持ちがよくわかっていた。
「じゃあおれは坊主になるな」
「馬鹿なことを」
ピシャリと言下に否定される。
そこだけは叔父は頑なに譲らなかった。
もう二度と家に帰りたくない。
「お前は細川家の嫡子。わけが違う」
「何が嫡子だ!ほったらかしにしてどこぞに行きくさったくせに!都合が悪けりゃまた捨てるのだろ、こうやって!」
思いっ切り叫んだ。
「叔父上もおれがいやか!めんどうか!」
まだ織田家の小姓などという晴れがましい立場も知らず、この戦乱の世についても何もわからない、幼い熊千代は、背中に玉甫和尚の声を聞きながら走って逃げた。
町屋の捨て子育ちだ、邪魔だ、こんな餓鬼ならいらなかったと何度も言われて傷つき、また一方では嫡子だ、それらしく振る舞え、責任を持てと言われても納得がいかない。
こらえようとしても次から次に鼻水が流れ出てくる。熊千代は腹を立てている。この世のすべてに腹を立てて、嫌い、呪っていた
「何という情けない顔じゃ」
鋭い声が聞こえる。女の声だ、聞き覚えがある。熊千代が振り向くと、そこには、小女一人を連れた母が立っていた。
母上!
慌てて顔をこする熊千代の側にかがんで、麝香は熊千代の顔をしっかり捕まえ、懐から出した懐紙でこすった。それがあまりにもざらざらとして痛かったので、思わず顔をしかめてしまった
「母は喧嘩に参加したぐらいで咎めはせぬ。これからいくらでも戦に出て行かねばならぬからな。熊千代、おまえがあの争いに入ったは、短慮か、我儘か?それとも甘えか?」
「わからん」
熊千代はぶっきらぼうに答える。
「甘えならば母は許しませぬ。父上はな、粉骨砕身して戦っておる。上野方ではな、殿がお前を紛れ込ませ、扇動したと申しておるそうな」
「まさか、そんな…」
和尚が思わず口を出した。
「たかだか六歳の子じゃぞ?どうやったら扇動などできると言うのだ」
「何歳だろうと、嫡男がそこにおったというだけで相手方には十分なのよ。丘から指をさし、笑っていたとも申すではないか。どこに落とし穴があるかなど、誰にもわからぬ。熊千代、父も母も、なかなかおまえを構うてやれぬ。だが甘えなど許されぬこの世の中よ。よう考えなされ、たわけ者!」
まるで男のような叱り方をして、さっさと麝香は去って行った。
熊千代の身体を抱きもせず、真正面から射るような強い目を見据えただけだ。
和尚が麝香の持ってきた小包を熊千代に渡しながらしみじみと言う。
「母上はな、お前のことを人一倍心配しているのだぞ」
熊千代が包みを開くと、中には干し柿がいくつか入っていた。さっき強くこすられた頬に、母の手の温かみはかすかに残った。
はじめて母を、あれは本当のおれの母なのだと感じた最初の出来事だった。
◇
藤孝にとって、三好一党の放逐は旧主・義輝の時代からの悲願、そのためにも絶対に信長に負けてもらってはならない。
大名たちの動向に目を配り、公家に根回しをしながら子供の増えた我が家の采配をする。一門の立て直しを図り、信長に言われるまま転戦に継ぐ転戦をして、目が回るほど忙しい。
元亀二年(1571)の年、信長は比叡山焼き討ちを決行している。細川藤孝は山城西岡一帯を与えられ青竜寺城主となった。
近江志賀五万石を与えられ、破格の待遇を受けている明智の加増とは比べ物にならないが、やっと少しばかり陽の目を見、食い扶持だけは確保できた。藤孝はほっとしながらも、油断なく形勢に目を配っていた。いつ、どのように何事が起きるか誰にもわからないのだ。城には二重の堀を掘らせ、堅固な城に改修をはじめる。
「八歳にもなったとて、そろそろ分別がついた頃であろうか」
藤孝は熊千代を呼びにやった。
来てみたは良いが、斜め下から睨め付けるような猜疑心に満ちた恨みがましい顔を見て、藤孝は一目でうんざりした。
熊千代は城に馴染めない。たいして大きくもない平城で、母は妹、弟と次々に産み、ついに第四子まで生まれて奧屋敷には赤ん坊がごろごろしている。熊千代の乳母ももう、熊千代の面倒から離れて妹、弟たちの世話に大わらわだ。
弟の頓五郎(興元)は五歳となっていたが、きちんと正座をして、既に四書五経をはじめとする勉強に励んでいた。
寺で少しは仕込まれたので、しぶしぶ書見台の前に正座をしても、頓五郎が隣で「子、曰く!」などと朗々たる声でやると、熊千代はむかっと来る。
先を越されたな、と父が皮肉げに言うのに腹を立て、弟の書や硯や筆を蹴り飛ばした。
父に鉄拳を受け、投げ飛ばされて(藤孝は牛殺しの与一郎の異名もあるほどの怪力の持ち主だった)鼻血を出し、また和尚のもとへ行かされる。
こんな騒ぎの間にも、細川輝経の養子となる話が持ち上がったり立ち消えたりしながら時は過ぎた。何しろ細川家はあっちの養子だこっちの猶子だと、名前も子供も玩具のように振り回す。名家の名前は金銭がからむ。また家同士の協力をはかっては血統を確保する。そういう時代だった。
有吉万助だけが、鈍重そうな顔をしてじっと黙ったまま、いつでも熊千代の後ろに控えている。何も言わないが決してそばを離れない。
こちらは十三歳になっていた。
◇
元亀三年(1572)、熊千代が九歳の年に、あの石合戦の騒動の相手方、上野氏による義昭への讒言により、藤孝は勝竜寺城に蟄居することとになった。
熊千代は三年も前の騒動など、ぼんやりとしか覚えていない。
だが、城内の不穏な空気、ひそひそ話、頻繁に出入りする侍たちの会話から、子供なりに察せられる。
そうか、おれのせいか。
たかが喧嘩に混じって走り回ったぐらいで、こんなことになるのだな。
どこに落とし穴があるか誰にもわからぬ!たわけ者!
実際には、あの騒動こそ元々あった両者の不和が顕在化したに過ぎず、また上野清延の讒言は、理由がないことではない。藤孝がどんどん力を強めていく信長にあまりにも近く寄り添い、明智とともに義昭周辺の情報を流していることは事実だった。甘い汁を吸えないやっかみもあり、影響力を危惧してのことでもある。
いつものことではあるものの、熊千代がふいとどこかに行ってしまい、いつまでも見つからない。お守り役の有吉も探しあぐねて、松井康之も城内の捜索に駆り出されていた。
ふと見ると、今日、藤孝の客人となっていた明智十兵衛光秀が、縁側にゆったりと座って誰かと話している。明智の身体の影に隠れて相手は見えないが、ぶらぶらと動かした裸足の爪先が見えたので松井は気付いた。
「これは、明智様」
「かまいませぬ。今、熊千代君と面白い話をしてござる」
明智は若い松井康之にも丁寧な口をきいた。
「うむ、それで?それで?」
「卯の刻(午前六時)に、鬨の声が上がり申した。槍ぶすまがぶつかり、火花を散らしたあとは、敵味方入り乱れての激戦でござる。だが次第に織田方は押されてきた。勢いづいた敵にじりじりと下がり始める中、戦上手の三河殿(家康)はさすがに目ざとかった。朝倉・浅井がたは勢いづくあまり、陣が伸びておる。三河殿は榊原に命じ、この弓の蔓のように伸びた筋を断つように、側面から攻めよとお命じになった。こう、ぐわっと(明智は手で形を作ってみせた)横から突っ込ませたのでござる」
熊千代の顔は興奮に満ちていた。
松井も思わず聞きほれた。明智の声はまろやかで耳に優しかった。目にも優しい整った顔立ちで、なよやかに、囁くように話したが、低くはっきりした声でよく聞き取れた。
「姉川での御合戦でござるか」
二年前の浅井・浅倉連合軍を撃退した戦いだ。
熊千代の興奮ぶりからすると、突然の浅井の裏切りから金ヶ崎の撤退戦を経て、姉川で反撃するまでの流れをみっちりと語って聞かせたとみえる。
明智は照れたように頭を曲げた。
「このように見たことのように語ってはおるが、わたしは姉川には参加できなんだ」
「明智殿の話の方が、父上より面白い。父上は源氏だとか、和歌だとか読ませようとしてくるが、あんなのめそめそした女子がたくさん出て来るだけでおれは大嫌いだ」
「源氏物語も面白うございますぞ。人間の心の機微をこまかに描いてござる。政治を学ぶ上でも、決して馬鹿にはできませぬ。ですが熊千代君には、先に平家物語の方がよろしいかな」
ぽつりと熊千代はつぶやいた。
「頓五郎は面白いと言うのかもしれぬ。まだ小さいが、父上の話を熱心に聞く」
そして、元気にこんなことを言いだすので、松井は驚いた。
「おれは本気で出家しようと思っている」
「ほう、それはまたなぜ」
「父上に迷惑をかけるから」
「迷惑とな」
「うん、おれのせいで、父上は蟄居になってしまったらしいのだ。おれは気性が荒くて父上の邪魔になる。だから坊主になろうと思う」
明智は腕を組んだ。
「なるほど。心がけは誠に立派、したがそれは残念でござるなあ」
「残念とは何だ?何が残念なのだ?」
明智は笑った
「熊千代君は、坊主にはなりなさらぬ」
あまりにもはっきりと言ったので、熊千代も、背後の松井も思わず明智十兵衛の顔を見上げた。笑顔ではあったが、その目が真剣であるのを見た。
「そうか?」
「はい。負け知らずの強い武将におなりなさる」
まるで見て来たような風に言う、と熊千代は不思議に思った。だが、奇妙だ。風はそよとも吹かず、鳥の声も止んでいる。予言を受けたような気分だ。
「おれは坊主にはならない」
「はい」
「向いてもいないしなる気もない」
「左様でござる」
「強い武将になる。おれは負けない!」
明智は、この少年の背中に手を当てた。その手もまた、温かかった。
「熊千代君。またこの十兵衛と遊んで下されよ」
◇
「何と勇猛で利発な御子息でござろうか」
多少、阿るような響きもなくはない。
信長のおぼえにより、藤孝を追いつき追い越すこととなって、藤孝が拘りを見せまいとしているように、明智の方も気を使っているのを感じた。だが、松井には藤孝がそれほどその明智の気遣いを有難がっているようにも見えない。
誰よりも気が合い話が合い、趣味も合う相手だからこそなのかもしれない、と松井は考えた。気に入っておればこそ、ということもあるものだ…
「そんな、明智殿にも御嫡男が誕生されたではありませんか」
今度は松井が阿るような口をきいていた。
「いや小そうて乳を吸う力も弱く、とても長生できるかわかりませぬ。このような弾けるように元気なお子を持つ細川殿が心底、羨ましゅうござる」
「ははは……」
ものは言いようだ。元気、やんちゃと言えば聞こえは良いが、一度火が付くと、大の大人でも止められぬほどの狂いようで、侍女の手になどとても負えず、手が付けられない。
明智は、松井とともに廊下を歩きながら、何気なくこんなことを言う。
「松井殿はもう二十三歳。立派に独り立ちしてもよい歳とお見受けするが、どのようにお考えか。細川殿も心配してござったが」
永禄の変は、松井康之の運命にも暗い影を落としている。
松井家は足利将軍に仕えて来た代々の重臣の家柄だった。永禄の変で弟は義輝とともに討ち死にをして、家督を継いでいた兄、松井勝之は追い腹を斬って死んだ。
次男である康之は十六歳だった。
やむなく彼が家督を継いだが、若年の身だ。義昭を担ぐために奔走する藤孝と行動を共にして数年、松井はまだこうして藤孝のもとにいる。
藤孝と共に転戦を重ね、家柄、実力共に備わる松井には、あちこちから士官の道が来ていた。再三、問うてくる者もいたし、藤孝のもとにいても直轄の信長家臣と見てくれる者もいた。
松井自身も意識してあちこちに顔を出し、連歌も茶会も積極的にこなしている。話をすれば皆が松井康之には一目を置き、顔を見る。
立たぬのか。身を起こさぬのか。
なぜ三淵家の次男にすぎぬ藤孝の下にいるのだと問われたこともある。
だが松井康之は、そろそろ旧領をどうかと言われた時の義昭の言葉、「信長に口をきいてやるぞ」と、その一言が気に入らなかった。
松井にとってあらゆる芸事の師匠であり、強い信頼で結ばれている藤孝と、何の会話を交わしたわけでもないが、ここ数年の苦しい戦いを経て、二人の間に共通した認識がある。
結局、力なのだ。
力がなくば、何事も成し得ない。
そしてもう、足利将軍家にその力は失われている。
ここで義昭は何やら暗躍を始めているようだが、信長が気に入らないからといって、誰を連れて来ようと武田でも上杉でも同じこと。
三好長慶亡きあとの三好一党を追い払うために信長を連れ出して来た自分たちが、結局は三好の方がましであったのかもしれないという苦い現実をかみしめている。
長慶どのは節度をわきまえられていた。義輝さまともうまく付き合えていた御嫡男があんなに早く死ななければ、とも思うが、きっと遅かれ早かれ、こうなることは目に見えていたのだろう。
このまま藤孝のもとにいれば、いずれ主君となるかもしれないのは熊千代だ。自分のせいではないとはいえ、この少年が、いつも比べられる自分のことを大嫌いであることも松井は知っている。
しかし、松井には不思議な思いがあった。
熊千代は松井康之の父が死に、三好長慶の長男、義興が死に、細川氏綱が死んだその年に生まれた。
翌年には三好長慶が死に、そして義輝という主君と同時に兄も弟も失なった。
時代が大きく、うねりを上げて変わって行くそのちょうど転換期のことだ。
藤孝に容易にねじ伏せられない、その激しい気性を見ていると、この少年は何か新しい力を秘めているように思われる。
大きくなれば変わるかもしれぬ。良い方にとは限らない。大器のように見えても、小さくまとまってしまうかもしれないし、小さい頃に暴れ者であっても、大きく成ればうそのようにおとなしくなると聞いたこともある。
どうなるかはわからぬが、この少年の持つ容易ならぬ生命力のようなものが、新しい時代に相応しいのではないかと、そう信じてみたいような気もするのだ。
明智も同じことを思っているように感じた。
ふりかえって、我が身の振り方は慎重にせねばならない。
「この情勢の中で、力を併せねば乗り切ることは難しいと存じます」
明智はうなずいて、草履に足を通して細川家を辞した。
足利義昭が追放され、室町幕府が滅亡する、前の年のことだった。
第四話終わり
画像(縦書き・ルビつき)
画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。




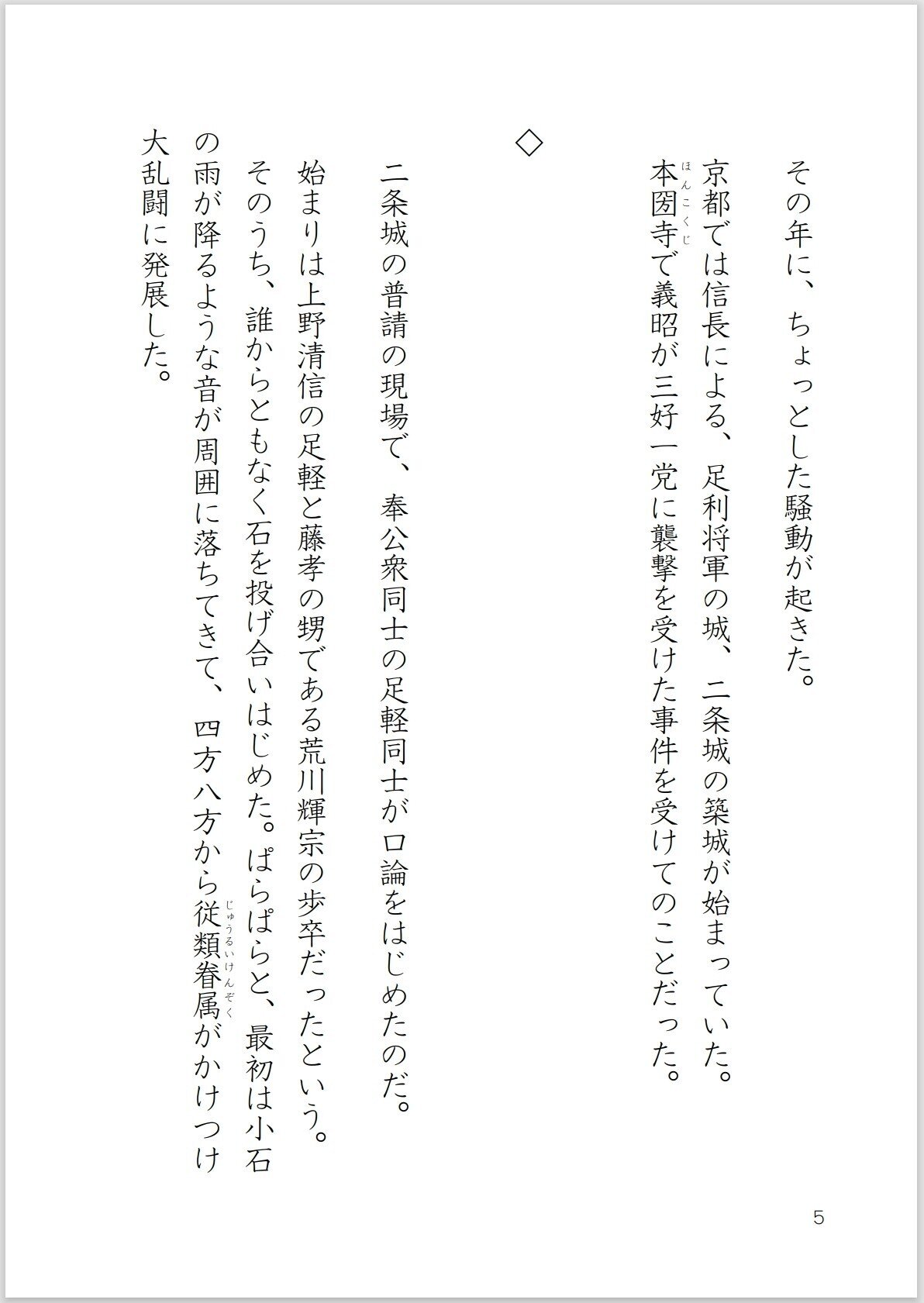




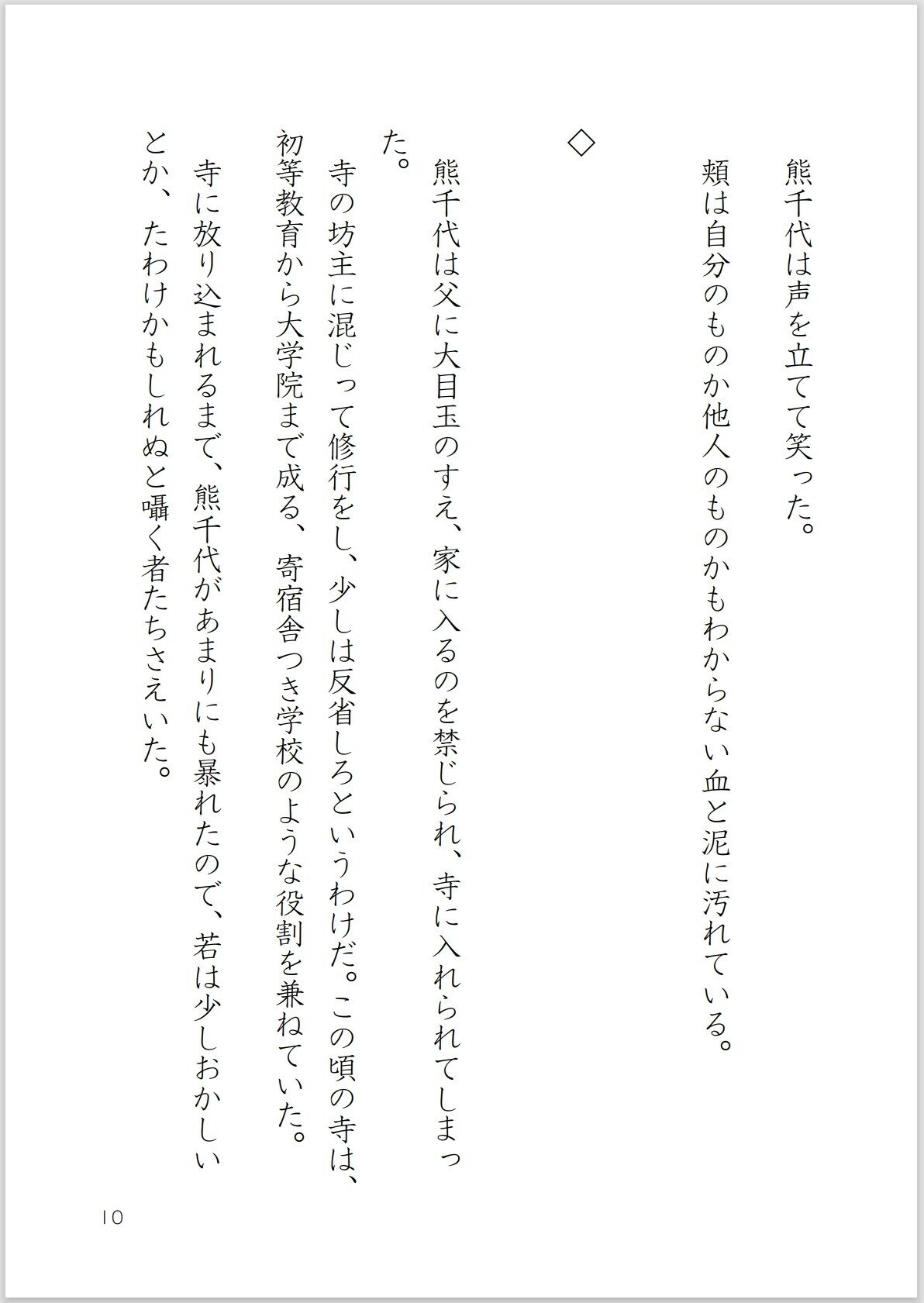

















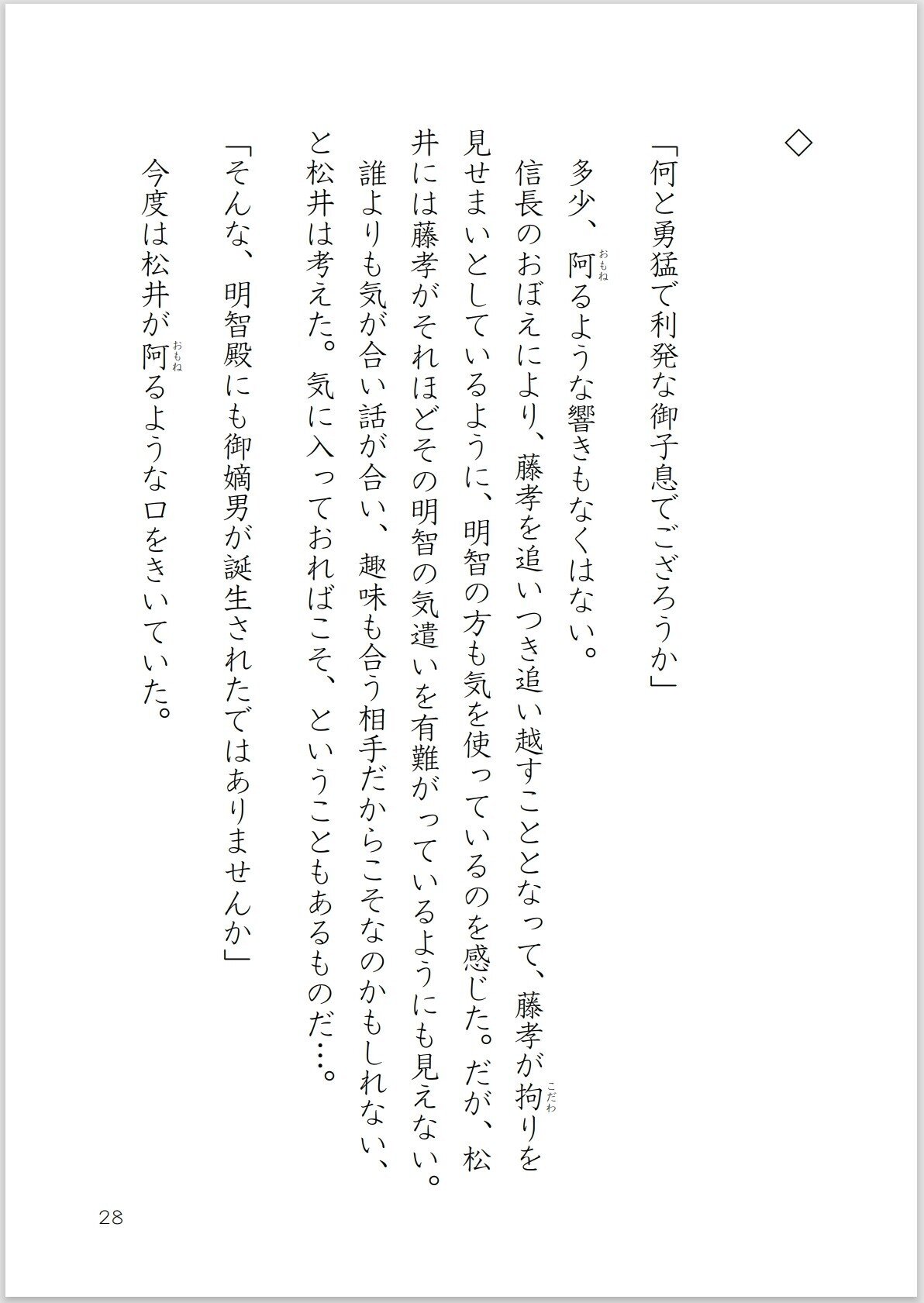

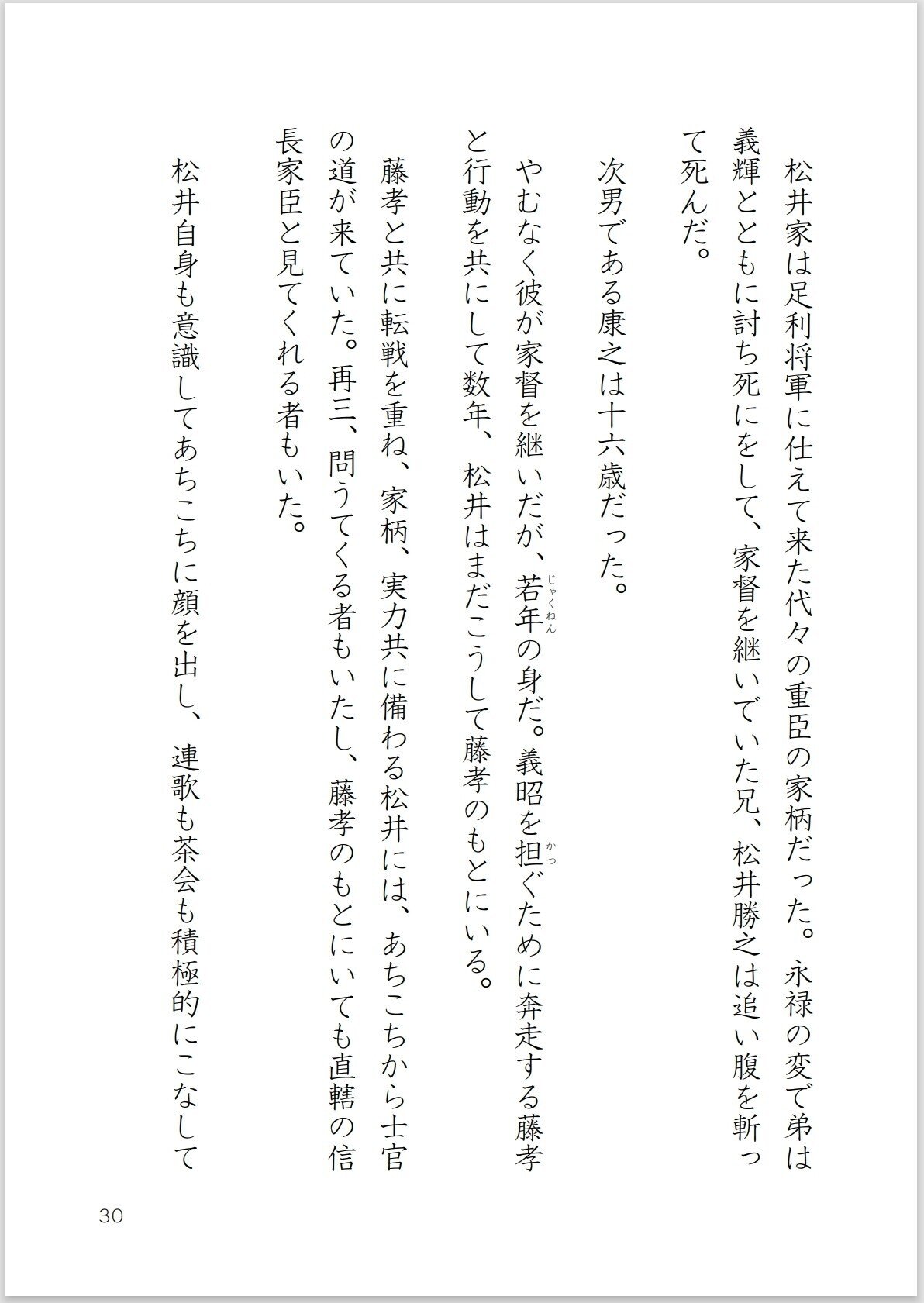




児童書を保護施設や恵まれない子供たちの手の届く場所に置きたいという夢があります。 賛同頂ける方は是非サポートお願いします。
